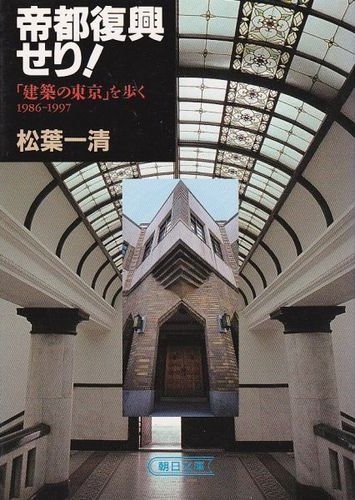写真嫌い
2015.2.1|facebook
昨日は店を早仕舞いさせていただき、急逝した叔父の通夜にかけつけた。

「母の弟」なので「叔父」なのだが、ぼくら従兄弟たちはみな「おじさん」とは呼ばず、もっぱら「進ちゃん」「進ちゃん」と呼んでいた。親から「おかしい」と指摘されても直さなかったのは、子供は「理屈」より感覚的に納得できるほうを優先するからだろう。ぼくらにとって、「歳のはなれたお兄さん」のような存在だったのだ、進ちゃんは。
会場では、遺影の前で従兄弟たちがアルバムのようなものを見ながらなにやら談笑している。家族が自宅から持ってきたという幾冊かのアルバムには、若いころの写真が几帳面に整理され貼られていた。まるで「昭和の大スター」のようなポーズできめているものもあれば、いまとはまるで別人のようにスリムな体型の母の姿もある。湿っぽくて当然の場所なのに、ページを繰るたびこらえきれず笑ってしまう。悲しいし寂しい。が、写真にはそういう力もあるのだ。
写真嫌いだが、いまからでも遅くない、おもろい写真をできるだけ遺しておこう、帰りの電車に揺られながらぼんやりそんなことを考えていた。
米澤穂信『夏期限定トロピカルパフェ事件』
2015.2.2|review
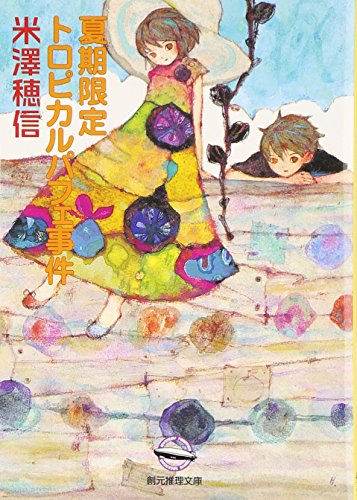
ちょっとクセのある高校生ふたりが身近なナゾに挑む地方都市を舞台にしたライトなミステリ……
と思いつつ読んだ前作『春期限定〜』だったのだが、この作品ではいい意味で読者の予想を裏切ってくれる。
前作では、主人公たちがしばしば口にする「小市民」とか「互恵関係」といった言葉がいちいち口実めいていて、なんだか喉に刺さった小骨のように鬱陶しくも感じられたのだが、今作ではその意味が少しずつ明らかになり輪郭を帯びてきた感じ。小佐内サンが暗黒すぎて不気味ですらある。
「過去」を葬り去りたいふたりだが、どうもそうはいかない様子。次回作がいよいよ楽しみになってきた。
冒険家
2015.2.3|facebook
「冒険家」という肩書きをもつ人たちに、子供のころからどうも共感できずにいる。
スキー場のコースを外れ、ただただ自己満足のために危険エリアに立ち入り、結果、遭難して救助にあたる人たちを二次遭難の危険にさらすひとをぼくらは糾弾するいっぽうで、同じように自己満足のために南極大陸をめざし遭難したひとをまるで「英雄」でもあるかのように扱う。これはいったいどういうことなのだろう?
「『冒険家の遺伝子』というのがあるらしいですよ」。そんな話をしていたら、スタッフが教えてくれた。いわゆる「冒険家」には、「報酬依存」や「損害回避」の因子は低く、「新奇性探求」の因子が高いタイプのひとが多いらしい。「冒険家の遺伝子」か、なるほどそれなら自分にも覚えがある。
小学生のころの話になるが、ぼくは二度ほどこのまま死ぬのではないかという思いを味わったことがある。一度目は、パチンコ玉大のイミテーションの真珠を、二度目はおなじくパチンコ玉大のプラスチックの青いビーズを鼻の穴に入れ、それが取れなくなってしまったのだ。そんなぼくをつかまえ、親はなぜそんなことをしたのだと問いただしたが、そこに「理由」などありはしなかった。あえて言うとすれば、そこに「山」があるように、鼻の穴にぴたりとはまりそうな大きさの「玉」があったから、そう言うほかない。そしていまなら言える。あれは、「冒険家の遺伝子」のなせるわざだったのだ、と。
スリルを求めて、ひとは冒険するのではない。ただただ衝動に突き動かされてそうするのだ。「鼻の穴に入れた真珠が取れなくなったら、さぞかしお母さんに怒られるだろうな」そんなことをいちいち考えていたら、ひとは冒険なんぞできないのである。その意味で、「冒険家」というのは厄介かつ迷惑な存在である。そして冒険家たちは、そうした自分の気質について自覚的でなければならない。
そこで、おなじ「冒険家の遺伝子」をもつこのぼくから彼らにひとつアドバイスしたい。ある日突然ヨットで太平洋を横断したり、犬ぞりで南極大陸を横断したいという衝動をおぼえたら、まずは鼻の穴にパチンコ玉大の球体を入れてみろ。家族から「伝説のアホ」扱いはされるが、さして世間に迷惑はかからない。
パトリック・デウィット『シスターズ・ブラザーズ』
2015.2.4|review
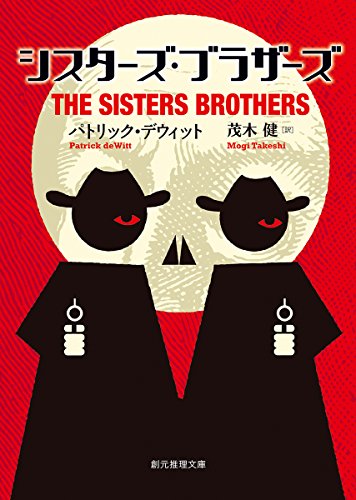
チャーリー&イーライ・シスターズは、泣く子も黙る兄弟殺し屋。「山師ウォームを殺れ」との雇い主からの依頼を受け、オレゴン・シティからゴールドラッシュに沸くサンフランシスコめざしハチャメチャな旅がはじまる。
暴力、博打、裏切り、復讐、泥酔、皮肉な笑い……
知っているところでは、ブコウスキーの小説、コーエン兄弟やタランティーノの映画とおなじ匂いをもつ小説。破天荒で不思議な彼らの旅は、また家族再生の旅でもある。
事件は次から次に起こるも、そこにミステリー要素はなし。解説にある「ウェスタン・ノワール」という表現がいちばん近いかな。
北杜夫『どくとるマンボウ航海記』
2015.2.6|review

現実逃避には紀行文がいちばん。できれば、凡人とは目線がズレていて、しかもコミカルなのがいい。『どくとるマンボウ航海記』は、まさしくそんな条件を満たす絶好の一冊。
「掘りだされて一年目のゴボウのごとく疲れ果てた…」(上陸がうれしくてついはしゃぎすぎたマンボウ先生)
「もっとも安くもっとも面白い場所を古ギツネのごとく捜しだす…」(古参乗組員について)
「海と空の中間の色彩で、ほそく一直線におどろくほど起伏なくつづいている」「それはいかにも涯がなく,窺いきれぬほど暗黒なものを蔵しているかのようだ…」(船上から目にしたアフリカ大陸の眺めについて)
こんな独特の表現とともに、いまはもう二度とこの目で見ることはできない60年近くも前の世界が生き生きと立ち上がってくるのだから、なんとすてきなことだろう。
中島京子『小さいおうち』
2015.2.12|review
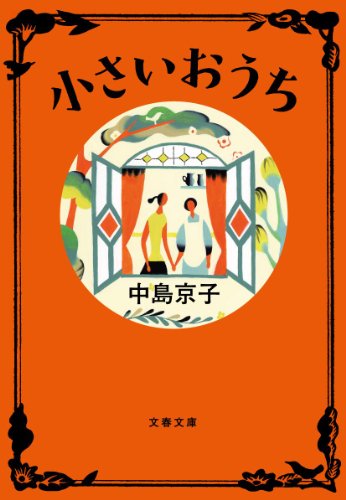
坂の上の小さいおうちとそこに暮らす人たちの世界、さらには、その小さいおうちを取り巻く世界。さいしょは同じだったはずのそのふたつの「世界」は、戦争の足音が大きくなるにつれ次第にズレてゆく。やがて小さいおうちは、まるで荒波にもまれる小さな船のように思わぬ方向へと流されてゆくのだった。
語り手は、この小さいおうちとそこに暮らす人びとに深い愛情を感じている女中のタキ。晩年、タキが綴る手記をもとにストーリーは進んでゆくが、それを「盗み読み」する甥っ子のいかにも現代っ子らしい視点がミックスされているのがこの小説の特徴といえるだろう。おかげで、物語が「昔話」に終わらずに済んでいるからだ。
「謝らなくていいわ。わたしが欲しいのは、心のゆとりなのよ」と奥様の時子は言う。また、巻末に収められた作者との対談で、船曳由美さんは次のように述懐する。「戦争というのは、そういうハイカラな、もっとも大事な心に響くものからなくなっていくんだというイメージがありますね」。
街から、心にゆとりをもたらす物や店が次第に消え、またそうした考え方がなんとなく憚られるようになったら要注意だ。ここ日本にあって、庶民にとっての戦争とはある日突然に火蓋が切られるといったものではなく、平和な日常のすきまからじわじわと浸み込み、気がついたときにはもう手の施しようがなくなっているのだ。
おやつ
2015.2.15|facebook
声に出して読みたい日本語。それは、お・や・つ。おやつ…… なんという甘美な響き。世界に広めたい日本のことば、それは、O・YA・TSU。

そして、今日も今日とて出勤前から優雅におやつタイムです。頂き物の「FIKA」の北欧菓子ハッロングロットルと、淹れたてのコーヒー。コーヒーは、銀座「北欧の匠」さんが埼玉県の「珈琲屋コスタリカ」さんに特別にお願いしこしらえたというオリジナルブレンド「ブルー・コペンハーゲン」。バランスの整った透明感あふれる軽やかな味わいで、朝から甘いものをツマミにちょっと一杯ひっかけるには最高です。円錐ドリッパーでさらっと淹れると、その特徴がいっそううまく引き出されるみたい。
では、次回【おやつの部屋】にてまたお目にかかりましょう。
松葉一清『帝都復興せり!―「建築の東京」を歩く』
2015.2.17|review

著者は関東大震災による壊滅的な被害からの約10年間、いわゆる「復興期」の建築ラッシュこそが現在の東京の原風景をつくったと考え、昭和10(1935)年に都市美協会が発行した写真集『建築の東京』を手に、そこに収められた500件ちかい建物を地道なフィールドワークによって訪ねあるく。
訪ねあるいた昭和61(1986)年、『建築の東京』発刊から50年を経過した時点で踏査できたのは450軒、すでに半数以上の建築が姿を消していた。建物の現存を確認すると同時に著者は、そのわずかな期間のうちに出現した建築の数もさることながら、そのスタイルの百花繚乱ぶりに驚かされる。
アールデコ、ドイツ表現派、フランク・ロイド・ライト風、インターナショナルスタイル、古典風、日本趣味……そうしたさまざまな様式と思想があたかも当然のごとく並立し、ときに混交しながら乱れ咲いている。その折衷的なあり方こそが、「復興期」の建築のなによりもの特徴であると著者は言う。
建築に限らず、そこには西欧の文化をわずかな時間のうちに受容し消化していった島国「日本」の姿があるのではないか。
扉のむこうがわ日記
2015.2.19|facebook

さまざまスタイルを変えながらも8年間にわたって続いてきた雑誌「カフェアンドレストラン」の連載「扉のむこうがわ日記」ですが、本日発売の3月号をもって最終回となりました。ご愛読いただいたみなさま、この連載を読んで「moi」に遊びにきてくださったみなさま、本当にありがとうございました。また、《立体》コラムというスタイルでご一緒させていただいたバールボッサの林さん、おつかれさまでした!!!
ひとつの「お題」を、それぞれカフェ目線/バー目線で語ってみた「カフェをやるひとバーをやるひと」、カフェのマスターやバーのマスターは日々どんなことを思いながらカウンターに立っているのか、「覗き見」的なオモシロさを狙ってみた「扉のむこうがわ日記」。連載は毎月でしたが、あらためて8年分の原稿を読み返すことで、あるいは飲食の世界からみたゼロ年代の「東京」の定点観測としての面白さもあるのではないかといま思っています。どこか、まとめて出版してくれる出版社はないでしょうかねぇ?(笑)。
ぼくらのアイデアを拾って企画を通してくれた旭屋出版の北浦さん、北浦さんの異動後、担当してくれた笹木さん、そしてぼくらの野放図なアイデアにもいつも辛抱強くおつきあいくださった前田編集長、お世話になりました。ふたりの文章を美しくレイアウトしてくれたサンクデザインの保里さん、そしてブックデザインの世界で活躍中の川畑あずささん、ありがとうございました。イラストで、ときには切り絵もまじえつつ扉絵と挿絵を描いてくださったイラストレーターの日置由香さん、アイデアを捻り出すだけでも大変だったと思います。毎月、毎月、楽しみにしてました。毎月、当時原宿にあった保里さんの事務所に集まりミーティングを重ねたことも、いまとなっては「部活」のようで楽しい思い出です。
そしてなにより、8年間も連載を続けられたのは読者のみなさんの支えあってこそ。お店で、「いつも読んでます」と声をかけていただけるのは本当にしあわせな経験でした。チャンスがあればまたいずれ、團伊玖磨の『パイプのけむり』よろしく「続々・カフェをやるひとバーをやるひと」とか「ひねもす・カフェをやるひとバーをやるひと」とかやってみたいものです。そのときは林さん、お付き合いの程どうぞよろしくお願い致します。
ヘレン・マクロイ『幽霊の2/3』
2015.2.20|review

読者には早々に犯人とその手口をなんとなく仄めかしておいて、種明かしはジワジワあぶりだしのように時間をかけてというのがこの小説のスタイルなのだろうか?
まんまとじらされてイライラしながら読了。
登場人物の会話のなかに出てくる「イギリス人はかんたんなフランス語の題がつけられた小説を好む」というエピソード同様、この作品からチラチラ顔を覗かせるディレッタントな雰囲気は、ヘレン・マクロイが「意図して」流行小説風の装いをしてみせたということなのだろうか?(他の作品を読んだことがないのでわからない)いや、ただの考え過ぎ?
登場人物や舞台をはじめ、とても洒脱な雰囲気をもったミステリだと思う。そんな中、探偵役のベイジル博士が他の登場人物たちと比べてヒューマンな魅力に欠けるので、なんとなく事件は解決しても物足りない気分になってしまうのだった。笑
どうでもよい話
2015.2.23|facebook
バターの香りはいい。食欲をそそる。が、その「いい匂い」が時々、そう、頻度にしたら10回に2回くらいなのだが「ケモノの匂い」に感じられることがある。
世の中に味や匂いはさまざまあるが、かなりの部分は「慣れ」で克服できるのではないか。小学生のときそうかんがえたぼくは、「肉詰めフライ」の助けをかりてピーマンを克服した。いまでは、ふつうにおいしく食べている。はじめて口にしたときには約2秒で吐き出したサルミアッキだって、おみやげにいただいたり、身近なフィンランド人からの勧めを断り切れず口にしているうち、いつしか平気で食べられるようになった。ただしサルミアッキに限って言えば、いまだ「おいしい」とは思っていないが。
明治2年、東京の芝・露月町、いまの新橋駅のちかくに「牛鍋屋」ができた。江戸のころから英国人相手に牛肉を商っていた中川さんというひとが、なんとか日本人にも牛肉を食べさせられないものかとかんがえ、「牛鍋」の店を出すことにしたのだ。だが、牛肉を食わせる以前に、「牛鍋屋」を開くのがまず大変だった。「牛鍋」と聞いただけで、店を貸すのを大家が渋る。なんとか決まったと思ったら、こんどは近隣住民の反対でキャンセルされるといった具合。いまでもよく「ラーメン店不可」といった条件つきの店舗物件をみかけるが、まあ、だいたいそんなところだろう。中川さんがようやく「牛鍋屋」のオープンにこぎつけたのは、大家が相場の4倍ほどの家賃を支払うことで納得したからであった。
どうしてそこまで「牛鍋」は嫌われたのか? 「肉を食らう」ことの気色悪さもさることながら、やはりなんといってもあの独特の「匂い」なのではないか。まだ「肉食」が身近ではなかった時代にあって、生肉の放つあの「ケモノの匂い」は生理的に受け付けがたいものがあったろう。おそらく、その後100年あまりの時間をかけて、日本人のDNAはその「ケモノの匂い」を「おいしい」にじわじわと上書きしてきた。とはいえ、その上書き作業はまだ完結したわけではない。ぼくの嗅覚がバターのなかに不意にケモノの存在を感じるとき、文明開化以前の、〝俺のいまだ散切り(ざんぎり)頭になっていないDNA〟がぐいっと首をもたげているのである。
寺田寅彦『銀座アルプス』
2015.2.28|review
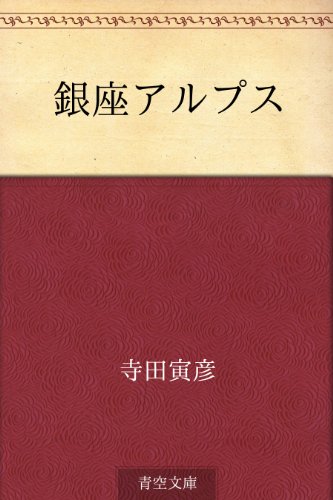
「雪や寒い雨の日にコーヒーのうまいのはどういうわけであるか気象学者にも生理学者にもこれはわからない。空気が湿っていて純粋な「渇(かわき)」を感じないために、余裕のできた舌の感覚が特別繊細になっているかもしれないと思われる」。つい先日ネットでみかけたこんな一節をあらためて読みたくて、パブリックドメインにつき無料でダウンロードできるキンドル版で入手した。明治12(1879)年生まれの著者が、昭和8(1933)年に発表したエッセイである。
記憶の「対流」によって、前後に流れる明瞭な時間の感覚を失ったまま、しかしかえって部分的にはさながら映画のように鮮明に思い出される明治の「銀座」の光景が、幼少時代の、青春時代の、著者のまなざしを通して投射される。
「心がにぎやかでいっぱいに充実している人」にはあえて避けて通りたい銀座のにぎわいも、「心の中に何かしらある名状し難い空虚を感じている」人にとっては、そこに行けばさながら「アルプス」のごとく「空虚が満たされそうな気がして」つい足がつい向いてしまう、著者はそう語る。
もういっぽうで、このエッセイが発表された昭和8年当時の銀座について思いをはせる必要がある。関東大震災で壊滅歴な打撃を受けた東京は、国を巻き込んでの大規模な帝都復興のスローガンの下、雨後のタケノコのごとく近代的な建築がつぎつぎと誕生する。
「摩天楼」とまでは呼べないまでも、モダンでノッポの「ビルヂング」を山々の連なる嶺として、また、きらびやかなネオンの輝く様を咲き乱れる草花として、著者は突然姿を現した「銀座」の姿を「アルプス」に見立てたのであろう。そこには、新しく誕生した都市の姿を愛で、称賛する著者の心持ちをうかがうことができる。その証拠に、著者は都市を破壊する地震への備えを訴えてこのエッセイを締めくくるのだ。しかし皮肉なことに、そのわずか10年ほど後に「戦争」がこの美しい「アルプス」を蹂躙してしまうことを、まだこのとき著者は知らない。