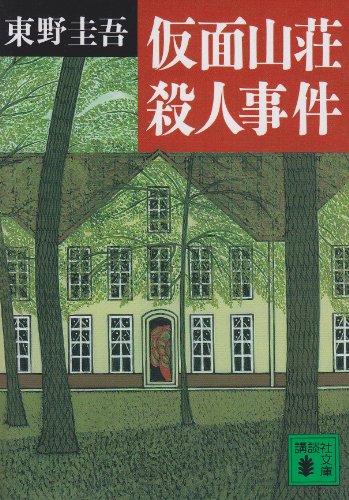シャーロット・アームストロング『始まりはギフトショップ』
2015.1.8|review

いい大人たちが「ブタの貯金箱」を奪い合うお話。シャーロット・アームストロングの作品を読むのはこれで3作目だが、この「ほんわかさ」こそが彼女の真骨頂なのだろう。嫌いじゃない。
空港のみやげもの屋ではたらく平凡な貧乏女子大生が、ある日ひょんなことから事件に巻き込まれる。事件のカギを握るのは、そのみやげもの屋で売られていた赤、黄、緑、3個のブタの貯金箱。その貯金箱の行方をめぐって、イケメン資産家vsマフィアが激しい争奪戦を繰り広げる。なかば強制的に、イケメン資産家と「ブタの貯金箱」を求めて世界中を旅するハメになった彼女の運命やいかに……。ストーリーだけ書き抜くといかにもくだらない(失礼!)のだけど、軽〜い気分で読み進め読後感も上々なので、ぜひ旅のお供にどうぞ。
円居挽『丸太町ルヴォワール』
2015.1.8|review

まるで、糸の切れた凧を追いかけるような……。
いにしえの昔より京都の貴族たちのあいだで密かに執り行われてきた私的裁判「双龍会(そうりゅうえ)」。その決着は、「龍師」と呼ばれる者たちの弁舌次第。そこでは真実よりも、いかに論理的に破綻なく、「火帝」と呼ばれるいわば裁判長を、そして群衆(ぐんじゅ)と呼ばれる観衆を魅了し、納得させるかが重要となる。その凄絶な舌戦は、まさにめくるめくドンデン返しの連続であり、ポンコツ読者にとっては追いついてゆくだけで精一杯なのである。フ〜フ〜息切れしながらも、しかしその懸命の追走はクセになる。読了後の爽快感、そして切なさ。
シリーズ第一作であるこの『丸太町ルヴォワール』では、祖父殺しの疑惑とその事件のカギを握る女性「ルージュ」との白昼のミステリアスな邂逅を通して、龍師の家系としての宿命を担ってきた「龍樹家」と、論語、達也、流ら後に龍師として活躍する者たちとの「因縁」が語られる。ややこしいがすこぶる面白く、青春小説としても読める。
円居挽『烏丸ルヴォワール』
2015.1.8|review

天才肌の登場人物たちの中で、唯一〝人間臭い〟キャラクター流(みつる)。このシリーズは論語、達也、撫子らそれぞれがみな主役の青春群像劇でもあるのだが、個人的にはこれから先「流」がどのように成長してゆくのかが楽しみでならない。おそらく読み手の多くも、(とりわけ双龍会の場面では)「流」のいかにも〝人間臭い〟視点からドラマを眺めているのではないだろうか。その意味で、重要な狂言回しの役割を担っているのがこの「流」なのである。
シリーズ第二弾であるこの『烏丸ルヴォワール』では、「流」がその人間臭さゆえ敵方の陰謀に翻弄されることになる。伝説の龍師「ささめきの山月」、「流」同様コンプレックスを抱えたまま姿を消していた「烏有」ら新たなキャラクターも登場。双龍会における容赦ない騙し合いのスリリングさは相変らず、息を詰めて読み切ってしまった。
今後「ささめきの山月」はどのようなかたちでストーリーに絡んでくるのか?
はたして「黄昏卿」との直接対決はあるのか?
ますます楽しみになってきた。
円居挽『今出川ルヴォワール』
2015.1.11|review
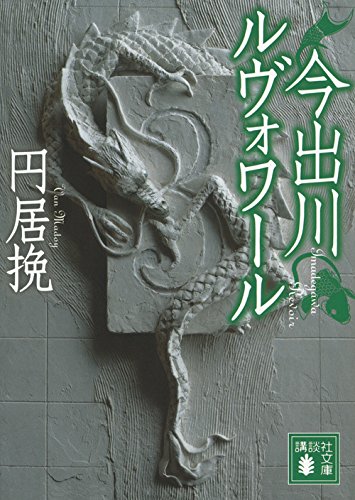
「オ・ルヴォワール」というフランスの別れの挨拶は、〝別離〟と〝再会〟という反対の意味を一語のうちに孕んでいる。いっぽう、ふたつの通りが交差する点によってあらわされる京都の地名もまた、そこに〝別離〟と〝再会〟とを孕んでいる。「ルヴォワール」シリーズ第3弾の舞台は、大怨寺という怪しげな寺院のある「河原町今出川」。当然、そこは積年の〝別離〟と〝出会い〟の交差点となる。
メインが、私的裁判「双龍会」におけるディベート以上に「権々会」における「鳳」と呼ばれるカードゲームに変わるとはいえ、その息を呑むような壮絶な騙し合いの連続は相変らずだ。そして最後、登場人物らの人間ドラマにも大きな変転が……
文庫化されているのはここまでだが、こうなったらこの勢いで「BOX版」で最終章まで読んでしまうべきか、はたまたご馳走は最後まで残しておくべきか……
悩ましい。
森川智喜『スノーホワイト』
2015.1.14|review

「魔法の鏡」というお題で抜群に頭の良いひとが小説を書くと、なるほどこんなミステリが出来上がるのか……。
「あちらの世界」では王家を継承する血を引くママエは、それとは知らず「こちらの世界」で世話役の小人イングラムとともに暮らす中学生。そのいっぽう、母の形見の「魔法の鏡」を密かに駆使して探偵業も営んでいる。そんなある日、とある依頼人の手引きでおなじ探偵業を営むふたりのクセもの、緋山燃、そして「我こそは名探偵」と公言してはばからない三途川理と引き合わされたママエは、「あちらの世界」の戴冠式に絡んだ陰謀から思わぬ事件に巻き込まれてしまう……
ミステリーながら、いきなり「魔法の鏡」「小人」といった飛び道具(?)の登場に面喰らうし、年齢的に仕方ないとはいえ、ママエの幼さ、身勝手さに共感できないのも読んでいてつらいところ。とはいえ、「魔法の鏡」を縦横無尽に使い倒す三途川の頭脳には舌を巻かずにいられない。とにかく、読者に息つく暇をも与えない矢継ぎ早のトリックは面白く、おとぎばなし的な舞台設定もさほど気にならなくなってしまうのだ。ラストの種明かしは……う〜ん……ひとひねりせずにはいられない作者の性格が出ている感じ?
──
【以下、ネタバレ】
「白雪姫」的なオチというのは分からないでもないが、個人的には、とどめはママエ自身の手でお願いしたかったかな?
オトナへの階段として。シリーズものらしいので、そのあたりの事情からママエのキャラは変えたくないかもしれないけれど。
島田荘司『異邦の騎士 改訂完全版』
2015.1.20|review

評判通り、ミステリの教科書のような精緻に構成されたストーリーに一気読み。
序ー記憶を失った男。ふとしたことから出会った女との蜜月。飄々としてつかみどころのない、しかし憎めない人柄の青年、御手洗潔との不思議な友情。
破ー失われた過去への執着とともに、理性を失ってゆく女。過去を辿るなかで知った、自身にまつわるおぞましい事件の存在。
急ー復讐。御手洗潔による推理。愛の完結。
ところどころで引っかかっていた事柄が、まさかこのようにつながっていたとは……そして、読了後にはその秀逸なタイトル(ロマンティック・ウォリアー)に感服。
全編をつらぬく、昭和の湿り気を帯びた空気感も重要な要素。
本気の銀ブラ
2015.1.21|facebook
〝銀ブラ〟をしてきた。ただの〝銀ブラ〟ではない。〝本気の銀ブラ〟である。
じつはもともと、〝銀ブラ〟という言葉についていえばぼく自身「銀座をぶらぶらとそぞろ歩く」くらいの意味にしかとらえていなかった。ところが、あるとき手にした一冊の本を読んでそれとは異なるまたべつの「説」があることを知ったのだった。
その本とは、長谷川泰三『日本で最初の喫茶店 「ブラジル移民の父」がはじめた カフェーパウリスタ物語』(文園社)。そのなかでいくつかの文献を引用しつつ長谷川は、「銀ブラ」の語源とは
「銀座のカフェーパウリスタでブラジル珈琲を飲む」
ことであるという説を紹介している。大正初期の慶應義塾大学の学生らが作り、流行らせたというのである。「アナ雪」しかり、「セカオワ」しかり、どんなに凝ったネーミングもいずれは「4文字」に縮められる宿命にあると言ったのはバールボッサの林さんだが、銀座の「銀」とブラジル珈琲の「ブラ」で「銀ブラ」、ふむ、ありそうな話話である。
成毛五十六。大正初期の慶応大学の学生で、「ピーリ」という同人誌を主宰する詩人でもあった。〝銀ブラ〟という言葉の命名者はこの成毛であると、作家で、同級生でもあった小島政二郎が自身の作品(『甘肌』)のなかでくわしく披露しているという。かいつまんで紹介すると、成毛とその仲間らは授業後、よく完成まもない銀座のカフェーパウリスタまで繰り出した。もちろん、当時も市電くらいは走っていたのだろうけれど、彼らはむしろだらだら5キロほどの道のりを歩いてゆくことのほうを好んだようだ。じっさい1時間半弱の道のりは、気の合う仲間と一緒ならたいした距離には感じられなかったのではないか。
彼らはまず、三田のキャンパスを出ると芝公園へ。芝山内から増上寺、大門を経て芝神明の「太々餅屋」で一服。そこから日陰町通りを抜けて新橋ステーション、新橋を渡ってカフェーパウリスタまでたどりついた。つまり〝銀ブラ〟とは、「よお、〝銀ブラ〟しようぜ」そんなひとことに始まり、ようやくたどりついたカフェでブラジル珈琲を味わうまでの一連の時間の流れをさしていわれた言葉にちがいない。そしてもちろん、そこにはぶらぶら歩きながらの友との会話や目に飛び込んでくる光景までふくまれることだろう。
前置きが長くなってしまったけれど、今回はこの〝本気の銀ブラ〟がどんなものだったのか、大正初期の慶應の学生らの足跡をたどってみた。

ほんらい「起点」は三田の慶應大学でなければいけないのだが、家を出る時間が遅くなってしまったのでいきなり脱線、新橋駅前ビルの「ビーフン東」で焼き五目ビーフンを食べた後、地下鉄で「大門」に移動、増上寺をとりあえずの「起点」とした。
◎増上寺

およそ400年前に建造された赤い「三門(三解脱門)」を抜けると、広大な境内には計算したわけでもないだろうがやはり赤い「東京タワー」を背後に従えた巨大な本堂は目に飛び込んでくる。浄土宗の大本山なので「南無阿弥陀仏」と唱えるべきのだが、「二礼二拍手一礼」しているおじさんがいた……。
◎芝山内

慶應の学生らとは逆行するかたちになるが、プリンスホテルわきを抜けて弁天池のある宝珠院をめざす。かつて「芝山内」と呼ばれたこの界隈、江戸時代には辻斬りや追いはぎが頻発するような物寂しい場所だったそうだが、たしかにいまだって目の前にそびえたつ東京タワーさえなかったらずいぶん殺風景な場所である。落語「首提灯」の舞台。
◎弁天池(宝珠院)

想像よりもかなり、とてもちいさな池。意外にひとがいる、と思ったら、なんのことはないドラマのロケでした。ちいさなお堂には、源頼朝や徳川家康も信仰したといわれるきれいな弁天様が祀られている。
ここからぐるりと芝公園をまわって増上寺まで戻る。縄文時代、東京の都心はあたかもフィヨルドのように複雑な地形をもつ入り江だったと中沢新一は著書『アースダイバー』で言っている。そしていま東京タワーが建つ芝公園の高台は、湾にせりだした岬の突端だったそうである。たしかにあの一角をのぞいては、まるで海底のように低い土地になっている。
◎芝大神宮

大門を抜けて芝大神宮へ。ビルの谷間にひっそりたたずむ鉄筋コンクリート製の神社。残念ながら風情に欠ける。もちろん「太々餅屋」もみつからず。学生らが贔屓にしたという「看板娘」の姿もみあたらない。町火消しと力士による、実際にあった乱闘事件をもとにした芝居「め組の喧嘩」はここが舞台。落語にもなっている。
◎芝神明

商店街とあるが、雑居ビルが立ち並ぶ閑散とした通りである。落語「富久」で、しくじりを挽回しようと幇間の久蔵が浅草から火事見舞いに駆けつける旦那のお屋敷があったのが、たぶんこのあたり。江戸時代は、そしてたぶん大正初期もにぎわっていたのだろうけれど、まったくその面影はなし。唯一、いちばん年季の入っているとおぼしき建物を写真に収める。酒屋さん。
◎日陰町通り

芝神明から新橋駅まで続く、第一京浜から一本入った通り。旧町名だと、芝井町(新橋6)〜露月町(新橋5)〜源助町(新橋4)〜日陰町(新橋3)と変わる。雑居ビルのせいで、正真正銘の「日陰町通り」である。寒い。歩いていると、なぜかポツポツといわゆる「純喫茶」が現れるのがおもしろい。このあたり、江戸から明治にかけて古着屋がひしめくにぎやかな通りだったとのこと。落語にも登場する。じっさい、1824(文政7)年に大坂で出版された『江戸買物独案内』にもこの界隈にあった店は掲載されている。江戸の商店2600軒あまりを掲載した、いわば「るるぶ〜お江戸」みたいなガイドブックである。新橋駅前の高架橋の名前に、いにしえの名残りを発見。
◎新橋ステーション

日本の鉄道開業のメモリアルな駅だが、いまはむしろ「サラリーマンの聖地」として有名。1時間に5人くらいの割合で、ペルーのフジモト元大統領に似たひとを発見できる。学生らはしばしば「駅の待合室で一休みしつつ旅客たちを眺めた」(前掲『カフェーパウリスタ物語』より)という。
◎カフェーパウリスタ

「終点」に到着。昨年のリニューアルで2フロアに増床、2階が禁煙フロアになったのはありがたいが、雰囲気はやはりかつての面影を残す1階のほうに軍配があがる。いつもきまって深めの煎りの「パウリスタオールド」を注文するのだけれど、きょうのはちょっと薄かったな……。ちなみに、大正初期の「カフェーパウリスタ」は現在の場所にほど近い別の場所にあった。交詢ビルの向かい、たしか現在1階にテナントとして「ピアジェ」のブティックが入っているところだったはずである。
長谷川泰三の本で紹介されている小島政二郎の述懐によると、この〝本気の銀ブラ〟にはしばしば教授も付き合って「課外授業」のようになったそうである。さぞかし、わいわいとにぎやかに、ときには熱い議論など戦わせながらの道行きだったことだろう。〝日本のベルエポック〟、そんな言葉がふと浮かぶ。
カフェとは、〝コーヒー一杯のある時間〟のこと。大正時代の学生らの〝銀ブラ〟という言葉には、「よお、〝銀ブラ〟しようぜ」という会話にはじまる一連の時間が、道々で出会う光景、なされる会話、そしてようやくたどりついたカフェで口にしたブラジル珈琲の深い味わい、そこまでのすべてが、ひっくるめて含まれている。カフェとはつまるところ、それぞれのひとの〝時間〟をかけがえのない〝記憶〟に変える不思議な装置なのだろう。
2015年1月21日 新宿全労済ホール
2015.1.22|facebook
【落語】
落語の世界では、ありえないことがふつうに起こる。登場人物たちはみなそれ相応にドタバタ翻弄されはするが、けっきょくいま起こっている出来事をありのまま(Let It Go♪)受け入れ、最後には収まるところに収まるようにできている。さて、現実は思うようにはいかないものだから、こうした噺の世界にしばし身を浸すことはときに〝最良のくすり〟になる。
ことし最初の落語会は、『スペース・ゼロ新春寄席vol.23〜落語でわかる江戸の暮らし』。五街道雲助、柳家喬太郎、三遊亭萬橘、桂宮治に太神楽の仙三郎社中が加わるという豪華さ。客席の雰囲気からすると、主催者の招待客が多いのか、ふだん落語にはあまり馴染みのない人たちがかなりの割合でいる模様。関係先の接待も兼ねたイベントなのだろうか。とはいえ、テレビで顔が売れていることよりも個性と実力を優先する顔付けに主催者サイドの良識(?)がうかがわれる。いいね。(ちなみにすべてネタ出し。)
────
開口一番 柳家さん坊「初天神」
◎桂宮治「元犬」
◎三遊亭萬橘「代書屋」
◎柳家喬太郎「うどん屋」
〜仲入り〜
◎鏡味仙三郎社中 太神楽曲芸
◎五街道雲助「幾代餅」
お囃子 森本規子社中
────
「元犬」のようなバカバカしい噺は、やっぱり宮治さんのような馬力のある噺家で聴きたいもの。もう、なんというか、せっかく人間になれた「シロ」だけど…… オマエ、もういっかいイヌに帰れ!!!
「代書屋」は、いまなら西は雀々、東は権太楼あたりが「横綱」ではないかと思っているのだけれど、そんななかはたして萬橘師匠がどんな「代書屋」を聴かせてくれるのか? おおお、そうきたか! 案の定、一筋縄ではいかない歪んだユーモアが展開される唯一無二の「代書屋」。この噺の場合、生真面目な代書屋がトンチンカンな客に翻弄されるところが愉快なところ。しかしここまでトンチンカンの嵐だと、さすがの代書屋も廃業したくなるだろうな。あと、これは以前から感じていたことだけれど、萬橘師匠が高座にあがっているとき、客席の笑いが他の噺家のときと様子がちがう。ふつうドワッと一瞬にして弾ける感じなのだが、萬橘師のときはジワーッと笑いがクレッシェンドしながら持続するのだ。どうやら、そのあたりに「萬橘落語」の秘密が隠されていそう。
外は冷たい雨。喬太郎師匠は、ジャンクな食べものネタのまくらから『うどん屋』へ。うどん屋は一見善人そうなのに、酔っぱらいの話がループ状態に入った途端、先手を打ちつつさらに軽いジャブまで繰り出してくる。喬太郎師匠が描くと人物描写には、そういう「根の暗さ」が付きものだな。師匠の目もまた笑っていないけど。ところで、「うどん屋」といえば先代小さん師匠のが絶品。冬になるときまって聴きたくなる。
いいな、いいな、人間っていいな〜「まんが日本昔ばなし」のエンディングの歌を思い出す雲助師匠の「幾代餅」。全盛の花魁が、搗き米屋の職人の真心に触れ、一晩のうちに夫婦約束をするという、まあ、「こうあって欲しいもんだよね」という人びとの願望を汲んだファンタジー。随所に笑いをまじえながら、ホッとするようなぬくもりを帯びた雲助師匠の「幾代餅」は、それじたいおおらかな「人間讃歌」になっている。
2015年1月21日 於新宿 全労済ホール スペース・ゼロ
Kさん
2015.1.26|facebook
オープンした年の秋にスタートした最初のフィンランド語クラスのメンバーであるKさんとは、このあいだあらためて数えてみて驚いたのだが、なんと12年来のおつきあいになる。時をおかずして始まったクラスの参加者であるSさん、元は先生のプライベートレッスンの生徒さんであったTさん含め、現在の土曜日クラスのみなさんはもはや部室にやってくる古参部員のような趣きを呈している。「教室」というより、傍から見る授業の眺めはほぼ「部活動」であり、ときには「おたのしみ会」であったりする。
アキ・カウリスマキの映画が好きで、会社勤めのかたわら映画の製作にもかかわっているKさん、フィンランド語を10年以上も学んでいるというのに、どうやら実際にフィンランドに行く気はさらさらないらしい。ふしぎなひとである。そのかわり、というわけでもないだろうが、あの震災以降、頻繁に出かけているのが宮城や岩手といった東北地方。週末、時間があるときにはボランティアとして被災地へ赴き、復興のための作業を手伝い、さらに現地では飲食や買い物を通してべつの〝貢献〟をしてまた東京に戻ってくる。そういう暮らしを月2回ほど、すでに3年以上続けていらっしゃるのだから頭が下がる。
そんなKさんのおかげで、こちらもずいぶんと美味しい東北みやげには詳しくなった気がする。今回いただいたのは、おなじみの銘菓「かもめの玉子」。しかも「限定」みかんフレーバー。濃厚でおいしい。そして釜石のHappiece Coffee(ハピスコーヒー)さんのブレンド。その後ツイッター経由で判明したのだが、ハピスコーヒーのオーナーさんは東京にいらっしゃったとき何度かmoiにもご来店くださったとのこと。こういう「再会」はまた格別。Kさん、〝いろいろな〟プレゼントごちそうさまでした!
米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』
2015.1.24|review

人一倍「執念深い」小山内サンと人一倍「口を出したがる」小鳩クンとは、おなじ高校に通う同級生。ふたりとも、どうやら過去にそんな性格が災いし手痛い目にあっている様子。高校入学を機にそんな「短所」を封印し、「小市民」として地味ながらも穏やかなスクールライフを送ろうと誓うふたりだったが、皮肉なことにそんなふたりの前に次から次におかしな事件が起こり……。
いわゆる学園を舞台にした「日常の謎」モノ。文庫書き下ろしの四部作。この『春期〜』は、第1作だけにまだまだプロローグといった印象。今後に期待をもたせる感じ。「おいしいココアの作り方」は、もっと単純なやり方もあるように思うのだが、賢吾のキャラクターに引っかけつつ、読者が思いもしないような方法を披露したかったってこと、かな?
※アアルトコーヒー庄野さんからのおすすめ本
2015年1月27日 渋谷PARCO劇場
2015.2.4|facebook
昨年につづき、パルコ劇場のお正月興行『志の輔らくご』に行ってきた。プログラムはというと、前半が新作と古典、仲入りをはさんで新作をもうひとつ。いつも通り前座はなく、志の輔師のみ3席という構成である。
一席目の「スマチュウ」は、スマートフォン中毒の大学生がおじさんのところにお金を借りにゆく話。なんとなくコント「山口君と竹田君」にありそうな展開。つづく二席目は、「大岡裁き」を題材にとった古典「三方一両損」。機知にとんだ裁きで、大岡越前守が江戸っ子どうしの意地の張り合いを取りなすというのがこの噺の標準型。ところが、そこをふつうにやらないのが「志の輔らくご」の「志の輔らくご」たるゆえんである。大岡越前は、こういう一筋縄ではいかない訴えをこそむしろ嬉々として手がけていたふしがあるというマクラから、大岡越前そのひとにスポットをあてた「三方一両損(志の輔らくごバージョン)」へ。お裁きの内容にいまひとつ合点のゆかない江戸っ子ふたりに向かって、「いいのじゃ!(この裁きが)面白いのじゃ!」と訴えるお奉行様。おもしろくないとは言わないけれど、ちょっとひねりすぎ?!
仲入り後のトリネタは、富山の薬売りを題材にした志の輔師の「I♡富山」的新作。これがおもしろかった。今年はパルコ劇場で正月興行をスタートし10年目、しかも北陸新幹線開業のメモリアルイヤーということで富山県を題材にした新作をつくろうと広くアンケートをとったところ、「富山県といえば置き薬」という回答が多かったことからこの噺を思いついたそう。そういえばあったなァ、置き薬。「頭痛にケロリン」とか。
この、富山の置き薬のいちばんの特徴といえば、年に2回の訪問販売、そして使った分のみを精算するという仕組みである。この仕組みのもとになっている考え方を、「先用後利(せんようこうり)」というのだそうだ。はじめて知った。しかし信用のある相手ならいざしらず、見知らぬ客にひとまず商品をタダで預けてしまうというこの仕組みは当時の人びと、とりわけ商人らにとっては画期的すぎて理解ができないものだったらしい。そんな誤解から生じる混乱ぶりを描いたのがこの噺である。
支店を預かる番頭さん、出世のためにはけっして本家をしくじることがあってはならない。そのため日頃から店の様子には人一倍気づかい、小言も多い。ところが、ある日たまたま番頭さんが留守の間に富山の薬売りがやってきて商品をタダで置いていってしまう。ふだんから猜疑心にとらわれている番頭は、なにか魂胆があるのでは?と勘ぐり不安になる。しばらくして後、またまた番頭さんのいないある日、店先で具合を悪くした得意客「近江屋」の奥様に小僧が気をきかせ「置き薬」を使ってしまったから、さァ大変。番頭さんの不安と猜疑心は、妄想でふくれあがりもはや爆発寸前に……。
時代を超え場所を超え、「落語」が落語らしいおかしみを持ちうるためには、そこにはある「お約束」が厳然と存在していなくてはならない。少なくともぼくはそうかんがえる。その「お約束」とは、「落語」は人間なら誰しもが多かれ少なかれ備えもっている「人間らしさ」を描くものだということ。たとえば、落語に登場する粗忽者はもはやファンタジーの域にまで達してしまった超絶な粗忽者にはちがいないが、自分のなかにも、ごく身近な誰かのなかにも「おっちょこちょい」は存在するものだ。だからこそ、心の底から笑える。そこに自分や、身近な誰かの姿を《発見》するからだ。そしてその笑いには罪がない。志の輔師は、たとえそれが「新作」であっても、その落語のなかでこうした「人間らしさ」をきっちり描くことを忘れない。「志の輔らくご」を聴いた後の「ああ、落語を聴いたなァ」という満腹感の秘密は、おそらくその点にあるのではないか。
────
志の輔らくご in PARCO 2015
◎立川志の輔「スマチュウ」※新作
◎立川志の輔「三方一両損」
〜仲入りから
◎立川志の輔「先用後利」※新作
三本締め
2015年1月27日 於渋谷PARCO劇場
万城目学『鴨川ホルモー』
2015.1.28|review
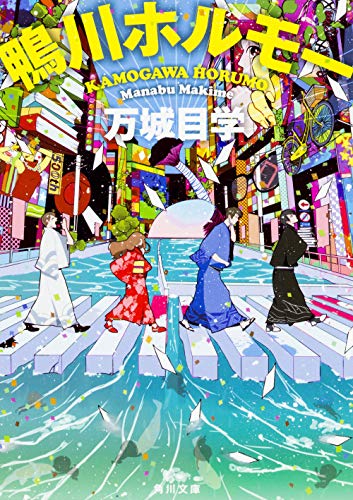
生まれ変わったら、大学生活は京都で送りたい。是が非でも。鴨川の河岸に等間隔で並んだカップルを見て以来、ずっとそう思っている。もしも京都で大学生活を過していたら、この人生もまた相当ちがったものになっていたにちがいない。かえすがえすも残念である。
ひとことで言えば「青春小説」だが、こんな小説の舞台は京都をおいてほかにない。バカバカしさが(だいたい100匹のオニを引き連れた大学生って!)、奇妙にリアルでありうるのは、なによりもここでは「京都の大学生たち」が主人公だからである。憧れと嫉妬をもって読んだこの小説、かなり面白い。悔しいけれど。
最後に、大学生活を京都で送った人たちになにかメッセージするとするなら次のように言わせてもらう。人生におけるあなたのピークはすでに終わっている、と。
「ほんやら洞」支援イベント
2015.1.28|facebook
先ごろ、不慮の火災により焼失してしまった京都の喫茶店「ほんやら洞」。その「ほんやら洞」を支援するイベントが、友人が営む新宿二丁目のカフェ「ラバンデリア」で開催されます。

友人は「アメリカンブックジャム」という雑誌の副編集長だったひとで、かつてイベントの企画担当としてぼくもこの雑誌に参加させていただいていました。そして90年代後半、その「アメリカンブックジャム」の企画として、ビートの流れを汲む詩人らを引き連れこの「ほんやら洞」の2階でポエトリーリーディングのイベントを開催させていただいた思い出があります。
「ほんやら洞」の2階は、いまにして思えば、ほんとうの意味での〝フリー〟スペースだったと思います。あのような空間は、どんなにお金をつぎこんだところで作ることはできません。悔しいけれど、どんなにひっくり返っても東京では無理でしょう。ひとつの《財産》が地上から失われた、火事のニュースを聞いて最初に思ったのはそういうことでした。「今出川のほんやら洞」が、またいつの日かなんらかのかたちで復活することを願ってやみません。
なお、イベント当日は、劇作家の宮沢章夫さん、詩人ヤリタミサコさんらのトークも予定されているそうです。