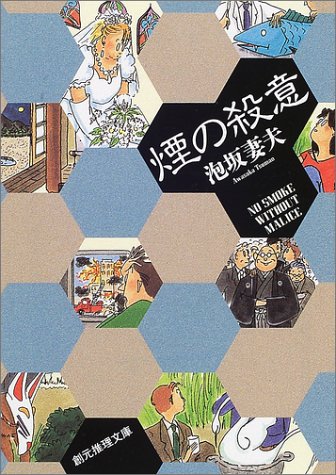夏の朝、すっと気持ちよく目がさめると
2014.8.5|facebook

夏の朝、すっと気持ちよく目がさめると、〝動物〟という本来のありかたからすれば、こうやって明るくなったら目を覚まし、暗くなったら眠りにつくという生活こそが、そもそも人間にとってのいちばん幸福な生き様(いきよう)なのではないか、と思えてくる。
我が家の寝室は、2面ある窓のうち一方にしかカーテンを付けていないおかげで夏には4時くらいになればぼんやり薄明るくなってくるし、窓でも明けていようなら騒々しい鳥の声にどうしてもいちどは目が覚める。いっそ、そのまま起きてしまえばよいようなものだが、床についた時間から逆算し、「あと、2、3時間は寝ておかないとしんどいな」などとかんがえてふたたび眠りにつく。現代にあっては、体内時計よりも、機械仕掛けの時計が刻む〝時間〟のほうがはるかにエラいのである。
「住みやすい国ランキング」といったものがあると、しばしばその上位を北欧の国々が占めていたりするけれど、そう思うと、あくまでもそれは「機械仕掛けの時計に従って生きる現代人にとって」のものであって、人間がじぶんの体内時計とともに生きる〝豊かさ〟とはまたべつの〝ものさし〟によって計られた基準であるということがわかる。だって、夏はほぼ一日じゅう太陽が沈まず、冬は反対に太陽が姿をみせない北欧の国々の自然環境は、他の生きもの同様、冬眠でもしないかぎりはとてもじゃないが暮らしやすいはずはないからである。
アイザック・アシモフのSF小説『鋼鉄都市』では、都市全体を巨大な鋼鉄製のドームによって覆ってしまうことでなんとか快適な環境を保持している〝未来の地球〟の危うい姿が描かれる。ある意味、北欧の都市もまた、さまざまな現代の利器と社会システムという〝ドーム〟によって「住みやすさ」を維持する〝鋼鉄都市〟といえるかもしれない。
北欧とくらべれば、はるかに体内時計にしたがって生きやすいここ日本が本来めざすべき〝豊かさ〟とは、24時間遊べる(ということは、つまり24時間働ける)コンビニエンスな暮らしではなく、もっとべつの社会システムによるものだと思うのだけれど。
〝あたたかい〟コーヒー
2014.8.6|facebook
夏の暑い日に、カフェや喫茶店で〝あたたかい〟コーヒーを飲むのは最高である。カンカン照りの道を汗だくになりながら歩いているときは、絶対アイスコーヒーと心に決めていたはずなのに、けっきょく店に入って注文するのはいつも〝あたたかい〟コーヒー。

エアコンの効いた店内に腰を落ち着け、注文を終え、豆を挽く音に耳を澄ませる。ていねいにハンドドリップされたコーヒーがカップに注がれ、目の前にサーブされるころにはちょうどいい具合に汗も引き、ゆっくりあたたかい飲み物を楽しみたい心持ちになっているのである。なので、そういう、いわば〝間合い〟のない店では、あえてホットは頼まずアイスで済ませたりすることもある。ただ、個人的には、作り置きのお店とか立ったままドリンクが出るのを待っていなければならないようなお店はあまり得意ではないので、そんなには行かないのだけれど。
ところでモイのメニューブックには、ふつう「ホットコーヒー」とか「コーヒー」とか書かれるべきところをあえて「あたたかいコーヒー」と書いている。もちろん、意味は変わらない。日本語の〝あたたかい〟という語感が好き、ただそれだけの理由である。
もしお客様が、物理的に「温度が高い」というだけでなく、そこに「人心地(ひとごこち)がつく」「エンジンが温まる」「おだやかな時間が流れ出す」といった、そんなニュアンスまで感じ取っていただけたならしめたもの。コーヒーカップ一杯分の時間が、よりたっぷり豊かになることは間違いない。
夏の暑い日、カフェや喫茶店で飲むあたたかいコーヒーには、じつは〝間合い〟という目に見えない〝オマケ〟がついてくるのである。
斉須政雄『調理場という戦場』
2014.8.8|review

『ボクの音楽武者修行』のような「読み物」を期待して気軽に手にすると、あるいは肩すかしにあうだろう。
著者の生い立ちやどうして料理人をめざしたかといった事柄は、ここでは一切触れられない。主題ではないからだ。技術論もまた、主題ではない。この本で語られるのは、「コミュニュケーション」をはじめ料理人が「現場」で生き残ってゆくために手放してはならない、いわば「矜持」のような事柄についてである。そしてそれは、右も左もわからないまま単身フランスに渡った著者が、およそ10年にわたるサバイバルのような日々のなかで理解し体得したものにほかならない。
インタビューをもとにリライトしたものなので読みにくくはないはずなのだが意外に読み疲れしたのは、おそらく硬派な著者の人柄から溢れ出る「圧力」ゆえではないか。
ラップランド室内管弦楽団
2014.8.12|facebook
今年の「プロムス」より、フィンランドの指揮者ヨーン・ストルゴーズと北極圏の都市ロヴァニエミを拠点とするラップランド室内管弦楽団による演奏会の模様がオンデマンドで公開されています。2014年8月9日、ロンドンのカドガンホールでおこなわれた「サタデーマチネ」でのライブ録音。
コンサートでは、バロックから近現代までさまざまな作品がとりあげられていますが、どれも夏の土曜日の昼下がりにふさわしく涼やかでチャーミングな楽曲ばかり。
「フランス6人組」のひとりとして知られるアルテュール・オネゲルが1920年の夏、アルプスをのぞむスイスの景勝地ヴェンゲンで作曲した交響詩「夏の牧歌」。フィンランドのヤン・シベリウスが合唱用に書いた曲をみずから弦楽合奏にアレンジした組曲「恋人」は、《恋人》《恋人のそぞろ歩き》《別れ》の3曲からなるロマンティックな音楽だ。スウェーデンのトランペッター、ホーカン・ハーデンベルガーをソリストに迎えての「エンドレス・パレード」は、イギリスの作曲家ハリソン・バートウィッスルによって書かれた1987年の作品。ヴィヴラフォンと弦楽合奏、そしてハーデンベルガーの美音と超絶技巧によって描かれる、さながら北園克衛の抽象詩のような美しい世界。アンコールに演奏されるのは、フィンランドの指揮者にして作曲家ニルス=エリク・フォグシュテットが映画用に書いた「ロマンス」。短いながらも、レーヴィ・マデトヤやトイヴォ・クーラに通ずる甘い旋律が楽しめる作品である。
寝苦しい夜中や真夏の早朝、ぼんやり聞き流すには悪くないプログラムだと思います。4週間限定の配信なのでお早めに。
http://www.bbc.co.uk/programmes/b04d1jc6
銀座
2014.8.13|facebook

ここのところの銀座の変わりようには、行くたび驚かされる。4丁目の交差点にあった「サッポロ銀座ビル」、6丁目の「松坂屋」につづき、とうとう3丁目の「松島眼鏡店」まで閉店してしまった。ここは、小学生のとき天体望遠鏡を買ってもらった思い出の店である。おまけに8丁目の「カフェーパウリスタ」まで改装のため閉店中。あの空間、改装しなくていいのに……。
いっぽう、ここ数年、中央通りを歩いていてやたら目につくのは中国系の観光客たち。集団で行動するうえ総じて声がデカい、しかも舗道の真ん中で荷物整理をしていたりするので(笑)余計に目立つ。一瞬、「ココハ中国デスカ?」と錯覚してしまうほど。
「銀座」という土地の成り立ちについて、中沢新一は著書『アースダイバー』のなかでこんなふうに解説する。
江戸時代、海を埋め立ててこしらえた「銀座」にはそれゆえ歴史がない。やがて江戸幕府は、「貨幣の生産と販売をコントロール」する目的で、京都から銀の職人たちをそのなにもないのっぺりとした土地に移住させる。「銀座」という地名の由来である。
銀座がその後、貴金属店や広告代理店、たくさんのホステスを擁する歓楽街として繁栄しつづけてきたのは、中沢によれば、掘り出された鉱物にさまざまな処理を施すことで「銀」という「高い価値物」を取り出す「婆娑羅な」風体をした職人たちの独特の職能への「記憶」がいまなお人びとのなかに生きているからということになる。いわれてみればたしかに、銀座という土地で幅を利かせてきたのは、みな「付加価値」でひとを惹きつけることに長けた人びとだったという気がしてくる。見た目は変わっても、なにもない下地にその時代時代にあった「化粧」を施しターゲットを惹きつける、そういう銀座という土地の〝本質〟には、じつはなにも変わったところはないのである。
銀座はいま、まさにその新たなるターゲットにむけて化粧直しの真っ最中なのかもしれない。あまりおもしろくはないけれど、しかたない。
デザインをつくるのは
2014.8.17|facebook
あれはあれで嫌いではないけれど、雑然としていて、チープかつ混沌としたヴィレッジヴァンガードの店内は、よくもわるくもいまの日本人の趣味やライフスタイルをとてもわかりやすく象徴しているようにみえる。「とりあえず」という気分で買った雑貨、使っているのかいないのかよくわからない便利グッズやガジェットの類いであふれかえった日本人の中流家庭のすまいが、あの空間のむこうに透けてみえるような気がするからだ。「あったらいいなをカタチにする」企業が人気のこの国だが、「あったらいいな」の反対語は、あるいは「なくてもそれほど困らない」かもしれない。

照明デザイナー石井幹子さんの『フィンランド〜白夜の国から光の夢』(NHK出版)は、20年ちかく前にはじめて手にとって以来、たびたび読み返してきたぼくのいわば〝バイブル〟である。
1965年、27歳で単身フィンランドに渡った著者は、ストックマン・オルノ社でその修行生活をスタートする。当時、主任として切り盛りしていたのは、かのリサ・ヨハンソン=パッペ女史。迷いのない線で光の道筋をデザインした照明器具は、とてもうつくしい。
パッペ女史のアシスタントとして日々をすごすなかで、石井さんは日本のデザイナーとはあまりにちがう「一つのデザインをじっくり時間をかけて、ゆったりとした環境でのびのびとやっている」彼女らの仕事ぶりに驚かされる。「どうして、そういうことでやっていけるのですか」と尋ねる石井さんに、ストックマン・オルノ社のデザイナーたちは口を揃えてこう答えたという。「一つのデザインをつくったら、これが30年、40年と売れればいいのです。一つのデザインの寿命が長ければ、そんなに次々といっぱいつくることはないのです」。
たとえいくらデザイナーがそう考えたとしても、消費者がそれを望んでいなければ、つまり、ひとつのデザインを長く愛するより新しいデザインをつぎつぎ乗り換えてゆくことのほうによろこびを見いだすならば、そうした仕事のやりかたは受け入れられないにちがいない。デザインをつくるのはデザイナーであると同時に、じつはきっと消費者なのである。
池袋演芸場 8月中席 昼の部
2014.8.20|facebook
ひさしぶりの池袋演芸場。トリの鯉昇師はじめ、なかなか豪華な顔付けである。
瀧川鯉昇師のネタは夏らしく「船徳」。船宿に居候している若旦那、みずから船頭を買って出たはいいが「竿は三年、櫓は三月(みつき)」という世界、そうかんたんにいくはずがない。若旦那があやつる船はふたりの客をのせ、ギラギラと真夏の太陽が照りつける隅田川へと危なっかしくも漕ぎ出すのであった……。
まず、鯉昇版「船徳」では勘当された若旦那の徳さんは「質屋の倅」という設定。これがオリジナルなサゲにつながる。とにかく噺の隅々にまで笑いが詰まったこの鯉昇版だが、とりわけいっぱしの船頭気取りの徳さんのしぐさー 鉢巻きの締め方や竿の扱いなど ーがいかにも「まずは見た目のカッコよさ」にこだわる(でもぜんぶ不器用という)「若旦那あるある」で、いちいちおかしい。船が「ななめに」揺れるのも斬新。パニックに陥った客が気を静めようとタバコを吸おうと試みるが、「ななめに」揺れるおかげでうまく火がつかない。この場面のふたり客によるアクロバティックなやりとりの面白さは、さながら古い無声映画のコメディーを観ているかのよう。ついに、文字通りすべてを放り出す船頭。そして思わず呆気にとられる未曾有の(?)サゲへ。
志ん朝師も小三治師も「船徳」はおかしいが、この鯉昇師の「船徳」も最高。聴かせる「船徳」は若旦那のたたずまいがよく描けている、というのが本日の結論。
遊雀師で「電話の遊び」を聴いたのは2度目。遊びにでかけるのを番頭から止められた大旦那が〝テレフォン芸者遊び〟に興じるというごく馬鹿げた噺。そうして、こういう馬鹿げた噺を遊雀師が演るとほんとうに馬鹿馬鹿しくって…… 最高。
桃太郎師「浮世床」。決着は「じゃんけん」でつける囲碁、王様不在の将棋、与太郎もチョイ役で登場し「本」へ。が、『太閤記』に入るまでがひたすら長い。横から訂正が入るたび、音読とおなじ口調で「そうだ」と繰り返して済ますのがおかしい。小三治師「出来心」の「花色木綿」同様、反復の美学(?)。
笑遊師のアレは、いったいなんだったのか…… いや、「替り目」なのだけれど。「元帳」までもたどり着かずダジャレであがってしまった。たんなる「よっぱらい」。
ふだん縁遠いせいか、たまに芸協のベテラン勢の高座に接すると日ごろ聞き慣れた噺がちょっとちがう演出で聴けたりするのが、また興味深い。とくに寄席に頻繁に登場する師匠方の場合、長年高座にかけるたびに剪定を重ねてでできあがった独特の型をもっているようである。蝠丸師の「へっつい幽霊」がまさにそんな感じ。マクラもふくめ15分でおさまるコンパクト版。幽霊は「左官の長五郎」ではなく「半ちゃん」。オリジナルは先代の小さん師? そこに「粗忽長屋」や「狸賽」「家見舞」などべつの噺がちょいちょい浸食してくるという、まさに「寄席のお客さん」を意識したアレンジ。サゲは、もういい加減博打からは足を洗ったらどうなんだと言われた幽霊が、「足がないので洗えません」というもの。
二つ目の夢吉さんは、「自分が田舎者のせいか、どうも江戸っ子気質というのは胡散臭くみえてしまう」とマクラで触れつつ「絵に描いたような」江戸っ子が登場する「強情灸」へ。「おい!」と思わずツッコミたくなるくらいの、過剰な江戸っ子っぷり。馬鹿馬鹿しさを突き抜けて、ある意味、一編のファンタジーにまで昇華されていた。すばらしい。この夢吉さんを筆頭に、芸協は個性派の二つ目がのびのび育っている印象。小助六師や鯉橋師など若手真打ち含め、もっともっと寄席に登場するようになれば足繁く通うのだけれどなァ。
────
開口一番 昔昔亭喜太郎「転失気」
◎三笑亭夢吉「強情灸」
◎ぴろき ギタレレ漫談
◎三遊亭遊雀「電話の遊び」
◎桂米福「持参金」
◎北見伸、スティファニー
◎柳家蝠丸「へっつい幽霊」
◎昔昔亭桃太郎「浮世床」
仲入り
◎宮田陽・昇 漫才
◎三遊亭笑遊「替り目」
◎桂竹丸 漫談
◎鏡味正二郎 太神楽曲芸
◎瀧川鯉昇「船徳」
────
2014年8月19日 於池袋演芸場
カッリオ地区
2014.8.26|facebook

カッリオ地区はヘルシンキのダウンタウン。ダウンタウン(下町)なのに、場所は、急な坂道を登った丘にある。いまでこそ新進アーティストらがこぞってアトリエを構える注目エリアなどと紹介されるけれど、元々は観光客にはまず縁のない〝労働者の町〟だった。
アキ・カウリスマキの映画『カラマリ・ユニオン』では、日々の生活に疲れた風采のあがらない男どもが、そのカッリオ地区を捨て海辺の高級住宅地エイラ地区へと無謀な〝逃避行〟を試みる。じっさいの地図上では、カッリオ地区からエイラ地区へは余裕で歩ける程度にしか離れていないというのが笑えるところだが、にもかかわらず、そこに生きる人びとの暮らしには天と地ほどの隔たりがある、というのがシニカルなことで知られる監督の言いたいところなのだろう。
2008年にカッリオ地区を散策したときには、真っ昼間でもそこかしこによっぱらいが徘徊し、教会の近くでは食事の配給に並ぶホームレスたちが列をなしていた。向こうからやってきたチャイニーズとおぼしきおっさんが、「いま配給やってるぜ」と嬉しそうに教えてくれたのもそのときだ。異国の街で腹を空かせたホームレスとでも間違われたのだろうか。いや、たしかにそのときお腹はペコペコだったのだけれど……。
カッリオ地区のてっぺん、カタツムリのような渦巻き状の道を登り切ったところに小さなパン屋さんがある。おばあちゃんが焼くシナモンロールは、「よくぞここまでたどりついたね」というご褒美のような味がした。
安鶴先生
2014.8.30|facebook
フランキー堺主演の映画『羽織の大将』(昭和35)で、安藤鶴夫は〝念願の〟映画デビューをはたす。やがて落語家になる主人公の大学時代の恩師「安鶴先生」役で登場しているのだ。そして拾い読みしていた『ある日その人』と題されたエッセイに、そのときの興味深いエピソードをみつけた。

安藤鶴夫いわく、なにより苦労したのは寄席でかつての教え子の高座姿を目にした「安鶴先生」の演技だったという。そのとき、まばらな寄席の見物客を相手に、フランキー堺扮する前座の小文(こぶん)が演じていたのは「廿四孝」という噺。安鶴先生は、それを見て「ちぇッ、なんて下手な野郎なんだい」としかめっ面をしなければならないのだが、それができない。どうしてできないかというと、フランキー堺の落語があまりに達者するぎるからである。「軽くって、さらさらとしていて、いきがよくって、愛きょうがあって、いやなんとも巧い」。演技しようにも、うっかり「演劇評論家・安藤鶴夫の耳が、高座のフランキーの落語をきいているから」演技できないのだという。じっさい劇中で披露される落語はどれも、たしかに見事としかいいようがない。そういえば、入門した小文が兄弟子から一番太鼓の叩き方を教わるシーンもあるのだが、こちらも「ドラマー」らしい器用さで華麗にこなしている。
映画じたいは、落語家になる夢をかなえた才気あふれる若者が、時代の寵児としてマスコミに祭り上げられたあげく人生の歯車を狂わせてゆくというほろ苦いストーリー。〝おいしい〟役どころでで準主役級の活躍をみせるのは、なにかと小文の世話を焼く兄弟子役の桂小金治。
小金治(二代目小文治の弟子で、先代の文治の弟弟子)といえば、子供のころワイドショーやクイズ番組の司会者としてよくテレビに登場していた記憶がある。じっさい、小金治は将来を嘱望されていたにもかかわらず、二つ目時代に芸能人として売れまくってしまったため落語界からは遠ざかり、けっきょく真打ちに昇進することもなく高座から引退してしまった。まるでこの映画の主人公そのものだが、小金治が芸能人として活躍するようになるのはさらに数年後のことである。昭和のなかごろは、どうやら落語家にとってなかなか誘惑の多い時代だったようだ。