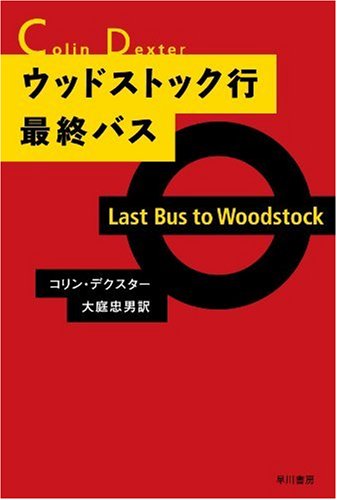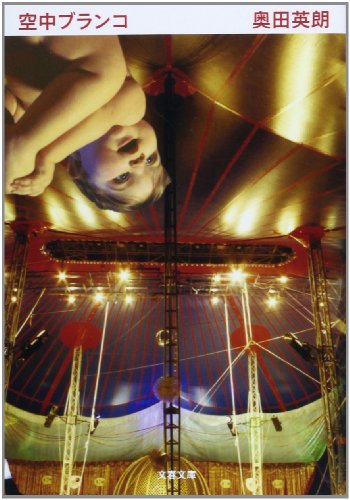広瀬正『エロス』
2014.1.1|review
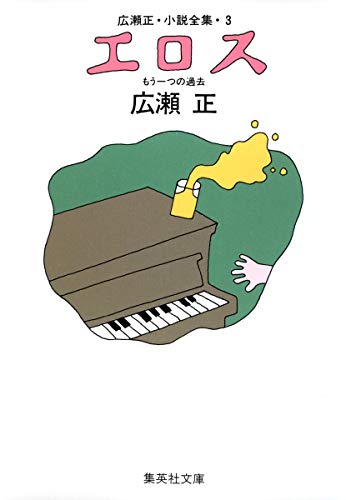
ん?エッ?そういうことだったの!!最後の最後に用意されているオチに仰天させられることうけあい。
東北地方の寒村から上京し、いまや「先生」と呼ばれるほどの大物女性歌手に、ある日ひとりの雑誌記者が「先生が歌手にならなかったら、桶屋式につぎつぎと連鎖反応を起こして、だんだんひろがって、そのあとの日本の姿まで変わっていたかもしれない……」と言ったところから始まる、もうひとつの人生のストーリー。
ふたつの「現実」はそれぞれパラレルに進行してゆくが、この小説の独創的なところは、登場する人々の顔ぶれはほぼ同じにもかかわらず「演じる役割」が異なるだけで〝ほんとうに〟「そのあとの日本の姿」まで変わってしまうという点にある。しかしその結末がどうであれ、これは「みつ子」と「慎一」という男女が紡ぐ大いなる「愛」の物語なのであり、作者があえてこのタイトルにこだわった理由もまたそこにあると思うのだ。
中田永一『くちびるに歌を』
2014.1.4|review

薄めのカルピスを小説にしたような、つまりさっぱり爽やかだけどなんとなく物足りなくもあるような、そんな青春小説である。
舞台は長崎県の五島列島。とある島の、合唱部に所属する中学生たちとそこに赴任した音楽教師との交流を淡々としたタッチで描いた物語。
彼らが出場をめざすのはNコン(全国学生音楽コンクール)と呼ばれる合唱コンクール。Nコンには「課題曲」があり、彼らは、15歳の「ぼく」が未来の自分に宛てて手紙を書くというストーリーをもつ『手紙』という作品を歌うことになる。そして、作品と向き合うため出された宿題(じっさいに未来の自分に宛てて手紙を書くこと)を通じて、15歳の彼らもまた、それぞれがいま抱えている「課題」と向き合うことになるのだった。
感動はないが、ひんぱんに登場する「サクマ式ドロップ」のエピソードなどちいさな仕掛けが最後にジワジワと効いて心地よい余韻を残す。
原宏一『ヤッさん』
2014.1.7|review

第一話「ホームレスのグルメ帳」をもじって「ホームレスのグルメ事件簿」とでもすれば、そのままテレビドラマに仕立てられそうな小説。
訳あって銀座を根城にホームレスとして生きる「ヤッさん」。一方、サラリーマンからドロップアウトし成り行きまかせでホームレスになってしまった「タカ」。そんな「タカ」に、なにより「ありきたりな身の上話」を毛嫌いする「ヤッさん」は、その生き様を通じて〝背中で〟生きることの意味を教え込んでゆくのだった。
〝正論〟を吐く主人公を「ホームレス」にでも設定しないとそのことばが読者の心に届きにくいという現実が、ある意味、現代という時代のややこしさを象徴している。
池波正太郎『殺しの四人 仕掛人・藤枝梅安』
2014.1.9|review
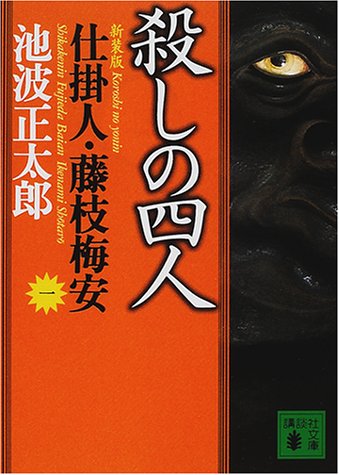
エッセイ以外ではじめて読んだ池波正太郎の作品。
主人公は藤枝梅安。オモテの顔は腕の立つ鍼医だが、「世の中に生かしておいては、ためにならぬやつ」をカネで闇へと葬る仕掛人というウラの顔をもつ。過酷な生い立ちが、彼を裏稼業へと追いやったのだ。そしてもうひとり、同じく仕掛人という顔を持ち、梅安が唯一「友」と心をゆるす彦次郎もまた悲惨な過去を背負って生きているのだった。
作者は、梅安らに「正義のヒーロー」という顔をあたえないが、そのかわり、彼らの存在を認めることで彼らに「居場所」をあたえる。「ためにならぬやつ」を生かしておかぬためには、彼らは生きねばならぬのだ。作者の梅安らに注がれるまなざしはどこまでも優しく、あたたかい。
コリン・デクスター『ジェリコ街の女』
2014.1.30|review

自信満々に誤った推理を展開する、尊大だがどこか憎めないモース主任警部と、お人好しで翻弄されてばかりな反面、モースの推理をたったひとことで崩してしまう意外な鋭さももつルイス部長刑事。そんなふたりの凸凹コンビぶりが相変らず楽しいシリーズ第5作(前回読んだ『ウッドストック行き最終バス』が第1作とのこと)。
イギリスの郊外が舞台だけに登場人物も限られ事件の内容も地味とはいえ、そういうことだったのか!!と唸らせる仕掛けはなかなか。
作者も訳者も『ウッドストック行き〜』と同じなのに、文章のリズムが異なり読みやすかった反面、モースのとぼけた笑いが薄まっていたのはすこし残念。ルイス部長刑事の登場も後半からでやきもきさせられた。
それにしても、このシリーズに登場する中年男性はなぜこうも揃いに揃ってモテるのか……。