シューヴァル&ヴァールー『テロリスト』
2013.9.2|review
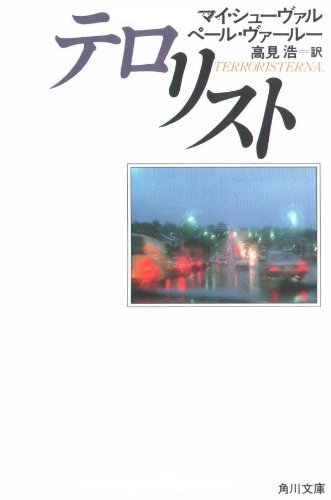
1965年から10年間にわたり、一年一作のペースで発表されてきた北欧ミステリの傑作とされる〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの完結編である。以下は、全10作品を通しての個人的印象。
◎定点観測としての警察小説
現代のスウェーデン社会が抱える問題について、〝定点観測〟的な手法で描き尽くしたいとかんがえた作者マイ・シューヴァル=ペール・ヴァールー夫妻が選んだのが「警察小説」というスタイルだった。犯罪こそは「高度福祉国家」のネガであり、それを職業柄誰よりも冷静にみつめているのが「警察官」という人種だからだろう。ひとによっては、ミステリ的要素よりもときに作者による社会批判的な要素が強調されることに違和感をもつかもしれない。たとえばこの『テロリスト』では、社会システムに翻弄される少女を登場させ、彼女のためにひと肌脱ぐ〝名物弁護士〟の言葉をかりて自分たちの考えを代弁させている。娯楽小説としてはノイズとなりうるこうした部分も、「となりの芝生はよく見える」的にふだん好意的に「北欧」を捉えているぼくらにとっては、〝内側〟からの眺めということで興味深い。
◎アンチヒーローとしての警察官
ここには、スーパーマンはひとりも登場しない。便宜上〝刑事マルティン・ベック〟シリーズとなっているが、他の警察官のほうが活躍する作品もあるくらいだ。全編をとおしてたびたび語られる警察官の〝素養〟とは「論理的な思考力、常識、律儀さ」であり、「すぐれた記憶力、ときとしてロバ並みと称されるほどの頑固さ、それに論理的な思考力」を兼ね備えたマルティン・ベックこそは実直で泥臭い、いってみれば〝警察官の中の警察官〟ということなのだろう。そうした警察官たちが、地道に、少なからぬミスもやらかし、ときに幸運に助けながらも難事件を解決してゆく様に、おなじくふつうの人間であるぼくらは共感をおぼえ、登場人物たちに対しヒューマンな魅力を感じるのだ。
◎笑い
シューヴァル=ヴァールー夫妻の〝笑い〟のセンスが個人的にツボであったことは、続けざまに全10作を読み通す上で大きな助けになった。緊迫した場面で、絶妙のタイミングで挿入されるアキ・カウリスマキ顔負けの脱力系ユーモアは、この〝マルティン・ベック〟シリーズのもうひとつの魅力である。ところどころに往年のコメディアン、ローレル&ハーディの名前も出てくるが、作者のふたりはきっとスラップスティックコメディーにも通じているにちがいない。『テロリスト』でいえば、たとえばテロとは無関係に唐突に起こる暗殺がいい例だが、階段から足を踏み外したかのような錯覚&失笑を読者にあたえ効果抜群。そうした仕掛けに、創作上のテクニックというよりは、むしろふたりの〝遊び心〟を感じる。
〝北欧〟と〝ミステリ〟という、個人的なふたつの関心事を同時に満たしてくれるという点で、このシリーズはまちがいなくぼくにとっては★★★★★だが、ここ最近注目されている「北欧ミステリ」の〝元祖〟ともいうべきこれらの作品が、現在『笑う警官』を除きふつうに書店で入手できないのはとても残念なことである。角川書店には、ぜひ新装版での復刊を願うばかり。
PS.このシリーズを読むことをすすめてくれたアアルトコーヒーの庄野さんに心より感謝!!
のら犬とジェンカ
2013.9.3|column
のら犬をみかけなくなって久しい。ぼくが、小学校の6年生から中学の2年までを過ごした静岡県沼津市には、まだまだたくさんののら犬たちがわがもの顔に町内を闊歩していた。通称〝四つ目〟も、そうしたのら犬たちのなかの一匹であった。黒白の中型犬で、黒い顔のちょうど両目の上にふたつ白い斑点があった。それが、遠目には4つ目あるようにみえるため〝四つ目〟である。〝四つ目〟は、よく言えばフレンドリー、わるく言えば素行のあまりよろしくない犬であった。
ある朝、ぼくは学校へ行くため家を出た。自宅と小学校とは目と鼻の先である。家を出て、駐車場を兼ねた空き地を突っ切り、信号を渡ればもう学校の裏門だった。〝四つ目〟につかまったのは、まさに空き地に入った瞬間である。「よぉ、兄ちゃん、どこ行くんかい?」「が、学校です」そんなやりとりをしながら目も合わさず、足早に振り切ろうとするぼく。そのときである。肩のあたりにイヤな感触をおぼえた。恐ろしくて振り向くことができなかったものの、いままさに起こっていることはだいたい想像がついた。
後ろ足立ちになった〝四つ目〟が、ぼくの両肩に前足をかけている。そう、フォークダンスの「ジェンカ」のかたちである。とにかくぼくはそろそろと、そのままのかたちをキープしながら空き地を横切った。飽きたのか、疲れたのか、思ったほどには面白くなかったのか、信号の手前で〝四つ目〟はどこかに消えてしまった。
家に帰ったぼくはさっそく、その恐怖体験の一部始終を母に語った。ゲラゲラ笑いながら、「面白かった!」と母は言った。窓から見ていたのだ。「助けろよ!!!」そのままグレなかったのが、いまでもふしぎである。
【落語メモ】萬橘師匠の「田能久」
2013.9.7|rakugo
三遊亭萬橘師匠で「田能久(たのきゅう)」をきいた(あらすじ→「落語400文字ストーリー」様)。萬橘師は、〝親孝行〟というよりも、〝久兵衛が一人前の役者になるべく肚を決める〟までのドラマにフォーカスする。そして結果、それが〝親孝行〟につながる。〝親孝行〟はどちらかといえばオマケなのである。
役者になることを決意した倅に、反対するかわり、「田畑は売ってしまうがそれでかまわないか?」と覚悟を迫る母親も、とっさにカツラをつけて女や坊主に〝化けた〟久兵衛に対し、感心するかわりに、「上手く化けたつもりかもしれないが了見がなってない」とアドバイス(?)するうわばみ(大蛇)も、結果的には久兵衛が一人前の役者になるべく〝肚を決める〟後押しとなる。そもそも、巡業先から郷里にあわてて帰るきっかけとなる「母が急病」との手紙も、萬橘バージョンでは、他の役者に人気を持ってゆかれたことでくさった久兵衛による〝自作自演〟という趣向。
最後、うわばみが久兵衛にむかって千両箱(大金)を投げつけるのは、肚を決めた久兵衛がその後ますます芸道に精進した結果、成功して大金持ちになったことをあらわしているのだろうか。「独演会」とは銘打ってあるものの、実質的には「勉強会」というスタンスなのか、手探りの口演ではあったけれど(ネタおろし?)、いずれ、よりブラッシュアップされた〝萬橘版「田能久」〟をきける日が楽しみである。
北村薫『いとま申して「童話」の人びと』
2013.9.11|review
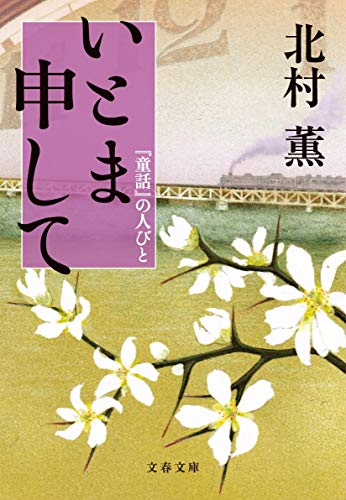
〝父と子の絆〟と言ってしまえば陳腐だが、その残された日記をここまで瑞々しく〝読む〟ことができるのは、読み手が「北村薫」という優れた作家だからという以上に、日記を残した人物の実の息子であるという事実の方がずっとずっと大きいだろう。
旧制中学〜大学予科にかけて、まさに青春時代まっただ中の「父」が記したことばの放つきらめき。それはときに、息子の知る、「謹厳実直を絵に描いたよう」な父親とはまるで別人のように映る。その驚き。冒頭の「スイカ」のエピソードが生きてくる。息子は、その日記のことばを媒介にして父と再会する。そして、その生前にはけっしてかわせなかったような親密な対話を果たす。
北村薫の父「宮本演彦」は、1909年横浜の生まれ。まさに多感な時期を大正デモクラシーとともに生きることのできた〝幸福な〟世代にあたる(同い年に、淀川長治、小森和子、山野愛子、野口久光、浜口陽三らがいる)。児童文学に熱をあげ、雑誌『童謡』の投稿コーナーの常連だった中学時代、おなじ投稿コーナーの仲間だったのが金子みすゞであり淀川長治であった。北村氏のていねいな注釈のおかげで、大正〜昭和初期、1920年代の横浜、東京の風景が鮮やかに立ち上がる。氏の「ベッキーさん」シリーズが好きなひとにはまた、たまらないものがあるだろう。
けっして楽な暮らし向きとはいえないまでも、医者で、地元の名士ともつながりのあった家庭で育った父はまだしも、その日の暮らしにさえ苦労している若者たちまでが熱心に童話や小説を書き、食べるものを食べずに同人誌をつくり、発表していたことにはひどく驚かされる。身銭を切ってまで『狂った一頁』を製作した衣笠貞之助もそうだが、市井の人々の中にもそういう胸に〝熱〟をもった人たちがたくさんいて、そうした人々がそういう時代をつくっていたのだろう。
イワナ様
2013.9.15|column
数年前の話だ。どこか出先で食事をしようと思いファミレスに入ったのだが、ちょうど混み合う時間帯だったため、入口に置かれたウェイティングリストに名前を書き待つことにした。
前のひとにならってカタカナで「イワマ」と記入し、待つことしばし。女子高生とおぼしきアルバイトがメニュー片手にやってきて、こんなふうに言ったのだった。
──「二名でお待ちの〝イワナ〟様」
惜しい!でも違う!!と思ったが、ここでわざわざ言い直すのもなにか大人げないので、心の中では「サザエさんかよ!」とツッコミを入れつつそのまま「イワナ」のまま席に案内され、「イワナ」のまま和風おろしハンバーグステーキなど食べ、「イワナ」のままお会計を済ませて店を後にしたのであった。
そんなことがあってからしばらくしたあるときのことである。同じようにウェイティングリストに記入し空席を待つ機会があったのだが、そのときは家族が名前を記入した。
しばらくして順番がきて、フロアマネージャーらしき人物がぼくらの名前を呼び上げる。
──「二名でお待ちの〝イワナ〟様」
ウソ!?また?!と思い家族の顔をみるとニヤニヤしている。「面白いから〝イワナ〟にしといた」。おい!!
梨木香歩『エストニア紀行』
2013.9.14|review

風変わりな旅だ。梨木香歩は、なぜエストニアを目的地に選んだのか。〝理由〟はけっきょく明かされないまま。にもかかわらず、その旅はこってり濃厚だ。旅をつづけるうち、どんどんエストニアの波長に同期してゆく著者は〝魔法使い〟のようなふしぎな力を備えた者にみえる。そのなかで発せられることばもまた、魔法のことばのオンパレード。
「人が森に在るときは、森もまた人に在る」
「性にまつわるものでも、そうでないものでも、野卑や下品は、世界ぜんたいの豊さを深める陰影のようなもの。そこだけ取り去ることはできない」
「人が自分の生理的な『これ以上はできない』の線引きをする場所は、それぞれ違っていて、その線引きの場所がその人の個性そのものの発露のように思われ、愛おしく感じられる。」
フィンランドと同じフィン・ウゴル語系に属するエストニア人。登場する単語もフィンランド語の響きに近いし、サウナを愛し、森を愛し、孤独を好むというエストニアの人びとの気質は、またフィンランドの人びとのそれに重なる。けれども、その「血」はエストニアの人びとにあってより純度が高く思われる。
彼らにとっての祖国愛とは「おそらく国家へのものというよりも、父祖から伝わる命の流れが連綿と息づいてきた大地へのもの」のように思われる、と梨木はいう。たしかにそうにちがいない。700年あまりの長きにわたって他国の支配を受け続けてきたという過酷な歴史が、彼らエストニアの人びとに「国家」という存在の空しさを教えるとともにそこから引きはがし、結果、コウノトリとおなじようなまなざし〜祖国は大地〜をもたらしたからなのだろう。
もう一度、たっぷりとエストニアを旅してみたいとこの本を読んで思った。
海老沢泰久『美味礼讃』
2013.9.25|review
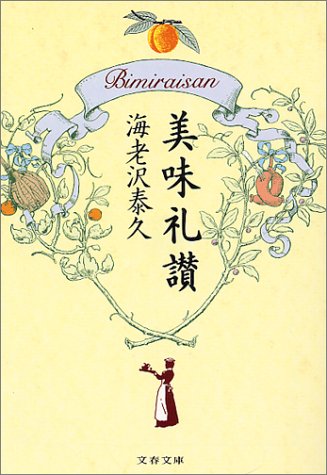
「辻調」こと辻調理師専門学校の経営者にして、日本に〝本物のフランス料理〟を広めた伝道者、辻静雄の半生を描いた伝記風味の物語。
プロの料理人でもない男が、なぜ〝フランス料理の最高の理解者〟としてキラ星のごときフランス料理界の重鎮たちから慕われ、信頼されえたのか?
それは、稀有な「舌」と「探究心」をもつ辻の存在を、彼らが〝ガストロノーム〟として認めたからにほかならない。そこに、料理人と〝ガストロノーム〟と呼ばれる客とのハイレベルな〝共犯関係〟によって栄華を極めてきた、フランスの食文化の奥深さを垣間見ることができる。
実在の人物を取り上げつつ、おそらくはかなりフィクションの要素も多いと思われるが、まるで運命に導かれるように辻静雄が料理の世界へと引き込まれてゆく様は、読んでいてワクワクする。著者のストーリーテリングの巧みさだろう。
高度経済成長前夜、世界へと飛び出した日本人のサクセスストーリーという意味で、小澤征爾の『ボクの音楽武者修行』にも通じる爽やかさも。子供のころ、テレビで『オーケストラがやってきた』や『料理天国』を観るのを楽しみにしていた世代には絶対に手に取ってほしい一冊。
高橋義孝『蝶ネクタイとオムレツ』
2013.9.30|review

大正2(1913)年、東京・神田生まれのドイツ文学者によるエッセイ。この世代によくみられるモダニスト、やわらかい心の持ち主かと思い手にとってみれば、やや期待外れ。
文中しばしば登場する「昔の日本はよかった」「近頃の若いもんは」「女というものは」式な発言は、なんだかおじいさんのお小言に付き合わされているようで、現代のぼくらからするとあまり居心地のよいものではない。とはいえ、エッセイを読むということは、心にピタリとくる一文をみつけるいわば「宝探し」のようなものと思えば、著者のいかにも江戸っ子らしい歯に衣着せぬ物言いと人間への洞察力に富んだ見方には、読んでいて目から鱗が落ちる瞬間も少なくなかった。
たとえば著者は、「はっきり言うと、うまいものは民主主義的ではありえないのである。うまいものは、少数の人間の独占物なのである。いや、そうならざるをえないのではないかと思う」と、〝自称グルメ〟たちがメディアに影響されて一流料理店に押し寄せるような風潮に釘を刺す(「異説・食べもの考」)。この点は、辻静雄の半生を描いた先日読み終えたばかりの伝記小説から受けた印象とも通じる部分があり興味深く読んだ。
また、おなじ文脈から「おしゃれ」を論じるとこうなる。おなじ「平凡な」身なりでも、「さんざん衣裳道楽した揚げ句の果ての平凡」と「ただの何の変哲もない平凡」とではその中身がちがうとした上で、こう言うのだ。「『渋さ』に至るには、その前に華美、派手の段階を通過していなければならない」。
他にも、無用のものへの偏愛を綴った「北海の魚」、エピソードから〝師匠〟内田百閒の〝人物〟をユーモアたっぷりに語った「忘れ得ぬ人々」などもよかった。
文庫版のあとがきは常盤新平、装丁は柳原良平。

