シューヴァル&ヴァールー『笑う警官』
2013.8.1|review
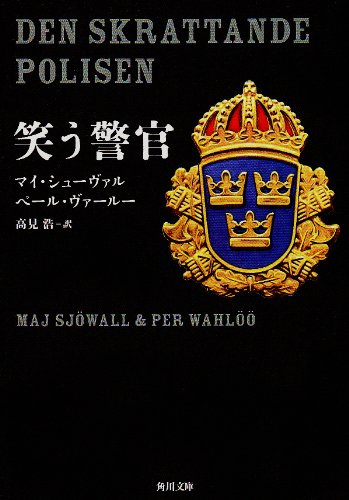
11月。長く厳しい冬の到来という〝現実〟を目の前に突きつけられる、北欧の人びとにとってもっと暗鬱な季節にその事件は起こる。ストックホルム市内を運行する路線バスの車内で発生した銃乱射事件。事件もまた、11月にふさわしく暗鬱だ。
偶然にも、その凶行の被害者の中にストックホルム警視庁の刑事マルティン・ベックの若い部下がふくまれていた。犯行の手がかりを探るため丹念に被害者たちの素性を洗ってゆくうちベックは、部下の死をたんなる偶然の事故として片付けるにはあまりにも不可解だという印象を抱く。やがて、捜査線上に16年前に発生し未解決のままとなっているひとつの殺人事件が浮上する……。
この『笑う警官』は、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの第4弾となるが、このシリーズの魅力は謎解き的な側面以上に、事件捜査にあたる個性豊かな警察官たちによる群像劇と必ずしもうまくいっていない夫婦間の心のすれちがいを描いたホームドラマというふたつの人間ドラマが同時進行してゆくところにあるのではないか。コルベリ、メランデルらいつもの面々は、それぞれの〝領分〟でいつも以上にその持ち味を発揮している。ノルディンやモーンソンら〝地方招集組〟もまた然り(ん?アールベリは?)。
前回から登場した〝憎まれ役〟グンヴァルド・ラーソンは今回もなかなかの舌好調ぶりだが、最後事件について語る言葉に彼に対する読者の印象も変わる。なお、タイトルの意味するところは、最後のページの最後のセンテンスで明らかになるのでお楽しみに。苦笑いと泣き笑いの青年刑事への鎮魂歌。
*北欧の名前になじみのない読者には、あるいは登場人物の名前に苦労するかも…。
シューヴァル&ヴァールー『消えた消防車』
2013.8.5|review

〝スウェーデン・ミステリの原点〟といわれる「刑事マルティン・ベック」シリーズの第5弾。
ストックホルムのダウンタウンで発生したアパートの爆発炎上事故、時をおなじくしてメモにマルティン・ベックの名前を残したまま謎の自殺を遂げた男、忽然と消息を絶った第三の男の足どりを追う中でぼんやりと浮かび上がってくる大規模な自動車密売組織の影……
。事件性の有無さえはっきりとしないまま、ベックらいつもの面々はこの〝支離滅裂〟な事件にずるずると巻き込まれてゆくのだが、この『消えた消防車』最大のみどころはといえば、グンヴァルト・ラーソン〜新人ベニー・スカッケ〜マルメ市警のモーンソンによる〝華麗なる捜査リレー〟だろう。こうした「脇役」たちの渋い活躍ぶりこそがまた、このマルティン・ベックシリーズの魅力のひとつなのだ。
春から夏、夏から秋へと季節が移り変わるのとおなじく、妻との不和、家庭内で唯一の理解者ともいえる娘の自立などベックの家庭を取り巻く景色も様変わりしてゆく。それはまた、厳しい季節の到来を告げる声でもあるだろう。自動車の盗難と密売、家庭崩壊や児童にまで蔓延するドラッグ問題、そして銃器を身につけない主義のコルベリを見舞った不運……
ここではスウェーデンの「負」の側面が拡大鏡でみるように誇張される。このシリーズがしばしば「社会派」、あるいは「スウェーデン社会の変遷をも描くドラマティックな大河小説」(訳者)といわれるゆえんである。とはいえ、テーマは深刻ながらも、随所に散りばめられた北欧流ユーモアのおかげでけっして重苦しいだけの気分には終わらない。モーンソンがおこなった尋問のテープを聞きながら、その予想外の〝巧みさ〟に一同首をかしげるシーンなどすごく可笑しい。これはモーンソンと作者、そして読者だけのヒミツ。そしてもうひとつのナゾ「〝消えた消防車〟は無事発見されるのか?」もお楽しみに。
ブルーノ・マットソンの椅子
2013.8.7|book

プールサイドのブルーノ・マッソン風の椅子に、両目を軽く閉じている全裸の女は、シャーロッテ・パルムグレンだった。(シューヴァル=ヴァールー『サボイ・ホテルの殺人』高見浩訳78ページ)
スウェーデンの南部、スコーネ地方の都市マルメがその小説の舞台である。〝タンバリンスタジオ〟しか思いつかないほどに、ぼくはマルメという街をまったく知らない。スウェーデンの首都よりは、隣国デンマークの首都のほうがはるかに近い(たしか鉄道で40分弱?)ということは知っている。もちろんまだ行ったことはないが、いつか行くことにはなるのではないか。〝希望的観測〟だけど。
マルメには、その小説によると「ヴェストラ・フェルスターデン」なる高級住宅エリアが存在するらしい。事件の被害者にして実業界の大立て者、ヴィクトール・パルムグレンはその一角に建つ豪奢な屋敷に暮らしていた。おなじマルメでも「メレヴォン広場周辺の労働者階級住宅地」の出身であるモーンソン警部は、それゆえ、いい大人になったいまでもこの地区に来ると「違和感」を感じずにはいられない。推測するに、その「違和感」とは「この国には本当に〝平等〟は存在するのか?」という幼い時分から抱きつづけてきた感覚だろう。
こっそり忍び込んだパルムグレンの屋敷でモーンソンが目にしたモノ、それが冒頭に引用した「ブルーノ・マッソン風の椅子」だった。1907年スウェーデンの南部ヴァルナモの生まれ。家具職人を父親に育ったブルーノ・マットソンは早くからその才能を開花させ、人間工学と優美な曲線を融合させた洗練されたデザインで一躍人気デザイナーの仲間入りを果たす。おそらくプールサイドで全裸の女性が横たわっていたのは、1944年に世に出た〝Pernilla3〟と呼ばれる長椅子だったのではないか。いかにもブルーノ・マットソンらしい優美で、こう言ってよければ〝スノッブ〟な匂いのするデザインである。バブルのころ、都心の億ションにはたいがいカッシーナのソファが置かれていた。あ、すいません、見てきたように書いてしまいました…… 置かれていた、らしい。ちょうどこの『サボイ・ホテルの殺人』が執筆された当時、60年代後半の裕福なスウェーデンの家庭には、きっとそんなふうにブルーノ・マットソンの椅子が置かれていたにちがいない。
貧しい地区で育ったモーンソン警部にはしかし、それは「ブルーノ・マッソン風」としか判らなかったのである。
魚を愛でる〜大野麥風のたしかな〝眼〟
2013.8.7|art & design
心に残ったという点で、東京ステーションギャラリーでみた大野麥風(おおのばくふう)の展覧会は、ここ何年かにふれた美術展の中でも五本の指に数えられるものだった。

〝原色木版二百度手摺〟などという気の遠くなるような行程を経て、大野麥風がようやく西宮書院から『大日本魚類画集』の刊行にこぎつけたのは1937年のこと。それから44年までの足掛け7年にわたり6回に分けて全72作品が出版、500部限定で頒布された。この〝大しごと〟のいきさつについてはミステリアスな点が多いという。なぜ麥風は木版にこだわったのか? すでに〝魚の画家〟として知られていた麥風の原画を印刷するのではいけなかったのか? という〝素朴な疑問〟もそのひとつ。
そこには、ふたりの名人〜彫師・藤川象斎、摺師・禰宜田萬年との出会いもあったろうし、また海外の版画コレクターの懐をあてこんだということもあったろう。その〝答え〟は、けれども、会場で原画/摺り見本/完成作を並べて観れば明らかだ。その造形のおもしろさ、色彩のうつくしさ。とりわけ透明感や質量から生み出される生命の躍動といった、写実には叶わないいわば〝本質〟をつかみだすのに、木版という日本の伝統的な、しかしすでに廃れかけた技芸はなんとしても必要だったのだ。そこに、まず洋画を学び、日本画に転向、さらには版画まで手がけた麥風というひとの、たしかな〝眼〟がある。出版に際して、和田三造(監修)、徳富蘇峰、谷崎潤一郎(ともに題字の揮毫)といった当時の有力者たちがこぞって協力したのも頷ける。
もうひとつ、この『大日本魚類画集』には魚類学の権威、田中茂穂、そして釣り研究家、上田尚による解説文が付されているのだが、それらがこの作品に美術書でも学術書でもない独特の〝奥行き〟をあたえているのがすばらしい。とりわけ上田の、ときに詩的、ときにユーモアあふれる解説はたいへん味わい深いものである。
「鯛があでやかな上方女ならば、鱸はいなせなあづま男に見立てたい。(中略)そして鯛に春霞の日の出を聯想せしめ、スズキに涼しい夏の月光をしのばしめる」(「スズキ」)
魚を愛でる。その持てる技能と情熱のすべてをつぎこんだ大野麥風の『大日本魚類画集』を貫いているのは、そんな理屈を超えたピュアなまなざしであり、それが観るものの顔を自然とほころばせる。
前世占い
2013.8.10|column
〝前世〟について話すひとがある。たいがいは、どこそこに〝前世〟をみる能力を持ったひとがいて、ためしにみてもらったところ自分の〝前世〟は◯◯であった、という内容である。
かねがね不思議に感じ、かつツマラナく思っていたのは、そうして話される〝前世〟の多くが「中世ヨーロッパのお姫様」であったり「戦国時代の武将」であったりするからである。いっぽう、〝前世〟が「村いちばんのキノコ採り名人」であったり「フグにあたって死んだ板前」であったり、また場合によっては「一般的なサイズのオニヒトデ」であったりするひととは出会ったためしがない。まるで〝いまの自分よりもステキであること〟が、なにより前世占いの〝お約束〟であるみたいに。
これはその昔、ぼくが友人のそのまた友人から直接聞いた話である。彼女はやはり、なにかの縁で出会った〝その筋のひと〟に〝前世〟をみてもらった。ところが、彼女が聞かされた自分の〝前世〟はちょっと想像の域を超えていた。というか、むしろ納得しがたいものだったという。なぜなら彼女に告げられたその〝前世〟というのが、「ダンプカーの運転手」だったからである。
ただでさえ男前なオーラを醸し出している姉さんが、憤懣やるかたなしといった様子で話す姿にはいかにも「ダンプカーの運転手」という〝前世〟は似つかわしく感じられた。しかし、それはやはり〝占い〟とはまた別ものだろう。なにしろ、それは〝見たまんま〟なのだから。
シューヴァル&ヴァールー『サボイ・ホテルの殺人』
2013.8.11|review
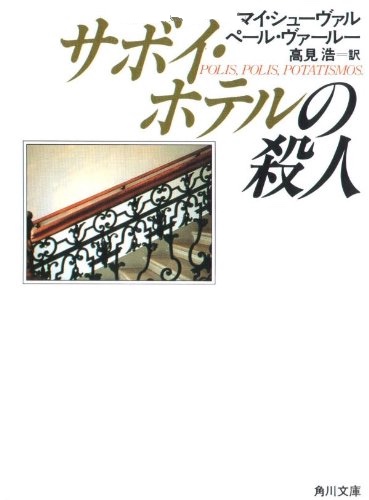
スウェーデン・マルメの高級ホテル、乱入したひとりの男によって射殺された〝ブラック企業〟のワンマン経営者。被害者は、国交をもたない国への武器の闇取り引きで巨万の富を築いたと噂される男だけに身内をふくめ〝敵〟は多い。それが捜査を攪乱させる。けっきょくは、些末な証拠の積み重ねとベテラン刑事の〝勘〟が事件を解決へと導くのは警察小説ならでは。しかし、事件の解決がかならずしも一警察官の気持ちを朗らかにさせるものではないというのもまた事実なのだった。「主任警視マルティン・ベックは、はなはだおもしろくなかった」(文庫版366頁)。
シリーズ〝刑事マルティン・ベック〟第6弾の特徴は、そこで起こる事件以上に、登場人物たちの〝私生活〟と彼らの〝心情〟がいつになくみっちり描かれている点にあるかもしれない。ついに妻との別居を決意したベックをはじめ、中途半端な夫婦生活もいよいよ終焉に近づきつつあるモーンソン、前作のアクシデントをきっかけにマルメに異動したスカッケ、コルベリ、オーサ・トーレル、そして独身主義者グンヴァルト・ラーソンがみせる意外なナイーヴさなどなど。このあたりの〝人間観察〟を楽しむために、読者はやはり第一作から順に読み進めるのがよさそうだ。
公安課のポールソンが道化役としておもに本作でのユーモア担当。そして、意外にモテるマルティン・ベック……うーむ、イメージの修正を図らねば。
2013年 お盆休み中の営業について
2013.8.12|info

そろそろみなさんお盆休みなのでしょうか? 都会なのに人のくらしの匂いがあって自然(井の頭公園)がある、そんな〝東京のヘルシンキ〟吉祥寺に遊びにいらっしゃいませんか?
お盆休み中の「moi」の営業時間は下記の通りです:
8/12[月] 12時〜20時(19時30分L.O.)
8/13[火] 定休日
8/14[水] 13時〜16時 シナモンロールテイクアウト、物販のみ
*カフェはお休みです
8/15[木] 12時〜20時(19時30分L.O.)
8/16[金] 12時〜20時(19時30分L.O.)
8/17[土] 12時〜20時(19時30分L.O.)
*シナモンロールのテイクアウトあり
9/18[日] 12時〜20時(19時30分L.O.)
*シナモンロールのテイクアウトあり
つまり…… 通常営業ですね。
なお、「フィンランド風シナモンロール」は水、土、日のみテイクアウトできます。お取り置きは、日にち、お名前、お電話番号、数、おおよそのご来店時間を明記の上、メールをお願いいたします。当日営業時間内にお電話いただいてもOKです。メールの場合、受付後確認メールを送らせていただきます。
お盆休み中も、みなさまのご来店お待ちしております。
シューヴァル&ヴァールー『唾棄すべき男』
2013.8.13|review
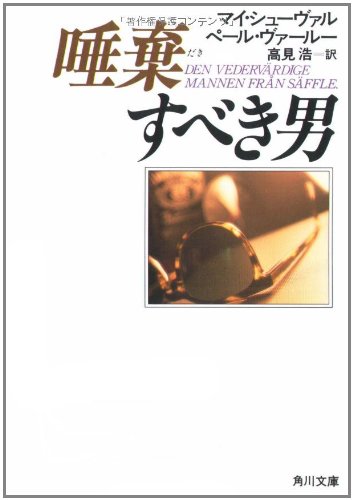
被害者も加害者も、そして捜査にあたる人間もすべてことごとく〝警官〟ばかりという徹底ぶり。それも当然、警察という〝組織〟こそが、ここでの主役なのだから。シューヴァル=ヴァールー夫妻が、〝警察小説〟という形式によって10年の歳月をかけて現代社会を描きつくそうと挑んだモニュメンタルな作品であるこの〝刑事マルティン・ベック〟シリーズもこれで第7弾である。
組織とそこに属す人間が、個と公(©アアルトコーヒーの庄野さん)のはざまで見せるさまざまな顔。職務上、自我を抑圧することが求められる日々ゆえ、ときにはほんとうの自分の顔すらわからなくなってしまうようなことさえある彼ら。無関心はまた、そんな爆発しそうな自我を押さえ込むためのいってみれば〝処世術〟ともいえる。公>個の日本では、同じように組織を描けば硬派な社会派ドラマになるが、個>公、あるいは個と公がおなじレベルで拮抗しているスウェーデンでは、組織を描いてもけっきょくは泥臭い人間ドラマになるのが面白い。そのちがいが興味深い。
ちょっとした会話やふるまいから、水と油と思われていたコルベリとラーソンのあいだの関係に変化の兆しが窺われるのがうれしいところ。これは続刊でのお楽しみ。いつになくド派手な展開ゆえ、映画化に際してこの作品が選ばれたのも納得!?
でも、ラストはそこで終わっちゃって本当にいいの?!
シューヴァル&ヴァールー『密室』
2013.8.17|review
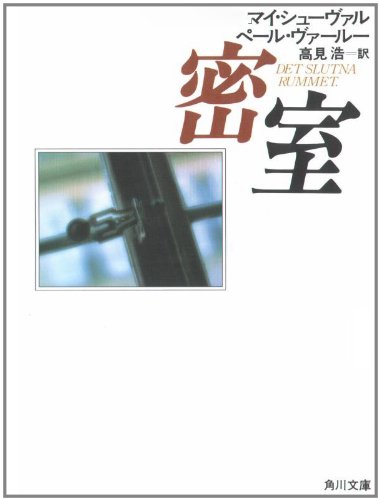
〝密室〟を描くことで、作者は都会に暮らす人びとの深い孤独を浮き彫りにする。1972年当時のストックホルムを覆っていた重苦しい空気について、作者はこんな風に書いている。「暴力は反感や憎悪のみならず、不安や恐怖をも醸成するものである。人々はしだいに互いを恐れるようになり、ストックホルムは不安に怯える数十万もの人々を擁する都市となった。そして、恐怖にすくみあがった人々は危険な人々でもある」(73頁)。そこでは、誰もが被害者になりうると同時に、いっぽう加害者にもなりうる。
そんな、抑圧された現代社会のもとで畏縮した都会人の心もまた、ある意味〝密室〟のように閉ざされている。その点、主人公マルティン・ベックも例外ではない。ようやく負傷からは立ち直ったものの、心に負った傷はまだ癒えていない。そんな折り、現場復帰し不可解な密室殺人事件の捜査に乗り出した彼は、その過程でひとりの生き生きとした女性と出会う。殺伐とした都会にあって、なにより人間的な絆を尊重する彼女の存在にやすらぎを見い出し、少しずつ生気を取り戻してゆくベック。読んでいて思わずホッとする。
密室殺人と銀行強盗、ふたつの事件が複雑に絡み合いながらストーリーは展開してゆく。都会特有のエゴイスティックな情報に翻弄され、身も心も疲れきった警官たち。不注意によるミス、独善的な捜査、情報の読み違い、焦燥感…… そんな負の連鎖の中まんまと網の目をすり抜ける狡猾な悪人の姿もまた、ほかならぬ都会人のもつひとつの顔なのだ。ラスト、現代社会にむける作者の目は、いつになく厳しい。
文中、ドッグフードを食べて細々と命をつなぐ老人という描写がたびたび登場するが、それについてはぼくも以前フィンランド人の知人から聞いたことがある。女性の社会進出が進んでいる北欧の社会保障制度は、そのぶん専業主婦に対してはひどくシビアなのだという。そのため、夫に先立たれ年金の支給を打ち切られた年老いた専業主婦のなかには、やむなくスーパーで手に入れた安価なドッグフードで命をつないでいるひともいるのだとか。まさに〝福祉国家の光と影〟といったところか。
そのあたりの経緯は、巻末に付された訳者によるペール・ヴァールー女史へのインタビューでも触れられている。シリーズが進むにつれペシミスティックな色合いが濃くなってきたのでは?という問いかけに対し、社会民主党政権が導入した「社会主義と資本主義をミックスしたような経済システムはけっして良い結果を生まなかった」と指摘しつつ、けっして当初から社会批判的なものを書こうとしていたわけではないと語る彼女。「つまり、この十年間におけるスウェーデン社会の変化が、わたしたちにペシミスティックになることを強いたと受けとっていただきたいわ」。
給水塔
2013.8.20|book
どこか恐ろしくも魅力的なのが、「給水塔」と呼ばれる建造物である。〝恐ろしくも魅力的〟という点で、ぼくにとって「給水塔」は「不協和音」にも通じる。不意に挿入されるモーツァルトの不協和音に、ひとは〝驚く〟よりもむしろ〝不安〟をおぼえる。おなじように、ごくありふれた街並に忽然と姿を現す「給水塔」の存在も、まるでそこだけが〝現実の中の非現実〟であるかのようにひとを不安におののかせる。
道に迷って偶然出くわした大谷口の給水塔。まるで松本竣介の絵のような、鉛色の空を背景に屹立するその威容をいまだ忘れることができない。わざわざバスに揺られて野方まで給水塔(配水塔)をみにでかけたのは、東日本大震災のすこし前のことだった。「この揺れで、あの給水塔は無事だろうか?」地震の中でそんな思いがふと頭をかすめたのは、「給水塔」のもつ〝街の不協和音〟としての強い印象ゆえだろうか。
スウェーデンのマルメに現在では共同住宅として使われている「給水塔」があると知ったのは、シューヴァル=ヴァールーのミステリ『サボイ・ホテルの殺人』で犯人が暮らすキルセベリ地区を描写するなかにそれが登場しているからだ。それはマルメ市のイーストサイド、「〝ブルトフタの丘〟とも、単に〝丘〟とも呼び慣わされている」すこしばかり殺伐としたダウンタウンに建っている。
「給水塔とは名のみで、実はかなり前から一般住宅に改造されている塔だった。中の部屋はさしずめパイのような形にでもなっているのだろうか。いつか新聞に、その改造住宅の衛生状態たるや不潔きわまりないもので、住民は九分九厘ユーゴスラビア人が占めているという記事が載っていたことを、スカッケは思い出した」(『サボイ・ホテルの殺人』高見浩訳 349頁)。
その給水塔は、第一次世界大戦さなかの1916年、避難所として貧しい人々に解放されたのをきっかけに本来の役割を失い、もっとも多いときで200人あまり(!)の人々ががそこで生活するほどの過密ぶりだったという。一種スラムと化していたのだろう。その後、民間の不動産会社がリノベーションを施し、現在では眺望に恵まれた高級アパートとしてなかなかの人気ぶりなのだそうだ。調べてみると、世界のあちらこちらに、いまは住居として第二の人生を送っている給水塔があるらしい。それはたしかに〝魅力的〟ではあるかもしれないが、ひとが暮らす「給水塔」に〝恐ろしさ〟はない。
内に満々と水をたたえた見上げるほどの塔、水の塔、そのどこか矛盾した存在様式にこそ「給水塔」の〝ひみつ〟が隠されているような気がしてならない。
テレビとわたし
2013.8.24|column
ただでさえテレビを観ないのに、夏になるとますますテレビから遠ざかる生活になるのは、ひとえに〝暑さ〟のせいである。というのも、我が家のテレビのある部屋にはエアコンがない。あれは去年のことだったか、仕事から帰りその部屋に置いてある温度計を見たところ「37℃」あったことがある。ちなみに、おなじ日のインドの首都の最高気温は「32℃」だった。こうなると、テレビを観ているのかガマン大会に参加しているのか、もはやわからなくなるレベルである。
つい先日のことだ。スタッフと、テレビ東京のある番組の話をしていて思わず「12チャン」と言ったところ、彼女の頭上にクエスチョンマークが3つくらい浮かんでいるのがみえた。恐ろしいことに、いまテレビ東京は「7チャン」なのだという。そう、未だに我が家は「地デジ化」されていない。テレビをつけると、画面の上下に「デジアナ変換。このサービスは2015年3月末日をもって終了します」というテロップが流れつづけていて観づらいことこのうえない。しかも、元々15インチほどしかない小さなテレビなのに上下をテロップに占められているせいで、いま観ることのできる画面は実質12インチを切っているのではないか。おかげで、我が家でみるAKBのメンバーはみんなとても可愛い。
そういうわけだから、もちろん、録画機能などという便利な機能は備えていない。テレビ番組は放映時間に観るもので、それを逃したらもう二度と観ることの叶わないものである。以前はビデオデッキを所有していたこともある。自慢じゃないが「S-VHS」とかいうやつだった。最近ツイッターのタイムラインなど眺めていると、曜日、時間を問わず「あまちゃん」を観ているひとびとがいて、いくら人気だからって公共放送が四六時中「あまちゃん」ばかり放送するのはいかがなものか? とおののいていたところ、みな録りためたものを休日などにまとめて観るのだという。録画は、3倍モードで最長8時間までと思っていたのだが……。
あればあったで観るけれど、なければないで済んでしまう。現在のじぶんの生活における「テレビ」の重要度は、おそらくピラフの上にふりかけるパセリと同じくらい、そう感じている。
マイ・シューヴァル『警官殺し』
2013.8.25|review
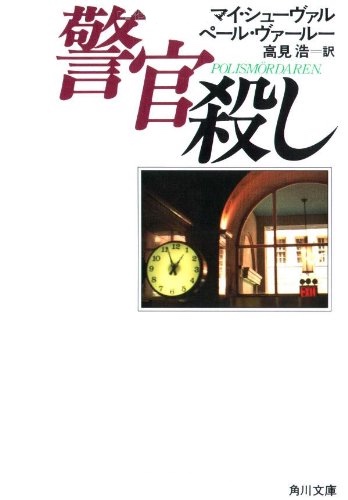
過去に登場した警官や犯人の〝その後〟を描き、〝主役〟にコルベリを据えた、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズのいわばスピンオフ的作品。
完結編を前に、ここで読者は作者とともにいったん立ち止まり、これまでの〝時間〟をあらためて確認することになる。よって、他の作品は単体でもじゅうぶん読むことができるが、この作品にかぎっては過去の8作品を読んでいないことには愉しみも半減してしまうにちがいない。
個人的に、このスウェーデンミステリの傑作シリーズで好きなのはシュールでアイロニカルな〝笑い〟の要素である。なので、前作に付された作者マイ・シューヴァル女史への訳者によるインタビューでそのあたりの〝秘密〟が触れられていなかったのがすこし残念だったのだが、ここでも『警官殺し』というタイトルふくめそうしたユーモアにあふれている。アキ・カウリスマキの映画にも通ずるこの〝笑い〟こそ、まさに北欧的だと思うのだ。
レゴの青色とスウェーデンのスニーカー
2013.8.26|column
レゴの「青色」は、ぼくら日本人が思う「青色」からするとすこしばかり暗い。ところが、その「青色」も緯度の高い北欧の〝光〟でみるとちょうどよく、とても美しくみえるのだという。むかし、そんな話をなにかで読んだ気がする。
たとえば、旅先の北欧で撮った写真を誰かにほめられる。「もしかして写真の腕が上がった?」なんて思ってしまいがちだが、どうやらこれも緯度の高い北欧の〝光〟のなせる技らしい。波長の短い北欧の〝光〟が、〝ふつうに〟撮っても引き締まった輪郭とヴィヴィッドな色彩をもたらしてくれるのだ。
つい最近、スウェーデン製のスニーカーを手に入れた。なにげなくネットを徘徊していて偶然みつけたものだ。セールで値段も安かったので、あまりかんがえることもなく購入してしまった。色はたしか、「ブラック」「カーキ」それに「ベージュ」の3色用意されていたのだが、ぼくが手に入れたのは「ブラック」。あまり印象の重くなりすぎない黒のスニーカーをちょうど探していたのだ。
ところが、ネットでいくつかのショップを回っているうち気になるコメントを目にした。《ブラックとありますが、実際にはネイビーに近いです》。たしかに、画像によってはそうみえなくもない。おそらくは薄墨色だろう、勝手にそう解釈して買ってみることにした。
〝ほぼネイビー〟だ。
届いた荷物を開けて、ぼくはそう思った。黒と薄墨なら、まあイコールで結べないこともないが(個人的に)、黒と紺は…… なかなか厳しいものがあるのではないか。とはいえ、基本〝出されたごはんは残さず食べる〟タイプである。そこで、こう考えることにした。
このスニーカーは、北欧の〝光〟でみると「黒」にみえます。
橘蓮二『カメラを持った前座さん』
2013.8.28|review
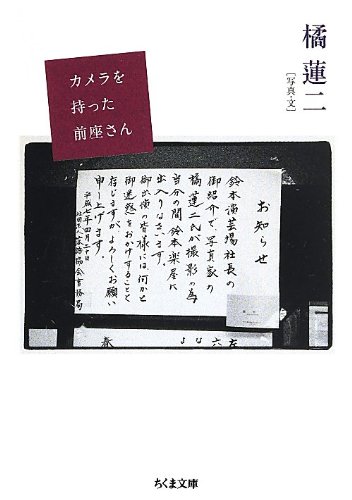
まさに「決定的瞬間ならぬ演芸的瞬間」!
時間調整のために入った本屋さんで、たまたま手にとりパラパラめくったが最後、そのままレジへ直行。よっぽどのことがないと、ふだん写真集は買わないんだけどなァ……。
ここで被写体となっている噺家の姿から伝わってくるのは、落語が、〝没入〟と〝俯瞰〟のギリギリの均衡の上に初めて成立する至芸であるということ。その所作は即興などではなく、練って練って、練り上げられてできたカタチなのだというのが手に取るようにわかる。その意味でも、オフショットではなく、高座での写真が多いのもうれしい。木之下晃が撮影した演奏家の写真からそのひとの音がきこえてくるように、橘蓮二というひとの写真からもまた、たしかに、そのひとの声がきこえてくるからだ。
「橘蓮二は十八年前、演芸に救われた写真家です」というあとがきの一節に集約されるような、それぞれの芸人に寄せたエピソードも淡々としているぶん、余計に心にしみる。いい買い物をしました。
