橋本千代吉『火の車板前帖』
2013.7.3|review
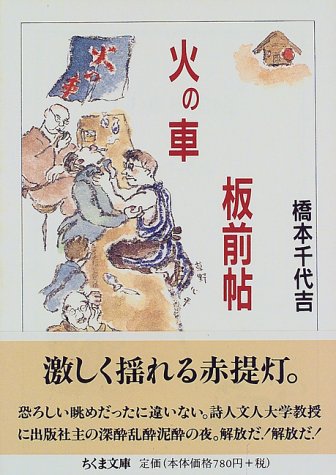
迷惑千万な人々。「商売を始めたら、手伝ってくれるね?」「ああ、いいですよ」うっかり返事してしまったばかりに、ある日突然、詩人・草野心平が開いた居酒屋の板前をやらされることになってしまった千代吉さんの怒涛の日々を綴った回想記。
しかし、それにしても、そこに集う人間どもの、揃いも揃ってなんと迷惑千万なことか。営業時間は完全無視、深夜に板前を拉致して他人の家を強襲、店主も入り乱れての殴り合いの喧嘩は日常茶飯事、増える一方の借金……ハッキリ言って常連客のほぼ全員が酒乱である。それがまた、みな綺羅星のごとき作家や文化人、事業家ばかりなのだから空いた口もふさがらない。そしてその喧騒に付き合わされ、尻拭いをさせられるのはいつもきまって千代吉さんときまっている。
それでも、たとえどんな目に遭わされようとも、千代吉さんの心平さんに対する忠誠心、忍耐強さ、心優しさは変わらない。本当に、千代吉さんは心平さんのことが大好きなんだなァ。
PS.思いがけず、戸板康二の名前が出てきたのには驚いた。彼もまた、酒好きらしく「火の車」の客人だったのである。
ヘニング・マンケル『目くらましの道』
2013.7.8|review

◎ 上巻
史上最悪の夏休み。白夜の北欧スウェーデンのスコーネ地方が舞台のクライム・ノベル(厳密には”警察小説”というらしい)。
北欧が、表面的にはもっとも美しく明るく輝く季節に、その裏側で繰り返される凄惨な殺人事件。その極度のコントラストは、ごくふつうの生活を送っている人間がその裏では陰惨な事件を引き起こすもうひとつの顔を持っている、というこの作品の中の犯人像と重なる。
主人公の警部ヴァランダーの「繊細さ」「小心さ」が、ときに捜査の上では武器になっている反面プライヴェーとではぐだぐだなところが可笑しい。

◎ 下巻
ふだんは人一倍読むのが遅いのに、半日で読了。新記録。
センテンスが短いのでリズムよく読み進むことができる。淡々と進みながらもいや増してゆく緊張感。訳者の手腕かもしれない。
北欧のひとびとがいかに夏休みを楽しみにしているか? 彼らがどのように夏を過ごすのか?
マイペースで、いなたい登場人物たち……(事件は悲惨だが、なんとなくの〜んびりした印象なのはそれゆえ?)。「北欧の人と暮らし」という視点から読んでも、なかなか興味深い一冊。
レーナ・レヘトライネン『雪の女』
2013.7.14|review

フィンランドを舞台に、女性刑事マリア・カッリオが活躍する警察小説だが、主人公はもちろん、被害者や被疑者にいたるまでそのすべてが「女性」という一風変わったミステリ。作者レヘトライネンも当然、女流。
ある冬の日、雪に覆われたヘルシンキ近郊の森の片隅で、男子禁制のセラピーセンター「ロースベリ館」の女主人が死体となって発見される。さっそく捜査に乗り出す男勝りのマリア。ところが、犯人探しと平行して、マリアの身に、《女性》性を意識せざるをえないある事件が起こるのだった。そして、突然見舞われた状況に逡巡しながらも、星座をつなぐように事件の真相は徐々にその全貌を明らかにしてゆく。
世界的にも女性の社会進出が進んでいることで知られるフィンランドから、こうした切り口の作品が登場することが興味深い。必ずしも、男女平等の夢の国ではないという現実。社会制度とはべつのところに、厳然と存在しつづける性差をめぐる差別意識の根深さ。現代の北欧社会が抱えるさまざまな問題を知るうえでも、とても参考になった。
全体にほろ苦いストーリーであるが、そんな中がさつなマッチョイズムの権化のようでありながら、マリアに対して人一倍繊細な気遣いをみせる同僚ペルッティの存在が微笑ましい。
シューヴァル&ヴァールー『ロゼアンナ』
2013.7.18|review
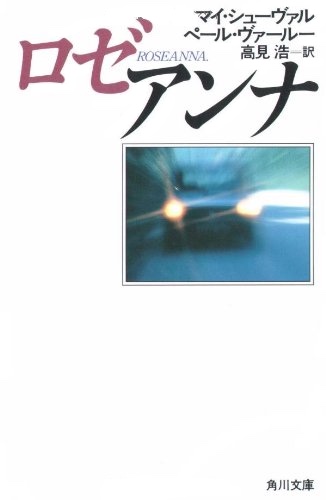
シリーズ「刑事マルティン・ベック」第一弾。犯人の動機に意外性があり、またそこに1960年代当時のスウェーデン固有の匂いのようなものが感じられる。
主人公が「頑固」「論理的」「沈着」という「警官として誇るべき3つの貴重な資質」に恵まれているのは本当としても、とはいえ、けっして「全能ではない」という点で警察小説ならではの醍醐味(?)は健在。じっさい、ここでも、地方の警察署や婦人警官、アメリカの片田舎の刑事などさまざまな個性的なメンツを巻き込みながら難事件の捜査は進められてゆく。それはけっしてすべてにおいて美しいチームワークとはいかないが、いざという場面でそれぞれが自分の役割を見事に演じ切っているところが気持ちいい。
美しく輝かしい夏に湖水地方で発生した事件が、なんの解決の糸口も見出せないまま季節は移ろい、秋を過ぎ、やがて不毛な冬へとさしかかる。この季節の経過がもたらすやるせなさに北欧人マルティン・ベックの焦燥感がシンクロし、沈鬱なムードを醸し出す。相手の性格を見抜き、巧みな尋問で自白を引き出してゆくマルティン・ベックの手腕はお見事。次作への期待も高まる。
持っているのは角川文庫の旧版。古書で探すなら新版(画像)より、日暮修一による装丁のすばらしい旧版の方をおすすめしたい。
名前
2013.7.20|column
鉄道好きのエヌ氏、子どもに名前をつける際、さっそくかねてから温めていた《こだま》という名前を候補に挙げた。すると、「《ひかり》も《のぞみ》もある時代になんで《こだま》なのよ!」と奥様から即却下されたという。
「夢の超特急」なのに鈍行という、堀江敏幸が好みそうなその〝慎ましさ〟にあえてこだわる旦那の気持ちもなんとなく理解できるし、そのいっぽうでいかにも常識人にふさわしい奥様の反応にも納得がゆく。このあたりのバランスが「夫婦の妙」というか、戸板康二的ちょっといい話で毎度思い出してはホクホクしてしまう。
けっきょく夫婦の合意のもと、その子にはべつの、思いのつまった夢のある名前がつけられた。もちろん、《ひかり》でも《のぞみ》でもない。
選挙
2013.7.21|column
参院選。結果はあらかた出ているようなものとはいえ、白票を投じたところで無意味だし、政権与党に対するなにがしか「セーフティーロック」のような仕掛けはやはり必要だと思うので、考えに考えて、そこが〝予想外に〟票を伸ばしたら政権与党としては(心理的に)さぞかしやりづらいだろうなァと思われる政党に一票を投じてきた。「対抗馬がいないのでこういうことになってるけど、けっしてアンタらを信任してるわけじゃないんだからね」という意思を示すことで勝利の美酒にイヤ〜な後味を残せればという、地味かつまわりくどいささやかな抵抗である。
支持政党を「持たない」のではなく「持てない」、というのは自分も含めおおかたの日本の「無党派層」の感じているところではないか? 毎度毎度、選挙のたびにあの手この手で「清き一票」の使い道を考えてはいるのだが、徒労感にとらわれることも少なくない。固有の支持政党をもつ人だけが熱心に投票に出かけ、結果ますます無党派層は政治離れしてゆく。ずっとむかしから、日本の政治風土をかたちづくってきたのはそうした構図なんじゃないかなァ。
ソーダ水
2013.7.22|food & drink
なんて秀逸なメニューなんだろうと、「ソーダ水」を見てかんがえる。「ソーダ水」の秀逸さは、もちろんその「色」にある。メロンソーダの緑(みどり)とさくらんぼの赤(あか)。ただの緑と赤ではない。それは「ありえない緑」であり、「ありえない赤」である。あんなヴィヴィッド過ぎる配色の食べ物、ふつうの家庭にあるだろうか?(いや、あるまい。反語調)。そう、ないのである。「ソーダ水」とはつまり、喫茶店にしか存在しない神秘そのものであり、「ソーダ水」というメニューがあるかぎり「喫茶店」もまた妖しい輝きを放ちつづけることができる。
子どものころ、たまに親に連れられてゆく喫茶店ではたいがい、「ソーダ水」か「クリームソーダ」を飲んでいた記憶がある。「レモンスカッシュ」や「コーラフロート」、「バナナジュース」といったメニューも魅惑的にはちがいなかったが、子供心に「もしかしたらあれなら家でも飲めるかもしれない」という打算がはたらき、けっして家では飲ませてもらえないようなありえない緑とありえない赤が織りなすシュワシュワする誘惑の前にとたんに色あせてしまうのだった。あんなにカラダによくなさそうなものを、だれからも叱られることなく公然と口にすることができる喫茶店という場所はなんて素晴らしいんだ! 目の前の「ソーダ水」をうっとり眺めながら、少年はかんがえる。そうして、いつでも好きなときに喫茶店に入れて、しかもどれでも好きなメニューを注文できる大人の〝豪奢〟について思うのだった。大人はときに、そうした〝豪奢〟を忘れがちである。
Vampire Weekend
2013.7.25|music

ヴァンパイア・ウィークエンドの3枚目のアルバムを聴いているうち、ふと〝ペイズリーアンダーグラウンド〟などという、とっくの昔に忘れたはずの単語が思い浮かぶものだからすっかり可笑しくなってしまった。
思うに、60年代と80年代はあるメンタリティーを共有しているという点において〝地続き〟であった。レインパレード、グリーン・オン・レッド、ドリームシンジケート…… 80年代初頭、アメリカ西海岸のカレッジシーンに突如巻き起こった〝ペイズリーアンダーグラウンド〟は、まさにそのことを裏付けるムーヴメントといえた。当時、彼らが奏でる60年代後期風のガレージサウンドを〝時代錯誤〟とかんがえるひとは少なかったのではないか。それほどまでに、それはごく自然に80年代の空気になじんでいたのだった(全体的にスパイスに乏しすぎるきらいはあったけれど)。
これといった根拠があるわけではないが、60年代、80年代は、つぎに00年代と〝地続き〟になるだろうという漠然とした予感があった。じっさいのところ、00年代にそれらしい動きは感じられなかった。ようやく00年代の後半になって、80年代のヒットソングの安易なカヴァーやあけすけなサンプリング、ペナペナなシンセサウンドが目立つようになってきた程度だろうか。
それがいま、やや到着は遅れたものの、10年代は60年代、80年代と〝地続き〟となったことを、最近リリースされた『Modern Vampires of the City』というヴァンパイア・ウィークエンドのCDを聴いて確信した次第。そのサウンドがどうのこうの ー60年代ぽいとかNWぽいとかー いったことではなく(もちろんそういう〝匂い〟はたしかにあるにせよ)そこには、あのメンタリティーが、〝柔なくせに時代にむかって牙を剥いてみせるような〟メンタリティーがわんわんとアルバム全体にわたって五月蝿いほどこだましているからである。
シューヴァル&ヴァールー『蒸発した男』
2013.7.25|review
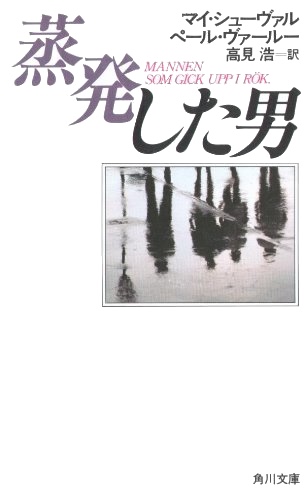
刑事マルティン・ベック、シリーズ第2弾は東欧ハンガリー編。冷戦下のブダペストで忽然と姿を消したスウェーデン人ジャーナリストの行方を追って、夏休みを〝24時間〟で切り上げたマルティン・ベックは単身ハンガリーへと飛ぶ。彼をつきうごかすものはただ、「どんな任務でも引き受けて、解決にベストを尽くそうとする本能」、一種の「刑事根性」にほかならない。
東西が分断された冷戦下のヨーロッパにあって、政治的な思惑から思うように進展しない捜査、麻薬密売組織、尾行者の影……
とさまざまなに伏線を張りめぐらしながらも真犯人は意外なところに。前作『ロゼアンナ』のカフカ刑事につづき、ベックは今回もハンガリーですばらしい協力者を得る。幸運な刑事なのだ。〝水と油〟な印象の同僚コルベリとも、ますます不思議に息があってきた。
犯罪小説と呼ぶには、前のめりになった読者を軽くいなすような結末はあまりに淡白すぎる気もしなくもないが、いっぽうで、絵葉書のように風光明媚なブダペストの夏を堪能できるのがこの本の最大のポイントとなっている。それは、待ちに待った夏休みを取りあげたことに対する、作者からのベック刑事へのせめてもの「罪滅ぼし」だろうか?
土曜ワイド劇場的な観光気分も満点。ラスト、バカンスに戻ったベック刑事に対する妻の態度が、不気味(笑)。
ブロック抜け
2013.7.27|info
〝散歩の達人〟植草甚一に、たしか「ブロック抜け」という秘技があった。それは、マンハッタンのあるブロックからべつのブロックに移動するのに、途中ビルディングの中を通り抜けたりすることで最短のルートで辿り着けるといったものだったと記憶している。
ところで、この夏も暑い。願わくは、日中おもてなんぞ歩きたくないものである。ぼくがそう思うくらいだから、吉祥寺の駅から約600メートル、徒歩で6、7分かかる「moi」にお客様がいらっしゃらない理由(ワケ)もよくわかる。当然だ。しかし、だからといって納得しているわけにもいかない。そこで思いついたのが、〝J・J氏〟こと植草甚一の考案による「ブロック抜け」である。
東急百貨店北側から店へと至るラスト200メートルの直線はしかたないとして、この「ブロック抜け」のワザを駆使することで、全行程の2/3にあたる約400メートルはひんやりエアコンの効いた涼しいところを通ってこれるのではないか。人間やっぱりアタマを使わなきゃね。
まずは、吉祥寺駅の西改札からそのままアトレ本館(2F)に入る。
↓
パークサイドコート(ブック1stの先)のエスカレーターで1Fへ。
右手すぐの出口から外へ。
↓
道路を横断し、正面の「パルコ」に入る。
入って左手に進み、公園通り方面の出口から外へ。
↓
50メートルほど直進、道路を渡り「東急百貨店」に入る(南口)。
館内を対角線上に突っ切り「北口」から外へ。左手へ直進200メートルで到着!!
ためしに気温が30℃を越える夏の昼間、この「ブロック抜け」を実践してみることで吉祥寺駅から「moi」に辿り着くまでに必要とするエネルギーの約50%を節約することができた(注「個人の感想であり、効果・効能を確約するものではありません」笑)。ぜひ、この夏「moi」にいらっしゃるお客様はこのルートをご活用下さい。ただし百貨店の営業時間内しか使えないこの「ブロック抜け」、故に〝考案者〟であるぼく自身はまったく恩恵にあずかることができないのだった。ぐぅ。
シューヴァル&ヴァールー『バルコニーの男』
2013.7.28|review
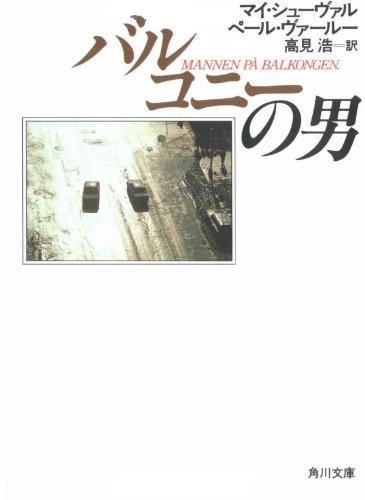
〝刑事マルティン・ベック〟シリーズ第4弾は、ストックホルムが舞台。「都会」が舞台ゆえ、ここではさまざまなパターンの「目撃」がストーリーを生んでゆく。見ていないようで見ていたり、偶然に見たり、こっそり見たり、あるいはまた見ているようで見ていなかったり……都市では無数の視線が交錯し、事件はその網の目のすきまに起こる。いわゆる都市型犯罪である。
連続強盗事件と連続少女誘拐事件、ふたつの神出鬼没に発生する事件を追いかけるマルティン・ベックらいつもの面々(今回新たに「グンヴァルド・ラーソン」なるなかなか強烈なキャラクターが加わる)は、クモの巣のように複雑に入り組んだ無数の「視線」に絡めとられてしまったか、今回ばかりはいつになく切れ味が鈍いようだ。そのかわり、ここでは市中を巡回している警官たちが思わぬ活躍をみせるが、それは彼らもまた、ある意味〝都市の目撃者〟なのであり、ときに「見ること」にかけてはマルティン・ベックら以上に〝プロ〟と呼べるからである。しかしこの、あえて「ヒーロー」をつくるのを拒むかのようなラストの呆気なさは前作同様。そこがまた、いかにも北欧らしくもあるなぁ。
5種類ある!
2013.7.29|book

5種類ある! 古本屋から届いた包みをあけたぼくは、思わず声を上げた。たしかに、注文した本にはちがいない。それはまちがいない。ただ、思っていたのと、カヴァーがちがったのである。
アアルトコーヒーの庄野さんにすすめられて、ここ最近スウェーデンの作家マイ・シューヴァル=ペール・ヴァールー夫妻による警察小説〝刑事マルティン・ベック〟シリーズを読んでいるのだが、これがめっぽう面白い。一人の、超人的キャラクターが八面六臂の活躍で難事件を解決へとみちびく〝探偵もの〟よりも、等身大の人間臭いひとびとが四苦八苦しながら事件の核心へとジリジリ近づいてゆく〝警察小説〟のほうに親しみを感じてしまうのは、ぼく自身また不器用な凡人だからだろうか。ストックホルムの街を舞台に、いかにも北欧人といった風情のひとびとが奔走するのもぼくにとっては魅力的なポイントである。
〝事件〟は、シリーズ第4作にして最大のヒット作『笑う警官』を手に入れたときに起こった。この〝刑事マルティン・ベック〟シリーズは全10作、日本では1971年から83年にかけてそのすべてが角川文庫から刊行されている。まず、〝ミステリ通〟庄野さんの指導にしたがいシリーズ第1作である『ロゼアンナ』を手に入れた。つづいて、第2作『蒸発した男』、第3作『バルコニーの男』と手に入れた。その際、カヴァーをすべて「旧版」で統一することにこだわったのは、コラージュ風の日暮修一によるイラストが往年のミステリらしい味わいで気に入ったからである。ちなみに、彼はSSKHKH(←わかるひとだけわかってね)の日暮愛葉のおじさんにあたるらしい。
ところが、「新版」と「旧版」2種類あると思っていた角川文庫版のカヴァーだが、じつはこの『笑う警官』にかぎって4種類存在することが調べているうち、わかった。アメリカ探偵作家クラブから「エドガー賞 長編賞」を授与されたこの作品は、76年『マシンガン・パニック』というタイトルの下ハリウッドで映画化もされている。その人気を受けてだろう、日本でも『笑う警官』はたびたび版を重ね、どうやらそれにあわせてカヴァーデザインも更新されたきたらしいのだ。しかも厄介なことに、この『笑う警官』、日本では2番目に刊行されている。
ネットでみかけた4種類の『笑う警官』のカヴァーのうち、日暮修一バージョンを除く2種類は比較的最近のデザインであることがわかる。もう1種類は、いつ刊行されたものか定かではない。そこでぼくは、細心の注意を払って72年発行のものを古書店に注文してみたのだが、その結果は冒頭のとおり。つまり、包みを開いたぼくが目にしたものは、その存在すら知らなかったなんと〝5種類目の〟カヴァーだったのである。
この〝5種類目の〟カヴァー、いま手元にある『笑う警官』の奥付をみると、「昭和47(1972)年12月30日発行の7刷」とある。初版が同じ年の7月20日だから、半年足らずのうちに7回も版も重ねたことになる。ふつうにかんがえれば、大石一臣というひとのイラストによるこのカヴァーが初出にちがいない。相変わらず日暮バージョンを手に入れようと、しかもできるだけ〝安価で〟手に入れようともくろんでいるぼくとしては、それが2番目なのか3番目なのか、はたまたいつごろの時期にあたるのか、気になってしかたない。確率1/2ならまだいい。いつまた、こんなふうに叫ぶことになるのではないかとかんがえると恐ろしくてしかたないのである……
6種類もあったのか?!
