アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 4』
2013.6.1|review
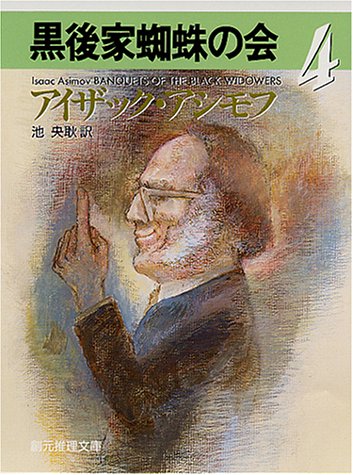
なぜか、この短編集では作家による「あとがき」が作品ごとに付されていて、このシリーズを読み出した当初こそ「これって必要?
蛇足じゃね?」と思っていたのだが、いつのまに、むしろちょっと楽しみに読むまでになってしまったのは、しばしば語られる初出時のタイトルをめぐっての《応酬》がことのほか愉快だからである。そして、その相手こそ、「エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン」の当時の編集長フレデリック・ダネイなる人物。
《応酬》とはいえ、作家本人によるあとがきゆえ攻撃は一方的なもので、たいがいは原稿を受け取ったダネイ氏によってあたえられたタイトルが「よろしくない」というものだが、ごく稀に、ダネイ氏によるタイトルの方に潔く軍配をあげることもある。けれども、その《応酬》の背景にふたりの強い信頼と友情が感じられなんともほほえましい限りなのだ。そう、ちょうど黒後家蜘蛛の会のメンバーにして、「犬猿の仲」であるルービンとゴンザレスのように。
内容は、第一巻から読んできたなかではこれがいちばん読みやすかった(逆に読みにくかったのは前刊)。読みやすいというのは、たぶんよりスノビッシュではないという意味で、そのぶん切れ味もやや鈍くなった印象もあるし、この巻ではこれまでにはなかった「椿事」が起こったりとそろそろ遠くに「黒後家蜘蛛の会」の終焉が感じられて愛読者としてはややしんみりした気分にもさせられる。残された最後の楽しみをいつ読もうか、目下思案中である。
PS.「フレデリック・ダネイ」なる人物について知りたくて調べてみてはじめて、エラリー・クイーンが「藤子不二雄」だという事実を知る。ハハハ
中村弦『天使の歩廊―ある建築家をめぐる物語』
2013.6.6|review

″A House is not a Home″というバカラックの名曲を思い出す。明治から大正、そして昭和という激動の時代を舞台に、ひとりの「異端の」建築家の姿を6つのエピソードからあぶりだした不思議な風合いをもつ物語。
「家」とは奇妙なものである。たいがいの「家」は地面に建つ。物理的にはもちろんのこと、メタフォロジカルな意味でも、また。だから、ときに「家をもつ」ということはそのまま、そこに暮らす人間の〝現世への執着の現れ〟でもある。ところが、主人公・笠井泉二のつくる「家」はちがう。それは、現世に定着できず、ふわふわと宙空に舞っている依頼人の「思い」をかきあつめ、そこに納めてやるための「うつわ」、あるいは「モニュメント」のようなものとして描かれる。その意味で、主人公はみずから宙空を舞いながら人々のやりきれない「思い」を回収する、まさに天使的存在なのである。
彼の建築は普遍的ではないが、だれか一人のために役立つと語る、笠井の理解者である卯崎教授のことばが心にしみる。その後の主人公は、大陸でいったいどんな「街」をつくったのだろうか?
ほんのりとあたたかい心持ちで本を閉じた。
余談。主人公が暮らしているのは小石川植物園にほど近いところとなっているが、そこは当時「貧民窟」として知られた場所である。華族や実業界の大立て者をクライアントとし、みずからもけっして貧しくはなかったであろう主人公に自身の「家」としてあえてこうした土地を選ばせたところに、作者の、天上と地上とを自由に行き来する中間的存在に対する考え方を透かし見ることができておもしろい。装幀は、有元利夫が描いた作品であったなら……と個人的には思わずにいられない。
戸板康二『黒の狂女―中村雅楽探偵全集3』
2013.6.11|review
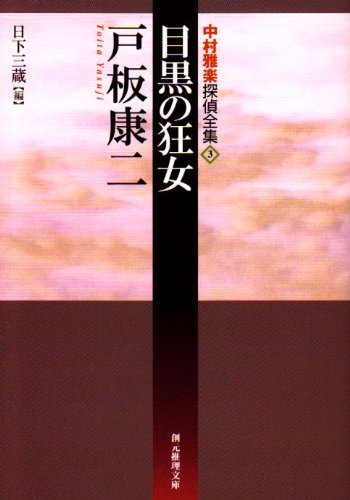
人間のよさ。戸板康二が描く「中村雅楽」という人物の魅力をひとことで言えば、そういうことになるのではないか。
鋭い観察力と洞察力とで身の回りに起こる「面白い」事件(「日常の謎」と言ってもいいが)を鮮やかに解決しながらも、そこにはいつも人間のあたたかい血の流れが感じられるのだ。それは、主人公「中村雅楽」が歌舞伎役者(しかも名門の出ではない)として人生の大部分を劇場で過ごしてきたことと無関係ではないだろう。役者はひとりでは生きられない。相方や脇役、裏方としてはたらくたくさんの人々、そして劇場に足を運ぶ観客がいてはじめて、舞台の上でスポットライトを浴びることができる。雅楽の、事件の当事者に対する慈愛にみちたまなざしはまた、そのように人は人を支え、人に支えられているという事実を彼がわきまえていることの証左であるだろう。
中村雅楽探偵全集の第3弾となるこの『目黒の狂女』では、これまで以上にそうした雅楽の「善さ」を感じさせる作品が多いような印象を受けた。このシリーズが発表年代順に収録したものであることからかんがえれば、そのような傾向にはこの時期(おもに昭和50年代)の作者の心境が映し出されているといえるかもしれない。この巻のおしまいに収められた『木戸御免』など、まさにそんな戸板流ヒューマニズムにあふれた佳作ではないだろうか。
そのむかし新劇が盛んだったころ、シェイクスピアの戯曲なども歌舞伎にならって見せ場だけを上演するようなことが行われていたらしい。雅楽の口を介してそんな大正期の演劇界の姿を知ることができるのもまた、このシリーズを読む愉しみのひとつである。
中村弦『ロスト・トレイン』
2013.6.12|review

はたして『銀河鉄道の夜』へのオマージュなのだろうか……?忌まわしい記憶とともに抹消された「まぼろしの廃線跡」をめぐるパラレルワールド譚。ふだんこの手の小説に縁がないため、こうした設定が古いのか新しいのかはまったく判らず。
人の一生というのは鉄道に乗るのと似ている、と鉄オタの平間さんは語る。「どこへでも自由に行けるかのように見えて、じつはそれほど自由があるわけではない」。すすむべき線路は一本ではなく、ところどころに乗り換え駅もあるけれど、うっかりすると「目指しているのとは全くちがう場所へ連れていかれてしまう」のだ。そんな平間さんが、ある日、忽然と姿を消してしまう。そして若い友人である菜月さんと主人公であるぼくは、わずかな手がかりをもとに消えた平間さんを捜して「まぼろしの廃線跡」をめざすのだが……。
ラスト、主人公の抱く不安は、菜月さんへの愛情と表裏一体をなすものであり、その意味で、大切な誰かを愛するということはまた、そこから逃げることのできない一本のレールの上にあって不安とたたかい続けることでもあるのだろう。
有吉佐和子『青い壺』
2013.6.14|review

この世に産み落とされ、その後数奇な運命を辿るのはなにも人間だけの専売特許ではない。「もの」だって同じこと。いや、むしろ自分の意志で移動できないぶん、「もの」の一生のほうがじつははるかにドラマティックといえるかもしれない。
というわけで、これは一個の青磁の経管をめぐる物語である。壷が「主人公」というので、壷がいきなり自分の人生についておしゃべりを始めるのではないかと心配したが、もちろん、そういうことはない。さまざまな偶然が重なり、さまざまな「家」を転々とする青い壷。そうしてその壷は、それぞれの場所で、思いがけずそのときどきの持ち主の心(それは美しい思い出であることもあれば、ときに醜悪な虚栄心だったりもするのだが)をまるごと映し出す鏡になる。最後、一見無関係と思われるエピソードが唐突に挿入されるが、そこから一息に導き出される決意が清々しい読後感をあたえる。
「弓香と律子は手を繋いで部屋を出た」。ごく短いセンテンスだが、50年ぶりに再会した女学校時代の旧友たちの時間を一気に巻き戻してしまうあるエピソードの後ろに置かれるとき、そこに彼女らの歳月が凝縮されて鮮やかに立ち上がる。いまの感覚からすると、それぞれの物語の描き方は往年のホームドラマのように大仰で滑稽な印象を拭えないものの、こういうハッとするような瞬間とたびたび出会えるのが、読んでいてなんとも楽しい一冊だった。
矢野誠一『落語家の居場所―わが愛する芸人たち』
2013.6.16|review

トラウマ?
はたまたナントカ症候群?
運よく「巨匠の時代」に居合わせてしまったがために、その後ずっと食い足りない気分を抱えながら過ごさざるを得ないこういう《不運》のことをはたしてなんと呼ぶべきか?
この『落語家の居場所』という本について、志ん生や文楽、圓生ら往年の「巨匠」たちと身近に接してきた筆者は、「むかしほど落語にのめりこむことのできないでいる自分」を発見し、それでも断じて「團十郎爺い」にはなりたくないと抵抗をみせながらも、けっきょくは「世紀末落語論」をめざしたつもりが「『よき時代の落語讃歌』にかたちを変えてしまった気味がある」と告白する。
とはいえ、この本からは年寄りの昔話に付き合わされたようなうっとうしさはほとんど感じられない。ひとつには、それは筆者が過去と現在とを比較するような書き方を意識的に避けているからだろうし、もうひとつには、現在にも通じるや寄席の「気分」といったものが、さながらRPGの「アイテム」のようにこの本の随所に隠されて(?)いて、そのつどいろいろなことにあらためて気づかされるからではないか。
「つまり、ふだん着で、ふだん使っているものを手にして、ふだんの声で、ふだんの言葉ではなすのが、落語なのである」(「古今亭志ん生の執念」)
これからの新作落語について。三遊亭圓歌の「中沢家の人々」や林家木久蔵(現木久扇)を引き合いに出しながら(風俗描写やナンセンスな状況ばかりにたよらない)「ますますパーソナルな色彩を加えていくような気がする」(「寄席」94.2.16)
三代目小さんと圓遊についての夏目漱石による評をとりあげ、小さんの方を持ち上げるのは漱石が「なにより江戸趣味のひと」だっかからと指摘、むしろ「新しい時代にふさわしい感覚」にあふれていたのは圓遊の方であった(「世紀末落語論」)
今日の落語を取り巻く状況について、聴衆をふくめた当事者たちのその危機感の薄さは四半世紀前とまったく変わっていないと指摘する一方で、そのぬるま湯につかっているような居心地のよさがかえって「激しい世の移り変わりという時間の流れのなかで、少しも動かない静かな時間をつくり出していたことに、じつは最近になってやっと気づいた」(「世紀末落語論」)
生涯つつましい長屋暮らしを通したことで知られる彦六の正蔵師匠に、反面、コーヒーは自分で挽いた豆をサイフォンでたて、食堂車でオートミールの食べ方を著者に得意げに教授し、「落語家のなかでホームスパンのジャケットを最初に着」るようなモダンな横顔があったことをはじめて知った。へぇ〜(「林家正藏の反骨精神」)
その他にも落語好きには刺激的なエピソードや指摘が多数。
沢村貞子『私の浅草』
2013.6.20|review

「江戸」と「東京」とがせめぎあう、さながら汽水湖のような1920年代の浅草。その浅草に生きる人々の暮らしを、ひとりの少女の目を通して活写した素晴らしいエッセイ。季節の到来を告げる年中行事の数々、無駄を出さない生活の知恵、どんなときにも背筋をシャンと伸ばした浅草の女たち…… そうしたひとつひとつが、まるでその場に居合わせているかのようにくっきりと像を結ぶ。少女時代の沢村貞子の観察眼、文章の腕前も見事だが、ひとりの大女優を育んだ1920年代の浅草の庶民の暮らしの《豊かさ》を見抜き、筆をとることを勧めた花森安治の編集者としての目利きぶりにも拍手をおくりたい。
ジェイムズ・エルロイ『ブラック・ダリア』
2013.6.25|review

《ブラック・ダリア》とは、ロサンゼルスで惨殺されたひとりの女に献じられた呼び名である。
猟奇的な殺人事件とその核心に迫ろうとする警官が主人公という点で、これはれっきとした犯罪小説であるが、と同時にこのフィクションの肝はもっと別のところに、《ブラック・ダリア》という女の存在によってはからずも自身が抱える心の闇に向かい合わざるをえなくなった人々の孤独な葛藤とその悲劇的結末を容赦なく描き出すところにあるようだ。ひとつの事件をきっかけに、平和な日常がアリ地獄のようにグズグズと崩落してゆくことの恐ろしさ。息をのむようなスピード感とは無縁。物語は、からまった糸を忍耐強くほどいてゆくようにジリジリした歩みで進んでゆく。
全編を貫く生々しさ、不吉さは、ロサンゼルスの暗部を身をもって知りつくした著者ゆえだろうか? 読者にもそれ相応のタフさが要求される。
芝木好子『湯葉・隅田川・丸の内八号館』
2013.6.30|review
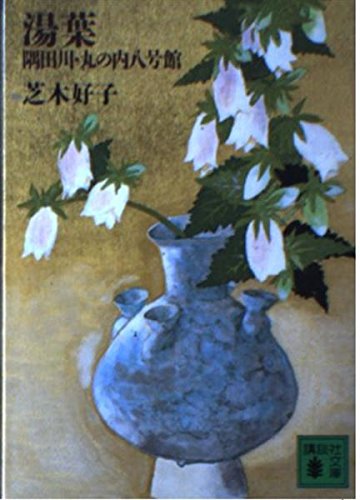
父権的なるものを失ったとき、ひとりの女としてどう生きるか?
母娘3代の生き様のちがいを描くことで、この3部作はあざやかに明治から大正、そして昭和という時代を映し出す。
3作通じて if(もし…)の用法を使うことで、「男」の死、あるいは消失によって「女」の生を描くという手法がおもしろいが、同時にそれぞれの時代を象徴するものとして、独自の工夫で一目置かれる湯葉屋、芸術的な染織にこだわりをもつ呉服商、そして当時「一丁倫敦」などともてはやされた丸の内ではたらく「タイピスト」といった仕事がえらばれているのが興味深い。
海野弘にならって1910年代、20年代、30年代という区分で読んでゆくと、またひと味ちがう眺めがひらけてくるのも印象的。第3部『丸の内8号館』の主人公・恭子は、じぶんの母や祖母とちがい、最後にはみずから父権的なるものに引導を渡すことでみずからの人生を歩き出そうとする。物心ついた時分に、浅草という当時の東京の「へそ」で道楽者の父親に溺愛されて育つことで大正デモクラシーの甘い蜜の味を知ったいかにも30年代の女らしい生き様だし、またそういう道しか選べないことでひとつの時代の終焉をまざまざと知らしめるのだった。
