海野弘『東京風景史の人々』
2013.5.5|review
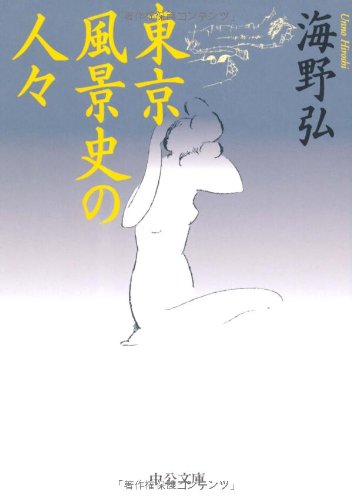
東京を、モダニストたちの歩幅でぐわしぐわしと闊歩したくなる一冊。『日本のアールヌーヴォー』で世紀末の、『モダン都市東京』で20年代の「東京」の姿をみごとに浮き彫りにした海野弘が、ここでは1910年代の東京をとりあげる。
20年代に花開く大正デモクラシーへの、どちらかというと過渡期とかんがえられてきた10年代だが、芸術家たちの意識の上である大きな変化が起こったのがこの時代であると著者は言う。具体的にいえば、00年代の画家たちにとって芸術とは「職業」を意味していたのに対し、10年代の画家たちにあって芸術とは「みずからの生き様そのもの」であった、と。
交通手段や複製技術の進歩によって相互に交流が生まれ、西欧の芸術運動と時間差なくリンクすることができるようになったことで「個」としての意識が日本の芸術家たちの中に芽生えたのがこの時代なのである。西洋/東洋という「空間軸」、明治・大正・昭和という「時間軸」ではなく、日本の近代アートを「年代」によって西欧のアートとひとつかみで捉える必要を著者が説くのはそのためである。
それぞれのエッセイすべてがするする読み進むことを邪魔するくらい刺激的であるが、たとえば「川端康成の都市彷徨」、東京をみつめる川端の「まなざし」のデリケートな変化をみごと逃さず捉えた論考の鋭さには思わず唸らされる。モダン都市東京の「へそ」がすでに浅草から銀座へと移った二十年代の終わりに、川端は浅草への「回帰」を力説する。「欧米の直訳」にすぎない銀座に対して、東京のどん欲な「胃袋」であり「大胆な和洋混合酒」である浅草に川端は日本独自の都市文化を生み出す可能性の中心をみたのである。そして、それはまぎれもなく三十年代の先鋭的な文化人ならではのまなざしといえる。日本主義や西洋と東洋の融合といった彼らのイノセントな思想は、やがて軍国主義にのみこまれることで骨抜きにされるだろう。
文学や美術が、「個」としての芸術表現であると同時に、その時代に生きた人々の息づかいを生々しく刻みこんだすぐれた都市表現でもあるということをこの本は教えてくれる。
高野正雄『喜劇の殿様―益田太郎冠者伝』
2013.5.10|review

ナゾ多き人物ではあるが、現代に続く「お笑い」の種をまいた人物であるという点ではまちがいないだろう。
三井財閥の発展に貢献した明治の大実業家の御曹司にして、数々の喜劇、レビュー、落語、小唄や端唄の作者として人気を博した益田太郎冠者こと益田太郎の評伝である。著者は元毎日新聞社学芸部の記者で、「ハイカラ通人」なるタイトルで獅子文六が連載する予定だった太郎冠者を主人公とした新聞小説の担当記者だった。ところが、いよいよ連載が始まろうというそのときに獅子文六が他界、獅子のために準備した取材ノートを元にいわばその遺志を継ぐようなかたちで書かれたのがこの本である。
太郎冠者のホームグラウンドは、みずから取締役を務めていた帝国劇場の「女優劇」だった。洋行帰りならではのバタ臭い笑いのセンスに大正期の観客たちは拍手喝采し、劇場はつねに大入りだったという。制作費が足りなくなると、毎度ポケットマネーで補って思い通りの舞台をつくるというほどの熱の入れようで周囲を唖然とさせた。なにせ、中学生の身分で品川の芸者を総揚げして自宅で宴会を開いてしまうほどの規格外の金持ちゆえ、そんなこともできたのである。しかし反面、それゆえ同時代の演劇人やインテリからは評判が悪かった。曰く「金持ちの道楽」。
太郎冠者は、帝劇の経営が松竹の手に渡った1930年を機に筆を折る。それにはさまざまな事情があったようである。個人的には、軍国主義へと向かう小さな足音が太郎冠者の耳には聞こえていて、もはや自分の出る幕ではないという思いがどこかにあったのではないか(時の警視総監、丸山鶴吉によるカフェー大弾圧は1929年のことである)。しかし一方で、太郎冠者のまいた種はあちらこちらで確実にその花を咲かせようとしていた。金龍館時代の浅草オペラの第一回興行では太郎冠者の手になる「唖旅行」が取り上げられているし、後には「コロッケの唄」や「おてくさん」が取り上げられ庶民の間でも大ヒットしている。また、関係者の証言をもとに、宝塚の『モン・パリ』や『パリゼット』といったレビューが太郎冠者の作品を下敷きに誕生したことを突き止めたのは著者である高野氏による大発見である。益田太郎冠者は、やはり日本の1920年代をつくったひとりであった。
それが「何か大正といふ時代を象徴してゐるやうな気」がするという理由で、久保田万太郎は自身が社長兼編集責任者を務める雑誌「日本演劇」に益田太郎冠者についての論評を書くよう渋沢秀雄に要請する。言論統制下にあった昭和二十年の話だ。なんの思想もなく批判もない、ただただ「笑のための笑、娯楽のための娯楽」(渋沢)をめざした太郎冠者の作品にあえてその時期スポットライトを当てようと考えた久保田の「思い」について、少し深く考えてみたい。少なくとも、そんな罪のない爽やかな「軽さ」に人々が笑い転げていた時代を、しばし振り返ってみたかったのかもしれない。
太郎冠者作の落語については、現在よく取り上げられるのは「宗論」「かんしゃく」「堪忍袋」といったところだろうか。寄席で頻繁に遭遇する「動物園」も太郎冠者の作だとする声もあるようだが、それを裏付ける証拠はいまのところないとのこと。晩年の太郎冠者から贔屓にされていた六代目春風亭柳橋は、「洋行帰り」という噺を太郎冠者に直接稽古をつけてもらったのだそうだ。「女天下」は、正岡容によれば、初代三遊亭圓左が舞台をみて落語化したとのことだが、正確なところはやはりわかっていない。現在では、六代目の蝶花楼馬楽を経て柳家小袁治師がしばしば高座にかけているようである。いつか聴いてみたいものだ。「かんしゃく」に登場する口うるさい主人は、なんでも太郎冠者にそっくりだそうである。つねに同時代や同時代人を容赦なくネタにして笑いをとることで人気を博してきた太郎冠者だが、ときには自分自身ですら笑いのタネにしてしまうその道化精神に、「余技」と呼ぶにはあまりにも徹底した《喜劇人》としての矜持を感じずにはいられない。
戸板康二『ぜいたく列伝』
2013.5.14|review
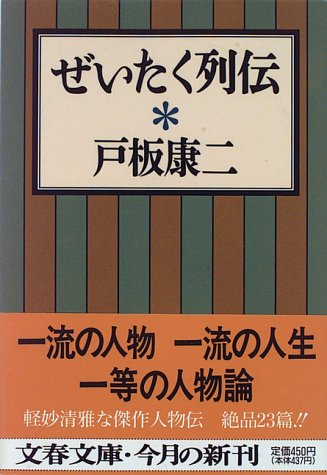
ぜいたくってなんだろう?「私自身は、ぜいたくな生活をほしいままにできる人間ではないし、また、しようとは思わない」と言う著者が、それでも魅力を感じずにはいられない「正しい意味で、ぜいたくな生涯を送った先人」たちを取り上げ、戸板流「ぜいたく」の定義を示してみせたのがこの本。
光村利藻の愛妾
十一代目片岡仁左衛門の豪遊
谷崎潤一郎の四季
吉田茂の白足袋
横山大観の富嶽図
大倉喜七郎のホテル
藤原義江の女性
内田百閒の御馳走
長谷川巳之吉の出版
徳川義親の虎狩り
西条八十のかなりや
小林一三の宝塚
堀口大学の月光
梅原龍三郎の北京
鹿島清兵衛のぽん太
花柳章太郎の衣裳
御木本幸吉の真珠
福地楼痴の團十郎史劇
益田太郎の喜劇
志賀直哉の座右寳
五代目中村歌右衛門の下げ髪
薩摩治郎八のパリ
西園寺公望の清雅
明治の大富豪から実業家、歌舞伎や新派の役者、芸術家らのそれぞれの「ぜいたく」が紹介されるが、そこはなんというか「戸板マジック」とでもいうのか、読み進めてゆくうちになぜかその人物に対して好感をおぼえてしまうのが不思議である。戸板康二は、人物を語るときつねに「加点評価」するひとである。ある人物の繊細なところ、独特のところ、鋭いところ、新奇なところばかりを巧みにすくいあげてゆく。意図的にというよりは、それはきっと戸板康二というひとの「人間のよさ」に由来しているという気がする。あとがきで「ぜいたく自身が人徳になっている人たちが、私にすがすがしい余韻を残してくれた」と語っているが、戸板康二というフィルターを透してこそ、読者もまたここに登場する人物たちの豪放な生き様に「すがすがしい余韻」を感じるのである。ぜいたくとは、「物質的な奢り」ではなく、ある人物をその人物たらしめている心の棲み処のようなものなのだろう。
海野弘『モダン都市東京―日本の一九二〇年代』
2013.5.23|review
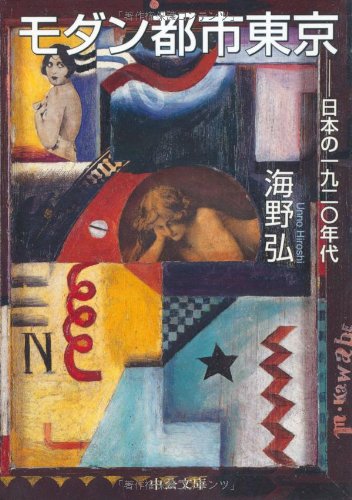
ここで語られる東京の20年代は、なぜこうも《苦い》のだろう。
大学生のとき夢中で読んで以来、ひさびさの再読。あらためて読んでも、やっぱり十分に刺激的な論考だ。明治期の画家のしごとから日本の世紀末を探った『日本のアールヌーヴォー』、おなじく大正デモクラシーの胎動期といえる1910年代を論じた『東京風景史の人々』とくらべると、この『モダン都市東京』は少しばかり読みにくい。小説や詩といった文学作品における都市表現から《20年代》(著者の定義によれば大正7、8年から昭和7年くらい)の東京を読み解くという試みのため、どうしても観念的にならざるをえないせいもあるだろうけれど、それ以上にやはりそれは《20年代》という時代のとらえどころのなさによるところが大きいのではないか。
「日本の《20年代》は失われている。それはまるで、存在しなかったかのように、切りとられ、前後がそれをはずして縫い合わされてしまっている」と海野弘は言う。多くの作家たちが東京という都市にあこがれ、東京を描こうと格闘しながらも、結果的に彼らは十分に都市を表現することでその時代を描き出す技法を編み出せないまま《都市》に別れを告げてゆく。その原因は、「ファシズムへと傾斜してゆく国家権力の弾圧による沈黙という外的なものであると同時に、都市表現の未成熟と行き詰まりという内的なもの」でもあった。じっさい、テクノロジーやメディアの進歩により東京は20年代、いまだかつてないスピードで変転していたし、作家たちにとっては影法師のようにするするとその手から逃れていってしまうような感覚だったにちがいない。そのあたりは、20年代を象徴する都市である「銀座」の特徴を、郡司次郎正、上司小剣、貴司山治らの作品から「すべてのものを出会わせ、混ぜ合わせ、媒介する」という空間性にあるとする第5章、第6章にくわしい。また、「雨の降る品川駅」という中野重治の詩に鋭い解釈をほどこした第11章は、「詩」を文学という局面からだけでなく、川柳や盛り場案内記、ルポルタージュなどをふくむ「都市表現」のひとつとしてとらえるべきと主張する海野弘の真骨頂で、全体の中でももっとも読み応えのある一章であった。
個人的な関心はこれまで、大正デモクラシーをつくった世代/大正デモクラシーを享受した世代にあったのだが、ここで取り上げられているのはいわば「大正デモクラシーを懸命に生きた世代」である。その多くは19世紀末に生まれた地方出身者であり、東京にあこがれ、その理想と現実のはざまで揺れ動きながら20年代に創作に打ち込み、30年代には失敗や挫折を経験する芸術家たち。この本は、彼らの格闘と挫折の痕跡に東京の《失われた20年代》を発見しようという試みであり、読みながら通奏低音のようにつきまとう《苦さ》の理由もまた、そこにある。その中では、雑草のように新宿に根っこをおろししたたかに生き抜こうとする林芙美子や平林たい子の姿は印象的で、一服の清涼剤となっている。
