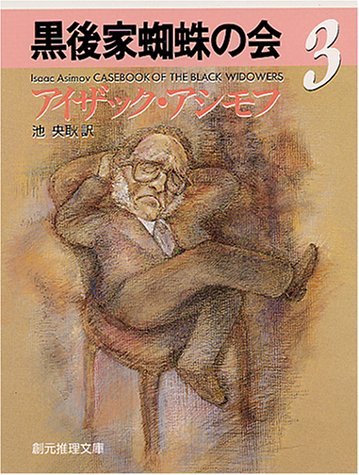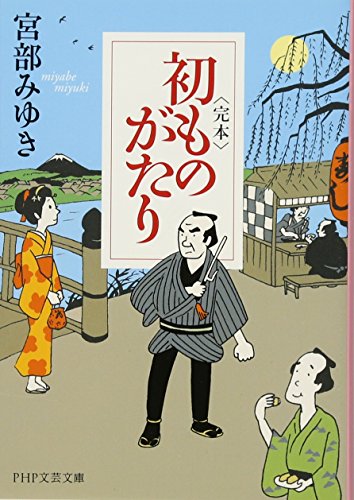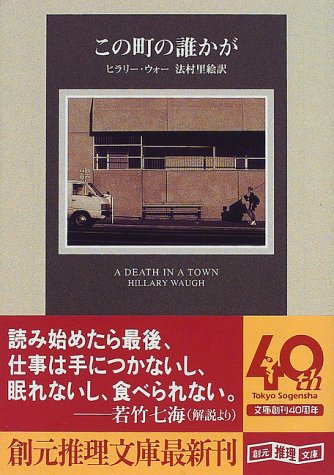北村薫『玻璃の天』
2013.2.2|review
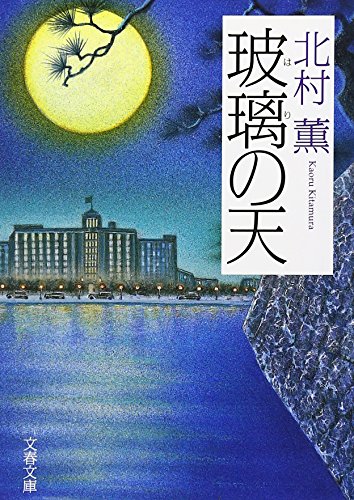
ミステリという「形式」を借りながら、テーマはいよいよ骨太に、作家はますます饒舌になってきた印象。《ベッキーさんとわたし》シリーズ第2弾。
1930年代、軍国主義に突き進む日本。その渦中に否応なく巻き込まれてゆく上流階級の人々を描きながら、そこはさすがに「日常のなぞ」の名手、けっして韓流ドラマ的臭さを読者に感じさせないのはさすがである。むしろ抑制された筆致だからこそ、かえって徐々に暗雲に囲まれてゆくような不穏さがあるのもたしか。
主人公が、ある宴で出会った若い軍人にむかって思わず語る言葉こそ、また、作者北村薫の思いでもあるのではないか。「わたしのいう自由とは、基本的な徳に向かう行進の中で、右を向き左を向く自由です。鳥の声に耳を傾け、空の雲を見る自由です」。
ここでその正体が明らかになった「ベッキーさん」こと別宮みつ子が、続く第3弾でどのような役回りを演じることになるのか、ますます楽しみになってきた。
北村薫『鷺と雪』
2013.2.4|review

☆5つでは足りないくらい。《ベッキーさんとわたし》シリーズ第3弾にして、完結編。
最後に収められた表題作が、圧巻。シリーズ3作を立て続けに読んだせいもあるが、すべての物語が、まるで大きな時計を見ているかのように、ここに向かって刻々と運命の時を刻んでいたのだとわかる。第一作が「服部時計店」に始まり、この最終作がおなじ「服部時計店」で終わる構成も、そう思えば時計のように精巧だ。
月、能面、カメラ……さまざまなメタファーを通じて、この『鷺と雪』では目にみえるものの向こうには、じつは広くて深い目にみえないものが存在していることが暗示される。ことばの向こう側に、ことばにできない「思い」を汲み取ること。それは、(目前に迫った)自由にものが言えない時代にこそ大切な「力」であり、また「生きる糧」ともなるだろう。それを、ベッキーさんはその職分を超えてまで、わたしに教え諭そうとする。
「その日」を前にして、桐原侯爵の長男で軍人の「勝久」様が「ベッキーさん」に問いかけたことば、叩き上げの陸軍少尉「若月」が三冊の詩集を介して「わたし」に託したことば……。そのことばの向こうにある、思い。勝久と若月、ベッキーさんとわたしの、ドッペルゲンガー。そしてドッペルゲンガーには、不吉なイメージ、死の前兆が重なるという。
ことばの向こうには思いが、ある。その思いは、往々にしてことば以上に多くを物語る。その思いをひとが汲み取る手がかりは、ただことばしかない。その意味で、北村薫というひとは「ことば」のもつ力を信じている。
泡坂妻夫『亜愛一郎の狼狽』
2013.2.7|review

とぼけた味わいと軽みが身上の、コミカル・ミステリー・ツアーへようこそ。
「笑い」とは「緊張と緩和」だと言ったのはたしか、哲学者カントだったろうか?
イケメンなのに不器用で運動神経ゼロというこの小説の主人公にして探偵役「亜愛一郎」の存在は、まさにこの小説では破壊力抜群な「緩和」そのものとして機能している。だから、陰惨な殺人事件が起こるにもかかわらず、読者はたびたび読みながら吹き出さずにはいられない。巧妙なトリックに裏打ちされたミステリと脱力系ユーモアとが奇跡的なバランスで両立しているのだ。
地味な飛行機爆破予告を発端に、残忍な殺人事件の背後に潜む思わぬ動機が明かされる第一話「DL2号機事件」などは、いきなり意表をつくようなタネ明かしにキツネにつままれたような気分にさえなるが、それが日頃「雲」や「虫」など多くのひとがあまり気にもとめない自然観察にばかり熱中しているカメラマンによる推理と聞けば、なるほどその推理力というよりも並外れた観察眼に脱帽してしまう。ここには8つのストーリーが収められているが、全編そんな常識や先入観の裏をかくようなトリックが目白押しで飽きさせない。
ただ、毎回登場する「三角形の顔をした老婦人」はともかくとして、第一話に登場する柔道家の女の子とはいったい何者なのか?
あまりに意味ありげに登場するわりにトリックにはまったく関わってこないという……不思議。
*北村薫が選ぶミステリー通になるための文庫本100冊
北村薫『謎のギャラリー―謎の部屋』
2013.2.12|review
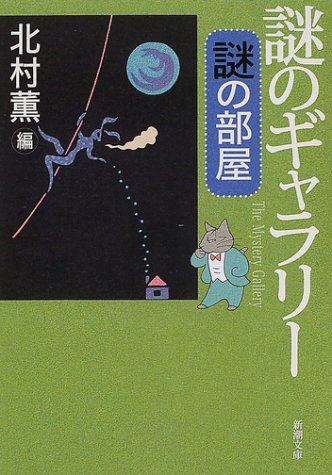
自称《本格原理主義者》、アアルトコーヒーの庄野さんにすすめていただいた一冊。
北村薫が、《謎》をキーワードに選んだ古今東西の16人の作家による短編を収めたアンソロジー。さまざまなタイプの作品が含まれるが、CDにしても個性的な選曲家の手によるコンピレーションを好む自分としては、そこに「北村薫」というひとの個性も感じつつ最後まで楽しく読書した。
「謎の部屋」というこの本のタイトルにふさわしく、宇野千代/東郷青児コンビによる超現実的で、しかもどことなく淫微な匂いを放つ物語でいきなり冒頭から読者を煙に巻く。その余韻を引きずりながら読む阿部昭『桃』は、なんというかとても官能的に映る。同じトーンは次の作品『俄あれ』(里見弴)にもつづく。途中で気づく、「にわかあれ」というタイトルのダブルミーニングはなかなかパンチが効いている。終わり方はあまり好みではないとはいえ、吉祥寺が舞台の『遊びの時間は終わらない』は、落語「だくだく」を想起させるストーリーともども親しみをもって読んだ。
「昔、私が柘榴の実の中に住んでいた頃……」と始まる『柘榴』を書いたカリール・ジブランというひとは、「あとがき」として収められた宮部みゆきと北村薫との対談によればレバノン出身の作家とのことなのだが、その寓話のような語り口といいアルメニア出身の映像作家パラジャーノフの『ざくろの色』を彷彿とさせる。レバノンとアルメニアがおなじ文化圏といえるかどうかはわからないが、メタファーとしての「ざくろ」はこの一帯においてはなにか特別な意味を持つのだろうか?
これはまた、べつの《謎》。グロテスクでありながら、神話のようでもある『豚の島の女王』、星新一のショートショートにも似た『どなた?』もおもしろい。おなじ立場に追い込まれたら、たぶんぼくもこの主人公とおなじ態度をとるだろう。諦観こそ幸福への近道、か?
タネあかしの見事さに思わず唸らされるのは、ハードボイルドな『定期巡視』。『猫じゃ猫じゃ』『埃だらけの抽斗』のふたつは、銀行もの。どちらも後味があまりよくないのは「カネ」にまつわる話だからだろうか。最後に収録されたゴフスタインの絵本『私のノアの箱船』は、いってみれば映画のエンドロール。「謎の部屋」を後にして日常へと読者が戻るきっかけ。一服の鎮静剤!?
なかでも、マージャリー・アランというひとの『エリナーの肖像』は個人的にいちばんおもしく読んだ一編。イングランドのマナーハウスを舞台に、そこで変死した少女の遺志を一枚の肖像画から読み解いてゆくという本格ミステリー。恣意的に感じられた要素のすべてが、彼女を愛していた周囲の人々の記憶の助けを借りつつジワジワと焦点を結び、最後には犯人の姿をくっきりとあぶりだす。探偵の登場しないこの物語では、《謎》は彼女を慕う人々の《愛情》の力があってはじめて解き明かされるのだ。そこに言い得ない感動が生まれている。
出久根達郎『御書物同心日記 虫姫』
2013.2.15|review
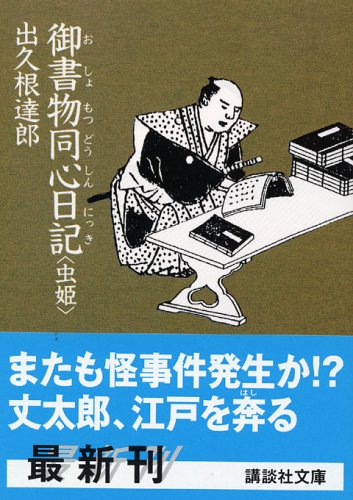
それでも、退屈至極な日々はつづく……。将軍家の蔵書番、御書物同心の「退屈至極な日々」を描いた大好きなシリーズの第3弾。
前作に続きこの《虫姫》でも、丈太郎は「本の虫」に似つかわしからぬ勇猛な一面を見せる一方(「虫姫」「州崎」)、恋愛については相変わらずの奥手ぶりが微笑ましい(「鷽替」)。
このシリーズ、けっきょく事件らしい事件はなにひとつ起こらない。事件というよりもそれは、市井のひとびとの日々にポツンとついた「しみ」のような出来事にすぎない。けれども、読み進むにつれて登場人物のひとりひとりがそれぞれ、心の裡になにがしかの《なぞ》を隠したミステリアスな存在に思えてくるのがおもしろい。ひとの心の奥底に秘められた《なぞ》は、あるとき不意に顔をのぞかせることもあるが、むりやり暴き立てたり解き明かしたりしないほうがよい類いのものなんじゃないだろうか?というのも、「安穏さ」とは、その「暗黙の諒解」の上にあってはじめて成立しうるものだと思うからだ。だから、丈太郎を取り巻く世界の節度をもった「安穏さ」が、ときにとても美しく、かけがえのないものに映るのだろう。
柳家小満ん『べけんや』
2013.2.23|review
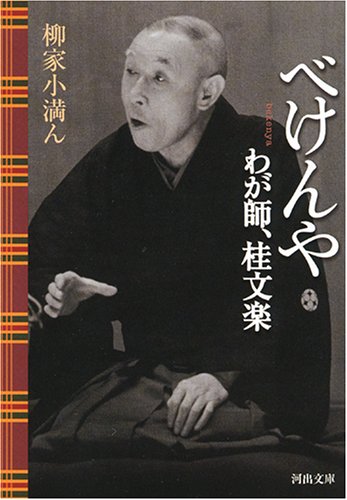
たとえば、第3章「師匠の食事」。
なんて「美しい」朝食なのだろう。名人・八代目桂文楽の「芸」から受ける ─端正、緻密、モダン、色気─ といった印象のすべてが、毎朝「黒門町」の長屋で繰り返される、さながら「儀式」のようなその食事風景からも同じように感じられたのは驚きである反面、また当然のような気もした。まさにその「人」こそが「芸」そのものであり、そういう生き方が許された時代、いわば「巨匠の時代」の芸術家なのだろう(その点で、「修業中の弟子の目からみた師匠」という切り口は同じでも、立川談春の『赤めだか』とは決定的にちがっているように思われる)。
その意味で、この『べけんや』に綴られた桂文楽というひとのことばや振る舞いは、その芸をより深く理解する上で役に立つことはあっても、けっして邪魔になるということはないように思う。
また、「伝説」ともいえる「勉強し直してまいります」というよく知られる台詞がとっさに口をついて出た文句ではないと知るとき、文楽というひとの「引き際」に対する美意識に感心するとともに、その、自身をみつめるまなざしの峻厳さには凄みすら感じる。師匠の死後、著者(柳家小満ん)が五代目小さんの元に引き取られることになった経緯なども静かに感動的なエピソード。
アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 2』
2013.4.3|review
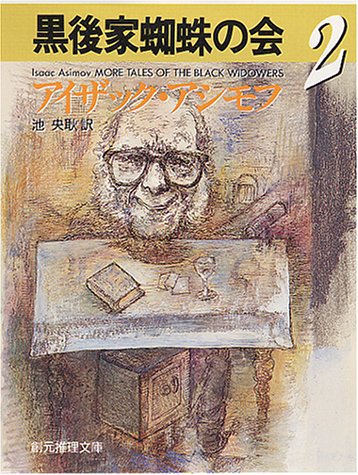
いよいよ面白くなってきた…のは、たぶんこのシリーズを読むのも2作目となり、《ブラック・ウィドワーズ》の面々の多彩なキャラクターがこちらの頭になじんできたせいもあるだろう。
じっさい、作者のトールキンやコナン・ドイルへの偏愛から生まれたとおぼしき『殺しの噂』や『終局的犯罪』、文字や発音など言語のもつさまざまな側面がカギとなる『三つの数字』『省略なし』などアシモフの博覧強記ぶりがますます冴える、言いようによっては重箱の隅っこを突くかのような作品が前作以上に並んでいる。よって、ミステリというよりは、《ブラック・ウィドワーズ》の面々&ヘンリーの会話を部屋の片隅からワクワクしながら聞き耳立てる知的好奇心を刺激するストーリーとして楽しんだ、といったほうが正しいかもしれない。そして、けっきょく3作目にも手を出してしまうのだろうな…(アシモフの思うツボ)
三遊亭円朝『三遊亭円朝探偵小説選』
2013.4.3|review
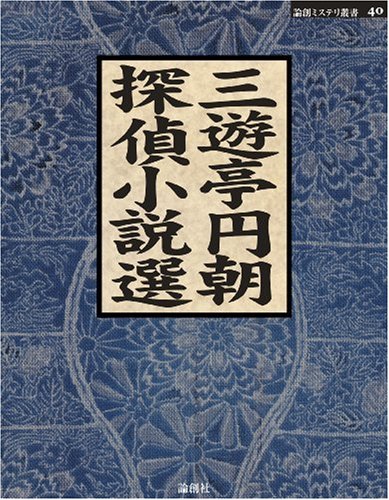
「落語中興の祖」三遊亭円朝が「翻案」を手がけたミステリ(あるいはサスペンス)仕立ての物語5編を収めたアンソロジー。
円朝といえば「真景累ヶ淵」「鰍沢」「死神」「怪談牡丹燈籠」といった名作落語の作者として、また円山応挙をはじめとした幽霊画のコレクターとして知られる大名人であるが、ここでは翻訳ではなく翻案というとおり、モーパッサン『親殺し』(→『指物師名人長二』)などの海外文学を人づてに聞き知った円朝が、同時代の市井の人々にも理解しやすいよう舞台や登場人物を日本に移し、また言文一致体に直すと同時に、部分的に原典にはないシーンや人物を登場させることでよりテンションの高い作品にまで磨き上げた珠玉の《創作》作品が取り上げられている。
収録されているのは、
『英国考子ジョージスミス之伝』
『松の操美人の生埋』
『黄薔薇』
『雨夜の引窓』
『指物師名人長二』
の5作品。表題には「探偵小説」とあるがべつに誰かしら「探偵」が登場し謎解きをするわけではなく、どれもどちらかといえば「ミステリ的要素、あるいはサスペンス的要素の強い人情噺」といった趣きである。
円朝というひとはつくづくモダニストであったのだと、ところで、このアンソロジーを読むとよくわかる。ひとつには、やむにやまれぬ事情があったといはいえ芝居噺の世界を離れ、扇子と手ぬぐいのみであとは「ことば」の力だけによる素噺へと転向、近代落語のひとつのスタイルを築き上げた改革者であるという点で。もうひとつには、みずから江戸時代に生まれ江戸の美学を貫くことに執心しつつも、明治維新後の近代国家の礎を築いた思想家や文学者などと積極的に交わることで、異文化をどん欲にみずからの「芸」に吸収していったという点で。円朝による《翻案》のプロセスについては、それが比較的明らかな「指物師名人長二」についての考察「『名人長二になる迄』〜翻案の経路」が余録として収められているので、それを読むと面白いと思う。
江戸から明治へ、その移り変わりを「激動の時代」と呼んで片付けてしまうことはかんたんだが、実際そこに居合わせた人々にとってはとても容易には受け容れがたい、しかし差し迫った大問題であったにちがいない。思うに、この《翻案》という作業は三遊亭円朝にとって、「落語」という芸を「要」として、江戸と明治というふたつの時代を結びあわせ、乗り越え、受容するためのひとつの試みだったのではないか。その意味で、円朝はその翻案物を通じて同時代の、同じ境遇を生きる市井の人たちのための「水先案内人」をみずから買って出たのだ、とぼくはなんとなくかんがえずにはいられない。心やさしき名人の姿がそこにある。
堀江敏幸『アイロンと朝の詩人 回送電車3』
2013.4.7|review

雨音に催促されるようにして、積ん読の山から掘り出してきてポツポツと読み始める。
堀江敏幸の書く散文は、どこか音楽に似ている。ポンと心を打つ響きもあれば、よそよそしく響く和音もある。時間を経て、抽象的な響きの奥からひょっこり顔をのぞかせるひとなつこい旋律がある。そしていつもこのひとの散文を読むとき思うのは、そこに置かれた「ことば」を読むことでもたらされる余韻のようなものに浸りたくて読むのだ、ということである。そこで鳴らされる音以上に、それによってもたらされる余韻に浸りたくて聴くモンポウの音楽のように。
個人的に大好きな天野忠翁の詩とともに、柔らかく、軽い「むかし」が行間からこぼれ落ちる「メロンと瓜」、身の回りの壊れたものを必要にせまられて「取り繕う」行為から日々を送るということへ、アナロジーの飛躍が不意に視界が開けたかのような錯覚をもたらす「日々を取り繕う」など、いつもながらちいさな「気づき」に満ちた散文集。
矢野誠一『戸板康二の歳月』
2013.4.20|review

戸板康二の評伝。
① 名探偵「中村雅楽」のルーツを探って。
② 大正デモクラシーの落とし子たるモダニストの肖像。
ふたつの《視点》から読む。
① 作者みずから探偵「中村雅楽」シリーズのあとがきなどで明かしているように、このキャラクターは数人の実在する人物たちによるモザイクとして生み出されたものらしい。この評伝では、「推理小説作家」戸板康二についてはわずかしか触れられていないものの、その人柄に「親炙」する「若い友人」矢野誠一の目に映った戸板の言動は、どことなく、と言う以上に「中村雅楽」に似ている。著者、矢野誠一が強調するいかにも「山の手の東京人」らしい品格、人間関係における絶妙な間合いなど、まさに中村雅楽に通じる部分であり、大きな魅力のひとつといえる。
ちょっとしたことだが、この本の冒頭で披露される少年時の改名にまつわる戸板本人による安楽椅子探偵的な「推理」などに触れると、まさしく雅楽本人のようでついうれしくなってしまう。交友関係については、著者をふくむ「若い友人」たちに慕われ、始終にぎやかに囲まれていた反面、久保田万太郎や折口信夫のような一癖も二癖もある年上の「怪人」からも信頼され可愛がられていた。他方、同年代との腹を割った付き合いは苦手だったのか、あまり登場しないような印象を受けた(実際のところはどうだったのだろう?)。
② 物心ついたときに大正デモクラシーの空気を吸い込んで育った人物には、軽快で、やわらかい心のモダニストが多い。著者も本文中でその人柄をたびたび「しなやかな自由人」と評しているとおり、1915年生まれの戸板康二はまさにその世代の人物の特徴を持ち合わせているように思われる。じっさい本人にもそうした意識はあったようで、そのことは「兄は、つねづね自分がとてもいい時代に育てられたことを感謝していました」という弟の言葉からもわかる。戸板康二の「人のよさ」を説明するのに著者はおもに「山の手育ちの東京人」という点を強調しているように思えるが、それにくわえてやはり徒花のようにいっとき花開いた「大正デモクラシー」という時代の影も同じくらい大きな要素として取り上げられてよいだろう。
父親に連れられて行った「平和祈年東京博覧会」など本文で引かれているエピソードからも、その時代の開放的な空気や幼少時の甘い記憶が伝わってくる。だから、植草甚一や吉田健一といった東京という場所と大正という時間が生んだ稀代のモダニストとして、個人的には「戸板康二」という人間に魅力を感じずにはいられないのである。
山本嘉次郎『洋食考―食べものダンディ学』
2013.4.22|review
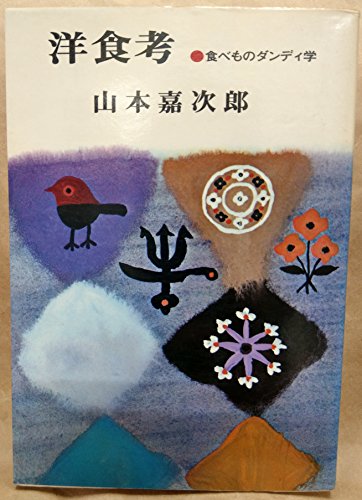
「いまの洋食のまずいのは、その匂いの良さを失っているからである」と映画監督であり、食通としても知られる著者は力説する。明治〜大正にかけての東京下町の食卓にあがる「下手(げて)な味」への郷愁、その味以上に魅力的な洋食の「不思議な魔法のような芳香」、その土地でしか出会えない味の数々……。
一章まるごと「親子どんぶり」に捧げた第2章では、「におい」を失った親子どんぶりを嘆き、「親子が退廃したのではない。文明が敗退したのである。いまの世の食物のまずさが、親子どんぶり一碗のなかに結集しているのである。昭和元禄文化の劣性が、親子どんぶりで象徴されているのである」などと壮大に持論を展開してみせる。
その一方で、酒を「コキン、コキンと飲んだ」、「紀州沖をすぎると、サンマはドカッと不味くなる」といった言語感覚もおもしろい。椎名誠じゃないよ。明治生まれ、執筆当時69歳のおじいちゃんの言葉である。ウスターソースの「A・ペリンズ」(リーペリン?)、「まめさんたいさん」(まめさんたいたん?)など記憶ちがいと思われる箇所もままあるが、ここは昭和のおおらかな仕事ということで大目に見ておくべきかもしれない。
しかし、「食べものダンディ学」などという素敵な副題を備えておきながら、それを打ち壊すかのような永六輔によるコメントを冒頭に引用するあたり、いかにも東京っ子らしいユーモア精神である。
海野弘『東京風景史の人々』
2013.5.5|review
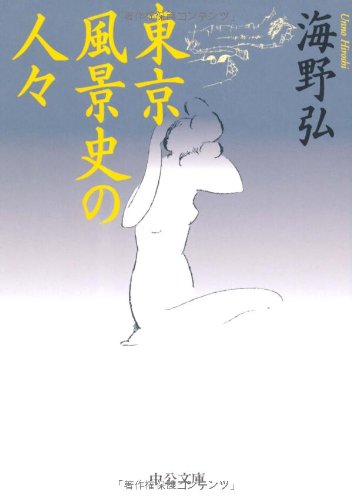
東京を、モダニストたちの歩幅でぐわしぐわしと闊歩したくなる一冊。『日本のアールヌーヴォー』で世紀末の、『モダン都市東京』で20年代の「東京」の姿をみごとに浮き彫りにした海野弘が、ここでは1910年代の東京をとりあげる。
20年代に花開く大正デモクラシーへの、どちらかというと過渡期とかんがえられてきた10年代だが、芸術家たちの意識の上である大きな変化が起こったのがこの時代であると著者は言う。具体的にいえば、00年代の画家たちにとって芸術とは「職業」を意味していたのに対し、10年代の画家たちにあって芸術とは「みずからの生き様そのもの」であった、と。
交通手段や複製技術の進歩によって相互に交流が生まれ、西欧の芸術運動と時間差なくリンクすることができるようになったことで「個」としての意識が日本の芸術家たちの中に芽生えたのがこの時代なのである。西洋/東洋という「空間軸」、明治・大正・昭和という「時間軸」ではなく、日本の近代アートを「年代」によって西欧のアートとひとつかみで捉える必要を著者が説くのはそのためである。
それぞれのエッセイすべてがするする読み進むことを邪魔するくらい刺激的であるが、たとえば「川端康成の都市彷徨」、東京をみつめる川端の「まなざし」のデリケートな変化をみごと逃さず捉えた論考の鋭さには思わず唸らされる。モダン都市東京の「へそ」がすでに浅草から銀座へと移った二十年代の終わりに、川端は浅草への「回帰」を力説する。「欧米の直訳」にすぎない銀座に対して、東京のどん欲な「胃袋」であり「大胆な和洋混合酒」である浅草に川端は日本独自の都市文化を生み出す可能性の中心をみたのである。そして、それはまぎれもなく三十年代の先鋭的な文化人ならではのまなざしといえる。日本主義や西洋と東洋の融合といった彼らのイノセントな思想は、やがて軍国主義にのみこまれることで骨抜きにされるだろう。
文学や美術が、「個」としての芸術表現であると同時に、その時代に生きた人々の息づかいを生々しく刻みこんだすぐれた都市表現でもあるということをこの本は教えてくれる。
高野正雄『喜劇の殿様―益田太郎冠者伝』
2013.5.10|review

ナゾ多き人物ではあるが、現代に続く「お笑い」の種をまいた人物であるという点ではまちがいないだろう。
三井財閥の発展に貢献した明治の大実業家の御曹司にして、数々の喜劇、レビュー、落語、小唄や端唄の作者として人気を博した益田太郎冠者こと益田太郎の評伝である。著者は元毎日新聞社学芸部の記者で、「ハイカラ通人」なるタイトルで獅子文六が連載する予定だった太郎冠者を主人公とした新聞小説の担当記者だった。ところが、いよいよ連載が始まろうというそのときに獅子文六が他界、獅子のために準備した取材ノートを元にいわばその遺志を継ぐようなかたちで書かれたのがこの本である。
太郎冠者のホームグラウンドは、みずから取締役を務めていた帝国劇場の「女優劇」だった。洋行帰りならではのバタ臭い笑いのセンスに大正期の観客たちは拍手喝采し、劇場はつねに大入りだったという。制作費が足りなくなると、毎度ポケットマネーで補って思い通りの舞台をつくるというほどの熱の入れようで周囲を唖然とさせた。なにせ、中学生の身分で品川の芸者を総揚げして自宅で宴会を開いてしまうほどの規格外の金持ちゆえ、そんなこともできたのである。しかし反面、それゆえ同時代の演劇人やインテリからは評判が悪かった。曰く「金持ちの道楽」。
太郎冠者は、帝劇の経営が松竹の手に渡った1930年を機に筆を折る。それにはさまざまな事情があったようである。個人的には、軍国主義へと向かう小さな足音が太郎冠者の耳には聞こえていて、もはや自分の出る幕ではないという思いがどこかにあったのではないか(時の警視総監、丸山鶴吉によるカフェー大弾圧は1929年のことである)。しかし一方で、太郎冠者のまいた種はあちらこちらで確実にその花を咲かせようとしていた。金龍館時代の浅草オペラの第一回興行では太郎冠者の手になる「唖旅行」が取り上げられているし、後には「コロッケの唄」や「おてくさん」が取り上げられ庶民の間でも大ヒットしている。また、関係者の証言をもとに、宝塚の『モン・パリ』や『パリゼット』といったレビューが太郎冠者の作品を下敷きに誕生したことを突き止めたのは著者である高野氏による大発見である。益田太郎冠者は、やはり日本の1920年代をつくったひとりであった。
それが「何か大正といふ時代を象徴してゐるやうな気」がするという理由で、久保田万太郎は自身が社長兼編集責任者を務める雑誌「日本演劇」に益田太郎冠者についての論評を書くよう渋沢秀雄に要請する。言論統制下にあった昭和二十年の話だ。なんの思想もなく批判もない、ただただ「笑のための笑、娯楽のための娯楽」(渋沢)をめざした太郎冠者の作品にあえてその時期スポットライトを当てようと考えた久保田の「思い」について、少し深く考えてみたい。少なくとも、そんな罪のない爽やかな「軽さ」に人々が笑い転げていた時代を、しばし振り返ってみたかったのかもしれない。
太郎冠者作の落語については、現在よく取り上げられるのは「宗論」「かんしゃく」「堪忍袋」といったところだろうか。寄席で頻繁に遭遇する「動物園」も太郎冠者の作だとする声もあるようだが、それを裏付ける証拠はいまのところないとのこと。晩年の太郎冠者から贔屓にされていた六代目春風亭柳橋は、「洋行帰り」という噺を太郎冠者に直接稽古をつけてもらったのだそうだ。「女天下」は、正岡容によれば、初代三遊亭圓左が舞台をみて落語化したとのことだが、正確なところはやはりわかっていない。現在では、六代目の蝶花楼馬楽を経て柳家小袁治師がしばしば高座にかけているようである。いつか聴いてみたいものだ。「かんしゃく」に登場する口うるさい主人は、なんでも太郎冠者にそっくりだそうである。つねに同時代や同時代人を容赦なくネタにして笑いをとることで人気を博してきた太郎冠者だが、ときには自分自身ですら笑いのタネにしてしまうその道化精神に、「余技」と呼ぶにはあまりにも徹底した《喜劇人》としての矜持を感じずにはいられない。
戸板康二『ぜいたく列伝』
2013.5.14|review
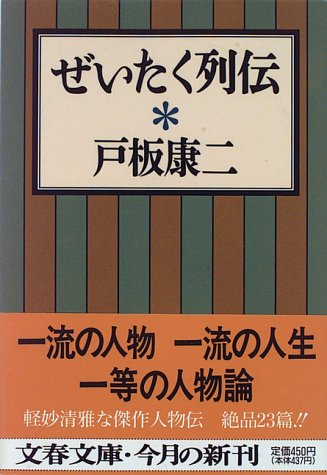
ぜいたくってなんだろう?「私自身は、ぜいたくな生活をほしいままにできる人間ではないし、また、しようとは思わない」と言う著者が、それでも魅力を感じずにはいられない「正しい意味で、ぜいたくな生涯を送った先人」たちを取り上げ、戸板流「ぜいたく」の定義を示してみせたのがこの本。
光村利藻の愛妾
十一代目片岡仁左衛門の豪遊
谷崎潤一郎の四季
吉田茂の白足袋
横山大観の富嶽図
大倉喜七郎のホテル
藤原義江の女性
内田百閒の御馳走
長谷川巳之吉の出版
徳川義親の虎狩り
西条八十のかなりや
小林一三の宝塚
堀口大学の月光
梅原龍三郎の北京
鹿島清兵衛のぽん太
花柳章太郎の衣裳
御木本幸吉の真珠
福地楼痴の團十郎史劇
益田太郎の喜劇
志賀直哉の座右寳
五代目中村歌右衛門の下げ髪
薩摩治郎八のパリ
西園寺公望の清雅
明治の大富豪から実業家、歌舞伎や新派の役者、芸術家らのそれぞれの「ぜいたく」が紹介されるが、そこはなんというか「戸板マジック」とでもいうのか、読み進めてゆくうちになぜかその人物に対して好感をおぼえてしまうのが不思議である。戸板康二は、人物を語るときつねに「加点評価」するひとである。ある人物の繊細なところ、独特のところ、鋭いところ、新奇なところばかりを巧みにすくいあげてゆく。意図的にというよりは、それはきっと戸板康二というひとの「人間のよさ」に由来しているという気がする。あとがきで「ぜいたく自身が人徳になっている人たちが、私にすがすがしい余韻を残してくれた」と語っているが、戸板康二というフィルターを透してこそ、読者もまたここに登場する人物たちの豪放な生き様に「すがすがしい余韻」を感じるのである。ぜいたくとは、「物質的な奢り」ではなく、ある人物をその人物たらしめている心の棲み処のようなものなのだろう。
海野弘『モダン都市東京―日本の一九二〇年代』
2013.5.23|review
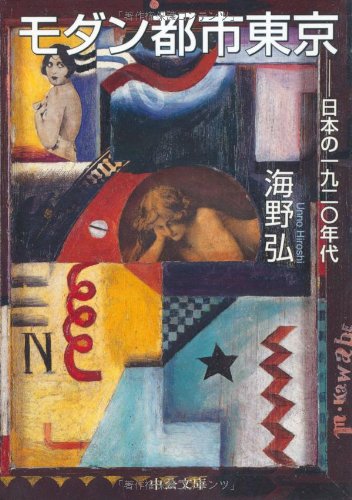
ここで語られる東京の20年代は、なぜこうも《苦い》のだろう。
大学生のとき夢中で読んで以来、ひさびさの再読。あらためて読んでも、やっぱり十分に刺激的な論考だ。明治期の画家のしごとから日本の世紀末を探った『日本のアールヌーヴォー』、おなじく大正デモクラシーの胎動期といえる1910年代を論じた『東京風景史の人々』とくらべると、この『モダン都市東京』は少しばかり読みにくい。小説や詩といった文学作品における都市表現から《20年代》(著者の定義によれば大正7、8年から昭和7年くらい)の東京を読み解くという試みのため、どうしても観念的にならざるをえないせいもあるだろうけれど、それ以上にやはりそれは《20年代》という時代のとらえどころのなさによるところが大きいのではないか。
「日本の《20年代》は失われている。それはまるで、存在しなかったかのように、切りとられ、前後がそれをはずして縫い合わされてしまっている」と海野弘は言う。多くの作家たちが東京という都市にあこがれ、東京を描こうと格闘しながらも、結果的に彼らは十分に都市を表現することでその時代を描き出す技法を編み出せないまま《都市》に別れを告げてゆく。その原因は、「ファシズムへと傾斜してゆく国家権力の弾圧による沈黙という外的なものであると同時に、都市表現の未成熟と行き詰まりという内的なもの」でもあった。じっさい、テクノロジーやメディアの進歩により東京は20年代、いまだかつてないスピードで変転していたし、作家たちにとっては影法師のようにするするとその手から逃れていってしまうような感覚だったにちがいない。そのあたりは、20年代を象徴する都市である「銀座」の特徴を、郡司次郎正、上司小剣、貴司山治らの作品から「すべてのものを出会わせ、混ぜ合わせ、媒介する」という空間性にあるとする第5章、第6章にくわしい。また、「雨の降る品川駅」という中野重治の詩に鋭い解釈をほどこした第11章は、「詩」を文学という局面からだけでなく、川柳や盛り場案内記、ルポルタージュなどをふくむ「都市表現」のひとつとしてとらえるべきと主張する海野弘の真骨頂で、全体の中でももっとも読み応えのある一章であった。
個人的な関心はこれまで、大正デモクラシーをつくった世代/大正デモクラシーを享受した世代にあったのだが、ここで取り上げられているのはいわば「大正デモクラシーを懸命に生きた世代」である。その多くは19世紀末に生まれた地方出身者であり、東京にあこがれ、その理想と現実のはざまで揺れ動きながら20年代に創作に打ち込み、30年代には失敗や挫折を経験する芸術家たち。この本は、彼らの格闘と挫折の痕跡に東京の《失われた20年代》を発見しようという試みであり、読みながら通奏低音のようにつきまとう《苦さ》の理由もまた、そこにある。その中では、雑草のように新宿に根っこをおろししたたかに生き抜こうとする林芙美子や平林たい子の姿は印象的で、一服の清涼剤となっている。
アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 4』
2013.6.1|review
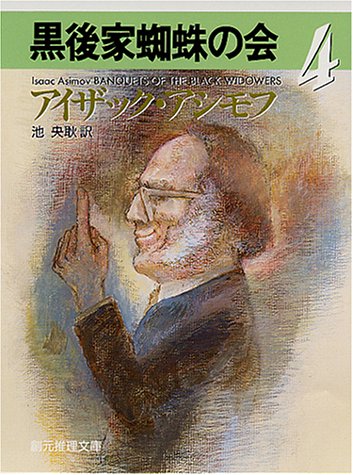
なぜか、この短編集では作家による「あとがき」が作品ごとに付されていて、このシリーズを読み出した当初こそ「これって必要?
蛇足じゃね?」と思っていたのだが、いつのまに、むしろちょっと楽しみに読むまでになってしまったのは、しばしば語られる初出時のタイトルをめぐっての《応酬》がことのほか愉快だからである。そして、その相手こそ、「エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン」の当時の編集長フレデリック・ダネイなる人物。
《応酬》とはいえ、作家本人によるあとがきゆえ攻撃は一方的なもので、たいがいは原稿を受け取ったダネイ氏によってあたえられたタイトルが「よろしくない」というものだが、ごく稀に、ダネイ氏によるタイトルの方に潔く軍配をあげることもある。けれども、その《応酬》の背景にふたりの強い信頼と友情が感じられなんともほほえましい限りなのだ。そう、ちょうど黒後家蜘蛛の会のメンバーにして、「犬猿の仲」であるルービンとゴンザレスのように。
内容は、第一巻から読んできたなかではこれがいちばん読みやすかった(逆に読みにくかったのは前刊)。読みやすいというのは、たぶんよりスノビッシュではないという意味で、そのぶん切れ味もやや鈍くなった印象もあるし、この巻ではこれまでにはなかった「椿事」が起こったりとそろそろ遠くに「黒後家蜘蛛の会」の終焉が感じられて愛読者としてはややしんみりした気分にもさせられる。残された最後の楽しみをいつ読もうか、目下思案中である。
PS.「フレデリック・ダネイ」なる人物について知りたくて調べてみてはじめて、エラリー・クイーンが「藤子不二雄」だという事実を知る。ハハハ
中村弦天使の歩廊―ある建築家をめぐる物語』
2013.6.6|review

″A House is not a Home″というバカラックの名曲を思い出す。明治から大正、そして昭和という激動の時代を舞台に、ひとりの「異端の」建築家の姿を6つのエピソードからあぶりだした不思議な風合いをもつ物語。
「家」とは奇妙なものである。たいがいの「家」は地面に建つ。物理的にはもちろんのこと、メタフォロジカルな意味でも、また。だから、ときに「家をもつ」ということはそのまま、そこに暮らす人間の〝現世への執着の現れ〟でもある。ところが、主人公・笠井泉二のつくる「家」はちがう。それは、現世に定着できず、ふわふわと宙空に舞っている依頼人の「思い」をかきあつめ、そこに納めてやるための「うつわ」、あるいは「モニュメント」のようなものとして描かれる。その意味で、主人公はみずから宙空を舞いながら人々のやりきれない「思い」を回収する、まさに天使的存在なのである。
彼の建築は普遍的ではないが、だれか一人のために役立つと語る、笠井の理解者である卯崎教授のことばが心にしみる。その後の主人公は、大陸でいったいどんな「街」をつくったのだろうか?
ほんのりとあたたかい心持ちで本を閉じた。
余談。主人公が暮らしているのは小石川植物園にほど近いところとなっているが、そこは当時「貧民窟」として知られた場所である。華族や実業界の大立て者をクライアントとし、みずからもけっして貧しくはなかったであろう主人公に自身の「家」としてあえてこうした土地を選ばせたところに、作者の、天上と地上とを自由に行き来する中間的存在に対する考え方を透かし見ることができておもしろい。装幀は、有元利夫が描いた作品であったなら……と個人的には思わずにいられない。
戸板康二『黒の狂女―中村雅楽探偵全集3』
2013.6.11|review
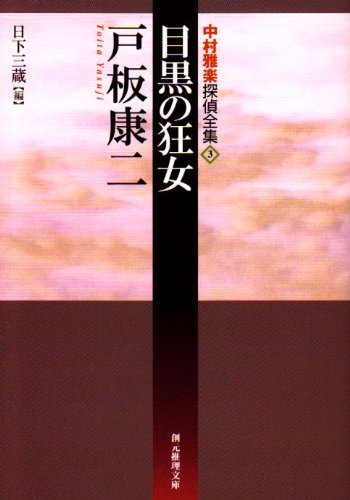
人間のよさ。戸板康二が描く「中村雅楽」という人物の魅力をひとことで言えば、そういうことになるのではないか。
鋭い観察力と洞察力とで身の回りに起こる「面白い」事件(「日常の謎」と言ってもいいが)を鮮やかに解決しながらも、そこにはいつも人間のあたたかい血の流れが感じられるのだ。それは、主人公「中村雅楽」が歌舞伎役者(しかも名門の出ではない)として人生の大部分を劇場で過ごしてきたことと無関係ではないだろう。役者はひとりでは生きられない。相方や脇役、裏方としてはたらくたくさんの人々、そして劇場に足を運ぶ観客がいてはじめて、舞台の上でスポットライトを浴びることができる。雅楽の、事件の当事者に対する慈愛にみちたまなざしはまた、そのように人は人を支え、人に支えられているという事実を彼がわきまえていることの証左であるだろう。
中村雅楽探偵全集の第3弾となるこの『目黒の狂女』では、これまで以上にそうした雅楽の「善さ」を感じさせる作品が多いような印象を受けた。このシリーズが発表年代順に収録したものであることからかんがえれば、そのような傾向にはこの時期(おもに昭和50年代)の作者の心境が映し出されているといえるかもしれない。この巻のおしまいに収められた『木戸御免』など、まさにそんな戸板流ヒューマニズムにあふれた佳作ではないだろうか。
そのむかし新劇が盛んだったころ、シェイクスピアの戯曲なども歌舞伎にならって見せ場だけを上演するようなことが行われていたらしい。雅楽の口を介してそんな大正期の演劇界の姿を知ることができるのもまた、このシリーズを読む愉しみのひとつである。
中村弦『ロスト・トレイン』
2013.6.12|review

はたして『銀河鉄道の夜』へのオマージュなのだろうか……?忌まわしい記憶とともに抹消された「まぼろしの廃線跡」をめぐるパラレルワールド譚。ふだんこの手の小説に縁がないため、こうした設定が古いのか新しいのかはまったく判らず。
人の一生というのは鉄道に乗るのと似ている、と鉄オタの平間さんは語る。「どこへでも自由に行けるかのように見えて、じつはそれほど自由があるわけではない」。すすむべき線路は一本ではなく、ところどころに乗り換え駅もあるけれど、うっかりすると「目指しているのとは全くちがう場所へ連れていかれてしまう」のだ。そんな平間さんが、ある日、忽然と姿を消してしまう。そして若い友人である菜月さんと主人公であるぼくは、わずかな手がかりをもとに消えた平間さんを捜して「まぼろしの廃線跡」をめざすのだが……。
ラスト、主人公の抱く不安は、菜月さんへの愛情と表裏一体をなすものであり、その意味で、大切な誰かを愛するということはまた、そこから逃げることのできない一本のレールの上にあって不安とたたかい続けることでもあるのだろう。
有吉佐和子『青い壺』
2013.6.14|review

この世に産み落とされ、その後数奇な運命を辿るのはなにも人間だけの専売特許ではない。「もの」だって同じこと。いや、むしろ自分の意志で移動できないぶん、「もの」の一生のほうがじつははるかにドラマティックといえるかもしれない。
というわけで、これは一個の青磁の経管をめぐる物語である。壷が「主人公」というので、壷がいきなり自分の人生についておしゃべりを始めるのではないかと心配したが、もちろん、そういうことはない。さまざまな偶然が重なり、さまざまな「家」を転々とする青い壷。そうしてその壷は、それぞれの場所で、思いがけずそのときどきの持ち主の心(それは美しい思い出であることもあれば、ときに醜悪な虚栄心だったりもするのだが)をまるごと映し出す鏡になる。最後、一見無関係と思われるエピソードが唐突に挿入されるが、そこから一息に導き出される決意が清々しい読後感をあたえる。
「弓香と律子は手を繋いで部屋を出た」。ごく短いセンテンスだが、50年ぶりに再会した女学校時代の旧友たちの時間を一気に巻き戻してしまうあるエピソードの後ろに置かれるとき、そこに彼女らの歳月が凝縮されて鮮やかに立ち上がる。いまの感覚からすると、それぞれの物語の描き方は往年のホームドラマのように大仰で滑稽な印象を拭えないものの、こういうハッとするような瞬間とたびたび出会えるのが、読んでいてなんとも楽しい一冊だった。
矢野誠一『落語家の居場所―わが愛する芸人たち』
2013.6.16|review

トラウマ?
はたまたナントカ症候群?
運よく「巨匠の時代」に居合わせてしまったがために、その後ずっと食い足りない気分を抱えながら過ごさざるを得ないこういう《不運》のことをはたしてなんと呼ぶべきか?
この『落語家の居場所』という本について、志ん生や文楽、圓生ら往年の「巨匠」たちと身近に接してきた筆者は、「むかしほど落語にのめりこむことのできないでいる自分」を発見し、それでも断じて「團十郎爺い」にはなりたくないと抵抗をみせながらも、けっきょくは「世紀末落語論」をめざしたつもりが「『よき時代の落語讃歌』にかたちを変えてしまった気味がある」と告白する。
とはいえ、この本からは年寄りの昔話に付き合わされたようなうっとうしさはほとんど感じられない。ひとつには、それは筆者が過去と現在とを比較するような書き方を意識的に避けているからだろうし、もうひとつには、現在にも通じるや寄席の「気分」といったものが、さながらRPGの「アイテム」のようにこの本の随所に隠されて(?)いて、そのつどいろいろなことにあらためて気づかされるからではないか。
「つまり、ふだん着で、ふだん使っているものを手にして、ふだんの声で、ふだんの言葉ではなすのが、落語なのである」(「古今亭志ん生の執念」)
これからの新作落語について。三遊亭圓歌の「中沢家の人々」や林家木久蔵(現木久扇)を引き合いに出しながら(風俗描写やナンセンスな状況ばかりにたよらない)「ますますパーソナルな色彩を加えていくような気がする」(「寄席」94.2.16)
三代目小さんと圓遊についての夏目漱石による評をとりあげ、小さんの方を持ち上げるのは漱石が「なにより江戸趣味のひと」だっかからと指摘、むしろ「新しい時代にふさわしい感覚」にあふれていたのは圓遊の方であった(「世紀末落語論」)
今日の落語を取り巻く状況について、聴衆をふくめた当事者たちのその危機感の薄さは四半世紀前とまったく変わっていないと指摘する一方で、そのぬるま湯につかっているような居心地のよさがかえって「激しい世の移り変わりという時間の流れのなかで、少しも動かない静かな時間をつくり出していたことに、じつは最近になってやっと気づいた」(「世紀末落語論」)
生涯つつましい長屋暮らしを通したことで知られる彦六の正蔵師匠に、反面、コーヒーは自分で挽いた豆をサイフォンでたて、食堂車でオートミールの食べ方を著者に得意げに教授し、「落語家のなかでホームスパンのジャケットを最初に着」るようなモダンな横顔があったことをはじめて知った。へぇ〜(「林家正藏の反骨精神」)
その他にも落語好きには刺激的なエピソードや指摘が多数。
沢村貞子『私の浅草』
2013.6.20|review

「江戸」と「東京」とがせめぎあう、さながら汽水湖のような1920年代の浅草。その浅草に生きる人々の暮らしを、ひとりの少女の目を通して活写した素晴らしいエッセイ。季節の到来を告げる年中行事の数々、無駄を出さない生活の知恵、どんなときにも背筋をシャンと伸ばした浅草の女たち…… そうしたひとつひとつが、まるでその場に居合わせているかのようにくっきりと像を結ぶ。少女時代の沢村貞子の観察眼、文章の腕前も見事だが、ひとりの大女優を育んだ1920年代の浅草の庶民の暮らしの《豊かさ》を見抜き、筆をとることを勧めた花森安治の編集者としての目利きぶりにも拍手をおくりたい。
ジェイムズ・エルロイ『ブラック・ダリア』
2013.6.25|review

《ブラック・ダリア》とは、ロサンゼルスで惨殺されたひとりの女に献じられた呼び名である。
猟奇的な殺人事件とその核心に迫ろうとする警官が主人公という点で、これはれっきとした犯罪小説であるが、と同時にこのフィクションの肝はもっと別のところに、《ブラック・ダリア》という女の存在によってはからずも自身が抱える心の闇に向かい合わざるをえなくなった人々の孤独な葛藤とその悲劇的結末を容赦なく描き出すところにあるようだ。ひとつの事件をきっかけに、平和な日常がアリ地獄のようにグズグズと崩落してゆくことの恐ろしさ。息をのむようなスピード感とは無縁。物語は、からまった糸を忍耐強くほどいてゆくようにジリジリした歩みで進んでゆく。
全編を貫く生々しさ、不吉さは、ロサンゼルスの暗部を身をもって知りつくした著者ゆえだろうか? 読者にもそれ相応のタフさが要求される。
芝木好子『湯葉;隅田川;丸の内八号館』
2013.6.30|review
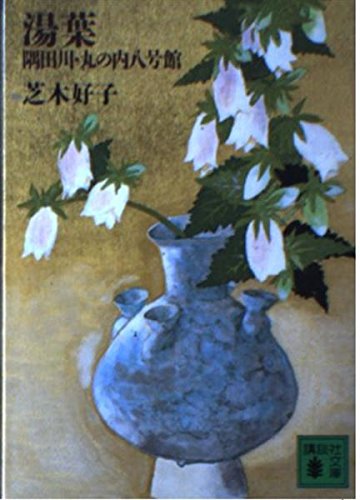
父権的なるものを失ったとき、ひとりの女としてどう生きるか?
母娘3代の生き様のちがいを描くことで、この3部作はあざやかに明治から大正、そして昭和という時代を映し出す。
3作通じてif(「もし…」)の用法を使うことで、「男」の死、あるいは消失によって「女」の生を描くという手法がおもしろいが、同時にそれぞれの時代を象徴するものとして、独自の工夫で一目置かれる湯葉屋、芸術的な染織にこだわりをもつ呉服商、そして当時「一丁倫敦」などともてはやされた丸の内ではたらく「タイピスト」といった仕事がえらばれているのが興味深い。
海野弘にならって1910年代、20年代、30年代という区分で読んでゆくと、またひと味ちがう眺めがひらけてくるのも印象的。第3部『丸の内8号館』の主人公・恭子は、じぶんの母や祖母とちがい、最後にはみずから父権的なるものに引導を渡すことでみずからの人生を歩き出そうとする。物心ついた時分に、浅草という当時の東京の「へそ」で道楽者の父親に溺愛されて育つことで大正デモクラシーの甘い蜜の味を知ったいかにも30年代の女らしい生き様だし、またそういう道しか選べないことでひとつの時代の終焉をまざまざと知らしめるのだった。
橋本千代吉『火の車板前帖』
2013.7.3|review
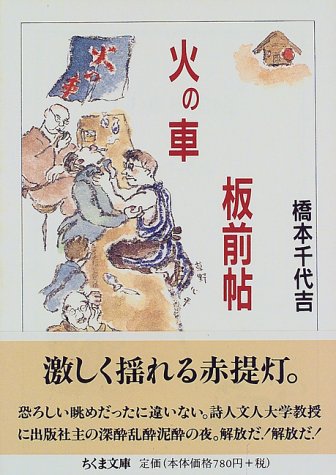
迷惑千万な人々。「商売を始めたら、手伝ってくれるね?」「ああ、いいですよ」うっかり返事してしまったばかりに、ある日突然、詩人・草野心平が開いた居酒屋の板前をやらされることになってしまった千代吉さんの怒涛の日々を綴った回想記。
しかし、それにしても、そこに集う人間どもの、揃いも揃ってなんと迷惑千万なことか。営業時間は完全無視、深夜に板前を拉致して他人の家を強襲、店主も入り乱れての殴り合いの喧嘩は日常茶飯事、増える一方の借金……ハッキリ言って常連客のほぼ全員が酒乱である。それがまた、みな綺羅星のごとき作家や文化人、事業家ばかりなのだから空いた口もふさがらない。そしてその喧騒に付き合わされ、尻拭いをさせられるのはいつもきまって千代吉さんときまっている。
それでも、たとえどんな目に遭わされようとも、千代吉さんの心平さんに対する忠誠心、忍耐強さ、心優しさは変わらない。本当に、千代吉さんは心平さんのことが大好きなんだなァ。
PS.思いがけず、戸板康二の名前が出てきたのには驚いた。彼もまた、酒好きらしく「火の車」の客人だったのである。
ヘニング・マンケル『目くらましの道』
2013.7.8|review

上巻
史上最悪の夏休み。白夜の北欧スウェーデンのスコーネ地方が舞台のクライム・ノベル(厳密には”警察小説”というらしい)。
北欧が、表面的にはもっとも美しく明るく輝く季節に、その裏側で繰り返される凄惨な殺人事件。その極度のコントラストは、ごくふつうの生活を送っている人間がその裏では陰惨な事件を引き起こすもうひとつの顔を持っている、というこの作品の中の犯人像と重なる。
主人公の警部ヴァランダーの「繊細さ」「小心さ」が、ときに捜査の上では武器になっている反面プライヴェーとではぐだぐだなところが可笑しい。
下巻
ふだんは人一倍読むのが遅いのに、半日で読了。新記録。
センテンスが短いのでリズムよく読み進むことができる。淡々と進みながらもいや増してゆく緊張感。訳者の手腕かもしれない。
北欧のひとびとがいかに夏休みを楽しみにしているか?
彼らがどのように夏を過ごすのか?
マイペースで、いなたい登場人物たち……(事件は悲惨だが、なんとなくの〜んびりした印象なのはそれゆえ?)。「北欧の人と暮らし」という視点から読んでも、なかなか興味深い一冊。
レーナ・レヘトライネン『雪の女』
2013.7.14|review

フィンランドを舞台に、女性刑事マリア・カッリオが活躍する警察小説だが、主人公はもちろん、被害者や被疑者にいたるまでそのすべてが「女性」という一風変わったミステリ。作者レヘトライネンも当然、女流。
ある冬の日、雪に覆われたヘルシンキ近郊の森の片隅で、男子禁制のセラピーセンター「ロースベリ館」の女主人が死体となって発見される。さっそく捜査に乗り出す男勝りのマリア。ところが、犯人探しと平行して、マリアの身に、《女性》性を意識せざるをえないある事件が起こるのだった。そして、突然見舞われた状況に逡巡しながらも、星座をつなぐように事件の真相は徐々にその全貌を明らかにしてゆく。
世界的にも女性の社会進出が進んでいることで知られるフィンランドから、こうした切り口の作品が登場することが興味深い。必ずしも、男女平等の夢の国ではないという現実。社会制度とはべつのところに、厳然と存在しつづける性差をめぐる差別意識の根深さ。現代の北欧社会が抱えるさまざまな問題を知るうえでも、とても参考になった。
全体にほろ苦いストーリーであるが、そんな中がさつなマッチョイズムの権化のようでありながら、マリアに対して人一倍繊細な気遣いをみせる同僚ペルッティの存在が微笑ましい。
シューヴァル&ヴァールー『ロゼアンナ』
2013.7.18|review
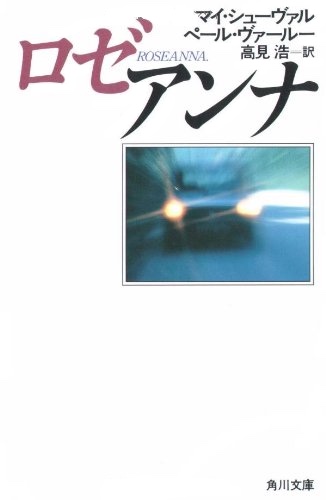
シリーズ「刑事マルティン・ベック」第一弾。犯人の動機に意外性があり、またそこに1960年代当時のスウェーデン固有の匂いのようなものが感じられる。
主人公が「頑固」「論理的」「沈着」という「警官として誇るべき3つの貴重な資質」に恵まれているのは本当としても、とはいえ、けっして「全能ではない」という点で警察小説ならではの醍醐味(?)は健在。じっさい、ここでも、地方の警察署や婦人警官、アメリカの片田舎の刑事などさまざまな個性的なメンツを巻き込みながら難事件の捜査は進められてゆく。それはけっしてすべてにおいて美しいチームワークとはいかないが、いざという場面でそれぞれが自分の役割を見事に演じ切っているところが気持ちいい。
美しく輝かしい夏に湖水地方で発生した事件が、なんの解決の糸口も見出せないまま季節は移ろい、秋を過ぎ、やがて不毛な冬へとさしかかる。この季節の経過がもたらすやるせなさに北欧人マルティン・ベックの焦燥感がシンクロし、沈鬱なムードを醸し出す。相手の性格を見抜き、巧みな尋問で自白を引き出してゆくマルティン・ベックの手腕はお見事。次作への期待も高まる。
持っているのは角川文庫の旧版。古書で探すなら新版(画像)より、日暮修一による装丁のすばらしい旧版の方をおすすめしたい。
シューヴァル&ヴァールー『蒸発した男』
2013.7.25|review
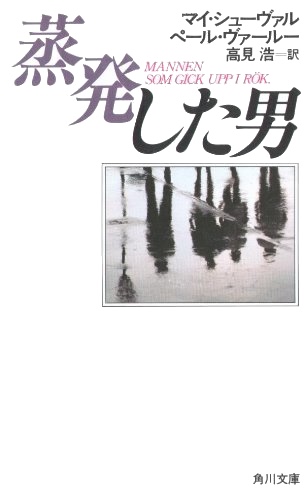
刑事マルティン・ベック、シリーズ第2弾は東欧ハンガリー編。冷戦下のブダペストで忽然と姿を消したスウェーデン人ジャーナリストの行方を追って、夏休みを〝24時間〟で切り上げたマルティン・ベックは単身ハンガリーへと飛ぶ。彼をつきうごかすものはただ、「どんな任務でも引き受けて、解決にベストを尽くそうとする本能」、一種の「刑事根性」にほかならない。
東西が分断された冷戦下のヨーロッパにあって、政治的な思惑から思うように進展しない捜査、麻薬密売組織、尾行者の影……
とさまざまなに伏線を張りめぐらしながらも真犯人は意外なところに。前作『ロゼアンナ』のカフカ刑事につづき、ベックは今回もハンガリーですばらしい協力者を得る。幸運な刑事なのだ。〝水と油〟な印象の同僚コルベリとも、ますます不思議に息があってきた。
犯罪小説と呼ぶには、前のめりになった読者を軽くいなすような結末はあまりに淡白すぎる気もしなくもないが、いっぽうで、絵葉書のように風光明媚なブダペストの夏を堪能できるのがこの本の最大のポイントとなっている。それは、待ちに待った夏休みを取りあげたことに対する、作者からのベック刑事へのせめてもの「罪滅ぼし」だろうか?
土曜ワイド劇場的な観光気分も満点。ラスト、バカンスに戻ったベック刑事に対する妻の態度が、不気味(笑)。
シューヴァル&ヴァールー『バルコニーの男』
2013.7.28|review
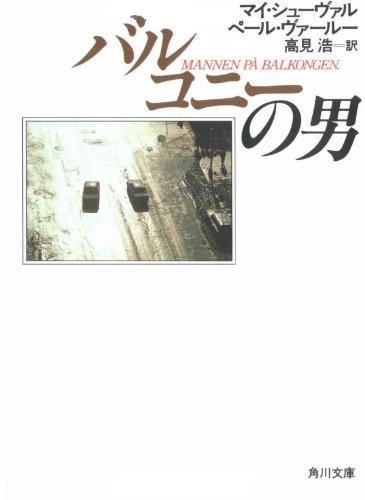
〝刑事マルティン・ベック〟シリーズ第4弾は、ストックホルムが舞台。「都会」が舞台ゆえ、ここではさまざまなパターンの「目撃」がストーリーを生んでゆく。見ていないようで見ていたり、偶然に見たり、こっそり見たり、あるいはまた見ているようで見ていなかったり……都市では無数の視線が交錯し、事件はその網の目のすきまに起こる。いわゆる都市型犯罪である。
連続強盗事件と連続少女誘拐事件、ふたつの神出鬼没に発生する事件を追いかけるマルティン・ベックらいつもの面々(今回新たに「グンヴァルド・ラーソン」なるなかなか強烈なキャラクターが加わる)は、クモの巣のように複雑に入り組んだ無数の「視線」に絡めとられてしまったか、今回ばかりはいつになく切れ味が鈍いようだ。そのかわり、ここでは市中を巡回している警官たちが思わぬ活躍をみせるが、それは彼らもまた、ある意味〝都市の目撃者〟なのであり、ときに「見ること」にかけてはマルティン・ベックら以上に〝プロ〟と呼べるからである。しかしこの、あえて「ヒーロー」をつくるのを拒むかのようなラストの呆気なさは前作同様。そこがまた、いかにも北欧らしくもあるなぁ。
シューヴァル&ヴァールー『笑う警官』
2013.8.1|review
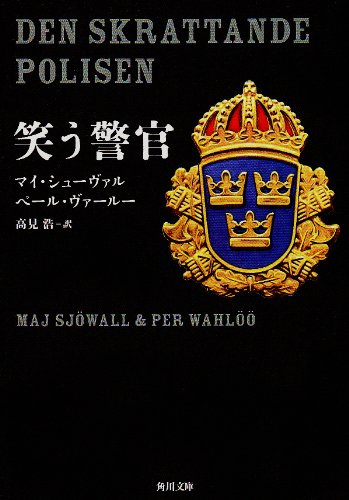
11月。長く厳しい冬の到来という〝現実〟を目の前に突きつけられる、北欧の人びとにとってもっと暗鬱な季節にその事件は起こる。ストックホルム市内を運行する路線バスの車内で発生した銃乱射事件。事件もまた、11月にふさわしく暗鬱だ。
偶然にも、その凶行の被害者の中にストックホルム警視庁の刑事マルティン・ベックの若い部下がふくまれていた。犯行の手がかりを探るため丹念に被害者たちの素性を洗ってゆくうちベックは、部下の死をたんなる偶然の事故として片付けるにはあまりにも不可解だという印象を抱く。やがて、捜査線上に16年前に発生し未解決のままとなっているひとつの殺人事件が浮上する……。
この『笑う警官』は、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの第4弾となるが、このシリーズの魅力は謎解き的な側面以上に、事件捜査にあたる個性豊かな警察官たちによる群像劇と必ずしもうまくいっていない夫婦間の心のすれちがいを描いたホームドラマというふたつの人間ドラマが同時進行してゆくところにあるのではないか。コルベリ、メランデルらいつもの面々は、それぞれの〝領分〟でいつも以上にその持ち味を発揮している。ノルディンやモーンソンら〝地方招集組〟もまた然り(ん?アールベリは?)。
前回から登場した〝憎まれ役〟グンヴァルド・ラーソンは今回もなかなかの舌好調ぶりだが、最後事件について語る言葉に彼に対する読者の印象も変わる。なお、タイトルの意味するところは、最後のページの最後のセンテンスで明らかになるのでお楽しみに。苦笑いと泣き笑いの青年刑事への鎮魂歌。
*北欧の名前になじみのない読者には、あるいは登場人物の名前に苦労するかも…。
シューヴァル&ヴァールー『消えた消防車』
2013.8.5|review

〝スウェーデン・ミステリの原点〟といわれる「刑事マルティン・ベック」シリーズの第5弾。
ストックホルムのダウンタウンで発生したアパートの爆発炎上事故、時をおなじくしてメモにマルティン・ベックの名前を残したまま謎の自殺を遂げた男、忽然と消息を絶った第三の男の足どりを追う中でぼんやりと浮かび上がってくる大規模な自動車密売組織の影……
。事件性の有無さえはっきりとしないまま、ベックらいつもの面々はこの〝支離滅裂〟な事件にずるずると巻き込まれてゆくのだが、この『消えた消防車』最大のみどころはといえば、グンヴァルト・ラーソン〜新人ベニー・スカッケ〜マルメ市警のモーンソンによる〝華麗なる捜査リレー〟だろう。こうした「脇役」たちの渋い活躍ぶりこそがまた、このマルティン・ベックシリーズの魅力のひとつなのだ。
春から夏、夏から秋へと季節が移り変わるのとおなじく、妻との不和、家庭内で唯一の理解者ともいえる娘の自立などベックの家庭を取り巻く景色も様変わりしてゆく。それはまた、厳しい季節の到来を告げる声でもあるだろう。自動車の盗難と密売、家庭崩壊や児童にまで蔓延するドラッグ問題、そして銃器を身につけない主義のコルベリを見舞った不運……
ここではスウェーデンの「負」の側面が拡大鏡でみるように誇張される。このシリーズがしばしば「社会派」、あるいは「スウェーデン社会の変遷をも描くドラマティックな大河小説」(訳者)といわれるゆえんである。とはいえ、テーマは深刻ながらも、随所に散りばめられた北欧流ユーモアのおかげでけっして重苦しいだけの気分には終わらない。モーンソンがおこなった尋問のテープを聞きながら、その予想外の〝巧みさ〟に一同首をかしげるシーンなどすごく可笑しい。これはモーンソンと作者、そして読者だけのヒミツ。そしてもうひとつのナゾ「〝消えた消防車〟は無事発見されるのか?」もお楽しみに。
シューヴァル&ヴァールー『サボイ・ホテルの殺人』
2013.8.11|review
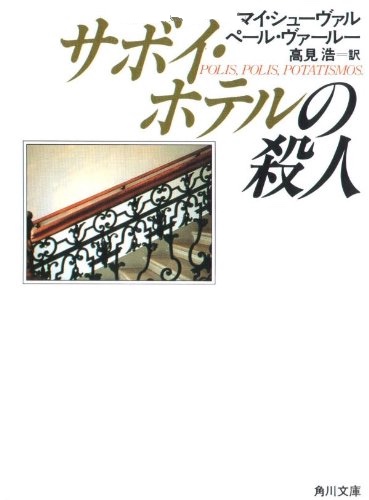
スウェーデン・マルメの高級ホテル、乱入したひとりの男によって射殺された〝ブラック企業〟のワンマン経営者。被害者は、国交をもたない国への武器の闇取り引きで巨万の富を築いたと噂される男だけに身内をふくめ〝敵〟は多い。それが捜査を攪乱させる。けっきょくは、些末な証拠の積み重ねとベテラン刑事の〝勘〟が事件を解決へと導くのは警察小説ならでは。しかし、事件の解決がかならずしも一警察官の気持ちを朗らかにさせるものではないというのもまた事実なのだった。「主任警視マルティン・ベックは、はなはだおもしろくなかった」(文庫版366頁)。
シリーズ〝刑事マルティン・ベック〟第6弾の特徴は、そこで起こる事件以上に、登場人物たちの〝私生活〟と彼らの〝心情〟がいつになくみっちり描かれている点にあるかもしれない。ついに妻との別居を決意したベックをはじめ、中途半端な夫婦生活もいよいよ終焉に近づきつつあるモーンソン、前作のアクシデントをきっかけにマルメに異動したスカッケ、コルベリ、オーサ・トーレル、そして独身主義者グンヴァルト・ラーソンがみせる意外なナイーヴさなどなど。このあたりの〝人間観察〟を楽しむために、読者はやはり第一作から順に読み進めるのがよさそうだ。
公安課のポールソンが道化役としておもに本作でのユーモア担当。そして、意外にモテるマルティン・ベック……うーむ、イメージの修正を図らねば。
シューヴァル&ヴァールー『唾棄すべき男』
2013.8.13|review
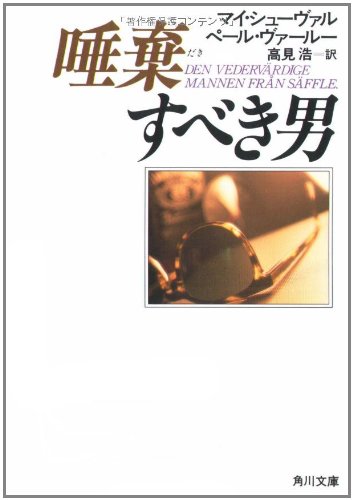
被害者も加害者も、そして捜査にあたる人間もすべてことごとく〝警官〟ばかりという徹底ぶり。それも当然、警察という〝組織〟こそが、ここでの主役なのだから。シューヴァル=ヴァールー夫妻が、〝警察小説〟という形式によって10年の歳月をかけて現代社会を描きつくそうと挑んだモニュメンタルな作品であるこの〝刑事マルティン・ベック〟シリーズもこれで第7弾である。
組織とそこに属す人間が、個と公(©アアルトコーヒーの庄野さん)のはざまで見せるさまざまな顔。職務上、自我を抑圧することが求められる日々ゆえ、ときにはほんとうの自分の顔すらわからなくなってしまうようなことさえある彼ら。無関心はまた、そんな爆発しそうな自我を押さえ込むためのいってみれば〝処世術〟ともいえる。公>個の日本では、同じように組織を描けば硬派な社会派ドラマになるが、個>公、あるいは個と公がおなじレベルで拮抗しているスウェーデンでは、組織を描いてもけっきょくは泥臭い人間ドラマになるのが面白い。そのちがいが興味深い。
ちょっとした会話やふるまいから、水と油と思われていたコルベリとラーソンのあいだの関係に変化の兆しが窺われるのがうれしいところ。これは続刊でのお楽しみ。いつになくド派手な展開ゆえ、映画化に際してこの作品が選ばれたのも納得!?
でも、ラストはそこで終わっちゃって本当にいいの?!
シューヴァル&ヴァールー『密室』
2013.8.17|review
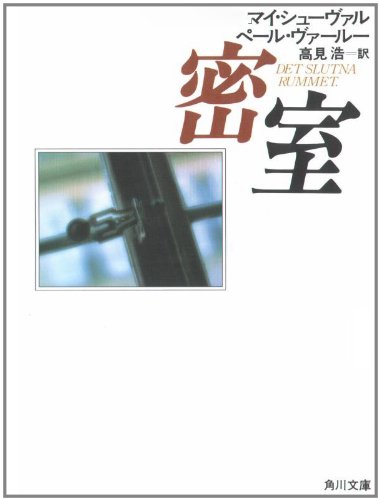
〝密室〟を描くことで、作者は都会に暮らす人びとの深い孤独を浮き彫りにする。1972年当時のストックホルムを覆っていた重苦しい空気について、作者はこんな風に書いている。「暴力は反感や憎悪のみならず、不安や恐怖をも醸成するものである。人々はしだいに互いを恐れるようになり、ストックホルムは不安に怯える数十万もの人々を擁する都市となった。そして、恐怖にすくみあがった人々は危険な人々でもある」(73頁)。そこでは、誰もが被害者になりうると同時に、いっぽう加害者にもなりうる。
そんな、抑圧された現代社会のもとで畏縮した都会人の心もまた、ある意味〝密室〟のように閉ざされている。その点、主人公マルティン・ベックも例外ではない。ようやく負傷からは立ち直ったものの、心に負った傷はまだ癒えていない。そんな折り、現場復帰し不可解な密室殺人事件の捜査に乗り出した彼は、その過程でひとりの生き生きとした女性と出会う。殺伐とした都会にあって、なにより人間的な絆を尊重する彼女の存在にやすらぎを見い出し、少しずつ生気を取り戻してゆくベック。読んでいて思わずホッとする。
密室殺人と銀行強盗、ふたつの事件が複雑に絡み合いながらストーリーは展開してゆく。都会特有のエゴイスティックな情報に翻弄され、身も心も疲れきった警官たち。不注意によるミス、独善的な捜査、情報の読み違い、焦燥感…… そんな負の連鎖の中まんまと網の目をすり抜ける狡猾な悪人の姿もまた、ほかならぬ都会人のもつひとつの顔なのだ。ラスト、現代社会にむける作者の目は、いつになく厳しい。
文中、ドッグフードを食べて細々と命をつなぐ老人という描写がたびたび登場するが、それについてはぼくも以前フィンランド人の知人から聞いたことがある。女性の社会進出が進んでいる北欧の社会保障制度は、そのぶん専業主婦に対してはひどくシビアなのだという。そのため、夫に先立たれ年金の支給を打ち切られた年老いた専業主婦のなかには、やむなくスーパーで手に入れた安価なドッグフードで命をつないでいるひともいるのだとか。まさに〝福祉国家の光と影〟といったところか。
そのあたりの経緯は、巻末に付された訳者によるペール・ヴァールー女史へのインタビューでも触れられている。シリーズが進むにつれペシミスティックな色合いが濃くなってきたのでは?という問いかけに対し、社会民主党政権が導入した「社会主義と資本主義をミックスしたような経済システムはけっして良い結果を生まなかった」と指摘しつつ、けっして当初から社会批判的なものを書こうとしていたわけではないと語る彼女。「つまり、この十年間におけるスウェーデン社会の変化が、わたしたちにペシミスティックになることを強いたと受けとっていただきたいわ」。
マイ・シューヴァル『警官殺し』
2013.8.25|review
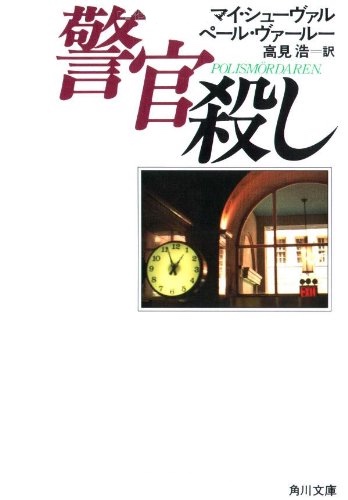
過去に登場した警官や犯人の〝その後〟を描き、〝主役〟にコルベリを据えた、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズのいわばスピンオフ的作品。
完結編を前に、ここで読者は作者とともにいったん立ち止まり、これまでの〝時間〟をあらためて確認することになる。よって、他の作品は単体でもじゅうぶん読むことができるが、この作品にかぎっては過去の8作品を読んでいないことには愉しみも半減してしまうにちがいない。
個人的に、このスウェーデンミステリの傑作シリーズで好きなのはシュールでアイロニカルな〝笑い〟の要素である。なので、前作に付された作者マイ・シューヴァル女史への訳者によるインタビューでそのあたりの〝秘密〟が触れられていなかったのがすこし残念だったのだが、ここでも『警官殺し』というタイトルふくめそうしたユーモアにあふれている。アキ・カウリスマキの映画にも通ずるこの〝笑い〟こそ、まさに北欧的だと思うのだ。
橘蓮二『カメラを持った前座さん』
2013.8.28|review
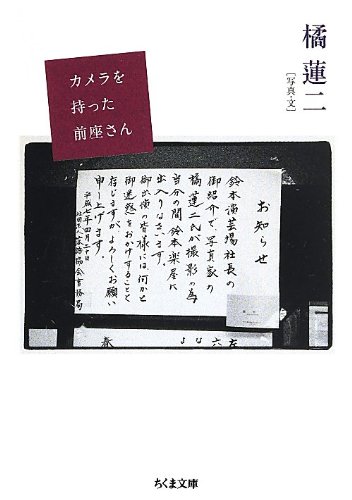
まさに「決定的瞬間ならぬ演芸的瞬間」!
時間調整のために入った本屋さんで、たまたま手にとりパラパラめくったが最後、そのままレジへ直行。よっぽどのことがないと、ふだん写真集は買わないんだけどなァ……。
ここで被写体となっている噺家の姿から伝わってくるのは、落語が、〝没入〟と〝俯瞰〟のギリギリの均衡の上に初めて成立する至芸であるということ。その所作は即興などではなく、練って練って、練り上げられてできたカタチなのだというのが手に取るようにわかる。その意味でも、オフショットではなく、高座での写真が多いのもうれしい。木之下晃が撮影した演奏家の写真からそのひとの音がきこえてくるように、橘蓮二というひとの写真からもまた、たしかに、そのひとの声がきこえてくるからだ。
「橘蓮二は十八年前、演芸に救われた写真家です」というあとがきの一節に集約されるような、それぞれの芸人に寄せたエピソードも淡々としているぶん、余計に心にしみる。いい買い物をしました。
シューヴァル&ヴァールー『テロリスト』
2013.9.2|review
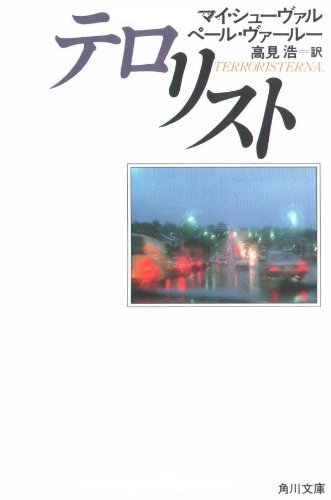
1965年から10年間にわたり、一年一作のペースで発表されてきた北欧ミステリの傑作とされる〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの完結編である。以下は、全10作品を通しての個人的印象。
◎定点観測としての警察小説
現代のスウェーデン社会が抱える問題について、〝定点観測〟的な手法で描き尽くしたいとかんがえた作者マイ・シューヴァル=ペール・ヴァールー夫妻が選んだのが「警察小説」というスタイルだった。犯罪こそは「高度福祉国家」のネガであり、それを職業柄誰よりも冷静にみつめているのが「警察官」という人種だからだろう。ひとによっては、ミステリ的要素よりもときに作者による社会批判的な要素が強調されることに違和感をもつかもしれない。たとえばこの『テロリスト』では、社会システムに翻弄される少女を登場させ、彼女のためにひと肌脱ぐ〝名物弁護士〟の言葉をかりて自分たちの考えを代弁させている。娯楽小説としてはノイズとなりうるこうした部分も、「となりの芝生はよく見える」的にふだん好意的に「北欧」を捉えているぼくらにとっては、〝内側〟からの眺めということで興味深い。
◎アンチヒーローとしての警察官
ここには、スーパーマンはひとりも登場しない。便宜上〝刑事マルティン・ベック〟シリーズとなっているが、他の警察官のほうが活躍する作品もあるくらいだ。全編をとおしてたびたび語られる警察官の〝素養〟とは「論理的な思考力、常識、律儀さ」であり、「すぐれた記憶力、ときとしてロバ並みと称されるほどの頑固さ、それに論理的な思考力」を兼ね備えたマルティン・ベックこそは実直で泥臭い、いってみれば〝警察官の中の警察官〟ということなのだろう。そうした警察官たちが、地道に、少なからぬミスもやらかし、ときに幸運に助けながらも難事件を解決してゆく様に、おなじくふつうの人間であるぼくらは共感をおぼえ、登場人物たちに対しヒューマンな魅力を感じるのだ。
◎笑い
シューヴァル=ヴァールー夫妻の〝笑い〟のセンスが個人的にツボであったことは、続けざまに全10作を読み通す上で大きな助けになった。緊迫した場面で、絶妙のタイミングで挿入されるアキ・カウリスマキ顔負けの脱力系ユーモアは、この〝マルティン・ベック〟シリーズのもうひとつの魅力である。ところどころに往年のコメディアン、ローレル&ハーディの名前も出てくるが、作者のふたりはきっとスラップスティックコメディーにも通じているにちがいない。『テロリスト』でいえば、たとえばテロとは無関係に唐突に起こる暗殺がいい例だが、階段から足を踏み外したかのような錯覚&失笑を読者にあたえ効果抜群。そうした仕掛けに、創作上のテクニックというよりは、むしろふたりの〝遊び心〟を感じる。
〝北欧〟と〝ミステリ〟という、個人的なふたつの関心事を同時に満たしてくれるという点で、このシリーズはまちがいなくぼくにとっては★★★★★だが、ここ最近注目されている「北欧ミステリ」の〝元祖〟ともいうべきこれらの作品が、現在『笑う警官』を除きふつうに書店で入手できないのはとても残念なことである。角川書店には、ぜひ新装版での復刊を願うばかり。
PS.このシリーズを読むことをすすめてくれたアアルトコーヒーの庄野さんに心より感謝!!
北村薫『いとま申して「童話」の人びと』
2013.9.11|review
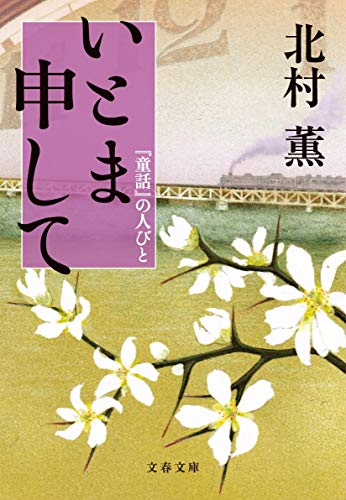
〝父と子の絆〟と言ってしまえば陳腐だが、その残された日記をここまで瑞々しく〝読む〟ことができるのは、読み手が「北村薫」という優れた作家だからという以上に、日記を残した人物の実の息子であるという事実の方がずっとずっと大きいだろう。
旧制中学〜大学予科にかけて、まさに青春時代まっただ中の「父」が記したことばの放つきらめき。それはときに、息子の知る、「謹厳実直を絵に描いたよう」な父親とはまるで別人のように映る。その驚き。冒頭の「スイカ」のエピソードが生きてくる。息子は、その日記のことばを媒介にして父と再会する。そして、その生前にはけっしてかわせなかったような親密な対話を果たす。
北村薫の父「宮本演彦」は、1909年横浜の生まれ。まさに多感な時期を大正デモクラシーとともに生きることのできた〝幸福な〟世代にあたる(同い年に、淀川長治、小森和子、山野愛子、野口久光、浜口陽三らがいる)。児童文学に熱をあげ、雑誌『童謡』の投稿コーナーの常連だった中学時代、おなじ投稿コーナーの仲間だったのが金子みすゞであり淀川長治であった。北村氏のていねいな注釈のおかげで、大正〜昭和初期、1920年代の横浜、東京の風景が鮮やかに立ち上がる。氏の「ベッキーさん」シリーズが好きなひとにはまた、たまらないものがあるだろう。
けっして楽な暮らし向きとはいえないまでも、医者で、地元の名士ともつながりのあった家庭で育った父はまだしも、その日の暮らしにさえ苦労している若者たちまでが熱心に童話や小説を書き、食べるものを食べずに同人誌をつくり、発表していたことにはひどく驚かされる。身銭を切ってまで『狂った一頁』を製作した衣笠貞之助もそうだが、市井の人々の中にもそういう胸に〝熱〟をもった人たちがたくさんいて、そうした人々がそういう時代をつくっていたのだろう。
梨木香歩『エストニア紀行』
2013.9.14|review

風変わりな旅だ。梨木香歩は、なぜエストニアを目的地に選んだのか。〝理由〟はけっきょく明かされないまま。にもかかわらず、その旅はこってり濃厚だ。旅をつづけるうち、どんどんエストニアの波長に同期してゆく著者は〝魔法使い〟のようなふしぎな力を備えた者にみえる。そのなかで発せられることばもまた、魔法のことばのオンパレード。
「人が森に在るときは、森もまた人に在る」
「性にまつわるものでも、そうでないものでも、野卑や下品は、世界ぜんたいの豊さを深める陰影のようなもの。そこだけ取り去ることはできない」
「人が自分の生理的な『これ以上はできない』の線引きをする場所は、それぞれ違っていて、その線引きの場所がその人の個性そのものの発露のように思われ、愛おしく感じられる。」
フィンランドと同じフィン・ウゴル語系に属するエストニア人。登場する単語もフィンランド語の響きに近いし、サウナを愛し、森を愛し、孤独を好むというエストニアの人びとの気質は、またフィンランドの人びとのそれに重なる。けれども、その「血」はエストニアの人びとにあってより純度が高く思われる。
彼らにとっての祖国愛とは「おそらく国家へのものというよりも、父祖から伝わる命の流れが連綿と息づいてきた大地へのもの」のように思われる、と梨木はいう。たしかにそうにちがいない。700年あまりの長きにわたって他国の支配を受け続けてきたという過酷な歴史が、彼らエストニアの人びとに「国家」という存在の空しさを教えるとともにそこから引きはがし、結果、コウノトリとおなじようなまなざし〜祖国は大地〜をもたらしたからなのだろう。
もう一度、たっぷりとエストニアを旅してみたいとこの本を読んで思った。
海老沢泰久『美味礼讃』
2013.9.25|review
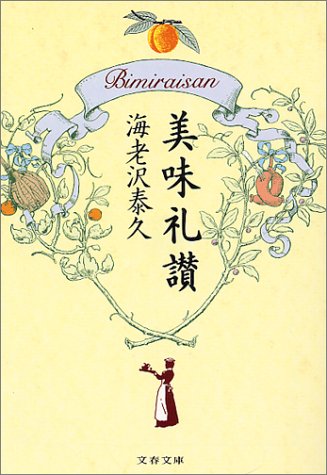
「辻調」こと辻調理師専門学校の経営者にして、日本に〝本物のフランス料理〟を広めた伝道者、辻静雄の半生を描いた伝記風味の物語。
プロの料理人でもない男が、なぜ〝フランス料理の最高の理解者〟としてキラ星のごときフランス料理界の重鎮たちから慕われ、信頼されえたのか?
それは、稀有な「舌」と「探究心」をもつ辻の存在を、彼らが〝ガストロノーム〟として認めたからにほかならない。そこに、料理人と〝ガストロノーム〟と呼ばれる客とのハイレベルな〝共犯関係〟によって栄華を極めてきた、フランスの食文化の奥深さを垣間見ることができる。
実在の人物を取り上げつつ、おそらくはかなりフィクションの要素も多いと思われるが、まるで運命に導かれるように辻静雄が料理の世界へと引き込まれてゆく様は、読んでいてワクワクする。著者のストーリーテリングの巧みさだろう。
高度経済成長前夜、世界へと飛び出した日本人のサクセスストーリーという意味で、小澤征爾の『ボクの音楽武者修行』にも通じる爽やかさも。子供のころ、テレビで『オーケストラがやってきた』や『料理天国』を観るのを楽しみにしていた世代には絶対に手に取ってほしい一冊。
高橋義孝『蝶ネクタイとオムレツ』
2013.9.30|review

大正2(1913)年、東京・神田生まれのドイツ文学者によるエッセイ。この世代によくみられるモダニスト、やわらかい心の持ち主かと思い手にとってみれば、やや期待外れ。
文中しばしば登場する「昔の日本はよかった」「近頃の若いもんは」「女というものは」式な発言は、なんだかおじいさんのお小言に付き合わされているようで、現代のぼくらからするとあまり居心地のよいものではない。とはいえ、エッセイを読むということは、心にピタリとくる一文をみつけるいわば「宝探し」のようなものと思えば、著者のいかにも江戸っ子らしい歯に衣着せぬ物言いと人間への洞察力に富んだ見方には、読んでいて目から鱗が落ちる瞬間も少なくなかった。
たとえば著者は、「はっきり言うと、うまいものは民主主義的ではありえないのである。うまいものは、少数の人間の独占物なのである。いや、そうならざるをえないのではないかと思う」と、〝自称グルメ〟たちがメディアに影響されて一流料理店に押し寄せるような風潮に釘を刺す(「異説・食べもの考」)。この点は、辻静雄の半生を描いた先日読み終えたばかりの伝記小説から受けた印象とも通じる部分があり興味深く読んだ。
また、おなじ文脈から「おしゃれ」を論じるとこうなる。おなじ「平凡な」身なりでも、「さんざん衣裳道楽した揚げ句の果ての平凡」と「ただの何の変哲もない平凡」とではその中身がちがうとした上で、こう言うのだ。「『渋さ』に至るには、その前に華美、派手の段階を通過していなければならない」。
他にも、無用のものへの偏愛を綴った「北海の魚」、エピソードから〝師匠〟内田百閒の〝人物〟をユーモアたっぷりに語った「忘れ得ぬ人々」などもよかった。
文庫版のあとがきは常盤新平、装丁は柳原良平。
入江相政『侍従長のひとりごと』
2013.10.11|review
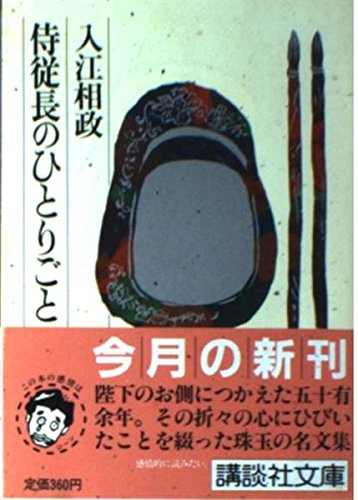
ジジュウチョウ。肩書きは硬いけれど、著者の心はとても柔らかい。
たとえば、趣味として楽しんでいた「書」について、その〝いきさつ〟をこう語る。「街をあるいていて、そば屋の看板の『そ』の字がすばらしいと思えば、すぐ手帳に書きとめる」といった手習いならぬ「目習い」を通して「書」に触れてきた。ゆえに「師はないが、またすべてが師でもある」と(「すべてわが師」)。
数え年というものがあったからこそ、すべての日本人が同じように感じ得た「大晦日」がもたらす「甘いセンティメンタリズム」(「歳末、正月」)など、戦前の日本人の心のありようについて触れた文章も、なるほどなぁと面白い。
せわしない現代に生きる読者にとっても、鷹揚なジジュウチョウの「ひとりごと」につきあうのは至福のひとときといえるだろう。
戸板康二『劇場の迷子―中村雅楽探偵全集4』
2013.10.21|review

鷹揚な「千駄ヶ谷の小父さん」が、意外な〝童心〟をのぞかせる「中村雅楽探偵全集」第4巻。77年から91年にかけて発表された28篇が収録されており、これで「中村雅楽」が登場する短編はすべて出尽くしたことになる。
事件は、劇場やその近辺に生じるいわゆる「日常の謎」がすべて。血なまぐさい殺人などいっさい起こらない。戸板康二の関心は、劇的な事件そのもよりも、歌舞伎役者ら劇を演ずる人間の心の内側のドラマに迫ることにあったのかもしれない。
この第4巻であたらしいのは、若き編集者「関寺真知子」がひんぱんに登場し、中村雅楽にさまざまな影響をあたえるところ。わずか3ページ強で、二人の役者が重ねてきた長い歳月を読者に感じさせる「銀ブラ」、失意の雅楽のために竹野がひと肌ぬぐ「おとむじり」など、これまで以上に地味ではあるが味わい深い小品が並ぶ。
林伸次『バーのマスターはなぜネクタイをしているのか?』
2013.10.21|review

舞台裏なんてわざわざ見せる必要はない、と主張する人たちがいる。いま見えている舞台こそがすべて、だからだ。一理ある。けれども、お店の主人がどんなところに心を砕きつつ日々を過ごしているか知るとき、客として、その店への共感や愛着がますます強くなるということだってあるだろう。
ここには、とある渋谷のワインバーの「舞台裏」が、ときにちょっと生々しいくらい書かれている。もしかすると、それをちょっと厭だなと感じるひともいるかもしれない。けれども、夜な夜な笑い声に包まれるそのステージはこんな舞台裏なくしては存在しがたい儚い世界だというのも、また事実。店の当事者にして、こういうことがらをしれっと書くことができ、しかもそれが許されてしまうのは、もう、ひとえに著者である林さんの人徳以外のなにものでもない(真面目に笑)。
知り合いの書いた本だけに勧めづらいこともなくはないけれど、これから個人でお店を開くことをかんがえているひとはもちろん、客としてお店を利用する側の人たちにもぜひ読んでもらいたい一冊。お店という「ステージ」は、お客様の存在ひとつで輝きも濁りもするということを、きっとこの本を通じていっそう深く知ることになるだろうから。
広瀬和生『落語評論はなぜ役に立たないのか』
2013.10.30|review

「BURRN!」編集長として音楽評論の世界に携わってきた著者が、落語評論家としてのみずからのアティチュードをまとめた一冊。
ここで著者は、落語の本質を「同時代の観客の前で演者が語る芸能」としたうえで、評論家とは「ツウの客」「最も良い客」であろうとすることで「演者」と「客」の中間に位置する「媒介」として、客の側に語りかける者、いわば「水先案内人」のうような存在であるとする。それゆえ入門者に対しては、歴史でもあらすじでもなく、まず同時代の「誰を聴けばいいか」という情報を提供することこそが評論家の役割ということになる。そしてこうした立場から生まれたのが、著者の『この落語家を聴け!』(2008年、集英社文庫)である。ここでも、最後に特別付録として「『落語家』『この一席』私的ランキング2010」が収められており、本編と付録とで一応は(というのは、本人がこれは「落語ファンとしての2010年の総括であって「決して『お薦めの落語家』のガイドではない」とわざわざ断っているので)「理論と実践」のような構成がとられている。
「なぜ知っている噺を何度聞いても面白いのか?」「『ネタバレ』で問題無し」「マクラの意味」など、落語初級者にとって興味をそそられる内容もすくなくない。
ロバート・チャールズウィルスン『時間封鎖』
2013.11.7|review

ある夜、突然いっせいに空から星が消える。そのとき地球は、何者かによってすっぽり皮膜のようなものに覆われてしまったのだ。同時に、地球上の時間だけが一億分の一になってしまっていた…。
いったい誰が?何のために?という疑問は最後の最後まで明かされない。わけのわからない状況に直面したとき、ひとは「科学的に理解するか、それとも宗教的に認識するかの二者択一を迫られる」。前者がここではジェイソンであり、後者がサイモンである。その仕方は正反対だが、ふたりはこの《スピン》と呼ばれる不可解な現象を自分なりに理解しようと努める点ではコインの表と裏のような存在といえるだろう。
《火星移住計画》《仮定体》といったキーワードは登場するけれど、この小説の背骨にあたるのはやはり人間を描くこと、ゆるぎない存在と信じていた地球がもはやグズグズと崩壊してゆく頼りない足場に過ぎないと知ったとき、ひとはなにを考え、どう行動するか、という人間のドラマを描くことにあるようだ。
いわゆるSFを読んだのは2冊めだが、人間のありようがしっかり描かれていること、訳文がこなれていて読みやすかったこと、そのふたつのおかげで最後まで一息に読み進むことができた。
追記
ただし…
ぼくの理解力不足だとは思うが、皮膜の外側に移住した地球の人間がなぜ「外側の時間」の制約を受けないのか?最後までなんとなく腑に落ちないままだった。
クラーク『幼年期の終わり』
2013.11.19|review

ちゃんと読んだSFはこれで3冊め。SFの世界では〝古典的名作〟とのこと。
ある日とつぜん巨大な円盤が上空に現れ、静止したまま地球を制圧する。やがて人類はそれに「オーバーロード(最高君主)」という呼び名をあたえ、畏怖するようになる。たとえば、子供にとっての親もそうだが、ガミガミ怒鳴られているほうがまだ気安く、対処のしようもある。恐ろしいのはむしろ、ただじっと黙って見守られているほうである。「オーバーロード」とはその意味で、人類にとっての「親」であり「庇護者」なのである。
〝好奇心〟からなんとか「オーバーロード」の実体に迫ろうとする人間の姿をえがいた第1部、第2部(ちなみに、第1部に登場する国連事務総長はフィンランド人!)。
さらに、ちょっと想像を超えたかたちで〝進化〟のありようが描かれる第3部。フィクションとはいえ、進化論にかんするまったくべつの異なる視点からの仮説(?)という意味で、著者の構想力に度肝を抜かれた。
広瀬正『マイナス・ゼロ』
2013.12.1|review
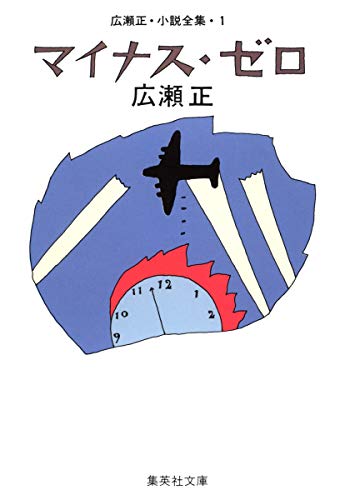
〝タイムトラベルもの〟と一言でくくってしまうには、あまりにもたくさんの仕掛けと色彩をもつ〝びっくり箱〟のような小説。
空襲のさなか、少年だった主人公に、18年後の同じ日、同じ時間にここに来るようにと言い残し絶命した隣家の〝先生〟。18年後、言いつけどおりその場所を訪れた主人公を待ち受けていたのは、人と人との不思議な縁(えにし)をめぐる時間を越えた旅であった……。
たとえどんな道を選ぼうとも、最後に辿り着く場所はひとつ。それが運命の赤い糸ならば、けっして途中でプツンと切れたりはしないものなのだ。
ちなみに、文中に登場するエピソードで個人的にいちばん好きなのは、自分に自分でごちそうを奢って少年時代の密かな思いを果たすところ。ちょっと乾いた洒脱な〝笑い〟もまた、この小説の魅力のひとつである。あとは、文字通り「現代っ子」らしい最後の娘の言葉。タイムマシンがあろうとなかろうと、けっきょく一番たいせつなのは「いま」なんだよね。
トレヴェニアン『夢果つる街』
2013.12.8|review

感想はひと言。「渋い」。
カナダのモントリオール、〝ザ・メイン〟と呼ばれる地区がこの小説の舞台である。一匹狼の〝警部補〟ラポワントは、移民や労働者、売春婦や浮浪者がひしめくこの吹きだまりの土地の秩序を、長いあいだ自分なりのやり方で守ってきたいわば〝番人〟のような存在。しかし、この街とそこに生きる人たちを誰よりも理解し愛しているのもまた、ラポワントそのひとなのである。そんな彼のホームタウンで、ある夜ひとりのチンピラが刺殺される……。
そこから話は二転三転……というわけには、ところが、全然いかないのである。事件の捜査に、動きらしきものが見えるのはようやく333頁になってから。全体の4/5は、濁った池の水面をじっと眺めているような案配。最後の1/5でその濁った水面が一気に透き通り、事件の全貌が明らかになるのである。
ただ、これはたぶんミステリではないのだろう。〝ザ・メイン〟という、時代から取り残された人々が身を寄せ合って暮らす時代から取り残された土地の物語だ。そしてその土地も、そう遠くない将来、近代化の波に押し流され消えてゆく運命にある。そしてそこに生きる人たちもまた。老兵しかり、モイシェしかり、心臓に手術不可能な動脈瘤を抱え、もはや警察署の中に味方がひとりもいない古いタイプの警官であるラポワントもまた、しかり。読了後、なんとも苦い後味が残る一冊。
エド・マクベイン『ダウンタウン』
2013.12.17|review
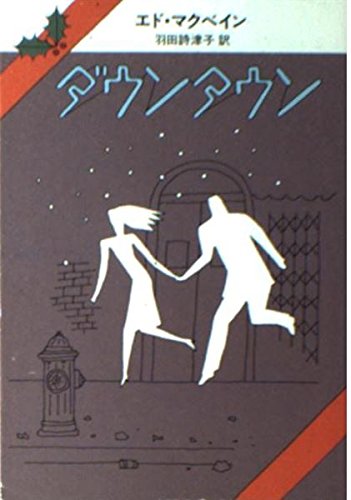
たんに相性の問題だと思う。警察小説の金字塔(と呼ばれているらしい)「87分署シリーズ」のエド・マクベインが手がけたクリスマスストーリー、しかも和田誠によるカバーということでワクワクしながら手に取ったのだが……残念ながら読了できず。
雪のクリスマスイブ。NYのダウンタウンでひょんなことから事件に巻き込まれ、なぜか警察から追われる身となってしまったちょっと軽いフロリダからやって来た男。そこに現れたのがひとりの中国系美女……。
さながら、80年代製ハリウッドのラブコメディーといった恋あり笑いあり殺しありのお話。たぶん主人公はマイケル・J・フォックス(ちなみに主人公の名前は、マイケル・J・バーンズ!偶然じゃないよね、コレ)。
トリックは面白そうなので、とにかくノリが合わなすぎて先に進めなかった。ノリの合うひと限定でおススメ。
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム『三秒間の死角』
2013.12.17|review

レコ屋のコメント的にいくと、まさに「必読!!北欧ミステリ最高峰!!」。
ジャーナリスト&元服役囚というスウェーデンの異色コンビ作家による第5作とのことだが、ぼくははじめて読んだ。これは凄い。読ませますね。
複数の登場人物たちの動きを、さながらカメラを切り替えるようにポンポンと見事なリズムで捉えつつ、巧みに読者をその特異で非日常的な犯罪世界に引き込んでゆく構成といい、それぞれ癖のあるキャラクターをさりげなく読者に刷り込んでゆくちょっとしたエピソードや振る舞いの描き方といい。
人々が生きるこの世界には表と裏、光と陰がある、という複眼的な世界観だけでなく、じつはそこにはそのふたつの世界を媒介するグレーゾンに生きる人種が存在するというのが、このストーリーのツボ。麻薬密売組織を壊滅するというミッションを担い、ある意味〝必要悪〟としてその存在の正当性を保証されている潜入者「パウラ」。ところが、彼は綱渡りのような危ういバランスの上に生きている。オモテの世界からもウラの世界からも切り捨てられたとき、「生き残る」という最後のミッションを賭けた「パウラ」の孤独な闘いが始まるのだ。そしてもうひとり、目の上のたんこぶ、昇進から永遠に見放された厄介者として上層部からも部下たちからも毛嫌いされている孤独な男、グレーンス警部もまた、その意味でグレーな存在にほかならない。この「簡単には諦めない男」と「命を賭けて生き残ることを決めた男」、ふたりの「執念」が火花を散らしながら重なり、爆発してゆくさまがたまらない。
そしてやはり、こんな重く暗いストーリーながら、そこかしこにあふれる北欧流のシニカルな笑いが好きだ。グレーンス警部と宿敵オーゲスタムのやりとりとか。
あっという間に読んでしまうので、買うときは上下巻まとめて購入するのがおすすめ。