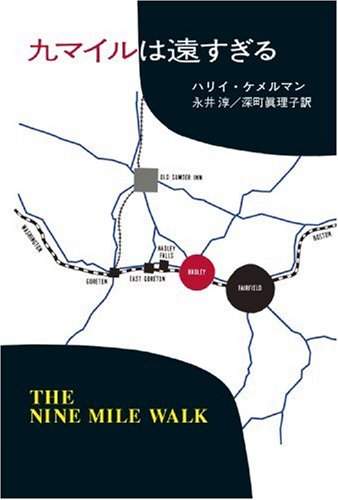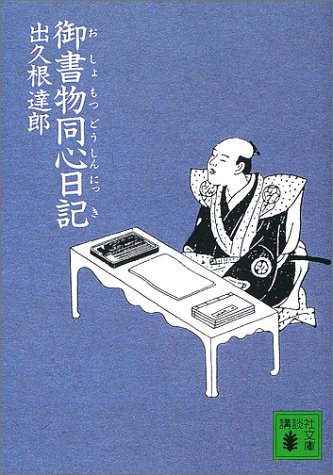阿刀田高『Aサイズ殺人事件』
2012.12.6|review
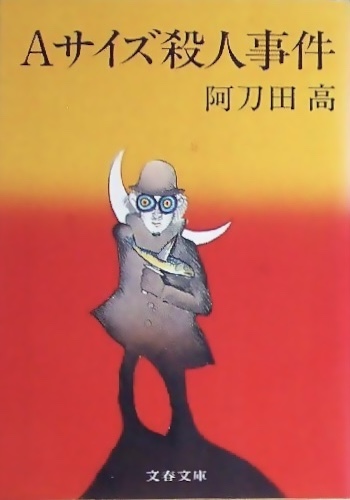
僧侶が囲碁の相手をしながら、そこで耳にしたわずかな情報をたよりに事件の謎解きをするという、いわゆる《安楽椅子探偵》モノの短編集。
北村薫の「円紫さん」にせよ、戸板康二の「中村雅楽」にせよ、「黒後家蜘蛛シリーズ」の「ヘンリー」や『九マイルは遠すぎる』の「ニッキイ・ウェルト教授」、『黒いハンカチ』の「ニシ・アズマ」にせよ、こちら側の世界に属していながらもどこか超然とした浮世離れしたところがあるのがぼくの考えるところの《安楽椅子探偵》の魅力であるのに対し、たぶんに狙ってのことではあると思うが、この阿刀田高の作品に登場する「方丈さん」はその個人的な理想像とはあまりにもかけ離れている。というよりも、むしろ正反対。ぼくにとってはその存在がややノイジーに感じられるが、これは完全にぼく個人の趣味嗜好の問題なのでなんともいえない。面白くないわけでは全然ないのだけれどね……。
読書にも、登場人物との相性というのがあるのだなと再確認。
小林信彦『紳士同盟』
2012.12.7|review

詐欺をテーマにしながらも、黄金時代のハリウッド映画を彷彿とさせる軽快かつ洒脱な娯楽小説。些細なスキャンダルをきっかけに次々と不幸に見舞われる(ちょっとカウリスマキっぽい)とあるテレビマンが、はからずも戦後の混乱期からバブル直前の80年代にまで及ぶ壮大な詐欺(コンゲーム)に巻き込まれてゆく。
カドカワ黄金期のアイドル映画の原作というイメージが強くなんとなく手を出さずにきたが、読んでビックリ最後の最後までダレさせない展開で面白いし、なにより犯罪小説ながら後味が悪くないのが好み。そして、薄っぺらくも、まだキラキラしていたころの東京の街の描写がなつかしい。
バロネス・オルツィ『隅の老人の事件簿』
2012.12.16|review
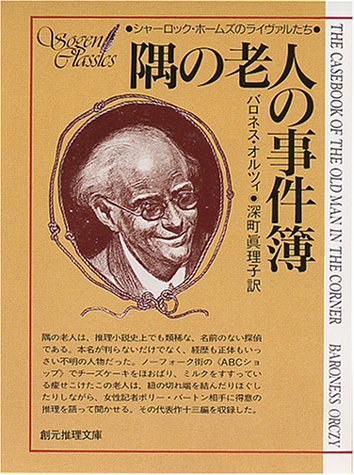
探偵、というよりはナゾトキスト!?
いつものカフェのお気に入りの席に陣取って、若き女性記者相手に楽しげに事件の謎解きをしてみせる怪しげな風貌の老人が主人公。最後の最後まで老人のプロフィールはおろか、名前すらも明かされない。
ミステリ好きの間では、この主人公をして「安楽椅子探偵」の最初期の一人と位置づけるひとも少なくないようだが、事件のたびに「検死審問(インクエスト)」まで出かけては、証言のみならず証言台にあがる人々の表情からその心理を読み取りつつ複雑に入り組んだ謎を解き明かしてゆく老人は、強いていえば「半=安楽椅子探偵」ということになるかもしれない。
ところで、おなじ「怪しげな風貌の老人」でも、「きょうはね、私は、ちゃんとやりますよ」と言いながら手にした紐を器用に操るのは寄席に登場する奇術師のアサダ二世だが、この老人も謎解きの「付属物」としていつも手にした紐に結び目をこしらえたり、ほどいたりしてみせる。そして、あたかも固い結び目をほどく仕草が謎解きの暗喩であるかのように、隅の老人は言うのだ。「あらゆる謎には解答がある。そしてわたしの経験によれば、もっとも単純な答こそ、つねに正しい答であるのさ」。
舞台は19世紀末から初頭のロンドン、上流階級の人々が次々と登場する物語は、ミステリ初心者にして、現代ニッポンの一般庶民には少しばかり分かりづらいものだったが、『黒後家蜘蛛の会』同様、繰り返し読むことで面白さが増してゆく本だと思う。
都筑道夫『砂絵くずし―「なめくじ長屋捕物さわぎ」傑作選』
2012.12.19|review

境界上の人々。奇体な香具師たちが巣食う江戸きっての巣乱(スラム)、ひと呼んで「なめくじ長屋」。その「なめくじ長屋」の住人にして砂絵師の「センセー」が、仲間たちの手も借りつつ江戸の町に起こる怪事件の謎を解き明かしてゆく短編集。
フィンランドで活動していたプロダクトデザイナー梅田弘樹さんとおしゃべりをしていたとき、日本人のつくるものには《湿度》がある、とおっしゃっていてなるほどと納得したおぼえがあるのだが、たしかに以前読んだ阿刀田高(『Aサイズ殺人事件』)にせよ大阪圭吉(『銀座幽霊』)やこの都筑道夫にせよ、不思議とその行間から《湿気》が立ちのぼってくるような気がする。主人公の「センセー」も、「センセー」をたよりに手柄を立てる岡っ引き「下駄常」もけっしていわゆる「善人」ではなく、人の心の光と闇をそのまま映し出す「鏡」のようなキャラクターとして描かれる。それゆえ、たんなる趣向としての「江戸時代」ではなく、庶民のあけすけな「生」への意志が充溢する「闇鍋」のような空間として、作者は舞台を「江戸」に選んだのではないだろうか。現代が舞台では、こんなふうに生き生きとマージナルな人々は活躍できなかったろうから。
主人公の生業が「砂絵師」であることから、推理に砂絵が役立つのかと思えばそうではないところが意外といえば意外。収められたもののなかには、「首つり五人男」や「らくだの馬さん」のように落語から着想を得たと思われるものも。作者と「推理小説マニアの従弟」とのゲームから生まれた「天狗起こし」「小梅富士」は、それゆえ「必然性を見いだすのに、かなり苦労した」と言うが、読者としてはその迷走しながら結論へと向かう道筋にむしろスリリングな読みごたえをおぼえる。最後に収められた「人食い屏風」のみがやや毛色が異なるが、物語的な面白みはいちばん。
加納一朗『ホック氏の異郷の冒険』
2012.12.24|review

痛快冒険活劇風ミステリ。欧化政策と国粋主義のはざまで揺れ動く明治時代の東京を舞台に、何者かによって盗まれた秘密文書のゆくえをめぐりイギリス人の探偵サミュエル・ホック氏(S・H氏)と医者の榎元信のふたりが協力して秘密の捜査に乗り出すという話。
幾多の障壁に行く手を阻まれながらも、西洋の知性と東洋の知性とが互いに補い合いながら事件の核心へと近づいてゆく、その様がなんといっても楽しい。また、大物政治家や男爵夫人、見世物小屋の人々、歌舞伎役者、壮士、警官、芸者などさまざまな「人種」が入り乱れて事件をややこしくしているのも、文明開化直後の東京の、そのメルティングポット的な様相を伝えるようで刺激的。
たまたま蔵の中から発見された、曾祖父の手記とも創作ともつかない文章をひ孫である「私」が現代語訳するという趣向が、読み手にほろ苦さを感じさせるエピローグで生きてくる。個人的には、いつも肝心なところで……
な梶原刑事がツボ。
出久根達郎『安政大変』
2012.12.30|review
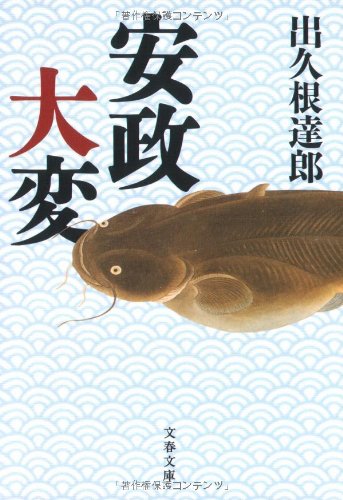
1855年の「安政江戸地震」を題材に、その発生前後の市井の人々にスポットをあてた短編小説集。
赤鯰も、群れをなす百足や季節外れの蒲公英も、夜鷹が口にする土のぬくもりや幕末の藩士が酒毒のせいと思う「揺れ」も、振り返ればすべて大地震の前兆にちがいないのだが、そのそれぞれが登場人物たちの人生に重ね合わせられることで、いつしか読者は人間の「生」について深く考えている自分に気づくことになる。巧いなぁ。
大地震や度重なる大火に幾度となく家や仕事を失いながらも懸命に生きる江戸の人々の姿は、だが、けっして哀れでも惨めでもない。むしろこの世の無常を理解しているからこそ、いまを生き抜く彼らの姿は強く、たくましい。