宇野信夫『はなし帖』
2012.9.5|review

「やあ、しぐれだしぐれだ」と相好を崩してはしゃぐ六代目菊五郎。初めて京都を訪れるという著者に、「まず京都の時雨を見せたい」と張り切って案内する歌舞伎の名優。ついに願が通じたのか、ある古刹で時雨に遭遇した折、その口をついて出た「ことば」がこれだ。
役者の台詞と思えばいかにも作為的なものを感じなくもないが、そうではない。むかしのひとの、それは世界への感受性の豊かさを物語る台詞であり、思わず口をついてでるこうした日々の「ことば」が、反対に名優の台詞を豊かに肉付けしてきたのだろうと思わせる。
紺屋の倅に生まれ、浅草橋場で生まれ育った著者はこうしてさまざまな人々と交流し、その豊かな「ことば」に触れてきた。植木屋や大工といった職人、物売り、志ん生をはじめとする芸人たち。だからこそ、この本を読むと、そうした市井の人々の暮らしが手に取るような感触をもって伝わってくる。
しかしそんな市井の人々の暮らしは、ある出来事を機にふっと消滅する。「戦争」である。著者はけっしてここで戦争について語っているわけではないが、市井の人々の暮らし向きの変化を物語るエピソードを介して、ぼくにはこの本がなにげに立派な「反戦歌」になっているような気がしてならないのだけれど……。
藤井宗哲『寄席―よもやま話』
2012.9.6|review
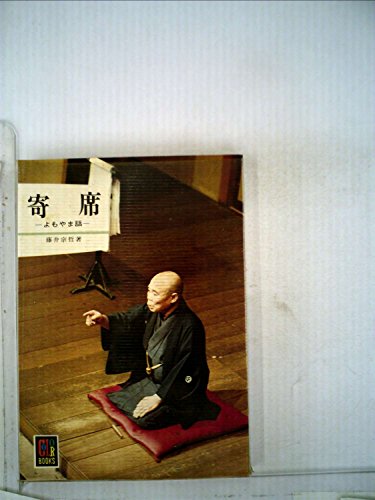
ときに「浮世の学問所」とも呼ばれる「寄席」という場所にスポットをあてた興味深い一冊。
著者は寄席で、「江戸や明治のころの職人や、武士や、さまざまな人たちの考えかた、生活ぶりなどの知識を得た」ばかりではなく、それらを通じて「人間として生きてゆくうえでの価値判断、そういったことまで教わりました」と語る(「はじめに」)。それはおそらく、いまもむかしも変わらないのではないだろうか?
ただノスタルジーをかきたてられる場所というだけでは、三百年以上も「寄席」は生き残れなかったろう。
カラーブックスらしく、寄席や寄席を支える人々の姿、そこに登場する芸人たちの表情、客のたたずまいなど興味深い写真も多数。だが、それ以上に興味深かったのは『醒睡笑』に始まり、上方、江戸における「中興の祖」たちの存在、そして三遊亭円朝から現代へと至る落語の変遷を、色物もまじえつつ「寄席」という場所が形成されてきた歴史としてまとめた巻末の解説文。たとえば、いまでも頻繁に口演される「野ざらし」という有名な落語が、明治期に活躍した三遊亭円遊によって現在のような滑稽噺として改作されたのはよく知られるところだが、そこには円遊なりのやむにやまれぬ「事情」があったことなど、この一文を介して知ることができた。
