Bear Pond Espresso『LIFE IS ESPRESSO』
2011.10.1|review
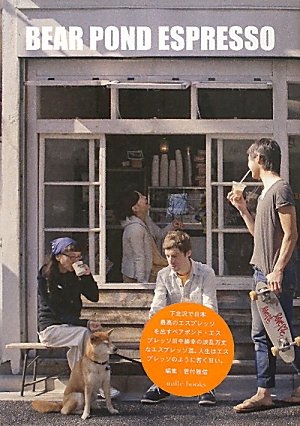
わずか15mlのエスプレッソに溢れんばかりのパッションとプライドを注ぎこむ、これは下北沢「BEAR POND ESPRESSO」のオーナー田中勝幸氏によるエッセイである。
大学時代はスキーやサーフィンにのめり込み、卒業後は大手広告代理店に勤めるも語学を磨くため仕事を辞め、渡米。その後、NYで一流企業に働きポストも得るが、ある日ダウンタウンで出会ったエスプレッソの味にノックアウトされ、気がつけば仕事をしながらバリスタの訓練を積む日々……。そして、「骨を埋める」気でいたアメリカの地を離れ下北沢にわずか6坪のカフェを開き、現在に至るまでのストーリーが熱い口調で語られる。
他人の目には波瀾万丈に映るかもしれないその過去も、本人にとってはたまたま情熱を傾けるべき対象が変わっただけで同じ一本道、いまの姿もことによったら「通過点」に過ぎないのかもしれない。チェーン店ではけっして味わえない、ちいさな個人店の魅力に触れるとともに、その「熱い」生き方に共感をおぼえるひとも少なくないだろう。ただしかなり熱いので、ヤケド注意!?
中沢新一『日本の大転換』』
2011.10.10|review
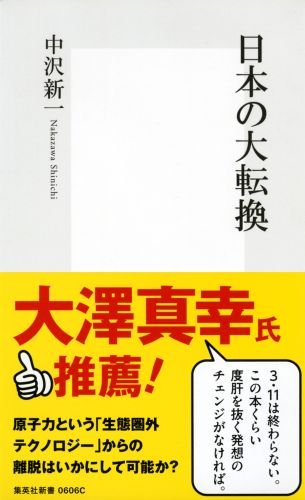
3.11をきっかけに「生き方や考え方を変えようとしている人々は、誰もがエネルゴロジストになれる」と中沢新一は言う。
エネルゴロジストとは、「地球科学と生態学と経済学と産業工学と社会学と哲学とをひとつの結合した、新しい知の形態」としてのエネルゴロジーを理解しようというひとのことであり、そうした視点から「この先」を見ようとするひとのことである。
そこで、まずこの本の前半では、いわゆる石炭や石油といった「化石燃料」と「原子力」との「ちがい」について語られる。太陽の恵みを、あくまでも生態圏の範囲内で長い時間とたくさんの媒介を経てつくられる化石燃料に対して、原子力は、ほんらい太陽圏の活動である核反応の過程をなんの媒介も経ずにそのまま生態圏のなかに持ち込んでしまう技術である。
石炭や石油について、限りある資源を大切にしよう、電気は大切に使おう、といわれるのは、それが自然によって与えてもらったものだというリスペクトがはたらいているからである。ところが、人間が科学技術によって自力でつくっている(と思い込んでいる)原子力については、オール電化を例に出すまでもなく「電気はどんどん使って、どんどんつくろう」ということになる。資本主義と原子力が「セット」であるゆえんだ。
それに対してエネルゴロジーは「第8次エネルギー革命」だと、中沢新一は言う。そのことは、補遺として収められた「太陽と緑の経済」でより具体的に説明が試みられている。
そこでは、原子力+資本主義から、自然の理法に則ってつくられるエネルギー+「つぎのかたち」の経済(ケネー=ラカン・モジュール)へと大きく舵を切ることの必要が、「贈与」「農業」「カタラテイン=交換」「地域通貨」「キアスム構造」といったキーワードとともに宣言される。
もし、このマニフェストがぼくら日本人に勇気をあたえてくれるとしたら、それは、今回の悲惨な災禍を体験したぼくらだからこそ、この大きな「使命」を成し遂げることができるのだと信じさせてくれる点にあるように思う。具体的な動きとして、著者が提唱する「緑の党のようなもの」が近々リアルな活動として始動し、この本はいわばその「マニフェスト」にもなるようだ。ぼく自身、よく考え、自分にできるかたちで積極的に関わっていこうと思っている。
許光俊『世界最高のピアニスト』
2011.10.12|review

「ピアノ嫌いのためのピアノの楽しみ方」という視点で書かれた、とにもかくにも刺激的なピアノ音楽の指南書。
ところで、ピアノという楽器は古くから人気の習い事である。なので、ここ日本にはピアノ学習経験者が山ほどいて、ピアノ曲愛好家の多くはじつはそうした人たちだったりする。けれども、伊達にピアノを知っているがために、ときにはそこでいわれる「感動」がじつは「感心」とイコールだったりもする。つまり、(自分が弾けないような)難解なパッセージを超絶技巧によってさらりと弾いてしまうとそれだけでひどく感動(じつは、それは「感心」なのだが)してしまうということである。なので、ピアノ好きのひとのおススメや解説書の多くは、そうした「技巧」という視点から評価され、紹介されることがとても多い。でも、ぼくのようにピアノを「知らない」人間にとっては、そうしたオススメや解説は「だからなに?」ってことも少なくないのである。
この本がピアノ曲を楽しむための指南書として画期的なのは、そうしたいわば「感心」と「感動」とをきっちり切り離した上で評価しようという意図が根底にあるところだろう。なので、シューマンやリスト,ラフマニノフといったピアノ学習者ウケのする作曲家の名前も、ここにはまったく登場しない。
そして、そうした「ルール」(?)をのみこんでさえいれば、ここで書かれている内容はけっして挑発でも過激でもなく、至極真っ当な意見と感じるはずである(もちろん、取り上げられたピアニストや演奏すべてに共感できるかどうかはまた別の話だが)。
個人的には、筆者のケンプに対する評価のツボは心からの共感をもって読んだ。
ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』
2011.10.19|review

表題どおり、この小説はなによりも美しく、なによりも儚いもの、つまり「きれいな女の子との恋愛」と「デューク・エリントンの音楽」に捧げられている。
ひさしぶりに読み直して感じたのは、精緻に描かれたコントラストの妙。物語は、街から色彩の消える冬に始まり生命が躍動する新緑の季節に終わるのだが、登場人物たちの世界はそれとは反対に、徐々に色を、そして音楽を失ってゆく。彼らはいってみれば、彼らの住む世界との「同期」に失敗したのだ。その残酷さと不条理さ……。
破天荒なファンタジーのような顔をもつこの小説をはたして「読める」かどうかは、ボリス・ヴィアンの「感性」にどこまで肉薄できるかにかかっているような気もするが、そのいちばんの方策はまず、解説で訳者が言うように「奇天烈さをごくりと飲み込」んで、そこに繰り広げられる「いっさいを受け入れる素直さ」をもつことだろう。
レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』
2011.10.26|review
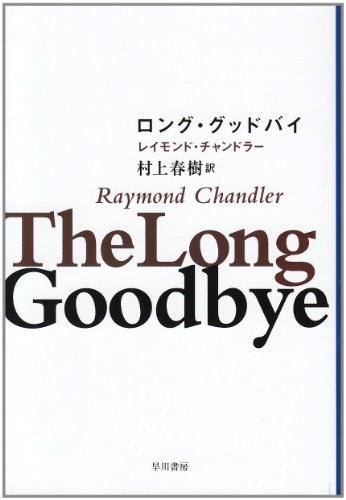
はたして、私立探偵フィリップ・マーロウの淹れるコーヒーの味は?
朝、フィリップ・マーロウはコーヒーメーカーでコーヒーを淹れる。それが習慣、というより彼にとって「決まり」なのだ。訳にはコーヒーメーカーとあるが、細かい描写を読むかぎり、それはパーコレーターのようだ。40年代、アメリカの一般家庭でよくみかけられたパイレックスの直火式パーコレーターかもしれない。一見ストーリーとは無関係のようでいて、そのじつコーヒーを淹れる所作はそのまま「フィリップ・マーロウ」という人間の説明にもなっている。
タフにみえて繊細、物事を順序立てて考える習性が身についている。すべてにおいて用意周到、こだわりが強く細かい部分もないがしろにしない。反面、頑固で、少しばかり融通のきかないところがある…。
すでに家庭ではふつうにインスタントコーヒーも普及していた時代だと思うが、毎朝わざわざパーコレーターを使ってコーヒーを淹れるような男、それがフィリップ・マーロウなのだろう。
山下清『日本ぶらりぶらり』
2011.10.28|review
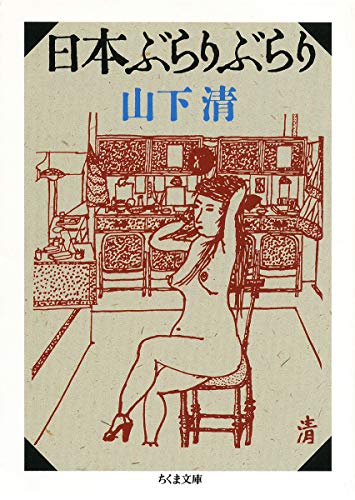
さながら山下清は、直球しか投げないピッチャーのようである。
「裸の大将」として知られる彼は、誰彼かまわずその言葉に疑問符を投げつける。なぜなら彼は、すべての言動の背後にはそう言われて然るべき理由があるとかんがえるからである。しかし、たいがいのひとは「なぜ」という理由を知らないで言葉を発していることのほうがずっと多い。
たとえば、道後温泉に行った清は、案内してくれたひとに「女ぶろ」を見学したいと申し出て断られる。そこで彼は、「なぜできないのですか?」と訊ねる。案内人は当然のように「キソクですから」と返答する。だが、納得のゆかない彼はさらにこう問いかける。「キソクは守らねばなりませんか?」。困った案内人はこう返答する。「(キソクを)もし守らなかったら温泉をやめさせられます。だからキソクはちゃんと守ります」。もちろん、これは「なぜ女ぶろを見学できないか?」の本源的な答えにはなっていない。なので彼はまったく納得していないが、場の空気を読んで「それ以上ぼくはききませんでした」となる。
こんな案配で、ときに清の投げる直球は胸元を鋭く抉って相手をのけぞらせる。それは、相手がよって立つ足場まで揺るがせかねないアナーキーな問いかけだからである。いつも清の問いかけに対してみんながどっと笑うのは、笑うことで問いじたいを無効化しようとしているからであり、いってみれば防衛反応にほかならない。けれども、彼は「どうしてみんなが笑うのか」いっこうにわからないのだ。ここに、山下清の孤独がある。
「ぼくだけがどうしておかしいのか、そのわけをきいてみたいが、きくとまたわからない返事にぶつかるので、ぼくはわからんでもだまっていようということにしている…」こんなにも笑えて、その後哀しくなる本もすくない。

