「世界ふしぎ発見」で発見!
2008.8.4|finland
フィンランドのラップランドを特集したテレビ番組『世界ふしぎ発見』。もちろんみなさんご覧になりましたよね?
じつは、この番組を放映している時間帯はふだんなら店で片づけの真っ最中、うっかり録画予約をし忘れてたぼくと遅番のスタッフは絶対に観れないねと半分あきらめていたのですが、この日奇跡的にお客様の引きが早く、もしやこれは「フィンランドの神様」の粋なはからい(?)と「音速」で作業をした結果、なんとか十五分遅れで観ることができたのでした。
そういうわけでひさしぶりにこの番組を観たもので、知花くららはポスト徹子の座を狙っているのでしょうか?とか、最後のクエスチョンを外したのは徹子サイドからの圧力がかかったせいでしょうか?などといったまったくフィンランドとは無関係なことばかり邪推しながら観てしまいました。
冗談はさておき、
番組中もっとも印象的だったシーンといえば、やはり「蚊」でしたね。レポーターの、そしてトナカイ追いの人々の頭に容赦なくこびりつく無数の蚊、蚊、蚊。最後のほうはもう蚊ばっかり見てしまって、いったいなにをしゃべっていたのかさっぱり頭に入らなくなってしまいました・・・。事実とはいえ、これはやっぱりイメージ的にはマイナスなんじゃないでしょうか。どうですかね?今後は夏場の北極圏での取材は受け付けない、もしくは経費等を全面的に世話するかわり画面上の蚊はすべてCG処理によって消すことと、といった対策をフィンランド的には講じたほうがよいのでは?などと思った次第。
ちなみに番組でも紹介された「リンゴンベリーのジャム」はmoiでも好評発売中!現在品切れ中ですが、今月半ばには再入荷するでしょう。
狂った野獣
2008.8.5|cinema
八月、夏休み、京都に行きたい、でも行けない(暑いしね)。それならば、というわけで、ゴロゴロピカピカと雷鳴が轟くなか「シネマ紀行 京都ものがたり」にでかけたのだった。

京都を舞台に撮影された三十本あまりの日本映画が日替わりで上映されるという好企画なのだが、そのなかでも「コレだけは絶対に観ておけ!」という三本を荻窪時代からの常連で、シネフィルのW女史にセレクトしておいてもらったのだ。きょうはその一本目、一九七六年の東映映画『狂った野獣』である。
W女史いわく「これはあまり岩間さん向きじゃないかもしれないけど」とのことだったが、パンフレットの「暴走バスが京都市内を猛スピードで大疾走!!全編ノンストップの傑作アクション」という超ハイテンションなコメントについついのせられてしまったというべきか。
で、ひとことで言うなら、この作品はスリル満点のド派手なカーチェイスと、一歩まちがえるとスラップスティックコメディーになりかねない危うさを秘めた「七十年代型娯楽大作」です。
宝石強盗犯が乗ったバスに逃走中の銀行強盗が乗り込んでくるというストーリーからしてキレているのだが、乗り合わせた乗客がチンドン屋に不倫カップル、おじいちゃん、思いっきり関西のおばちゃん、小学生ふたり(京都が舞台なのに、なぜかかぶっている野球帽は「巨人」と「大洋ホエールズ」)などというだけですでに笑える。そのうえ、運転手は心臓病持ちで途中ニワトリと犬も登場するのだからもうこれはほとんど史上最低のノアの箱船といったところ。観たひとならわかるだろうが、行き着く先がまた最低な世界なのだ(ちょっとモンティパイソン的でもある)。
あと、この作品では登場するすべてのひとびと(横転したパトカーからはいだしてくる警官さえも)が主人公であり、脇役である。それがめまぐるしく入れ替わる。なので、観ている側も視点の置き場を見つけられないままいっしょに翻弄されることになる。それはまた、観る側に善悪の判断をつけさせないための仕掛けでもある。だれが主人公かわからないので、どんな結末を望んでいるのか、迷走するバスと同様、観ている側もわからなくなってしまうのだ。
ストーリーはとにかくめちゃくちゃだが、見せ方(エピソードの挿入の仕方やタイミングとか細部へのこだわりといった)がとても巧みなので、途中飽きさせないし見終わった後にもちゃんと余韻が残る。ただ肝心の京都はといえば、どこを走っているのかさっぱりわからなかった(最終的には琵琶湖畔だったけれど)。ちなみに会期中、あと二作品観る予定。
水戸へゆく
2008.8.7|travel
八月、夏休み、どこかに行きたい(近場で、しかも涼しいところにね)。近場で涼しいところ、といえばどこだろう?
新幹線にのって軽井沢あたりの高原へ、というのも悪くない。が、夏の高原というのはじつのところそう涼しくはないものだ。空気が澄んでいる分、日射しは東京よりもはるかに強烈。しかもクルマなしで(←世界でもっともデンジャラスなゴールドカードホルダー)こういう土地に遊ぶというのは無謀というか、ほとんど不可能である。そのむかし、清里で熱中症になりかかった苦い経験が脳裏をよぎる(車で5分とあったので歩けると判断したら、30分ちかく店も自販機すらもない炎天下を歩くはめになったのだ)。
いっそ水族館へ、というのもひとつの手だろう。だが、ちょっと待て。夏休みの水族館なんて、ヘタしたらサカナの数より子供の数のほうが多かったりするものだ。涼しげに泳ぐサカナの前を、嬌声をあげながら駆け回る無数のコドモ・・・プラス、マイナス、ゼロ。ぜんぜん涼しくなんてない。
それならば、というわけで午前十時上野発の「スーパーひたち」に乗り込んだのだった。目的地は「水戸」。正確にいえば「水戸芸術館」である。館内の現代美術ギャラリーではいまジュリアン・オピーの大規模な個展がひらかれている上、さらに音楽ホールではこの日の午後、19世紀に製作されたピアノによる一時間強のコンサートもおこなわれる。
特急列車にのって片道およそ一時間で水戸に到着。バスにのりかえ水戸芸術館へ。その後は場所を移動することなく興味深いコンサートと展覧会のふたつを堪能、あとはおいしいコーヒーをのめる店を探して、名物の納豆でも買って帰ればちょっとした小旅行のできあがりである。《つづく》
エラールを聴いてかんがえる
2008.8.8|music

水戸ではまず、「ラ・カンパネラの生まれたころ」と題されたコンサートを聴いた。
「ラ・カンパネラ(鐘)」というのはパガニーニがつくった曲をもとにリストがピアノ用に編曲したもので、この曲がつくられた時代、つまり十九世紀半ばに活躍したリストやショパンの名曲を、その当時につくられたピアノ(フランス・エラール社1845年製)の音色で聴いてみよう、という企画である。
この十九世紀半ばのピアノと現代のグランドピアノとでは、ずいぶんいろいろな点でちがっている。たとえば大きさも三分の二くらいだし、鍵盤の数も三つ少ない。いちばんちがうのは駆体の構造で、現代のピアノにくらべるとはるかに木材から作られた部分が多いのだそうだ。そのため音量はより控えめだし、音色も現代のピアノに聞かれるような金属的なものではなく、もっと柔らかい響きがする。いままで当たり前のように耳にしてきた現代のピアノが、楽器というよりはなにやらフル装備の超合金ロボットめいたいかつい物体にさえ見えてくるのだった。
じっさい現代のピアノというのは低い音から高い音まで、すべてがムラなくきれいによく鳴る。ある意味、「優等生」というか。それに対してエラールだと、高い音や低い音はちょっと辛そうというか、相当キツいんだけど頑張って音出してます的な感じがするのだ。リストのような超絶技巧の曲を聴くと、その感じがいっそうリアルに伝わってくる。リストにせよショパンにせよ、彼らの創作意欲はその時代のピアノという楽器がもつ可能性をはるかに凌駕し、その枠組みを飛びだそうとしていたのかもしれない。
たとえば、ものすごく高い音や低い音、はたまた猛スピードでかけぬけるようなパッセージは聴くひとをハラハラさせドキドキさせ圧倒する。ものすごいことをやっているのだから、ものすごいことをやっているということが聴くひとにちゃんと伝わっていなければ意味がない。楽器が軋むくらい、音にムラがあるくらいのほうがかえってエキサイティングだ。ことにライブのような場であったなら。
すぐれた作曲家であると同時にすぐれた演奏家でもあったリストは、そういう《魔法》を誰よりも熟知していたにちがいない。エラールで弾かれた「ラ・カンパネラ」を聴きながらぼくはそうかんがえていた。ものすごいことも、やけにきれいに無理なく聞かせてしまう現代のピアノでもって聴き手を熱狂させるというのはじつはなかなか大変なことなのかもしれないな、とも。ピアノの弦にゴムや木片やらを挟んで、むりやり優等生にくわえタバコをさせる不良のような真似をするジョン・ケージみたいな作曲家もいなくはないけれど(じっさいある時代にはそれで熱狂するひとも大勢いたのだし)。
これまでショパンもリストもぜんぜん興味ないというか、むしろ嫌ってさえいるようなところがあったのだけれど、彼らの音楽をその時代の楽器で聴いたことでなんとなくツボがみえたというか、たまには聴いてみるのも悪くないなと思えたのは収穫だった。

などとかんがえつつホールを出て、水戸芸術館のミュージアムショップをのぞいたら『大作曲家名鑑』などというとんでもないガチャガチャを発見してしまった。旅におみやげはつきもの、しかも後々振り返ったとき、なんでこんなもん買っちゃったんだろうと後悔の念を抱くようなものほどよい、というわけのわからない理由からついつい手をだしてしまった。出てきたのは、よりによってショパン。しかもなんか不気味なんですけど。《つづく》
水戸でフィンランド!?
2008.8.9|cafe

京都の朝がイノダからなのだとすれば、茨城の午後はやはりサザからということになるだろうか。せっかくなら勝田の本店を訪れたかったのだが、残念ながら時間がなかったので水戸芸術館にほどちかいデパート内の支店でがまんすることに。待つ事しばし。たくさんのカップの中から選ばれて出てきたのは、おなじみアラビア社の「Paratiisi」。水戸まで来てもやっぱり待っているのはフィンランド、か。
そういえばもうひとつ。芸術館のすぐ目の前にはマリメッコの「UNIKKO」を看板のように大々的につかった美容室もあった。でも、なんだかちょっと残念な感じではあったなあ。《つづく》
ジュリアン・オピー展
2008.8.10|art & design

水戸へ行くことにしたのは、ちょうどいま水戸芸術館の現代美術ギャラリーでひらかれているジュリアン・オピーの個展を観たかったからだ。などというと、なんだかわざわざジュリアン・オピーを観るために水戸まで行ったように聞こえるかもしれないがべつにそういうわけではなく、以前からちょくちょくその作品を目にする機会があってなんとなく気になっていた作家の展示と、東京をはなれてどこかに行きたいというささやかな願望とが、たまたま「水戸」という点の上で交わったといった程度の意味である。
ジュリアン・オピーの、今回はBlurのベスト盤ジャケットに代表されるようなポートレイト、電光掲示板などをつかった動く人物、それに日本の浮世絵にインスパイアされた風景画といった最近の作品をあつめた展示だったのだが、とりわけぼくにはポートレイトがおもしろかった。遠目には同じようにしかみえない作品が、近くでみるとそれぞれ異なる技法―シルクスクリーンだったりフェルトのような起毛材だったり、あるいはカッティングシート(?)や液晶モニターを使ったものだったり―で描かれている。このあいだ雑談のなかで、「技法」にもっと注意を払って作品を観れば、作家がどんな主題をどのように描きたかったのか?よりくっきりと伝わってくるかもしれないなとあらためて、いまさらながら気づき目からウロコな思いをしたばかりなのだが、ジュリアン・オピーの場合はどうだろう?通る道(=技法)はちがっても、けっきょく行き着く場所はおんなじなんだ、と言っているかのよう。ここで、行き着く場所とはつまりポートレイトの対象となっている存在の揺るぎなさ、だろうか?
電光掲示板やアニメーションによる「動く人物」も、ひとを妙な気分にさせるシリーズだ。ダンスをしたり歩いたりしているひとびとの動きはやけにリアルで生々しい。ところがその身体の生々しい動きに反して、その頭はすべてたんなる「円」なのだ。それは記号をもった肉体なのか?それとも肉体をまとった記号なのか?これもじつは、『歩くジュリアンとスザンヌ』とか『下着で踊るシャノーザ』といった具合に「顔」ではなく、身体の動き、その特徴によって描かれるポートレイトなのだ。その意味では、「右手」だけ描かれたポートレイトもありかもしれないし、ことによったら発せられた「ことば」、「声」によるポートレイトというのだってありかもしれない。しかしそれ(もっともわかりやすい特徴としての「顔」)を「省く」ことによってではなく、あえて「円」という記号に還元してしまうことで新しいポートレイトの可能性を暗示してみせたオピーというひとは、やっぱり自覚的に現代を生きる先鋭的なアーティストのひとりなのだった。

ところで旅にはおみやげがつきものということで、水戸芸術館がこのオピー展のため特別にこしらえたという「オピー金太郎飴」である。だれに見せても「三谷幸喜」としか言ってくれません。
第一阿呆列車
2008.8.11|book
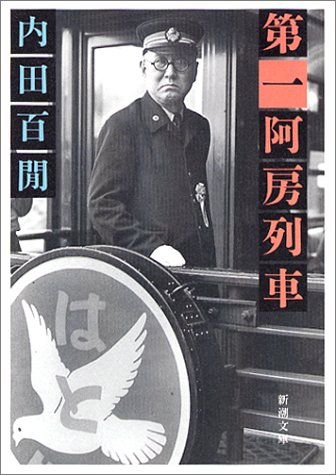
旅にもってゆく本については前にもいちど書いたことがあるけれど、読むたのしみもさることながら、来るべき旅についてあれやこれや思いめぐらしつつ選ぶことのたのしさのほうが、じつはむしろ勝っているのではないかと密かにかんがえている。
水戸にもっていったのは内田百閒のエッセイ『第一阿房列車』。
「用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」。なんの目的ももたず、とりたてて用意もせず、ただ列車にのってどこかへ行く、どうやらそれが内田百閒のいうところの「阿呆列車」であるらしい。まあ、今回のぼくだって、展覧会を観たりコンサートを聴いたりというのは「目的」というよりはむしろ東京をはなれるための言いわけみたいなものであって、そう思えばれっきとした「阿呆列車」にちがいない。
ところでその百閒先生、わざわざ「阿呆列車」のために借金までこしらえるのだが、その言い草がいかしている。いわく、「いちばんいけないのは、必要なお金を借りようとすること」である。それにくらべれば(阿呆列車のための借金は)「こちらが思いつめていないから、先方も気がらくで、何となく貸してくれる気がするであろう」云々。勝手な言い分だが、一事が万事この調子である。大阪へと出発するためやってきた東京駅の改札では、「何の為にどんな用件でこうまで混雑するのか解らないが、どうせ用事なんかないにきまっていると、にがにがしく思った」なんて言っている。いちばんのひま人はアンタだっつーの!
それにしても、なこの偏屈100%っぷり。小心者が、理屈をこねて自分を正当化しているこの感じにどこか見覚えがあると思ったら・・・なんだ、自分だった。というわけで、いまのうちからぼくも「ヒマラヤ山系」君のような絶妙な相方をさがしておかねば。
喜劇の黄金時代
2008.8.12|cinema

京橋の東京国立近代美術館フィルムセンターで、一九五七年につくられらた映画『喜劇の黄金時代』を観た。
いにしえの、という言い方がいかにもぴったりくるアメリカのコメディー映画なら、ぼくはわりと観ているほうじゃないだろうか。ダニー・ケイやアボット&コステロの凸凹シリーズ、ディーン・マーティンとジェリー・ルイスの底抜けシリーズ、広川太一郎がやりたい放題の吹き替え芸を披露したトニー・カーチス主演の軽妙なコメディーなど、そのほとんどは平日の午後や雨で野球が中止になったときなどに埋め合わせ的にテレビで放映されたものだが、そういったしょうもないコメディー映画を高校生のころのぼくは心待ちにしていたのだった。
でも、きょうこの映画のなかに登場したコメディアンたちはもっともっと古い時代、一九二〇年代のサイレント映画の時代に活躍し、そしていまではすっかり忘れ去られようとしているコメディアンたちであり、もちろんぼくは彼らについてはなんにも知らない(かろうじてローレル&ハーディの名前くらいは知っていたけれど)。
ベン・ターピン、ハリー・ラングドン、ローレル&ハーディといったコメディアンたちが活躍した場はスラップスティックコメディー、つまりドタバタ喜劇の世界である。『喜劇の黄金時代』は、これら古きよき時代のドタバタ喜劇をこよなく愛するフランスの映画監督ルネ・クレールが「過去のすばらしい遺産」を次の世代に引き継いでゆくため、その典型的なパターンや当時のひとびとから喝采をうけた名場面、撮影技法などを編集し再構成した作品なのである。
すっぽり穴に落ちたり木の葉のようにひとが吹き飛ばされたりするシーン、頑丈そうな壁が突然ガラガラと崩れたりポッキリと電信柱が折れたかと思えば、ズボンやシャツ、スカートがおもしろいように破れ、パイ投げの大パニック(参加人数は百人単位!)に発展するといったいまではすっかり「お約束」のギャグも、ほとんどすべてこの時代に「発明」されたもの。いまあらためて観ても、こんなにどでかいスケールのギャグを次から次にCGなしに、役者たちがみな体を張って撮影していたかと思うとまったく感嘆させられる。セリフで笑いをとれないサイレント映画の時代のコメディアンたちにとって「体を張る」ことはもっとも重要な才能のひとつだったかもしれないが、『世界の喜劇人』のなかで小林信彦が指摘しているように、観客を驚かせ、手に汗握らせ、最後に大爆笑へと導くためにはそれだけではじゅうぶんではなかった。
ジェームズ・エイジーという人物のエッセイを引き合いにだしながら、小林信彦はそのあたりのことをこんなふうに書いている。
その動きは単なるドタバタではなく、詩があった。つまり、当時のベン・ターピンのようなスタアたちは、笑わせる技巧に加えて、アクロバット、ダンス、パントマイムなどの訓練を積んでいたのである。
クローゼットの奥にぐちゃぐちゃに放り込まれた本の山からひさしぶりに発掘されたこの本を、映画を見終わった後、銀座の「十一房珈琲店」でパラパラとめくっていたのだけれど、上の文章をみつけて「なるほどね~」と腑に落ちた。コーヒーだってそうかもしれない。いい豆を使ってきれいに淹れることは大切だが、はたしてどうしたらその一杯のコーヒーに「詩」が宿るのか?
夏休みに、なかなかいい「宿題」をもらった。
切手で旅するフィンランド
2008.8.13|event

八月は通常の火曜日にくわえて、夏休みとして水曜日もお休みをいただいているmoiですが、きょうはイベント開催のため夜のみ営業させていただきました。以前よりご案内しているトークカフェ#03『切手で旅するフィンランド』です。
夜になってもいっこうに暑さが引かない鬱陶しい天気の中、今回もたくさんの方においでいただくことができました。足を運んでくださったみなさま、どうもありがとうございます!
イベントはフィンランドの四季をさまざまな切手デザインをとおして辿ってゆくような内容で、歴史的なお話からフィンランドのひとびとの意外な一面まで、上山美保子さんのわかりやすいお話でご紹介していきました。背景にあるストーリーを知ることで、一枚一枚の切手の図案が愛おしく感じられるような、そんなお話になっていたのではないでしょうか?
なお、来週の水曜日20日開催分につきましてはまだ若干の空きがございます。ぜひ参加されたいという方は、お早めにお申し込みいただければと思います。どうぞよろしくお願い致します!
だからなんだよ
2008.8.14|column
都内某所の商業ビルで上の階へ行こうとエスカレーターにのっているときだった。
足下になにやら気配を感じる。見れば、動いているエスカレーターにイモ虫のように這いつくばってひとのズボンの裾をツンツン引っ張るやつがいる。しかも外人だ。ジローラモに三ヶ月間ハンバーガーとコーラしか与えなかったらこうなるだろうという予想図みたいな風体をした外人である。
なに?
と問うと、ジローラモの不良品のような男はこう言うのだった。「ドゥ、ユー、ノウ、シュウジ・テラヤマ?」
シュウジ・テラヤマ?寺山修司??なんだコイツと思いながら、ああ、寺山なら知ってるよ、と答えると、
ユー、ノウ、シュウジ・テラヤマ!グレイト!アイ、ライク、シュウジ・テラヤマ!などと勝手に感動している。ますますなんだコイツである。いけないクスリでもやっているんじゃないか。握手しようと差し出す手を振りきり、「Oh....Oh...」という叫び声もそのまま無視してさらに上の階へと上がってしまった。
しかしこのとき、じつはなぜか思い浮かべたのは「シュウジ・テラヤマ」ではなく、「シンジ・タニムラ」のことだった。寺山修司と谷村新司がなぜ、じぶんの中で一緒くたになってしまったのかはまったくもってナゾであるが、突き詰めて考えたいと思わせるところのまったくないナゾでもあるので、もうどうでもいい。
それにしてもこういう
だからなんだよ。
と言いたくなるような経験はなんとなくひとをイライラさせる。だからこうしてブログに書いて発散しているわけだが、これを読んだひとはたぶんこんなふうに呟くんだろうな。
だからなんだよ。
最近のパブリシティーから
2008.8.17|publicity
雑誌「散歩の達人」のエリア版MOOK『ザ・東京さんぽ―昭和な東京を歩く』の「吉祥寺」のパートにてmoiをご紹介いただいています。店主がれっきとした昭和生まれということ以外にとりたてて「昭和」を感じさせる要素はありませんが、お散歩がてらぜひお立ち寄り下さい!
個人的には、人生の大半を東京で過ごしてきたくせにほとんどなにも知らない「下町編」が興味深かったです。ぶらぶら散歩してみたいものです(・・・涼しくなったら)。
もうひとつ、雑誌「MOE(モエ) 2008年 09月号」のポニョ特集、じゃなくて、フィンランドの絵本作家ユリア・ヴォリの特集で、フィンランドのイラストにかんするインタビューにちょこっと登場させていただいています。
フィンランド人の世界観にはどこか汎神論的なところがあり、ちょっと乱暴かもしれないのですが『カレワラ』にも『ムーミン』にもそういった世界観が反映されていて(もちろんユリア・ヴォリにも)、それゆえ日本人にとっても皮膚感覚で理解できる部分がとてもあると思うのです。というわけで、ぜひフィンランドの絵本やイラストをもっと身近に楽しんでもらいたいと思います。今回は、個人的に好きなふたりの作家もご紹介していますのでぜひご覧下さい!
なお、あさって19日[火]まで東武百貨店船橋店で「白夜の国からのおくりもの~フィンランド・エストニア絵画展」が開催中です。お近くの方はぜひ!
詩の話にはじまって
2008.8.19|book
こうるさい父さんのように、ひまな日にはいろいろとスタッフに質問攻めして煙たがられているのだが、このあいだもいろいろと質問攻めにしていたらスタッフのひとりが休みの日には「詩を読んだりしている」と言うのだった。
「へぇ~、どんな詩?」と聞き返すこうるさい父さんは、もちろん「詩」なんてぜんぜん知らないのである。高校時代なんとなくかっこよさそうというだけで、当時池袋の西武デパートの本屋の一角にあった「ぽえむ・ぱろうる」というちいさな詩の専門店でアレン・ギンズバーグの詩集を買ったはいいが、生きている世界のあまりの違いに挫折。それならば、とコクトーやアポリネールに挑戦するものの、物売りの口上のような堀口大學の七五調の訳文にまったく「パリのエスプリ」なんて感じられずこちらも玉砕。唯一、天野忠翁のユーモアと北園克衛は楽しめたが、北園克衛のは「詩」というよりもカルダーのモビールみたいな、「ことばによるオブジェ」といったほうがふさわしいので、やっぱりあまり「詩」は肌にあわないのだと思っている。それでも、ひょんなことからポエトリーリーディングのイベントやCDを制作したりしていたこともあるので、正直こころの片隅ではなんとなく気にかかっているのかもしれない。
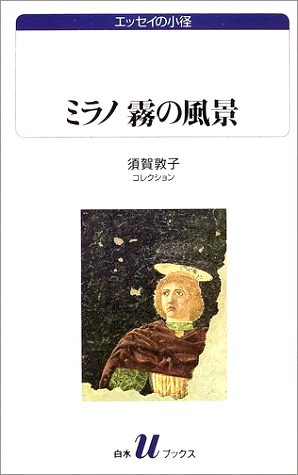
で、そのスタッフがよく読むのはウンベルト・サバの詩集だという。ウンベルト・サバ・・・、ウンベルト・サバ?名前だけはどこかで、しかもごく最近耳にした憶えがあるのだけれど・・・思い出せない。でも、あるとしたらやっぱりいま読んでいる須賀敦子の本の中でしかないだろう。そう思って、読みさしの本のページをもういちど最初からパラパラとめくってみるが見つからないのである。不思議だ。すると目次よりもさらに前、扉のところにウンベルト・サバの、須賀敦子自身によって訳された詩の一節の引用されているのを発見したのだった。
石と霧のあいだで、ぼくは休日を愉しむ。
というフレーズではじまる『ミラノ』という題名の詩だ。この詩をみたとき、エットーレ・スコラという監督が撮った『BAR(バール)に灯ともる頃』という映画のことを思い出した(舞台はミラノではないけれど)。夜霧のなかにぼんやりと光るオレンジ色のバールのあかりがすごく象徴的で、しみじみ心に残るよい映画だった。なんとなくあべこべだが、どうやらウンベルト・サバの詩集を翻訳し紹介したのが須賀敦子だったみたいだ。
ぼくはイタリアにはまったくと言ってよいほど関心がないので、いままで須賀敦子の本を手に取ったことがなかった。なぜ急に読むことにしたのかというと、毎日あまりにも暑いから、にほかならない。あんまりにも暑いと、CDでもつい音数がすくないものを選んでしまうのとおなじで、静かな文章が読みたかったのだ。
それだけの話。
追加開催決定!『切手で旅するフィンランド』
2008.8.20|event

トークカフェ『切手で旅するフィンランド』。おかげさまで8/13分は受付終了しましたが、追加開催が決定致しましたのでご案内させていただきます。なお、内容は13日と同じです。
フィンランドといえば、じつは知るひとぞ知る切手天国。ヘルシンキ中央郵便局のミュージアムで、その多様な切手デザインの世界に魅了されたひとも少なくないはず。そして、その一枚一枚の愛らしい図柄の数々はまた、フィンランドのひとびとの暮らしや文化を知る重要な手がかりでもあります。
今回は、フィンランドの子供たちに大人気の『フーさん』シリーズの翻訳家で、自身切手コレクターでもある上山美保子さんをお迎えし、切手を道しるべにしたフィンランドの旅へとご案内いたします。
参加方法については下記の通り、どうぞふるってご参加下さい!
◎ トークカフェ『切手で旅するフィンランド』
おはなし:上山美保子(翻訳家/通訳/語学学校講師)
日 時:8月20日[水]19時30分~21時
※13日分は受付終了いたしました。
会 場:moi[吉祥寺]
参 加 費:2,000円(おみやげつき)
申し込み:メールにて予約受付。定員に達し次第受付を終了させていただきます。
おかげさまをもちまして、無事終了致しました。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。
パラジャーノフの『ざくろの色』
2008.8.21|cinema
パルコ。
パラジャーノフの映画『ざくろの色』を観ながら、なんども心の中でそうつぶやいてしまった。

一九八十年代のPARCO(パルコ)のCMは強烈だった。ワケのわからない映像(たいていは奇抜なメイクをした外人によるおかしなパフォーマンスとか)が延々とつづき、「なんだこりゃあ?」と思っていると最後にようやく「パルコ」というナレーションがロゴとともに登場するというもの。それまでの商品連呼型CMのいわばアンチテーゼとして、究極のイメージ戦略(=CMを見てもいったい「パルコ」が何なのかさっぱりわからない)をとった八十年代のセゾングループの象徴ともいえるシリーズだった。そしてぼくらは、いつしか「ワケわからんもの」の代名詞として「パルコ」を認識するようになっていたのである。テレビでワケのわからないCMが流れれば「ああ、パルコね」と理解し、街でワケわからない光景に出くわしても、ひとこと「パルコ」とつぶやけばすべてが納得できるような、そんな錯覚にすらとらわれていたのである。
調べてみると『ざくろの色』が製作されたのは一九七一年。そして日本で公開されたのは八十年代を通り過ぎた一九九一年で、配給はやっぱりと言うべきかシネセゾンだった。十八世紀のアルメニアの詩人サヤト・ノヴァの生涯を伝記としてではなく、無数のイメージによる織物としてつづった「映像詩」といってよいこの『ざくろの色』は、(変な話だが)それほどぼくにとってはどこかなつかしい匂いのする作品だったのである。思うに、往年のパルコのCMを製作したCMディレクターたちはきっとこうしたパラジャーノフらの映像作品から多大な影響を受けているにちがいない。
ところで、この映画ではたくさんのイコンで埋め尽くされた伽藍の中をさまよっているかのような絵画的な映像美が印象的なのだが、じつは忘れてはならないのはその「音」の扱いではないだろうか。流れ落ちる水の音、風にはためく本のページの音、岩肌にノミを立て墓碑銘を刻む音、馬の蹄の音、ざくろをむさぼり食う音などなど。五官を狂わすほどに過剰なまでにデフォルメされたこれらの「音」は、観るひとを現実から引きはがしてしまうに十分である。ホラー映画ではいまや常套手段だが、音が映像の強烈さをいっそう引き立てている。
(すでに評価が定まっていたり、採算性の見込めるものしか日の目を見ることがなくなった)九十年代以降のカルチャーしか知らない世代は、ストーリーも解釈の余地すらもなく、ほとんどすべてを観るものの感性に託したこの映画を観て、自分の感じ取れる世界のあまりの狭さに愕然とし、ぶちのめされて欲しいものだ。それは、けっこう快楽でもあるから。↑YouTubeにすこしだけ映像がありました。
→セルゲイ・パラジャーノフ監督作品『ざくろの色』
日本での上映契約満了にともなうスクリーンでの最終上映。8/22[金]まで渋谷シアターイメージフォーラムにて。
リンゴンベリージャム
2008.8.22|info

先日放映されたテレビ番組『世界ふしぎ発見』でも「クエスション」として登場した「リンゴンベリージャム」が再入荷しました。スウェーデンで定評のあるFELIXブランドのものです。
テレビではトナカイ肉に添えて食べるということで登場していましたが、北欧ではミートボールに添えて食べたりもします。すごく酸っぱいということはないのですが、さわやかな酸味があるのでお肉などにも合うのですね。もちろん、パンやヨーグルトに添えても文句なしにおいしいのですが、ベタベタと甘くないので濃厚なバニラアイスクリームにかければそれだけで北欧風デザートになります。ちなみにmoiではスコーン、それにプレーンのパウンドケーキで生クリームといっしょにお出ししています。
ところでリンゴンベリーといってもあまり聞き覚えがないかもしれません。日本名で言うとコケモモ、フィンランドではPuolukka(プオルッカ)と呼ばれていて、その絵柄はアラビアの陶器のモチーフになるほど親しまれています。
まだまだ日本では販売しているお店も多くはないので、ぜひご来店の折にはお求め下さい。なお、おなじFELIXの「スライスピクルス」も同時に入荷しております。こちらもディル(香草の一種)とシナッピ(北欧独特の甘みが強めのからし)で味付けをした北欧独特の、とてもおいしいピクルスです。
百年「と」ピエール
2008.8.23|music
友人で、音楽家・ギタリストの高橋ピエール君のイベントが明晩、吉祥寺のブックストア「百年」でひらかれます。
ピエール君はなんというか、ムーミンのお話に登場するスナフキンのような人物です(本人はきっと顔をしかめるだろうけれど)。ひょろっと背が高くて、いつもよっこらしょとギターをかついでいて、おまけに寒くなる季節にはマントを羽織ったりしています。そしてそれがすごく似合ってるのです。まあ、そんな雰囲気もあるのだけれど、それ以上にかれの登場の仕方がなんともいえずスナフキン的で、ふらっと遠くから帰ってきたように、いつも不意にモイを訪ねてきてくれるのです。
じつはきょうも閉店の片づけをしていたら、薄暗い店内にニコニコ立っていてほんとビックリさせられました(笑)。ひさしぶりにもかかわらず、おたがいの近況報告などよりも「耳鳴りの話」とか「おたがい白髪が出てきたね」などといった雑談で盛り上がってしまうゆるさも、まあ相変わらずでしょうか・・・。
今回のイベントでは、高橋ピエール君のギター演奏を中心に映像や効果音、詩の朗読なども織り交ぜた多彩な内容になるとのこと。個人的には、ちいさなブックストアでひらかれるというだけで、もうなんだかどこか遠い異国の匂いなどがしてきて、いてもたってもいられない気分になってきます。モイから歩いて三分くらいの場所なので、ぼくも片付けが早く済んだら駆けつけたいと思ってます。ここを読んでくださっているようなみなさんにもおすすめですヨ!
詳細は、OLD/NEW SELECT BOOKSHOP「百年」さんのホームページをご覧下さい。
【SALE】2008 ムーミン サマーボウル
2008.8.24|finland

フィンランドのアラビア社が夏季限定で販売するムーミンのイヤーマグ&ボウルのシリーズ。ことし2008年は海辺を優雅に散策するフローレンが描かれています。水色とオレンジ、それに山吹色のストライプが印象的ですが、眩しすぎないというか、ちょっとくすんだトーンが子供っぽくならず大人の方にもおすすめです。
さて、気がつけばここのところめっきり朝晩は涼しくなってきました。夏もそろそろ終わりに近づいたようですね。そこで、ムーミンの2008年版サマーボウルをネットショップよりも安い最終セール価格で限定販売させていただきます!もちろんベースとなっているのは、カイ・フランクのデザインによるARABIA社のTEEMA(テーマ)ですので品質、使い勝手は大変すばらしいものです。
アラビア ムーミン 2008 サマーボウル【限定3個のみ】
通常価格¥6,300 →¥5,500(税込み)
※取り扱いは当店店頭のみです。在庫がなくなり次第終了させていただきます。
※正規品ですが輸入品のため化粧箱はつきません。あらかじめご了承下さい。
※地方発送は承れませんが、ご連絡いただければお取り置きは可能です。
なお、マグカップ(写真前方)につきましては、おかげさまで当店の扱い分はすべて完売となりました。ご了承ください。
カフェ&レストラン 2008年9月号
2008.8.25|publicity

連載中のコラム「CAFEをやるひと×BARをやるひと」。発売中の雑誌『カフェ&レストラン』2008年09月号では、「お店にできること」というテーマで「飲食店と文化発信(?)」といったことについて書かせていただいてます。
モイではちょこちょこイベントをやったりもしていますが、個人的には、「文化を発信」しようなどという気概は毛頭もなく、かといって自分もいっしょに楽しみたいから、という理由でやっているのかというとそれもちょっと違うような気がしています。とにかく日頃からかんがえているのは、モイにできること、モイがやるべきこと、モイにしかできないことってなんだろう?という問いかけであって、モイでお客様にコーヒーを出したりサンドイッチを出したりしているのとおなじように、なにかモイならではの楽しみを提供できたらいいな、という感じ、つまりメニューをかんがえるのと同じようなことだったりします。いまもいろいろ画策中なので、乞うご期待!
ところで、今号から『カフェ&レストラン』は大リニューアルでカラーページが大幅に増えました。特集はずばり「コーヒー大特集」。アアルトコーヒーの庄野さんも登場しています。べつのページでは「オリジナルブレンドをつくろう!」という内容でグラウベルの狩野さんも・・・。書評では、新調したモイのメニューボードのデザインをお願いした川畑あずささんが手がけた『新宿駅最後の小さなお店ベルク 個人店が生き残るには?』もとりあげられていて(ちなみに「ベルク」さんは個人的にとても好きなカフェのひとつです)いつも以上に楽しんで読んじゃいました。
ハンネス、列車の旅
2008.8.27|cinema
夏休み最後(店主的には…)のきょう、モイではスタッフをあつめてプライベート上映会を開催した。上映したのは、「ハンネス、列車の旅」。

ドルトムントでビールを配達する仕事をしている鉄道オタク(厳密に言うと「時刻表オタク」)のハンネスが、フィンランドの北極圏に位置するちいさな町イナリで開催される「列車時刻表国際大会」に参加するため列車を乗り継いで北へと向かう。ところが、ひょんなことから殺人事件に巻き込まれ追われる身に。途中、偽札偽造団の一味とまちがわれたり、おかしなフィンランド人夫婦(アキ・カウリスマキの「浮き雲」に登場するカティ・オウティネン&カリ・ヴァーナネン)に酒をおごってもらったり、故郷へもどる途中のフィンランド人女性と恋におちたりといろいろしながら珍道中をくりひろげる。
手に汗握る(?)大会シーンの結末には、最上のルート>最速のルートというなかなか粋なオチが用意されていて、この結末へと導くためにストーリー展開はかなり無茶しちゃいましたという感じもなくはないのだが、まあ許せる範囲。むしろこの映画の「カルト人気」のヒミツは、アキ・カウリスマキのトリビュート作品と言っていいその作りにありそう。キャストはもちろん、そこここにアキ的ギャグ(?)が散りばめられていて思わずニヤっとしてしまう。とりわけ、ハンネスがフィンランドに入ってからはやりたい放題だ。
さらに、
ストックホルムから「シリヤライン」で海路トゥルクへ、そのまま北上するはずがなぜかヘルシンキで途中下車してロヴァニエミ、そしてイナリへという、さしずめ「山村美紗サスペンス」なら清水寺から金閣寺、嵐山まで行った後に高雄の紅葉でダメ押しみたいな移動ルートに、フィンランド好きは思わず身震い(?)してしまうのである。
ところでこの映画、DVD化(現在は廃盤)にあたってタイトルが変更されている。題して『逃走特急 インターシティ・エクスプレス』(笑)。封切り当時の『ハンネス、列車の旅』では売上が見込めないという担当者の判断にちがいないが、サスペンスだと思ってこんなユルい映画を観させられたら怒るよみんな。むしろ、昨今の「鉄道ブーム」に便乗して最初のタイトルに戻して再発したら案外売れちゃったりするんじゃないだろうか?
ルイジ・ギッリの写真
2008.8.28|art & design

髪を切りにいった美容室で、ルイジ・ギッリ Luigi Ghirriというイタリアの写真家がジョルジオ・モランディのアトリエを撮った写真集をながめていたら、ほかにも何冊かおなじギッリの写真集を出してきてくれたのだった。
むかしから好きなエグルストンの写真にしてもそうなのだが、このギッリというひとの写真もまた、世界からそれを覆っている薄い皮膜を一枚ぺりっと剥がしてしまったかのような印象をうける。そのため、いつもの見慣れた風景も、まるでおろしたてのシャツのような真っ白さをもって立ち上がってくるのだ。そこにあるのは、知っているけれど見たことのない世界。
ありふれた日常にあらためて「真新しさ」を《発見》するのはうれしい。そういう気持ちで眺めると、この世界もまだまだ捨てたもんじゃないなという気分になる。ギッリの写真には、そういう、生きることの充足感を見るひとに感じさせるなにかがあると思うのだ。
『Luigi Ghirri』という写真集をぱらぱらとめくりながら、一枚の写真に目がとまった。磨りガラスにもたれて立つ赤いコートの人物を撮った写真である。ベルトに金ボタンをあしらったモード系の赤いコートを着た人物(長髪の男性?)が、だれかを待っているのか、うしろに手を組み磨りガラスに寄りかかっている。ガラス越しの手のひらは、からだの圧力でべたっとつぶれて白くなっている。晩秋か、それとも初冬のモノトーンの景色の中で、磨りガラスのむこう側の赤いコートと白い手のひらだけがぽっかり宙に浮いたかのように存在を主張しているのだ。こんな光景と出会ってしまう、それだけでもうギッリというひとは「写真の神様」に愛されていると言っていいんじゃないだろうか?
リアルタイムレーダーはえらい
2008.8.30|column
ここのところ、東京は毎日のように突然の雷雨に見舞われている。天気予報は、かつてのぼくの競馬予想とおなじくらいの「的中率」でまったくアテにならない。いっそのこと、天気予報も「天気予想」に名前を変えてしまったほうがいいのではないか。となると「天気予報士」は「天気予想家」だから、印とかつけて的中率を競わせたらおもしろそうだ。
それはともかく、こうした突然の雨などのときに威力を発揮するサイトがある。知っているひともいるだろうが、国土交通省の防災情報提供センターというところが運営する「リアルタイムレーダー」だ。ぼくはここの存在を、荻窪で店をやっているときの常連さんから教えてもらった。
「リアルタイムレーダー」は、その名のとおり現在雨が降っているポイントと雨量を10分間隔で地図上に表示するというもので、サイト内の動画機能を使えば「あとどれくらいで雨が降り出しそうか?」とか「あとどれくらいで雨が止みそうか?」といったことが、かなりの確度で予想できとても便利である。
何年か前、杉並を集中豪雨が襲ったとき(このとき初めて「ゲリラ豪雨」という言葉が使われたような気がする)、見たこともないような勢いの雨があまりにも続くので店でこのサイトを見たところ、100ミリを超える雨量を意味する赤い印がつぎからつぎに杉並のあたりで発生しているのを確認してこれはただごとじゃないな、と思った記憶がある(けっきょくその日は日付が変わるまで店を出れなかった)。雷雲の塊が移動してゆくだけのふつうの夕立とは、あきらかにちがう異常な動きをしていたのだ。
さあこれから出かけようというときに雲行きがあやしくなってきたら、ぜひここをチェックするといい。傘を持って出るべきか?折りたたみにするか、それとも長い傘にしておくか?目的地は雨が降りそうか?といった情報がひと目でわかる。
使い方は、
まず、地域別表示の地図から見たいエリアをクリック(東京だったら「関東・北陸・中部」)する。
次に、地域拡大のタブから見たいエリアをクリック(東京だったら「関東南部」)する。
さらに、都道府県庁・支庁のタブからよりくわしいエリアをクリック(東京だったら「東京・神奈川」)する
といった感じ。おすすめです。


