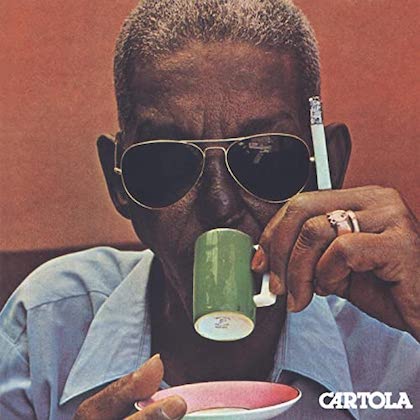謹賀新年
2007.1.1|column
あけましておめでとうございます。

昼過ぎに近所の神社へと初もうでに出かけ、お雑煮を食べ、映画(『ここに泉あり』)を観てのんびりとすごしています。
『ここに泉あり』の舞台は群馬県の高崎市。建築家ブルーノ・タウトが暮らした「洗心亭」や、同じく建築家のアントニン・レーモンドが設計した群馬音楽センターがある街でもあります。ちなみに高崎を郷里にもつJUSSIさんの話では、ブルーノ・タウトという名前の銘菓(!)もあるらしい。新宿から直通で二時間弱。行ってみたい、食べてみたい。
さて、ことしはさる雑誌にてコラムの「連載」が始まったり、イベント会場でコーヒーを淹れさせていただく話があったりと、お店以外でみなさんとお目にかかる機会が増えそうでいまからとても楽しみです。どうか今年もよろしくおつきあいの程お願いいたします!
二〇〇七年 元日 moi店主
忙しい。
2007.1.2|column
あれして、これやって、あそこ行ってと、みなさんそうだと思うのですが「お正月」ってけっこう忙しいですよね?案外ふだんのお休みよりも忙しいかも・・・。
それにしても、元日もきょうもけっこう街はにぎやかで、個人的にはまったくと言ってよいほど実感はないのですが、やはり景気が回復してきているのかもしれません。
きょうは実家に戻り、いとこたちと新年会。アメリカで暮らしているいとこも帰国していて、一年に一回の、ある意味「イベント」。
原稿の日
2007.1.3|column
原稿を書いていた。
年末のうちから、きょうは「原稿を書く日」と決めてある。きのうからすでに、「そうだ、あしたは原稿を書くんだよな」となんども考えた。けさはけさで、コーヒーをすすりながら「これから原稿を書かなきゃなあ」と考えている。以前にも書いたことがあるが、子供のころから八月三十一日に泣きながら宿題を片づけるタイプなのだ。こうやって自分を崖っぷちに追い込むことも仕事のうちといえばいえなくもない。
そして原稿を書いた。
日がな一日ということはなく、たぶん正味二時間とか三時間とかだと思うのだが、なんとなく煮詰まると紅茶をいれたり、実家から持ってきたCDを聴いてみたり、あるいはただチンパンジーのように部屋のなかをウロウロしていたりして、じっさいにはそういった時間のほうがはるかに長い。短いコラムですらそうなのだから、「書き下ろし三百枚」なんていったらいったいどうなってしまうのだろう。想像もつかない。まあ、想像する必要もなのだけれど。
原稿を書いた、といってもじつはまだ下図にすぎない。
いつもそうなのだが、いったん下図をこしらえて、それからまた全部書き直す。全部、白紙からまた書き直す。八割がたおなじようなものが出来上がることもあれば、まったくちがったものが出来上がるということもある。だから、じっさいにはまだ完成していない。一応、〆きりは十日ということになっている。それにしても、モーツァルトの楽譜には書き直した痕跡がまったくみあたらないらしい。「天才」というよりも、非常にレベルの高い「職人」という気もする。
気づけば三ヶ日も終わっている。
仕事始め
2007.1.4|column
営業はあしたからなのだが、年末に終わっているはずの大掃除をなぜかして、買い物に出かけ、すこし仕込みをした。午前中に店に行き、とりあえずメドがついたのが七時前。考えたら、その間いちども腰かけなかった。軽く考えていたのだが、終わってみればきょうが実質的な「仕事始め」だったようだ。
それはそうと、ようやく読み終えた本にこんな一節があった。
「トナカイは、人間の尿にフェチと言ってもいいくらいに夢中なのです。そのため、野性のトナカイを捕まえるためには、まずおしっこをしてトナカイたちを引きつけます」
ラップランドで立ち小便をするときは、くれぐれも用心しなければなるまい。
なお、あすは平日なので通常通り十三時開店です。よろしくお願いします。
ことしもお待ちしております。
2007.1.5|info
新年の営業はきょうがスタート。
さっそくお越しいただいたみなさま、どうもありがとうございました(Kさん、沼津銘菓ほさかの「栗せん」ごちそうさまです)。
それはそうと、新年早々おどろいたわけですよ。仕込みのために買い物にでかけたら、なんとキューリが一本百五十円!年末年始で品薄なのはわかるけど、ついこのあいだまで四十円で売っていたものがいきなり百五十円って、そりゃあまりにも露骨すぎやしませんか?ならば、品物が豊富な時期には値段が四分の一になるかというと、たぶん絶対そういうことはなわけですよ(すくなくとも末端では)。
ここのところ、葉もの野菜が高騰するのは毎年のことだし、かといって野菜を使っているメニューをかんたんに値上げするわけにもゆかない飲食業にとってはツラい日々です。早く元の値段に落ち着いてくれないと、ほんと困ります。
と、いきなりグチから始まりましたが、
どうぞことしもよろしくお願いします!
DVD『GREAT CONCERTOS』
2007.1.6|music

お正月にゆっくり観ようと、年末にDVDを手に入れた。なんと10枚組である。
このDVD『GREAT CONCERTOS』は、スイス・ルガーノにある「スイス・イタリア語放送」が所有するクラシックコンサートの映像を収めたもので、1980年代から90年代にかけておこなわれたスイス・イタリア語放送管弦楽団(OSI)の演奏会のライブが中心になっている。ちなみに全10枚の収録時間は映像が800分、さらに特典として静止画+音楽が540分、トータルで1,340分にもおよんでいる。
しかも驚くべきは、
DVD10枚組にしてたったの2,400円
という超破格のそのお値段。つまり一枚あたり240円、きのうの話のつづきでいけばわずかきゅうり1本半というワケである。いま、空のDVDメディアを買ってきたって一枚200円くらいはするんじゃないだろうか?クラシック音楽界の「価格破壊」はますます大変なことになっているようだ。
とはいえ、いくら値段が安くたって中身がクズ同然(失礼!)ならぜんぜん食指は動かない。安かろう悪かろう、である。ところがこのDVD、登場するメンツ、そしてとりあげられている曲目もなかなか興味深い。ぼくとしては、ハンガリー出身のピアニストゾルターン・コチシュによるいい感じに鄙びた劇場(テアトロ・ソシアーレ・ベリンツォーナ)でのリサイタル、さらになんていっても《親愛なるヴィエラ先生》じゃなくて、ペーター・マーク大先生の映像が拝めるだけでも十二分にもとを取ったと断言できる。
しかし、収録された映像&音楽をぜんぶ楽しむとしたら不眠不休でも22時間あまりかかるという事実を後から知った・・・。正月はとっくに終わったけれど、もちろんまだまったくといってよいほど観ていない。
祝!Re OPEN
2007.1.9|cafe
ご存知WILLcafeさんが、十一日[木]よりJR南武線谷保駅そばに場所を移しRe OPENされます。去年の十月にいったんお店をクローズされて以来、ほぼ三ヶ月ぶりの再開です。
カフェ営業は、
木・金・土曜日 12:00~18:30(ラストオーダー18:00)
となるそうです。もちろんいままでどおりテイクアウトもOKとのことですので、お近くまでおいでの方はぜひ足をはこんでみてください。ちなみに場所はJR南武線谷保駅南口より徒歩二分、谷保天満宮のすぐ近くだそうです。
手帳が必要だ
2007.1.10|column
どうやら手帳が必要になってきた。
会社勤めしていたころは肌身離さず持っていたものだけれど、店を始めてからというものすっかり手帳を持つ習慣がなくなってしまった。そもそも店の仕事はルーティンに属するものがほとんどなので、あえて手帳に書き込むまでもないというのが実際のところ。持ったはいいが、中身はスカスカというのではあまりにも淋しい。とはいえ、手帳を持たない生活というのもそれはそれでいいものだ。まず、身軽だ。出かけるときも手ぶらですむ。携帯と財布、それにキーケースをポケットに突っ込めばそれでオーケー(そういえばBAR BOSSAのはやしさんも手ぶら率が高い)。
それがここのところ、どうもそういうわけにもゆかなくなってきた。手帳に書き込まなければそのまま忘れてしまい、後々ちょっとまずいことになってしまいそうな用事がポツポツ増えてきた。ところが、それに反して記憶力のほうはというとますますあやしくなってゆくばかりだ。
そこで、いまさらながら手帳を買おうと思ったのだが、これがなかなか難しい。持つとなればそれなりに「こだわりらしきもの」が出てくるからだ。つねに持ち歩くものだけに、やはり気に入ったものでないことには気が済まない。売り場をのぞいても、どうもいまひとつピンとくるものがみあたらない。ユンジョンおすすめのMOLESKINEはよさそうだけれど、めぼしいものはすでに完売状態のようだし・・・。まあ、いまごろお気に入りの手帳を探そうということからしてすでに間違っているわけだが。
とうわけで、いま手元に手帳がないということに対し俄然不安になってきた自分がいる。来年までに、お気に入りの手帳(2007年版)を見つけられるとよいのだけれど。
身悶えするほど安く、しかもすばらしい
2007.1.11|music
身悶えするほど安く、しかもすばらしいCD。

スウェーデンの指揮者ヘルベルト・ブロムシュテットが、名門オーケストラシュターツカペレ・ドレスデンを相手に録音したベートーヴェンの交響曲全集。しかも全5枚組でたったの1,700円ちょっと!!!
ところでブロムシュテットといえば、これまで幾度となく来日しているおなじみの指揮者だけれど、端正な表現とその人のよい銀行員風なルックスがあいまって、どうも「巨匠」と呼ぶにはあまりにも地味という印象が拭えなかった。ところがこのベートーヴェンを聴くと、その実直さがプラスに作用して、とても懐の深い立派な演奏になっているのがわかる。ひとことでいえば造型美。あんこと皮のバランスが絶妙で、しかも見た目にもパーフェクトなたいやきをイメージしてほしい。それがこのブロムシュテットのベートーヴェンである。やたら頭でっかちだったり、しっぽばかりが目立っていたり、なかには「ふぐ」みたいだったり「いわし」みたいだったりする「たいやき」さえある中で、正直一筋八十年、ブロムシュテット印の「たいやき」はまさに「老舗」の風格をたたえている。
ドラマ「のだめカンタービレ」のテーマとしても使われていた第七番をはじめ、「英雄」「運命」「田園」、それに「第九」まで、すべて充実した演奏で堪能できるこのCDは、それゆえ、「のだめ」にハマりもっとクラシックを聴いてみようとおっしゃるMIZUKIさんにも自信をもっておすすめできる一枚(セット)なのである。
ピッカー
2007.1.12|finland
まあ、そうなんだろなぁと思いつつも、あらためて聞くとやっぱり「へぇ~」と感心してしまうのは、取材でおみえになった「わかさ生活」(ブルーベリーを使った健康食品でおなじみの会社。↑に広告がときどき登場しますね)の方からうかがった、原料となるビルベリー(野生種のブルーベリー)をどうやってフィンランドで調達しているかというお話。
じつは「わかさ生活」はフィンランドに広大な「ビルベリー農園」を所有していて、ということはまったくなく、そのつど「ピッカー」と呼ばれるひとたちと契約して収穫するのだそうである。つまり、「ブルーベリー摘み」を生業としている人々が存在するということである。プロの「ブルーベリー摘み」、「ピッカー」(語尾を上げて発音するといかにもそれっぽいなぁ)である。
おそらく「ピッカー」の歴史は古い。店でブルーベリージャムが売られたり、ブルーベリーを使った料理がカフェやレストランでふるまわれるようになったのと歩調をあわせて、「村のベリー摘み名人」はプロの「ピッカー」になったのではないだろうか?その長い歴史のなかでは、当然かれらの「縄張り争い」に端を発する血なまぐさい抗争も起こったことだろう。ピッカーたちによる「仁義なき戦い」である。
と、いつものごとく空想はどこまでも果てしなく広がるわけだが、「ピッカー」たちの冬の暮らしはいったいどうなっているのか?丹念に道具を手入れしてやがて訪れる「夏」を待つのだろうか?それとも「黒マグロ漁船」のひとびとのように(←イメージ)、ひと夏で一年分を稼いで冬は飲んだくれていたりするのだろうか?気になってしかたない。
それより、どうしてだれも「ブルーベリー農園」をつくろうとしないのだろう?どなたかご存じの方がいらっしゃったら教えてください・・・。
瓜二つ
2007.1.13|column
ときどき恥をさらしたりするのも、じつはこのブログのお茶目なところである(本人談)。
きょうのお題は、
瓜二つ
ということわざである。ぼくは長いこと、っていうかいまのいままで、「瓜二つ」というのは二個の瓜が似ているところから「顔や形がそっくりの様子」を意味するものだとばかり思っていた。そのうえで、「なす二つ」とか「栗二つ」と言わないところをみると、よほど「瓜」ってやつはどれもこれも似通ているんだろうななどと思っていたわけである。
ところが、である。
ふと思い立って調べてみたところ・・・え、えーっ、全然ちがうじゃん!!!なんでもそこには、「二つに割った瓜のそれぞれのように、顔形が良く似ていることの喩え。」と書かれているではないか。ってことは「二個の瓜」が似ているんじゃなくて、「一個の瓜の半分ずつ」がすごく似ているってこと?!なぁ~んだ、当たり前じゃん!
なら、べつに
「なす二つ」でも「栗二つ」でもかまわなかったわけだ。たぶん昔、「瓜」がいまよりもっと身近でポピュラーなものだったからそうなった、というだけの話だろう。しかし、いまは二十一世紀である。「瓜」はもはやポピュラーではありえない。断じて言うが、ぼくは生まれてこのかた瓜をふたつに割った経験など一度だって、ない。つまり、このことわざ、なんだかちょっと分かりにくくないですか?いっそのこと、
梨二つ
とか、「瓜」にこだわる「瓜フェチ」の意向も汲んで
水瓜(すいか)二つ
とかに変えてしまってはどうだろう?ほら、「瓜」よりずっと分かりわすい。まったくソックリだよ、「梨」も「水瓜(すいか)」も。
アラビヤン焼そば
2007.1.14|food & drink


常連のTさんが「群馬遠征」でゲットしてきた「アラビヤン焼そば」。
じつは千葉限定の商品らしいのですが、製造している工場が群馬にあるため、わずかながら群馬県内の店でも買えるのだとか。ちなみに、製造しているのは「サッポロ一番」でおなじみのサンヨー食品という会社。なぜ「千葉限定」なのかというと、よくわからんけど千葉県でしか売れないからというパッケージ同様のゆる~い理由からだそうです。
それにしても、フライパンでつくるインスタントラーメンの焼そばというところからしてなつかしい。鉄のフライパンだとぜんぶ底にくっついちゃうんですよね、これが・・・。
はやる心をおさえつつ(?!)、さっそく試食。お味はこれが、案外トレビヤンでした。
フィンランドがぐっと近くなるセミナー
2007.1.16|event
三軒茶屋の昭和女子大学オープンカレッジで、五回にわたり『小さなフィンランド・大きな魅力』というセミナーが開催されます。毎回テーマに沿ってその道のプロフェッショナルな方々が登場することになっていますが、2月10日[土]に開催される
第3回「フィンランド・デザイン」
には、ここmoiの設計者としておなじみの建築家関本竜太さんが登場します。関本さんには一昨年、ここmoiでも「アルヴァー・アールトの三十代」をテーマにお話ししていただいたのですが、建築家の視点からアールトの魅力をわかりやすく解説した内容はたいへん好評で充実したものでした。
今回は「建築家の目で見たフィンランドの造形美、その背景にあるライフスタイルを紹介」とのことで、建築にかぎらず、フィンランドのデザイン全般について幅広く、またフィンランドで実際に生活していた経験をふまえてさまざまなエピソードが聞けるはずです。フィンランドの建築やデザインをもっと身近に感じたいひと、この機会にぜひ参加されてみてはいかがでしょう。
このセミナーについてのくわしい情報、および参加のお申し込みは昭和女子大学オープンカレッジのサイトをごらんください。
再入荷です
2007.1.17|book

お待たせしました。『アンティ・ヌルメスニエミについての小さな本』が再入荷しました。
今回入荷したのは、ブルー、イエロー、ブラウンというmoiで売れ筋の三色です。お早めにどうぞ。
ところで、先日この本の著者である原宿の雑貨店CINQさんにお邪魔したときに伺った話なのですが、この本をフィンランドのアカデミア書店で扱うことが決定したそうです。わからない方のために説明すると、「アカデミア書店」はフィンランドで最大手の書店で、ヘルシンキの本店は建築家アルヴァー・アールトが設計したビルにあります。ちなみに、映画「かもめ食堂」で小林聡美が片桐はいりに「ガッチャマンの歌」を教えてもらっているシーンは、その「アカデミア書店」のカフェで撮影されています。
なんでも、アンティ・ヌルメスニエミの奥様で著名なデザイナーであるヴオッコさんがたいへんこの本のことを気に入り、いっしょに「アカデミア書店」まで出向いて話をつけてくださったそうです。余談ですが、この夏ヘルシンキの「デザインムセオ」で開催される目玉展示はそのヴオッコ・ヌルメスニエミさんの回顧展。この時期、旅行を計画されている方は要チェックですよ!
オッコ・カムのシベリウス
2007.1.19|music

寒い。凍えるようなとはいかないまでも、冷たい北風が身にしみる。そこで引っぱりだしてきたのは、ことし二〇〇七年がちょうど没後五十年にあたるフィンランドの国民的作曲家シベリウスの、交響曲第二番のCD。
ところでこのシベリウスの「交響曲第二番」といえば、「プラティニ国際指揮者コンクール」で優勝した「千秋真一」が、そのパリ・デビューにあたってとりあげた曲ということになっている。で、それと同じく(?)、弱冠二十三歳で「第一回カラヤン指揮者コンクール」に優勝したフィンランドの指揮者オッコ・カムが、その「ごほうび」としてカラヤンの手兵「ベルリン・フィル」とともにレコードデビューを飾ったのもまた、この「交響曲第二番」である。
それにしても、このオッコ・カム指揮ベルリンフィルによるシベリウスの交響曲第二番はすごい!(しかも一枚たったの千円だ)。カムの演奏はライブもふくめたびたび耳にしてきているが、どちらかといえば手堅いアプローチをする渋い指揮者というイメージがあった。とりわけ、長身でスリムなルックス同様、その演奏もスマートで、ちょっと線の細い印象があったのだ。ところが、である。これは違う。ぜんぜん、違う。「若さゆえ」ということもあるだろうし、「お国もの」のシベリウスということもあるのだろう、とにかく自信に満ちた足取りで悠然と歩を進める堂々たるシベリウスだ。終楽章など、まったくありえないような遅さでありながら、最後までテンションが下がることがない。もちろんそれは、相手がベルリンフィルという世界最強のオケだからこそできた思い切ったテンポ設定であって、その意味ではまさに一期一会の名演奏ということになるかもしれない。
その後のカムはといえば、人望は厚いが、出世街道からはやや外れてしまった万年「課長」的なスタンスに甘んじているようにみえる。だいたい、「Virtual Finland」の「Famous Finns」の欄にかれの名前がないというのはいったいどうなっているのか?「moiのプッラを食べたかもしれない指揮者」として、ここ数年、以前にもましてカムを応援しているぼくとしてはまったく歯がゆいばかりである。ぼくの勝手な推理では、多分に「フィンランド人的気質」が影響しているのではないだろうか?いずれにせよ、ベルリンフィル相手にこれだけの熱い演奏を繰り広げられる指揮者のこと、まだまだこの先ドカン!とやらかしてくれるのではないかと密かに期待せずにはいられないのだ。
Timo Sarpaneva
2007.1.20|finland

店の壁にかかったポスターを指差して曰く、「このイーッタラのマークって、ティモ・サルパネヴァがデザインしたんだよね」。「えっ」と驚いたのは、その発言の主がリーサ先生だったからにほかならない。リーサ先生はフィンランドのデザインのことなどほとんど関心がないような(失礼!)、ある意味とても「標準的な」フィンランド人である。そんな「標準的な」フィンランド人であるところのリーサ先生の口から、「ティモ・サルパネヴァ」などという玄人好みなデザイナーの名前が出たから思わず驚いてしまったというわけだ。
リーサ先生は続ける。「死んだよね、このひと」。「え、えっ?」うかつにもまったく知らなかった。あちらのニュース報道を調べたところ、「二〇〇六年十月六日に七十九歳で他界」したらしい。
なるほど、新聞かなにかでリーサ先生はかれの訃報に接したというわけか。じっさい、記事にも「イーッタラ社のロゴマークを手がけたのもサルパネヴァ氏である」と書かれているし。これで謎(?)が解決した。
それにしても、タピオ・ウィルッカラ、アンティ・ヌルメスニエミに続き五十年代のフィンランド・デザインの黄金期を支えたデザイナーのひとりがまたいなくなってしまった。仕方ないとはいえ、淋しいことである。ちなみに、moiではジュースなどにつかっている大きめのグラスがティモ・サルパネヴァによるもの。その意味では、毎日お世話になっていると言っても言い過ぎではない。
ご冥福をお祈りします。
FazerのMarianne
2007.1.21|finland

ファッツェル(フィンランドの製菓会社)のキャンディー「マリアンネ」です。チョコレートクリームがハッカ味(ミントというよりもハッカという雰囲気)のキャンディーでコーティングされた、フィンランドで古くから愛されているお菓子です。
この「マリアンネ」をくださったのは、現在フィンランドに留学中のUさんという方。おともだちがご来店、届けてくださいました。お菓子と一緒にUさんによる手紙も同封されていて、それによるとUさんはいまヘルシンキで生活しながら、日本人ツーリスト向けのガイドツアーをおこなっている会社「My Suomi」で仕事をなさっているとのこと。じつは、ちょっとしたご縁からmoiにも「My Suomi」さんのフライヤーを置かせていただいているのですが、日本にいたころちょくちょく通っていたmoiに「My Suomi」のフライヤーを置いてもらえたことがうれしくて、あくまでも個人的にプレゼントさせていただいたとの内容。心のこもったお手紙とともに、こうして思いがけないプレゼントをいただくというのは、ほんと店主冥利に尽きます。
本来なら直接Uさんにメールさせていただけばよいところですが、Uさんのメールアドレスを存じ上げないのと、「個人的に」ということを考慮してあえて「会社気付」ではなく、このブログでお礼を申し上げさせていただきます。
Uさん、Kiitos !!!
ところで、手紙を読んでいたところ気になる一文が・・・。「お店にうかがったとき、店主さんからサルミアッキを食べさせていただいたことなど思い出されます」。うわぁ、「被害者の一人」だったのですね~。
そんな、文字通り「苦い」経験をしたにもかかわらず、こんなふうにあたたかい気持ちをもって接してくださるUさんは、絶対にすばらしいひとにちがいありません(汗)。
カフェをやるひと、バーをやるひと
2007.1.23|publicity
おしらせです。
雑誌『カフェ&レストラン』三月号(2/15発売)から、「カフェをやるひと、バーをやるひと」というタイトルでコラムの連載をさせていただくことになりました。
東京砂漠のまんなかで雨ニモ負ケズ風ニモ負ケズ(実際にはときどき「負ける」)小さなお店を一人で切り盛りしているふたりのマスター
ぼく(=カフェをやるひと)と
林伸二さん(bar bossa店主、=バーをやるひと)
が、毎回ひとつのテーマについて「マスター視点」(?)で書いてゆく立体コラムです。カフェとバーのマスターの捉え方のちがいや共通点など、うまく浮き彫りにできればと考えています。テーマは日々のお店のことのみならず、趣味や休日の過ごし方、ふたりのすきな国(フィンランド、ブラジル)のことなど幅広くとりあげる予定ですので、とりたててお店の経営なんて興味ないやという方々にも楽しんでいただけるはず。
また、今回ページレイアウトをCINQ DESIGNの保里正人さんが、そしてイラストをイラストレーターの日置由香さんがそれぞれ手がけてくださることになりました。日置さんのイラストは、背後にストーリーを感じさせてくれるようなとてもいい感じの線画です。
ここのところ、毎週のように編集者さんを含め五人で集まってはああでもないこうでもないとアイデアを煮詰めてゆくミーティングをしていますが、これがなかなか「たのしい」のです。そして、この「たのしさ」が読者の方々にも伝わるような連載にできたらと思っています。
どうぞおたのしみに!
かつて「この会社でよかった」と思ったこと。
2007.1.25|column
『プロフェッショナル』というテレビ番組に指揮者の大野和士さんがとりあげられていた。大野さんといえば、かつてこんなことがあった。
かつてはたらいていた職場で、昼休みから戻ってみると、となりのデスクに大野和士が座っていた。
夢ではなくて、ほんとうにあったお話。まったく考えられないシチュエーションではないとはいえ、えらくビックリしたのを憶えている。その会社に入るよりはるか以前から、ぼくは彼のファンだった。彼がタクトをとる都内でのコンサートは、ほとんどすべてといってよいほど足を運んでいたくらいだ。ビックリしたのも無理はない。たしか入社して一年目くらいの出来事だったろうか。そのときは心から「この会社ではたらいていてよかった」と思ったものだ。舞い上がっているぼくのかたわらで、席を奪われた女の子(筋金入りの短気)が鬼のような形相で彼の背中をにらみつけていたのが忘れられない・・・。
それとはべつにやはり、「この会社ではたらいてよかった」と思ったことがもうひとつある。入社当時事務所によく、ゴダールをはじめヌーヴェル・バーグの字幕翻訳でおなじみの寺尾次郎氏が現れたことである。でもぼくにとっては、寺尾さんといえばなんといっても「シュガー・ベイブの寺尾サン」としてこれまた眩しい存在なのだった。さっそく、寺尾氏のことをよく知る同僚に「あの人って、シュガーベイブの寺尾サンですよね!」と確認したところ、「はぁ?」と怪訝そうな顔をした後、「でも、おたくだよ、アハハ」といなされてしまった。
まあ、それでもとにかく、そんなことがあったからこそ八年間のサラリーマン生活もそれなりに実り多いものだったといまは思ったりもするのである。
「不気味社」が歌う
2007.1.29|music
謎の集団「不気味社」が歌う「ムーミン」のテーマソング。こんなのあり!?ムーミン好きには聞かせられません・・・。
「浜離宮」へ行く
2007.1.30|travel

もうじき、うかつに外も歩けなくなる季節がやってくる(←花粉症のため)。心おきなく散歩できるのもいまのうちだ。そこで、銀座へ出たついでにひさびさに「浜離宮」まで足をのばしてみる。

浜離宮といえば手入れのゆきとどいた日本庭園としてよく知られているけれど、あいにくぼくは「庭園を愛でる」などという高尚な趣味は持ち合わせていない。ただただぶらぶらと、季節柄まだ人気の少ない庭園を歩きながら「光」や「色」が織りなす即興的な景色にいちいち目を奪われたり感心したりしながら、「やっぱりたまにはこういう時間も必要だよなぁ」などといまさらながらに思ったりするのだった。

ところで、ここ「浜離宮」には彫刻家だったぼくの曾祖父がこしらえた銅像がある。

「可美真手命」と書いて「ウマシマデノミコト」と読む。『古事記』に登場するらしいのだが、くわしいことは知らない。むかしは正門から入ったすぐのところに立っていたと思うのだが、いつのまにか庭園の中央あたりに移設されていた(たぶん)。
ユンジョンのこと
2007.1.31|column
一年間の日本での生活を終え、ユンジョンが韓国に帰っていった。お別れを言おうとなじみのお客さんたちが集まって、日曜日の夜のmoiはずいぶんとにぎやかになった。
思い返せば、ユンジョンとの出会いは一通の手紙からはじまったのだった。ある日韓国から届いた一通の手紙、消印をみると二〇〇五年十一月とある。そこには、ハンドドリップのコーヒーやカフェが大好きであること、ネットでmoiを見つけてとても気に入ったこと、そして近々ワーキングホリデーを利用して日本に滞在するので可能ならばmoiで働きたいといったことが、漢字まじりの上手な日本語で書かれていた。本人は恥ずかしがるけれど、いまあらためて読み返してみても立派な手紙だ。
思いがけない海外からの便りに感激するそのいっぽうで、正直なんとなく気が重たくもあった。というのも、ぼくはそれまで韓国の人と個人的に知り合った経験がなかったからである。「韓国人」といえば「韓流スター」か、はたまたニュース報道か、いずれにせよマスメディアからの情報でしか知らなかったのである。「韓流スター」のほうはともかく、すくなくともニュース報道で接する韓国のひとはみな、日本嫌いでつきあいづらい、そんなイメージがあった。おとなりの国であるにもかかわらず、というよりはたぶんおとなりの国ゆえに、韓国の人と仲良くなることは、たとえばパプアニューギニアの人と仲良くなるよりもはるかにずっと難しいことのような気がしていたのだ。
じっさいにユンジョンと会ったのは、年が明けた去年の二月のこと。来日後、さっそくmoiを訪ねてくれたのだ。じっさいに会ったユンジョンは好奇心旺盛でひとなつっこく、いつも屈託のない笑顔をうかべているようなごくふつうの女の子だった。そしてそんな感じだから、moiのお客さんたちともあっという間に打ち解け、仲良くなってしまう(←「どうぶつ占い」は「こじか」)。旅行にでかけたり、着物を着せてもらったり、お正月に手作りの「おせち料理」をふるまってもらったり。そのかたわら、おすすめのカフェや喫茶店を教えてもらったり、グラウベルさんの「コーヒー講座」に参加してみたり、道具を一式そろえ自宅でもドリップの練習(?)に励んだりと、「日本のカフェやコーヒー文化にふれる」という当初の目的も着々とこなしている様子だった。
そしてぼくはといえば、相手が韓国人だろうとパプアニューギニア人だろうと、あるいはもしかしたら宇宙人だろうと、そのひとがカフェが好きでコーヒーが好きで音楽が好きであるかぎり仲良くなるのはとてもかんたんなことだという、ごくごく当たり前のことを彼女の存在から「学んだ」のだった。さらにこの一年、ここmoiでユンジョンと出会ったお客さんひとりひとりの、「笑い声」のむこうのあたたかい気持ちにいつもいつもシアワセな気分を味わわせてもらってもいた。
韓国にもどったユンジョンは、これからいろいろと勉強してまた必ず日本に帰ってきたいと言っている。日本のカフェや、そこでのたくさんのすてきな出会いを一冊の本にまとめたいという密かな野望もあるらしい。とても楽しみだ。またいつでも、その明るい笑い声を連れてmoiに戻ってきてもらいたいと思う。お元気で、アンニョン!(←この一年で覚えたたったひとつの韓国語)。