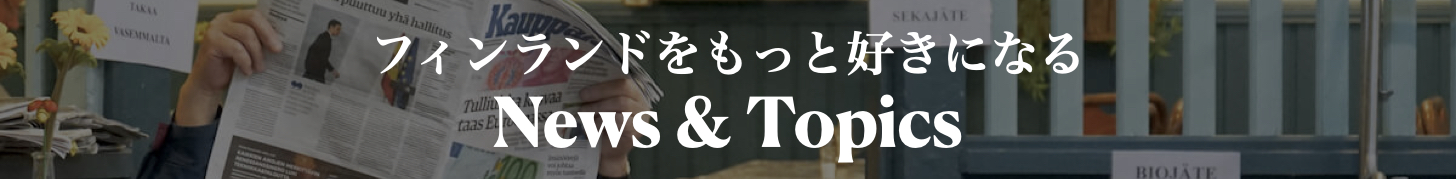──ヨーロッパ各国から作家、詩人、翻訳家が一堂に介して開催される欧州文学の祭典、ヨーロッパ文芸フェスティバル。一昨年のミカ・ヴァルタリ『エジプト人 シヌへ』(セルボ貴子訳/みずいろブックス)、昨年のヘイッキ・アアルト=アラネン『アイノとアルヴァ アアルト書簡集』(上山美保子訳/草思社)につづいて、今年のフィンランドはトーヴェ・ヤンソン『ムーミン』をテーマに、ムーミン研究家・翻訳者の森下圭子さんとフィンランドセンター所長のアンナ=マリア・ウィルヤネンさんのおふたりによるトークセッションがおこなわれました。
ムーミンの物語は、1945年にシリーズ第1作目『ムーミントロールと大きな洪水』が刊行されてから来年で80年(『エジプト人 シヌへ』も同年)、55カ国以上*で翻訳され、たのしまれています。こうしてムーミンが世代や地域をこえて読みつがれてきたのは、なによりトーヴェ・ヤンソンの生みだした世界観がどんな境遇にあるひとにもとどくような普遍性をもっていたからだとおもいます。トークでは森下さんとアンナ=マリア所長それぞれの体験談をまじえながら、ムーミンの物語がいまを生きるひとたちにどんな影響をあたえているのかについて話しあわれました。
(*ムーミン公式サイトより)
ムーミンはだれのもの?

アンナ=マリア所長からの最初の質問は、「ムーミンはこども向けの本か? それともすべてのひとに向けられた本か?」というもの。もともと児童書として出版されたムーミンでしたが、転機となったのは第6作目『ムーミン谷の冬』でした。その時点でトーヴェ・ヤンソン自身も「これはそろそろおとな向けなのではないか」と考えていましたが、出版社側の要望でそのまま児童書あつかいとなったそうです。とはいえ、トーヴェ本人としてはおそらく最初からムーミンがこども向けであると意識していたことはなかったのではないでしょうかと森下さん。
また、森下さんがあるフィンランド語の絵本を翻訳したときに「年齢が設定されていると反対にとまどってしまう」といわれたことがあるそうです。もしかするとフィンランドの出版業界で絵本に年齢層を設定しないという理由のひとつには、こうしたムーミンという前例があったからなのかもしれません。
いっぽう美術史家でもあるアンナ=マリア所長は、美術鑑賞で作品にそえられた説明書きなどをついさきに読んでしまうことを例に挙げて、作品をみるときにはまず自分自身がどう感じるかをたいせつにしてもらいたい、といいます。おなじようにムーミンもだれに向けられた本かという先入観は必要なく、人生のさまざまな場面でそれぞれが感慨にひたることができるような、だれもがたのしめる世代をこえた物語なのではないでしょうか、と。そのことばをうけて、森下さんがフィンランドへいこうとおもったきっかけについて話してくれました。
それまでムーミンほど〈潔い文学〉を読んだ記憶がなかったという森下さん。トーヴェ・ヤンソンのムーミンには「わたしはこういうふうに理解されたい」とか「これをこういうふうに読んでもらいたい」というような説明書きがなく、「どうぞ自由に読んで!」といわれているような気がして、その世界にとても飛びこみやすかったとのこと。森下さんは、そうした〈潔い文学〉が生まれた背景をしりたい、その環境に身をおいてみたいとつよくおもい、30年ほど前にフィンランドへとむかいました。
姿の見えない子どもたち

いま日本の美術大学で教鞭をとっているというアンナ=マリア所長。その講義のなかで気づいたことが失敗をおそれなくてもいいということ。ふだん失敗してはいけないといわれることが多い子どもたちにとって、しょっちゅう失敗するムーミントロールの存在はとてもおおきなインパクトがあるのではないでしょうか。
日本にいるとよりミスをしちゃいけないとか、正しくなくちゃいけないといったプレッシャーがあるかもしれないと森下さんもいいます。いまはフィンランドで暮らし、いつも正解なんてないといっているけれども、どこかでまだそうした考えにとらわれているのか、いまだに正しくありたいというおもいもあり、むずがゆい気持ちがしている、と。
そうした子どもたちのプレッシャーについて考えさせられるが、第7作目『ムーミン谷の仲間たち』に収録されている〈姿の見えない子〉というエピソード。ニンニという名の〈姿の見えない子〉がその姿をあらわすとき、最初にみせるのはつよい怒り。親切にしてくれたムーミンママをたすけようとムーミンパパに噛みつき、そのあと桟橋からムーミンパパが落ちるのをみてニンニは大笑いします。これは自分のなかにある感情をしっかりとはきだすことによって自分の顔がちゃんとみえるということなのだとおもいますと森下さん。
フィンランドではここ数年、そんな〈姿の見えない子〉のお芝居(人形劇?)が定期的に上演されています。森下さんによると上演後には子どもたちと演者のふれあう時間があり、そこで「いつもいい子でいることだけが、あなた自身であることではないんだよ」というメッセージを伝えていることが印象的だったそうです。子どもたちが生きていくなかで自分の顔をもつことを知ってもらう、意識してもらうためにこうして上演が続いているのではないか。そしてムーミンという作品は、わたしがわたしとして生きるための支えとなって、自由というものを気づかせてくれるものなのではないか。
声のちいさな存在へのまなざし

トーヴェ・ヤンソンの描く物語の世界では、いつもどこかマイノリティへのあたたかいまなざしが感じられます。みんなから怖がられ孤立しているモラン、トフスランとビフスラン、リスやはい虫といったちいさな生きものにいたるまで。まるでマイノリティではない存在なんてこの世界のどこにもいないかのように。そうしたものたちが自分以外にもいるのだとおもえることはとても勇気づけられることだとおもいます。
トーヴェ本人も、スウェーデン語話者であること(人口の約5%:Visit Finlandより)、パートナーが同性であること、女性であることなど、マイノリティである部分をもっていました。けれどもトーヴェ・ヤンソンは、そうした自身のマイノリティ性をおもてにだすことでその地位をなんとかしようというよりも、まず〈声のちいさな存在〉に目を向け、愛情をそそいでいたようにおもいますと森下さん。
さらに、トーヴェ・ヤンソンは自然というものも〈声のちいさな存在〉のひとつとしてあつかっていたのではないかと森下さんはいいます。昨今、自然災害というかたちであらわれているものは、きっと自然というものがあげている悲鳴なのかもしれない。あたりまえのようにいつもそこにあるけれど、きちんとそこに目を向けてほしいとでもいうように。
そして、森下さんは文章を読むだけでなく、トーヴェが挿絵の線ひとつひとつにたくさんの感情をこめて描いた、自然の表情に目を向けてほしい。きっとそこからも文学的な声がきこえてくるのではないでしょうかといいます。個人的にもムーミンの小説の魅力は、トーヴェ自身が描く挿絵にこそあるとおもっています。とくに背景のある挿絵からは、その場面の雰囲気やキャラクターの気持ちまで伝わってくるように感じられるほどです。
ムーミン谷にみる家族とフィンランド

「ムーミンの物語にはじっさいトーヴェ・ヤンソン自身の家族の影響はあるのでしょうか」とアンナ=マリア所長の質問がつづきます。フィンランドで暮らしはじめて3年目くらいのときにトーヴェ・ヤンソンのすぐ下の弟であるペル・ウーロフさんと知り合ったという森下さん。またもうひとりの弟ラルスさんは蝶を集めるのが好きだったときいて、「あ、ヘムレンさんがここにいた(笑)」と。ふたりともすっかりおじいさんになっているのにとつぜん10代のころにもどったように、トーヴェにまつわる思い出をきのうのことのように話してくれたり。そうしたかれらの話のあちらこちらにムーミンの要素がたくさんつまっていたそうです。
また、夏になるといつも群島地域ですごしていたトーヴェ・ヤンソン。島のひとたちと接することがおおかったらしく、砂ぼこりがたつような道路をヒールをはいてあるくフィリフヨンカそっくりなご婦人をみかけたりもしたとか。そうしたひとたちの話もムーミンの物語にじょうずに活かされていて、トーヴェ自身も自分の家族やまわりの様子をよくみていたのでしょう。ムーミンの物語を読んでいると、フィンランド人をそのままみているような気がすることがある、と森下さん。
こうして森下さんやアンナ=マリア所長の話をきいたり、フィンランドの文化やその暮らしを知ったりするなかで、ムーミンのなかにいままで気づかなかったフィンランド的な要素をみつけられるようになったことをおもしろく感じています。
トーヴェ・ヤンソンからのメッセージ
ムーミンの物語を読みかえすといつもあらたな発見があるというアンナ=マリア所長。ムーミンのシリーズのなかでいちばん好きなのは『ムーミンパパ海へ行く』だそうです。もしかしたらムーミンパパのようにもういちど自分の人生をやりなおしたい、リセットしたいといった気持ちがうかんできたりするかもしれません。そうした意味でムーミンの物語はひとそれぞれのライフサイクルをうまく反映していて、なにか人生で迷ったときに読みかえすことによって自分にいまなにが必要なのかわかることもあるとおもいます、と。森下さんもそのときどきの自分の気分によって、こんなふうに読めるんだと気づいたりすることがあるといいます。
またトーヴェ・ヤンソンは絵本のなかでも革命を起こしたといわれていますと森下さん。それまで教育的な絵本の多かったフィンランドではじめてそうではないものをつくりました。さきほど〈潔い文学〉だとおもったといったけれど、メッセージ性みたいなこととかはあまり意識していなかったのではないか。彼女はもっとシンプルに描きたいものを描いた、その結果がムーミンの物語。だからこそ時代や世代をこえて、いろいろなひとたちにつうじる響く言葉、響く声をとどけてくれている。きっと時代がちがっても彼女は変わらなかったような気がします、と。
最後にひとつ 〜 物語はつづく

最後にひとつだけといって、森下さんがムーミンの好きな理由を教えてくれました。それはムーミンのおはなしにはかならずちゃんとしあわせなハッピーエンドがあるということ。でもそのハッピーエンドというのは、おうちに帰ってきて、ただいまっていうハッピーエンド。大きなことではなくて、ちょっとこう、ほっとできるところに戻ってきたっていう、そんなハッピーエンドがすごく好きです、と森下さん。
ムーミンを読みおえるといつもなんだかさみしい気持ちになります。ちょうど遠足や夏休みがおわってしまったときみたいに。そのさみしさはけしてかなしいことではなくて、しあわせをしっかり胸のなかにとどめておくため、宝箱にしまって鍵をかけるようなものなのかもしれません。そして世界には、ただひとつのしあわせがあるのではなく、それぞれのしあわせがあるとトーヴェ・ヤンソンに教えてもらったような気がします。
最後の最後にもうひとつ。はじめてフィンランドセンターの存在を知ったのは、2019年の「トーヴェ・ヤンソンと日本の影響力|Tove Jansson and the impact of Japan」というカンファレンスを聴講したときのこと。アンナ=マリア所長が司会でした。そのころはフィンランドのことをまったく知らず、すこしでも役にたてるようにと、フィンランドセンターのアートレクチャーやセミナーをほぼ毎回聴くようにしました。それらは自分にとってフィンランドの学校でした。もうすぐアンナ=マリア所長がフィンランドへ帰国されるとお聞きして、なんとかお礼を伝えようとトークセッションの前にごあいさつする機会があったのですが、いつものようにうまく話せず、ただありがとうございましたとしか言うことができませんでした。それでもいつかまたどこかでお会いできたらうれしくおもっています。Tack så mycket!
そんなアンナ=マリア所長から参加者へ宿題が出されました。さっそくきょうからムーミンの小説を一冊ぜひ読みはじめてください。そして読んだ文章のひとつでもよいのでどんなことを感じたのかおもいをめぐらせてみてください。ここまでレポートを読んでくれたみなさんもぜひどうぞ!
text + photo : harada