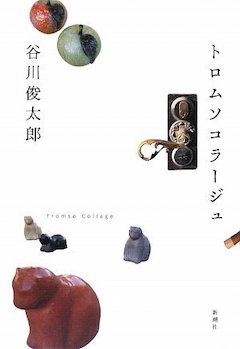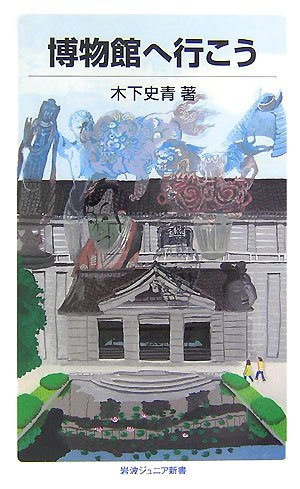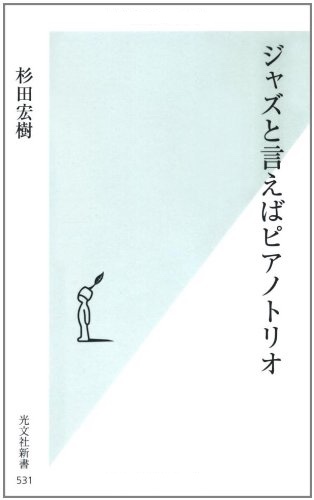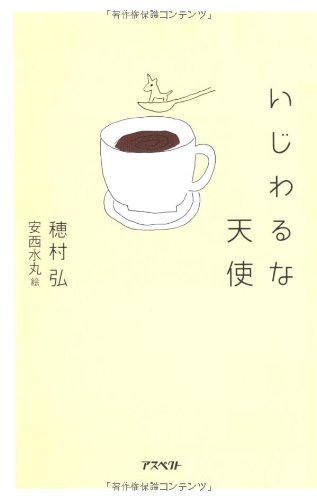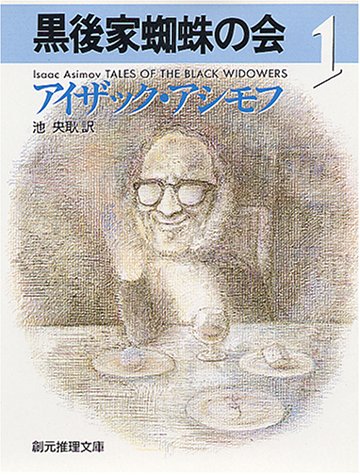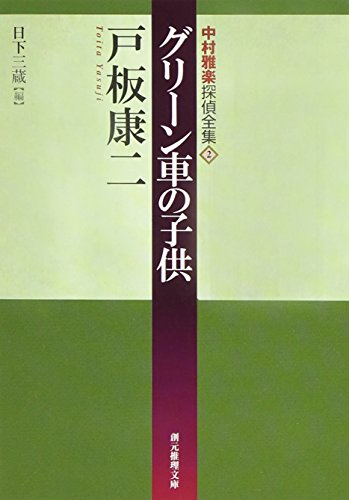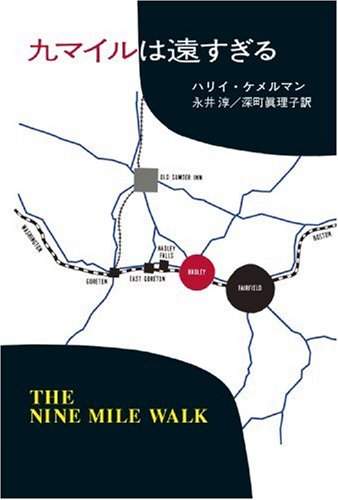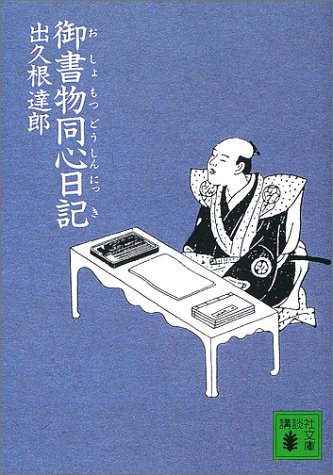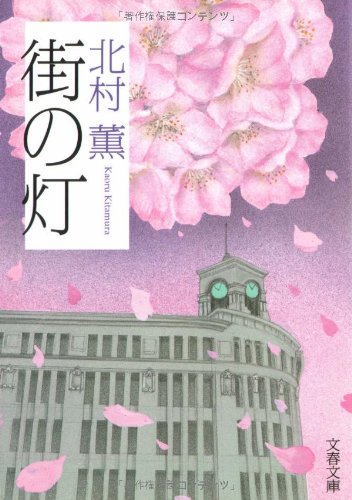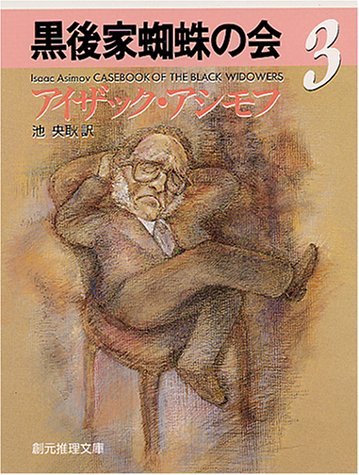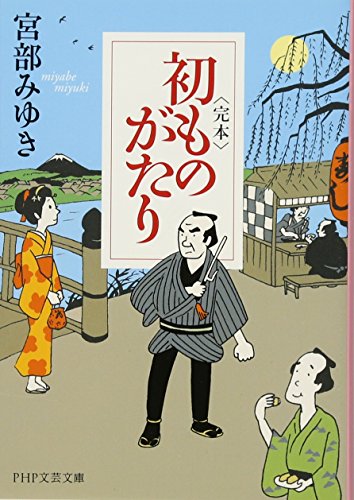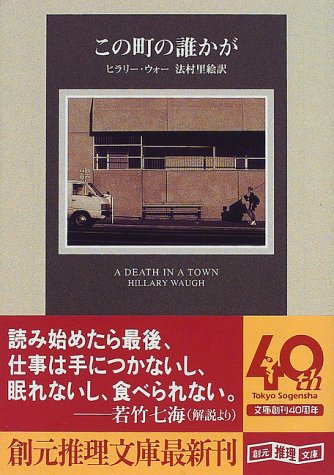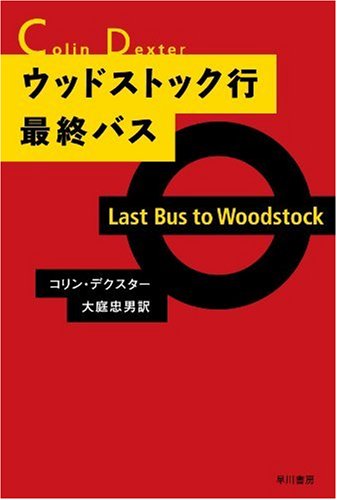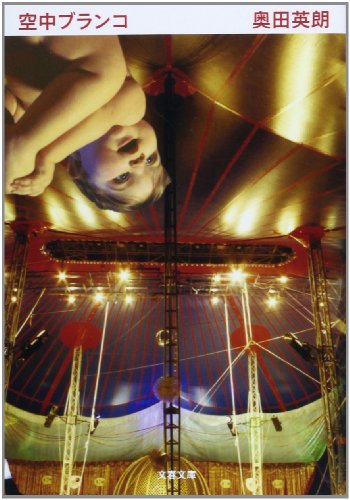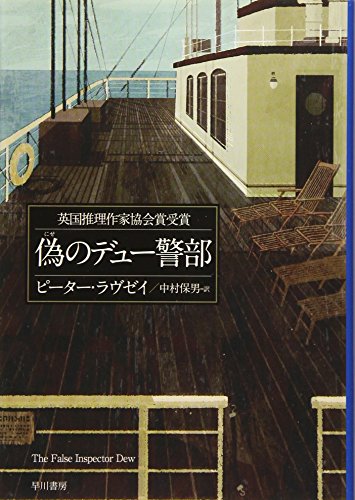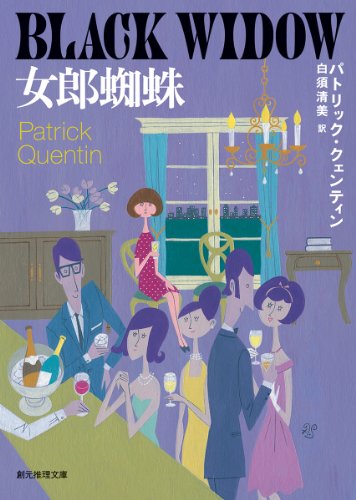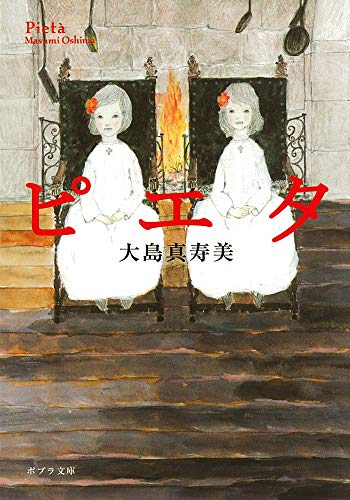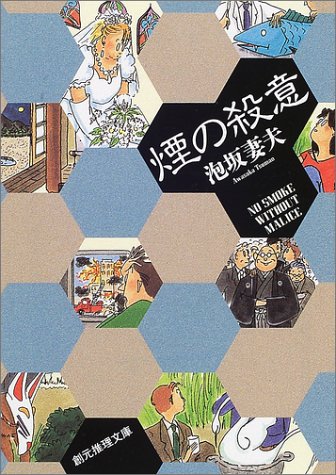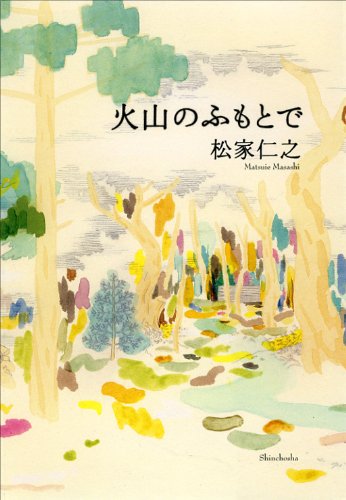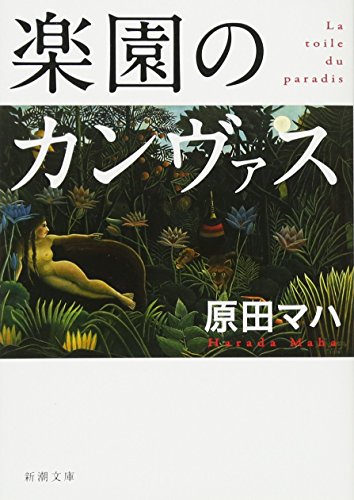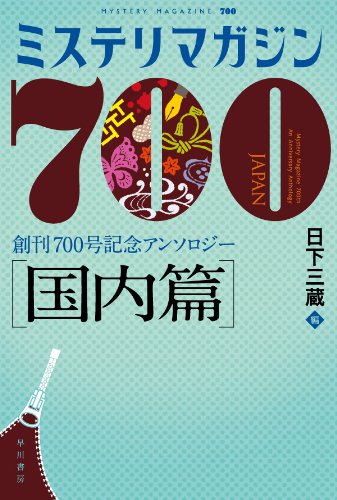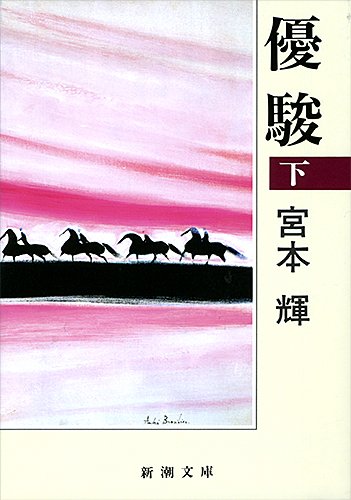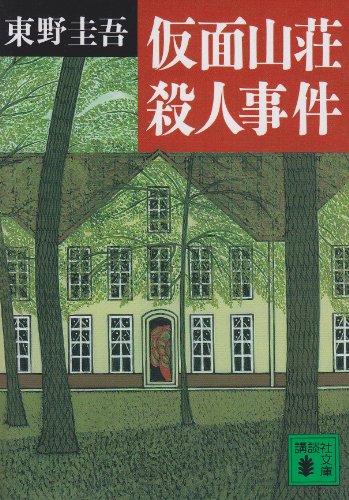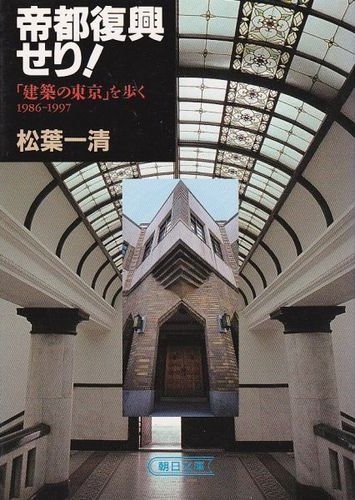本のない家
2004.8.7|book
意外そうな顔をされることもあるのだけれど、ぼくは読書家ではない。読書家ではないけれど、活字中毒者ではある。たとえば古本屋で、無造作に並んだ本の背表紙をながめてすごす時間はなかなか楽しいひとときだ。
もちろん、たまには買うことだってある。でも、たいていは拾い読みで終わってしまう。
たぶん集中力に欠ける性格が問題なのだとは思うが、ストーリーを追うことよりも、ちょっとしたセンテンスに「おおっ」と感心したりすることのほうが好きなのかもしれない。
それはともかく、世の中には本のない家というのがあるらしい。知り合いのライターさんが取材でたずねた先が、にわかには信じがたいのだが、そういう家だったというのだ。話によれば、その家にはなにかの雑誌が一冊あった以外は、見事なまでに一冊の本もなかったらしい。
本のすくない家、これはわかる。だが、本のない家となると話は別だ。ふつう生きていれば、酔った勢いで『世界の中心で、愛をさけぶ』を買ってしまうということだってないとはいえない。
活字を読むと死んでしまう奇病、はたまた一切の活字を否定するカルト宗教の信者・・・ここまで徹底された本の排斥の背後に、理解をはるかに超えたなにがしかの引力の存在を疑りたくもなるのだが、正直あまり意味があるとも思えない。
ただ、ちょっとビックリするような話を聞いてしまったのでそれについてなんとなく書いてみたい、そうかんがえただけなのだから。
そして、ひとはそれを活字中毒者の宿命、という。
森 麗子さんの画文集
2004.8.17|book
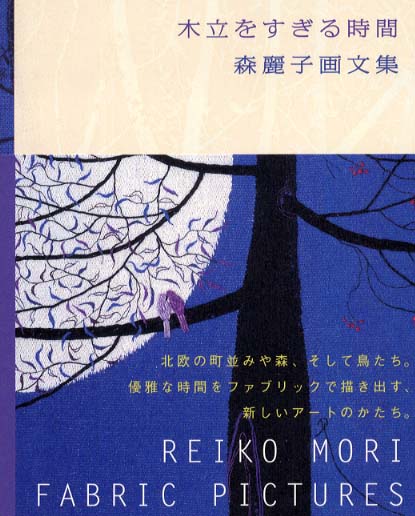
糸で絵を描く、ファブリックピクチャーとよばれる技法によってすばらしい作品をつくりつづける森麗子さんの画文集『木立をすぎる時間』を手に入れました。
公私共々お世話になっているIさん(自家製バジルペースト、たいへん美味しゅうございました)から、この本の存在をおしえていただいたのはたしか去年の秋ごろのこと。
その作品を構成するモダンな感覚にまず驚き、つづいて、まさに北欧的といえる透明なリリシズム(森さんは、1960年代にスウェーデンで刺繍を学んだりもしているのです)に感銘をうけたのでした。
森さんのファブリックピクチャーは、たんなる「刺繍」にとどまらないもっと自由なもの。「筆と絵の具の代わりに、織る・刺す・布を置く等」さまざまな技法を、そのつど自由な感覚で選びとるところから作品がうまれてきます。この『木立をすぎる時間』では、森さんの心象風景が、その作品と北欧をはじめとするさまざまな国々での出来事を綴った味わいぶかいエッセイによってたおやかに表現されています。
北欧やテキスタイルに関心のある方(とくにminäのスカートを穿いたあなた)はもちろんのこと、まいにちをゆったりとした心持ちで生きたいと願うすべての方にスイセンします(いまさら「スイセン」なんておこがましい話ですが)。
追記:来月には、東京・千疋屋ギャラリーにて小品展も催されるようです。
Think different.
2004.8.31|book
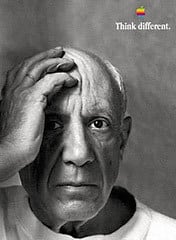
いま手もとにあるのは、『アップル宣言(マニフェスト)~クレイジーな人たちへ』と題された一冊のちいさな本。かつてアメリカで「エミー賞」を受賞したCF"Think different"をまとめたものだ。
この本では、アップルコンピュータの〈企業理念〉ともいえる散文が、さまざまな分野で〈偉業〉をなしとげた唯一無二の〈天才〉たち ── アインシュタイン、ボブ・ディラン、キング牧師、、ガンジー、ジム・ヘンソン(「セサミ・ストリート」の人形作家)、ピカソなどなど ── のポートレイトとともにレイアウトされている。
「クレイジーな人たちを称えよう」という一文ではじまるその〈散文〉で、「クレイジー」とよばれるのは「自分は世界を変えることができる」と考えるような人たちのことであるが、しかし「ほんとうに世界を変える」のは実はそういう人たちなのである、と語られる。そしてアップルコンピュータは「そんな種類の人々のために道具を作っている」のであって、「クレイジーとしか見られない人々だが、私たちには天才が見える」、そう〈宣言〉するのである。
なにか「壁」のようなものにぶちあたったとき、ぼくはいつもこの短い文章を思い出す。そしてほんのすこしだけ、救われたような気分になるのだ。
モノをつくる人は、たんにモノをつくるのみならず、どんな人にどう使ってほしいのか、深く見据えたうえでモノをつくってほしいと思う。なぜといえば、明確な理念に裏うちされたプロダクトはうつくしいからだ。
ボサノヴァの教科書
2004.9.5|book
ブックカバーなしでよみたい〈ボサノヴァの教科書〉が出ましたよ。

B5 books編『BOSSA NOVA』(アノニマ・スタジオ)がそれです。いつもお世話になっているbar bossaのマスター林さんがテキストを、カリスマ雑貨店「5(サンク)」のオーナーでもある保里さんがアートワークを手がけた、まさにかゆいところに手がとどく一冊。
ボサノヴァのルーツであるサンバ、ショーロから、ボサノヴァ以降のポピュラーミュージック(MPB)までが、たんなる史実のられつに終わることなく、たのしいエピソードをまじえながらソフトな口調でわかりやすくつづられています。紹介される音源にはいわゆる〈隠れた名盤〉も多いので、耳の肥えたリスナーでもじゅうぶん満足できるはず。また、後半にはボサノヴァをより深く楽しむための「ポルトガル語講座」なんて章もあって、空振り三振よりも見逃し三振を狙ったニクい内容とでもいいましょうか・・・。参りました。
ところで、この本の刊行にあわせて、林さんがコンパイルしたCD『BOSSA NOVA~compiled by bar bossa』(ユニバーサル)もリリースされました。今回はじめてCD化された曲や惜しくも廃盤になってしまった名盤からの曲などが中心で、とにかく買って損はしない一枚となっています。それになんといっても、保里さんがデザインした内ジャケ、すごくいい感じに仕上がってます。音楽への愛情がひしひしと伝わってきますね。必見。
これからの季節、秋の夜長に鼻うたまじりの"お勉強"なんて、なかなかしゃれてるとは思いませんか?
アートと喫茶
2004.9.25|book
品切れでご迷惑をおかけしていた小冊子『アートと喫茶』が再入荷しました(税込み315円)。

イベント〈アートと喫茶〉については、このブログでもたびたび触れてきました。この秋、都内12のカフェ/ギャラリーをリンクして行われる展覧会イベントで、moiでも参加企画として10/3(sun)までひらいみもさんのイラスト展「森のカモメ」を好評開催中です(もうご覧いただけましたでしょうか?)。
この〈アートと喫茶〉は、かつて植草甚一が暮らしていた街、経堂にあるappel(アペル)とROBA ROBA cafeというふたつのカフェ/ギャラリーの呼びかけで実現しました。
このイベントのおもしろく、意義深い点は、ここにあつまった12のカフェ/ギャラリーは、原則としてすべて個人オーナーの店であるというところにあります。家賃がべらぼうに高いうえ、すまいと職場、遊び場が完全に切りはなされてしまっている「東京」という場所は、たとえば関西とくらべて、個人でことをおこすにはあまりにも不向きな場所です。結果、街にはチェーン店や企業のアンテナショップばかりがあふれ、店の数だけは多いけれどおもしろい店、個性的な店は少ない、そんな状況になってしまうのです。
「個性的な店」といっても、なにも風変わりなコトをしている店という意味ではありません。「オーナーの『顔』がみえる店」、オーナーの人格や思いがさりげなく感じとられる店こそが「個性的」だとおもうのです。「そこに行かなければ出会えないなにか」があるからこそ、ぼくらは「そこに行く」のではないでしょうか。
そうした意味で、このイベントに参加している12のカフェ/ギャラリーはどれも、もちろんmoiもふくめて、唯一無二の個性をもった空間だとおもいますし、すくなくともそうありたいとかんがえて日々(それぞれのやりかたで)奮闘している店ばかりです。
山椒は小粒でもピリリと辛いなんていいます。「アート」とのふれあいをつうじて、この秋はそんなピリリと辛い空間を味わってみませんか?なんといっても、こういう空間を支えられるのはそこを気に入ってくれて、たびたび足を運んでくれるようなお客様だけなのですから。
小冊子『アートと喫茶』は、そんなみなさんにとっての〈航海図〉としてきっと役立ってくれることでしょう。
ボサノヴァ
2004.10.27|book

ボサノヴァを、こじゃれた音楽の代名詞のようにかんがえているひとって多いのではないでしょうか?だから、ボサノヴァはひとつの「生き方」であるなんて言ったら、ちょっとびっくりしてしまうひとだっていないとは限りません。
でも、このちいさな本『ボサノヴァ』(アノニマ・スタジオ刊)を読んで、いつ、だれが、どこで、どんなふうに「ボサノヴァ」をつくり、育てたのかということを知ると、つい気取ってそんなふうに言いたくなってしまうのです。
ボサノヴァを聴くのにぜひ知っておきたいエピソードや貴重な写真などが満載のこの本は、ボサノヴァが好き、あるいは気になるというひとにとって、まさに格好の「入門書」といえます。けれども、ぼくがこの本をおススメする理由はもっとべつのところにあるのです。ひとことで言えば、この本『ボサノヴァ』には「空気」や「匂い」があります。ボサノヴァが誕生した1950年代後半のリオの街のざわめきや、そこで暮らす若者たちの生活ぶりが活字をとおして伝わってくるようです。そして読みすすむうちぼくらは、最初ちいさなひとつの「点」でしかなかったボサノヴァが、その波紋をぐんぐんひろげて世界中を巻き込んでゆくさまを〈目撃〉するのです。
そしてもうひとつ、ボサノヴァを育てたのは「ひと」なんだというのもまたこの本から知ったことです。ボサノヴァの波紋は、「ひと」と「ひと」とをつなぎながら、それを原動力にどんどん大きくなってゆくのですね。「友情」や「恋愛」がボサノヴァを育んだ、そんなふうにも言えるかもしれません。ボサノヴァにおおらかさやある種の〈ヒューマニズム〉を感じるとしたら、それはきっとそういうことなのでしょう。
とにもかくにも、このちいさな本を手にいれれば、耳なれたはずの「ボサノヴァ」が俄然おもしろくなることまちがいなしなのです。
B5ブックス編『"BOSSA NOVA"』(アノニマ・スタジオ刊)はmoiでも好評発売中です(1,250円+税)
秘密のコーヒー
2004.11.12|book
秘密のコーヒー。
フィンランドの小説家レーナ・クルーンの短編小説に、それは登場する。八月のちょっとせつない物語だ。主人公の少女ヴェーラは家でコーヒーをのむかわりに、ちかくの荒れ果てた桟橋で、生い茂った葦になかば隠れるようにしてひとりコーヒーをのむのがお気に入りだ。それを、家族たちは皮肉って「秘密のコーヒー」とよぶ。そしてある夏の終わりの午後のこと、「秘密のコーヒー」に導かれたヴェーラはひとりのふしぎな少年と《出会う》のだった・・・。

これは、カップ一杯のコーヒーとそれがもたらす特別な時間についての物語である。「場所」、つまり「秘密の桟橋」ではなく、ヴェーラを訪れるふしぎな出来事は、なにより「秘密のコーヒー」とその「時間」によってもたらされるものだ。いいかえれば、ヴェーラの「秘密のコーヒー」とは、見なれた世界を見知らぬ世界へと変えてしまう、ちょっとした「スウィッチ」のようなものである。「秘密のコーヒー」をもつ者は、あるいは、世界を二重に生きているのかもしれない。
もし、あなたのまわりに葦の生い茂った古い桟橋がなかったとしても、だいじょうぶ、あなたが「秘密のコーヒー」をもつのはさしてむずかしいことではない。まちには「カフェ」や「喫茶店」という、「秘密のコーヒー」をたのしむのにうってつけの隠れ家が用意されているのだから。ヴェーラが、ポケットにプッラ(フィンランドの菓子パン)をつっこみ、コーヒーカップ片手に意気揚々と家をとびだしてゆくように、「都会のヴェーラたち」はカフェをめざす。
秋の昼下がり、moiで思い思いのひとときをすごすひとたちを見ていると、ぼくにはなんだかヴェーラの姿がだぶってみえる。
COFFEE AND ROASTER
2005.2.10|book
コーヒーをじぶんで淹れる、最近そんな「たのしみ」にハマっているという方、おおいのではないでしょうか?
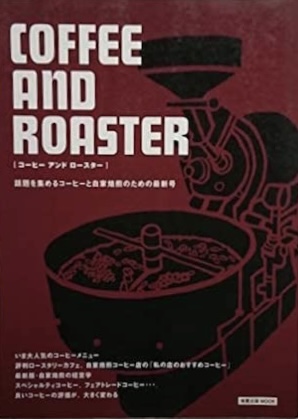
「おいしいコーヒー」を飲むためにいちばん大切なこと、それはよく「教則本」にあるような知識-どんな器具をつかって、何グラムの豆をどのくらいの温度のお湯で抽出すればよいかといった-である以前に、じぶんにとって「おいしい」とおもえるコーヒーとはどんな味なのかを知ることにあるとぼくはかんがえています。というのも、あくまでも「目的地」は「おいしいコーヒーを飲むこと」にあるのであって、「目的地」があってはじめて、その「道筋」(たとえば「抽出技術」)も決まってくるものとおもうからです。ですから、これからじぶんで「おいしいコーヒーを淹れたい」という方にはぜひ、じぶんにとっての「目的地」といえる味と出会うところからはじめてもらいたいものです。いろいろな喫茶店やカフェでコーヒーを飲んでみたり、自家焙煎店でコーヒー豆を買ってみたり、そんななかで、ある日きっと「これだ!」とおもえる味と出会えるはずだからです。
最近でた本『COFFEE AND ROASTER』(旭屋出版)は、そんなみなさんにぜひ手にとっていただきたい一冊です。とくにおすすめしたいのは、「私のおすすめコーヒー」と題したロースタリーカフェ(自家焙煎したコーヒーを提供しているカフェ)や自家焙煎コーヒー店へのインタビュー記事。じぶんにとっての「理想の味」を追求するロースターたちの、百人百様の《哲学》のようなものが伝わってきます。また、焙煎技術の基本やブレンドの意図、それに近ごろよく耳にする「スペシャルティコーヒー」や「フェアトレード」といった言葉の解説もされていて、焙煎にも関心がある、コーヒーについてもっと深く知りたい、といったひとにも役立つ内容になっています。
コーヒーを飲むというよりはコーヒーと出会う、そんなたのしみを教えてくれる一冊です。
白夜の「青」
2005.3.7|book

東山魁夷が、じつは「北欧」の風景画をたくさんのこしているということを知ったのは、そう古い話ではない。それまで《日本画の大家》くらいにしかかんがえていなかった魁夷とその作品に、親しみを抱くようになったのはそのことがあったためである。
「北欧の風景が、その森や湖が、私を呼んでいるように感じ」た魁夷は、1962年54歳のとき、はじめての北欧をめぐる旅にでる。その旅は決定的なものだった。かれは、こうしるす。「心の故郷に巡り会った」。北の国々で、魁夷の琴線に触れたのはたんなる見事な景観ではなく、そこにつよく息づく「寒さの中での暖かさ」「暗さの中での明るさ」「生に対して過酷な条件の中での、生の輝き」であった。
ふたたび、東山魁夷が描いた北欧の絵をながめてみる。そして気づくのは、「青」のこと。東山魁夷の幽玄な世界に不可欠な、あの「青」。それは白夜の「青」にほかならない。北欧の夏に「黒」はない。そこでは「青」は、夏のつよい光を孕んで刻々とその階調を変えながら移り変わってゆくのである。そして魁夷の「青」には、たしかに「光の兆し」がみとめられる。
心のなかに「北方を指す磁針」をもつすべてのひとは、ぜひもういちど、あらためて東山魁夷の世界にふれてみてほしいとおもう。
◎ 参考図書/東山魁夷全集4『北欧の旅』(昭和54年 講談社)
※なお、現在moiにてこの本を販売中。31×26cmの大判の画集(函つき)です。新古本ですが、経年変化に伴う若干の汚れ、キズはあります。2,000(税込み)。もちろん一点限りですので、売り切れの際にはご容赦ください。←おかげさまで売り切れました。
『エクスプレス』がおもしろい
2005.4.9|finland
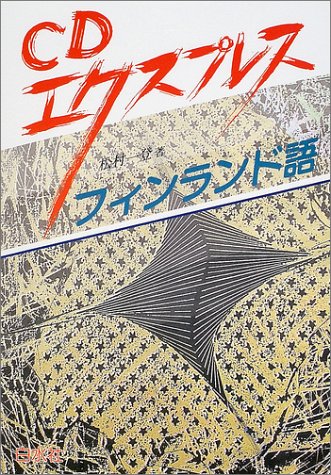
フィンランド語を勉強しようというひとは、いまなら何冊かのテキストからじぶんに適したものをえらぶことができる。ところが数年前まではそうはいかなかった。日本語で「フィンランド語」を学ぼうという初心者にとって唯一のテキストは、『エクスプレス~フィンランド語』(松村一登著/白水社)だった。いまとなっては表現にやや古めかしさが目立ったりはするものの、あいかわらずぼくの中でのこの本の「王座」はゆらぐことはない。なぜなら、例文がめちゃくちゃシュールでおもしろいからである。
第一章のタイトルは「あなたはだれですか?」とあり、フィンランド人の女性「レーナ」と日本人の男性「徹」との会話からなっている。
レーナ:こんにちは、徹さん!
徹:こんにちは!あなたはだれですか?
いきなりじゃないか。「こんにちは、あんただれ?」って、そんな返答の仕方があるだろうか。しかしレーナはレーナでどこかズレているのだった。「わたしはレーナです」と冷静に自己紹介をしたあと、徹にこう問いかける:
レーナ:あたなは「日本人」ですよね?
見ず知らずのフィンランド人がじぶんの名前を知っている上に、「日本人か?」と訊ねてきているのである。これはかなり怪しむべきシチュエーションではないだろうか?しかしながら、徹にはまったく動じている様子がない。
徹:はい。そしてあなたは「フィンランド人」です。
って、いったいこのひとたちときたらなにを確認しあっているのだろうか?にもかかわらず、「その通り(Aivan.)」と悠然と返すレーナには「クイズ$ミリオネア」の「みのもんた」のような貫禄すら感じられる。その後、レーナから「フィンランド語」をほめられた徹はよほどうれしかったのか、すさまじい暴走ぶりを発揮する:
徹:ありがとう。あなたは美しい。
「イタリア人」のような徹である。しかしレーナの顔色を窺うでもなく、徹はこう続ける:
徹:あ、バスがくる!ごきげんよう。
レーナ:ごきげんよう。
ここからわかるのは、「徹はかなり身勝手な男である」ということである。しかし、それはそれとしてレーナはいったいなにが「目的」で徹に声をかけたのだろう。この会話の中でレーナがえた情報は、「やはり徹は日本人だった」ということだけである。まったくもってよくわからない。それでもあんまりおもしろいので、気づいたらこの会話をまるごと暗唱できるようになってしまった。
ほかにも、フィンランドっぽいユーモアを感じさせる第14章「彼女は水ばかり飲んでいました」、それに「美晴」と「パイヴィ」の会話から、「レーナ」と「徹」の暴走カップルがつきあっていることが判明する第9章「わたしはテープレコーダーをもっていません」もいい。
とにかく、この『エクスプレス』からぼくは確信する。著者の松村一登先生はかなりおもしろいひとにちがいない。
まのいいりょうし
2005.4.17|book
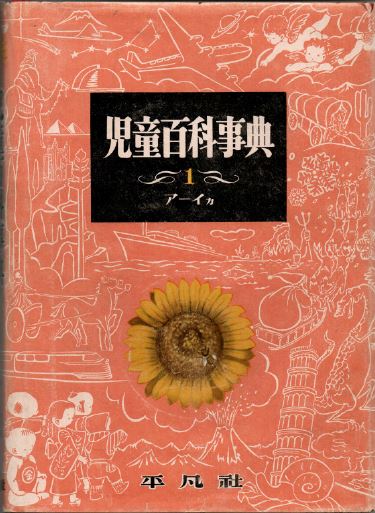
とにかく呆れかえるほど、子供のころなんども読みかえしたのが平凡社の『児童百科事典』。文字どおりボロボロになるまで、毎日あきもせずながめていた。どのページをひらいても、まっさきにきれいなイラストが目に飛びこんでくるような本だった。
そのいっぽうで、いったいこれはどうしたものかというようなやけにシュールな「むかしばなし」も、子供心によくおぼえている。とりわけお気に入りだったのが、「まのいいりょうし」というお話。ひとりの猟師がいつものように狩りにでかけるのだが、どうしたわけかその日にかぎってつぎつぎと思いがけないハプニングに見舞われる。ところが、そのハプニングがことごとく猟師にとって「プラス」にはたらき(なんたって「まのいいりょうし」なのだ)、山ほどのごちそうをかかえて家に帰る、といったお話である。このお話のいいところは、そこにいっさいの教訓も戒めも見あたらないところにある。
「まのいいりょうし」がいったいどれほどまでに「まがいい」のかというと、たとえば、切り株につまづいてコケたら、そのコケた目の前にたくさんのキノコがはえていたり、転んだひょうしに銃身が折れ曲がってしまった鉄砲でうったら、なぜかその弾の飛んでいったさきにカモの群れがいたりと、まあずっとそんな調子なのである。まさに結果オーライ、たんなる運のいいオトコのお話にしか思えないわけだが、まだろくすぽ物心もついていないようなコドモにこんな話をきかせていったいどうするつもりだったのかと編集者に問いただしたい気分ではある。
じっさい、子供だったぼくはこの「まのいいりょうし」のお話を読んでこう感じた。うん、これはいい!「まのいいりょうし」のようになりたいものだ。こうして、「まのいいりょうし」はぼくのこころのヒーローとなった。それから三十年あまりの歳月をへて、いまのぼくの心境はこうだ。「まのいいりょうし」にはなれなかった・・.。
まったく、苦々しいったらありゃしない。
ちいさいサンパン 原画展
2005.4.20|book
三鷹の古書上々堂で、いま山本忠敬さんの原画展「ちいさいサンパン」がひらかれている(~30日)。

『しょうぼうじどうしゃ じぷた』や『はたらくじどうしゃ』などなど、すこやかにそだった「男子」ならばだれでも、きっといちどは山本さんのえがいた絵を目にしているにちがいない。そんな山本さんが、1961年に月刊絵本『ひかりのくに』に発表したのがこの、今回原画が展示されている「ちいさいサンパン」である。
ぼくじしん、山本忠敬さんの絵本には親しんできたこともあって、こうした展示が実現したことに心踊るものがあるのだけれど、それ以前に、今回はちょっとした「縁」のようなものを感じている。山本さんは二年ほどまえ、86歳でこの世を去られている。そしてその最期の日々をすごされたのが、じつはmoiの目と鼻の先にある某病院であり、よく山本さんの奥様が看病の合間をぬってはmoiに来てくださり、偶然にもいろいろなお話をうかがう機会にめぐまれたからである(フライヤーを届けてくださった「上々堂」の方のお話では、奥様も「moi」のことをおぼえていてくださったとのこと)。
さらにいえば、このあいだこのブログでもふれた『平凡児童百科事典』は、後から知ったのだが、山本さんの絵本作家としての「初仕事」であったらしい。それに、今回の企画がmoiのお客様の口からよくその名前があがる「上々堂」さんによるものであることもまた、ぼくにとってはすこしばかりうれしい偶然だったりする。
むかしもいまも、そしてこれからも、きっとこどもたちの心をワクワクさせつづけるであろう山本忠敬さんの作品たち。機会があればぜひ、みなさんも三鷹の「古書上々堂」まで足をはこんでみてもらいたいとおもう。
→ちなみに銀座の教文館書店でも、いま山本忠敬絵本原画展「はたらくじどうしゃ」が開催中(~5/15)とのこと。あわせてどうぞ。
『シベリウス』がおもしろい
2005.5.12|book

夢想家で浪費家、見栄っ張りで、おまけに小心者、そんな作曲家シベリウスの素顔をわかりやすいことばでつづった『シベリウス アイノラ荘の音楽大使』(ひのまどか著 リブリオ出版)は、相当おもしろい。
「禿げ上がった石臼のような頭をもち、つねに眉間にシワをよせた気むずかし屋の国民的作曲家」というイメージは、ここではあまり感じられない。酒に溺れては何日も家をあけ、イタリアでは家族を放置していきなり失踪、莫大な借金で自己破産寸前にもかかわらず、出版社との契約を結べばいきなり庭に念願の「サウナ小屋」を建てしまう。そのくせ「私がいったい何をしたというのか!私は借金を払うためにこの世に送られてきたのか!」などと逆ギレする始末。家族からしたら、これはもうAランクの「ダメおやじ」である。「人間くさい」といえばいえなくもないが。それにしても、浪費家でおカネの苦労が絶えなかったシベリウスが紙幣の肖像になってしまうのだから、世の中というのは皮肉なものだ(画像/旧100mk紙幣 現在の通貨はユーロのためすでに廃止)。
ところで、そんなシベリウスのお孫さんがここmoiをおとずれたことがある。ウソみたいな話だがホントである。建築家で、フィンランド建築博物館の館長もされているセヴェリ・ブロムシュテットさんがそのひと。お母さんが、シベリウスの六女ヘイディさん、お父さんは高名な建築家でシベリウスの墓碑の設計も手がけたアウリス・ブロムシュテットさんである。2002年に「アルヴァー・アールトの住宅展」が開催された折り、レクチャーの打ち上げがてら立ち寄ってくださったのだ。お会いしたセヴェリさんはとてもフレンドリーで、なおかつ身のこなしも洗練されていて「なんかフィンランド人っぽくないなぁ」と感じた記憶がある(笑)。いまにして思えば、上流家庭の出身で、同じような境遇の人々との交流がほとんどだった「シベリウス家の血」がなせるわざだったかもしれない。
ちなみにmoiのコーヒーを口にしたセヴェリさんの感想は、「Velvet!」。シベリウスの伝記をよんだおかげで、思いがけず記憶がよみがえった。
PLAYBILL
2005.5.15|book
むかしむかしといってもたぶん8年前くらいのこと、表参道の青山通りからちょっとはいった路地に「プレイビル」という名前のちいさなブックストアがあった。素っ気ないけれど雰囲気のある、ニューヨークの街角に佇むブックストアのような空気をもつ店だった。ちかくには、イームズが流行るずっと前からイームズの家具をあつかっていた「Moder Age Gallery」があったり(現在は「目黒通り」に移転)、すこしさきには「LAS CHICAS(ラスチカス)」というユニークなカフェがあったりと、当時その界隈にはそんなすごく「いい匂い」が漂っていたのだ。
ところで「プレイビル」には、いつもおんなじCDをエンドレスでリピートしながら店番している「アヤちゃん」という女の子がいて、「プレイビル」の「空気」の大半はたぶんアヤちゃんがかもしだす「空気」だった。ぼくは、当時手伝っていた「American Book Jam」という雑誌のためにそこで「ポエトリーリーディング」のイベントをやらせてもらったことがある。メインはNYと東京のふたりの詩人による競演だったのだけれど、「ボクシング」をテーマにしたコミック本を手にそのイベントに飛び入り参加したアヤちゃんのボーイフレンド「タケ」は、魂のこもったリーディングで会場の温度をぐっと上昇させてくれた・・・バシッ、グギッ、うぐっ。
その後「プレイビル」は店じまいし、アヤちゃんとタケは結婚して、アヤちゃんは「いいお母さん」になった。「プレイビル」はなくなってしまったけれど、そのお店の「ちいさな魂」はいま、かれらの「家庭」におだやかに宿っているにちがいない。
余談だが、コミックを読まないぼくが吉田戦車『ぷりぷり県』を全巻こっそり揃えているのはアヤちゃんの影響だ。ちなみにアヤちゃんのお気に入りは「イサム本部長」、ぼくは・・・「でっち義兄さん」だな。
ストックホルム・カフェマニア?!
2005.7.5|book
「北欧みやげ市」に出品する商品のごあんないです。

ストックホルムをあるきながら思ったのは、「ああ、ここストックホルムにも「東京カフェマニア」のようなサイトがあったらよかったのに・・・」ということ。サイトはけっきょくみつからなかったけれど、ちょっと気のきいたこんなガイドブックならみつけました。題して、『ストックホルム「夏カフェ」案内』。

案内役をつとめるのは、ストックホルムの「サマンサ」さんこと(?)ミア・エールンさん。この本では、ストックホルムとその近郊の「夏カフェ」(夏季限定、あるいは夏こそ「最高」という湖畔や海に面していたり、気持ちのいいテラス席をもつカフェ)がエリア別に50カ所あまりピックアップされ、紹介されています。
たとえば「ベルマン美術館のCafe Bla Kanin」を例にとると、
「ベルマン美術館の庭では、あの有名な《吟遊詩人の時代》に迷いこんでしまったよう・・・。ルピナスやホップ、ルバーブが咲き乱れる花壇をそぞろ歩いていると、やがて湖水を臨むことのできる裏庭に出くわします。そして17世紀にたてられた建物にあるこのカフェでは、年季の入ったかまどの上にパイやパン、それにクッキーなどが並べられているのです。」
といった具合。
この本、北欧の「夏カフェ」に思いをはせながら眺めているだけでも愉しいのですが、本文のスウェ-デン語とともに英文も併記されているので実践的な旅行ガイドとしても威力を発揮してくれるでしょう。値段やカード利用の可否、トイレの有無、提供している料理がホームメイドがどうかといった情報が、ひとめでわかるようマーク表記されているところも便利です。
book baton
2005.7.13|book
ついこのあいだ、「musical baton」にあたまを悩ましたばかりだというのに、macoさんからまたまた選ぶのに苦労しそうな「book baton」なるものがまわってきました・・・。「読書家」というわけでもないのに、それでも、いざ選ぶとなるとたやすいことではありませんね。選べなかった「本(音楽)」にはホントすまんかった、そんな気分。では、いってみましょう。
◎ 持っている本の冊数
300冊くらい、でしょうか。その大半は実家に放置状態。「なんとかせんかい!」という親からのプレッシャーを再三無視しつづけていたら、ついには「強制執行」の憂き目に・・・。年末ひさびさに実家に戻ったところ、なかば強制的に処分させられてしまいました。よって、いまは200冊くらいかも。
◎ いま読みかけの本、または読もうと思っている本

植草甚一(瀬戸俊一編)『コラージュ日記2 ニューヨーク1974』
《お気に入りのモノ》だらけのニューヨークで、なりふりかまわず弾けまくるJ・J氏の衝撃(笑撃?!)の買い物アディクトっぷりにただただ唖然。古本屋で台車を借りてホテルまで運び、荷物を置いてからまた出かけた、とか・・・最高!
◎ 最後に買った本(既読、未読問わず)

川上弘美『センセイの鞄』
小説はよめない体質なのですが、このひとのだけはかなりよんでいます。文庫化されているものの中で唯一これだけ手に入れていなかったことを思い出し、駅前の「ブックオフ」で買いました。飄々として素っ頓狂な「センセイ」は、かつての上司に似ています(笑)。
◎ 特別な思い入れのある本、心に残っている本5冊

田口護『コーヒー 味わいの「こつ」』
「カフェ・バッハ」の田口氏によるビギナー向けのコーヒー指南書。コーヒーのおいしさを知ってはじめて手にした、思い出ぶかい一冊。以前、「コーヒー」をテーマにしたあるテレビ番組に出演させていただいたときのこと、そこには著者の田口氏も登場されていたのですが、おなじ番組の中にじぶんがいるという現実がどうにも信じがたく、オンエアを観ながらまるで夢の中にまよいこんでしまったかのような不思議な感覚にとらわれたのをおぼえています。

『歎異抄』
思想家としての「親鸞」はかなりおもしろい。善人が救われるのだから(もっともっと救いを必要としている)悪人が救われるのは当然でしょ?という「悪人正機説」をはじめ、ちょっとアナーキーで思わずニヤリとさせられるような思考がいっぱいつまった「玉手箱」のような一冊です。ところで、植木等も好きらしいですね、親鸞。わかるなぁ。
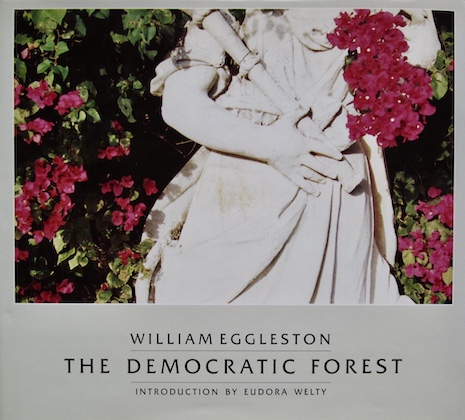
William Eggleston『The Democratic Forest』
どんな写真家のそれよりも、エグルストンの写真がすきです。ヴィム・ヴェンダースの映画『パリ・テキサス』を観たとき、このひとはエグルストンがすきにちがいないと確信した。本当のところは知りませんけど。
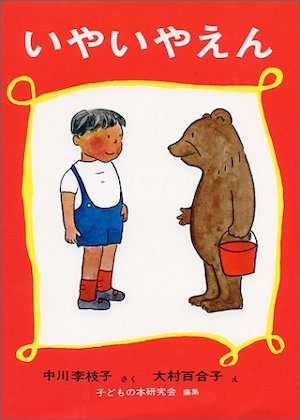
中川李枝子 作・大村百合子 絵『いやいやえん』
「ももの山」にのぼりたかった、いたいけな幼年時代?!
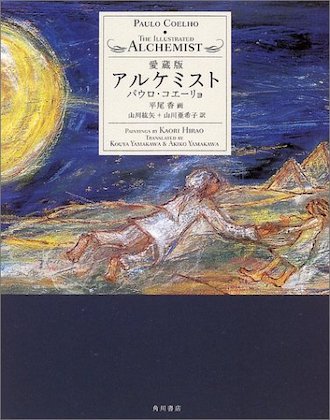
パウロ・コエーリョ『アルケミスト』
暗記してしまうくらいくりかえし読んでいるのに、読むたびに新たな《発見》があるこの本。平明な「ことば」で語られるのは「宇宙」のこと。いままで、この本を読むことでどんなにか助けられてきたことか。いつか無人島に行く機会があったなら、忘れずこの一冊をたずさえてゆきます。
◎ 次に回す5人
懲りずにまたもや「逆エントリー」で。いまこれを読んでいるアナタの「愛読書」をおしえてください!ぜひ、あなたの「book baton」をこの記事にトラックバックしてください。あと、
talk is toyのTANAKAさん、
BAR BOSSA通信のはやしさん
ノッてくれるとうれしんだけど、どうですかー?
エルサ・ベスコフ
2005.7.27|book
北欧のこどもたちはベスコフの絵で育つ、といわれるほどに、スウェーデンの絵本作家エルサ・ベスコフ(Elsa Beskow)は北欧のひとびとのあいだではよく知られた存在のようです。じっさい、知り合いのフィンランド人もこどものころ親しんだそうです。

1874年にストックホルムでうまれたベスコフは、1953年に亡くなるまでのあいだに数多くの絵本を未来のこどもたちのために残しました。その作風は、ケイト・グリーナウェイらイギリスのヴィクトリア朝を代表する挿絵画家の作品につうじるクラシックなものですが、白樺の森や摘みとったベリーをたっぷりいれた樹皮で編んだカゴ、ありとあらゆる生命のざわめきがきこえてきそうな夏の情景や、どうぶつや精霊たちと交感するこどもたちといった情景は、まさにまごうことなき北欧の清澄な世界そのものといえます。
ベスコフの絵本はここ日本でも古くから翻訳出版されていますし、また通販のフェリシモからも彼女のいくつかの作品が出版されているので、あるいはよく知っているというかたもいらっしゃることでしょう。たまたま近所の古本屋で手にした『ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん』という本をとおしてぼくはベスコフの存在を知ったのですが、淡い情景のなかにも凛とした空気が感じられるところが最大の魅力ではないかと思っています。
そんなわけで、せんだっての北欧旅行ではベスコフにまつわる品物をいくつか手に入れたいとかんがえていたのですが、ストックホルムで、ではなくヘルシンキで、日本ではおよそ目にしたことのないベスコフのアートポスターを発見しました。ぜんぶで3種類あるのですがスペースの都合上すべてを展示するわけにはいきませんので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にお声をかけてください。また、ご希望の方にはおゆずりします(ただし全種類、各一枚のみ)。
Elsa Beskow 原画ポスター(70×50cm) 4,200(税込み)
震災時帰宅支援マップ
2005.8.21|book


最近でかけるときに持ち歩いているのがこれ、『震災時帰宅支援マップ 首都圏版』(昭文社)。
火曜日の宮城県沖につづいて、きょうも新潟県中部で「震度5強」の地震を観測した日本。もう、いつどこで巨大地震が発生したとしても不思議ではない、いよいよそんな状況になってきたような気がしてなりません。
この『震災時帰宅支援マップ』は、外出時に、不幸にも交通機関のマヒをきたすような災害に見舞われたとき、自力で最寄りの「安全な場所」まで避難するとともに、最終的には「自宅」まで無事帰還することを目的としてつくられたマニュアル的色合いの濃い地図なのです。
この地図の特徴は、都心から埼玉、千葉、神奈川へと放射状に伸びる16の幹線道路を「帰宅支援対象道路」と位置付けて、その道筋にそって詳細な情報とともにまとめているところにあります。
コンビニやトイレ、病院、ガソリンスタンド、また一時避難場所に適した公立学校の場所などのほか、「ブロック塀」「歩道狭い」「両側切り立った崖」といった要注意ポイントもあわせて記載しているところが、ふつうの地図とはおおきく異なります。
幹線道路からはずれた全エリアを掲載しているわけではありませんが、ふだん持ち歩く地図としてもじゅうぶんに役立つ内容のものになっているのではないでしょうか。それに、薄く重さもさほどではないので、女性がバッグにしのばせておくぶんにもさほど不都合は感じられないと思います。
もうじき「防災の日」もやって来ますが、ぜひオススメしておきたいと思います。
読書の秋にちなんで
2005.10.10|book

あるご縁で、moiにもたびたびご来店いただいている作家鈴木佐代子さんより、moiのお客さまへということで著書『相続図鑑』をご寄贈いただきました。
この春に上梓された『潮ホテル・グラフィティ』も読ませていただいたのですが、鈴木さんの文体は「水」のようにさらりとしていて、なおかつ静かに心にしみ入ってゆくような余韻が残ります。潔い生き方をつらぬく大人の女性が主人公のこの『相続図鑑』は、女性が読むとよりいっそう強いあこがれと共感を抱くのではないでしょうか?ちなみに、装丁もたいへんきれいです。
そこで「読書の秋」にちなみ、moiでは「ぜひ読んでみたい」という方3名様にこの本をプレゼントさせていただきます。
ご応募は「メール」にて、「鈴木佐代子さんの本希望」とお書きの上お申し込みください。プレゼントは、先着で3名様。なお大変申し訳ないのですが、ご応募は「moi」まで受け取りにくることのできる方に限らせていただきます。また、「当選」のご連絡は「当選者」のみにさせていただきますのでご了承ください。
秋の夜長、虫の声をBGMに読むのがとても似合う、そんなおすすめの一冊です。ぜひご応募お待ちしております。
10/12追記:受付は終了させていただきました。ご応募ありがとうございました!
こどもの絵
2005.11.2|book
こどもの描く絵がすきだ。それは、たとえば街でこどもの絵をあしらったジャケットのレコードなどを見かけると、内容にかかわらずついつい手にとってしまっている自分に気づくといった調子だ。

こどもの絵には「味」がある。「ヘタ」ではない、「味」である。「下手」というのは、いっぽうに「上手」という意識があって、それに対して「ヘタだ」ということにほかならない。けれども、無心に描くこどもにあって「上手」という意識は存在しない。だから当然「下手」も存在しない。すべからく「味」である。たとえば「ダダ」と名乗るひとびとは、この「味」に芸術的価値を見ようとした一群であったろう。けれどもその「試み」が成功しているとは言いがたい。というのも、かれらが描く絵はたいてい分別のある大人が作為的に「下手」に描いた絵にしか見えないからだ。こどもの絵は、こどもにしか描けないところに価値がある。
このあいだ、一冊の古本をみつけた。『子どもの絵-成長をみつめて-』という本だ。東山明と東山直美というひとの共著である。読み始めてまもないのだが、読んでいていろいろと発見があった。
まず、こどもの絵の表現をとおしてその発達過程をみてゆくと、成長までにいくつかの段階があるという。その過程は、あるいは「味」から「下手」へともいいかえられるかもしれない。はじめの段階は「なぐりがき」である。これはこれで「味」がある。つぎにあらわれるのは「円や線」だ。円と線だけで描くもっとも原初的な人物画(たいていは「おとうさん」だったり「おかあさん」だったりする)はこの時期に登場する。そして「認識力」の段階がつづく。数の認識が絵に反映されるようになるのがこの時期だ。「下手」の芽生えかもしれない。「正しい認識」イコール「正しい絵」という「ものさし」が、おとなから押しつけられるようになるからだ。あとは「空間関係」、「自己主張」、「写実・客観性」そして「持続力」へとこどもの絵は《発達》を遂げてゆく。
ここでぼくがおもしろいと思ったのは、「認識力」の段階である。「数」をおぼえることで、こどもは、それまで三本だったり七本だったりした手の指を「指は五本」という認識にしたがって絵を描くようになる。けれどもここがいかにもこどもらしいところなのだが、こどもの認識力はじぶんが興味をもったものごとにしか向けられない。
それは、この本に登場するK子(四歳九ヶ月)が描いた「おとうさん」の絵である。指は両手ともにきっちり五本ずつ描かれている。ところが、だ。どうしたことかK子は、「おとうさん」のスーツのボタンを「20個ぐらい」描いてしまったのだった。どういうスーツなんだ。K子にはボタンの数は興味がなかった。そういうことなのだろう。すごいじゃないか、これぞ「こども」だ。「興味ないしー」とか言って無視しようとする「おとな」はすくなくないが、興味がないからといってボタンを20個も描いてしまう、それが「こども」の底力である。
分別あるおとなであるところのぼくとしては、こどもの絵に対してはこう言うほかない。こどもの絵はパンクだ。
『カレワラ物語』がおもしろい
2006.1.11|book
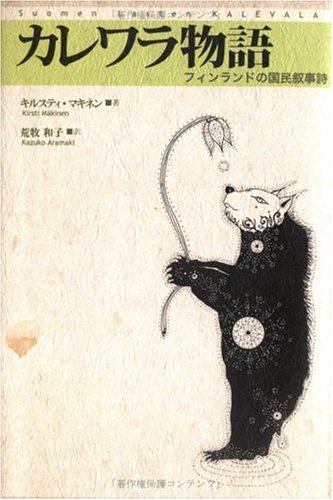
休業中、何冊かの本を読んだ。この 『カレワラ物語』は、フィンランドでベストセラーになったキルスティ・マキネン著『フィンランドのこどもたちのための「カレワラ」』の邦訳である。さぞかし暇にしていることだろうと、みほこさんが送ってくださった。キートス!
ところで「カレワラ」とはなにか?というと、フィンランドの長編叙事詩で、19世紀にエリアス・レンロットが《再発見》したことで当時帝政ロシアの占領下にあったフィンランドの民族運動に火がつき、結果「独立」へとつながったという、フィンランドを知るうえではとてもとても重要なものである。まあ、日本でいえば『古事記』みたいなものだろうか。けれども、「民族叙事詩」というスタイルからしてたいへんとっつきにくく、気にはなるけれどとてもじゃないが読もうとは思わない、そういう微妙なポジションにあるのもたしか。それはまたフィンランドでもおなじようで、「カレワラ」のおいしいところだけを上手につまんで、こどもにもわかるよう読みやすく編集をほどこしたのがこの本、『カレワラ物語』なのである。
じっさい読んでみての感想はというと、おもしろいし、なんといっても笑える。たとえるなら、「まんが日本昔話」をより猥雑にした感じだろうか。なんというか、登場人物のキャラクターが強力すぎる。ヴァイナモインネンは「英雄」というよりほとんど「エロじじい」だし、「ポホヨラの娘」の母ロウヒをはじめ、母親はみんなじぶんの娘をダシにして私腹を肥やさんとたくらむ「強欲ばばあ」である。レンミンカイネンにいたっては、誰かに似てると思ったら「少女監禁事件」の小林容疑者だった・・・と、まあこんな調子である。なんて書いたらみほこさんに叱れそうだなぁ・・・ごめんなさい、こんな通俗的な読み方しかできなくって・・・。
で、思ったのだが、そもそも「カレワラ」というのはこういうひどく土着的で猥雑なエネルギーに満ちたものなのではないかということだ。冬の間つめたい雪に閉ざされて暮らす極北のひとびとの豊かな想像力によって、長い時間をかけて醸成されてきた《ワタシたちの物語》。それは、文字によって書き記す必要なんてない。なぜなら、つねに書き換えられたり、書き加えられたりすることで変容し成長しつづける《物語》だからであり、その「書き手」は共同体に属するすべてのひとなのである。極論するなら、レンロットがこの《物語》を採集し「カレワラ」としてまとめたことで、それは広くひとびとの知ることになったわけだが、同時にその豊かな広がりをもつ《物語》は死んでしまった、ともいえるかもしれない。
この『カレワラ物語』は、笑いも悲しみも、怒りも喜びも、そしてエロも内包するそんな《ワタシたちの物語》のグルーヴのようなものをとてもいきいきと伝えてくれる本である。テレビもラジオもインターネットもなかった時代、この極北の地に暮らすひとびとの心性が産み落とした《物語》に人間のたくましい生命の営みをみる思いだ。
きょうというひ
2006.1.18|book
年末に、お客様のMさんが一冊の本を送ってくださった。荒井良二さんの絵本『きょうというひ』である。
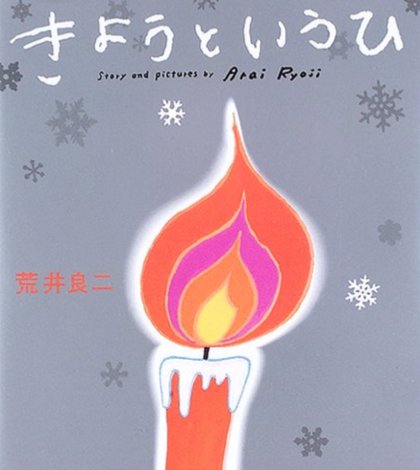
この絵本のことはしらなかったが、著者である荒井良二というひとが2005年の「アストリッド・リンドグレン記念文学賞」を受賞したということはニュースで聞き、しっていたし、それゆえ興味も抱いていた。そして、はじめてこの絵本をひらいてみたとき、不思議とある画家のことを思い出した。松本竣介である。
松本竣介の絵と、この『きょうというひ』での荒井良二の絵とを結びつけるもの-それは、どちらも無音の世界が描かれているということではないだろうか。13歳のとき病気により聴力を失った竣介が描く絵は、前に立つたびその無音の世界にひきこまれそうになる不思議な引力をもった絵画だ。かれはたぶん、音のない世界を生き、そこで絵を描いているのである。それに対して、荒井良二というひとはこの絵本で、音を必要としない世界を描きたかったのではないか。うまく言えないけれど。音を必要としない世界とはつまり、いのりの世界である。静かに目をとじて、ゆっくりと手をあわせる。もっとも自然で、もっとも敬けんな「いのり」にあって、「音」は無用だ。その「いのり」がピュアであることを守るため、消しゴムで「音」を消しとっていったのがこの『きょうというひ』なのではないだろうか。
きょうというひの ちいさな いのりが
きえないように、きえないように...
きょうというひが音もなく降りつもってゆく。
北欧デザインを知る
2006.1.23|book

ひどい頭痛で一日ふせっていたので、ネタがない。そこで、いま読んでいる北欧関連の本を紹介してお茶を濁しておこう。雑誌などで、北欧デザインにかんするコラムを精力的に発表されているライター渡部千春さんの新著『北欧デザインを知る~ムーミンとモダニズム』(NHK生活人新書)である。
ところで現在の「北欧ブーム」というのは、じつはかなりの程度「北欧デザイン・ブーム」なのであって、それも巷の「かわいい雑貨・インテリアブーム」とリンクしているというのは一目瞭然である。そしてそれがもうちょっと深化すると、「ていねいに暮らす」といったポスト「清貧の時代」的なスローガンにまで「昇華」(?!)されることになるのだが、まあ、それはそれとして、こうした背景をもった現在の「北欧ブーム」が紹介されるとき、その紹介のされ方がヴィジュアル中心になってしまうのはいたしかたないとはいえ、どうしても「浅い感じ」がしてしまうのはちょっと残念なことである。
「北欧デザイン」について語ることは、それらが生まれた《背景》について語ることである。渡部さんはこの本で、「新書」という制約のなかで最大限、その「軸」がブレないことに細心の注意を払っているように感じる。もうひとつ、この本からは「日本人」である筆者の「北欧デザイン」(つまり、それらを生んだ「背景」)に対する驚きや感動、リスペクトといった感情が、とてもフレッシュに伝わってくる。だから、「北欧デザイン」に愛着を抱いているひとにとっては安心して読めるし、また共感もできるのだ。
この本は、ヴィジュアル中心の「北欧ブーム」にはなんとなく飽きたというひとにこそうってつけの一冊だと思う。
『アンティの本』ただいま品切れ中です
2006.4.25|book
『アンティ・ヌルメスニエミについての小さな本』。この本のたのしさについては、以前こちらのブログでもご紹介した通り。よって、もっともっとたくさんの方々に手にしてもらいたいところなのですが、現在品切れにつき増刷中となっております。
なお、次回納品は5月なかばの予定です。たいへんご迷惑をおかけいたしますが、どうぞいましばらくお待ち下さい。
去年ルノアールで
2006.5.3|book
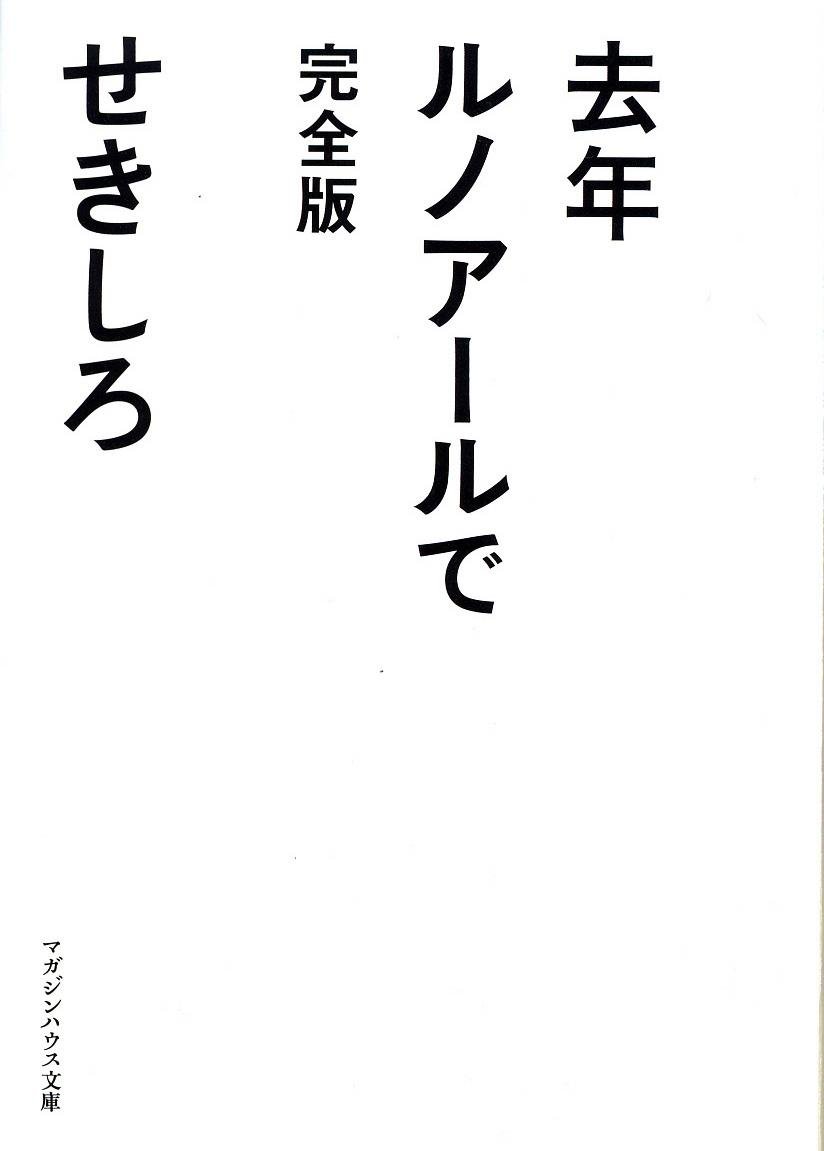
カフェが舞台になっていたり、コーヒーがさかんに登場するような小説やエッセイがあれば、職業病かたんなる趣味の世界かはともかく、つい手にとってしまう。寺田寅彦『珈琲哲學序説』、ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』、それに獅子文六『可否道』などなど。そしていま読んでいるのは、「せきしろ」のエッセイ『去年ルノアールで』。
著者が日々通いつめる喫茶室「ルノアール」で、ある意味「出会うべくして出会ってしまった」出来事や人々について綴った異色の《喫茶エッセイ》である。かりに(まさかそんなひとは存在しないとは思うが)いまだかつて「ルノアール」に入ったことがないというひとにとっては、この本はある種の「SF」と映るかもしれない。けれども、一度でもあのねじれた時空の中に身を置いたことのあるひとにとっては「なるほど」な、さもありなんワールドが繰り広げられている。
そういえば、この本を読んでいて思い出したのだが、かつてサラリーマンをやっていた頃、いちど職場の先輩とミーティングのために「ルノアール」に入ったことがあった。おもいっきりルノアール初心者であったぼくらは、うかつにもソファー席に陣取ってしまったうえ、そのふかふかすぎるソファーに身を委ねてしまったのだ。結局、ソファーに深く深く身を沈めたぼくらは、至近距離で向かいあっているにもかかわらず最後まで視線を合わすことなく、ひたすら斜め45度の天井をみつめたままミーティングを続けた。そしてそれは、おそらくぼくが体験したもっとも不毛なミーティングといえた。
そんな記憶の奥底に沈殿した「わたしとルノアール」を眠りから呼び覚まし、思わずひとに語らせてしまうこの本は、なんというかある種の《パンドラの箱》なのかもしれない。
ボサノヴァ読本
2006.5.16|book
いま、ちょっと大きなCDショップに足をはこぶと、こんなフリーペーパーを手にすることができます。
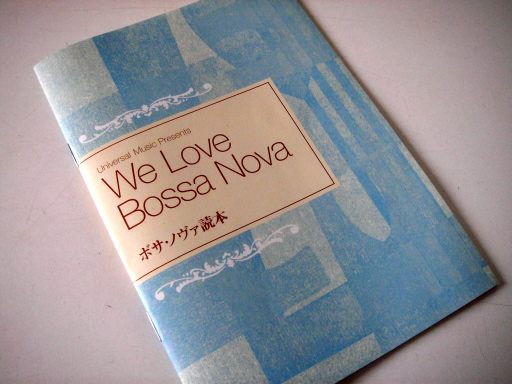
『We Love Bossa Nova~ボサノヴァ読本』です。ボサノヴァの名盤を完全限定&1,500円で発売するユニヴァーサルミュージック「BOSSA NOVA 1500」シリーズの宣伝用アイテムのひとつなのですが、これがなかなかおすすめなのです。
このフリーペーパーでは、CD紹介にくわえて「ボサノヴァって?」「ジョアン・ジルベルトの恋人達」「イパネマの娘」という3つのちいさなコラムがおさめられています。テキストを担当するのは、『ボサノヴァ』の著者としてもおなじみ、bar bossa/bossa recordsの林 伸次さん。
さて、ボサノヴァを聴く、ってどういうことなのでしょう?
それはもしかしたら、「ボサノヴァ」という音楽を生んだ《時代の空気》のようなものを感じることなのかもしれません。林さんのコラムを読んで、ふとそんな気になりました。 1950年代末のリオデジャネイロ。海、太陽、恋愛、ともだちとの語らい、お酒、コーヒー、ジャズそして声とギターに縁どられた儚くも幸福な時間・・・じぶんの現実の生活とはあまりにも遠くかけ離れた世界ではあるけれど、ほんのわずかでもそこに「共通の匂い」を見いだしたとき、ボサノヴァはじぶんにとってかけがえのないものになるのです。
今回リリースされるCDはどれもまちがいなく、数あるボサノヴァのCDのなかでも「名盤」とされるものばかり。これからボサノヴァを聴いてみようというひとにはまさにうってつけのシリーズだと思います。まずはこの『ボサノヴァ読本』を道先案内人に、じぶんだけの宝探しに出るというのはいかがでしょう。
アームチェアトラベラー
2006.6.16|book
地図帳はたのしい。
学校の教材としてお世話になって以来、すっかりその存在すら忘れていた「地図帳」をテレビのかたわらに置くようになったのは、塾のセンセイをなさっている常連のお客様のすすめがあったからにほかならない。たとえばテレビのニュースなどでどこか「地名」がでてきたとき、かたわらの地図帳をめくってその場所をたしかめてみる。するとテレビの映像とあいまって、その「見知らぬ土地」がなぜだかぐっと身近な場所に感じられてくるのだ。ときには無性に旅心をかきたてられ、あてのない旅の計画など夢想してみたり。
たとえば、いまだったら「ワールドカップ」。先日、韓国と戦って惜しくも敗れた「トーゴ」、生まれてはじめて耳にする国名である。さっそく、「トーゴってどこよ?」と思いながら地図帳をめくる。その国はアフリカにあった。ちいさな、ちいさな国である。550万人ほどの人口はほぼフィンランドと同じだが、面積はというとフィンランドの1/7程度。あふれかえる人波が、かれらのドリブルの技術を高めたのだろうか?
きのうはきのうで、エクアドルとコスタリカとのゲームがあった。エクアドルもコスタリカも、どちらもコーヒーの原産地としておなじみである。コスタリカは中米、エクアドルは南米、赤道直下の国。中米も南米も、日本からすれば遠いことに変わりはなく思わず混同しそうになる。だが、中米と南米では「コーヒー」だって味がちがう。フィールドを駆け回る選手たちの姿も微妙に異なっていて当然だ。
地図帳にはまた、思いがけぬすてきな発見もある。オセアニアあたりの地図をながめているときだった。発見したのは、こんな名前の場所。エロマンガ島。どんな「島」なんだ、いったい。オランダにあるという「スケベニンゲン」とならんで、ぼくがもし「中学生」だったなら、ネタにしたい、クラスの「人気者」になりたい、ただそれだけのために「夏休みに行きたい場所ベスト1」である。中学生でないのがかえすがえすも残念だ。ただし二学期からのアダ名は、「スケベ人間」もしくは「エロマンガ」になることまちがいなし、だが。
こんな調子で、日々アームチェアトラベラーの《旅》はとまらない。ぜひ一家に一冊、地図帳を!
AKU ANKKA
2006.6.22|book
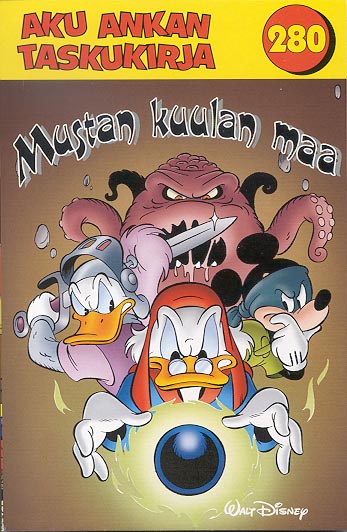
タイトルのAKU ANKKAって、なによ?と思われたひともきっといることでしょう。答えは、そうディズニーのキャラクター「ドナルドダック」。ちなみに「Ankka」は「アヒル」。「Aku」は・・・名前。たぶん。で、なぜかフィンランドでは、この「AKU ANKKA」が「MIKKI HIIRI」こと「ミッキーマウス」をおさえて断トツの人気なのだとか。このあたり、日本人の「かわいい」という感覚とはちょっとちがうのでしょうか・・・
ところで、その「AKU ANKKA」のコミック(もちろんフィンランド語バージョン)を"黒い例のたべもの"でおなじみのJUSSIさんよりご提供いただきました。ご興味のある方はぜひmoiでごらんください!
郊外へ
2006.6.26|book
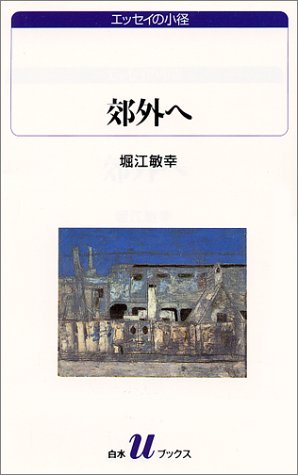
鍼の行き帰りによく利用するのは西武国分寺線という電車。中央線の「国分寺」と西武新宿線の「東村山」とをむすぶ全長8km足らず、所要時間にしてわずか10分あまりの路線である。
中央線の車窓からの眺めがほとんど、きゅうくつそうに立ち並ぶ一戸建て、アパート、マンションばかりなのにたいして、西武国分寺線では、家々にまじっていかにも武蔵野を縦断するこの路線らしいのどかな風景-雑木林や畑など-がひろがる。停車する駅も「恋ヶ窪」「鷹の台」「小川」と、ふらりと途中下車したい誘惑にかられるような「土の匂い」のする名前だ。それにくらべると、荻窪-西荻窪、東小金井-武蔵小金井、国分寺-西国分寺といった中央線の駅名は、いかにも旧「国鉄」らしい「事務的な匂い」を感じずにはいられない。
あいにくの雨模様の月曜日、まもなく終点の「国分寺」に着くというそのとき、突然、目の前の景色が一面の「緑色」に変わる。わずか数秒にもかかわらず、それは、あたかも電車ごと深い森に迷いこんでしまったかのような奇妙な感覚であった。たっぷりと水分をふくみ、より色鮮やかにボリュームを増したかのようにさえみえる樹々の緑は、なにか巨大な獣の横腹のようでもあり、「怖い」、わけもわからずそんな言葉が脳裏をよぎるのだった。
「郊外」へおもむくということは、「中心」から「周縁」へと移動するというただそのことを指し示すのみならず、そのことがもたらす「日常」の異化作用という体験そのことであるかもしれない。
※『雪沼とその周辺』の著者である堀江敏幸が、パリ郊外をめぐってつづった刺激的なエッセイへの、これは「なんちゃってオマージュ」です。
ヘルシンキの空の下
2006.6.27|finland
ちかごろのお気に入りは、フォトグラファーエエヴァ&シモ・リスタが撮影したヘルシンキの膨大なフォト・アーカイヴ《ヘルシンキの空の下》。
1969年から87年にかけてヘルシンキの中心部やダウンタウンなどで、ときにアジェのように、ときにアーウィットのように写し撮られた、いわば《素顔のヘルシンキ》。ここにあるのは、まさに写真集をめくるような愉しみ。
『さっぽろ喫茶店グラフィティー』を読む
2006.7.2|book

札幌にはいい喫茶店が多いらしいーなにかの折に、ふと耳にするそんな台詞。『さっぽろ喫茶店グラフィティー』という本を読んでいたら、またそんな言葉を思い出した。
この本に登場する「喫茶店」はざっと50軒あまり。そのほとんどは札幌で青春時代をすごし、タウン誌の編集長もつとめた著者にとって思い入れのある、70年代から80年代にかけて札幌のまちを彩った喫茶店である。
読んでいてまず驚かされるのは、どの喫茶店もたいへんユニークで個性にあふれていること。それが「札幌」という場所のせいなのか、時代のせいなのか、はたまたその両方なのか、判然とはしない。ただ、いま自分が生きている時代、場所について、ひとはふつう俯瞰する眼を持ち合わせてはいないものだ。案外、こうして時を経て整理し直すことではじめて明らかになることなのかもしれない。
そしてもうひとつ、多くの店のオーナーが、コーヒーの味についてひとかたならぬ「こだわり」を持っていること。しかも時代は「喫茶店」という業態の全盛期、一日15回転(!!!)などというほとんど「天文学的数字」のような狂騒の中でなお、けっしてその「軸」だけはブレていないのはまさに札幌の「喫茶人」の気概であると同時に、よい店を育てる札幌のひとびとの質の高さといえるかもしれない。
余談だが、個人的に気に入ったのは「act:(アクト)」という名のジャズ喫茶。オープンは1970年、内装はなんと内田繁。そのむかし、ぼくが夢想した架空のジャズカフェのイメージにあまりにもぴったりなのだ!スゴイ!行ってみたかった。
『安南の王子』を読む
2006.7.16|book
ひょんなことから山川方夫の小説『安南の王子』を読む。
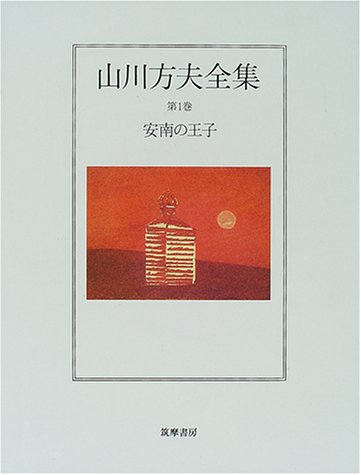
ピンとこない。二回読んでピンとこなかったので、三回読んでみたもののやはりピンとはこなかった。現実と幻想とがいつしかオーバーラップしてゆくお話。こういう小説はやっぱり、そこに描かれる世界に《酔えない》ことには楽しめないのだということがよくわかった。良し悪しの問題ではなく、たんに《酔えなかった》、それがすべてである。たとえば、嶽本野ばらとかすきなひとだったら《酔える》世界ではないだろうか。あるいは、50年代の「東京」のアンダーグラウンドをおしゃれに描いているという意味で、鈴木清順の『殺しの烙印』だとか中平康の『月曜日のユカ』だとかのような趣きもあるかもしれない。
ストーリーには酔えなくとも、この『安南の王子』には短くて、しかもキャッチーなフレーズがところどころにあらわれる。
「馬鹿が結局いちばん気楽なことを、この賢明な馬鹿どもは知っていたのだ。」
「つまり、かれは一日ずつしか生きなかった。」
いまだったら、さしずめコピーライターとしてその才能をいかんなく発揮するようなひとだろう。などと思ったら、後に『洋酒天国』の編集にもかかわっていたそうだ。納得。
ちなみに、いま手に入る集英社文庫版の表紙はイラストが荒井良二、アートディレクションが菊池信義でこの「お伽噺」にふさわしいつくり。夏休みの小旅行に。
『安南の王子』山川 方夫(集英社)
みほこさんの本棚から
2006.8.9|book
本日より、フィンランド語の翻訳/通訳をはじめフィンランド文化の紹介でおなじみのしらねみほこさん所蔵の書籍、雑誌、CDなどを一部店内にて展示販売しています。
題して、
「みほこさんの本棚から~泣く泣く処分市」

文学、政治、語学、デザイン、絵本など硬軟とりまぜおよそ50点ほどが出品されています。なかには、こってこてのスオミ・ロック(笑)のCDも(イスケルマではございませんので、念のため)。プライスは、定価の約1/2~1/3くらいとたいへんお買い得!もちろん、早いもの勝ち&売り切れ次第終了となりますので、moiにお越しのおりにはぜひチェックしてみてください!
カフェの扉を開ける100の理由
2006.8.16|book

インターネットで『東京カフェマニア』を主宰されているサマンサさんこと川口葉子さんの新刊『カフェの扉を開ける100の理由』(情報センター出版局)が出版されました。
旅先や散歩の途中で出会った数々のカフェとその印象が、静かな落ち着いた語り口でつづられたすてきなエッセイ集です。
じつは、ここmoiも【話せば長くなりそうな場所をめぐる散歩】という章のなかで取り上げていただいています。おなじ章では、ほかにふたつのカフェが紹介されています。
ひとつは、神宮前にある「J-Cook」。そしてもうひとつは、かつて表参道にあった「Posset Pot」です。
「キラー通り」からすこし入った路地にたたずむ「J-Cook」は、いつも変わらずにそこにあることのすばらしさを教えてくれるカフェです。その証拠に、このお店は近所に事務所をかまえフリーで仕事をしているひとびとたちから絶大な支持を受けています。じつはそのむかし、ぼくをここに連れていってくれたのもそんなひとりだったのですが、なんとその知人と川口さんにここを紹介した人とが同一人物であることがこの本を読んで判明(笑)。ふしぎな縁を感じます。
もうひとつの「Posset Pot」については残念ながらぼくは記憶にないのですが、その名前だけは数人の友人たちの口から聞き知っていました。それだけきっと、ひとの記憶に静かな余韻を残すようなカフェだったのでしょう。
そんなふたつの《名店》とともにmoiが紹介されているなんて、なんだか場違いな感じがして気恥ずかしいったらないのですが、よく恥をかいてこそ人は成長するなどともいいますので恥を忍んでページの上に居座ろうかと思います。
ロアルド・ダールの『少年』を読んだら、
2006.8.27|book

夏休みといえば宿題。宿題、といえば読書感想文。というわけで、映画『チャーリーとチョコレート工場』の原作者でもある、作家ロアルド・ダールの『少年』を読んだ。
この『少年』という本はけっして「自伝ではない」、そうダールは言う。ではなにかというと、それは六歳から二十歳にかけて彼の身に実際におきた「数多くの事件」-なかには「滑稽な出来事もあれば苦痛にみちた出来事もある。思い出すに不愉快なこともある」-を綴ったエピソード集といった体裁をとっている。
ダールの言葉どおり、ページを開くとそこには大胆で機知に富み、それでいて人一倍ナイーヴな「少年」の記憶が顔をのぞかせる。両親の祖国ノルウェーで過ごす、家族そろっての極上の夏休み。友人や兄弟と仕掛けた「いたずら」の数々。なかには、「靴紐の形をした甘草入りのアメ(リコリス・ブートレース)」の思い出も・・・
でも、この本でいちばん多いのは学校生活の話題、とりわけ不可解で窮屈な校則や、教師や上級生からうける理不尽な仕打ちに対する「怒り」にかんするものだ。そして、読み進むにつれこちらまで熱くなってしまった。というのも、じぶんの「高校生活」にもすくなからず似たような状況があったからにほかならない。
ぼくが通っていたのは都内にある私立の男子校で、「進学校とはいえない程度の」進学校だった。そこでは体罰は日常茶飯事。見上げるような高い塀に囲まれ、すべての窓という窓には金網がつけられた校舎は、まさに陰気な監獄そのものといえた。そして校内を仕切っているのは、柔道部や剣道部の顧問をつとめる数人の「生活指導」の教師たちで、竹刀片手に廊下をガニマタで闊歩するのが連中の日課だった。
とりわけ、いま思い出しても凄かったのは「始業時間」の光景だ。始業時間になると、校門のかたわらに立つ顔色のわるいフランケンシュタインのような守衛がボタンを押す。すると、天井から鉄製の自動ドアが降りてきて校門をシャットアウトするという仕掛けだ。当然、遅刻を免れようと生徒はみなその「けっして止まらない」自動ドアの下をくぐり抜けることになる。これが毎朝「儀式」のように繰り広げられていたのだから、よく事故が起こらなかったものだと思う。ほかにも、校則で禁じられていた「パーマ」がみつかり、そのまま近所の床屋に連れていかれ丸坊主にされたクラスメートもいた。
ロアルド・ダールは書いている。「みなさんはなぜわたしが学校における体罰をかくも強調して書くのかと不思議に思われるに違いない。その答えは、要するに書かずにいられないからである」と。そして「わたしにはそのこと(教師や上級生ががほかの生徒たちを傷つけるという事実)がどうしても納得できなかった。いまだに納得していない」とも。ぼくもまた、「納得」できずにいる。
そんな高校生活でのぼくの「たのしみ」はといえば、いかにスマートに校則を破るかであった。髪型や制服や持ち物、放課後の過ごし方などなど、周到な準備をもって「校則を破る」ことに快感をおぼえていたのだ。おかげで、全身「校則違反だらけ」にもかかわらず、高校生活を通じていちども「敵」に捕まったことはなかった。「夜の校舎 窓ガラス壊してまわった」なんて「敵」を喜ばすだけでなんの「反抗」にもなっていない、そう考えていた。出し抜いてなんぼ、そんなことばかり考えている皮肉で屈折して暗い高校生だったのだ。
唯一残念なのは、ぼくに「文才」が足りなかったこと。もしあったなら、きっといまごろロアルト・ダール顔負けのシニカルな小説をたくさん書いていたことだろうに。
散歩者と景観
2006.9.5|book
「郊外の美の悦楽は、慎重に、あたかも『煎じたように』消化され、散歩者自身が長い時間をかけて見出すものなのである」。(エッセイ「給水塔へ」から)
高速道路の高架付近や崩れかけた工場跡、丘の中腹を走る高圧線の鉄塔の下に小さな家々が「埋もれるようにたっている」パリ郊外の《魅力的》な眺めについて、堀江敏幸はそう述べる。「パリ郊外」についてはなにも知らなくとも、《散歩者のまなざし》をもって「都市計画における美醜の明確な区別」とはまったく次元を異にする「郊外の美」の存在を説くかれの意見にはまったく同感である。
個人的には、都市計画における「ランドスケープ」という概念には、なにやら胡散臭さをかんじずにはいられない。それは、人間が、人間の価値判断にもとづいて自然をコントロールしようとすることへの違和感といってもいい。自然を壊すことでおこなわれる「都市計画」が、同時に「ランドスケープ」という名前のもと自然を作り出そうとするのもおかしな話である。
けれども、おなじ「景観」について語っていても、じつは「都市計画」におけるそれと「郊外」におけるそれとではそのありようがまったく異なるのだと、堀江敏幸はそう言っているのである(たぶん)。都市計画においては、「景観」とは「発見させる」ものである。それに対して「郊外」にあっては、「景観」はそれに触れるひとが時間をかけて、つまり《散歩者のまなざし》をもって「発見する」ものにほかならない。
「人間の直裁なドラマではなく、湿った石塀や草いきれのする丘、泥濘のつづく小道にひそむ人間の息づかいを捜し求めるささやかな旅」。
「ひなびた独特の雰囲気」を醸しだす郊外に「美」を見出す《散歩者》にとって、「景観」とはじっさいにはそのひとのなかにあるもの、なのかもしれない。
東京タワーへ
2006.9.25|book


思いがけずよいお天気だったので、所沢に鍼をしにいったあと「東京タワー」へと向かった。リリー・フランキーの影響(江國香織の、でもない)ではなく、いま読んでいる中沢新一の『アースダイバー』に刺激されたのだ。
内容の真偽ではなく、この本に書かれたことにぼくは「リアリティー」を感じる。「東京」のそこかしこについて子供のころから茫漠と抱いてきた「感覚」、あるいは「直感」のようなものが、読み進むうちにするするとほどけて霧が晴れてゆくような気分を味わっている。

タモリ×糸井重里×中沢新一による対談「ほぼ日刊イトイ新聞-はじめての中沢新一。」も面白そう(まだ読んでいないけれど)。
国際こども図書館に行く
2006.10.9|book
4つの「目的」をはたすため(?!)上野にある「国際こども図書館」にいってきた。

目的その1/「北欧からのおくりもの~子どもの本のあゆみ」 いま開催中の、北欧各国の絵本、児童書をあつめた展示「北欧からのおくりもの~子どもの本のあゆみ」を観る。年代別の展示によって、北欧各国における絵本や児童書のあゆみが俯瞰できるというのがポイント。デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、そしてフィンランド(アイスランドやラップランドのものあり)と地理的にはとてもちかいにもかかわらず、絵のテイストが国によってすこしずつちがっているのがおもしろいところ。それぞれの国の、こどもの「嗜好のちがい」が投影されているということでしょうか?本によっては資料室で実物を手に取って読むことができるそう。
目的その2/「江戸絵本とジャポニズムコーナー」を体験する このブログにもちょくちょくご登場いただいているピアニストの新澤健一郎さん。現在フィンランド人のギタリスト&ドラマーとともに日本各地でのライブツアー中ですが、その新澤さんがこの「江戸絵本とジャポニズム」の音楽を担当されているのです。でも、いったいどこで体験できるのかよくわからず、けっきょく聴けずじまい・・・。この「図書館」、サイン表示がちょっとわかりづらいところがありますね。どこでどういうことが体験、学習できるのか、かんたんなリーフレットがあればいいのにと思いました。でも、くだんのコーナーはオフィシャルサイトの「絵本ギャラリー」でネットからも体験できるそうです。
目的その3/たてものを観る ここ「国際こども図書館」は、ちょうど100年前に建てられた建造物を修復・改修して使われています。そして、このリノヴェーションにたずさわったのが建築家の安藤忠雄。外観は一見したところほとんどそのままですが、ガラス箱のようなエントランスやガラス張りのバルコニーが新たに追加されているのが目立ったところでしょうか。建築についてくわしいことはわかりませんが、違和感なく気持ちよくすごせる空間でした。
目的その4/「まのいいりょうし」を読む いまとりかかっている「宿題」のため、こどものころ愛読していた「まのいいりょうし」というお話をもういちど読みたいのですが、残念ながらこのお話がはいっていたはずの平凡社『えほん百科』が手元にもうありません。調べたところ、ここの蔵書にその『えほん百科』があるということなのですが・・・ところが、あるべきはずのところにそれはなく、かといって誰かが閲覧している気配もない。というわけで、けっきょくのところ読めずじまいに終わったのでした。
初の「国際こども図書館」訪問は、打率5割でもちょっと不本意な結果・・・
京都 吉田屋料理店
2006.10.17|book

おいしい創作料理系おばんざいが食べれるということでつとに知られる京都の「吉田屋料理店」のレシピブック、『京都 吉田屋料理店』(吉田裕子著)を手に入れた。
料理本(とりわけレシピブック)というのは、たいがい二種類にわけることができるように思う。ひとつは、実用的で、そのままアレンジなしにすぐにでも使えてしまうもの。たとえば、雑誌「オレンジページ」などがその代表選手だろうか。そしてもうひとつは、けっして実用的ではないけれど、たくさんのヒントや刺激にあふれていて想像力をかきたてられるもの。有名なシェフやパティシエが著したものは、たいていこちらに属する。
この本は、どちらかといえば「後者」にあたる。あくまでもベースは家庭料理だけれども、京都ならではの食材やジビエなどもとりいれているのでそのままつくるのはなかなか難しい。けれども、技術的にものすごく込み入っているというわけではないし、エスニックやイタリアンなどをとりいれたアイデアも多く、食材を置き換えてみたり、もうひとひねりしてみたりとアレンジする楽しみを刺激してくれる。ササッと家でつくれそうな気軽なレシピからお酒のアテ、そしてデザートまで、個性的な「料理店」のレシピは想像力も豊かだ。
エルスケンの家
2006.12.9|book

土曜日の夜には、(首尾よく家にたどりつければの話だが)テレビで「美の巨人たち」をみることがおおい。先週は、エド・ヴァン・デル・エルスケンの写真集『セーヌ左岸の恋』がとりあげられていた。
ヒッチハイクで、ほとんど一文無しの状態でパリにたどりついたエルスケンが、どのようにしてあのよく知られる写真集をつくり上げるに至ったのか、その「メイキング・オブ~」的なストーリーも興味深くはあったのだが、それ以上に目が釘付けになってしまったのはほかでもない、番組のなかに登場した「エルスケンの家」。
母国オランダの「エダム」にあるその家は、いまもエルスケン夫人によって守られている。かれの写真からイメージしたのは都会的でモノクロームな空間だったのだが、意外なことに、じっさいの自宅兼アトリエは牧歌的な風景のなかにたたずむ古い農家(記憶では平屋だったような・・・)を改築した、どちらかといえば雑然とした空間だった。
天井や外壁の一部には、超特大サイズに引き伸ばされたエルスケン自身によるモノクロームのポートレートがパネルのように全面にはめこまれていて、キッチンやアトリエには原色系のポップな色合いの雑貨類が雑然と置かれている。けれども、それはまったくアンバランスではなく、むしろとてもあたたかな空気をかもしだしているようにみえた。つまり、その「家」はエルスケンそのひとの深い「人間愛」のような感情を表出しているようにみえたのだ。
素朴で、人間への愛が人一倍強い若者が、まさに異邦人として孤独と闘いながら大都会パリの片隅をさまよい、じぶんとよく似た境遇の若者たちを共感とともに写しとったのこそが、この『セーヌ左岸の恋』ではなかったか。「エルスケンの家」を見たことで、ぼくにはこの写真集がかれの(その意味で)セルフ・ポートレートであるような気がしてならないのだ。
再入荷です
2007.1.17|book

お待たせしました。『アンティ・ヌルメスニエミについての小さな本』が再入荷しました。
今回入荷したのは、ブルー、イエロー、ブラウンというmoiで売れ筋の三色です。お早めにどうぞ。
ところで、先日この本の著者である原宿の雑貨店CINQさんにお邪魔したときに伺った話なのですが、この本をフィンランドのアカデミア書店で扱うことが決定したそうです。わからない方のために説明すると、「アカデミア書店」はフィンランドで最大手の書店で、ヘルシンキの本店は建築家アルヴァー・アールトが設計したビルにあります。ちなみに、映画「かもめ食堂」で小林聡美が片桐はいりに「ガッチャマンの歌」を教えてもらっているシーンは、その「アカデミア書店」のカフェで撮影されています。
なんでも、アンティ・ヌルメスニエミの奥様で著名なデザイナーであるヴオッコさんがたいへんこの本のことを気に入り、いっしょに「アカデミア書店」まで出向いて話をつけてくださったそうです。余談ですが、この夏ヘルシンキの「デザインムセオ」で開催される目玉展示はそのヴオッコ・ヌルメスニエミさんの回顧展。この時期、旅行を計画されている方は要チェックですよ!
旅にもってゆく本
2007.7.9|travel
旅のたのしみのひとつに、旅に携えてゆく本を選ぶというたのしみがある。結局ほとんど読まないままに帰ってきてしまうことが多いとなると、やはり「選ぶ」という行いのうちにたのしみを見い出しているといったほうが正しそうだ。
今回携えていったのは二冊。まずは、星新一『ほら男爵現代の冒険』。

はじめて出雲・松江にいった小学生の夏、もっていった本だ。そのころクラスの「学級文庫」では星新一の本が大人気で、たぶんそんなこともあって持っていったのだと思う。行きの寝台列車(ブルートレイン)で読むつもりだったのだが、はじめて乗る寝台列車がうれしくそれどころではなかった。
深夜まで、うれしくて列車の中を行ったり来たりくりかえしているうち「ちょっと、ぼく?」、車掌さんに呼びとめられた。
「鼻血出てるよ」
興奮のあまり鼻血を出していたのだった。「ちょっと待ってて」と言うと、車掌さんはトイレットペーパーをぐるぐると腕に巻きつけもどってきた。「ほら、これをつめときなさい」と手渡され鼻にトイレットペーパーをつめて眠ったので、けっきょく本は読まなかった。というわけで、ある意味リベンジである。
大人になって読む星新一は、あらためて面白い。軽快な文体とスパイスのようにぴりっとくるシニカルな表現、それに「近未来」への洞察の深さ……子供のころに全部読んじゃったというひと、あらためてこの夏読み直してみてはどうだろう。
もう一冊は、岡倉天心『新訳・茶の本』。

出発前、ちょうどこの本をめぐってとても刺激的な企画を進行中のKサンからメールをいただいた。じつはずいぶん前のこと、この本を読もうと思い立って岩波文庫版を手に入れたのだが、そのあまりにも格調の高い訳文に圧倒されあっという間に逃げ出したのだった。けれどこれもなにかの偶然、せっかく「『茶の湯』の都市」に出かけるのだしもういちど挑戦してみるか、と気をとりなおした。調べてみるとこの『茶の本』、いろいろな翻訳者による版が存在している。
大久保喬樹氏によるこの訳文はとてもこなれていて読みやすいうえ、各章につけられた解説も親切だ。日本人とはいえ「茶道」についての知識なんてまったく持ち合わせていず、しかも日本的な美意識からもほど遠い生活をしているのだから、ある意味ぼくも「外国人」みたいなものである。あらためて感心することや驚かされることもすくなくない。なかにはなんとなく納得したり、また理解できたりすることもあり、「ああ、やっぱり日本人なんだなぁ」とあらためて感じてみたり……。
「不可能を宿命とする人生のただ中にあって、それでもなにかしら可能なものをなし遂げようとする心やさしい試みが茶道なのである」
なんて、わかったようなわからないような、でもちょっとぐっとくる一文ではある。ストーリーよりもむしろ、ちょっとした一文の印象のほうが強烈に記憶に残る、これはもしかしたら本を旅先で読んだときならではの特徴といえるかもしれない。
もうひとつのガイドブック
2007.7.14|book

ガイドブックというとふつう、旅に出る前にひらくものと相場がきまっている。事前に目的地の情報を仕入れたり、ときには旅の目的そのものをみつけるためひらくことだってある。まさに道しるべ、である。
その一方で、旅に行ってきたひとのためのガイドブックといえるものもある。旅のなかで出会った風景、音や匂いなど五感を介して刻みこまれた記憶が、その土地の印象や理解をぐっと深めてくれる。たとえば、松江、それに出雲を旅してきたひとにぜひ手にとってほしいのは、ラフカディオ・ハーン『新編・日本の面影』である。
これは、日本での日々やその印象をつづったラフカディオ・ハーンの代表作『知られぬ日本の面影』に収められたエッセイを厳選し新たにまとめ直したもので、池田雅之氏の訳文もこなれていてとても親しみやすい。さいしょ手に入れたときは完読できないかななどと思っていたのだけれど、気づけばあっという間に読み終えてしまっていたほど。
五感が研ぎすまされるという感覚は海外旅行にでかけたときなど、ぼくらもまた体験する感覚だが、このときのハーンはまさにそんな感じだったのだろう。あこがれの東洋の島国で見聞きするすべてが、全身が感度のいいアンテナのようになったかれの感覚をビンビンと刺戟しているさまが手にとるように伝わってくる。そしてその理解の深さと洞察の鋭さは、このエッセイをたんなる「見聞録」以上に価値のあるものにしている。読んでるこちらのほうが、「なるほどなぁ」とか「あ、そういうことだったんだ」とか感心さえられることしきりである。
それにもうひとつ、「音」に対する感性がすごい。橋を渡るひとびとの下駄の音、湖を行き来する船の音、虫や鳥の声にひとびとが打つ柏手の音……たぶん日本人であればあまりに「日常」すぎて気にもならないようなさまざまな「音」がここでは確実に拾われ、見事に描写されている。いくらここ日本の話とはいえ百年以上も前の遠いむかしの情景にもかかわらず、やけに生々しく感じられるのはきっと、こうした「音」がぼくらに伝えてくるライブ感のせいだろう。
すべての旅好きのひと、必読の一冊だと思う。
『坊っちゃん』を読む
2007.10.27|book
『坊っちゃん』を読んだ。
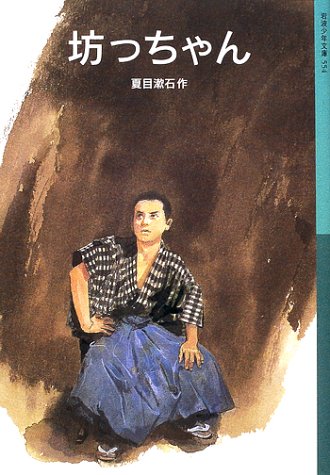
なぜ、いまさら『坊っちゃん』なのか?と問われれば、ただそこに『坊っちゃん』があったから、としか言いようがない。我が家の通称「ブックオフ行き」と呼ばれている紙袋(ただし、いまだかつてそれらが「ブックオフ送り」となった例はいちども、ない)のいちばん上で、カバーをかけられたまま放置されていた文庫本版の『坊っちゃん』をたまたま手にとってしまったのである。
だいたいここのところ、四六時中店のことをかんがえている。というか、店のことしかかんがえていない。で、かんがえているうちどんどん焦ってきて、やがて胃のあたりが痛みだす。そんなわけなので一日のうちに一時間でも二時間でも、映画を観るなり本を読むなり、なにか店のこと以外に意識をそらす時間を無理矢理にでもこしらえないと身がもたない、この先ちょっとヤバいんじゃないかと思ったのである。そう思い立って、とりあえず目についた本を手にとったところそれが『坊っちゃん』だったというわけだ。
あらためて読んだ『坊っちゃん』は、さすが『坊っちゃん』だけあっておもしろい。あっという間に読み終えてしまった。夏目漱石というひとは当時、コンサバというよりはむしろハイカラに属するひとだったと思うのだが、じっさい巷にあふれる「封建主義」のなごりを思いっきりくさしつつ、そのいっぽうでは「清(きよ)」のような「封建時代の遺物」みたいな人物に対し愛情に満ちたまなざしを注いでいる(なぜ名前が「清」なのか、納得した)。おそらく当時の日本の「近代化」は、ハイカラな漱石をもってしてもあまりに性急なものと映ったのだろう。続々と輸入される「ハイカラ」に魅了されながらも、流されてはならんと踏ん張っている、そういう「二律背反」にこの時代の「文化人」たちはみな生きていたのかもしれないし、逆にいえばそういうスタンスこそがこの時代の「文化人」がとるべき態度だったかもしれない。
それはともかく、いったいなぜ我が家に『坊っちゃん』があったのか?まあ、奥さんが買ったからにちがいないのだが。いまさら『坊っちゃん』など読む気になった理由(ワケ)を尋ねてみたい誘惑にかられなくもないが、やめておこう。どうせ「そこに『坊っちゃん』があったから」くらいな理由に決まっている。
カフェ東京
2007.10.28|book

ユンジョンのことは以前書いた。一年間のワーキングホリデーを終え韓国へと帰国したのは今年の一月のこと。東京での日々や人々との出会いがもたらした思い出を、大好きなカフェにからめつついずれ一冊の本にまとめてみたい、そう言い残しての帰国だった。その後、ほんとうに出版が実現しそうなこと、また本ができあがったら直接届けにいきたいことなど聞いてはいたのだが、きょう突然そのユンジョン本人ができあがった本を手に現れたのだからほんとうにビックリした。
じつは、きょう行くと何度かメールで知らせてくれていたらしいのだが、ここのところ携帯にいろいろな親切なメール ── 「バイアグラがとっても安い」というお買い得情報だったり、見知らぬ異性(ごくまれに同性)からの「つきあって欲しい」というモテモテメールだったり ── が日に三十件もやってくるものでさすがに煩わしくなり、「URLつきメールは受け付けない」という設定にしたのがいけなかったらしい。どうやら彼女のメールもサーバーの方で勝手に削除してしまっていたようなのだ。そんなわけで、狐につままれたような気分で記念すべきユンジョンの処女作を手にとった。
『カフェ東京』と題されたその本は、想像していたよりもはるかに立派な本(ぜんぶで二百三十ページあまり)である。ユンジョンが撮ったカラー写真もいい感じだし、イラストもかわいい。おまけにまるまる一章を割いてmoiのことが語れているのだから光栄な話だ。ただし、かえすがえすも残念なのは中身が「読めない」こと。韓国の本がすべてハングルで書かれているのは仕方ない(というか、あたりまえだ)が、なんだかすっごく歯がゆい感じである。

きっと、マスターの温かい人柄や優しい人柄、そして愛すべき人柄について書かれているにちがいない。まあ、そういうことにしておこう。ちなみに、関西エリアのカフェをテーマにした第二弾も予定しているとのこと。こちらも楽しみだ。
マイ・フェイヴァリット・シングス
2007.11.1|book
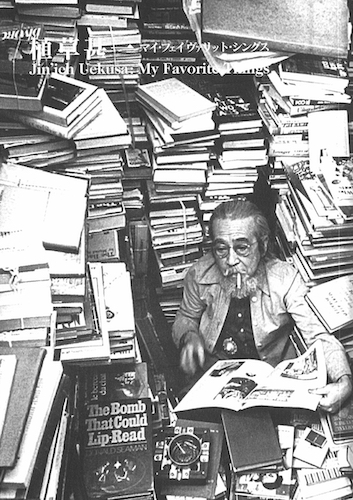
「植草甚一の展覧会やってますよ」という常連おくむらクンの言葉を思い出し、荻窪からバスにゆられて世田谷文学館まで行ってきた。
はじめて植草甚一のことを知ったのは、まだ高校に入りたてのころだった。愛読していた「LOO」というおかしな雑誌でとりあげられていたのだ。本の山に埋もれるようにしてこちらを見ている奇矯な風体の小柄な老人、その写真からはちょっとありえないような異様なオーラが放たれていた。ミステリーもジャズもシュールなイラストも、彼が語る興味の対象はどれも当時のぼくには縁遠いものだったけれど、それでも彼がものを語るときの語り口、その独特の文体には刺激を受けた。まるで喫茶店で友だちを前に世間話しているかのような口調で話がはじまったかと思うと、話題は突如なんの前触れもなく方向転換する。終わり方にしても唐突で、飽きてしまったので切り上げましたと言わんばかりだ。なんかいい加減な気もしなくはなかったが、かえって昔から集中力に乏しかったぼくにとっては好都合、さらっと読み進めたのである。
それからずっと今にいたるまで、折りにふれ「植草甚一」という人物と「出会って」きた気がする。それは本人であるときもあれば、彼から影響を受けた「子供」だったり「孫」だったりすることもあった。音楽にせよ映画にせよ美術にせよ文学にせよ、ちょっとカッコいいなあとか面白いなあと思わせるもので彼の「あしあと」が残されていないものはないんじゃないか、そんなふうにさえ感じられるのだった。
以前、はたらいていた場所で『ジャン・コクトー展』が開かれそれにあわせてトークイベントを企画したことがあるのだが、そのときイラストレーターの安西水丸さんがコクトーについてこんな印象を語っていたのがおもしろかった。もうずいぶん前でちょっと記憶もあやふやなのだが、だいだいこんな感じでまちがっていないと思う。つまり、なにかおもしろそうな匂いがして行ってみると、いつも必ず先回りしてそこにいるような気に障るヤツと。植草甚一というひとも、ある意味まあそんな「偉大なる目の上のタンコブ」なんじゃないだろうか?偉大な親をもった子供が伸び悩むように、七十年代以降、八十年代、九十年代と時は過ぎても、いまだある種のひとびとにとって「植草甚一」は乗り越えるべき存在でありつづけているし、結局のところ乗り越えられないまま「植草甚一のへたくそなコピー」に甘んじざるをえないジレンマに苦しんでいるような気がする。
展示されている原稿にほとんど書き損じがなく感心したり、意外にも蔵書をカード化してきっちり分類していたり、森村泰昌に先んじること四十年ちかく、すでに「モナ・リザ」に扮していたり(笑)と、いろいろ興味深い発見もあったのだが、そういった個々の印象よりも漠然といろいろなことを思い出したり考えさせられたりした展示だった。
◎ 展示「植草甚一 マイ・フェイヴァリット・シングス」は11/25[日]まで世田谷文学館にて開催中。
脇阪克二さんの展覧会図録
2008.5.31|book
脇阪克二 作品集を販売中

女子美アートミュージアムではいま、テキスタイルデザイナー脇阪克二さんの展覧会『北欧の夢 ニューヨークの洗練 日本の情緒』がひらかれています。
脇阪さんは一九六八年、二十四歳で単身フィンランドに渡りマリメッコ社のデザイナーとして仕事した後、ニューヨークのジャック・レノア・ラーセン社やワコールを舞台に活躍、現在は「SOU SOU」のテキスタイルデザイナーをされている方。moi店内のポストカードショップ「kortti」ではその脇阪さんのイラストによるポストカードを常時二十種以上とりそろえ販売しているので、あるいはそうとは知らずに手にされているお客様も多いかもしれません。
さて、moiでは今回の展示にあわせて制作された図録を販売しています。図録とはいえ、アートワーク的にも面白く、六十年代から現在に至る脇阪さんの仕事を一望の下見渡すことができる作品集的内容の濃い一冊となっています。とりわけ、脇阪さん自身による「まえがき」では、フィンランドで過ごした日々がいかに現在に至る脇阪さんの創作活動の「芯」を成してきたかが短い文章のなか控えめにつづられていて個人的に、ちょっとぐっときてしまいました。おすすめです。1,890円(税込)
第一阿呆列車
2008.8.11|book
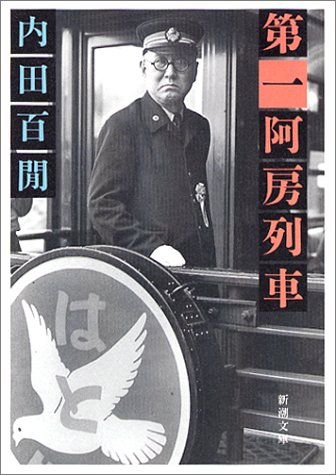
旅にもってゆく本については前にもいちど書いたことがあるけれど、読むたのしみもさることながら、来るべき旅についてあれやこれや思いめぐらしつつ選ぶことのたのしさのほうが、じつはむしろ勝っているのではないかと密かにかんがえている。
水戸にもっていったのは内田百閒のエッセイ『第一阿房列車』。
「用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」。なんの目的ももたず、とりたてて用意もせず、ただ列車にのってどこかへ行く、どうやらそれが内田百閒のいうところの「阿呆列車」であるらしい。まあ、今回のぼくだって、展覧会を観たりコンサートを聴いたりというのは「目的」というよりはむしろ東京をはなれるための言いわけみたいなものであって、そう思えばれっきとした「阿呆列車」にちがいない。
ところでその百閒先生、わざわざ「阿呆列車」のために借金までこしらえるのだが、その言い草がいかしている。いわく、「いちばんいけないのは、必要なお金を借りようとすること」である。それにくらべれば(阿呆列車のための借金は)「こちらが思いつめていないから、先方も気がらくで、何となく貸してくれる気がするであろう」云々。勝手な言い分だが、一事が万事この調子である。大阪へと出発するためやってきた東京駅の改札では、「何の為にどんな用件でこうまで混雑するのか解らないが、どうせ用事なんかないにきまっていると、にがにがしく思った」なんて言っている。いちばんのひま人はアンタだっつーの!
それにしても、なこの偏屈100%っぷり。小心者が、理屈をこねて自分を正当化しているこの感じにどこか見覚えがあると思ったら・・・なんだ、自分だった。というわけで、いまのうちからぼくも「ヒマラヤ山系」君のような絶妙な相方をさがしておかねば。
詩の話にはじまって
2008.8.19|book
こうるさい父さんのように、ひまな日にはいろいろとスタッフに質問攻めして煙たがられているのだが、このあいだもいろいろと質問攻めにしていたらスタッフのひとりが休みの日には「詩を読んだりしている」と言うのだった。
「へぇ~、どんな詩?」と聞き返すこうるさい父さんは、もちろん「詩」なんてぜんぜん知らないのである。高校時代なんとなくかっこよさそうというだけで、当時池袋の西武デパートの本屋の一角にあった「ぽえむ・ぱろうる」というちいさな詩の専門店でアレン・ギンズバーグの詩集を買ったはいいが、生きている世界のあまりの違いに挫折。それならば、とコクトーやアポリネールに挑戦するものの、物売りの口上のような堀口大學の七五調の訳文にまったく「パリのエスプリ」なんて感じられずこちらも玉砕。唯一、天野忠翁のユーモアと北園克衛は楽しめたが、北園克衛のは「詩」というよりもカルダーのモビールみたいな、「ことばによるオブジェ」といったほうがふさわしいので、やっぱりあまり「詩」は肌にあわないのだと思っている。それでも、ひょんなことからポエトリーリーディングのイベントやCDを制作したりしていたこともあるので、正直こころの片隅ではなんとなく気にかかっているのかもしれない。
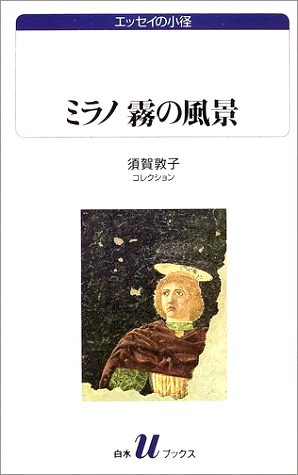
で、そのスタッフがよく読むのはウンベルト・サバの詩集だという。ウンベルト・サバ・・・、ウンベルト・サバ?名前だけはどこかで、しかもごく最近耳にした憶えがあるのだけれど・・・思い出せない。でも、あるとしたらやっぱりいま読んでいる須賀敦子の本の中でしかないだろう。そう思って、読みさしの本のページをもういちど最初からパラパラとめくってみるが見つからないのである。不思議だ。すると目次よりもさらに前、扉のところにウンベルト・サバの、須賀敦子自身によって訳された詩の一節の引用されているのを発見したのだった。
石と霧のあいだで、ぼくは休日を愉しむ。
というフレーズではじまる『ミラノ』という題名の詩だ。この詩をみたとき、エットーレ・スコラという監督が撮った『BAR(バール)に灯ともる頃』という映画のことを思い出した(舞台はミラノではないけれど)。夜霧のなかにぼんやりと光るオレンジ色のバールのあかりがすごく象徴的で、しみじみ心に残るよい映画だった。なんとなくあべこべだが、どうやらウンベルト・サバの詩集を翻訳し紹介したのが須賀敦子だったみたいだ。
ぼくはイタリアにはまったくと言ってよいほど関心がないので、いままで須賀敦子の本を手に取ったことがなかった。なぜ急に読むことにしたのかというと、毎日あまりにも暑いから、にほかならない。あんまりにも暑いと、CDでもつい音数がすくないものを選んでしまうのとおなじで、静かな文章が読みたかったのだ。
それだけの話。
美しき町
2008.10.15|book
クレタ人は嘘つきだ、とあるクレタ人が言った。
これは、学生のころ論理学の授業で教わった「自己言及のパラドックス」というヤツである。で、本当のところクレタ人は嘘つきなの?それともそうじゃないの?という話。で、なんでこんなことを思い出したかというと佐藤春夫の小説「美しき町」を読んだからである。

ボヘミアン気取りの貧乏画家のもとに、ある日「テオドル・ブレンタノ」という聞き慣れない名前の男から「或る不思議な、そうして最も愉快な企て」のために力を貸してほしいとの声がかかる。ほどなく、その男の正体はアメリカに帰化した旧友であることがわかるのだが、彼は父が遺した財産で隅田川の中州に「美しい町」を築きたいと言うのだった。そしてさらにもうひとり、老建築技師がその輪に加わり築地の高級ホテルの一室でくる日もくる日も「美しき町」を実現するための作業が着々と進められるのだ。そして三年の月日が経ち、いよいよ「美しき町」の実現ももうすぐ目の前というとき・・・。
以下、ネタバレあり。ま、誰でも途中で予測はつくと思うのであまり支障はないかもしれないけれど、一応。
読み終えて、物語に、もしも正しい答えというのがあるとしたら、ぼくにはこの小説の「正しい答え」がさっぱりわからないのだ。「私のおやじも山師であったが、山師の息子がまた山師なのだ」と告白することになる旧友の、だがどこまでが本当で、どこからが嘘なのか、その目線をどのあたりに据えるかによって、この物語の「答え」は大きく変わってくるように思われる。彼の言動をみれば、それが必ずしも「愉快犯」の行いでないことは察しがつく。本気でやろうと思っていたことが、ついスケールがデカくなりすぎて収拾がつかなくなったということもあるかもしれないし、金銭的な問題よりも、むしろ理想の協力者(共犯者?)を得たことで十分満足し、赤ん坊がオモチャに飽きるみたいにこの企てそのものへの興味がすっかり失せてしまったということだってないとも言い切れない。もちろんそこに書かれているままを信じて、じつはハナっからそんな大金なんてなかったのだ、と受け取ったってかまわない。ただ作者(佐藤春夫)が、親友の友人である画家E氏(=ボヘミアンの貧乏画家)による「証言」をまとめたというスタイルで書かれたこの小説では、そのあたりのことはなにも明かしてはくれない。むしろ幾重にもフィルターがかけられ、あえて核心に迫らせないかのように。
それでも、この「美しき町」の読後感はやけにさわやかだ。この物語の登場人物である画家のE氏、それに老建築技師と同じように。「美しき町」を読み、その町にすこしでも惹かれる部分を感じた者はみな、知らないうちに自分の心のなかに「美しき町」の存在を見るからなのかもしれない。
追記:そういえば先日話題にした画家の茂田井武は学生のころ、友人の家に下宿していた佐藤春夫の部屋にちょくちょく出入りしていたそうである。そして、そこで稲垣足穂に紹介されたりしたらしい。こういう、「わたがし」みたいに人が人を呼ぶ不思議な求心力はとても神秘的だ。
コーヒー雑学事典
2008.10.24|book

講談社から昭和六十一年(って何年だっけ?)にでた『The Book On Coffee コーヒー雑学事典』。タイトルどおり、コーヒーにかんするありとあらゆる小ネタが満載の一冊だ。とはいえ、全体に歯の浮くような調子はまさに八十年代のそれ。
たとえば、「いま、いちばん行きたいコーヒショップ」というコラム。「大学二年の菅原佳子サン」のご意見はこんな感じ。「はじめてのデートで、あそこに入ろうって、まるで決めてきたかのように指差したお店が、趣味の悪い店。彼とつきあっていく気がなくなった」。コワいですね~、八十年代の男子はコーヒーショップを選ぶのも命がけだったのですよ。というよりは、女子がなんにも主張しなくても男子がお膳立てを整えて「お姫様気分」(この「気分」っていうのがいちばん大切)にひたらせてあげるというのが八十年代的恋愛のツボだったわけで、それを巧みにゲーム化してみせたのが一連のホイチョイ・プロダクションの仕事だったのだ。そういう意味でゆくと、主張のはっきりした女子と従順な男子という組み合わせが目につく最近の若いカップルをみるかぎり、いまの女子のほうがはるかに、実際に、「お姫様」だと思う。
あ、本題から逸れた!
それはともかく、この本のすごさのひとつは参加しているイラストレーターの顔ぶれにある。表紙は「クシー君」で知られる鴨沢祐仁で、ほかにも内田春菊、蛭子能収、みうらじゅん、スージィ甘金、岡崎京子、ナンシー関など総勢十四名!たった一冊の本にこれだけのイラストレーターが必要なの?と思わず尋ねたくなうようなバブリーさ。しかも巻頭には「コーヒーまで7時間」と題されたわたせせいぞうによるハートカクテルな書き下ろしコミックまで。開いた口がふさがりません。
そういえばわりと最近の話、電車で向かいに座っていた女子高生ふたりの会話。携帯の待ち受け画像でも探しているのだろうか、ひとりが携帯の画面を見ながらもうひとりに話しかける。
「ねぇ、わたせせいぞうって誰?」
「知らない。なんか政治家っぽくね?」
もはや本題への復帰不能・・・
盆栽老人とその周辺
2008.11.3|book
深沢七郎の『盆栽老人とその周辺』を読む。
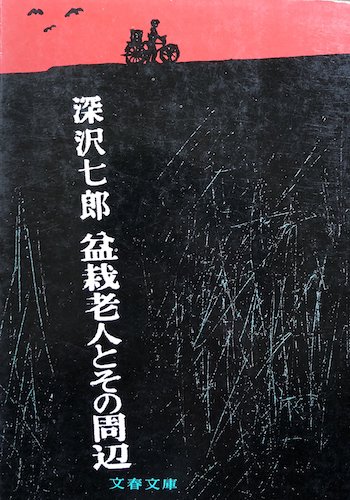
畑仕事が好きで、東京からわざわざ埼玉県のとある村へと移住した「私」。その「私」が、土地のひとびと(=農家のひとびと)から「盆栽」をすすめられたり、売りつけられそうになったり、はたまた強引に「預けられたり」しながら、そのたび断ったり、逃げ回ったり、うっかり「預かって」しまったりするお話である。
なぜ盆栽なのか?というと、このあたりはどうやら盆栽好きのあいだではよく知られた盆栽が盛んな土地であるらしく、農家のひとびともみな盆栽を趣味にしているうえ、なかには「副業」のようにしているひともいるらしい。とはいえ、みんながみんな盆栽で儲けているということはもちろんなくて、「名人」と呼ばれひとびとの尊敬を一身に受けるカリスマ的存在もいれば、下手くそでひたすら散財ばかりしているようなひともいる。この村にはつまり「盆栽」をめぐる堅固なヒエラルキーがどっかりとあるのであって、こうしたヒエラルキーに生きる村のひとびとにとって、東京からやってきた盆栽音痴の「私」はいわば最下層民(=いいカモ)なのだった。
途中まで読み進んではたと気づいたのだが、この小説はある意味「SF」だ。
選挙運動で対立するふたつの陣営が、優柔不断な対応ではぐらかす「私」をまえにどんどんエスカレートして買収合戦のような様相を呈したり、自動車で村に迷いこんできたよその土地の人間に農家のおばさんがすまして嘘をつく現場を目撃したり、あるいはまた「他人の不幸」を表面では同情するようなそぶりをみせながら、裏では嬉々としてうわさしあっていたり、そのたび「私」は困惑し途方に暮れてしまうのだ。ここにあるのは、「村」という小惑星に不時着した「私」が体験するディスコミュニケーションの物語。
それでも「私」はそんな村人たちに対して不平や不満を言うわけでも、ましてや批判をくりひろげるわけでもなく、ただ淡々とその状況を受け入れ翻弄されているばかりである。深沢七郎は「あとがき」に書いている。
農民の持っている根強い根性は、虐げられた反動で磨かれたふてぶてしさーこれを、たくましさ、とか、凄まじさとでも言っても、もう少しちがう、商人のずる賢さともちがうー盲滅法的なふてぶてしさは見事というか、スバラシイちから強さだと思う。
私はこんな底力のある無鉄砲なエゴイズムーかくさないエゴイズム、すぐに見破られてしまうエゴイズムこそ素晴らしいではないかと思う。
おいおい、ほめちゃってるよ。
ワケがわからないまま唐突に終わってしまうこの小説だが、そのワケわからなさの中にも一分の「晴れやかさ」が感じとれるとしたら、それはたぶん「私」が、このエイリアンたちを前に潔いまでにあっけらかんと「敗北」を認めてしまっているせいかもしれない。《不時着者の作法》をここまで見事に体現できる「私」もまた、言い方はよくないけれどゴキブリなみにしたたかで、強靭な生命力をもっているようにみえる。
盆栽老人とその周辺
2008.11.3|book
深沢七郎の『盆栽老人とその周辺』を読む。
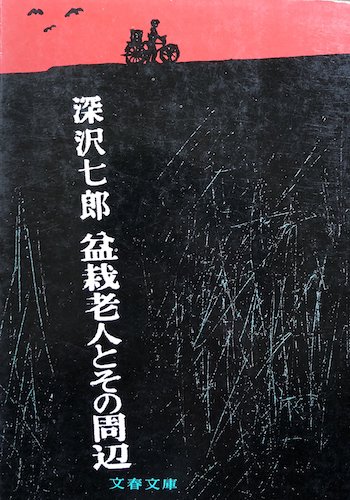
畑仕事が好きで、東京からわざわざ埼玉県のとある村へと移住した「私」。その「私」が、土地のひとびと(=農家のひとびと)から「盆栽」をすすめられたり、売りつけられそうになったり、はたまた強引に「預けられたり」しながら、そのたび断ったり、逃げ回ったり、うっかり「預かって」しまったりするお話である。
なぜ盆栽なのか?というと、このあたりはどうやら盆栽好きのあいだではよく知られた盆栽が盛んな土地であるらしく、農家のひとびともみな盆栽を趣味にしているうえ、なかには「副業」のようにしているひともいるらしい。とはいえ、みんながみんな盆栽で儲けているということはもちろんなくて、「名人」と呼ばれひとびとの尊敬を一身に受けるカリスマ的存在もいれば、下手くそでひたすら散財ばかりしているようなひともいる。この村にはつまり「盆栽」をめぐる堅固なヒエラルキーがどっかりとあるのであって、こうしたヒエラルキーに生きる村のひとびとにとって、東京からやってきた盆栽音痴の「私」はいわば最下層民(=いいカモ)なのだった。
途中まで読み進んではたと気づいたのだが、この小説はある意味「SF」だ。
選挙運動で対立するふたつの陣営が、優柔不断な対応ではぐらかす「私」をまえにどんどんエスカレートして買収合戦のような様相を呈したり、自動車で村に迷いこんできたよその土地の人間に農家のおばさんがすまして嘘をつく現場を目撃したり、あるいはまた「他人の不幸」を表面では同情するようなそぶりをみせながら、裏では嬉々としてうわさしあっていたり、そのたび「私」は困惑し途方に暮れてしまうのだ。ここにあるのは、「村」という小惑星に不時着した「私」が体験するディスコミュニケーションの物語。
それでも「私」はそんな村人たちに対して不平や不満を言うわけでも、ましてや批判をくりひろげるわけでもなく、ただ淡々とその状況を受け入れ翻弄されているばかりである。深沢七郎は「あとがき」に書いている。
農民の持っている根強い根性は、虐げられた反動で磨かれたふてぶてしさーこれを、たくましさ、とか、凄まじさとでも言っても、もう少しちがう、商人のずる賢さともちがうー盲滅法的なふてぶてしさは見事というか、スバラシイちから強さだと思う。
私はこんな底力のある無鉄砲なエゴイズムーかくさないエゴイズム、すぐに見破られてしまうエゴイズムこそ素晴らしいではないかと思う。
おいおい、ほめちゃってるよ。
ワケがわからないまま唐突に終わってしまうこの小説だが、そのワケわからなさの中にも一分の「晴れやかさ」が感じとれるとしたら、それはたぶん「私」が、このエイリアンたちを前に潔いまでにあっけらかんと「敗北」を認めてしまっているせいかもしれない。《不時着者の作法》をここまで見事に体現できる「私」もまた、言い方はよくないけれどゴキブリなみにしたたかで、強靭な生命力をもっているようにみえる。
吉本隆明『ひきこもれ』
2009.1.3|book
正月なのに、味がしない。初詣にすら行ってない(泣)。
去年最後に読んだ本は吉本隆明の『ひきこもれ―ひとりの時間をもつということ』。
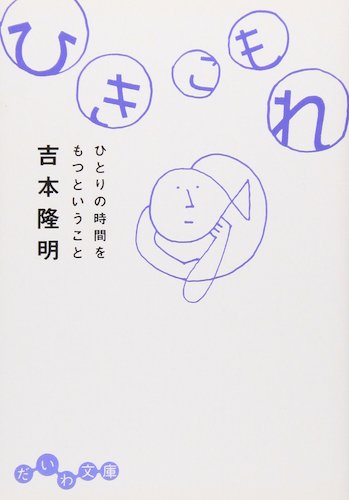
ひきこもること、イコール「分断されない、ひとまとまりの時間をもつこと」と定義した上で、そうした「時間」が「自分が発して自分自身に価値をもたらすような言葉。感覚を刺激するのではなく、内臓に響いてくるような言葉」(それを彼は他人とコミュニュケートするための言葉ではない「第二の言語」と呼んでいる)をもたらすことに着目し、じっくりと自分にとっての「価値」を育て熟成させるためには「それもいいじゃないか」とみずからの「ひきこもり体験」を引き合いに出しながら語っている。
また、人は何ものかになるために「分断されない、ひとまとまりの時間」を必要としていると説く吉本は、「仕事」についてこんなアドバイスもしている。
ひきこもっていてもいいし、アルバイトをやりながらでも何でもいいから、気がついた時から、興味のあることに関して「手を動かす」ということをやっておくのが大事だ、と。そしてそれを10年続ける。「のんびりやろうが、普通にやろうが、急いてやろうが、とにかく10年という持続性があれば、かならず職業として成立」すると。
さらに、たとえ身近に「頭のいい人」が現れたとしても競り合うことはないと言う。なぜなら、なにかにつけて「自分を鋭く狭めてゆくところのある」頭のいい人は長い目でみればそんなにいいことでもないのだから。それよりはむしろ、めざすべきは「少しゆるんでいて、いい加減なところがあって、でも持続力だけはある」熟練した職業人なのである。
ところで、夜中眠れなくなってなんとなくテレビをつけていたら、指揮者朝比奈隆の「生誕100周年」を記念して制作されたドキュメンタリーが放送されていた。
93歳で亡くなる直前まで頻繁に指揮台に上がっていた朝比奈だが、晩年の彼のコンサートはほんとうに独特なものだった。華やかさとも巧さとも無縁なのだが、その音楽の巨大さ、生々しさときたら他のどんな指揮者とも比較にならないほどのインパクトがあったのだ。
ちなみに朝比奈隆の指揮者としてのキャリアは、なんと、65年!べつに朝比奈を「ひきこもり」というわけじゃないけれど、長年にわたる「持続力」があの音楽に満ち満ちた説得力をあたえたと考えるのはけっして間違ってはいないように思える。
森とおじさん
2009.5.15|book
先日ご紹介した本『フィンランド・森の精霊と旅をする』をなんとはなしにめくっていたら、とても印象的な一本の木が紹介されていました。
ティンマキ村という場所の小高い丘にあった巨大なトウヒの木。巨人の足のようながっちりとした幹からほとんど水平に伸びた無数の枝、まるで巨大なテーブルのようにみえるその姿から、村人たちは「タピオ(森の王)の食卓」と呼んで大切にしてきたのだそうです。
おなじ本には、フィンランドの人々にとってタピオ、つまり森を支配する者とは「熊」であると書かれています。タピオといってまずぼくが思い浮かべるのはデザイナーのタピオ・ヴィルッカラなのですが、その風貌といい自然をモチーフとした無骨な作品といい、まさにこれほどこの名前にふさわしい人物もいない、そんな気がします。
ところで、いま「ほぼ日」で連載されている「フィンランドのおじさんになる方法。」を楽しみにしているのですが、毎回登場する魅惑的な? 「おじさん」たちのなかでも、今回紹介されていたレオさんという「きこり」のおじさんはとりわけ魅力的でした。代々、こういうひとたちが森を守り育ててきたからこそいまのフィンランドの森はあるんだな、ととても納得しました。
5/27のイベントでフィンランドの森についてどんなお話が聞けるのか、とてもワクワクしています。
海の底のアンテロ・ビプネン
2009.8.13|book
日曜日の夜、東海道南方沖で深発地震があった。たまたま向かいの魚屋さんの横を通りかかったら、まるでポルターガイストのようにシャッターがガッシャン、ガッシャンと鳴っていて何事かと思ったのだった。
そして火曜日の早朝、静岡県の駿河湾沖で大きな地震があった。ずいぶん揺れが長かったので、どこか離れた場所で大きな地震があったのではとテレビをつけて驚いた。
ぼくは子供のころ、たった二年ほどだが沼津市に住んでいたことがある。なので、「東海地震」は人ごとではない。その当時からいつ起こってもおかしくないと言われ、子供たちはみな「マイ防災頭巾」を持っていた。もちろんぼくも持っていた。山吹色の防災頭巾。一度はデマで学校が早退になったこともあったくらいだ。それに、富士市には「sinilintu」さんや「kaltio」さんら、モイを通して知り合ったフィンランド好きの仲間が暮らしている。月曜日にひさしぶりに顔を出してくれたSさんも、ちょうどこれから実家のある富士市に戻ると言っていたのが気がかりだ。「sinilintu」さんや「kaltio」さんは、地震によるお店や商品へのダメージも心配である。
その後それぞれブログを更新されていて、その中でほとんど被害がなかったとの報告をされていたのでホッとしている。こういう、相手の状況を把握できないときほど、かえって無闇にメールや電話をするのははばかられるものだ。その意味で、インターネットというのはあらためて便利なツールだと感心したのだった。
それにしても、今朝もまた地震である。気象庁は駿河湾沖の地震と東海地震との関連を否定し、今朝の八丈島沖の地震と駿河湾沖の地震との関連性も否定している。それぞれ震源も深さも異なるのだから、まあ、そう言われればそうなのだろう。とはいえ、やっぱりなんとなく気がかりである。
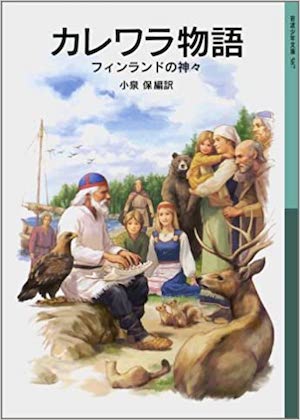
たまたま、岩波少年文庫版の『カレワラ物語ーフィンランドの神々』を読んでいたらアンテロ・ビプネンという「巨人」が出てきた。
「だいぶ以前から眠りこんで半分土になっている」ビプネンは、「ポプラが肩に生え、白樺が眉から伸び、松の木が歯の上に立って」いるという、まるで小山のような案配である(引用箇所は小泉保の訳による)。
いくら関係ないよと言われても、今回の一連の地震は海の底で眠っているビプネンが体をモゾモゾ動かしている、そんな感じにぼくには思えて仕方ない。『カレワラ物語』のなかで、「老ワイナミョイネン」は「呪文」を手に入れようと無理矢理ビプネンの口に鉄の棒を押し込んで起こすのだが、「寝た子を起こす」の格言どおり、こちらのビプネンは目を覚ますことのないよう祈るばかりである。
ジョン・アーヴィングの『第四の手』とか
2009.12.14|book
ジョン・アーヴィングは、忘れたころにやって来る。
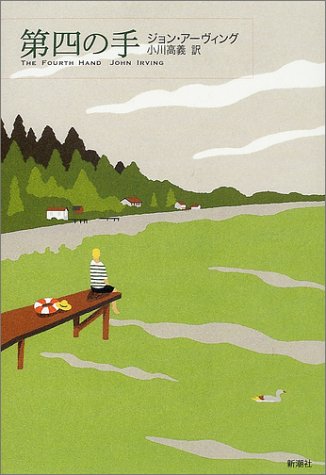
というわけで、最近文庫化された『第四の手』を読んでいる。もうじき読了。『ガープの世界』の映画化が話題になったのが高校のときで、その後すぐ『ホテルニューハンプシャー』も映画になって、『熊を放つ』のウィーンにひそかにあこがれ『サイーダーハウスルール』は映画を観たことをちょっと後悔した。ここまでで、二十年近い歳月がたっているわけだ。そして去年、『ウォーターメソッドマン』をひょんなことからTHE YOUNG GROUPのどしだ君からもらい、いま、この『第四の手』を読んでいる。ふだんそんなに小説は読むわけじゃないのに、なぜか二十年以上にわたりずっと読み続けているというのはなんだか不思議な気分である。とりたてて意識したわけではないけれど、この事実からすれば「好きな作家」と断言してもよさそうだ。
『第四の手』も、読みはじめれば当然のように引き込まれている自分がいる。このあいだ見た上海の夢ではないけれど、ジョン・アーヴィングの物語の世界も、どこか青空なのにいつも翳っているような印象がぼくにはあって、その現実と虚構のはざまみたいな「色」が好きだったりするのかもしれない。初めてビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」を聴いたときもおなじ「色」を感じた、ということをいま思い出した。そんな「色」のなかで展開する、「北をめざして」という章がいい。静謐で、なにか重力から解放されてゆく感じ。ここでの主人公パトリックは、そのヘタレ加減で『ゴダールのマリア』のジョゼフにも似ている。ちなみに、『第三の~』じゃなくて『第四の手』となっている理由もここで明らかになるので、まだ読み終わっていないけれどこの小説のハイライトなのかも。
気づけば感想文にもなってないし、ひたすらとりとめのない文章になっちゃってることを・・・反省。でも、ぜひ読んだひとひとりひとりに、その感想を教えてもらいたい気分だ。教えて下さい、今度ぜひ。
──
ところで、きょうから八重洲の千疋屋ギャラリーで森麗子さんの展示がはじまったことをフィン語クラスのnonoさんに教えてもらいました。nonoさんは、森さんのアトリエに最近通い始めたとのこと。今週いっぱいと会期が短いのだけど、ちょっと見逃せないと思っています。向かいのブリヂストン美術館で開催中の「安井曾太郎の肖像画」展も気になっているので、いっそこの際ハシゴしようかな、と。
こんなふうにつらつらと明日の予定をかんがえたりしているうち、どうやらそろそろ閉店の時間です。
池波正太郎の銀座日記
2009.12.3|book
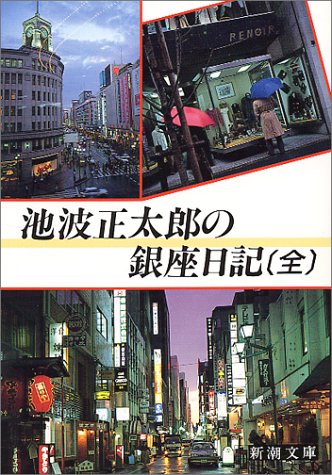
作家、池波正太郎がその晩年、八年間にわたり「銀座百点」に連載していた日記をまとめた『池波正太郎の銀座日記(全)』を読んでいる。
いまでいえば、さしずめ池波正太郎ブログといった感じ。食べたものと観た映画の話でほぼ7割、残りの3割は芝居の話と友人、知人の訃報とで占めている。
途中、しきりに「飲めなくなった」「食が細くなった」というぼやきとも嘆きともつかない独白がふえてくるあたりから、「『老い』と向きあうひとりの男の日常」という「通奏低音」が姿をあらわし、通して読んでゆくとおなじ本にもかかわらず明らかにその肌触りが変わってしまっていることに気く。
本人は「老い」をテーマに書こうと決めているわけではなくただ淡々とその日常を綴っているにすぎないのだが、それだけにむしろ読む側としてはチクチクとした「痛み」を感じないわけにはいかない。
ぼくのように、ほとんど酒を飲めないに等しい人間にとっては、以前ほどに「飲めなくなる」ことがそこまで嘆かわしいことなのかまったく理解はできないのだが、ひとはそんな思いがけない現実(よくわからないが、たとえば「トイレが近くなった」とか「たらばガニを食べるのが面倒臭い」とか、あるいはまた「テレビで松岡修造を見ると疲れる」とか)によってみずからの「老い」を突きつけられるものなのだろう。
映画についてはまさに雑食。試写状の届いたものはとりあえずなんでも、しかもそれ相応に楽しんでしまうというひとだったようでそのぶん「作家による映画評」といったものを期待すると肩すかしを喰うが、ぼくの場合はこの日記が書かれたころがちょうど学生時代にあたっていて、映画館にいちばん足を運んでいたころだったせいか登場する映画のひとつひとつがなつかしく、意外なところでおもしろく読むことができたのだった。
島村菜津『バール、コーヒー、イタリア人』
2011.4.24|review

世界進出をはかる北米発祥のコーヒーチェーンを横目に、ひたすら我が道を往くイタリアのバール。
著者はイタリア各地のバールでのエピソードはさみつつ、その歴史と発展の陰には、他人と違っていることをよしとするイタリア人ならでは価値観、そして人間力があると指摘する。
ナポリのバールに残る美しき慣習「カフェ・ソスペーゾ」、いまだに地元の樫の木による薪焙煎にこだわるロースター、誇り高きバールマン(バリスタとは異なる)など、この本を通じて知ったことがらも少なくない。
街がバールをつくりバールが街をつくる。
きょうもイタリアの街のいたるところで、ちいさなお店が胸を張って生き生きと仕事に励んでいる。なんと清々しい光景だろう。
波多野一郎・中沢新一『イカの哲学』
2011.4.27|review
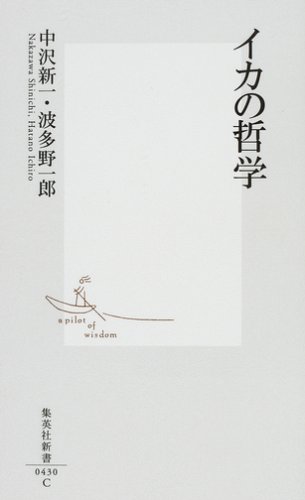
在野の思想家、波多野一郎が残したちいさなブックレット『烏賊の哲学』を地図がわりに、すべての存在が等しくもつ「実存」に立脚してより恒久不変の平和学、ひいてはエコロジーの可能性について探った意欲作。
そのカギは、そもそも人間に備わっていながら、自然を貨幣価値を生む資源とみなす資本主義経済のなかで見失ってしまった「比喩」の能力にある、と著者はいう。
比喩とは「意味と意味とを重ね合わせることによって、あたらしい意味を表現する力」であり、いわば、別のジャンルにあるもの同士をひとつにつなぐ「蝶番」なのである。
そうして、そもそもそれは人類の生命そのものにセットされた奥深い知性として、いざというときにはいつでも発動させられる状態に保たれてきた。その「奥深い知性」が発動することで、ぼくらがコンタクトできる「共感にみちた宇宙」を示したのが「神話」なのである。
戦争が終結し一応の平和が訪れたようにみえる陽光降りそそぐカリフォルニアの港町で、学費を稼ぐため捕獲された夥しい数のイカを加工していた波多野は、ある日突然イカの「実存」に気づき、その途方もない比喩の力に押し出されるようにして「世界平和のための鍵」を手に入れる。
なんとなく荒唐無稽に感じられなくもない仮説だが、使用済み核燃料を地中深くで10万年先まで保管するという壮大なプロジェクトを取り上げた映画『100,000年後の安全』で、未来の人類に危険物の存在を示すためSFまがいのアイデアを真剣に討議するフィンランドの科学者たちは、そのときたしかに、比喩の力がつなぐ神話的な宇宙にはからずも彼らは押し出されているのであり、それゆえこのプロジェクトの10万年先の完結を信じたい思いにかられたのだった。
森下圭子『ワンテーマ指さし会話 フィンランド×森』
2011.5.4|review
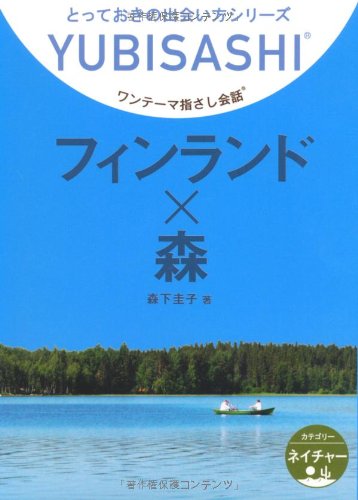
「自分の心に「森」と響いたら、そこは森」…… 翻訳家、コーディネーターで、映画『かもめ食堂』のアソシエートプロデューサーとしても知られる森下圭子さんが、みずからを「森の民」と称するフィンランド人にとっての「森」の存在から、季節ごとのアクティビティ、オススメの森へのアクセスなどについて懇切丁寧に語った一冊。
「指さし会話帳」のシリーズではあるけれど、語学書というよりむしろ読み物と美しい写真からなるフィンランドの森を知るためのハンドブックといったところ。
もちろん、フィンランド旅行を計画しているひと、とりわけ自然と触れ合いたいと考えているひとには必携の一冊だが、たとえ都会に暮らしていても、つねに身近な自然を日々の暮らしに上手に取り込むフィンランド人のライフスタイルは、いま価値観の転換を求められている3.11以降を生きるぼくら日本人にとっても少なからず参考になるはず。
オッリペッカ・ヘイノネン『「学力世界一」がもたらすもの』
2011.5.13|review

90年代のフィンランド、空前の不況にあえぐなか弱冠29歳という若さで「教育大臣」に就任、一連の「教育改革」を断行しわずか10年あまりでフィンランド経済を立ち直らせる礎を築いたオッリ=ペッカ・ヘイノネンへのインタビューを中心にまとめた一冊。
東日本震災以後、新しい価値観をもつことを迫られているぼくら日本人にとって、ひとつの「提言」となりうるかもという淡い期待を抱きつつ手にとったのだが、読了後はただただため息ばかり……。
まず、補佐官としての経験はあったとはいえ議員経験のまったくない29歳の若者に「教育大臣」として国家存亡の危機を託してしまう大胆さ。しかも本人によれば、議会で足を引っ張られるどころか、大臣就任の決議も含めほとんど全会一致で決まったという。日本では、まずありえない話だ。
そしてさらに、大不況のまっただ中での改革が、すぐには結果の出ない「教育改革」だっという点も驚かされる。付け焼き刃の改革ではダメだという大いなる判断の下とはいえ、「そんな悠長なことをやっていたらその間にたくさんの国民が飢え死にしてしまう」といった反対意見はなかったのだろうか?
フィンランド人の「不思議さ」でもある。
しかし結果的に、産業社会からポスト産業社会への転換期ということが後押しになったとはいえ、この「教育」に始まる一連の改革は大成功をおさめ、おもにIT分野での成功というかたちで国を再生させる。
では、日本とフィンランドとの差はどこにあるか?
ひとことでいえば「機会の均等」ということへの国民全体の意識の高さ(「誇り」といってもいいかも)であり、政府の国民に寄せる「信頼」(裏を返せば、国民の政府に寄せる「信頼」の)高さである。
カタチを踏襲するのではまったく意味がない。成功する「改革」には、その足下に成功させるための地平が広がっているのだと納得させられた。
北欧のライフスタイルに関心のあるひとは、ぜひ熟読すべき一冊。
内田樹・中沢新一・平川克美『大津波と原発』
2011.5.17|review

震災以降ずっと、こういう本の登場を待っていた。
原発事故は、「原子力発電所の事故」にはちがいない。けれども、事故は事故でも、この事故の解決はただ技術の問題でなんとかなるものではない、震災以後そういう予感がずっと続いている。だからこそ、物理や経済ではなく、哲学や宗教学といった方面からの真摯な発言を聞きたかったのだ。そしてこの一冊は、まさに原発の扱いから東北の復興ヴィジョンに至るまで、現在進行形でぼくらが直面しているさまざまな問題についてきわめて示唆に富んだ提言とともに論じられている。
たとえば、地球の生態圏の外側から持ち出してきたものである原子核の中に操作を加えることで成立する原子力発電を「第七次エネルギー」としたうえで、これまでのエネルギーとまったく別次元のものであると定義する。そして、生態圏の中に存在しないという理由から原子力を「一神教的な神」に類するものだとし、思想的な理解を疎かにしたまま技術だけでコントロールしようとしてきたことにそもそもの問題があったと指摘する。
さらにそこから、東北の復興、エネルギー問題、首都機能の分散、新しい農業の提案などをふまえた中沢新一による「緑の党のようなもの」の提唱にまでつながってゆく……。
大胆でありながら、きわめて腑に落ちる発言が散りばめられた、想像力を刺激される一冊。
萩原健太郎『北欧デザインの巨人たち』
2011.5.27|review
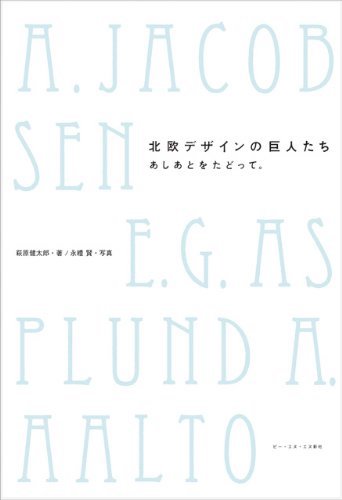
北欧デザインや建築を紹介する本はあまたあるけれど、この本『北欧デザインの巨人たち あしあとをたどって』は、デンマーク、スウェーデン、そしてフィンランドの「巨人」〜 すなわちヤコブセン、アスプルンド、そしてアールトの三人の「あしあと」を辿りつつ、唯一無二の北欧デザインの個性がどこから来て、どこへ行くのかを数々のエピソードから示してくれている点で興味深い。
ぼく自身は、数あるエピソードのなかから選び出されたエピソードのひとつひとつにとりわけ著者ならではのセンスの鋭さを感じたし、かならずしも作品紹介にこだわらない写真の数々も、美しくも短い北欧の秋をとらえている点でよりいっそう輝きを増している。
デザインや建築に関心があり北欧を旅するひとは、これを手に取ることで一段「深い」旅になることうけあい。
吉田修一『横道世之介』
2011.6.11|review
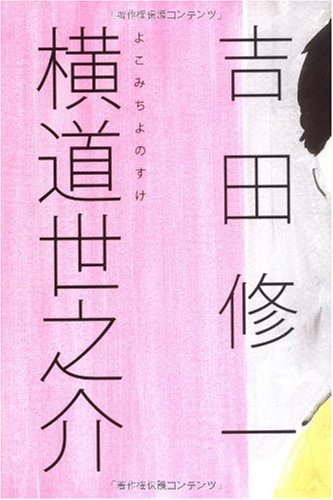
一陣の風のようにさわやかで、愛おしく、かつ鈍くさい男、横道世之介。あるいはまた、偉大なる凡人の物語。
世界、世界と言うけれど、その実体は自分と自分を取り巻く人々からできた案外ちっぽけで退屈なものにすぎないのかもしれない。主人公の「世之介」もまた、そんな世界の一部としてごくありふれた平凡な人物にすぎない。とはいえ、機械がたった一本のネジを失っただけで動作しなくなってしまうように、彼を取り巻く人々の世界もまた、世之介という存在がなければかけがえのないなつかしい光を失ってしまうのだ。
後半、世之介の目に映るありふれた風景のうつくしさ、その儚さに涙がこぼれた。もちろんそれは、著者の構成がパーフェクトゆえの効果。
ちなみに、80年代の東京で青春を過ごした読者にとっては、その固有名詞だけで時代の空気を感じ取り、物語の細部まで手に取るように伝わるだろうが、もちろんそうでないひとにとってもなんら支障はないはず。個人的には、あの『パークライフ』の吉田修一と同一人物とは思えないほど(自分にはまったく肌が合わなかったので)、その世界に引きずり込まれた。
村上春樹『村上ソングズ』
2011.6.14|review

なぜぼくらは音楽を愛するのか? その「答え」を、無類の音楽好きとして知られる小説家とイラストレーターが教えてくれるのがこの一冊。
ふたりがそれぞれの音楽遍歴のなかで出会ったたくさんの歌から29曲を選び、和田誠による挿絵と村上春樹による訳詞&エッセイ、それに原詞が添えられる。どれも味わい深く、好奇心をくすぐられるが、いまはYouTubeという優れたメディアのおかげで手軽に実際のサウンドに触れることができるので、この本の楽しみは何倍にもふくらむ。そして、
── 優れた音楽はいろんなことを『音楽的に』考えさせてくれる
という村上春樹のことばこそは、冒頭の疑問への「答え」になっている。
音楽は文学の代わりにならないし、文学は絵画の代わりにならない。そして絵画は、けっして音楽の代わりにはならない。それぞれが、それぞれのやりかたでいろんなことを考えさせてくれるのであり、それゆえぼくらは本も読めば、絵画を観るし音楽も聴くのだろう。
長谷川泰三『日本で最初の喫茶店「ブラジル移民の父」がはじめた―カフエーパウリスタ物語』
2011.6.17|review

日本のすべてのカフェのルーツここにあり。
いまからちょうど百年前、ブラジル移民の「父」水野龍は、コーヒー文化の紹介&普及、宣伝を条件にブラジル・サンパウロ州政府より12年間にわたりコーヒー豆の無償提供を受けることになる。そのために水野がつくったのが、いまも銀座に現存する喫茶店「カフェーパウリスタ」である。
そもそも日本にコーヒーという飲み物の需要がなかった時代に、水野らは徹底したパブリシティ戦略と(無償提供の豆だからこそできる)安価での提供により、あれよあれよという間に「カフェ」を時代の先端をゆく業態として都市に定着させてしまう。こうした「使命感」にも似た尽力がなければ、日本のコーヒー文化、喫茶文化はもっとちがったものになっていたかもしれない。つまり、「カフェーパウリスタ」こそは日本のすべてのカフェの「父」であると言っても過言ではないのである。
雑多な種類の人々が集い、文化人の「たまり場」としてリベラルな空気を漂わせていた「パウリスタ」こそは、日本のベルエポックともいえる「大正デモクラシー」の象徴といってよく、さまざまな文化人のエピソードは読んでいてとても愉しかった。また、貧しい若者のコーヒー代を見知らぬ客が立て替えてやるというナポリに残る人間味あふれる慣習「カフェ・ソスペーゾ」が、大正時代の「パウリスタ浅草店」にもあったと知ったのもうれしい発見であった。
「東京カフェマニア」のサマンサさんいわく「カフェは5年続けば老舗」だそうだが、「カフェーパウリスタ」は今年の6月25日で一号店である箕面店の開業から数えて満百歳を迎える。数々の喫茶店やカフェがことごとく息絶えてゆく昨今、細々とでも日本独自の喫茶文化が生き残っていってくれることを現場に身を置くひとりとして祈るばかりである。
『ミュージック・マガジン 2011年6月号』
2011.6.23|review

個人的に、今年上半期のベストワンに挙げたいピチカートワンこと小西康陽のソロアルバム『11のとても悲しい歌』。そのリリース前におこなわれたインタビューをここで読むことができる。
基本的に、これはピチカートファイヴとして人気を博していたときから一貫して言えることだと思うのだが、小西康陽には「孤独なひと」というイメージがつきまとう。幸福のうちに、その幸福が消え去る悲しみを同時に見てしまうひと、とでもいうか。ピチカートファイヴ時代、いつか野宮真貴が辞めると言い出す日が訪れると思うと心が痛む、なんていうエッセイを書いていたのが心に残っている。
「ソロ・アルバムとは”自分ひとりで作る音楽”じゃなくて、”自分ひとりのために作る音楽”なんだっていうことに気付きました」という本人の言葉どおり、この『11のとても悲しい歌』は「孤独なひと」小西康陽が自分の「孤独」と向き合うことから生まれたとても内省的なアルバムといえる。でも、その「ひとり」が同時にほかの誰かの「ひとり」と重なるとき、それは「名盤」と呼ばれるのだろう。
宮台真司・飯田哲也『原発社会からの離脱』
2011.6.24|review

一筋の希望の光とともに、この先のエネルギー問題について考えたいひと必読の一冊。
ここでは「3.11以後の日本」について、社会学者の宮台真司氏と環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏ふたりの対話を通じて、おもに「エネルギー」面から論じている。
宮台氏はここまで原発社会をつくってきた日本人の「心性」について、「《悪い共同体》とそれに結合した《悪い心の習慣》」「知識社会」「ガジェットの集積を尺度とした豊かさ」といったキーワードから語っているが、まさに核心をついている。
一方、もともと技術者として原発開発の現場に身を置き、原発行政にも深く関わってきた飯田氏の話も生々しく興味深い。その後訪れたスウェーデンで出会った自然エネルギーについて、ヨーロッパのみならずアジア諸国の導入例や、日本における可能性や過去の失敗例まで紹介されており勉強になる。
そして、この先のヴィジョンとして提唱される「小さな統治ユニットによる共同体自治」は、エネルギー問題だけでなく、この先の日本、とりわけ東北〜北関東の早期の復興のためにもぜひ実現してもらいたいと思う。もちろん、あわせて電力の固定価格制度の早期導入もまたれるところ。なぜか福島県や新潟県に「東京電力」の原発があるという不自然を是正するためにも。
網野善彦『日本社会と天皇制』』
2011.6.27|review

靴の中の小石みたいに、3.11以降それまでまったく気にもかけていなかった物事が気になって仕方ない。たとえば、「天皇制」について。
震災後の天皇陛下のお言葉やふるまいには、たしかに、なにかしら日本人の琴線に触れるものがあったように思う。その正体はいったい何なのだろう? 自分なりに探ってみる必要がありそうだ。
著者は日本中世史の研究者であるが、みずから「日本共産党」の党員であったこともあるだけに、「天皇制」については一貫して批判的な立場を貫いている。とくに、このブックレットの元となった講演が行われた80年代当時は中曽根政権のもと日本の右傾化が懸念されていた時期だけに、かなり直裁的な表現もみられる。
・歴史上、単一民族による統一国家としての「日本」が存在していたことはない。
・歴史上、天皇家が「日本」を統治していた時代もほぼ存在しない。
・皇国史観などを通じて、天皇家が重要視する「後醍醐天皇」という存在の「特異性」。
といった「視点」がここでのキータームになっている。これだけをもとになにかを判断することはまったくできないとはいえ、コンパクトながら日本人と天皇制(とりわけ中世の)を知る上で大変に興味深い論考。後醍醐天皇とその治世について論じた『異形の王権』もぜひ読んでみたいところ。
中山康樹『ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄』
2011.9.30|review
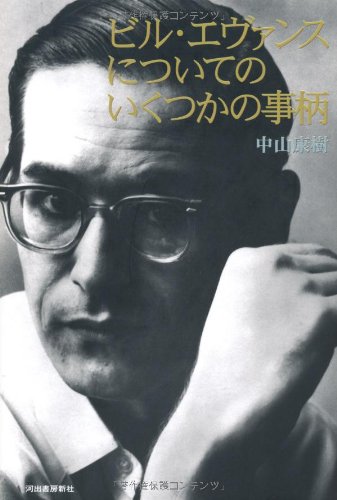
理想と現実とのギャップに翻弄されながらも、文字通りその生涯を「芸術」のために捧げた孤高の音楽家ビル・エヴァンス。
その苦悩に満ちた人生を、さまざまなかたちで彼に関わった人間たちの証言を引き合いに出しながら、ときに大胆な推理も交えつつ描いた評伝。読みながら、まるでテレビのドキュメンタリーでも観ているかのように鮮明なイメージを結んでゆく構成のおもしろさは、きっと著者の手腕によるところも大きいのだろう。
全幅の信頼を寄せていたベース奏者スコット・ラファロが不慮の事故により突然この世を去って以降、ビル・エヴァンスはソロ以外で「I Loves You, PORGY」を演奏することがほとんどなくなった。その「理由」は……
と言ってポール・モチアンが明かすエピソードは、その真相はともかく、哀しく、そして美しい。
Bear Pond Espresso『LIFE IS ESPRESSO』
2011.10.1|review
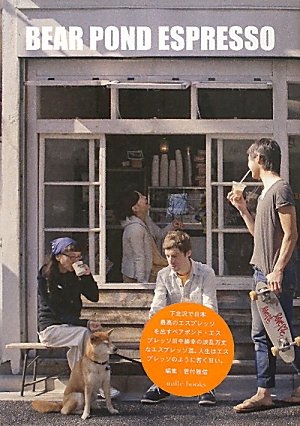
わずか15mlのエスプレッソに溢れんばかりのパッションとプライドを注ぎこむ、これは下北沢「BEAR POND ESPRESSO」のオーナー田中勝幸氏によるエッセイである。
大学時代はスキーやサーフィンにのめり込み、卒業後は大手広告代理店に勤めるも語学を磨くため仕事を辞め、渡米。その後、NYで一流企業に働きポストも得るが、ある日ダウンタウンで出会ったエスプレッソの味にノックアウトされ、気がつけば仕事をしながらバリスタの訓練を積む日々……。そして、「骨を埋める」気でいたアメリカの地を離れ下北沢にわずか6坪のカフェを開き、現在に至るまでのストーリーが熱い口調で語られる。
他人の目には波瀾万丈に映るかもしれないその過去も、本人にとってはたまたま情熱を傾けるべき対象が変わっただけで同じ一本道、いまの姿もことによったら「通過点」に過ぎないのかもしれない。チェーン店ではけっして味わえない、ちいさな個人店の魅力に触れるとともに、その「熱い」生き方に共感をおぼえるひとも少なくないだろう。ただしかなり熱いので、ヤケド注意!?
中沢新一『日本の大転換』』
2011.10.10|review
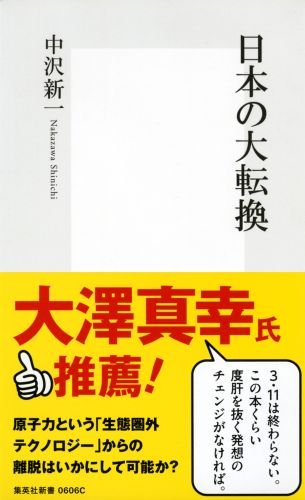
3.11をきっかけに「生き方や考え方を変えようとしている人々は、誰もがエネルゴロジストになれる」と中沢新一は言う。
エネルゴロジストとは、「地球科学と生態学と経済学と産業工学と社会学と哲学とをひとつの結合した、新しい知の形態」としてのエネルゴロジーを理解しようというひとのことであり、そうした視点から「この先」を見ようとするひとのことである。
そこで、まずこの本の前半では、いわゆる石炭や石油といった「化石燃料」と「原子力」との「ちがい」について語られる。太陽の恵みを、あくまでも生態圏の範囲内で長い時間とたくさんの媒介を経てつくられる化石燃料に対して、原子力は、ほんらい太陽圏の活動である核反応の過程をなんの媒介も経ずにそのまま生態圏のなかに持ち込んでしまう技術である。
石炭や石油について、限りある資源を大切にしよう、電気は大切に使おう、といわれるのは、それが自然によって与えてもらったものだというリスペクトがはたらいているからである。ところが、人間が科学技術によって自力でつくっている(と思い込んでいる)原子力については、オール電化を例に出すまでもなく「電気はどんどん使って、どんどんつくろう」ということになる。資本主義と原子力が「セット」であるゆえんだ。
それに対してエネルゴロジーは「第8次エネルギー革命」だと、中沢新一は言う。そのことは、補遺として収められた「太陽と緑の経済」でより具体的に説明が試みられている。
そこでは、原子力+資本主義から、自然の理法に則ってつくられるエネルギー+「つぎのかたち」の経済(ケネー=ラカン・モジュール)へと大きく舵を切ることの必要が、「贈与」「農業」「カタラテイン=交換」「地域通貨」「キアスム構造」といったキーワードとともに宣言される。
もし、このマニフェストがぼくら日本人に勇気をあたえてくれるとしたら、それは、今回の悲惨な災禍を体験したぼくらだからこそ、この大きな「使命」を成し遂げることができるのだと信じさせてくれる点にあるように思う。具体的な動きとして、著者が提唱する「緑の党のようなもの」が近々リアルな活動として始動し、この本はいわばその「マニフェスト」にもなるようだ。ぼく自身、よく考え、自分にできるかたちで積極的に関わっていこうと思っている。
許光俊『世界最高のピアニスト』
2011.10.12|review

「ピアノ嫌いのためのピアノの楽しみ方」という視点で書かれた、とにもかくにも刺激的なピアノ音楽の指南書。
ところで、ピアノという楽器は古くから人気の習い事である。なので、ここ日本にはピアノ学習経験者が山ほどいて、ピアノ曲愛好家の多くはじつはそうした人たちだったりする。けれども、伊達にピアノを知っているがために、ときにはそこでいわれる「感動」がじつは「感心」とイコールだったりもする。つまり、(自分が弾けないような)難解なパッセージを超絶技巧によってさらりと弾いてしまうとそれだけでひどく感動(じつは、それは「感心」なのだが)してしまうということである。なので、ピアノ好きのひとのおススメや解説書の多くは、そうした「技巧」という視点から評価され、紹介されることがとても多い。でも、ぼくのようにピアノを「知らない」人間にとっては、そうしたオススメや解説は「だからなに?」ってことも少なくないのである。
この本がピアノ曲を楽しむための指南書として画期的なのは、そうしたいわば「感心」と「感動」とをきっちり切り離した上で評価しようという意図が根底にあるところだろう。なので、シューマンやリスト,ラフマニノフといったピアノ学習者ウケのする作曲家の名前も、ここにはまったく登場しない。
そして、そうした「ルール」(?)をのみこんでさえいれば、ここで書かれている内容はけっして挑発でも過激でもなく、至極真っ当な意見と感じるはずである(もちろん、取り上げられたピアニストや演奏すべてに共感できるかどうかはまた別の話だが)。
個人的には、筆者のケンプに対する評価のツボは心からの共感をもって読んだ。
ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』
2011.10.19|review

表題どおり、この小説はなによりも美しく、なによりも儚いもの、つまり「きれいな女の子との恋愛」と「デューク・エリントンの音楽」に捧げられている。
ひさしぶりに読み直して感じたのは、精緻に描かれたコントラストの妙。物語は、街から色彩の消える冬に始まり生命が躍動する新緑の季節に終わるのだが、登場人物たちの世界はそれとは反対に、徐々に色を、そして音楽を失ってゆく。彼らはいってみれば、彼らの住む世界との「同期」に失敗したのだ。その残酷さと不条理さ……。
破天荒なファンタジーのような顔をもつこの小説をはたして「読める」かどうかは、ボリス・ヴィアンの「感性」にどこまで肉薄できるかにかかっているような気もするが、そのいちばんの方策はまず、解説で訳者が言うように「奇天烈さをごくりと飲み込」んで、そこに繰り広げられる「いっさいを受け入れる素直さ」をもつことだろう。
レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』
2011.10.26|review
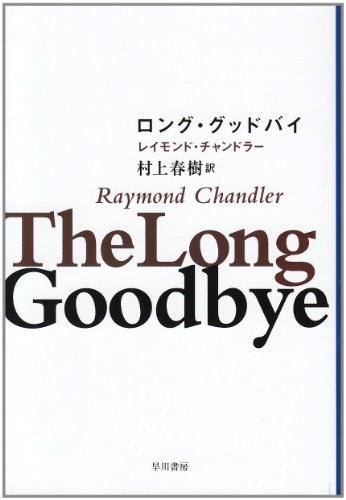
はたして、私立探偵フィリップ・マーロウの淹れるコーヒーの味は?
朝、フィリップ・マーロウはコーヒーメーカーでコーヒーを淹れる。それが習慣、というより彼にとって「決まり」なのだ。訳にはコーヒーメーカーとあるが、細かい描写を読むかぎり、それはパーコレーターのようだ。40年代、アメリカの一般家庭でよくみかけられたパイレックスの直火式パーコレーターかもしれない。一見ストーリーとは無関係のようでいて、そのじつコーヒーを淹れる所作はそのまま「フィリップ・マーロウ」という人間の説明にもなっている。
タフにみえて繊細、物事を順序立てて考える習性が身についている。すべてにおいて用意周到、こだわりが強く細かい部分もないがしろにしない。反面、頑固で、少しばかり融通のきかないところがある…。
すでに家庭ではふつうにインスタントコーヒーも普及していた時代だと思うが、毎朝わざわざパーコレーターを使ってコーヒーを淹れるような男、それがフィリップ・マーロウなのだろう。
山下清『日本ぶらりぶらり』
2011.10.28|review
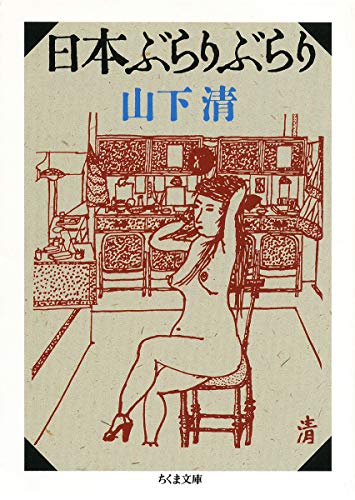
さながら山下清は、直球しか投げないピッチャーのようである。
「裸の大将」として知られる彼は、誰彼かまわずその言葉に疑問符を投げつける。なぜなら彼は、すべての言動の背後にはそう言われて然るべき理由があるとかんがえるからである。しかし、たいがいのひとは「なぜ」という理由を知らないで言葉を発していることのほうがずっと多い。
たとえば、道後温泉に行った清は、案内してくれたひとに「女ぶろ」を見学したいと申し出て断られる。そこで彼は、「なぜできないのですか?」と訊ねる。案内人は当然のように「キソクですから」と返答する。だが、納得のゆかない彼はさらにこう問いかける。「キソクは守らねばなりませんか?」。困った案内人はこう返答する。「(キソクを)もし守らなかったら温泉をやめさせられます。だからキソクはちゃんと守ります」。もちろん、これは「なぜ女ぶろを見学できないか?」の本源的な答えにはなっていない。なので彼はまったく納得していないが、場の空気を読んで「それ以上ぼくはききませんでした」となる。
こんな案配で、ときに清の投げる直球は胸元を鋭く抉って相手をのけぞらせる。それは、相手がよって立つ足場まで揺るがせかねないアナーキーな問いかけだからである。いつも清の問いかけに対してみんながどっと笑うのは、笑うことで問いじたいを無効化しようとしているからであり、いってみれば防衛反応にほかならない。けれども、彼は「どうしてみんなが笑うのか」いっこうにわからないのだ。ここに、山下清の孤独がある。
「ぼくだけがどうしておかしいのか、そのわけをきいてみたいが、きくとまたわからない返事にぶつかるので、ぼくはわからんでもだまっていようということにしている…」こんなにも笑えて、その後哀しくなる本もすくない。
深沢七郎『言わなければよかったのに日記』
2012.1.21|review
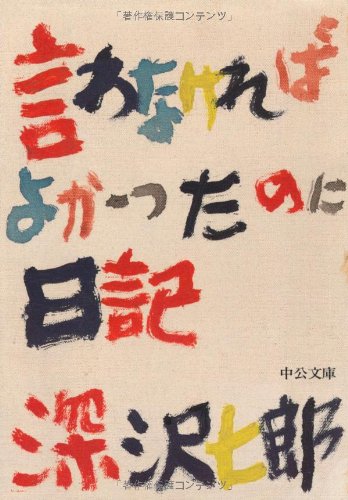
再読。いや、再々読? ときどき思い出しては読み返す深沢七郎のエッセイ集。
なかでは、「とてもじゃないけど日記」がいい。うっかり(?)小説『楢山節考』がベストセラーになってしまったことで巻き込まれる珍騒動の数々、そして、本人の思いとは別のところでひとり歩きするイメージに苦悩する日々…。とてもじゃないけどやってられないよ、というわけだ。
『楢山節考』が芝居化された折り、役者による迫真の演技を目の当たりにして「おっかなく」なってしまい、思わず結末を変えようと作者みずから言いだして周囲から止められるエピソードには失笑せずにはいられないが、そんななかすべてを心得た尾上梅幸のふるまいには一流の役者ならではの含蓄を感じさせてくれて感激する。そしてこういうところに、むしろ、深沢七郎というひとの観察眼の並々ならぬ鋭さを発見するのである。
それにしたって、文中に登場する石原慎太郎ときたらなんとも「いいひと」なんだがなぁ…(笑)。
広瀬和生『この落語家を聴け!』
2012.1.28|review
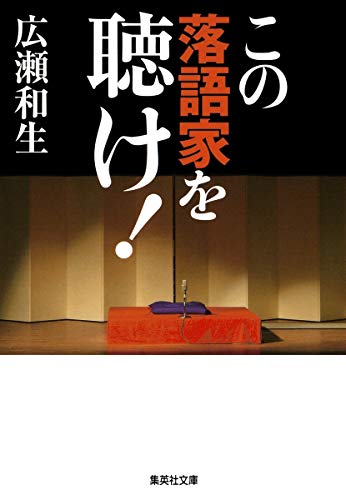
唐突に「落語」に興味をもって一ヶ月そろそろ寄席や落語会に出かけてナマの高座にも触れてみたい…… この本と出会ったのは、まさにちょうどそんなタイミングのことだった。
著者はヘヴィメタ専門誌「BURRN!」の編集長にして、年間1500を超える高座を観続けてきたというライブ至上主義の、筋金入りの「落語好き」である。著者によれば、現在の落語シーンは「名人」と呼べるような存在こそ極端に少ないものの、その一方で若手や中堅の噺家のなかに数多くの逸材が存在する、いわば「黄金時代」なのだという。そして、そのせっかくの「黄金時代」を満喫するために、いままさに寄席や落語会で聴くことのできる噺家たちを取り上げ、紹介したのがこの本『この落語家を聴け!』である。
寄席や落語会に出かけようと思ったが、いったいいまどんな噺家がいて、どんなネタを高座にかけているのか皆目見当がつかない。寄席の番組表を見たはいいが、なじみのない名前ばかりで誰を目当てに足を運べばいいのかわからない。そんなとき、この本はとても役に立つ。なぜなら、いくら百花繚乱の「黄金時代」とはいえ、すべての噺家が面白く、わざわざ時間を割いてまで聴くに値する噺家とはかぎらないからである。
しかしぼくらの生きるこの時代には、幸いなことにインターネットという文明の利器がある。まずはこの本でとりあえず聴いてみたい噺家をチェックした上で、ネットでさらに検索をすればその噺家のさまざまな情報(プロフィールや本人によるSNS、落語会の情報から、場合によっては高座の動画まで)にかんたんに触れることができる。これだけで、初心者にとってはひどく「敷居が高い」と感じていた寄席や落語会がぐっと身近なものになる。そして寄席や落語会といったライブ空間では、ときには新たな魅力的な噺家との出会いが待っているかもしれない。
落語をまったく知らないひとではなく、落語にちょっと興味をもったひとがさらなる深みにハマろうというとき紐解くと恰好の手引書になるにちがいない。
立川談春『赤めだか』
2012.2.1|review
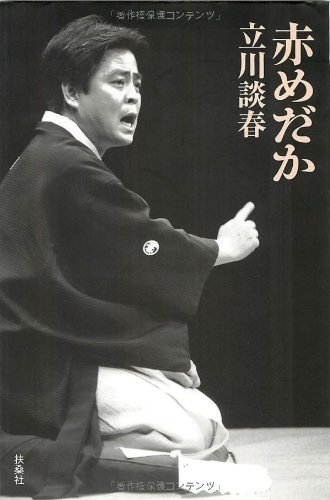
いまをときめく人気落語家がその地獄の修業時代をつづった半生記は、カラッとした文体もあいまってそんじょそこらの青春小説も吹っ飛ぶおもしろさ。
「本当は競艇選手になりたかった」少年は、課外授業の寄席に登場した立川談志の「芸」(というかその「存在」?)に打ちのめされ、高校を中退し半ば勘当状態のまま立川流に入門する。そんな彼を待ち受けていたのは、「個としての自由も権利も認められない」、つまり「人間」として扱われない「前座」としての地獄の修業……。もちろん、その「地獄」の実体はといえばほぼ100%師匠(イエモト)である立川談志という破天荒な人物にあるのだが。
ちなみにタイトルの「赤めだか」とは、談志が可愛がっていた金魚のこと。いくらエサを与えてもいっこうに成長しないその金魚をみて、弟子たちが密かに名付けたのがこの「赤めだか」という呼び名である。当時、落語協会を飛び出した草創期の「立川流」の内情はというと、まさにカオスそのもの。そんなカオス状態の中、未来への展望もなく溺れそうになりながら必死にあがいている自分たちの姿を、水がめの中で大きくなれずにいる「赤めだか」の姿に重ね合わせたのだろう。
とかくハチャメチャと思われがちな師匠「立川談志」という人間を、「いや、そんなことはないのですよ、実は……」というのではなくハチャメチャなままに談春は描く。じっさい談春にとっての師匠(イエモト)とは、離れて忘れたほうが身のためと知りながら忘れきれない、思いきれない魅力をもつ「悪女」のような存在だと言う。そしてここに、師匠と弟子とが「愛憎」によってきつく結ばれた「立川流」の特殊性があるのかもしれない。
一見したところ優等生的な印象のある談春が、まさかこんな無頼派とは…… その「意外性」もこのエッセイをいっそう楽しくしている。
堀井憲一郎『落語の国からのぞいてみれば』
2012.2.10|review

ある日突然「落語の国」に迷い込んでしまったビギナーにとって、この一冊はなかなか便利な「道しるべ」となっている。
ここでは落語の歴史やあらすじ、おすすめの噺家などが紹介されるかわりに、落語に登場する人たちー 熊さんや八っつぁん、長屋のご隠居や与太郎といった魅力的な人物たち ーのことばや動きの背景をなす「感覚」について、「時間」「金銭」「結婚」「恋愛」「酒」「死」といったキーワードを通して語られる。
たとえば「時そば」という有名な噺(はなし)の下げ(オチ)は、「九ツ」と「四ツ」という江戸時代の時間の数え方を知っているか知っていないかでその面白さがずいぶんとちがってくるように思えるし、現代よりもずっと「一年」という区切りの単位が重かった時代の噺(はなし)だからこそ、「芝浜」のおかみさんは「大晦日」に真実を告げるのだと合点がゆく。「夢」が「現実」に変わるとしたら、そのタイミングはまさに一年の変わり目にしかありえないからである(以上は、読みながら勝手に感じたぼくの解釈)。ほかには、じっさいに著者が「東海道」を日本橋から京都まで歩いたときの体験から語られる江戸の人々の「歩き」にかんする考察も、ふだんそんなこと考えたこともなかっただけにおもしろく読んだ。
ぼく自身は知らなかったのだが、著者は週刊誌などで活躍する人気コラムニストとのこと。読むひとのなかにはその軽い口調が気に障るひともいるかもしれないが、落語や町人が活躍する時代劇などに関心のあるひとにとっては、おそらくきっと興味深く読めるのではないかな?
江國滋『落語無学』
2012.2.19|review
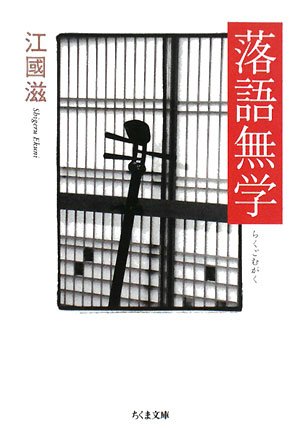
さいしょ「江國滋」という名前からなにやら堅苦しい評論めいたものをイメージして身構えたのだが、いざ読み始めてみればなんてことはない、とても軽やかな落語コラム集。
なるほど江國滋というひとは「落語」についても書くのかぁと思ったら、もともとフリーとして出発したときの肩書きは「演芸評論家」だったのですね…… 無知でスイマセン。そしてこれは、さまざまなところに発表したコラムをまとめて単行本化した『落語三部作』のなかの一冊とのこと。
批評をしようというのではなく、ひとりの落語愛好家として「落語の世界」に「生きる悦び」を思いのままに語るその言葉は、やはりおなじように「落語の世界」に魅了されるものの心にまっすぐ届く。音楽でいえば「嬉遊曲(ディヴェルティメント)」のような肩のこらない愉しさが、この本にはある。
「間(ま)の芸」を特徴とする江戸落語に対し、上方落語の最大の特徴にして魅力を「饒舌の芸」とする「上方落語の魅力と特質」と題された短い論考でも、著者は、その特質を知ることで「上方落語」というまた魅惑的な風景と出会えることを約束してくれる。否定したり、貶したりくさしたり、そういった言説の一切登場しない読んでいてとても気持ちのいい一冊だった。
安藤鶴夫『巷談 本牧亭』
2012.5.5|review

まず、「雨の降ることに感謝し、晴れて、喜び、風が吹いてもありがたいと思い、雪が降っても、ああそうか、と思う」そんなふうに淡々と、ただ「芸」にのみ生きる講釈師「桃川燕雄」の端然とした佇まいが魅力的だ。
変わりゆく昭和の東京の片隅で、ただ一カ所、講談の定席としてその灯を守りつづける「本牧亭」がこの「ものがたり」の舞台。「生まれたときからの寄席の娘で、それがもう血になっている」と自他ともに認めるおかみさんの「おひで」をはじめ、寄席の常連や「芸」のこと以外はからっきしダメ人間といった風情の芸人たちの愛すべき姿が、ここではまるで子供がだいじな「宝物」を抱きしめるかのように、やさしく描かれていて感動する。そうだ、そうなのだ、寄席はたんなる劇場(ハコ)ではない。寄席とは、さまざまなひとがそれぞれに、ちいさな喜びや悲しみによって結ばれたとてもとても人間臭い、ちいさな「町」のような場所なのだと、この「ものがたり」は教えてくれる。
ある日、若い興行師「湯浅」は、思いを寄せる娘義太夫「桃枝」のたっての希望で生まれて初めてローラースケート場を訪れる。カラフルな洋服を身にまとった若者たちに混じって、大音響で流れる流行の音楽にのって颯爽と滑る「桃枝」。その姿をひとり2階の見学席から見守りながら、「湯浅」はてっきり自分と同じ世界で同じ空気を吸っていると信じていた「桃枝」が、あたかも変わりゆく東京の風景のように自分からどんどんと遠ざかってゆくような気分にとらわれ、その恐怖とも孤独とも言いがたい感情におののく。そしてその焦燥が、やがて「湯浅」の人生を思わぬ方向へと狂わせる。
移りゆく時代の波に翻弄されながらも、不器用に自分らしく生きようとする心やさしき人たちの姿がここにはある。
松本尚久『落語の聴き方 楽しみ方』
2012.5.14|review

ナルホドソウイウコトカ。「落語」の最大の特徴を、「歴史」とは切り離された「時間」、語り手と聴き手とが回転木馬のように「同じ時間を生きる」ことにあるとして、歌舞伎や演劇、講談や能、アニメやコミックなどと比較しながら解説したとても興味深く、説得力のある一冊。
日本史の知識も時代劇への関心もさっぱりないにもかかわらず、うっかり「落語」にハマってしまった超初心者としては、かねがねこんなことでは「落語」を存分に楽しめないのではないか? というコンプレックスにも似た感情があったのだが、伝統芸能としての「落語」はいまひとつの過渡期にさしかかっていると著者が言う第8章「現代の落語」を読んで、ほんのわずか救われた気になったのだった。
ここで著者は、現代の噺家が担わなければならない課題として「距離」という問題を挙げる。つまり、落語に描かれた情景や風俗からすっかり遠ざかってしまった現在、落語の語り手は「みずからの位置とはなしの距離を ー その遠さを ー 」厳密に定め、示さなければならない。そうして、その「距離感」から「遠景としての八五郎や与太郎を、あるいは隅田川や長屋を現在に出現させる」ことではじめて、現代の落語は「芸」として成就するのだ、と。
つまり、落語の語り手がしっかりその「遠さ」を定め、示すことさえできれば、江戸時代や明治時代の情景や風俗とはさっぱり無縁な現代を生きているボクのような聴き手でも、いっしょに「回転木馬」にのって八五郎や与太郎の暮らす長屋を訪ねたり、春の隅田川でのんびり船遊びに興じたりすることができるというわけだ。
ひとまずは、目の前にそんな「情景」を出現させてくれるような噺家を追いかけてみようと思う。
和田誠『落語横車』
2012.5.20|review

ダールが好きだったりブラッドベリが好きだったりするのと同じように、落語のSF的な、奇想天外な噺に惹かれると言うイラストレーター和田誠。
ここには、そんな和田誠による創作落語が5編(うち4編は『和田誠寄席』にて実際に小三治、小朝、扇橋、二ツ目時代の雲助らによって口演されたもの)と、口演時に催された際におこなわれた山藤章二らとの座談会、そして落語にまつわるコラムのいくつかが収められている。
コラムでは、ホール落語の企画にかかわっていた若いころの話(このあたりの話は自伝的エッセイ『銀座界隈ドキドキの日々』でも触れられているが)が中心。まだ志ん朝が朝太、談志が小ゑんと名乗っていた時代の話だ。当時のジャズメンの落語好きをとりあげた「落語とジャズ」などは、落語家とジャズマン、その双方と交流のあった著者ならではのエピソードで「或る時代の証言」としても興味深い。
正直、個人的には、すでに存在する「古典」にスパイスをふりかけたかのような和田誠の「落語」はさほど面白いとも思えなかったのだが、おなじ噺を著者による「原本」と小朝による「口演バージョン」とで並べて読むといろいろなことに気づかされて興味深い。そこで小朝は、サゲを含む全体にわたって「換骨奪胎」と呼んでいいほどの大胆な改変をおこなっているのだが、その一方で、そこにこそ「書かれたもの」から「語られるもの」への跳躍、そのためにことばが必要とする筋力のようなものが垣間見られてただただ感心させられるのである。
堀江敏幸『いつか王子駅で』
2012.5.23|review

「待つこと」をめぐる私小説風の考察。
「待つ」ということにかんしていえば、たしかにぼくらはふだん、「なにがしかの静止状態」という程度のざっくりとした捉え方しかしていないかもしれない。ところが、主人公である「私」はそうではない。「おなじ静止状態でも『待機』と『待つこと』の内実には天と地ほどの開きがある」とかんがえている。そのうえで、「なんの役にも立たない拱手(きょうしゅ)とは無縁の待機」こそが「『待つこと』の本質」なのだと言う。では、待機ではなく、待つこととは?
回遊魚、生き方を左右するような思考の足首、心ののりしろ……
ポツポツ顔をのぞかせるこれら独白とも謎掛けともつかないフレーズに、作者はいつもながらなにがしかの「正解」を用意してくれているわけではない。だから読者もまた、カステラの箱を抱えて途方に暮れながら正吉さんの戻りをただ待つほかない「私」ともども、じぶんにとっての「待つこと」がもたらす「無為の極み」について、舌の上で飴玉を転がしてはその存在感を確認する子供のように、ただただ思いめぐらすことになるのである。
ところで、最初の数ページを開いただけで部屋の片隅に放り出したままになっていたこの本を数年ぶりに掘り出してきたのは、先日そのタイトルにもなっている街で開かれる落語会にたまたま出かけることになったからにほかならない。東京に生まれ育ちながら初めて降り立ったその街を、小雨の降る中しばし散策し、遠回りを覚悟でわざわざ路面電車に揺られて帰路についた。それゆえ、あらすじとは無関係とはいえ「先代は品川辺の、通いの旦那とほがらかな心中未遂でも起こしたくなるような店に勤めていて」というあきらかに滑稽噺の「品川心中」を思い起こさせる一節を文中に発見したときには、この作者との相変わらずの相性のよさを(勝手に)確認し、思わずにやりとさせられた。
吉川潮『江戸前の男―春風亭柳朝一代記』
2012.5.29|review

落語家、5代目春風亭柳朝の伝記小説ではあるけれど、ある典型的な「江戸っ子」の破天荒な一代記として読んでも面白い。
一時は志ん朝、談志、円楽とともに「四天王」などと呼ばれながら、他の3人とくらべるとどうも地味で影の薄い印象のある柳朝だが、この本を読むとそれもまたこのひとの「江戸っ子気質」に理由があったのか、と納得できる。
「自分が主役でないと思ったら、一気に隅のほうに引っ込んで悪あがきを見せない。石にかじりついてでも、ここで逆転してやろうなどという根性がない。淡白、見栄坊、恥ずかしがり屋……」
とはいえなにより落語が大好きで稽古熱心、「芸」で他の3人に劣っているというわけではまったく、ない。とりわけ「大工調べ」や「宿屋の仇討」といった噺では、その切れのいい江戸っ子口調や啖呵で魅せてくれる。そしてまた、惣領弟子の一朝師匠をはじめ現在寄席で活躍しているお弟子さんたちに、その「粋」な芸風がしっかり受け継がれているのはまったくもって素晴らしいことだと思う。
北村薫『夜の蝉』
2012.6.5|review

「私と円紫さん」シリーズの第2作とのこと。初夏から梅雨、そして盛夏のころが舞台となる。
前作とのいちばん大きな違いはといえば、物語の世界の規模が主人公を「軸」にぐっと狭まり、そのかわりより深くなったことだろうか。前作ではホームズとワトソンのようであった「円紫さん」と「私」の関係も、本作では主役はあくまでも「私」、「円紫さん」は謎解きの指南役といった役どころで一歩引いたかたちに収まっているように感じられる。その点、読後の印象も、ミステリよりは人情噺的な色合いを強く受ける。
読むことで感じるある種の生々しさは、前作よりも一段と「私」の内面に触れていることから生じるたぐいのものだろう。当然、その余韻もまた変わる。それは蝉しぐれのように、いつまでもシーンと頭の中に残響する。
北村薫『秋の花』
2012.6.10|review
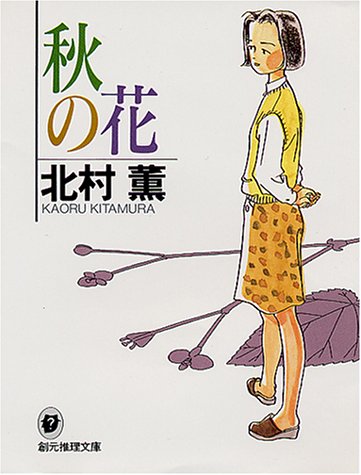
トリックは読み解けてもそこにカタルシスはない。むしろ残るのは、息苦しさ…。
幼なじみのふたりは、なぜこのような「事件」に巻き込まれなければならなかったのか? ふたりの出会い、なにげない会話や思い出…… そうしたエピソードがていねいに描かれ、それによって読者はそれが起こるべくして起こったこと、「偶然」のひとことでは片付けることのできない出来事だったことを思い知らされる。それはまた、主人公である「私」にも、そして読者にも、いつ起こっても不思議ではないということでもある。その厳然たる事実が、読むものを不安にし息苦しくさせるのだろう。
「私と円紫さん」シリーズ第3弾であるこの『秋の花』は、いわゆる「事件らしい事件」が起こる点、そして長編であるという点で明らかに前2作とはちがっている。物語の「軸」はますます「私」の日常へとシフトし、終盤近くなって登場する「円紫さん」もトリックを解明しはするが解決はしない。とはいえ、推理小説の体裁をとりながら、人間の感情の深い部分に触れようという著者の意志は第3作であるここでも一貫している。
北村薫『六の宮の姫君』
2012.6.13|review

へぇ、こういう「ミステリ」もアリなのか…… と驚き、戸惑いつつも一気に読み終えた。
いかにして芥川龍之介は短編「六の宮の姫君」を書くに至ったか? が、この「円紫さんと私」シリーズ第4弾となるこの作品をなす「謎」である。とはいえ、その底に流れるものは(よりミステリらしい風貌をした)前作『秋の花』から変わっていない。それは「操られるように巡り会い別れる」人と人との「繋がりの不思議さ」である。
コテコテの文学少女(死語? いま風に言えば「本ガール」?笑)である「私」が、親友の「正ちゃん」やバイト先の上司「天城さん」、文壇の長老「田崎先生」、そしておなじみ「春桜亭円紫師匠」らとの問答(キャッチボール)を通して徐々に「謎」の核心に近づいてゆくさまを描いた、静かに高揚してゆく唯一無二の「文壇ミステリ」。
最後に引用される親友にあてた無邪気な手紙の一節が、なんともいえない切なさをもって心に迫る。
北村薫『朝霧』
2012.6.16|review
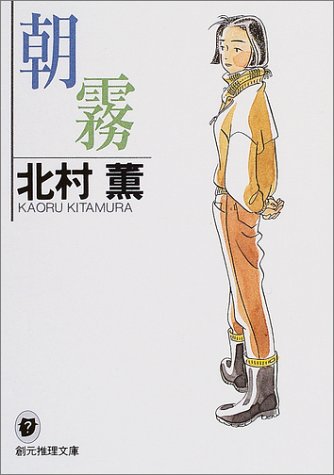
霧の中にあるものの姿は見えないけれど、そこにあるはずのものを思い、心を寄せることはできる。
北村薫の「円紫さんと私」シリーズはこれが第5作にして、いまのところ最終作。最後に収められた『朝霧』は、このシリーズを象徴するかのような珠玉の短編。
ひとを想うことの尊さが、そこにはある。
──
◎ 追記〜「円紫さんと私シリーズ」を読んで
これは、《探偵》と《探偵見習い》の話だと思った。
《探偵》はナゾを解く。でも、それは難解な殺人事件などではなく、ひとが生きてゆくなかでしばしば出会うナゾである。そのナゾは、人と人とが出会い、また別れる中でさまざまな姿をもって出現する。だから、そのナゾを解くには誰かが書いた《知識》に頼るだけでは解くことはできない、ヒントにはなりえたとしても。ひとを想い、心を寄せることではじめて解き得るナゾなのだろう。知識だけでなく、ひとの心の機微に精通した「円紫さん」は、そのことを辛抱づよく《見習い》である「私」に教えてゆく。「私」の成長とともに「円紫さん」の出番が減ってゆくのは、だから当然のことなのだ。ふたりはまさに「師匠」と「弟子」なのだ。
ところでこのシリーズはまだまだ続くのだろうか? たしかに、「朝霧」の最後のセンテンスは「続き」を暗示するようにもみえる。けれども、と同時にそれはまた「リドル・ストーリー」なのだとも思える。「その後」は読者の手にゆだねられた。きっと、そしてそれは少しばかり淋しいことではあるけれど、これで「完結」なのだろう。
小谷野敦『21世紀の落語入門』
2012.6.21|review

うーん、「21世紀の」というよりも「天の邪鬼のための」落語入門?
本文中うなづける箇所も少なからずあるのだけれど、読み終わってなんとなくモヤモヤっとした感じが残るのは、かゆいところにあと一歩のところで手が届かないからだろうか?
たとえば、「私は『現場主義』というのが嫌いなのである」と主張する著者が「寄席に行かずともよい」と言うとき、当然というべきかその「理由」を聞きたいと思ってしまうのだが、それがすっきり明かされないのである。名画は、やはり海外の美術館へ行ってでも「現物」に触れなければという意見に対する著者の回答は、こうである。「飛行機に乗れないこっちとしては、けっと言うほかない」。うーむ。著者がなぜ飛行機に乗れないのかはよくわからないが(タバコが吸えないから?)、「現物」に触れずとも名画を楽しむことができるという説得力十分な「理由」を知りたいところではある。これだとむしろ、もし飛行機に乗れたらホイホイ行っちゃいそうな印象すら受けるのだけど……。
著者は、「落語を聴くには寄席に行くべし」とか「現在活躍している落語家を聴くべし」といった思考が(じっさいはわからないが)最近の落語好きのあいだの「主流」と感じていて、そういう「風潮」に対して「いや、落語にはもっとちがう楽しみ方もあるよ!」というのが言いたくて、勢いでこの本を書いたんじゃないだろうか? そんな気がした。
ちなみにぼくは「録音」、しかも「志ん生」の録音(「品川心中」)から入ってまったく聞き取れず、悔しくて何度も聞き返しているうち7回目か8回目で突然、頬にサーッと品川の海風を感じたような気がして、それをきっかけについ半年ほど前から落語にハマった人間なので、著者が言うように過去の名人の録音でも十分落語はおもしろいと思っているが、行けるものならできるだけ寄席にも足を運びたいと思っている。著者とちがって寄席の雰囲気が好きということもあるが、それ以上に、「テキストが確定していない」落語ならばこそいまこの時代の聴き手として、自分の感覚に合う落語と出会いたいという気持ちが強くあるからである。
入江相政『侍従とパイプ』
2012.6.26|review
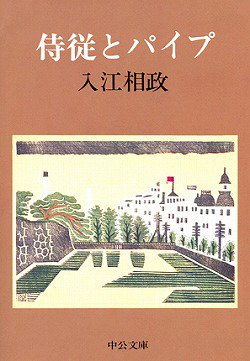
「人間 天皇」の《プロデューサー》とまでは言わないが、侍従・入江相政の目からみた昭和天皇にまるわるエピソードの数々は、終戦後のあるエポックに、かなりの破壊力をもって「現人神」という神秘のヴェールを取り去り、国民に人間味あふれる人物として天皇を印象づけるに十分だったのではないか。たとえば、御巡幸で訪れた四国の片田舎での「事件」は、「現人神」から「人間」への過渡期(昭和25年)に人々が「天皇」という存在をどう受容したかを物語るとても興味深く、かつ可笑しいお話だ(「お上とお風呂」)。
収められた文章ではやはり、「皇室」での知られざるエピソードを綴ったものが断然読んでいて楽しいが、一方、この本の後半、「侍従」という特殊な立場から離れて書いた文章にもこのひとのエッセイストとしての豊かな天分は感じられる。個人的に印象に残ったのは、他人の評価にいともかんたんに押し流されてしまう「日本人のたよりなさ」について書いた「流されて」、戦後、焼け跡にできた防空壕を改装して一家4人、庭でジャガイモやカボチャを育てつつ暮らした際の思い出をつづった「壕舎記」など。特に「壕舎記」からは、敗戦後の日本人の腹をくくった強さ、したたかさのようなものがある種の手応えとともに伝わってくる。
「今から考えればあのころは『なりふり』をかまう必要はないし、教養とかなんとかいうものはとっくにどぶに捨ててしまったし、ただ食うことだけ考えていればいいような、いっそすがすがしい時代だった」
こういう心持ちをバネにしてこそ、ほんとうの「復興」はかなうものなのかもしれない。著者がまだ若かった折、父親が建ててくれた家とともに息子に贈った「この家がお前の競争者だ…」という言葉の重みもすごい。すごすぎる。むかしの市井の人というのは、こんなにもすごいことを言うものなのか。すっかり感心してしまった(「中間搾取」)。
武田百合子『犬が星見た―ロシア旅行』
2012.8.19|review
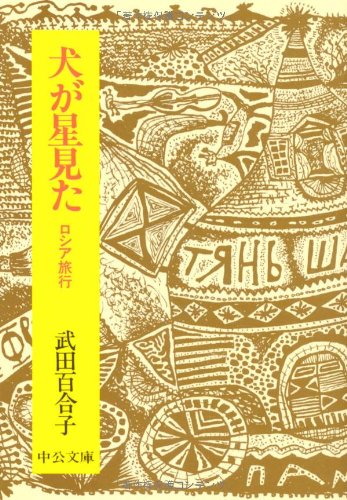
ただの紀行文ではない。それはたとえて言えば、《武田百合子カメラ》がとらえたスナップ写真を集めた一冊のアルバムである。
武田百合子という「カメラ」は、グルジアの首都にゆったり横たわる川をこんなふうに写し撮る。
「クラ河は緑青色に光って流れない。この河はいつ見ても流れていない。」
クラ河は「まるで流れていないように流れる」のではなく、彼女のレンズにはそれは「流れない」のだ。そこになにがしかの「意志」でも潜んでいるかのように。
また、彼女のレンズには降り立つカモメの姿態に思いがけず「官能性」を見出す瞬間もある。
「灰色と白のぼかしの胸もとや羽のつけ根が、女の二の腕や脇の下を見せられたようで、はっとする」
読んでいて、武田百合子の文章があたかも無造作に撮られたスナップ写真のように感じるのは、それがときに非情なまでのクールなまなざしに貫かれているからというのももちろんあるのだけれど、それと同時に、彼女が「旅の時間」の非日常性を理解しているからではないだろうか。彼女は旅の途中、幾たびもこんなふうにつぶやく。
「いまは一体、本当は何時なんだろう。今日は何日なのだろう」
そうつぶやきながら、彼女は「旅の時間」とは日常から切り離された瞬間、瞬間のただ積み重ねにすぎず、いま体験しているこの時間さえもテーブルにばらまかれたスナップ写真の一枚に過ぎないのだと悟るのだ。そしてそれは「クラ河」の水面同様に、流れない。
「いくつもの睡蓮の花のかたちの中から水を湧きこぼしている噴水。アメリカ人らしい旅行者の一団がやってきた。池のまわりを歩き、ベンチに腰かけたり、あたりを見まわしたり、写真を撮り合ったりしている、喉をのけぞらして笑ったりしている。
『旅行者って、すぐわかるね。さびしそうに見えるね』
『当たり前さ。生活がないんだから』」
武田百合子と武田泰淳。この会話に、ふたりの心の固い結び目をみる思いだ。
柳家喜多八・三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎『落語教育委員会』
2012.8.24|review
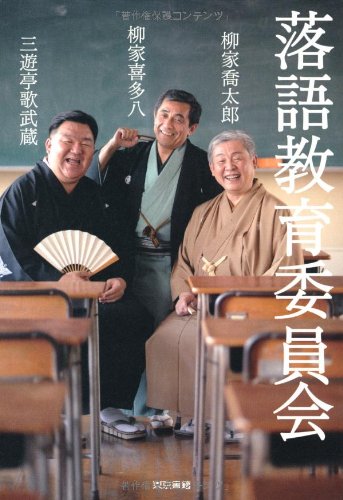
同タイトルの落語会をシリーズで開催する噺家3人による対談集。
「教育委員会」という看板をタテに(?)なかなか踏み込んだ会話もしているあたり、ふだんそういった類いの話がこちら側には伝わってこないぶん興味深い。
そういえば、登場する3人のうちのひとり柳家喜多八師匠が出演した落語会に出かけたときのこと、終演後会場にいた主催者にむかって「なんで落語って事前にネタを予告しないの?」と食ってかかっている客がいたのだが、奇しくも喜多八師本人がこの本の中でその「答え」を語っている。
「でもほんとうは、トリというのは格好をつけなきゃいけないのよ。見栄をはらないとね。(中略)前にどんな噺が出てきても、それにかぶらないネタは持ってるぞ、と。まあ、ハッタリというか、見栄というか」(118頁)
つまりは、噺家の「美学」ってことですね。
他に、芸人という立場からお客さんについて語っている「噺家の了見、お客さまの了見」も面白い。個人的には、それがライブである以上よりよい芸と出会いたければ「よい客」になるのが早道とかんがえるので、ここに語られている内容はいろいろ参考にもなった。なかには、
「ツイッターとかブログとか、個人の自由だからいいんですけど、責任とらなくていいのに発言できることを知っちゃったでしょ?
憶測でものを書くくせに記名制じゃないから、責任をとらない」(喬太郎師)
などという辛口の意見も。そういう「無責任」な発言が勝手にひとり歩きしてゆくのがインターネットの世界であるというのは飲食店をやっている人間として身にしみて知っているだけに、まったく同感。発言することが問題なのではなく、匿名で、責任をとる必要のない環境で言いたいことだけ言う風潮が問題なのですよね、つまり。
宇野信夫『はなし帖』
2012.9.5|review

「やあ、しぐれだしぐれだ」と相好を崩してはしゃぐ六代目菊五郎。初めて京都を訪れるという著者に、「まず京都の時雨を見せたい」と張り切って案内する歌舞伎の名優。ついに願が通じたのか、ある古刹で時雨に遭遇した折、その口をついて出た「ことば」がこれだ。
役者の台詞と思えばいかにも作為的なものを感じなくもないが、そうではない。むかしのひとの、それは世界への感受性の豊かさを物語る台詞であり、思わず口をついてでるこうした日々の「ことば」が、反対に名優の台詞を豊かに肉付けしてきたのだろうと思わせる。
紺屋の倅に生まれ、浅草橋場で生まれ育った著者はこうしてさまざまな人々と交流し、その豊かな「ことば」に触れてきた。植木屋や大工といった職人、物売り、志ん生をはじめとする芸人たち。だからこそ、この本を読むと、そうした市井の人々の暮らしが手に取るような感触をもって伝わってくる。
しかしそんな市井の人々の暮らしは、ある出来事を機にふっと消滅する。「戦争」である。著者はけっしてここで戦争について語っているわけではないが、市井の人々の暮らし向きの変化を物語るエピソードを介して、ぼくにはこの本がなにげに立派な「反戦歌」になっているような気がしてならないのだけれど……。
藤井宗哲『寄席―よもやま話』
2012.9.6|review
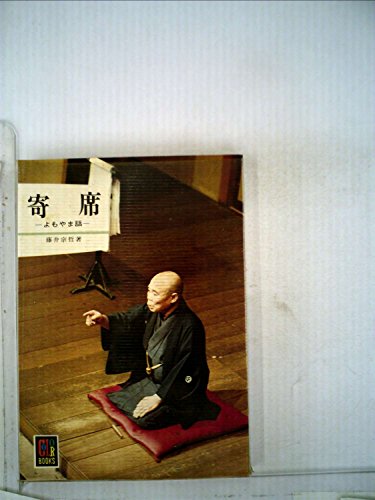
ときに「浮世の学問所」とも呼ばれる「寄席」という場所にスポットをあてた興味深い一冊。
著者は寄席で、「江戸や明治のころの職人や、武士や、さまざまな人たちの考えかた、生活ぶりなどの知識を得た」ばかりではなく、それらを通じて「人間として生きてゆくうえでの価値判断、そういったことまで教わりました」と語る(「はじめに」)。それはおそらく、いまもむかしも変わらないのではないだろうか?
ただノスタルジーをかきたてられる場所というだけでは、三百年以上も「寄席」は生き残れなかったろう。
カラーブックスらしく、寄席や寄席を支える人々の姿、そこに登場する芸人たちの表情、客のたたずまいなど興味深い写真も多数。だが、それ以上に興味深かったのは『醒睡笑』に始まり、上方、江戸における「中興の祖」たちの存在、そして三遊亭円朝から現代へと至る落語の変遷を、色物もまじえつつ「寄席」という場所が形成されてきた歴史としてまとめた巻末の解説文。たとえば、いまでも頻繁に口演される「野ざらし」という有名な落語が、明治期に活躍した三遊亭円遊によって現在のような滑稽噺として改作されたのはよく知られるところだが、そこには円遊なりのやむにやまれぬ「事情」があったことなど、この一文を介して知ることができた。
小沼丹『黒いハンカチ』
2012.10.22|review
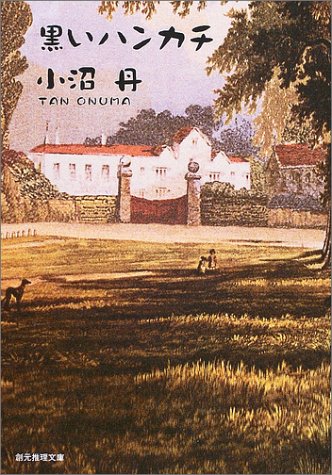
このミステリには、「洒脱」の風が吹いている。昭和30年代に女性雑誌の連載モノとして発表されたのがもともとだそうだが、「古めかしさ」は50年という時間を経てかえってほどよい「異国情緒のようなもの」に転化している。
さらりとした文体にも、日常のなかにちいさな「気づき」として表れるトリックを見破るカギにも、作者が、肩肘張らず必要最小限の「ことば」でもってこの小説を書こうと試みていただろうことが感じられる。最初のうち、あたかもそれが重要な小道具であるかのように扱われる「太い赤い縁のロイド眼鏡」がいつのまにか登場しなくなるあたりは、連載が進むにつれ主人公「ニシ・アズマ」のキャラクターがそれじたいで十分に魅力的に成長したせいだろうか。
たとえばジャック・ロジエが撮った短編映画のような、12本のかわいい探偵小説集。
芦原すなお『ミミズクとオリーブ』
2012.10.28|review

時計の針でいえば20分くらい、この物語の登場人物たちはズレている。
だいたい、事件のナゾを解くのは、割烹着姿でオリーブの木にやってくるミミズクを餌付けするような主婦なのだ。
「天然」と呼ぶにふさわしい中年小説家の夫も、その友人も、みんな一定の幅でズレている。ついでにいえば、食卓に並ぶ旨そうな食事の数々も、いわゆる家庭料理と呼ぶには微妙にズレた凝り具合だ。
いってみれば、そこは時計の針で20分くらいズレた世界、異次元なのだろう。むしろそこでは事件に巻き込まれる人々はみな、ふつうに映る。
ふつうの人々がふつうに生きようとあがくとき、そこに「事件」は生まれる。ふつうの世界とは、そういう「哀しみ」に溢れた世界なのだ。
登場人物にあわせて「20分」くらい視線をずらすとき、読者は自分の生きるこの世界の「哀しみ」にはじめて触れ、驚愕する。
柳家小里ん『五代目小さん芸語録』
2012.11.15|review
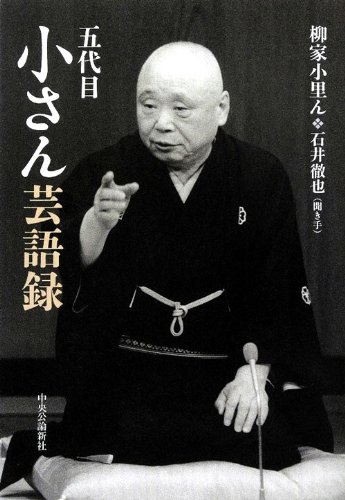
「落語は季節感と情景と人物が描ければ自然に面白くなる」「無駄なことは絶対に言うな」……。
この本は、五代目小さんの内弟子として、師匠の高座のみならずその「ことば」に数多く接してきた柳家小里んへのインタビューを通じて、五代目小さんの「芸」の精髄を後世に伝えるべくまとめようと試みた意欲作。
小さんがたびたび高座にかけた噺54席について、
①その噺の「型」がどこから伝わってのか?
②五代目を介してどのように広まっていったか?
③それぞれの噺の「勘所」はどこにあるのか?
を探ってゆく。五代目小さんについていえば、一般には芸談をあまりしないと思われていたというが、弟子が直接もしくは間接的に耳にしたその「ことば」は、簡潔でありながら物事の胸ぐらを瞬時にとらえるような迫力にみちていて、まさに噺の「急所」といったところ。落語を聴きこめば聴きこむほどに味わいを増す一冊といえそう。
「落語は大衆芸能じゃない。落語を本当に好きな奴のもんだ。大衆に合わせると落語のよさはなくなるよ」。コンビニとファミレスだけの世界なんて、たしかに便利にはちがいないが味気ないよね。
阿刀田高『Aサイズ殺人事件』
2012.12.6|review
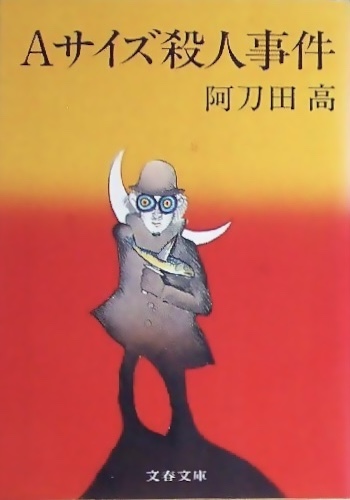
僧侶が囲碁の相手をしながら、そこで耳にしたわずかな情報をたよりに事件の謎解きをするという、いわゆる《安楽椅子探偵》モノの短編集。
北村薫の「円紫さん」にせよ、戸板康二の「中村雅楽」にせよ、「黒後家蜘蛛シリーズ」の「ヘンリー」や『九マイルは遠すぎる』の「ニッキイ・ウェルト教授」、『黒いハンカチ』の「ニシ・アズマ」にせよ、こちら側の世界に属していながらもどこか超然とした浮世離れしたところがあるのがぼくの考えるところの《安楽椅子探偵》の魅力であるのに対し、たぶんに狙ってのことではあると思うが、この阿刀田高の作品に登場する「方丈さん」はその個人的な理想像とはあまりにもかけ離れている。というよりも、むしろ正反対。ぼくにとってはその存在がややノイジーに感じられるが、これは完全にぼく個人の趣味嗜好の問題なのでなんともいえない。面白くないわけでは全然ないのだけれどね……。
読書にも、登場人物との相性というのがあるのだなと再確認。
小林信彦『紳士同盟』
2012.12.7|review

詐欺をテーマにしながらも、黄金時代のハリウッド映画を彷彿とさせる軽快かつ洒脱な娯楽小説。些細なスキャンダルをきっかけに次々と不幸に見舞われる(ちょっとカウリスマキっぽい)とあるテレビマンが、はからずも戦後の混乱期からバブル直前の80年代にまで及ぶ壮大な詐欺(コンゲーム)に巻き込まれてゆく。
カドカワ黄金期のアイドル映画の原作というイメージが強くなんとなく手を出さずにきたが、読んでビックリ最後の最後までダレさせない展開で面白いし、なにより犯罪小説ながら後味が悪くないのが好み。そして、薄っぺらくも、まだキラキラしていたころの東京の街の描写がなつかしい。
バロネス・オルツィ『隅の老人の事件簿』
2012.12.16|review
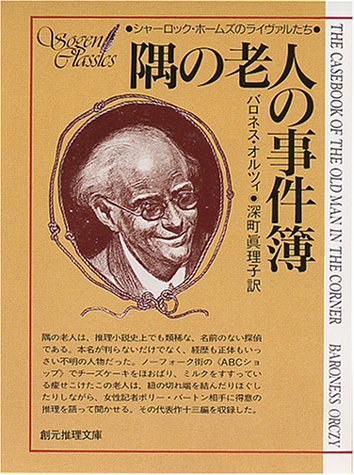
探偵、というよりはナゾトキスト!?
いつものカフェのお気に入りの席に陣取って、若き女性記者相手に楽しげに事件の謎解きをしてみせる怪しげな風貌の老人が主人公。最後の最後まで老人のプロフィールはおろか、名前すらも明かされない。
ミステリ好きの間では、この主人公をして「安楽椅子探偵」の最初期の一人と位置づけるひとも少なくないようだが、事件のたびに「検死審問(インクエスト)」まで出かけては、証言のみならず証言台にあがる人々の表情からその心理を読み取りつつ複雑に入り組んだ謎を解き明かしてゆく老人は、強いていえば「半=安楽椅子探偵」ということになるかもしれない。
ところで、おなじ「怪しげな風貌の老人」でも、「きょうはね、私は、ちゃんとやりますよ」と言いながら手にした紐を器用に操るのは寄席に登場する奇術師のアサダ二世だが、この老人も謎解きの「付属物」としていつも手にした紐に結び目をこしらえたり、ほどいたりしてみせる。そして、あたかも固い結び目をほどく仕草が謎解きの暗喩であるかのように、隅の老人は言うのだ。「あらゆる謎には解答がある。そしてわたしの経験によれば、もっとも単純な答こそ、つねに正しい答であるのさ」。
舞台は19世紀末から初頭のロンドン、上流階級の人々が次々と登場する物語は、ミステリ初心者にして、現代ニッポンの一般庶民には少しばかり分かりづらいものだったが、『黒後家蜘蛛の会』同様、繰り返し読むことで面白さが増してゆく本だと思う。
都筑道夫『砂絵くずし―「なめくじ長屋捕物さわぎ」傑作選』
2012.12.19|review

境界上の人々。奇体な香具師たちが巣食う江戸きっての巣乱(スラム)、ひと呼んで「なめくじ長屋」。その「なめくじ長屋」の住人にして砂絵師の「センセー」が、仲間たちの手も借りつつ江戸の町に起こる怪事件の謎を解き明かしてゆく短編集。
フィンランドで活動していたプロダクトデザイナー梅田弘樹さんとおしゃべりをしていたとき、日本人のつくるものには《湿度》がある、とおっしゃっていてなるほどと納得したおぼえがあるのだが、たしかに以前読んだ阿刀田高(『Aサイズ殺人事件』)にせよ大阪圭吉(『銀座幽霊』)やこの都筑道夫にせよ、不思議とその行間から《湿気》が立ちのぼってくるような気がする。主人公の「センセー」も、「センセー」をたよりに手柄を立てる岡っ引き「下駄常」もけっしていわゆる「善人」ではなく、人の心の光と闇をそのまま映し出す「鏡」のようなキャラクターとして描かれる。それゆえ、たんなる趣向としての「江戸時代」ではなく、庶民のあけすけな「生」への意志が充溢する「闇鍋」のような空間として、作者は舞台を「江戸」に選んだのではないだろうか。現代が舞台では、こんなふうに生き生きとマージナルな人々は活躍できなかったろうから。
主人公の生業が「砂絵師」であることから、推理に砂絵が役立つのかと思えばそうではないところが意外といえば意外。収められたもののなかには、「首つり五人男」や「らくだの馬さん」のように落語から着想を得たと思われるものも。作者と「推理小説マニアの従弟」とのゲームから生まれた「天狗起こし」「小梅富士」は、それゆえ「必然性を見いだすのに、かなり苦労した」と言うが、読者としてはその迷走しながら結論へと向かう道筋にむしろスリリングな読みごたえをおぼえる。最後に収められた「人食い屏風」のみがやや毛色が異なるが、物語的な面白みはいちばん。
加納一朗『ホック氏の異郷の冒険』
2012.12.24|review

痛快冒険活劇風ミステリ。欧化政策と国粋主義のはざまで揺れ動く明治時代の東京を舞台に、何者かによって盗まれた秘密文書のゆくえをめぐりイギリス人の探偵サミュエル・ホック氏(S・H氏)と医者の榎元信のふたりが協力して秘密の捜査に乗り出すという話。
幾多の障壁に行く手を阻まれながらも、西洋の知性と東洋の知性とが互いに補い合いながら事件の核心へと近づいてゆく、その様がなんといっても楽しい。また、大物政治家や男爵夫人、見世物小屋の人々、歌舞伎役者、壮士、警官、芸者などさまざまな「人種」が入り乱れて事件をややこしくしているのも、文明開化直後の東京の、そのメルティングポット的な様相を伝えるようで刺激的。
たまたま蔵の中から発見された、曾祖父の手記とも創作ともつかない文章をひ孫である「私」が現代語訳するという趣向が、読み手にほろ苦さを感じさせるエピローグで生きてくる。個人的には、いつも肝心なところで……
な梶原刑事がツボ。
出久根達郎『安政大変』
2012.12.30|review
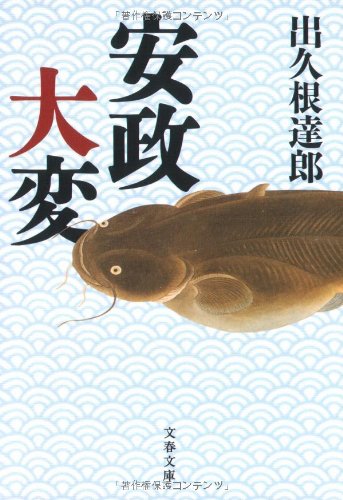
1855年の「安政江戸地震」を題材に、その発生前後の市井の人々にスポットをあてた短編小説集。
赤鯰も、群れをなす百足や季節外れの蒲公英も、夜鷹が口にする土のぬくもりや幕末の藩士が酒毒のせいと思う「揺れ」も、振り返ればすべて大地震の前兆にちがいないのだが、そのそれぞれが登場人物たちの人生に重ね合わせられることで、いつしか読者は人間の「生」について深く考えている自分に気づくことになる。巧いなぁ。
大地震や度重なる大火に幾度となく家や仕事を失いながらも懸命に生きる江戸の人々の姿は、だが、けっして哀れでも惨めでもない。むしろこの世の無常を理解しているからこそ、いまを生き抜く彼らの姿は強く、たくましい。
ジョセフィン・テイ『時の娘』
2013.1.8|review
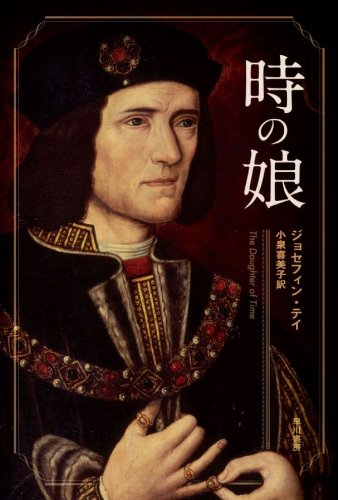
ロンドン市警の腕利き刑事が、その巧みな推理力によって犯人と目された《男》の疑惑を晴らし、真犯人を追い詰めてゆく……。というと、ごくありきたりな推理小説に思われるが、その疑惑の人物というのがイングランド王《リチャード3世》という歴史上の人物、しかも刑事は不慮の事故により現在入院中、ベッドに寝たきりの身というところが、なんといってもこの小説の設定のユニークなところ。
まず、「捜査の基本」に立ち返って歴史的なエピソードから不確かな伝聞を剥ぎ取ることで、登場人物たちを「ひとりの人間の姿」に戻してゆく手際が鮮やか。助手役をつとめるアメリカ人青年とのやりとりにもユーモアが感じられる。途中、英国史に無知ゆえとっつきにくい箇所も多々あったが、それでも一気にラストまで読んでしまった。さすが、ミステリ通のあいだで「名作」と呼ばれる一冊だけのことはある。
戸板康二『團十郎切腹事件―中村雅楽探偵全集1』
2013.1.14|review

歌舞伎役者「中村雅楽」が、不可解な事件の《なぞ》を解く人気シリーズ。老優・雅楽のたたずまいがとにもかくにも魅力的で、つい手に取ってしまう。
この第一巻に収められているのは、江戸川乱歩の後押しで世に出ることになった「車引殺人事件」をはじめ、初期に書かれた18の短編。なかには、第42回直木賞を受賞した表題作「團十郎切腹事件」も含まれる。これは、ナゾの自殺を遂げた八代目市川團十郎の有名な事件を、およそ百年後に「中村雅楽」がなぞ解きするというもの。若い時分に耳にした知人の昔話をきっかけに、次第に切れ味を増してゆく「雅楽」の推理に圧倒されるが、じつはこれ、ジョセフィン・テイの古典『時の娘』への秀逸なトリビュートとなっている。過去の歴史的事件のなぞ解きという構成はもちろんのこと、「雅楽」がその推理を披露するシチュエーションも、人間ドッグで入院中のベッドの上という凝りよう。
どうやら、戸板康二という作家は「無」からなにかをひねり出すよりも、実在するさまざまなものを巧みに組み合わせて新たな魅力的な存在を生み出す天才のようで、それはまた「中村雅楽」というキャラクターの造形にも活かされている。巻末に収められた自身による作品ノートによると、「雅楽」の名は中村歌右衛門と酒井雅楽頭を組み合わせたもの、老優の語り口などは親しくしていた歌舞伎界の古老・川尻清潭から、そのほかにも岡本綺堂『半七捕物帳』やエラリー・クイーンのミステリに登場する「ドルリー・レーン」などもヒントにしているとのこと。こんな具合にさまざまな影響を直接的間接的に受けながらも、「中村雅楽」がまったく独自の魅力的キャラクターとして生き生きしていることに感心せずにいられない。品格と威厳を兼ね備えた老人でありながら、無心で推理に没頭するその様子はなんとも無邪気で微笑ましい。
シャーロット・アームストロング『毒薬の小壜』
2013.1.19|review
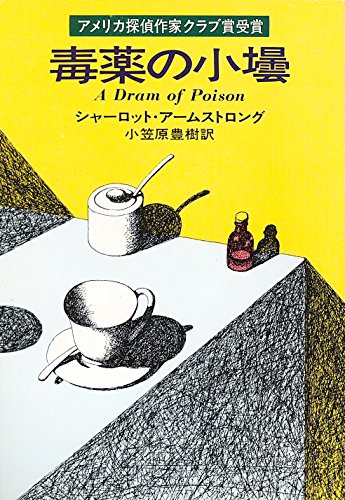
「善意のサスペンス」(by訳者)。あるいは、「善人だらけの毒薬さがし大会」!?
全体は、大きくふたつに分けられる。主人公の男が自殺を決意するまでを描いた前半は、心理描写が中心で登場人物もごく少なくやや退屈でシリアスな印象。とはいえ、時折あらわれるフレーズが後半になって生きてくる。再読推奨。一転、失われた毒薬の行方をめぐって一挙に登場人物がふえる後半は、突如にぎやかに、そしてコミカルに。映像的にいえば、前半はモノクロで後半はフルカラーという感じかな?
ハッピーエンドということもあるが、とにかく読んでいてじわじわ楽しくなってくる。話の発端は奇妙だが、落語のようでもあり、モーツァルトのオペラブッファのようでもある。
連城三紀彦『運命の8分休符』
2013.1.23|review

もっさり、愚直な珍探偵。ルックスも性格も鈍臭い上に、ワケあって定職にもつかず日々ぼーっと過ごす「軍平クン」のもとには、どうしたわけか続々と美女から難事件が持ち込まれてくる。
鈍臭い軍平クンのこと、当然その推理力も「カミソリのように」というわけにはいかない。あくまでも愚直に、ひたすら奥歯にはさまったモヤシの筋を取り除くかのように、あるいは牛が食物を反芻するかのようにモゴモゴとゴニョゴニョと事件のナゾを解いてゆく。その細々とした事柄をスルーできないじれったい性格が、彼のもっさりとした印象のゆえんであると同時に、また誠実さの証しでもある。
トリックはどれも凝っているが、ひとの先入観のウラを突いてくるという点でどれも共通している。そして、そういうトリックに「あっ」と「気づく」ことができるのは、なにより軍平クンの愚直さあってこそ。ミステリであると同時に、たいがいのひとがスルーしがちなそういう軍平クンの魅力をよりによって美女たちが見抜いてくれるという点で、この小説はまたなかなか甘やかなファンタジーでもある。
※「北村薫が選ぶミステリー通になるための文庫本100冊」からの一冊。
三島由紀夫『花ざかりの森・憂国―自選短編集』
2013.1.23|review
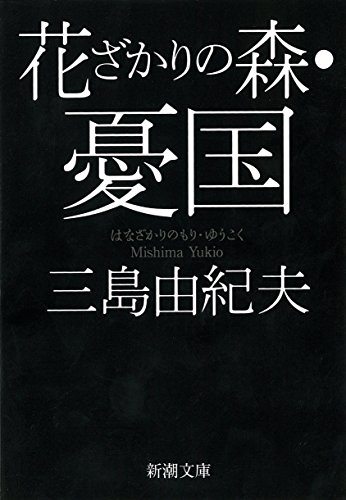
1956年のロールプレイングゲーム。七つの橋を、ひとこともしゃべらず、また誰からも声をかけられず渡り切ることができれば願い事が叶う。そんな迷信を信じて、四人の女たちが夏の宵闇へと繰り出すのだが……。
「橋を渡る」という単純な行為が、一つクリアしたのをきっかけに他愛のない《遊戯》から、いつしか興奮と陶酔、抜き差しならない緊張を孕んだ《儀式》へと様変わりしてゆく。そのプロセスの描写がじつに見事。「願事(ねぎごと)」にみずからの幸せを託すしか生きようのない女たちが繰り広げる、静かなるスラップスティックコメディー。
※『橋づくし』のみ
柳家花緑『落語家はなぜ噺を忘れないのか』
2013.1.28|review

噺が身についているから、落語家は噺を忘れない。
その「さおだけ屋はなぜ潰れないのか」的なタイトルから、《落語家が明かすマル秘暗記術》のような内容を期待するときっと肩すかしを食うだろう。落語家が噺を忘れないのは、ただ台詞を暗記しているだけではなく「立体的に」覚えているからだと著者は言う。それが「噺が身につく」ということであり、それはただただ稽古の賜物でしかない。ではいったい、落語家は噺を身につけるためにどんな具合に稽古を重ねているのか?この本の「肝」は、そこにある。
個人的には、花緑師が演じる『笠碁』がいままで聴いた誰の『笠碁』とも違うため、いったいその「型」がどこからやってきたのか知りたくて手にしたため、最後まで興味深く読むことができた(第4章「自分のネタを作る〜『笠碁』への挑戦」が、そのまま花緑版『笠碁』の誕生秘話(?)となっている)。これを読んで、花緑版の『笠碁』が、いわば伸び縮みする「時間」感覚という視点から再構築されたものであることがなるほど、よくわかった。ただ、「時間」という視点なら、従来どおりのサゲでもけっして矛盾はしないようにも思うのだけど。水滴が落ちてくるのも忘れて笠をかぶったまま碁盤にかじりつくおじいちゃんの大人げない様子から、碁を打とうにも相手がいない、そんな「待った」の日々の長さが手に取るように伝わってくるから。
落語家はどのようにして噺を自分のものにするか。落語好きなら読んで損はない、落語家の「了見」がよく伝わる一冊。
北村薫『玻璃の天』
2013.2.2|review
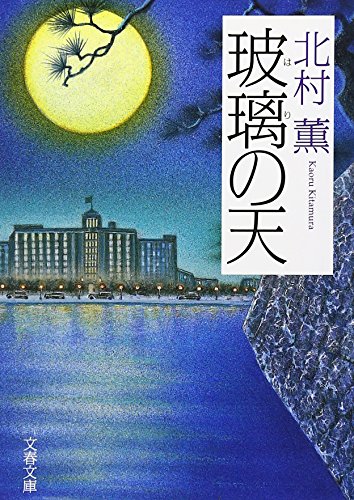
ミステリという「形式」を借りながら、テーマはいよいよ骨太に、作家はますます饒舌になってきた印象。《ベッキーさんとわたし》シリーズ第2弾。
1930年代、軍国主義に突き進む日本。その渦中に否応なく巻き込まれてゆく上流階級の人々を描きながら、そこはさすがに「日常のなぞ」の名手、けっして韓流ドラマ的臭さを読者に感じさせないのはさすがである。むしろ抑制された筆致だからこそ、かえって徐々に暗雲に囲まれてゆくような不穏さがあるのもたしか。
主人公が、ある宴で出会った若い軍人にむかって思わず語る言葉こそ、また、作者北村薫の思いでもあるのではないか。「わたしのいう自由とは、基本的な徳に向かう行進の中で、右を向き左を向く自由です。鳥の声に耳を傾け、空の雲を見る自由です」。
ここでその正体が明らかになった「ベッキーさん」こと別宮みつ子が、続く第3弾でどのような役回りを演じることになるのか、ますます楽しみになってきた。
北村薫『鷺と雪』
2013.2.4|review

☆5つでは足りないくらい。《ベッキーさんとわたし》シリーズ第3弾にして、完結編。
最後に収められた表題作が、圧巻。シリーズ3作を立て続けに読んだせいもあるが、すべての物語が、まるで大きな時計を見ているかのように、ここに向かって刻々と運命の時を刻んでいたのだとわかる。第一作が「服部時計店」に始まり、この最終作がおなじ「服部時計店」で終わる構成も、そう思えば時計のように精巧だ。
月、能面、カメラ……さまざまなメタファーを通じて、この『鷺と雪』では目にみえるものの向こうには、じつは広くて深い目にみえないものが存在していることが暗示される。ことばの向こう側に、ことばにできない「思い」を汲み取ること。それは、(目前に迫った)自由にものが言えない時代にこそ大切な「力」であり、また「生きる糧」ともなるだろう。それを、ベッキーさんはその職分を超えてまで、わたしに教え諭そうとする。
「その日」を前にして、桐原侯爵の長男で軍人の「勝久」様が「ベッキーさん」に問いかけたことば、叩き上げの陸軍少尉「若月」が三冊の詩集を介して「わたし」に託したことば……。そのことばの向こうにある、思い。勝久と若月、ベッキーさんとわたしの、ドッペルゲンガー。そしてドッペルゲンガーには、不吉なイメージ、死の前兆が重なるという。
ことばの向こうには思いが、ある。その思いは、往々にしてことば以上に多くを物語る。その思いをひとが汲み取る手がかりは、ただことばしかない。その意味で、北村薫というひとは「ことば」のもつ力を信じている。
泡坂妻夫『亜愛一郎の狼狽』
2013.2.7|review

とぼけた味わいと軽みが身上の、コミカル・ミステリー・ツアーへようこそ。
「笑い」とは「緊張と緩和」だと言ったのはたしか、哲学者カントだったろうか?
イケメンなのに不器用で運動神経ゼロというこの小説の主人公にして探偵役「亜愛一郎」の存在は、まさにこの小説では破壊力抜群な「緩和」そのものとして機能している。だから、陰惨な殺人事件が起こるにもかかわらず、読者はたびたび読みながら吹き出さずにはいられない。巧妙なトリックに裏打ちされたミステリと脱力系ユーモアとが奇跡的なバランスで両立しているのだ。
地味な飛行機爆破予告を発端に、残忍な殺人事件の背後に潜む思わぬ動機が明かされる第一話「DL2号機事件」などは、いきなり意表をつくようなタネ明かしにキツネにつままれたような気分にさえなるが、それが日頃「雲」や「虫」など多くのひとがあまり気にもとめない自然観察にばかり熱中しているカメラマンによる推理と聞けば、なるほどその推理力というよりも並外れた観察眼に脱帽してしまう。ここには8つのストーリーが収められているが、全編そんな常識や先入観の裏をかくようなトリックが目白押しで飽きさせない。
ただ、毎回登場する「三角形の顔をした老婦人」はともかくとして、第一話に登場する柔道家の女の子とはいったい何者なのか?
あまりに意味ありげに登場するわりにトリックにはまったく関わってこないという……不思議。
*北村薫が選ぶミステリー通になるための文庫本100冊
北村薫『謎のギャラリー―謎の部屋』
2013.2.12|review
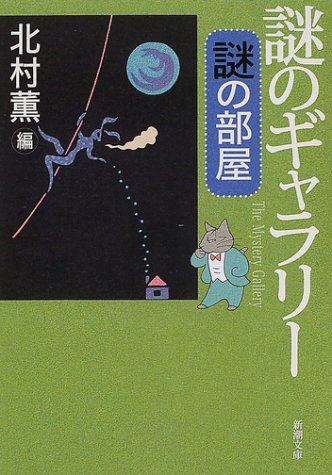
自称《本格原理主義者》、アアルトコーヒーの庄野さんにすすめていただいた一冊。
北村薫が、《謎》をキーワードに選んだ古今東西の16人の作家による短編を収めたアンソロジー。さまざまなタイプの作品が含まれるが、CDにしても個性的な選曲家の手によるコンピレーションを好む自分としては、そこに「北村薫」というひとの個性も感じつつ最後まで楽しく読書した。
「謎の部屋」というこの本のタイトルにふさわしく、宇野千代/東郷青児コンビによる超現実的で、しかもどことなく淫微な匂いを放つ物語でいきなり冒頭から読者を煙に巻く。その余韻を引きずりながら読む阿部昭『桃』は、なんというかとても官能的に映る。同じトーンは次の作品『俄あれ』(里見弴)にもつづく。途中で気づく、「にわかあれ」というタイトルのダブルミーニングはなかなかパンチが効いている。終わり方はあまり好みではないとはいえ、吉祥寺が舞台の『遊びの時間は終わらない』は、落語「だくだく」を想起させるストーリーともども親しみをもって読んだ。
「昔、私が柘榴の実の中に住んでいた頃……」と始まる『柘榴』を書いたカリール・ジブランというひとは、「あとがき」として収められた宮部みゆきと北村薫との対談によればレバノン出身の作家とのことなのだが、その寓話のような語り口といいアルメニア出身の映像作家パラジャーノフの『ざくろの色』を彷彿とさせる。レバノンとアルメニアがおなじ文化圏といえるかどうかはわからないが、メタファーとしての「ざくろ」はこの一帯においてはなにか特別な意味を持つのだろうか?
これはまた、べつの《謎》。グロテスクでありながら、神話のようでもある『豚の島の女王』、星新一のショートショートにも似た『どなた?』もおもしろい。おなじ立場に追い込まれたら、たぶんぼくもこの主人公とおなじ態度をとるだろう。諦観こそ幸福への近道、か?
タネあかしの見事さに思わず唸らされるのは、ハードボイルドな『定期巡視』。『猫じゃ猫じゃ』『埃だらけの抽斗』のふたつは、銀行もの。どちらも後味があまりよくないのは「カネ」にまつわる話だからだろうか。最後に収録されたゴフスタインの絵本『私のノアの箱船』は、いってみれば映画のエンドロール。「謎の部屋」を後にして日常へと読者が戻るきっかけ。一服の鎮静剤!?
なかでも、マージャリー・アランというひとの『エリナーの肖像』は個人的にいちばんおもしく読んだ一編。イングランドのマナーハウスを舞台に、そこで変死した少女の遺志を一枚の肖像画から読み解いてゆくという本格ミステリー。恣意的に感じられた要素のすべてが、彼女を愛していた周囲の人々の記憶の助けを借りつつジワジワと焦点を結び、最後には犯人の姿をくっきりとあぶりだす。探偵の登場しないこの物語では、《謎》は彼女を慕う人々の《愛情》の力があってはじめて解き明かされるのだ。そこに言い得ない感動が生まれている。
出久根達郎『御書物同心日記 虫姫』
2013.2.15|review
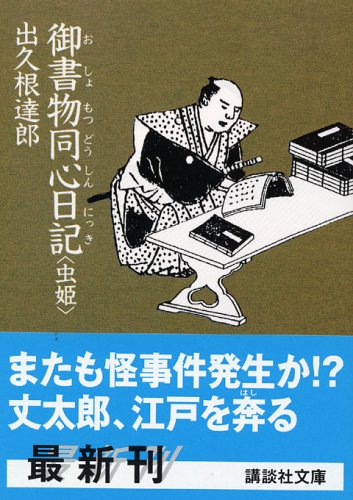
それでも、退屈至極な日々はつづく……。将軍家の蔵書番、御書物同心の「退屈至極な日々」を描いた大好きなシリーズの第3弾。
前作に続きこの《虫姫》でも、丈太郎は「本の虫」に似つかわしからぬ勇猛な一面を見せる一方(「虫姫」「州崎」)、恋愛については相変わらずの奥手ぶりが微笑ましい(「鷽替」)。
このシリーズ、けっきょく事件らしい事件はなにひとつ起こらない。事件というよりもそれは、市井のひとびとの日々にポツンとついた「しみ」のような出来事にすぎない。けれども、読み進むにつれて登場人物のひとりひとりがそれぞれ、心の裡になにがしかの《なぞ》を隠したミステリアスな存在に思えてくるのがおもしろい。ひとの心の奥底に秘められた《なぞ》は、あるとき不意に顔をのぞかせることもあるが、むりやり暴き立てたり解き明かしたりしないほうがよい類いのものなんじゃないだろうか?というのも、「安穏さ」とは、その「暗黙の諒解」の上にあってはじめて成立しうるものだと思うからだ。だから、丈太郎を取り巻く世界の節度をもった「安穏さ」が、ときにとても美しく、かけがえのないものに映るのだろう。
柳家小満ん『べけんや』
2013.2.23|review
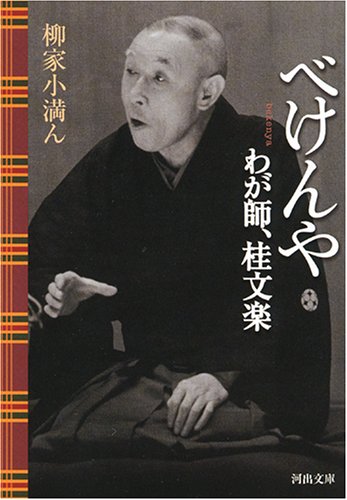
たとえば、第3章「師匠の食事」。
なんて「美しい」朝食なのだろう。名人・八代目桂文楽の「芸」から受ける ─端正、緻密、モダン、色気─ といった印象のすべてが、毎朝「黒門町」の長屋で繰り返される、さながら「儀式」のようなその食事風景からも同じように感じられたのは驚きである反面、また当然のような気もした。まさにその「人」こそが「芸」そのものであり、そういう生き方が許された時代、いわば「巨匠の時代」の芸術家なのだろう(その点で、「修業中の弟子の目からみた師匠」という切り口は同じでも、立川談春の『赤めだか』とは決定的にちがっているように思われる)。
その意味で、この『べけんや』に綴られた桂文楽というひとのことばや振る舞いは、その芸をより深く理解する上で役に立つことはあっても、けっして邪魔になるということはないように思う。
また、「伝説」ともいえる「勉強し直してまいります」というよく知られる台詞がとっさに口をついて出た文句ではないと知るとき、文楽というひとの「引き際」に対する美意識に感心するとともに、その、自身をみつめるまなざしの峻厳さには凄みすら感じる。師匠の死後、著者(柳家小満ん)が五代目小さんの元に引き取られることになった経緯なども静かに感動的なエピソード。
G.K.チェスタトン『ブラウン神父の童心』
2013.3.4|review
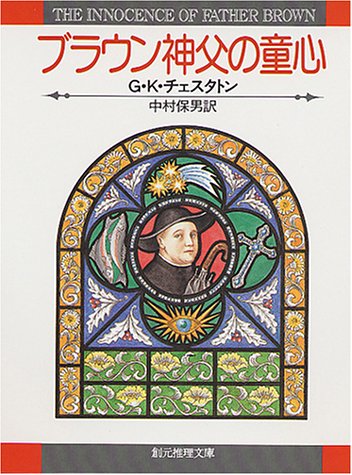
なじみのない人種(カトリックの神父さん)が主人公ということでなんとなく敬遠していたのだが、読んでビックリ問答無用のおもしろさ。
ぜんぶで5冊、51編あるという「ブラウン神父」シリーズのうち、この『ブラウン神父の童心』はその第一作である。
最初に収められた「青い十字架」では、その後「相棒」のようにたびたび登場する「フランボウ」との馴れ初めが語れる。読者の予想をいきなり裏切るかのような思いがけない結末を迎える「秘密の庭」、密室の中で、聞こえてくる足音だけをたよりに見事犯人をつきとめる「奇妙な足音」と前半3つのエピソードだけでも十分楽しめる。変わったところでは、プロファイリング的手法で歴史上の「英雄」の意外な素顔を暴き出す「折れた剣」なども面白い。
古風な文体やさまざまな宗派を揶揄したような人格描写など分かりづらい部分、ピンとこない部分も多々あるものの、イングランドの牧歌的風景の中で繰り広げられる推理譚は昼下がりや夜更けの読書にまさにうってつけ。主人公の「ブラウン神父」は、いかにも鈍重な印象の人物が事件に直面するやいなや冴えた推理力を発揮するという典型的なタイプの探偵だが、どこか人を食ったようなとぼけたキャラクターがたまらない。個人的には戸板康二の「中村雅楽」同様、長くつきあいたい人物である。
アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 2』
2013.4.3|review
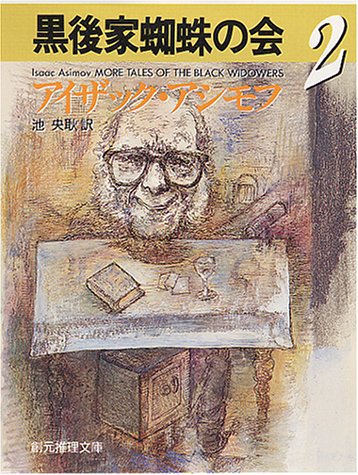
いよいよ面白くなってきた…のは、たぶんこのシリーズを読むのも2作目となり、《ブラック・ウィドワーズ》の面々の多彩なキャラクターがこちらの頭になじんできたせいもあるだろう。
じっさい、作者のトールキンやコナン・ドイルへの偏愛から生まれたとおぼしき『殺しの噂』や『終局的犯罪』、文字や発音など言語のもつさまざまな側面がカギとなる『三つの数字』『省略なし』などアシモフの博覧強記ぶりがますます冴える、言いようによっては重箱の隅っこを突くかのような作品が前作以上に並んでいる。よって、ミステリというよりは、《ブラック・ウィドワーズ》の面々&ヘンリーの会話を部屋の片隅からワクワクしながら聞き耳立てる知的好奇心を刺激するストーリーとして楽しんだ、といったほうが正しいかもしれない。そして、けっきょく3作目にも手を出してしまうのだろうな…(アシモフの思うツボ)
三遊亭円朝『三遊亭円朝探偵小説選』
2013.4.3|review
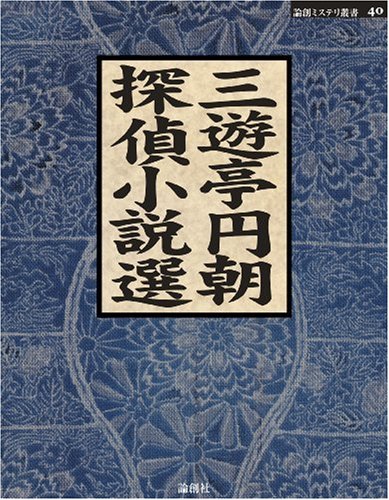
「落語中興の祖」三遊亭円朝が「翻案」を手がけたミステリ(あるいはサスペンス)仕立ての物語5編を収めたアンソロジー。
円朝といえば「真景累ヶ淵」「鰍沢」「死神」「怪談牡丹燈籠」といった名作落語の作者として、また円山応挙をはじめとした幽霊画のコレクターとして知られる大名人であるが、ここでは翻訳ではなく翻案というとおり、モーパッサン『親殺し』(→『指物師名人長二』)などの海外文学を人づてに聞き知った円朝が、同時代の市井の人々にも理解しやすいよう舞台や登場人物を日本に移し、また言文一致体に直すと同時に、部分的に原典にはないシーンや人物を登場させることでよりテンションの高い作品にまで磨き上げた珠玉の《創作》作品が取り上げられている。
収録されているのは、
『英国考子ジョージスミス之伝』
『松の操美人の生埋』
『黄薔薇』
『雨夜の引窓』
『指物師名人長二』
の5作品。表題には「探偵小説」とあるがべつに誰かしら「探偵」が登場し謎解きをするわけではなく、どれもどちらかといえば「ミステリ的要素、あるいはサスペンス的要素の強い人情噺」といった趣きである。
円朝というひとはつくづくモダニストであったのだと、ところで、このアンソロジーを読むとよくわかる。ひとつには、やむにやまれぬ事情があったといはいえ芝居噺の世界を離れ、扇子と手ぬぐいのみであとは「ことば」の力だけによる素噺へと転向、近代落語のひとつのスタイルを築き上げた改革者であるという点で。もうひとつには、みずから江戸時代に生まれ江戸の美学を貫くことに執心しつつも、明治維新後の近代国家の礎を築いた思想家や文学者などと積極的に交わることで、異文化をどん欲にみずからの「芸」に吸収していったという点で。円朝による《翻案》のプロセスについては、それが比較的明らかな「指物師名人長二」についての考察「『名人長二になる迄』〜翻案の経路」が余録として収められているので、それを読むと面白いと思う。
江戸から明治へ、その移り変わりを「激動の時代」と呼んで片付けてしまうことはかんたんだが、実際そこに居合わせた人々にとってはとても容易には受け容れがたい、しかし差し迫った大問題であったにちがいない。思うに、この《翻案》という作業は三遊亭円朝にとって、「落語」という芸を「要」として、江戸と明治というふたつの時代を結びあわせ、乗り越え、受容するためのひとつの試みだったのではないか。その意味で、円朝はその翻案物を通じて同時代の、同じ境遇を生きる市井の人たちのための「水先案内人」をみずから買って出たのだ、とぼくはなんとなくかんがえずにはいられない。心やさしき名人の姿がそこにある。
堀江敏幸『アイロンと朝の詩人 回送電車3』
2013.4.7|review

雨音に催促されるようにして、積ん読の山から掘り出してきてポツポツと読み始める。
堀江敏幸の書く散文は、どこか音楽に似ている。ポンと心を打つ響きもあれば、よそよそしく響く和音もある。時間を経て、抽象的な響きの奥からひょっこり顔をのぞかせるひとなつこい旋律がある。そしていつもこのひとの散文を読むとき思うのは、そこに置かれた「ことば」を読むことでもたらされる余韻のようなものに浸りたくて読むのだ、ということである。そこで鳴らされる音以上に、それによってもたらされる余韻に浸りたくて聴くモンポウの音楽のように。
個人的に大好きな天野忠翁の詩とともに、柔らかく、軽い「むかし」が行間からこぼれ落ちる「メロンと瓜」、身の回りの壊れたものを必要にせまられて「取り繕う」行為から日々を送るということへ、アナロジーの飛躍が不意に視界が開けたかのような錯覚をもたらす「日々を取り繕う」など、いつもながらちいさな「気づき」に満ちた散文集。
矢野誠一『戸板康二の歳月』
2013.4.20|review

戸板康二の評伝。
① 名探偵「中村雅楽」のルーツを探って。
② 大正デモクラシーの落とし子たるモダニストの肖像。
ふたつの《視点》から読む。
① 作者みずから探偵「中村雅楽」シリーズのあとがきなどで明かしているように、このキャラクターは数人の実在する人物たちによるモザイクとして生み出されたものらしい。この評伝では、「推理小説作家」戸板康二についてはわずかしか触れられていないものの、その人柄に「親炙」する「若い友人」矢野誠一の目に映った戸板の言動は、どことなく、と言う以上に「中村雅楽」に似ている。著者、矢野誠一が強調するいかにも「山の手の東京人」らしい品格、人間関係における絶妙な間合いなど、まさに中村雅楽に通じる部分であり、大きな魅力のひとつといえる。
ちょっとしたことだが、この本の冒頭で披露される少年時の改名にまつわる戸板本人による安楽椅子探偵的な「推理」などに触れると、まさしく雅楽本人のようでついうれしくなってしまう。交友関係については、著者をふくむ「若い友人」たちに慕われ、始終にぎやかに囲まれていた反面、久保田万太郎や折口信夫のような一癖も二癖もある年上の「怪人」からも信頼され可愛がられていた。他方、同年代との腹を割った付き合いは苦手だったのか、あまり登場しないような印象を受けた(実際のところはどうだったのだろう?)。
② 物心ついたときに大正デモクラシーの空気を吸い込んで育った人物には、軽快で、やわらかい心のモダニストが多い。著者も本文中でその人柄をたびたび「しなやかな自由人」と評しているとおり、1915年生まれの戸板康二はまさにその世代の人物の特徴を持ち合わせているように思われる。じっさい本人にもそうした意識はあったようで、そのことは「兄は、つねづね自分がとてもいい時代に育てられたことを感謝していました」という弟の言葉からもわかる。戸板康二の「人のよさ」を説明するのに著者はおもに「山の手育ちの東京人」という点を強調しているように思えるが、それにくわえてやはり徒花のようにいっとき花開いた「大正デモクラシー」という時代の影も同じくらい大きな要素として取り上げられてよいだろう。
父親に連れられて行った「平和祈年東京博覧会」など本文で引かれているエピソードからも、その時代の開放的な空気や幼少時の甘い記憶が伝わってくる。だから、植草甚一や吉田健一といった東京という場所と大正という時間が生んだ稀代のモダニストとして、個人的には「戸板康二」という人間に魅力を感じずにはいられないのである。
山本嘉次郎『洋食考―食べものダンディ学』
2013.4.22|review
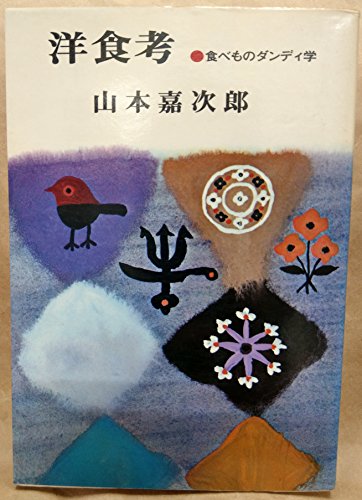
「いまの洋食のまずいのは、その匂いの良さを失っているからである」と映画監督であり、食通としても知られる著者は力説する。明治〜大正にかけての東京下町の食卓にあがる「下手(げて)な味」への郷愁、その味以上に魅力的な洋食の「不思議な魔法のような芳香」、その土地でしか出会えない味の数々……。
一章まるごと「親子どんぶり」に捧げた第2章では、「におい」を失った親子どんぶりを嘆き、「親子が退廃したのではない。文明が敗退したのである。いまの世の食物のまずさが、親子どんぶり一碗のなかに結集しているのである。昭和元禄文化の劣性が、親子どんぶりで象徴されているのである」などと壮大に持論を展開してみせる。
その一方で、酒を「コキン、コキンと飲んだ」、「紀州沖をすぎると、サンマはドカッと不味くなる」といった言語感覚もおもしろい。椎名誠じゃないよ。明治生まれ、執筆当時69歳のおじいちゃんの言葉である。ウスターソースの「A・ペリンズ」(リーペリン?)、「まめさんたいさん」(まめさんたいたん?)など記憶ちがいと思われる箇所もままあるが、ここは昭和のおおらかな仕事ということで大目に見ておくべきかもしれない。
しかし、「食べものダンディ学」などという素敵な副題を備えておきながら、それを打ち壊すかのような永六輔によるコメントを冒頭に引用するあたり、いかにも東京っ子らしいユーモア精神である。
海野弘『東京風景史の人々』
2013.5.5|review
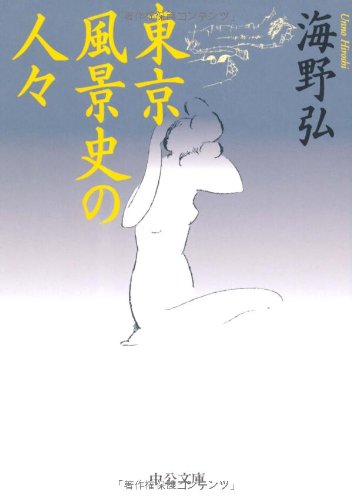
東京を、モダニストたちの歩幅でぐわしぐわしと闊歩したくなる一冊。『日本のアールヌーヴォー』で世紀末の、『モダン都市東京』で20年代の「東京」の姿をみごとに浮き彫りにした海野弘が、ここでは1910年代の東京をとりあげる。
20年代に花開く大正デモクラシーへの、どちらかというと過渡期とかんがえられてきた10年代だが、芸術家たちの意識の上である大きな変化が起こったのがこの時代であると著者は言う。具体的にいえば、00年代の画家たちにとって芸術とは「職業」を意味していたのに対し、10年代の画家たちにあって芸術とは「みずからの生き様そのもの」であった、と。
交通手段や複製技術の進歩によって相互に交流が生まれ、西欧の芸術運動と時間差なくリンクすることができるようになったことで「個」としての意識が日本の芸術家たちの中に芽生えたのがこの時代なのである。西洋/東洋という「空間軸」、明治・大正・昭和という「時間軸」ではなく、日本の近代アートを「年代」によって西欧のアートとひとつかみで捉える必要を著者が説くのはそのためである。
それぞれのエッセイすべてがするする読み進むことを邪魔するくらい刺激的であるが、たとえば「川端康成の都市彷徨」、東京をみつめる川端の「まなざし」のデリケートな変化をみごと逃さず捉えた論考の鋭さには思わず唸らされる。モダン都市東京の「へそ」がすでに浅草から銀座へと移った二十年代の終わりに、川端は浅草への「回帰」を力説する。「欧米の直訳」にすぎない銀座に対して、東京のどん欲な「胃袋」であり「大胆な和洋混合酒」である浅草に川端は日本独自の都市文化を生み出す可能性の中心をみたのである。そして、それはまぎれもなく三十年代の先鋭的な文化人ならではのまなざしといえる。日本主義や西洋と東洋の融合といった彼らのイノセントな思想は、やがて軍国主義にのみこまれることで骨抜きにされるだろう。
文学や美術が、「個」としての芸術表現であると同時に、その時代に生きた人々の息づかいを生々しく刻みこんだすぐれた都市表現でもあるということをこの本は教えてくれる。
高野正雄『喜劇の殿様―益田太郎冠者伝』
2013.5.10|review

ナゾ多き人物ではあるが、現代に続く「お笑い」の種をまいた人物であるという点ではまちがいないだろう。
三井財閥の発展に貢献した明治の大実業家の御曹司にして、数々の喜劇、レビュー、落語、小唄や端唄の作者として人気を博した益田太郎冠者こと益田太郎の評伝である。著者は元毎日新聞社学芸部の記者で、「ハイカラ通人」なるタイトルで獅子文六が連載する予定だった太郎冠者を主人公とした新聞小説の担当記者だった。ところが、いよいよ連載が始まろうというそのときに獅子文六が他界、獅子のために準備した取材ノートを元にいわばその遺志を継ぐようなかたちで書かれたのがこの本である。
太郎冠者のホームグラウンドは、みずから取締役を務めていた帝国劇場の「女優劇」だった。洋行帰りならではのバタ臭い笑いのセンスに大正期の観客たちは拍手喝采し、劇場はつねに大入りだったという。制作費が足りなくなると、毎度ポケットマネーで補って思い通りの舞台をつくるというほどの熱の入れようで周囲を唖然とさせた。なにせ、中学生の身分で品川の芸者を総揚げして自宅で宴会を開いてしまうほどの規格外の金持ちゆえ、そんなこともできたのである。しかし反面、それゆえ同時代の演劇人やインテリからは評判が悪かった。曰く「金持ちの道楽」。
太郎冠者は、帝劇の経営が松竹の手に渡った1930年を機に筆を折る。それにはさまざまな事情があったようである。個人的には、軍国主義へと向かう小さな足音が太郎冠者の耳には聞こえていて、もはや自分の出る幕ではないという思いがどこかにあったのではないか(時の警視総監、丸山鶴吉によるカフェー大弾圧は1929年のことである)。しかし一方で、太郎冠者のまいた種はあちらこちらで確実にその花を咲かせようとしていた。金龍館時代の浅草オペラの第一回興行では太郎冠者の手になる「唖旅行」が取り上げられているし、後には「コロッケの唄」や「おてくさん」が取り上げられ庶民の間でも大ヒットしている。また、関係者の証言をもとに、宝塚の『モン・パリ』や『パリゼット』といったレビューが太郎冠者の作品を下敷きに誕生したことを突き止めたのは著者である高野氏による大発見である。益田太郎冠者は、やはり日本の1920年代をつくったひとりであった。
それが「何か大正といふ時代を象徴してゐるやうな気」がするという理由で、久保田万太郎は自身が社長兼編集責任者を務める雑誌「日本演劇」に益田太郎冠者についての論評を書くよう渋沢秀雄に要請する。言論統制下にあった昭和二十年の話だ。なんの思想もなく批判もない、ただただ「笑のための笑、娯楽のための娯楽」(渋沢)をめざした太郎冠者の作品にあえてその時期スポットライトを当てようと考えた久保田の「思い」について、少し深く考えてみたい。少なくとも、そんな罪のない爽やかな「軽さ」に人々が笑い転げていた時代を、しばし振り返ってみたかったのかもしれない。
太郎冠者作の落語については、現在よく取り上げられるのは「宗論」「かんしゃく」「堪忍袋」といったところだろうか。寄席で頻繁に遭遇する「動物園」も太郎冠者の作だとする声もあるようだが、それを裏付ける証拠はいまのところないとのこと。晩年の太郎冠者から贔屓にされていた六代目春風亭柳橋は、「洋行帰り」という噺を太郎冠者に直接稽古をつけてもらったのだそうだ。「女天下」は、正岡容によれば、初代三遊亭圓左が舞台をみて落語化したとのことだが、正確なところはやはりわかっていない。現在では、六代目の蝶花楼馬楽を経て柳家小袁治師がしばしば高座にかけているようである。いつか聴いてみたいものだ。「かんしゃく」に登場する口うるさい主人は、なんでも太郎冠者にそっくりだそうである。つねに同時代や同時代人を容赦なくネタにして笑いをとることで人気を博してきた太郎冠者だが、ときには自分自身ですら笑いのタネにしてしまうその道化精神に、「余技」と呼ぶにはあまりにも徹底した《喜劇人》としての矜持を感じずにはいられない。
戸板康二『ぜいたく列伝』
2013.5.14|review
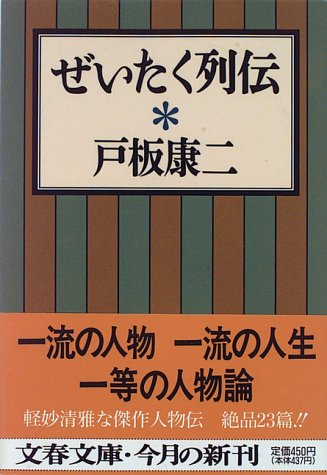
ぜいたくってなんだろう?「私自身は、ぜいたくな生活をほしいままにできる人間ではないし、また、しようとは思わない」と言う著者が、それでも魅力を感じずにはいられない「正しい意味で、ぜいたくな生涯を送った先人」たちを取り上げ、戸板流「ぜいたく」の定義を示してみせたのがこの本。
光村利藻の愛妾
十一代目片岡仁左衛門の豪遊
谷崎潤一郎の四季
吉田茂の白足袋
横山大観の富嶽図
大倉喜七郎のホテル
藤原義江の女性
内田百閒の御馳走
長谷川巳之吉の出版
徳川義親の虎狩り
西条八十のかなりや
小林一三の宝塚
堀口大学の月光
梅原龍三郎の北京
鹿島清兵衛のぽん太
花柳章太郎の衣裳
御木本幸吉の真珠
福地楼痴の團十郎史劇
益田太郎の喜劇
志賀直哉の座右寳
五代目中村歌右衛門の下げ髪
薩摩治郎八のパリ
西園寺公望の清雅
明治の大富豪から実業家、歌舞伎や新派の役者、芸術家らのそれぞれの「ぜいたく」が紹介されるが、そこはなんというか「戸板マジック」とでもいうのか、読み進めてゆくうちになぜかその人物に対して好感をおぼえてしまうのが不思議である。戸板康二は、人物を語るときつねに「加点評価」するひとである。ある人物の繊細なところ、独特のところ、鋭いところ、新奇なところばかりを巧みにすくいあげてゆく。意図的にというよりは、それはきっと戸板康二というひとの「人間のよさ」に由来しているという気がする。あとがきで「ぜいたく自身が人徳になっている人たちが、私にすがすがしい余韻を残してくれた」と語っているが、戸板康二というフィルターを透してこそ、読者もまたここに登場する人物たちの豪放な生き様に「すがすがしい余韻」を感じるのである。ぜいたくとは、「物質的な奢り」ではなく、ある人物をその人物たらしめている心の棲み処のようなものなのだろう。
海野弘『モダン都市東京―日本の一九二〇年代』
2013.5.23|review
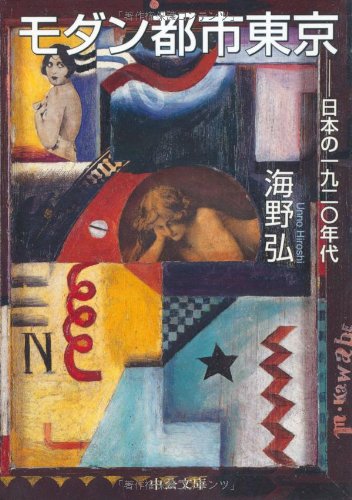
ここで語られる東京の20年代は、なぜこうも《苦い》のだろう。
大学生のとき夢中で読んで以来、ひさびさの再読。あらためて読んでも、やっぱり十分に刺激的な論考だ。明治期の画家のしごとから日本の世紀末を探った『日本のアールヌーヴォー』、おなじく大正デモクラシーの胎動期といえる1910年代を論じた『東京風景史の人々』とくらべると、この『モダン都市東京』は少しばかり読みにくい。小説や詩といった文学作品における都市表現から《20年代》(著者の定義によれば大正7、8年から昭和7年くらい)の東京を読み解くという試みのため、どうしても観念的にならざるをえないせいもあるだろうけれど、それ以上にやはりそれは《20年代》という時代のとらえどころのなさによるところが大きいのではないか。
「日本の《20年代》は失われている。それはまるで、存在しなかったかのように、切りとられ、前後がそれをはずして縫い合わされてしまっている」と海野弘は言う。多くの作家たちが東京という都市にあこがれ、東京を描こうと格闘しながらも、結果的に彼らは十分に都市を表現することでその時代を描き出す技法を編み出せないまま《都市》に別れを告げてゆく。その原因は、「ファシズムへと傾斜してゆく国家権力の弾圧による沈黙という外的なものであると同時に、都市表現の未成熟と行き詰まりという内的なもの」でもあった。じっさい、テクノロジーやメディアの進歩により東京は20年代、いまだかつてないスピードで変転していたし、作家たちにとっては影法師のようにするするとその手から逃れていってしまうような感覚だったにちがいない。そのあたりは、20年代を象徴する都市である「銀座」の特徴を、郡司次郎正、上司小剣、貴司山治らの作品から「すべてのものを出会わせ、混ぜ合わせ、媒介する」という空間性にあるとする第5章、第6章にくわしい。また、「雨の降る品川駅」という中野重治の詩に鋭い解釈をほどこした第11章は、「詩」を文学という局面からだけでなく、川柳や盛り場案内記、ルポルタージュなどをふくむ「都市表現」のひとつとしてとらえるべきと主張する海野弘の真骨頂で、全体の中でももっとも読み応えのある一章であった。
個人的な関心はこれまで、大正デモクラシーをつくった世代/大正デモクラシーを享受した世代にあったのだが、ここで取り上げられているのはいわば「大正デモクラシーを懸命に生きた世代」である。その多くは19世紀末に生まれた地方出身者であり、東京にあこがれ、その理想と現実のはざまで揺れ動きながら20年代に創作に打ち込み、30年代には失敗や挫折を経験する芸術家たち。この本は、彼らの格闘と挫折の痕跡に東京の《失われた20年代》を発見しようという試みであり、読みながら通奏低音のようにつきまとう《苦さ》の理由もまた、そこにある。その中では、雑草のように新宿に根っこをおろししたたかに生き抜こうとする林芙美子や平林たい子の姿は印象的で、一服の清涼剤となっている。
アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 4』
2013.6.1|review
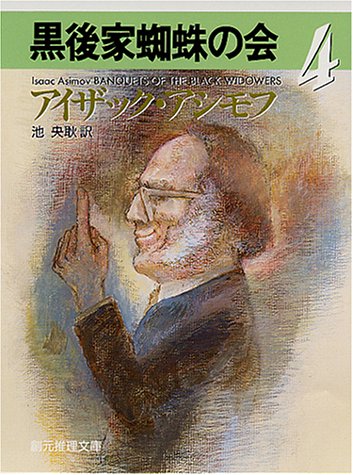
なぜか、この短編集では作家による「あとがき」が作品ごとに付されていて、このシリーズを読み出した当初こそ「これって必要?
蛇足じゃね?」と思っていたのだが、いつのまに、むしろちょっと楽しみに読むまでになってしまったのは、しばしば語られる初出時のタイトルをめぐっての《応酬》がことのほか愉快だからである。そして、その相手こそ、「エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン」の当時の編集長フレデリック・ダネイなる人物。
《応酬》とはいえ、作家本人によるあとがきゆえ攻撃は一方的なもので、たいがいは原稿を受け取ったダネイ氏によってあたえられたタイトルが「よろしくない」というものだが、ごく稀に、ダネイ氏によるタイトルの方に潔く軍配をあげることもある。けれども、その《応酬》の背景にふたりの強い信頼と友情が感じられなんともほほえましい限りなのだ。そう、ちょうど黒後家蜘蛛の会のメンバーにして、「犬猿の仲」であるルービンとゴンザレスのように。
内容は、第一巻から読んできたなかではこれがいちばん読みやすかった(逆に読みにくかったのは前刊)。読みやすいというのは、たぶんよりスノビッシュではないという意味で、そのぶん切れ味もやや鈍くなった印象もあるし、この巻ではこれまでにはなかった「椿事」が起こったりとそろそろ遠くに「黒後家蜘蛛の会」の終焉が感じられて愛読者としてはややしんみりした気分にもさせられる。残された最後の楽しみをいつ読もうか、目下思案中である。
PS.「フレデリック・ダネイ」なる人物について知りたくて調べてみてはじめて、エラリー・クイーンが「藤子不二雄」だという事実を知る。ハハハ
中村弦天使の歩廊―ある建築家をめぐる物語』
2013.6.6|review

″A House is not a Home″というバカラックの名曲を思い出す。明治から大正、そして昭和という激動の時代を舞台に、ひとりの「異端の」建築家の姿を6つのエピソードからあぶりだした不思議な風合いをもつ物語。
「家」とは奇妙なものである。たいがいの「家」は地面に建つ。物理的にはもちろんのこと、メタフォロジカルな意味でも、また。だから、ときに「家をもつ」ということはそのまま、そこに暮らす人間の〝現世への執着の現れ〟でもある。ところが、主人公・笠井泉二のつくる「家」はちがう。それは、現世に定着できず、ふわふわと宙空に舞っている依頼人の「思い」をかきあつめ、そこに納めてやるための「うつわ」、あるいは「モニュメント」のようなものとして描かれる。その意味で、主人公はみずから宙空を舞いながら人々のやりきれない「思い」を回収する、まさに天使的存在なのである。
彼の建築は普遍的ではないが、だれか一人のために役立つと語る、笠井の理解者である卯崎教授のことばが心にしみる。その後の主人公は、大陸でいったいどんな「街」をつくったのだろうか?
ほんのりとあたたかい心持ちで本を閉じた。
余談。主人公が暮らしているのは小石川植物園にほど近いところとなっているが、そこは当時「貧民窟」として知られた場所である。華族や実業界の大立て者をクライアントとし、みずからもけっして貧しくはなかったであろう主人公に自身の「家」としてあえてこうした土地を選ばせたところに、作者の、天上と地上とを自由に行き来する中間的存在に対する考え方を透かし見ることができておもしろい。装幀は、有元利夫が描いた作品であったなら……と個人的には思わずにいられない。
戸板康二『黒の狂女―中村雅楽探偵全集3』
2013.6.11|review
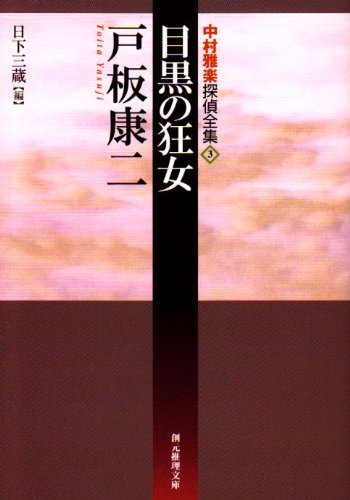
人間のよさ。戸板康二が描く「中村雅楽」という人物の魅力をひとことで言えば、そういうことになるのではないか。
鋭い観察力と洞察力とで身の回りに起こる「面白い」事件(「日常の謎」と言ってもいいが)を鮮やかに解決しながらも、そこにはいつも人間のあたたかい血の流れが感じられるのだ。それは、主人公「中村雅楽」が歌舞伎役者(しかも名門の出ではない)として人生の大部分を劇場で過ごしてきたことと無関係ではないだろう。役者はひとりでは生きられない。相方や脇役、裏方としてはたらくたくさんの人々、そして劇場に足を運ぶ観客がいてはじめて、舞台の上でスポットライトを浴びることができる。雅楽の、事件の当事者に対する慈愛にみちたまなざしはまた、そのように人は人を支え、人に支えられているという事実を彼がわきまえていることの証左であるだろう。
中村雅楽探偵全集の第3弾となるこの『目黒の狂女』では、これまで以上にそうした雅楽の「善さ」を感じさせる作品が多いような印象を受けた。このシリーズが発表年代順に収録したものであることからかんがえれば、そのような傾向にはこの時期(おもに昭和50年代)の作者の心境が映し出されているといえるかもしれない。この巻のおしまいに収められた『木戸御免』など、まさにそんな戸板流ヒューマニズムにあふれた佳作ではないだろうか。
そのむかし新劇が盛んだったころ、シェイクスピアの戯曲なども歌舞伎にならって見せ場だけを上演するようなことが行われていたらしい。雅楽の口を介してそんな大正期の演劇界の姿を知ることができるのもまた、このシリーズを読む愉しみのひとつである。
中村弦『ロスト・トレイン』
2013.6.12|review

はたして『銀河鉄道の夜』へのオマージュなのだろうか……?忌まわしい記憶とともに抹消された「まぼろしの廃線跡」をめぐるパラレルワールド譚。ふだんこの手の小説に縁がないため、こうした設定が古いのか新しいのかはまったく判らず。
人の一生というのは鉄道に乗るのと似ている、と鉄オタの平間さんは語る。「どこへでも自由に行けるかのように見えて、じつはそれほど自由があるわけではない」。すすむべき線路は一本ではなく、ところどころに乗り換え駅もあるけれど、うっかりすると「目指しているのとは全くちがう場所へ連れていかれてしまう」のだ。そんな平間さんが、ある日、忽然と姿を消してしまう。そして若い友人である菜月さんと主人公であるぼくは、わずかな手がかりをもとに消えた平間さんを捜して「まぼろしの廃線跡」をめざすのだが……。
ラスト、主人公の抱く不安は、菜月さんへの愛情と表裏一体をなすものであり、その意味で、大切な誰かを愛するということはまた、そこから逃げることのできない一本のレールの上にあって不安とたたかい続けることでもあるのだろう。
有吉佐和子『青い壺』
2013.6.14|review

この世に産み落とされ、その後数奇な運命を辿るのはなにも人間だけの専売特許ではない。「もの」だって同じこと。いや、むしろ自分の意志で移動できないぶん、「もの」の一生のほうがじつははるかにドラマティックといえるかもしれない。
というわけで、これは一個の青磁の経管をめぐる物語である。壷が「主人公」というので、壷がいきなり自分の人生についておしゃべりを始めるのではないかと心配したが、もちろん、そういうことはない。さまざまな偶然が重なり、さまざまな「家」を転々とする青い壷。そうしてその壷は、それぞれの場所で、思いがけずそのときどきの持ち主の心(それは美しい思い出であることもあれば、ときに醜悪な虚栄心だったりもするのだが)をまるごと映し出す鏡になる。最後、一見無関係と思われるエピソードが唐突に挿入されるが、そこから一息に導き出される決意が清々しい読後感をあたえる。
「弓香と律子は手を繋いで部屋を出た」。ごく短いセンテンスだが、50年ぶりに再会した女学校時代の旧友たちの時間を一気に巻き戻してしまうあるエピソードの後ろに置かれるとき、そこに彼女らの歳月が凝縮されて鮮やかに立ち上がる。いまの感覚からすると、それぞれの物語の描き方は往年のホームドラマのように大仰で滑稽な印象を拭えないものの、こういうハッとするような瞬間とたびたび出会えるのが、読んでいてなんとも楽しい一冊だった。
矢野誠一『落語家の居場所―わが愛する芸人たち』
2013.6.16|review

トラウマ?
はたまたナントカ症候群?
運よく「巨匠の時代」に居合わせてしまったがために、その後ずっと食い足りない気分を抱えながら過ごさざるを得ないこういう《不運》のことをはたしてなんと呼ぶべきか?
この『落語家の居場所』という本について、志ん生や文楽、圓生ら往年の「巨匠」たちと身近に接してきた筆者は、「むかしほど落語にのめりこむことのできないでいる自分」を発見し、それでも断じて「團十郎爺い」にはなりたくないと抵抗をみせながらも、けっきょくは「世紀末落語論」をめざしたつもりが「『よき時代の落語讃歌』にかたちを変えてしまった気味がある」と告白する。
とはいえ、この本からは年寄りの昔話に付き合わされたようなうっとうしさはほとんど感じられない。ひとつには、それは筆者が過去と現在とを比較するような書き方を意識的に避けているからだろうし、もうひとつには、現在にも通じるや寄席の「気分」といったものが、さながらRPGの「アイテム」のようにこの本の随所に隠されて(?)いて、そのつどいろいろなことにあらためて気づかされるからではないか。
「つまり、ふだん着で、ふだん使っているものを手にして、ふだんの声で、ふだんの言葉ではなすのが、落語なのである」(「古今亭志ん生の執念」)
これからの新作落語について。三遊亭圓歌の「中沢家の人々」や林家木久蔵(現木久扇)を引き合いに出しながら(風俗描写やナンセンスな状況ばかりにたよらない)「ますますパーソナルな色彩を加えていくような気がする」(「寄席」94.2.16)
三代目小さんと圓遊についての夏目漱石による評をとりあげ、小さんの方を持ち上げるのは漱石が「なにより江戸趣味のひと」だっかからと指摘、むしろ「新しい時代にふさわしい感覚」にあふれていたのは圓遊の方であった(「世紀末落語論」)
今日の落語を取り巻く状況について、聴衆をふくめた当事者たちのその危機感の薄さは四半世紀前とまったく変わっていないと指摘する一方で、そのぬるま湯につかっているような居心地のよさがかえって「激しい世の移り変わりという時間の流れのなかで、少しも動かない静かな時間をつくり出していたことに、じつは最近になってやっと気づいた」(「世紀末落語論」)
生涯つつましい長屋暮らしを通したことで知られる彦六の正蔵師匠に、反面、コーヒーは自分で挽いた豆をサイフォンでたて、食堂車でオートミールの食べ方を著者に得意げに教授し、「落語家のなかでホームスパンのジャケットを最初に着」るようなモダンな横顔があったことをはじめて知った。へぇ〜(「林家正藏の反骨精神」)
その他にも落語好きには刺激的なエピソードや指摘が多数。
沢村貞子『私の浅草』
2013.6.20|review

「江戸」と「東京」とがせめぎあう、さながら汽水湖のような1920年代の浅草。その浅草に生きる人々の暮らしを、ひとりの少女の目を通して活写した素晴らしいエッセイ。季節の到来を告げる年中行事の数々、無駄を出さない生活の知恵、どんなときにも背筋をシャンと伸ばした浅草の女たち…… そうしたひとつひとつが、まるでその場に居合わせているかのようにくっきりと像を結ぶ。少女時代の沢村貞子の観察眼、文章の腕前も見事だが、ひとりの大女優を育んだ1920年代の浅草の庶民の暮らしの《豊かさ》を見抜き、筆をとることを勧めた花森安治の編集者としての目利きぶりにも拍手をおくりたい。
ジェイムズ・エルロイ『ブラック・ダリア』
2013.6.25|review

《ブラック・ダリア》とは、ロサンゼルスで惨殺されたひとりの女に献じられた呼び名である。
猟奇的な殺人事件とその核心に迫ろうとする警官が主人公という点で、これはれっきとした犯罪小説であるが、と同時にこのフィクションの肝はもっと別のところに、《ブラック・ダリア》という女の存在によってはからずも自身が抱える心の闇に向かい合わざるをえなくなった人々の孤独な葛藤とその悲劇的結末を容赦なく描き出すところにあるようだ。ひとつの事件をきっかけに、平和な日常がアリ地獄のようにグズグズと崩落してゆくことの恐ろしさ。息をのむようなスピード感とは無縁。物語は、からまった糸を忍耐強くほどいてゆくようにジリジリした歩みで進んでゆく。
全編を貫く生々しさ、不吉さは、ロサンゼルスの暗部を身をもって知りつくした著者ゆえだろうか? 読者にもそれ相応のタフさが要求される。
芝木好子『湯葉;隅田川;丸の内八号館』
2013.6.30|review
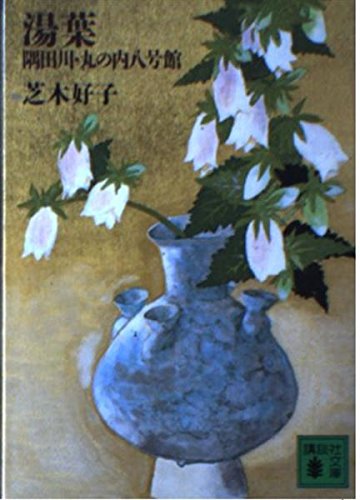
父権的なるものを失ったとき、ひとりの女としてどう生きるか?
母娘3代の生き様のちがいを描くことで、この3部作はあざやかに明治から大正、そして昭和という時代を映し出す。
3作通じてif(「もし…」)の用法を使うことで、「男」の死、あるいは消失によって「女」の生を描くという手法がおもしろいが、同時にそれぞれの時代を象徴するものとして、独自の工夫で一目置かれる湯葉屋、芸術的な染織にこだわりをもつ呉服商、そして当時「一丁倫敦」などともてはやされた丸の内ではたらく「タイピスト」といった仕事がえらばれているのが興味深い。
海野弘にならって1910年代、20年代、30年代という区分で読んでゆくと、またひと味ちがう眺めがひらけてくるのも印象的。第3部『丸の内8号館』の主人公・恭子は、じぶんの母や祖母とちがい、最後にはみずから父権的なるものに引導を渡すことでみずからの人生を歩き出そうとする。物心ついた時分に、浅草という当時の東京の「へそ」で道楽者の父親に溺愛されて育つことで大正デモクラシーの甘い蜜の味を知ったいかにも30年代の女らしい生き様だし、またそういう道しか選べないことでひとつの時代の終焉をまざまざと知らしめるのだった。
橋本千代吉『火の車板前帖』
2013.7.3|review
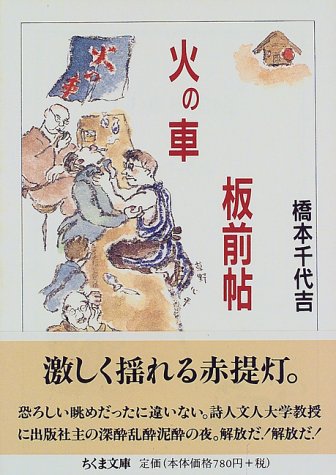
迷惑千万な人々。「商売を始めたら、手伝ってくれるね?」「ああ、いいですよ」うっかり返事してしまったばかりに、ある日突然、詩人・草野心平が開いた居酒屋の板前をやらされることになってしまった千代吉さんの怒涛の日々を綴った回想記。
しかし、それにしても、そこに集う人間どもの、揃いも揃ってなんと迷惑千万なことか。営業時間は完全無視、深夜に板前を拉致して他人の家を強襲、店主も入り乱れての殴り合いの喧嘩は日常茶飯事、増える一方の借金……ハッキリ言って常連客のほぼ全員が酒乱である。それがまた、みな綺羅星のごとき作家や文化人、事業家ばかりなのだから空いた口もふさがらない。そしてその喧騒に付き合わされ、尻拭いをさせられるのはいつもきまって千代吉さんときまっている。
それでも、たとえどんな目に遭わされようとも、千代吉さんの心平さんに対する忠誠心、忍耐強さ、心優しさは変わらない。本当に、千代吉さんは心平さんのことが大好きなんだなァ。
PS.思いがけず、戸板康二の名前が出てきたのには驚いた。彼もまた、酒好きらしく「火の車」の客人だったのである。
ヘニング・マンケル『目くらましの道』
2013.7.8|review

上巻
史上最悪の夏休み。白夜の北欧スウェーデンのスコーネ地方が舞台のクライム・ノベル(厳密には”警察小説”というらしい)。
北欧が、表面的にはもっとも美しく明るく輝く季節に、その裏側で繰り返される凄惨な殺人事件。その極度のコントラストは、ごくふつうの生活を送っている人間がその裏では陰惨な事件を引き起こすもうひとつの顔を持っている、というこの作品の中の犯人像と重なる。
主人公の警部ヴァランダーの「繊細さ」「小心さ」が、ときに捜査の上では武器になっている反面プライヴェーとではぐだぐだなところが可笑しい。
下巻
ふだんは人一倍読むのが遅いのに、半日で読了。新記録。
センテンスが短いのでリズムよく読み進むことができる。淡々と進みながらもいや増してゆく緊張感。訳者の手腕かもしれない。
北欧のひとびとがいかに夏休みを楽しみにしているか?
彼らがどのように夏を過ごすのか?
マイペースで、いなたい登場人物たち……(事件は悲惨だが、なんとなくの〜んびりした印象なのはそれゆえ?)。「北欧の人と暮らし」という視点から読んでも、なかなか興味深い一冊。
レーナ・レヘトライネン『雪の女』
2013.7.14|review

フィンランドを舞台に、女性刑事マリア・カッリオが活躍する警察小説だが、主人公はもちろん、被害者や被疑者にいたるまでそのすべてが「女性」という一風変わったミステリ。作者レヘトライネンも当然、女流。
ある冬の日、雪に覆われたヘルシンキ近郊の森の片隅で、男子禁制のセラピーセンター「ロースベリ館」の女主人が死体となって発見される。さっそく捜査に乗り出す男勝りのマリア。ところが、犯人探しと平行して、マリアの身に、《女性》性を意識せざるをえないある事件が起こるのだった。そして、突然見舞われた状況に逡巡しながらも、星座をつなぐように事件の真相は徐々にその全貌を明らかにしてゆく。
世界的にも女性の社会進出が進んでいることで知られるフィンランドから、こうした切り口の作品が登場することが興味深い。必ずしも、男女平等の夢の国ではないという現実。社会制度とはべつのところに、厳然と存在しつづける性差をめぐる差別意識の根深さ。現代の北欧社会が抱えるさまざまな問題を知るうえでも、とても参考になった。
全体にほろ苦いストーリーであるが、そんな中がさつなマッチョイズムの権化のようでありながら、マリアに対して人一倍繊細な気遣いをみせる同僚ペルッティの存在が微笑ましい。
シューヴァル&ヴァールー『ロゼアンナ』
2013.7.18|review
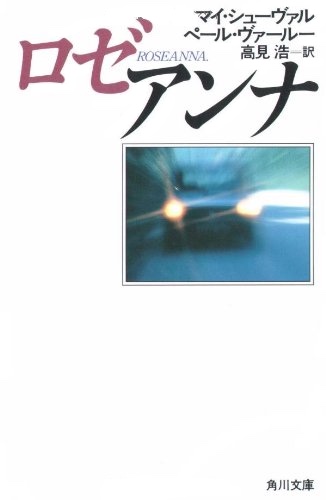
シリーズ「刑事マルティン・ベック」第一弾。犯人の動機に意外性があり、またそこに1960年代当時のスウェーデン固有の匂いのようなものが感じられる。
主人公が「頑固」「論理的」「沈着」という「警官として誇るべき3つの貴重な資質」に恵まれているのは本当としても、とはいえ、けっして「全能ではない」という点で警察小説ならではの醍醐味(?)は健在。じっさい、ここでも、地方の警察署や婦人警官、アメリカの片田舎の刑事などさまざまな個性的なメンツを巻き込みながら難事件の捜査は進められてゆく。それはけっしてすべてにおいて美しいチームワークとはいかないが、いざという場面でそれぞれが自分の役割を見事に演じ切っているところが気持ちいい。
美しく輝かしい夏に湖水地方で発生した事件が、なんの解決の糸口も見出せないまま季節は移ろい、秋を過ぎ、やがて不毛な冬へとさしかかる。この季節の経過がもたらすやるせなさに北欧人マルティン・ベックの焦燥感がシンクロし、沈鬱なムードを醸し出す。相手の性格を見抜き、巧みな尋問で自白を引き出してゆくマルティン・ベックの手腕はお見事。次作への期待も高まる。
持っているのは角川文庫の旧版。古書で探すなら新版(画像)より、日暮修一による装丁のすばらしい旧版の方をおすすめしたい。
シューヴァル&ヴァールー『蒸発した男』
2013.7.25|review
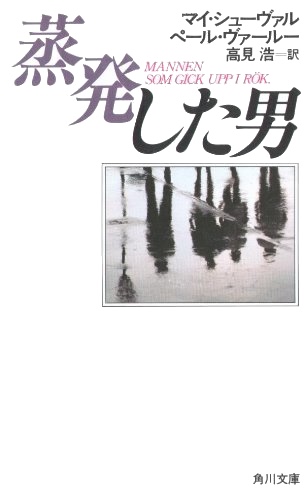
刑事マルティン・ベック、シリーズ第2弾は東欧ハンガリー編。冷戦下のブダペストで忽然と姿を消したスウェーデン人ジャーナリストの行方を追って、夏休みを〝24時間〟で切り上げたマルティン・ベックは単身ハンガリーへと飛ぶ。彼をつきうごかすものはただ、「どんな任務でも引き受けて、解決にベストを尽くそうとする本能」、一種の「刑事根性」にほかならない。
東西が分断された冷戦下のヨーロッパにあって、政治的な思惑から思うように進展しない捜査、麻薬密売組織、尾行者の影……
とさまざまなに伏線を張りめぐらしながらも真犯人は意外なところに。前作『ロゼアンナ』のカフカ刑事につづき、ベックは今回もハンガリーですばらしい協力者を得る。幸運な刑事なのだ。〝水と油〟な印象の同僚コルベリとも、ますます不思議に息があってきた。
犯罪小説と呼ぶには、前のめりになった読者を軽くいなすような結末はあまりに淡白すぎる気もしなくもないが、いっぽうで、絵葉書のように風光明媚なブダペストの夏を堪能できるのがこの本の最大のポイントとなっている。それは、待ちに待った夏休みを取りあげたことに対する、作者からのベック刑事へのせめてもの「罪滅ぼし」だろうか?
土曜ワイド劇場的な観光気分も満点。ラスト、バカンスに戻ったベック刑事に対する妻の態度が、不気味(笑)。
シューヴァル&ヴァールー『バルコニーの男』
2013.7.28|review
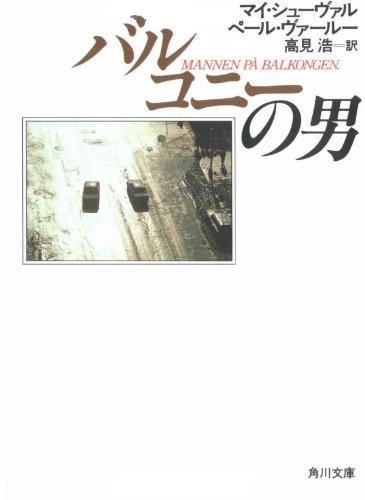
〝刑事マルティン・ベック〟シリーズ第4弾は、ストックホルムが舞台。「都会」が舞台ゆえ、ここではさまざまなパターンの「目撃」がストーリーを生んでゆく。見ていないようで見ていたり、偶然に見たり、こっそり見たり、あるいはまた見ているようで見ていなかったり……都市では無数の視線が交錯し、事件はその網の目のすきまに起こる。いわゆる都市型犯罪である。
連続強盗事件と連続少女誘拐事件、ふたつの神出鬼没に発生する事件を追いかけるマルティン・ベックらいつもの面々(今回新たに「グンヴァルド・ラーソン」なるなかなか強烈なキャラクターが加わる)は、クモの巣のように複雑に入り組んだ無数の「視線」に絡めとられてしまったか、今回ばかりはいつになく切れ味が鈍いようだ。そのかわり、ここでは市中を巡回している警官たちが思わぬ活躍をみせるが、それは彼らもまた、ある意味〝都市の目撃者〟なのであり、ときに「見ること」にかけてはマルティン・ベックら以上に〝プロ〟と呼べるからである。しかしこの、あえて「ヒーロー」をつくるのを拒むかのようなラストの呆気なさは前作同様。そこがまた、いかにも北欧らしくもあるなぁ。
5種類ある!
2013.7.29|book

5種類ある! 古本屋から届いた包みをあけたぼくは、思わず声を上げた。たしかに、注文した本にはちがいない。それはまちがいない。ただ、思っていたのと、カヴァーがちがったのである。
アアルトコーヒーの庄野さんにすすめられて、ここ最近スウェーデンの作家マイ・シューヴァル=ペール・ヴァールー夫妻による警察小説〝刑事マルティン・ベック〟シリーズを読んでいるのだが、これがめっぽう面白い。一人の、超人的キャラクターが八面六臂の活躍で難事件を解決へとみちびく〝探偵もの〟よりも、等身大の人間臭いひとびとが四苦八苦しながら事件の核心へとジリジリ近づいてゆく〝警察小説〟のほうに親しみを感じてしまうのは、ぼく自身また不器用な凡人だからだろうか。ストックホルムの街を舞台に、いかにも北欧人といった風情のひとびとが奔走するのもぼくにとっては魅力的なポイントである。
〝事件〟は、シリーズ第4作にして最大のヒット作『笑う警官』を手に入れたときに起こった。この〝刑事マルティン・ベック〟シリーズは全10作、日本では1971年から83年にかけてそのすべてが角川文庫から刊行されている。まず、〝ミステリ通〟庄野さんの指導にしたがいシリーズ第1作である『ロゼアンナ』を手に入れた。つづいて、第2作『蒸発した男』、第3作『バルコニーの男』と手に入れた。その際、カヴァーをすべて「旧版」で統一することにこだわったのは、コラージュ風の日暮修一によるイラストが往年のミステリらしい味わいで気に入ったからである。ちなみに、彼はSSKHKH(←わかるひとだけわかってね)の日暮愛葉のおじさんにあたるらしい。
ところが、「新版」と「旧版」2種類あると思っていた角川文庫版のカヴァーだが、じつはこの『笑う警官』にかぎって4種類存在することが調べているうち、わかった。アメリカ探偵作家クラブから「エドガー賞 長編賞」を授与されたこの作品は、76年『マシンガン・パニック』というタイトルの下ハリウッドで映画化もされている。その人気を受けてだろう、日本でも『笑う警官』はたびたび版を重ね、どうやらそれにあわせてカヴァーデザインも更新されたきたらしいのだ。しかも厄介なことに、この『笑う警官』、日本では2番目に刊行されている。
ネットでみかけた4種類の『笑う警官』のカヴァーのうち、日暮修一バージョンを除く2種類は比較的最近のデザインであることがわかる。もう1種類は、いつ刊行されたものか定かではない。そこでぼくは、細心の注意を払って72年発行のものを古書店に注文してみたのだが、その結果は冒頭のとおり。つまり、包みを開いたぼくが目にしたものは、その存在すら知らなかったなんと〝5種類目の〟カヴァーだったのである。
この〝5種類目の〟カヴァー、いま手元にある『笑う警官』の奥付をみると、「昭和47(1972)年12月30日発行の7刷」とある。初版が同じ年の7月20日だから、半年足らずのうちに7回も版も重ねたことになる。ふつうにかんがえれば、大石一臣というひとのイラストによるこのカヴァーが初出にちがいない。相変わらず日暮バージョンを手に入れようと、しかもできるだけ〝安価で〟手に入れようともくろんでいるぼくとしては、それが2番目なのか3番目なのか、はたまたいつごろの時期にあたるのか、気になってしかたない。確率1/2ならまだいい。いつまた、こんなふうに叫ぶことになるのではないかとかんがえると恐ろしくてしかたないのである……
6種類もあったのか?!
シューヴァル&ヴァールー『笑う警官』
2013.8.1|review
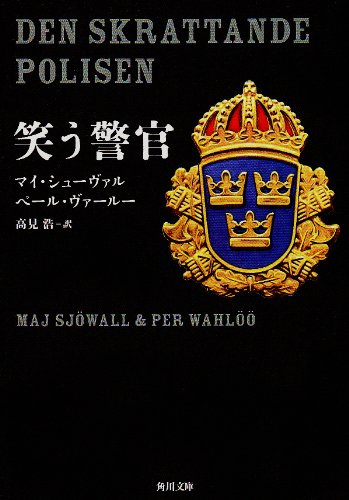
11月。長く厳しい冬の到来という〝現実〟を目の前に突きつけられる、北欧の人びとにとってもっと暗鬱な季節にその事件は起こる。ストックホルム市内を運行する路線バスの車内で発生した銃乱射事件。事件もまた、11月にふさわしく暗鬱だ。
偶然にも、その凶行の被害者の中にストックホルム警視庁の刑事マルティン・ベックの若い部下がふくまれていた。犯行の手がかりを探るため丹念に被害者たちの素性を洗ってゆくうちベックは、部下の死をたんなる偶然の事故として片付けるにはあまりにも不可解だという印象を抱く。やがて、捜査線上に16年前に発生し未解決のままとなっているひとつの殺人事件が浮上する……。
この『笑う警官』は、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの第4弾となるが、このシリーズの魅力は謎解き的な側面以上に、事件捜査にあたる個性豊かな警察官たちによる群像劇と必ずしもうまくいっていない夫婦間の心のすれちがいを描いたホームドラマというふたつの人間ドラマが同時進行してゆくところにあるのではないか。コルベリ、メランデルらいつもの面々は、それぞれの〝領分〟でいつも以上にその持ち味を発揮している。ノルディンやモーンソンら〝地方招集組〟もまた然り(ん?アールベリは?)。
前回から登場した〝憎まれ役〟グンヴァルド・ラーソンは今回もなかなかの舌好調ぶりだが、最後事件について語る言葉に彼に対する読者の印象も変わる。なお、タイトルの意味するところは、最後のページの最後のセンテンスで明らかになるのでお楽しみに。苦笑いと泣き笑いの青年刑事への鎮魂歌。
*北欧の名前になじみのない読者には、あるいは登場人物の名前に苦労するかも…。
シューヴァル&ヴァールー『消えた消防車』
2013.8.5|review

〝スウェーデン・ミステリの原点〟といわれる「刑事マルティン・ベック」シリーズの第5弾。
ストックホルムのダウンタウンで発生したアパートの爆発炎上事故、時をおなじくしてメモにマルティン・ベックの名前を残したまま謎の自殺を遂げた男、忽然と消息を絶った第三の男の足どりを追う中でぼんやりと浮かび上がってくる大規模な自動車密売組織の影……
。事件性の有無さえはっきりとしないまま、ベックらいつもの面々はこの〝支離滅裂〟な事件にずるずると巻き込まれてゆくのだが、この『消えた消防車』最大のみどころはといえば、グンヴァルト・ラーソン〜新人ベニー・スカッケ〜マルメ市警のモーンソンによる〝華麗なる捜査リレー〟だろう。こうした「脇役」たちの渋い活躍ぶりこそがまた、このマルティン・ベックシリーズの魅力のひとつなのだ。
春から夏、夏から秋へと季節が移り変わるのとおなじく、妻との不和、家庭内で唯一の理解者ともいえる娘の自立などベックの家庭を取り巻く景色も様変わりしてゆく。それはまた、厳しい季節の到来を告げる声でもあるだろう。自動車の盗難と密売、家庭崩壊や児童にまで蔓延するドラッグ問題、そして銃器を身につけない主義のコルベリを見舞った不運……
ここではスウェーデンの「負」の側面が拡大鏡でみるように誇張される。このシリーズがしばしば「社会派」、あるいは「スウェーデン社会の変遷をも描くドラマティックな大河小説」(訳者)といわれるゆえんである。とはいえ、テーマは深刻ながらも、随所に散りばめられた北欧流ユーモアのおかげでけっして重苦しいだけの気分には終わらない。モーンソンがおこなった尋問のテープを聞きながら、その予想外の〝巧みさ〟に一同首をかしげるシーンなどすごく可笑しい。これはモーンソンと作者、そして読者だけのヒミツ。そしてもうひとつのナゾ「〝消えた消防車〟は無事発見されるのか?」もお楽しみに。
ブルーノ・マットソンの椅子
2013.8.7|book

プールサイドのブルーノ・マッソン風の椅子に、両目を軽く閉じている全裸の女は、シャーロッテ・パルムグレンだった。(シューヴァル=ヴァールー『サボイ・ホテルの殺人』高見浩訳78ページ)
スウェーデンの南部、スコーネ地方の都市マルメがその小説の舞台である。〝タンバリンスタジオ〟しか思いつかないほどに、ぼくはマルメという街をまったく知らない。スウェーデンの首都よりは、隣国デンマークの首都のほうがはるかに近い(たしか鉄道で40分弱?)ということは知っている。もちろんまだ行ったことはないが、いつか行くことにはなるのではないか。〝希望的観測〟だけど。
マルメには、その小説によると「ヴェストラ・フェルスターデン」なる高級住宅エリアが存在するらしい。事件の被害者にして実業界の大立て者、ヴィクトール・パルムグレンはその一角に建つ豪奢な屋敷に暮らしていた。おなじマルメでも「メレヴォン広場周辺の労働者階級住宅地」の出身であるモーンソン警部は、それゆえ、いい大人になったいまでもこの地区に来ると「違和感」を感じずにはいられない。推測するに、その「違和感」とは「この国には本当に〝平等〟は存在するのか?」という幼い時分から抱きつづけてきた感覚だろう。
こっそり忍び込んだパルムグレンの屋敷でモーンソンが目にしたモノ、それが冒頭に引用した「ブルーノ・マッソン風の椅子」だった。1907年スウェーデンの南部ヴァルナモの生まれ。家具職人を父親に育ったブルーノ・マットソンは早くからその才能を開花させ、人間工学と優美な曲線を融合させた洗練されたデザインで一躍人気デザイナーの仲間入りを果たす。おそらくプールサイドで全裸の女性が横たわっていたのは、1944年に世に出た〝Pernilla3〟と呼ばれる長椅子だったのではないか。いかにもブルーノ・マットソンらしい優美で、こう言ってよければ〝スノッブ〟な匂いのするデザインである。バブルのころ、都心の億ションにはたいがいカッシーナのソファが置かれていた。あ、すいません、見てきたように書いてしまいました…… 置かれていた、らしい。ちょうどこの『サボイ・ホテルの殺人』が執筆された当時、60年代後半の裕福なスウェーデンの家庭には、きっとそんなふうにブルーノ・マットソンの椅子が置かれていたにちがいない。
貧しい地区で育ったモーンソン警部にはしかし、それは「ブルーノ・マッソン風」としか判らなかったのである。
シューヴァル&ヴァールー『サボイ・ホテルの殺人』
2013.8.11|review
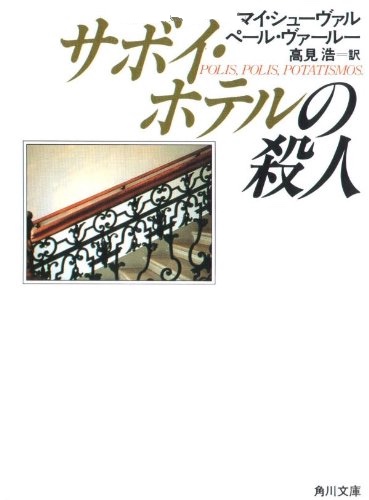
スウェーデン・マルメの高級ホテル、乱入したひとりの男によって射殺された〝ブラック企業〟のワンマン経営者。被害者は、国交をもたない国への武器の闇取り引きで巨万の富を築いたと噂される男だけに身内をふくめ〝敵〟は多い。それが捜査を攪乱させる。けっきょくは、些末な証拠の積み重ねとベテラン刑事の〝勘〟が事件を解決へと導くのは警察小説ならでは。しかし、事件の解決がかならずしも一警察官の気持ちを朗らかにさせるものではないというのもまた事実なのだった。「主任警視マルティン・ベックは、はなはだおもしろくなかった」(文庫版366頁)。
シリーズ〝刑事マルティン・ベック〟第6弾の特徴は、そこで起こる事件以上に、登場人物たちの〝私生活〟と彼らの〝心情〟がいつになくみっちり描かれている点にあるかもしれない。ついに妻との別居を決意したベックをはじめ、中途半端な夫婦生活もいよいよ終焉に近づきつつあるモーンソン、前作のアクシデントをきっかけにマルメに異動したスカッケ、コルベリ、オーサ・トーレル、そして独身主義者グンヴァルト・ラーソンがみせる意外なナイーヴさなどなど。このあたりの〝人間観察〟を楽しむために、読者はやはり第一作から順に読み進めるのがよさそうだ。
公安課のポールソンが道化役としておもに本作でのユーモア担当。そして、意外にモテるマルティン・ベック……うーむ、イメージの修正を図らねば。
シューヴァル&ヴァールー『唾棄すべき男』
2013.8.13|review
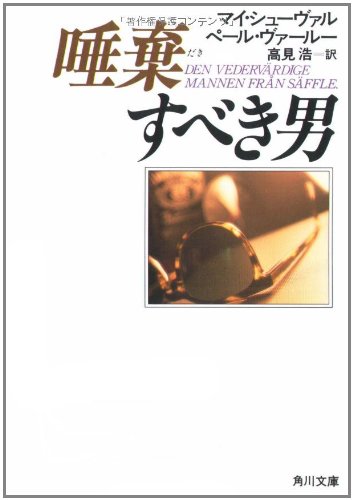
被害者も加害者も、そして捜査にあたる人間もすべてことごとく〝警官〟ばかりという徹底ぶり。それも当然、警察という〝組織〟こそが、ここでの主役なのだから。シューヴァル=ヴァールー夫妻が、〝警察小説〟という形式によって10年の歳月をかけて現代社会を描きつくそうと挑んだモニュメンタルな作品であるこの〝刑事マルティン・ベック〟シリーズもこれで第7弾である。
組織とそこに属す人間が、個と公(©アアルトコーヒーの庄野さん)のはざまで見せるさまざまな顔。職務上、自我を抑圧することが求められる日々ゆえ、ときにはほんとうの自分の顔すらわからなくなってしまうようなことさえある彼ら。無関心はまた、そんな爆発しそうな自我を押さえ込むためのいってみれば〝処世術〟ともいえる。公>個の日本では、同じように組織を描けば硬派な社会派ドラマになるが、個>公、あるいは個と公がおなじレベルで拮抗しているスウェーデンでは、組織を描いてもけっきょくは泥臭い人間ドラマになるのが面白い。そのちがいが興味深い。
ちょっとした会話やふるまいから、水と油と思われていたコルベリとラーソンのあいだの関係に変化の兆しが窺われるのがうれしいところ。これは続刊でのお楽しみ。いつになくド派手な展開ゆえ、映画化に際してこの作品が選ばれたのも納得!?
でも、ラストはそこで終わっちゃって本当にいいの?!
シューヴァル&ヴァールー『密室』
2013.8.17|review
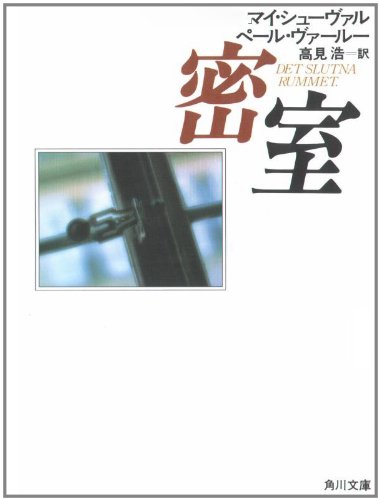
〝密室〟を描くことで、作者は都会に暮らす人びとの深い孤独を浮き彫りにする。1972年当時のストックホルムを覆っていた重苦しい空気について、作者はこんな風に書いている。「暴力は反感や憎悪のみならず、不安や恐怖をも醸成するものである。人々はしだいに互いを恐れるようになり、ストックホルムは不安に怯える数十万もの人々を擁する都市となった。そして、恐怖にすくみあがった人々は危険な人々でもある」(73頁)。そこでは、誰もが被害者になりうると同時に、いっぽう加害者にもなりうる。
そんな、抑圧された現代社会のもとで畏縮した都会人の心もまた、ある意味〝密室〟のように閉ざされている。その点、主人公マルティン・ベックも例外ではない。ようやく負傷からは立ち直ったものの、心に負った傷はまだ癒えていない。そんな折り、現場復帰し不可解な密室殺人事件の捜査に乗り出した彼は、その過程でひとりの生き生きとした女性と出会う。殺伐とした都会にあって、なにより人間的な絆を尊重する彼女の存在にやすらぎを見い出し、少しずつ生気を取り戻してゆくベック。読んでいて思わずホッとする。
密室殺人と銀行強盗、ふたつの事件が複雑に絡み合いながらストーリーは展開してゆく。都会特有のエゴイスティックな情報に翻弄され、身も心も疲れきった警官たち。不注意によるミス、独善的な捜査、情報の読み違い、焦燥感…… そんな負の連鎖の中まんまと網の目をすり抜ける狡猾な悪人の姿もまた、ほかならぬ都会人のもつひとつの顔なのだ。ラスト、現代社会にむける作者の目は、いつになく厳しい。
文中、ドッグフードを食べて細々と命をつなぐ老人という描写がたびたび登場するが、それについてはぼくも以前フィンランド人の知人から聞いたことがある。女性の社会進出が進んでいる北欧の社会保障制度は、そのぶん専業主婦に対してはひどくシビアなのだという。そのため、夫に先立たれ年金の支給を打ち切られた年老いた専業主婦のなかには、やむなくスーパーで手に入れた安価なドッグフードで命をつないでいるひともいるのだとか。まさに〝福祉国家の光と影〟といったところか。
そのあたりの経緯は、巻末に付された訳者によるペール・ヴァールー女史へのインタビューでも触れられている。シリーズが進むにつれペシミスティックな色合いが濃くなってきたのでは?という問いかけに対し、社会民主党政権が導入した「社会主義と資本主義をミックスしたような経済システムはけっして良い結果を生まなかった」と指摘しつつ、けっして当初から社会批判的なものを書こうとしていたわけではないと語る彼女。「つまり、この十年間におけるスウェーデン社会の変化が、わたしたちにペシミスティックになることを強いたと受けとっていただきたいわ」。
給水塔
2013.8.20|book
どこか恐ろしくも魅力的なのが、「給水塔」と呼ばれる建造物である。〝恐ろしくも魅力的〟という点で、ぼくにとって「給水塔」は「不協和音」にも通じる。不意に挿入されるモーツァルトの不協和音に、ひとは〝驚く〟よりもむしろ〝不安〟をおぼえる。おなじように、ごくありふれた街並に忽然と姿を現す「給水塔」の存在も、まるでそこだけが〝現実の中の非現実〟であるかのようにひとを不安におののかせる。
道に迷って偶然出くわした大谷口の給水塔。まるで松本竣介の絵のような、鉛色の空を背景に屹立するその威容をいまだ忘れることができない。わざわざバスに揺られて野方まで給水塔(配水塔)をみにでかけたのは、東日本大震災のすこし前のことだった。「この揺れで、あの給水塔は無事だろうか?」地震の中でそんな思いがふと頭をかすめたのは、「給水塔」のもつ〝街の不協和音〟としての強い印象ゆえだろうか。
スウェーデンのマルメに現在では共同住宅として使われている「給水塔」があると知ったのは、シューヴァル=ヴァールーのミステリ『サボイ・ホテルの殺人』で犯人が暮らすキルセベリ地区を描写するなかにそれが登場しているからだ。それはマルメ市のイーストサイド、「〝ブルトフタの丘〟とも、単に〝丘〟とも呼び慣わされている」すこしばかり殺伐としたダウンタウンに建っている。
「給水塔とは名のみで、実はかなり前から一般住宅に改造されている塔だった。中の部屋はさしずめパイのような形にでもなっているのだろうか。いつか新聞に、その改造住宅の衛生状態たるや不潔きわまりないもので、住民は九分九厘ユーゴスラビア人が占めているという記事が載っていたことを、スカッケは思い出した」(『サボイ・ホテルの殺人』高見浩訳 349頁)。
その給水塔は、第一次世界大戦さなかの1916年、避難所として貧しい人々に解放されたのをきっかけに本来の役割を失い、もっとも多いときで200人あまり(!)の人々ががそこで生活するほどの過密ぶりだったという。一種スラムと化していたのだろう。その後、民間の不動産会社がリノベーションを施し、現在では眺望に恵まれた高級アパートとしてなかなかの人気ぶりなのだそうだ。調べてみると、世界のあちらこちらに、いまは住居として第二の人生を送っている給水塔があるらしい。それはたしかに〝魅力的〟ではあるかもしれないが、ひとが暮らす「給水塔」に〝恐ろしさ〟はない。
内に満々と水をたたえた見上げるほどの塔、水の塔、そのどこか矛盾した存在様式にこそ「給水塔」の〝ひみつ〟が隠されているような気がしてならない。
マイ・シューヴァル『警官殺し』
2013.8.25|review
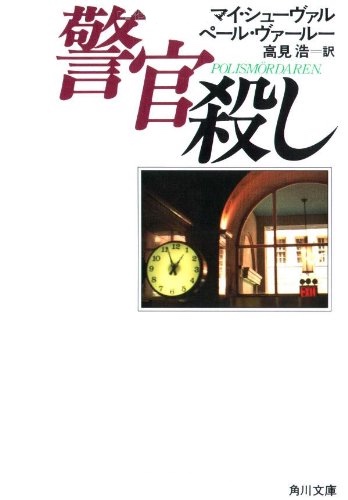
過去に登場した警官や犯人の〝その後〟を描き、〝主役〟にコルベリを据えた、〝刑事マルティン・ベック〟シリーズのいわばスピンオフ的作品。
完結編を前に、ここで読者は作者とともにいったん立ち止まり、これまでの〝時間〟をあらためて確認することになる。よって、他の作品は単体でもじゅうぶん読むことができるが、この作品にかぎっては過去の8作品を読んでいないことには愉しみも半減してしまうにちがいない。
個人的に、このスウェーデンミステリの傑作シリーズで好きなのはシュールでアイロニカルな〝笑い〟の要素である。なので、前作に付された作者マイ・シューヴァル女史への訳者によるインタビューでそのあたりの〝秘密〟が触れられていなかったのがすこし残念だったのだが、ここでも『警官殺し』というタイトルふくめそうしたユーモアにあふれている。アキ・カウリスマキの映画にも通ずるこの〝笑い〟こそ、まさに北欧的だと思うのだ。
橘蓮二『カメラを持った前座さん』
2013.8.28|review
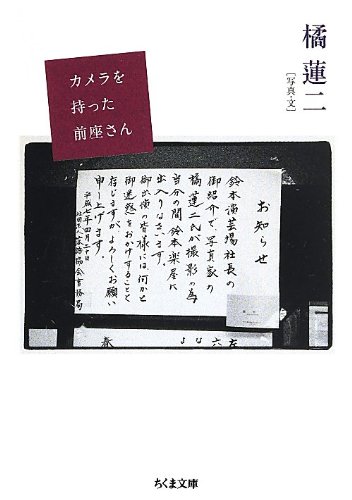
まさに「決定的瞬間ならぬ演芸的瞬間」!
時間調整のために入った本屋さんで、たまたま手にとりパラパラめくったが最後、そのままレジへ直行。よっぽどのことがないと、ふだん写真集は買わないんだけどなァ……。
ここで被写体となっている噺家の姿から伝わってくるのは、落語が、〝没入〟と〝俯瞰〟のギリギリの均衡の上に初めて成立する至芸であるということ。その所作は即興などではなく、練って練って、練り上げられてできたカタチなのだというのが手に取るようにわかる。その意味でも、オフショットではなく、高座での写真が多いのもうれしい。木之下晃が撮影した演奏家の写真からそのひとの音がきこえてくるように、橘蓮二というひとの写真からもまた、たしかに、そのひとの声がきこえてくるからだ。
「橘蓮二は十八年前、演芸に救われた写真家です」というあとがきの一節に集約されるような、それぞれの芸人に寄せたエピソードも淡々としているぶん、余計に心にしみる。いい買い物をしました。
シューヴァル&ヴァールー『テロリスト』
2013.9.2|review
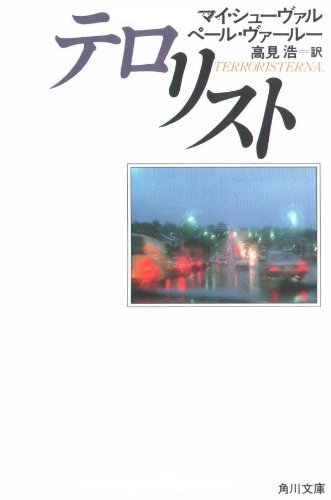
1965年から10年間にわたり、一年一作のペースで発表されてきた北欧ミステリの傑作とされる〝刑事マルティン・ベック〟シリーズの完結編である。以下は、全10作品を通しての個人的印象。
◎定点観測としての警察小説
現代のスウェーデン社会が抱える問題について、〝定点観測〟的な手法で描き尽くしたいとかんがえた作者マイ・シューヴァル=ペール・ヴァールー夫妻が選んだのが「警察小説」というスタイルだった。犯罪こそは「高度福祉国家」のネガであり、それを職業柄誰よりも冷静にみつめているのが「警察官」という人種だからだろう。ひとによっては、ミステリ的要素よりもときに作者による社会批判的な要素が強調されることに違和感をもつかもしれない。たとえばこの『テロリスト』では、社会システムに翻弄される少女を登場させ、彼女のためにひと肌脱ぐ〝名物弁護士〟の言葉をかりて自分たちの考えを代弁させている。娯楽小説としてはノイズとなりうるこうした部分も、「となりの芝生はよく見える」的にふだん好意的に「北欧」を捉えているぼくらにとっては、〝内側〟からの眺めということで興味深い。
◎アンチヒーローとしての警察官
ここには、スーパーマンはひとりも登場しない。便宜上〝刑事マルティン・ベック〟シリーズとなっているが、他の警察官のほうが活躍する作品もあるくらいだ。全編をとおしてたびたび語られる警察官の〝素養〟とは「論理的な思考力、常識、律儀さ」であり、「すぐれた記憶力、ときとしてロバ並みと称されるほどの頑固さ、それに論理的な思考力」を兼ね備えたマルティン・ベックこそは実直で泥臭い、いってみれば〝警察官の中の警察官〟ということなのだろう。そうした警察官たちが、地道に、少なからぬミスもやらかし、ときに幸運に助けながらも難事件を解決してゆく様に、おなじくふつうの人間であるぼくらは共感をおぼえ、登場人物たちに対しヒューマンな魅力を感じるのだ。
◎笑い
シューヴァル=ヴァールー夫妻の〝笑い〟のセンスが個人的にツボであったことは、続けざまに全10作を読み通す上で大きな助けになった。緊迫した場面で、絶妙のタイミングで挿入されるアキ・カウリスマキ顔負けの脱力系ユーモアは、この〝マルティン・ベック〟シリーズのもうひとつの魅力である。ところどころに往年のコメディアン、ローレル&ハーディの名前も出てくるが、作者のふたりはきっとスラップスティックコメディーにも通じているにちがいない。『テロリスト』でいえば、たとえばテロとは無関係に唐突に起こる暗殺がいい例だが、階段から足を踏み外したかのような錯覚&失笑を読者にあたえ効果抜群。そうした仕掛けに、創作上のテクニックというよりは、むしろふたりの〝遊び心〟を感じる。
〝北欧〟と〝ミステリ〟という、個人的なふたつの関心事を同時に満たしてくれるという点で、このシリーズはまちがいなくぼくにとっては★★★★★だが、ここ最近注目されている「北欧ミステリ」の〝元祖〟ともいうべきこれらの作品が、現在『笑う警官』を除きふつうに書店で入手できないのはとても残念なことである。角川書店には、ぜひ新装版での復刊を願うばかり。
PS.このシリーズを読むことをすすめてくれたアアルトコーヒーの庄野さんに心より感謝!!
北村薫『いとま申して「童話」の人びと』
2013.9.11|review
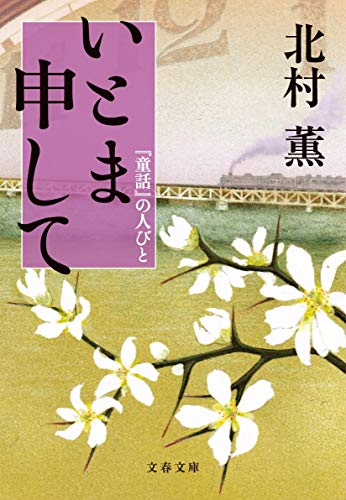
〝父と子の絆〟と言ってしまえば陳腐だが、その残された日記をここまで瑞々しく〝読む〟ことができるのは、読み手が「北村薫」という優れた作家だからという以上に、日記を残した人物の実の息子であるという事実の方がずっとずっと大きいだろう。
旧制中学〜大学予科にかけて、まさに青春時代まっただ中の「父」が記したことばの放つきらめき。それはときに、息子の知る、「謹厳実直を絵に描いたよう」な父親とはまるで別人のように映る。その驚き。冒頭の「スイカ」のエピソードが生きてくる。息子は、その日記のことばを媒介にして父と再会する。そして、その生前にはけっしてかわせなかったような親密な対話を果たす。
北村薫の父「宮本演彦」は、1909年横浜の生まれ。まさに多感な時期を大正デモクラシーとともに生きることのできた〝幸福な〟世代にあたる(同い年に、淀川長治、小森和子、山野愛子、野口久光、浜口陽三らがいる)。児童文学に熱をあげ、雑誌『童謡』の投稿コーナーの常連だった中学時代、おなじ投稿コーナーの仲間だったのが金子みすゞであり淀川長治であった。北村氏のていねいな注釈のおかげで、大正〜昭和初期、1920年代の横浜、東京の風景が鮮やかに立ち上がる。氏の「ベッキーさん」シリーズが好きなひとにはまた、たまらないものがあるだろう。
けっして楽な暮らし向きとはいえないまでも、医者で、地元の名士ともつながりのあった家庭で育った父はまだしも、その日の暮らしにさえ苦労している若者たちまでが熱心に童話や小説を書き、食べるものを食べずに同人誌をつくり、発表していたことにはひどく驚かされる。身銭を切ってまで『狂った一頁』を製作した衣笠貞之助もそうだが、市井の人々の中にもそういう胸に〝熱〟をもった人たちがたくさんいて、そうした人々がそういう時代をつくっていたのだろう。
梨木香歩『エストニア紀行』
2013.9.14|review

風変わりな旅だ。梨木香歩は、なぜエストニアを目的地に選んだのか。〝理由〟はけっきょく明かされないまま。にもかかわらず、その旅はこってり濃厚だ。旅をつづけるうち、どんどんエストニアの波長に同期してゆく著者は〝魔法使い〟のようなふしぎな力を備えた者にみえる。そのなかで発せられることばもまた、魔法のことばのオンパレード。
「人が森に在るときは、森もまた人に在る」
「性にまつわるものでも、そうでないものでも、野卑や下品は、世界ぜんたいの豊さを深める陰影のようなもの。そこだけ取り去ることはできない」
「人が自分の生理的な『これ以上はできない』の線引きをする場所は、それぞれ違っていて、その線引きの場所がその人の個性そのものの発露のように思われ、愛おしく感じられる。」
フィンランドと同じフィン・ウゴル語系に属するエストニア人。登場する単語もフィンランド語の響きに近いし、サウナを愛し、森を愛し、孤独を好むというエストニアの人びとの気質は、またフィンランドの人びとのそれに重なる。けれども、その「血」はエストニアの人びとにあってより純度が高く思われる。
彼らにとっての祖国愛とは「おそらく国家へのものというよりも、父祖から伝わる命の流れが連綿と息づいてきた大地へのもの」のように思われる、と梨木はいう。たしかにそうにちがいない。700年あまりの長きにわたって他国の支配を受け続けてきたという過酷な歴史が、彼らエストニアの人びとに「国家」という存在の空しさを教えるとともにそこから引きはがし、結果、コウノトリとおなじようなまなざし〜祖国は大地〜をもたらしたからなのだろう。
もう一度、たっぷりとエストニアを旅してみたいとこの本を読んで思った。
海老沢泰久『美味礼讃』
2013.9.25|review
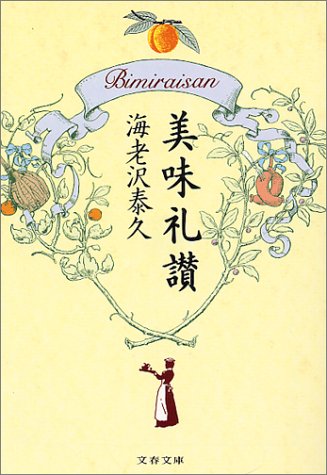
「辻調」こと辻調理師専門学校の経営者にして、日本に〝本物のフランス料理〟を広めた伝道者、辻静雄の半生を描いた伝記風味の物語。
プロの料理人でもない男が、なぜ〝フランス料理の最高の理解者〟としてキラ星のごときフランス料理界の重鎮たちから慕われ、信頼されえたのか?
それは、稀有な「舌」と「探究心」をもつ辻の存在を、彼らが〝ガストロノーム〟として認めたからにほかならない。そこに、料理人と〝ガストロノーム〟と呼ばれる客とのハイレベルな〝共犯関係〟によって栄華を極めてきた、フランスの食文化の奥深さを垣間見ることができる。
実在の人物を取り上げつつ、おそらくはかなりフィクションの要素も多いと思われるが、まるで運命に導かれるように辻静雄が料理の世界へと引き込まれてゆく様は、読んでいてワクワクする。著者のストーリーテリングの巧みさだろう。
高度経済成長前夜、世界へと飛び出した日本人のサクセスストーリーという意味で、小澤征爾の『ボクの音楽武者修行』にも通じる爽やかさも。子供のころ、テレビで『オーケストラがやってきた』や『料理天国』を観るのを楽しみにしていた世代には絶対に手に取ってほしい一冊。
高橋義孝『蝶ネクタイとオムレツ』
2013.9.30|review

大正2(1913)年、東京・神田生まれのドイツ文学者によるエッセイ。この世代によくみられるモダニスト、やわらかい心の持ち主かと思い手にとってみれば、やや期待外れ。
文中しばしば登場する「昔の日本はよかった」「近頃の若いもんは」「女というものは」式な発言は、なんだかおじいさんのお小言に付き合わされているようで、現代のぼくらからするとあまり居心地のよいものではない。とはいえ、エッセイを読むということは、心にピタリとくる一文をみつけるいわば「宝探し」のようなものと思えば、著者のいかにも江戸っ子らしい歯に衣着せぬ物言いと人間への洞察力に富んだ見方には、読んでいて目から鱗が落ちる瞬間も少なくなかった。
たとえば著者は、「はっきり言うと、うまいものは民主主義的ではありえないのである。うまいものは、少数の人間の独占物なのである。いや、そうならざるをえないのではないかと思う」と、〝自称グルメ〟たちがメディアに影響されて一流料理店に押し寄せるような風潮に釘を刺す(「異説・食べもの考」)。この点は、辻静雄の半生を描いた先日読み終えたばかりの伝記小説から受けた印象とも通じる部分があり興味深く読んだ。
また、おなじ文脈から「おしゃれ」を論じるとこうなる。おなじ「平凡な」身なりでも、「さんざん衣裳道楽した揚げ句の果ての平凡」と「ただの何の変哲もない平凡」とではその中身がちがうとした上で、こう言うのだ。「『渋さ』に至るには、その前に華美、派手の段階を通過していなければならない」。
他にも、無用のものへの偏愛を綴った「北海の魚」、エピソードから〝師匠〟内田百閒の〝人物〟をユーモアたっぷりに語った「忘れ得ぬ人々」などもよかった。
文庫版のあとがきは常盤新平、装丁は柳原良平。
入江相政『侍従長のひとりごと』
2013.10.11|review
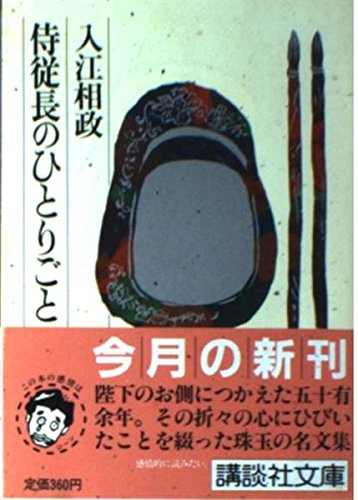
ジジュウチョウ。肩書きは硬いけれど、著者の心はとても柔らかい。
たとえば、趣味として楽しんでいた「書」について、その〝いきさつ〟をこう語る。「街をあるいていて、そば屋の看板の『そ』の字がすばらしいと思えば、すぐ手帳に書きとめる」といった手習いならぬ「目習い」を通して「書」に触れてきた。ゆえに「師はないが、またすべてが師でもある」と(「すべてわが師」)。
数え年というものがあったからこそ、すべての日本人が同じように感じ得た「大晦日」がもたらす「甘いセンティメンタリズム」(「歳末、正月」)など、戦前の日本人の心のありようについて触れた文章も、なるほどなぁと面白い。
せわしない現代に生きる読者にとっても、鷹揚なジジュウチョウの「ひとりごと」につきあうのは至福のひとときといえるだろう。
戸板康二『劇場の迷子―中村雅楽探偵全集4』
2013.10.21|review

鷹揚な「千駄ヶ谷の小父さん」が、意外な〝童心〟をのぞかせる「中村雅楽探偵全集」第4巻。77年から91年にかけて発表された28篇が収録されており、これで「中村雅楽」が登場する短編はすべて出尽くしたことになる。
事件は、劇場やその近辺に生じるいわゆる「日常の謎」がすべて。血なまぐさい殺人などいっさい起こらない。戸板康二の関心は、劇的な事件そのもよりも、歌舞伎役者ら劇を演ずる人間の心の内側のドラマに迫ることにあったのかもしれない。
この第4巻であたらしいのは、若き編集者「関寺真知子」がひんぱんに登場し、中村雅楽にさまざまな影響をあたえるところ。わずか3ページ強で、二人の役者が重ねてきた長い歳月を読者に感じさせる「銀ブラ」、失意の雅楽のために竹野がひと肌ぬぐ「おとむじり」など、これまで以上に地味ではあるが味わい深い小品が並ぶ。
林伸次『バーのマスターはなぜネクタイをしているのか?』
2013.10.21|review

舞台裏なんてわざわざ見せる必要はない、と主張する人たちがいる。いま見えている舞台こそがすべて、だからだ。一理ある。けれども、お店の主人がどんなところに心を砕きつつ日々を過ごしているか知るとき、客として、その店への共感や愛着がますます強くなるということだってあるだろう。
ここには、とある渋谷のワインバーの「舞台裏」が、ときにちょっと生々しいくらい書かれている。もしかすると、それをちょっと厭だなと感じるひともいるかもしれない。けれども、夜な夜な笑い声に包まれるそのステージはこんな舞台裏なくしては存在しがたい儚い世界だというのも、また事実。店の当事者にして、こういうことがらをしれっと書くことができ、しかもそれが許されてしまうのは、もう、ひとえに著者である林さんの人徳以外のなにものでもない(真面目に笑)。
知り合いの書いた本だけに勧めづらいこともなくはないけれど、これから個人でお店を開くことをかんがえているひとはもちろん、客としてお店を利用する側の人たちにもぜひ読んでもらいたい一冊。お店という「ステージ」は、お客様の存在ひとつで輝きも濁りもするということを、きっとこの本を通じていっそう深く知ることになるだろうから。
広瀬和生『落語評論はなぜ役に立たないのか』
2013.10.30|review

「BURRN!」編集長として音楽評論の世界に携わってきた著者が、落語評論家としてのみずからのアティチュードをまとめた一冊。
ここで著者は、落語の本質を「同時代の観客の前で演者が語る芸能」としたうえで、評論家とは「ツウの客」「最も良い客」であろうとすることで「演者」と「客」の中間に位置する「媒介」として、客の側に語りかける者、いわば「水先案内人」のうような存在であるとする。それゆえ入門者に対しては、歴史でもあらすじでもなく、まず同時代の「誰を聴けばいいか」という情報を提供することこそが評論家の役割ということになる。そしてこうした立場から生まれたのが、著者の『この落語家を聴け!』(2008年、集英社文庫)である。ここでも、最後に特別付録として「『落語家』『この一席』私的ランキング2010」が収められており、本編と付録とで一応は(というのは、本人がこれは「落語ファンとしての2010年の総括であって「決して『お薦めの落語家』のガイドではない」とわざわざ断っているので)「理論と実践」のような構成がとられている。
「なぜ知っている噺を何度聞いても面白いのか?」「『ネタバレ』で問題無し」「マクラの意味」など、落語初級者にとって興味をそそられる内容もすくなくない。
ロバート・チャールズウィルスン『時間封鎖』
2013.11.7|review

ある夜、突然いっせいに空から星が消える。そのとき地球は、何者かによってすっぽり皮膜のようなものに覆われてしまったのだ。同時に、地球上の時間だけが一億分の一になってしまっていた…。
いったい誰が?何のために?という疑問は最後の最後まで明かされない。わけのわからない状況に直面したとき、ひとは「科学的に理解するか、それとも宗教的に認識するかの二者択一を迫られる」。前者がここではジェイソンであり、後者がサイモンである。その仕方は正反対だが、ふたりはこの《スピン》と呼ばれる不可解な現象を自分なりに理解しようと努める点ではコインの表と裏のような存在といえるだろう。
《火星移住計画》《仮定体》といったキーワードは登場するけれど、この小説の背骨にあたるのはやはり人間を描くこと、ゆるぎない存在と信じていた地球がもはやグズグズと崩壊してゆく頼りない足場に過ぎないと知ったとき、ひとはなにを考え、どう行動するか、という人間のドラマを描くことにあるようだ。
いわゆるSFを読んだのは2冊めだが、人間のありようがしっかり描かれていること、訳文がこなれていて読みやすかったこと、そのふたつのおかげで最後まで一息に読み進むことができた。
追記
ただし…
ぼくの理解力不足だとは思うが、皮膜の外側に移住した地球の人間がなぜ「外側の時間」の制約を受けないのか?最後までなんとなく腑に落ちないままだった。
クラーク『幼年期の終わり』
2013.11.19|review

ちゃんと読んだSFはこれで3冊め。SFの世界では〝古典的名作〟とのこと。
ある日とつぜん巨大な円盤が上空に現れ、静止したまま地球を制圧する。やがて人類はそれに「オーバーロード(最高君主)」という呼び名をあたえ、畏怖するようになる。たとえば、子供にとっての親もそうだが、ガミガミ怒鳴られているほうがまだ気安く、対処のしようもある。恐ろしいのはむしろ、ただじっと黙って見守られているほうである。「オーバーロード」とはその意味で、人類にとっての「親」であり「庇護者」なのである。
〝好奇心〟からなんとか「オーバーロード」の実体に迫ろうとする人間の姿をえがいた第1部、第2部(ちなみに、第1部に登場する国連事務総長はフィンランド人!)。
さらに、ちょっと想像を超えたかたちで〝進化〟のありようが描かれる第3部。フィクションとはいえ、進化論にかんするまったくべつの異なる視点からの仮説(?)という意味で、著者の構想力に度肝を抜かれた。
広瀬正『マイナス・ゼロ』
2013.12.1|review
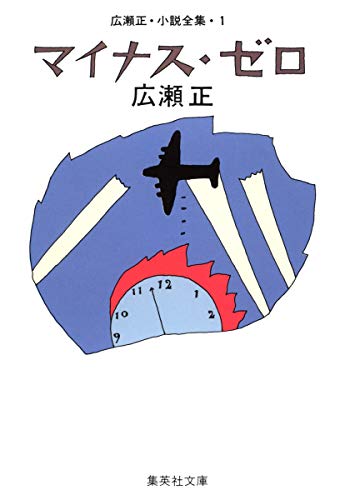
〝タイムトラベルもの〟と一言でくくってしまうには、あまりにもたくさんの仕掛けと色彩をもつ〝びっくり箱〟のような小説。
空襲のさなか、少年だった主人公に、18年後の同じ日、同じ時間にここに来るようにと言い残し絶命した隣家の〝先生〟。18年後、言いつけどおりその場所を訪れた主人公を待ち受けていたのは、人と人との不思議な縁(えにし)をめぐる時間を越えた旅であった……。
たとえどんな道を選ぼうとも、最後に辿り着く場所はひとつ。それが運命の赤い糸ならば、けっして途中でプツンと切れたりはしないものなのだ。
ちなみに、文中に登場するエピソードで個人的にいちばん好きなのは、自分に自分でごちそうを奢って少年時代の密かな思いを果たすところ。ちょっと乾いた洒脱な〝笑い〟もまた、この小説の魅力のひとつである。あとは、文字通り「現代っ子」らしい最後の娘の言葉。タイムマシンがあろうとなかろうと、けっきょく一番たいせつなのは「いま」なんだよね。
トレヴェニアン『夢果つる街』
2013.12.8|review

感想はひと言。「渋い」。
カナダのモントリオール、〝ザ・メイン〟と呼ばれる地区がこの小説の舞台である。一匹狼の〝警部補〟ラポワントは、移民や労働者、売春婦や浮浪者がひしめくこの吹きだまりの土地の秩序を、長いあいだ自分なりのやり方で守ってきたいわば〝番人〟のような存在。しかし、この街とそこに生きる人たちを誰よりも理解し愛しているのもまた、ラポワントそのひとなのである。そんな彼のホームタウンで、ある夜ひとりのチンピラが刺殺される……。
そこから話は二転三転……というわけには、ところが、全然いかないのである。事件の捜査に、動きらしきものが見えるのはようやく333頁になってから。全体の4/5は、濁った池の水面をじっと眺めているような案配。最後の1/5でその濁った水面が一気に透き通り、事件の全貌が明らかになるのである。
ただ、これはたぶんミステリではないのだろう。〝ザ・メイン〟という、時代から取り残された人々が身を寄せ合って暮らす時代から取り残された土地の物語だ。そしてその土地も、そう遠くない将来、近代化の波に押し流され消えてゆく運命にある。そしてそこに生きる人たちもまた。老兵しかり、モイシェしかり、心臓に手術不可能な動脈瘤を抱え、もはや警察署の中に味方がひとりもいない古いタイプの警官であるラポワントもまた、しかり。読了後、なんとも苦い後味が残る一冊。
エド・マクベイン『ダウンタウン』
2013.12.17|review
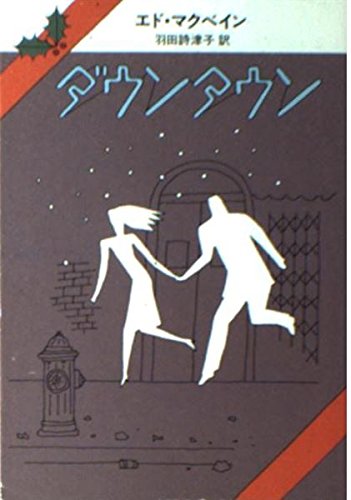
たんに相性の問題だと思う。警察小説の金字塔(と呼ばれているらしい)「87分署シリーズ」のエド・マクベインが手がけたクリスマスストーリー、しかも和田誠によるカバーということでワクワクしながら手に取ったのだが……残念ながら読了できず。
雪のクリスマスイブ。NYのダウンタウンでひょんなことから事件に巻き込まれ、なぜか警察から追われる身となってしまったちょっと軽いフロリダからやって来た男。そこに現れたのがひとりの中国系美女……。
さながら、80年代製ハリウッドのラブコメディーといった恋あり笑いあり殺しありのお話。たぶん主人公はマイケル・J・フォックス(ちなみに主人公の名前は、マイケル・J・バーンズ!偶然じゃないよね、コレ)。
トリックは面白そうなので、とにかくノリが合わなすぎて先に進めなかった。ノリの合うひと限定でおススメ。
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム『三秒間の死角』
2013.12.17|review

レコ屋のコメント的にいくと、まさに「必読!!北欧ミステリ最高峰!!」。
ジャーナリスト&元服役囚というスウェーデンの異色コンビ作家による第5作とのことだが、ぼくははじめて読んだ。これは凄い。読ませますね。
複数の登場人物たちの動きを、さながらカメラを切り替えるようにポンポンと見事なリズムで捉えつつ、巧みに読者をその特異で非日常的な犯罪世界に引き込んでゆく構成といい、それぞれ癖のあるキャラクターをさりげなく読者に刷り込んでゆくちょっとしたエピソードや振る舞いの描き方といい。
人々が生きるこの世界には表と裏、光と陰がある、という複眼的な世界観だけでなく、じつはそこにはそのふたつの世界を媒介するグレーゾンに生きる人種が存在するというのが、このストーリーのツボ。麻薬密売組織を壊滅するというミッションを担い、ある意味〝必要悪〟としてその存在の正当性を保証されている潜入者「パウラ」。ところが、彼は綱渡りのような危ういバランスの上に生きている。オモテの世界からもウラの世界からも切り捨てられたとき、「生き残る」という最後のミッションを賭けた「パウラ」の孤独な闘いが始まるのだ。そしてもうひとり、目の上のたんこぶ、昇進から永遠に見放された厄介者として上層部からも部下たちからも毛嫌いされている孤独な男、グレーンス警部もまた、その意味でグレーな存在にほかならない。この「簡単には諦めない男」と「命を賭けて生き残ることを決めた男」、ふたりの「執念」が火花を散らしながら重なり、爆発してゆくさまがたまらない。
そしてやはり、こんな重く暗いストーリーながら、そこかしこにあふれる北欧流のシニカルな笑いが好きだ。グレーンス警部と宿敵オーゲスタムのやりとりとか。
あっという間に読んでしまうので、買うときは上下巻まとめて購入するのがおすすめ。
広瀬正『エロス』
2014.1.1|review
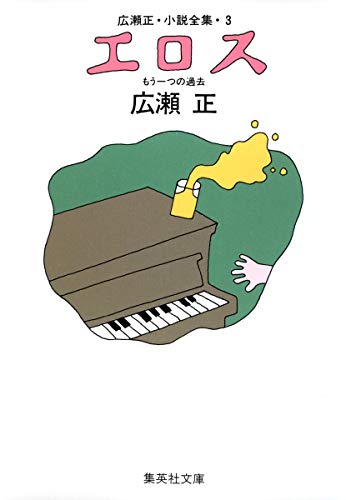
ん?エッ?そういうことだったの!!最後の最後に用意されているオチに仰天させられることうけあい。
東北地方の寒村から上京し、いまや「先生」と呼ばれるほどの大物女性歌手に、ある日ひとりの雑誌記者が「先生が歌手にならなかったら、桶屋式につぎつぎと連鎖反応を起こして、だんだんひろがって、そのあとの日本の姿まで変わっていたかもしれない……」と言ったところから始まる、もうひとつの人生のストーリー。
ふたつの「現実」はそれぞれパラレルに進行してゆくが、この小説の独創的なところは、登場する人々の顔ぶれはほぼ同じにもかかわらず「演じる役割」が異なるだけで〝ほんとうに〟「そのあとの日本の姿」まで変わってしまうという点にある。しかしその結末がどうであれ、これは「みつ子」と「慎一」という男女が紡ぐ大いなる「愛」の物語なのであり、作者があえてこのタイトルにこだわった理由もまたそこにあると思うのだ。
中田永一『くちびるに歌を』
2014.1.4|review

薄めのカルピスを小説にしたような、つまりさっぱり爽やかだけどなんとなく物足りなくもあるような、そんな青春小説である。
舞台は長崎県の五島列島。とある島の、合唱部に所属する中学生たちとそこに赴任した音楽教師との交流を淡々としたタッチで描いた物語。
彼らが出場をめざすのはNコン(全国学生音楽コンクール)と呼ばれる合唱コンクール。Nコンには「課題曲」があり、彼らは、15歳の「ぼく」が未来の自分に宛てて手紙を書くというストーリーをもつ『手紙』という作品を歌うことになる。そして、作品と向き合うため出された宿題(じっさいに未来の自分に宛てて手紙を書くこと)を通じて、15歳の彼らもまた、それぞれがいま抱えている「課題」と向き合うことになるのだった。
感動はないが、ひんぱんに登場する「サクマ式ドロップ」のエピソードなどちいさな仕掛けが最後にジワジワと効いて心地よい余韻を残す。
原宏一『ヤッさん』
2014.1.7|review

第一話「ホームレスのグルメ帳」をもじって「ホームレスのグルメ事件簿」とでもすれば、そのままテレビドラマに仕立てられそうな小説。
訳あって銀座を根城にホームレスとして生きる「ヤッさん」。一方、サラリーマンからドロップアウトし成り行きまかせでホームレスになってしまった「タカ」。そんな「タカ」に、なにより「ありきたりな身の上話」を毛嫌いする「ヤッさん」は、その生き様を通じて〝背中で〟生きることの意味を教え込んでゆくのだった。
〝正論〟を吐く主人公を「ホームレス」にでも設定しないとそのことばが読者の心に届きにくいという現実が、ある意味、現代という時代のややこしさを象徴している。
池波正太郎『殺しの四人 仕掛人・藤枝梅安』
2014.1.9|review
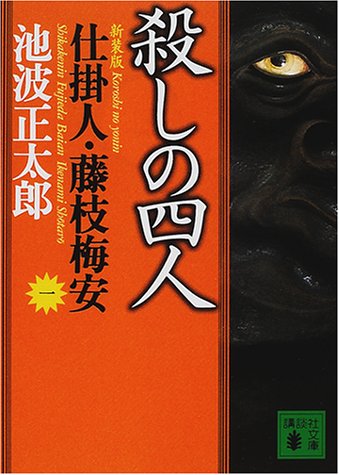
エッセイ以外ではじめて読んだ池波正太郎の作品。
主人公は藤枝梅安。オモテの顔は腕の立つ鍼医だが、「世の中に生かしておいては、ためにならぬやつ」をカネで闇へと葬る仕掛人というウラの顔をもつ。過酷な生い立ちが、彼を裏稼業へと追いやったのだ。そしてもうひとり、同じく仕掛人という顔を持ち、梅安が唯一「友」と心をゆるす彦次郎もまた悲惨な過去を背負って生きているのだった。
作者は、梅安らに「正義のヒーロー」という顔をあたえないが、そのかわり、彼らの存在を認めることで彼らに「居場所」をあたえる。「ためにならぬやつ」を生かしておかぬためには、彼らは生きねばならぬのだ。作者の梅安らに注がれるまなざしはどこまでも優しく、あたたかい。
コリン・デクスター『ジェリコ街の女』
2014.1.30|review

自信満々に誤った推理を展開する、尊大だがどこか憎めないモース主任警部と、お人好しで翻弄されてばかりな反面、モースの推理をたったひとことで崩してしまう意外な鋭さももつルイス部長刑事。そんなふたりの凸凹コンビぶりが相変らず楽しいシリーズ第5作(前回読んだ『ウッドストック行き最終バス』が第1作とのこと)。
イギリスの郊外が舞台だけに登場人物も限られ事件の内容も地味とはいえ、そういうことだったのか!!と唸らせる仕掛けはなかなか。
作者も訳者も『ウッドストック行き〜』と同じなのに、文章のリズムが異なり読みやすかった反面、モースのとぼけた笑いが薄まっていたのはすこし残念。ルイス部長刑事の登場も後半からでやきもきさせられた。
それにしても、このシリーズに登場する中年男性はなぜこうも揃いに揃ってモテるのか……。
乙一『箱庭図書館』
2014.2.5|review

あとがきで、読者から寄せられた原稿に手を入れた〝リメイク作品〟であると知り驚かされる。
収められた6つの作品はたしかにどれも手触りが異なるけれど、それぞれの舞台を【物語を紡ぐ町】というキャッチフレーズをもつひとつの土地に集約することで、見事、〝低体温の情念〟乙一ワールド全開の連作短編集に仕立てあげられている。
読み終わった後、つい雪の積もった日には〝しるし〟を探してしまうだろうなという作品、最後に収められた「ホワイト・ステップ」は、映像でもコミックでもおそらく伝わらないだろう、その意味で文字で書かれたものを読むことで〝なにか〟を受け取る小説ならではの表現の可能性をあらためて教えてくれる。
広瀬和生『談志の十八番:必聴!名演・名盤ガイド』
2014.2.17|review

クラシック初心者がいきなりフルトヴェングラーに手を出すのがキケンなように、落語初心者がいきなり立川談志に手を出すのはマズいのではないか?
そんな直観から、なんとなくずっと遠ざけてきた談志の落語。正直、まだまだ手を出す気にはなれていないが、いつか「その日」がやってくるであろうことは間違いない。「その日」に備えて、この本を手に取ってみた。
この本では、談志の「追っかけ」を自称する著者が、談志の手がけた数多い噺の中から誰もが認める得意の大ネタ10個(「鼠穴」「居残り」「芝浜」など)に加え、古典落語、談志ならではの噺、滑稽話、その他というカテゴリーから8個ずつの計42個をピックアップ、世に出ている音源をもとに詳細に比較しその特徴を挙げることで、絶えず更新され続ける談志落語の魅力について紹介してゆく。
談志ビギナーにとっては、どのあたりから手を付けるかということの大まかな「地図」になるし、ある程度すでに触れてきたひとにとってはまだまだ未知の領域があることを知るきっかけになるのではないだろうか。
五街道雲助『雲助、悪名一代 芸人流、成り下がりの粋』
2014.3.1|review

雲助師匠は、ぼくの中でちょっと〝ふしぎ〟な存在だ。他の噺家があまりやらない根多を持っていたり、他人から稽古をつけてもらわないという逸話もどこかで耳にした記憶がある。そういえば、二ツ目時代にはイラストレーター和田誠氏による新作落語も口演していたはず。〝一匹狼〟とでも言うのだろうか。さてさて、いったいどんな人物なのだろう?
そんな単純な興味を胸に読み始めた。
結果、ますますその〝ふしぎさ〟に輪が掛かったように思える。生まれ育った本所での暮らしぶり。情熱を傾ける対象をみつけると一気に燃え上がる青年時代のエピソード。十代目馬生の一門に身を置くことになったいきさつ。大師匠・志ん生の思い出や志ん朝一門に対する思い。古い速記本から根多を広げてゆくようになった背景には、師匠を失った孤独と同時に反骨精神も感じられる。また、入り浸っていたという浅草のハチャメチャな居酒屋の思い出や野坂昭如ら酒場で出会った人々との交友録からは、雲助師の意外な素顔も垣間見ることができ興味深い。
文中、みずからの生き様を称してたびたび言われる「成り下がり」という言葉については、その名前にふさわしく「雲」の如くひとところにとどまらず、自由に芸人としての一生をまっとうしたいという、雲助師による反ストイシズム宣言(?)と受け取った。
ダニエル・ペナック『人喰い鬼のお愉しみ』
2014.3.9|review

パリの百貨店に勤務するマロセーヌ。お客様のクレームを一手に引き受けるカリスマ苦情処理係といえば聞こえはいいが、真実は客の面前で上司から罵倒され、理不尽な処分を言い渡されることで同情を引き、寄せられたクレームをうやむやにするための「身代わりのヤギ」。そんな彼の目前で繰り返されるナゾの爆破事件。突然周囲から疑惑の目で見られるマロセーヌ。マロセーヌ危機一髪!はたして彼のヘンテコな友人や家族たちはマロセーヌの疑惑を晴らすことはできるのか……
というのが、この本のストーリー。もともと作者のペナックは児童文学の世界で人気の作家とのことで、この作品にもどこか童話のような残酷さやドタバタ騒ぎがあり、いわゆるミステリとは一線を画す。そば屋のエビ天よろしく、フランス文学臭たっぷりのレトリックが衣のごとくたっぷりまぶされふくれあがっているので読み進むにはかなり難儀した。そういうのが苦手じゃないというひとなら、ゲップの心配なくきっと楽しく読めるはず。
ピーター・ラヴゼイ『苦い林檎酒』
2014.3.9|review
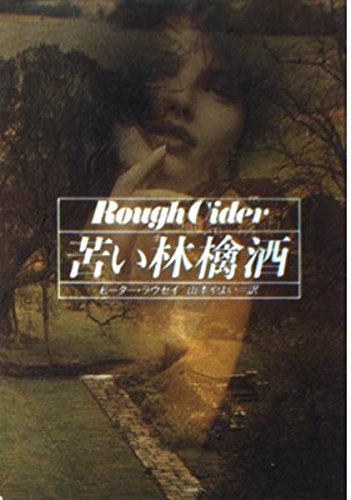
『偽のデュー警部』がやたらと面白かったラヴゼイのミステリ。舞台は60年代イギリスの片田舎。少年時代、疎開先の牧場で起こったある悲劇的な事件。
ある日突然、大人になり、大学講師となった主人公のもとをアメリカ人の若い女性が訪ねてくる。どうやら彼女は、その「事件」で彼の証言がもとで犯人と疑われ、絞首刑となった進駐軍兵士のひとり娘らしい。事件の真相を明らかにしようとする彼女の強引さに負け、封印したはずの二十数年前の記憶をいやいやながら辿らされるはめになる男……。慎重派で頑固なイギリス人男性vs奔放で強引なアメリカ娘、そんな対照的なふたりの「闘い」こそがこの作品のツボ。
タイトルにある「苦い」は、事件が発覚するきっかけとなったシードルの味と、孤独な少年の心模様とをかけあわせたダブルミーニング。読了後は、もちろんほろ苦い気分に。
ジェローム K.ジェローム『ボートの三人男』
2014.3.14|review
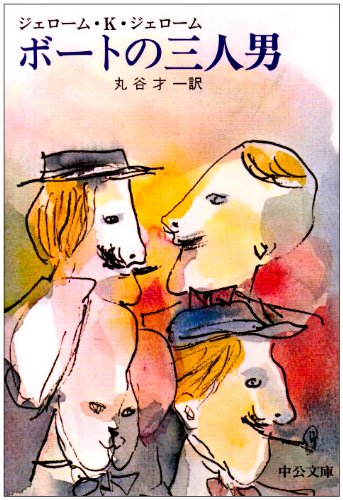
英国紳士3人のテムズ河ぶらり途中下船の旅(犬はさておき)。
1889年に出版されベストセラーになったイギリスのユーモア小説。小説といってもストーリーらしきものがあるわけでなく、ただただ3人の男と犬1匹が水門(ロック)から水門(ロック)へ、テムズ河を船で下ってゆくというだけの長閑な話。
にもかかわらず、船に縁がなく、ましてや紳士でもないぼくが読んでこうも面白いのはどうしたわけか。それはきっと、いかにもイギリス流の笑いにコーティングされてはいるが、万国共通の人間の《本性》が描かれているからにちがいない。いわば、「あるある」ネタ。
「自然に帰れ」とばかりに船旅に出たはいいが、ボートを漕ぐのに疲れたといっては不平をもらし、隙あらばサボろうとし、都合の悪いことが起これば他人のせいにする。そんな「いい大人」の「大人げない」七転八倒ぶりがおかしくてたまらない。そしてまさかのエンディング。晴れた休日の午後のんびり読むのにふさわしい、楽しい本と出会った。
ピーター・ラヴゼイ『絞首台までご一緒に』
2014.3.17|review
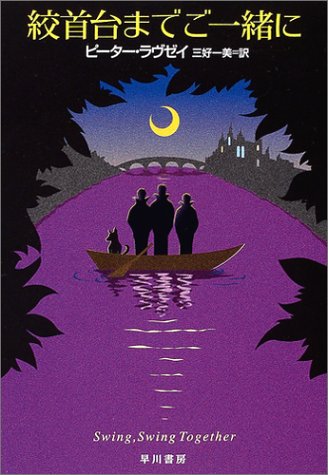
はたして犯人は「例の3人組」なのか?(犬はさておき)。
舞台は19世紀後半のイギリス。長閑なテムズ河で立て続けに水死体が発見される。よりによって目撃されたのは、ジェローム・K・ジェローム『ボートの3人男』そっくりの怪しげな「3人組」だった……。
「クリップ部長刑事とサッカレイ巡査」シリーズの一冊とのことだが、そういうわりには、ふたりの存在感はひどく薄い。どちらかといえば、犯人らしき人影を目撃したがために事件の捜査に巻き込まれる妄想暴走お嬢様こそが「主役」のような印象(シリーズの他の巻は未読なのでよくわからない)。
肩のこらない読書をご所望のみなさまに、ぜひラヴゼイ印のコミカルラブロマンスコージーミステリをどうぞ。
マージェリー・アリンガム『クロエへの挽歌』
2014.3.23|review

つねに腰が引けてるという点で、この『クロエへの挽歌』に登場する探偵キャンピオン氏はかなり風変わりな存在といえる。
劇場と劇場をめぐる人々による群衆劇。『クロエへの挽歌』はそうした体裁をとっている。生気には乏しいが、誰よりも人間観察に長けた探偵は、彼らが発する膨大な情報をひたすらインプットしてゆくことで、事件の背景にあるみえない相関関係をゆっくりゆっくりと可視化してゆく。
登場人物が多く、探偵に目を見張るような闊達さがなく、おそらくそれゆえにドラマに起伏が乏しいという点で、あるいはこの小説は読者を選ぶかもしれない。けれども、人間を描くことで事件の本質を描くという作者の手法にハマりさえすれば、淡々とした筆致のむこうに、ロバート・アルトマンの映画にも匹敵する〝コク〟を感じることもできるにちがいない。
ヒラリー・ウォー『事件当夜は雨』
2014.3.25|review
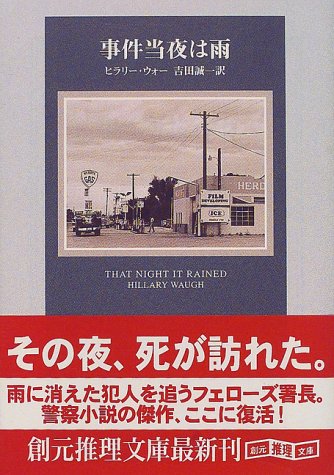
愚直なフェローズ署長が、アメリカのサバービアを舞台に執念深い捜査を繰り広げる警察小説。
しのつく雨の晩、ひとりの農夫が、全身ずぶ濡れの突然の来訪者によって射殺される。いわく、「わしはおまえさんに肥料代を50ドル貸してある」……。人間離れしたひらめきには欠けるフェローズ署長だが、ありとあらゆる仮説を立て、それをひとつひとつ丹念に潰してゆく胆力にかけては誰にも負けない。同僚は、その中に混じるあまりにも突飛な仮説を「成層圏的」などと揶揄するのだが、フェローズは聞く耳をもたない。そして、彼が必死になって「成層圏」にある真実をつかみ取ろうと手をのばす様こそが、読者にとってはこの小説のツボであるだろう。
真犯人が意外にあっさり逮捕されて終わりかと思いきや、アメリカの裁判制度がもつ矛盾にまで触れ、容易には事件にピリオドを打とうとはしないフェローズ署長の骨太な〝警察官魂〟にしびれる。
ミステリー文学資料館『探偵小説の風景』
2014.3.26|review

戦前に発表された「乗り物」が登場するミステリばかり15編を収めたアンソロジー。
鉄道、乗り合いバス、円タク、汽船やモーターボートなどさまざまな「乗り物」がさまざまなぐあいに登場するが、1905年前後に生まれた作家たち(個人的には日本のモダニズムをもっともよく体現している世代と思われる人々)の作品では、それ以前の作家たちの作品のそれとちがい、明らかに「都市」(あるいは「現代」と言ってもいいかもしれない)を描写する上での重要なモチーフになっている点が見逃せない。
作品の完成度、風合いはさまざまだが、そうした視点から読んでゆくと時代の移り変わりを感じさせる、なかなかに興味深いアンソロジーといえそう。
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム『制裁』
2014.3.30|review
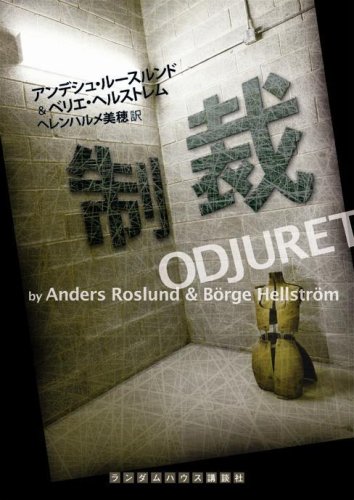
『三秒間の死角』のコンビによる、勢いのあるスウェーデン産犯罪小説。
ある日、ひとりの刑務官が私情に走った末に、護送中の服役囚(児童を狙った性犯罪者)を取り逃す。すべてのドラマはそこから、その小さな「しみ」から始まる。
卑劣な犯罪を憎む気持ちは、誰にとっても変わらない。しかし、その「憎み方」と、負の感情が周囲にもたらす影響はさまざまだ。被害者とその家族、捜査にあたる警官たち、職務上あくまで法に則って裁かざるをえない人びと、マスコミ、日ごろから不安や不満、不平で破裂寸前の「世論」という名の風船のような存在、そして独自の掟とプライドをもって生きる「塀の中の人びと」……。さまざまな人間がさまざまなかたちで関わることで、はじめ小さな「しみ」にしか過ぎなかった事件は、思いもよらない規模に広がってゆくのだった。
一見したところ端正な表情にみえる現代社会が、ボタンをひとつ掛け違えただけでいかに凶暴な姿のモンスターへと変貌してしまうか、重厚なテーマを映像のような速度と鮮やかさとで一気に読ませる傑作。
長井好弘『新宿末広亭のネタ帳』
2014.4.7|review

落語家という仕事が、寄席という場所が、新宿末廣亭のネタ帳(=寄席の「セトリ」)7年分を紐解くことで見えてくる。
毎日20人を超える芸人が登場する寄席。よって、ひとりあたりの持ち時間はせいぜい15分といったところ。その短い出番に、誰がどんなネタを掛けたのかを淡々と書き留めたものが寄席の「ネタ帳」である。
「我々の商売は、15分座って独り言を喋ったらそれで業務終了」とは瀧川鯉昇師のマクラだが、そのわずか15分の出番のために、落語家は「ネタ帳」でその日すでにどんなネタが掛かっているのかを確認し、噺が重複しないよう、全体の流れを損なわないよう配慮した上でみずからの高座に挑む。つまり、それなくしては寄席という場じたいが成立しないくらい重要な、いわば《羅針盤》、それが寄席にとっての「ネタ帳」なのだ。
寄席はまた、落語家にとって大切な修練の場でもある。長い噺をエッセンスはそのままに寄席で演じられるサイズにまで刈り込む創意工夫、演じなれたネタにさらなる磨きをかけるための試行錯誤、それらは寄席という《ホーム》なくしてはなしえないと、インタビューに答える噺家たちは異口同音に語る。なかには、そうした日々の鍛錬の積み重ねから、寄席専用の「勝負」ネタを編み出した落語家も。
寄席を出るとき、思わず「あぁ、楽しかった」と口に出るのは、芸人ひとりひとりのネタよりも、むしろ全体の流れ(グルーヴ)が気持ちよかった日であることを、この本を読みながらあらためて思い出した。
中村弦『伝書鳩クロノスの飛翔』
2014.4.24|review

読み終えた瞬間、眼前に大きな虹が架かったかのような気分になった。
昭和20年の中国、昭和36年の東京、そして「3.11」を経た現在の東京……
3つの時代が1羽の「伝書鳩」の活躍によってつながれるとき、そこに壮大な物語が完結する。
それにしても、なぜ「伝書鳩」なのだろう?
氾濫する情報や真実の意図的な歪曲や隠蔽によって、しばしば進むべき方向を見失いがちなぼくら現代に生きる人間がいまもっとも必要としている「力」、それを、あるいは彼ら「伝書鳩」が持ち備えているからだろうか。そしてその「力」とは、選び抜かれた言葉によって綴られた「真実」を、その直感と帰巣本能によって迷うことなく必要とする者の手にまっすぐ届ける力なのではないか。
過去に発表された2冊を読むかぎり、この作家はけっして声高に自身の主張を叫び読者に押し付けるようなひとではないが、そんな作者が「クロノス」という名をもつ伝書鳩に託したメッセージを、そしてしばしば彼を奮い立たせることになる「脚環」が放つ「光」の意味を、いま「3.11」以後の日本を生きるひとりの人間としてあらためて噛み締めてみたいと思う。
堀内隆志『鎌倉のカフェで君を笑顔にするのが僕の仕事』
2014.4.27|review

20周年を迎えた鎌倉のカフェ、「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」のマスター堀内さんの本である。
お店にとっていちばん大切なことは「続けること」である。いっとき脚光を浴びたとしても、一年や二年で消えてしまったとしたら、その店にはなんの価値もない、とぼくは思っている。続かない店は「店」ではなく、たんなる「イベント」に過ぎないからである。
お店をやっている人間はみな、ただただ明日もお店を無事開けられることだけを願い心を砕いて毎日を過ごしている。たとえばぼくのお店はようやく12年になろうというところだが、さて8年後となると、はたして続けられているかどうか正直なところよくわからない(もちろん続けられるものなら続けたいが)。それだけに、20年にわたりお店を続けてきた堀内さんに対しては、同業の端くれとしていつも尊敬の念でいっぱいである。
この本を読んだひとはきっと、「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」というお店が今日もここにあることの「すごさ」を理解するにちがいない。堀内さんが人知れず注いできた並々ならぬ努力と情熱、それに試行錯誤の繰り返しの「賜物」こそがディモンシュというお店なのである。
そして、「顔が見えるお客さんの笑顔のために続けてゆく」という、20年の歳月の中で堀内さんがたどり着いた「答え」こそはすべてのカフェオーナーの「思い」でもあるだろう。お店を「続けること」の中心は、お店に来てくださるお客様にほかならないのだから。
東川篤哉『館島』
2014.5.2|review

W浅野!! 冒頭、女探偵登場のシーンからそんななつかしのフレーズが脳裏をよぎる80年代フレーバー(というより、実際に設定が80年代なのだが)の本格推理小説。
永年の夢であった瀬戸大橋計画がようやく現実化しつつあった198×年、やがては瀬戸大橋の「橋脚」とならんとする瀬戸内海に浮かぶ小島に(岡山県ではその名前を知らないものはいない)〝孤高の天才建築家〟が酔狂なたたずまいの巨大な別荘を建てる。しかし、そのみずからが建てた別荘で、当の建築家が謎の転落死。さらに、真相はわからないままふたたび関係者たちが集った同じ場所で第二、第三の殺人が起こるのだった。
巨大な建築物をからめた壮大なトリックに舌を巻く一方で、登場人物たちがかわす会話のギャグセンスはどこまでも寒い。貴方はこの〝寒さ〟に耐えられるか?! W浅野!!
ジャック・フィニイ『ふりだしに戻る』
2014.5.14|review

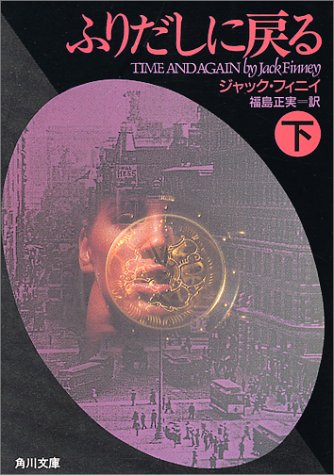
とある極秘プロジェクトの一員として《過去》へ行ってみないか?
ある日、イラストレーターとしてNYの広告代理店で平凡な日常をおくっていた主人公サイは、見知らぬ突然の訪問者からそう誘われる。
《過去》へ行くといっても、なにも「タイムマシン」のような機械が登場するわけではない。それは、アインシュタインの相対性理論に基づいた仮説に則っており、自己暗示による催眠術を援用することで狙いを定めた時空へと移動できるとするものである。職業柄すぐれた観察眼と描写力を備え、もともとノスタルジックな事物に人並みならぬ関心をもっていたサイはずば抜けた適応性を示し、プロジェクトの期待をあつめいよいよ《過去》へと向かうのだった。
向かった先は「1882年のニューヨーク、マンハッタン」。ガールフレンドの出自にまつわる謎めいた「遺書」の秘密を探るため、サイみずから志願したのだ。歴史を書き換えてしまう恐れから、「けっして干渉してはならない、観察に徹せよ」というのがこのプロジェクトの「鉄則」である。それゆえサイの「志願」に難色を示す上層部であったが、最後、このプロジェクトの発案者であるダンジガー博士の鶴の一声によってめでたく承諾される。そのとき、ダンジガー博士からひとつ「依頼」をされる。NYのとある場所へ行き、そこで自身の両親の「出会いの現場」を目撃、その様子を一枚の絵にしてプレゼントして欲しいというものである。この「依頼」が、最後、この小説全体のオチにつながる。
順調にタイムスリップしたサイは、まだ摩天楼も存在せず、街をひとや馬車が行き交う19世紀末の牧歌的なニューヨークの光景にすっかり心奪われてしまう。延々と続く細かい情景描写は、たしかにときに読み進めるのを辛くもするけれど、「タイムマシン」という便利な道具が登場しないぶん、読み手を物語の世界へ導く上では必要不可欠だとも感じる。とりわけ、そり遊びの情景は楽しく美しいし、乗り合い馬車の中で女性のスカートの裾がふわりと触れた瞬間の描写など、その「生々しさ」に思わず息をのんだ。
ガールフレンドから託された古ぼけた遺書の謎を解き明かすなかで、サイはひとりの女性ジュリアと出会う。やがて、遺書の謎がジュリアとも無関係ではないということがわかり、ともに行動するなかでふたりは思わぬ「犯罪」に巻き込まれてしまう。このあたりは、ちょっとしたミステリー風味である。いっぽう、おなじころ《現代》では、サイらによるタイムスリップの成功を受け、これを政治的に「利用」しようとする思惑をもつ一派と断固としてそれは認められないとするダンジガー博士とのあいだで激しい対立が起きていた。《現代》に戻り、この騒動を知ったサイはプロジェクトから離れる決意を固めるも、最後にひとつ「やり残した仕事」があると言い残し、ふたたびある決意を胸に「1882年」へと向かうのであった。
この『ふりだしに戻る』は、ジャック・フィニイによるファンタジーであり、ラブロマンスであると同時にときにミステリ、ときにサスペンスであるが、それ以上に「科学発明とその利用」をめぐるヒューマニズの物語でもあるのだと思う。
松尾由美『バルーン・タウンの殺人』
2014.5.21|review
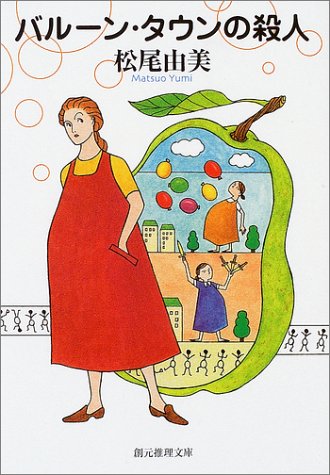
素行不良の《妊婦探偵》が活躍する、シュールな笑いにあふれたSFテイストのミステリ。
舞台は、東京都第七特別区。人呼んで「バルーンタウン」。そこは、「人工子宮(AU)全盛の世の中で、妊娠・出産という過程をへて子供を持つことをあえて選んだ女たちが、天然記念物なみの保護をうけて暮らす」妊婦の町である。そのちいさな、しかしかなり特殊な町で発生するさまざまな事件を、「妊婦のことは妊婦にきけ」とばかりに、見事な「亀腹」をもつ《妊婦探偵》暮林美央が鮮やかに解決する連作もの。
この妊婦探偵、厳密にいえばちがうのだろうが、分類としては《安楽椅子探偵》に入るのだろう。じっさい、電話口から示唆するだけのものもあるからだ(『バルーン・タウンの裏窓』)。「妊婦は透明人間なの。お腹以外は」などなど、全編をとおして名言(迷言)にもことかかない。
熊沢里美『だれも知らないムーミン谷』
2014.5.28|review

読書もまたひとつの《旅》であるとするならば、この本は著者による「ムーミン谷」への《旅》のいわばドキュメントであり、その足跡をたどることで、ぼくら読者もまた、べつの角度から捉えた「ムーミン谷」の新たな眺望を新鮮な驚きとともに手に入れることができる。
発端は、テレビアニメ「楽しいムーミン一家」を観て育った著者が、あるとき9冊からなる原作のシリーズを手にしたところからはじまる。本を読んだ著者は、当惑する。テレビアニメのなかでは「割愛」され感じることのなかった「ふたつの問題」が、原作ではシリーズ全体を貫く大きなテーマとなっていたからである。そして、著者はそこからひとつの仮説を導き出すのだった:「アニメ『楽しいムーミン一家』に描かれたムーミン谷は、原作において登場人物たちが直面するふたつの問題を克服した後のユートピア、いわば『省略されたユートピア』を描いたものなのではないか?」。
物語を丹念に読み解いてゆくことで、原作においてムーミン谷の住民たちが「克服」せねばならなかったふたつの問題ー「自然」と「住人どうしの関係」が浮き彫りにされる。読み解くにあたって、焚き火、ランタン、灯台、かまどなど物語に登場する《光》がもつ象徴的な意味に注目したのも面白い。「夏」と「冬」というふたつの季節が支配する世界の対峙も、北欧においては四季は日本ほど明確なものではなく、春は夏の、秋は冬のそれぞれ「露払い」程度にすぎないことを思えば納得のゆくところだ。
もちろん、ムーミン谷はフィンランドにあるわけではない。とはいえ、作者トーベ・ヤンソンが北欧の厳しい自然のなかで多感な少女時代を過ごし、物語を育んでいったことは紛れもない事実である。そして、そんな「北国のひと」トーベ・ヤンソンによる素朴な《民話》という側面から「ムーミン」を読み直すとき、著者は、現代の日本に生きるぼくらもまた未来を照らす《光》を手に入れることになるかもしれないと言う。まったく同感である。ムーミンの原作をいまこそ読もうと思う。
佐藤智子『「聞き上手」さんの習慣』
2014.6.9|review

口下手にもかかわらず、かれこれ10年あまり接客業に携わっている。接客とはいえ対面販売ではないのも幸いしているし、それにもうひとつ、自分がどちらかといえば「しゃべる」よりも「聞く」ほうが好きなのも、いまの仕事には好都合なのかもしれない。
かつて荻窪に店を構えていたころは、店内が狭く密な分、いまよりずっとお客様と会話する時間も長かった。そして、ときどき茶々を入れながら聞くお客様の話はなかなか面白く、楽しいひとときであった。いまは、そうした時間をあまり持てないのが残念である。
『1万人インタビューで学んだ「聞き上手」さんの習慣』(飛鳥新社)は、先日、常連のサトコさんと一緒にご来店いただいた佐藤智子さんの著書である。いただいたチラシの見出しが興味深かったので、ふだんあまりこの手のハウツー本は手にしないのだが、さっそく購入、読んでみた。
著者の佐藤さんは女性誌の編集者として十数年活躍した後、独立。1万人を超える著名人、スペシャリストら(そのなかにはクルム伊達公子や矢沢永吉の名前も!!)へのインタビュー実績を生かして、現在は編集者としての仕事以外にもタレント養成や各種セミナーでの講師としても活躍されている。ひと呼んで「カリスマインタビュアー」。
「質問する」という行為は、ちょっとしたコツ次第で、「知りたいことがら」への近道にもなれば、反対に遠回りにもなる。それゆえ、この「コツ」を知っているか知らないかは大きい。そしてそうした「コツ」を会得しているひとを、佐藤さんは「聞き上手」と呼ぶ。
口下手だから接客や営業には向かないとかんがえているひと、話し上手なのになぜか周囲とのコミュニュケーションがうまくゆかないと悶々としているひと、その両方のタイプに佐藤さんが教える「聞き上手のコツ」は役立ちそうだ。読んですぐ、近くのひとをつかまえて「実践」できるのもいい。
それにしても、ぼくを見るなり「色白いですね〜北欧っぽいわぁ」と言った佐藤智子さん、面白すぎです!!
小澤征爾・村上春樹『小澤征爾さんと、音楽について話をする』
2014.7.7|review

ハルキストでも熱狂的なオザワ信者でもないが、それでも、読み進むうちにどんどん膝を乗り出すように2人の対話に引き込まれてしまった。
音楽家は、楽譜に書かれた音符を通し作曲家と対話することで音楽と向き合う。それに対して、楽器を弾かず、ろくすぽ譜面も読めず、だが人一倍音楽を愛する人間は、とかく聴こえてくる音楽のむこうになにかしら文脈のようなものを読み取ろうとするものである。ここでの村上春樹の立場は、いわばそうした「音楽愛好者の代表」にほかならない。ぼく自身、まさにそのようなごくふつうの「音楽愛好者」なので、この本の中での村上春樹の発言やその意図については手に取るようにわかる。
ふつう、おなじ「音」について語ったとしても、こうしたまったく異なるアプローチの仕方で音楽とつきあってきた者同士の対話は失敗に終わることが多い。
ところが、会話が「滑ってる」という印象を受けないどころか、むしろ「奇跡」と呼んでよいほどに濃い対話が生まれているのは、それが一流の音楽家でありながら誰よりも強い好奇心と行動力をもつ小沢征爾と、音楽愛好者でありながら作家として誰よりも深い洞察力と多彩な語彙をもった村上春樹という選ばれた2人によるものだからにちがいない。元々、音楽を離れたところで2人が友人であったという事情も大きいだろう。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番をめぐっておこなわれた「第1回」のインタビューでは、村上春樹による巧みなリードの下、「指揮者という仕事」についてその手の内を明かすようなエピソードがさまざま語られていて興味深い。たとえば、太く長い「線」をつくることをなにより重視するカラヤンの音作りの指向性(文中、小澤は「ディレクション」と呼んでいる)は、たしかに指揮者カラヤンの音楽性を端的に表現したものである。
いっぽう、第3回「1960年代に起こったこと」を読んで、ぼくは、他にもたくさん優れた才能の持ち主がいるなかでなぜオザワが世界の頂点にまで登り詰めることができたのか、その「秘密」の一端に触れえた気がした。それは小沢征爾の天性の「人間力」、そしていい意味での「鈍感力」ではないか。
そのことは、第5回「オペラは楽しい」にもつながっている。しばしば「総合芸術」といわれ、音楽以外にも文学、美術、歴史などヨーロッパの文化や伝統に対する深い理解を求められるその特異な世界にあって、楽譜を深く読み込む力さえあれば十分通用することを小澤は証明してみせた。これは、もう、本当にすごいことだと思うのだけれど、ザルツブルグで、しかも『コシ・ファン・トゥッテ』(!)で彼をオペラデビューさせたカラヤンの慧眼にも驚かずにはいられない。
だが、いちばん興味深かったのは、小沢征爾がスイスで開催している若い音楽家たちのためのセミナーについて語り合った第6回「決まった教え方があるわけじゃありません。その場その場で考えながらやっているんです」。現地で視察した村上春樹によるレポートも併せて収められている。
技術を超えたところで、はたして「音楽」はどのように教えられるのか、教えられたものはどのように咀嚼され、継承されるのか。音楽家にとってはあたりまえでも、音楽愛好者にとっては秘密めいた儀式のようにもみえるそのやりとりが、「文字で」書かれていることにまず感動をおぼえる。目の前に、予期せぬご馳走を並べられた気分。
「それはちょっと僕には聞けないことだし、聞いてもきっと正直には言わないだろうな」。村上春樹が、セミナーに参加した東欧人+ロシア人からなるクアルテットに「どうして(自分たちのルーツとは疎遠な)ラヴェルの楽曲をあえて選んだの?」と質問したと聞いたときの小澤の反応である。
単身ヨーロッパに渡り、「東洋人がなぜベートーヴェンやモーツァルトを演るのか?
バッハは理解できるのか?」と言われながら現在の地位を得た小沢征爾の胸中には、そのときさまざまな思いがよぎったことだろう。そして、なによりも大切なのは、音楽と深いところで対話すること。それさえできれば、どこに行っても通用する。彼が若い音楽家たちに伝えたいのは、あるいはそういうことかもしれない。
文庫版の付録には、一度は引退を決めたジャズピアニスト大西順子を小澤がサイトウキネンフェスティバルになかば強引に引っ張り出し、共演を果たした際のエピソードが明かされている。そんな出来事があったとはまったく知らなかったのが、たまたま入った喫茶店で小澤・大西両氏の打ち合わせ場面に遭遇したぼくとしては、とても興味深かった。
たぶん、いずれまた読み返すであろう刺激的な一冊。
橘蓮二『この芸人に会いたい』
2014.7.9|review
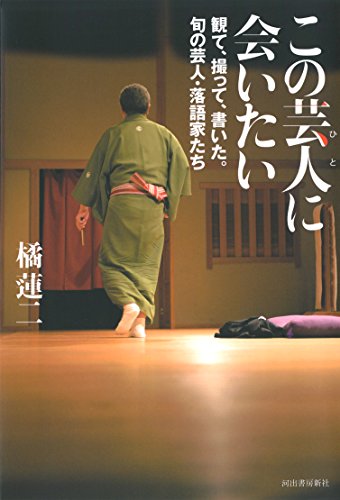
まるで、豪華な顔付けの「寄席」に出くわしたかのような満足感を得られる写真エッセイ。
開口一番に登場するのは、小三治師の弟子のなかでも若手真打ちの筆頭格、柳家三三師。本番前、高まる集中力の中まったくカメラの存在を意識していないかのような張りつめた表情、一転、高座の上での弾けるような活きのよさが印象的だ。
成城ホールで撮影された立川こしら師、鈴々舎馬るこさん、そして三遊亭萬橘師の3人会。馬るこさんのNHK新人演芸大賞受賞後のお祝いモード全開のこの日、こしら師がつけている「どくろ」紋の帯はポッドキャストで馬るこさんがプレゼントしていたものだなぁ。じんわりと感動。
既刊の『カメラをもった前座さん』でも思ったことだが、ぼくは個人的に橘さんが撮影した市馬師匠が好きだ。せせこましいところの一切ないゆったりとした高座が魅力的な師匠だが、被写体としての市馬師はこんなにも表情豊かなんだなぁ。
色物さんも多数。必殺仕事人の決定的瞬間がばっちり捉えられている。ふだんは見ることのできない寄席のお囃子さんたちの表情も新鮮。
そして、この本でトリに登場するのは柳家小三治師。「小三治師匠の高座は、ただ感じること。その一言に尽きる」。まさしくその通り。そしてそれは、写真を観るときの「作法」にもまた通じているのでは?
あ、そうか、だから小三治師がトリなのか。
斉須政雄『調理場という戦場』
2014.8.8|review

『ボクの音楽武者修行』のような「読み物」を期待して気軽に手にすると、あるいは肩すかしにあうだろう。
著者の生い立ちやどうして料理人をめざしたかといった事柄は、ここでは一切触れられない。主題ではないからだ。技術論もまた、主題ではない。この本で語られるのは、「コミュニュケーション」をはじめ料理人が「現場」で生き残ってゆくために手放してはならない、いわば「矜持」のような事柄についてである。そしてそれは、右も左もわからないまま単身フランスに渡った著者が、およそ10年にわたるサバイバルのような日々のなかで理解し体得したものにほかならない。
インタビューをもとにリライトしたものなので読みにくくはないはずなのだが意外に読み疲れしたのは、おそらく硬派な著者の人柄から溢れ出る「圧力」ゆえではないか。
東京建築探偵団『建築探偵術入門』
2014.10.29|review
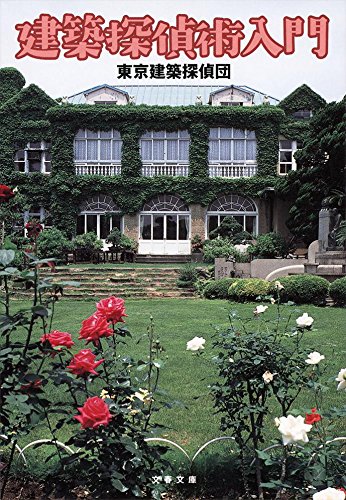
およそ30年ぶりの復刊。「東京建築探偵団」は、明治〜大正〜昭和(戦前)に建てられた「西洋館」のもつ《異物性》《用途の多様性》《デザインの多様性》に注目、そうした「西洋館」を自分の目と足で見つけ出し、生け捕りにしようという知的な狩猟のような試みである。
冒頭、「建築探偵『九つの心得』」が箇条書きにされているが、そのなかの「二、建物は手で見るをもって上とす」にはこんなふうに書かれている。「すぐ写真を撮るのは下」。町でこれという建物と出会ったら、まず眺め、手で眺め、そうしてペンを握りスケッチをすること。なぜなら「写真頼みの記憶は色褪せやすい」からである。納得。
ここに取り上げられた「西洋館」は、この30年の間にかなりの数が姿を消した。バブル期の再開発で取り壊されたものが多いような気がする。メンバーのひとり藤森照信氏があとがきに言うように、たしかにその意味ではもはやこの本はガイド本としては役立たずということになる。が、しかし、その後も、東日本大震災、2020年に開催予定の東京オリンピックを理由に古い建物はどんどん、なんの未練も躊躇もなく取り壊されている昨今、ぼくらも「建築探偵」にならって、自分たちが生きた時代を、ひとりひとりがその目と足と手で記憶に刻んでゆくべきときなのかもしれない。そういう意味で、いまだアクティブな一冊。
古川緑波『ロッパ食談 完全版』
2014.10.29|review

さしずめ、喜劇人ロッパの〝グルメブログ〟といった内容。
江戸っ子にもかかわらず蕎麦は食えず、寿司屋に行っても「こはだ、あなご、玉子」くらいしか食べられない。いっぽう、さすが男爵家に育っただけに物心ついたころからフォークとナイフを器用に操り西洋料理に親しむ反面、おでんや天ぷらといった「下司(げす)な味」をこよなく愛する。その偏食と大食が、こちら読者としてはかえってチャーミングである。
ロッパによれば、洋食や洋菓子の場合、おなじ店のおなじメニューでも戦争を境にすっかり味が変わってしまったという。もちろん「むかしの味」の方が、よかった、ということになる。ロッパとも親交のあった食通の映画監督.山本嘉次郎もたしか同様のことを言っていたと思う。戦争は、ことほどさように、ありとあらゆるものを変えてしまったのだ。
長井好弘『新宿末広亭―春夏秋冬「定点観測」』
2014.10.29|review

タイトルにあるように、1999年5月下席から2000年5月中席までの一年間、新宿末広亭に足を運んでの「定点観測」がこの一冊のテーマである。
読んで感じるのは「寄席は生きもの」ということ。お客さん、演者、天候……
さまざまな要素の組み合わせいかんによって寄席の表情もくるくる変わる。著者が通いつめた時期が、いわゆる「落語ブーム」前夜のもっともゆるみきった時代であったのも、逆に「寄席」が主役の読み物としてはかえっておもしろい。たとえば、いま2014年におなじことを試したとしても、こんな空気感は出ないのではないかなぁ。結果的に、ある意味しっかり「時代」を切り取ってしまっているところが興味深い。
『古今亭志ん朝』河出書房新社編集部
2014.10.29|review
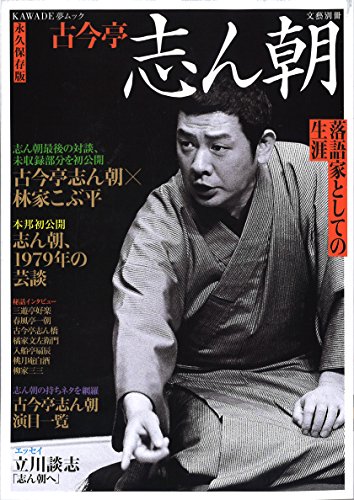
本人による芸談、対談、志ん朝に縁のある、また志ん朝を愛する人物によるエッセイ、後輩芸人たちへのインタビューからなるアンソロジー。掲載されたインタビュー等の大半は石井徹也氏がおこなっている。資料として演目一覧も所収。
読み進めてゆくうちに、いくつかのキーワードが浮上。
◎ 黒門町
いわずと知れた八代目桂文楽。独自の美意識に貫かれ、磨き上げれた楷書の「芸」。若き志ん朝は、みずからの範をこの黒門町にしていたようである。父として、師匠として、草書の「芸」の巨人、志ん生を身近に見ていたため、逆方向に突き進んでいったようだ。談志いわく、よくもわるくも「作品派」。
◎ くどさ
あるいは、わかりやすさ。芝居が好きで、役者をめざしたほどの人ゆえ、客席からみたときのわかりやすさ、イメージの共有を徹頭徹尾考え抜いたひとであったようだ。たしかに、説明調でありくどいのだが、聴いているときにはあまりそれを意識させないのは志ん朝の生まれ持った「芸品」のなせる技なのではないか。
◎ 太陽
「志ん朝師匠と関わりを持ったことがある人は、師匠のことを話すとき、本当にうれしそうな顔をする」と編集後記にあるように、後輩芸人たちのインタビューはしばしば志ん朝のことを「太陽のようなひと」と語り、しくじったときの経験までもうれしそうに語っている。
志ん朝の人となりを知るにつけ、落語の世界をあっという間に吹き抜けた一陣の、爽やかな風のように思う。
木内昇『漂砂のうたう』
2014.11.4|review

「水面はさ、いっつもきれいだけどなんにも遺さず移り変わっちまうでしょう。でも水底で砂粒はねェ、しっかり跡を刻んでるんだねェ」
明治維新から十年、刷毛で塗り替えるように新たな慣習や思想が過去を覆ってゆくなか、その急激な変化についてゆけないまま谷底の遊郭で砂粒のようにうごめいている人びとの姿を彼らの焦燥や哀感とともに描いている。その中で、「駕篭の鳥」という身分ながら決然と時代に立ち向かう花魁「小野菊」、ある種の諦観をもって飄々と生きる狂言まわし役の「ポン太」が印象的。
まさに漂砂のような速度で物語が進行するなか、後半、現実が三遊亭圓朝の噺とリンクしてゆく部分がスリリング。はたして、その後の言文一致運動に小野菊は一役買ったのだろうか……。
岡崎誠『かまくら落語会―いまから昔から』
2014.11.4|review
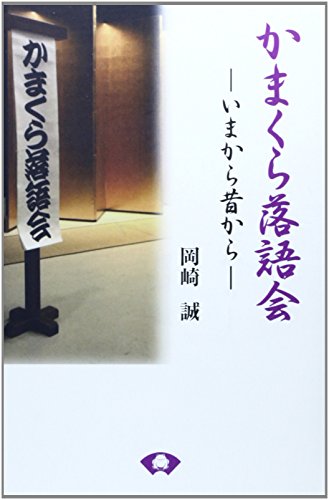
昭和47年にスタートした地域寄席の老舗「かまくら落語会」。その代表世話人を引き継ぎ、26年間あまり運営に携わってきた人物による貴重な記録。
著者の岡崎氏は本職が物理学者ということもあり、過去の資料を引きながらの叙述は読み物としてのおもしろおかしさには欠ける反面、出演した噺家とのやりとりや失敗談も含め感傷を排し事実のみを綴る「実直さ」に世話人としての人柄や落語会の会員に対する思いが感じ取られる。
地域寄席の貴重なドキュメントであるとともに、世話人とお客様、そして演者の三位一体によってつくられてきた歴史の重みに敬意を表したくなる。
アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会 5』
2014.11.12|review

ザ・様式美!?
このシリーズも第5弾、ついに最終作になってしまった。本人は、命あるかぎり書き続けると高らかに宣言していただけに名残惜しい。
ルービンの不機嫌に始まり、ゴンザロが出すきっかけに応じてヘンリーが鮮やかに、だが控えめに謎解きをするという黄金のワンパターンがここにきて完全に定着した印象。形式が決まった分、読み手も(ブラックウィドワーズのメンバーになった気分で)いっそう集中して謎解きに「参加」できるようになった。
なお、毎回密かに楽しみにしていた訳者あとがきが、この巻にかぎって有栖川有栖氏による解説に変わってしまったことだけが唯一、個人的には残念。
マージェリー・アリンガム『窓辺の老人』
2014.11.17|review
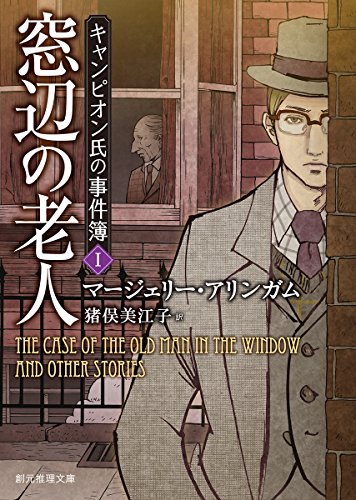
ミルクティーの似合う英国産ミステリ。マージェリー・アリンガムの短編集が文庫本で愉しめるようになったのが、まずうれしい。表紙の酷さはともかく。
古今東西の探偵のなかで、ここまで腰がひけ、覇気の感じられないキャラクターというのも珍しいのではないか。そんなキャンピオン氏とは対照的に、ギラギラしたスコットランドヤードのオーツ警視。掛け合い漫才のような面白さが、そこに生まれる。
あれ?
という感じに一気に「答え」があぶり出されるのもいつものパターンで、ご都合主義な部分もなくはないのだが、そういった部分もふくめて休日の午後にうってつけのコージーミステリとして気楽につきあいたい。
シャーロット・アームストロング『始まりはギフトショップ』
2015.1.8|review

いい大人たちが「ブタの貯金箱」を奪い合うお話。シャーロット・アームストロングの作品を読むのはこれで3作目だが、この「ほんわかさ」こそが彼女の真骨頂なのだろう。嫌いじゃない。
空港のみやげもの屋ではたらく平凡な貧乏女子大生が、ある日ひょんなことから事件に巻き込まれる。事件のカギを握るのは、そのみやげもの屋で売られていた赤、黄、緑、3個のブタの貯金箱。その貯金箱の行方をめぐって、イケメン資産家vsマフィアが激しい争奪戦を繰り広げる。なかば強制的に、イケメン資産家と「ブタの貯金箱」を求めて世界中を旅するハメになった彼女の運命やいかに……。ストーリーだけ書き抜くといかにもくだらない(失礼!)のだけど、軽〜い気分で読み進め読後感も上々なので、ぜひ旅のお供にどうぞ。
円居挽『丸太町ルヴォワール』
2015.1.8|review

まるで、糸の切れた凧を追いかけるような……。
いにしえの昔より京都の貴族たちのあいだで密かに執り行われてきた私的裁判「双龍会(そうりゅうえ)」。その決着は、「龍師」と呼ばれる者たちの弁舌次第。そこでは真実よりも、いかに論理的に破綻なく、「火帝」と呼ばれるいわば裁判長を、そして群衆(ぐんじゅ)と呼ばれる観衆を魅了し、納得させるかが重要となる。その凄絶な舌戦は、まさにめくるめくドンデン返しの連続であり、ポンコツ読者にとっては追いついてゆくだけで精一杯なのである。フ〜フ〜息切れしながらも、しかしその懸命の追走はクセになる。読了後の爽快感、そして切なさ。
シリーズ第一作であるこの『丸太町ルヴォワール』では、祖父殺しの疑惑とその事件のカギを握る女性「ルージュ」との白昼のミステリアスな邂逅を通して、龍師の家系としての宿命を担ってきた「龍樹家」と、論語、達也、流ら後に龍師として活躍する者たちとの「因縁」が語られる。ややこしいがすこぶる面白く、青春小説としても読める。
円居挽『烏丸ルヴォワール』
2015.1.8|review

天才肌の登場人物たちの中で、唯一〝人間臭い〟キャラクター流(みつる)。このシリーズは論語、達也、撫子らそれぞれがみな主役の青春群像劇でもあるのだが、個人的にはこれから先「流」がどのように成長してゆくのかが楽しみでならない。おそらく読み手の多くも、(とりわけ双龍会の場面では)「流」のいかにも〝人間臭い〟視点からドラマを眺めているのではないだろうか。その意味で、重要な狂言回しの役割を担っているのがこの「流」なのである。
シリーズ第二弾であるこの『烏丸ルヴォワール』では、「流」がその人間臭さゆえ敵方の陰謀に翻弄されることになる。伝説の龍師「ささめきの山月」、「流」同様コンプレックスを抱えたまま姿を消していた「烏有」ら新たなキャラクターも登場。双龍会における容赦ない騙し合いのスリリングさは相変らず、息を詰めて読み切ってしまった。
今後「ささめきの山月」はどのようなかたちでストーリーに絡んでくるのか?
はたして「黄昏卿」との直接対決はあるのか?
ますます楽しみになってきた。
円居挽『今出川ルヴォワール』
2015.1.11|review
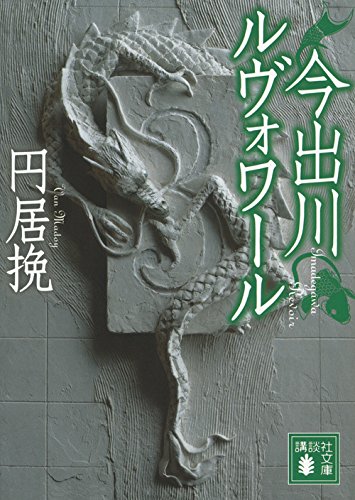
「オ・ルヴォワール」というフランスの別れの挨拶は、〝別離〟と〝再会〟という反対の意味を一語のうちに孕んでいる。いっぽう、ふたつの通りが交差する点によってあらわされる京都の地名もまた、そこに〝別離〟と〝再会〟とを孕んでいる。「ルヴォワール」シリーズ第3弾の舞台は、大怨寺という怪しげな寺院のある「河原町今出川」。当然、そこは積年の〝別離〟と〝出会い〟の交差点となる。
メインが、私的裁判「双龍会」におけるディベート以上に「権々会」における「鳳」と呼ばれるカードゲームに変わるとはいえ、その息を呑むような壮絶な騙し合いの連続は相変らずだ。そして最後、登場人物らの人間ドラマにも大きな変転が……
文庫化されているのはここまでだが、こうなったらこの勢いで「BOX版」で最終章まで読んでしまうべきか、はたまたご馳走は最後まで残しておくべきか……
悩ましい。
森川智喜『スノーホワイト』
2015.1.14|review

「魔法の鏡」というお題で抜群に頭の良いひとが小説を書くと、なるほどこんなミステリが出来上がるのか……。
「あちらの世界」では王家を継承する血を引くママエは、それとは知らず「こちらの世界」で世話役の小人イングラムとともに暮らす中学生。そのいっぽう、母の形見の「魔法の鏡」を密かに駆使して探偵業も営んでいる。そんなある日、とある依頼人の手引きでおなじ探偵業を営むふたりのクセもの、緋山燃、そして「我こそは名探偵」と公言してはばからない三途川理と引き合わされたママエは、「あちらの世界」の戴冠式に絡んだ陰謀から思わぬ事件に巻き込まれてしまう……
ミステリーながら、いきなり「魔法の鏡」「小人」といった飛び道具(?)の登場に面喰らうし、年齢的に仕方ないとはいえ、ママエの幼さ、身勝手さに共感できないのも読んでいてつらいところ。とはいえ、「魔法の鏡」を縦横無尽に使い倒す三途川の頭脳には舌を巻かずにいられない。とにかく、読者に息つく暇をも与えない矢継ぎ早のトリックは面白く、おとぎばなし的な舞台設定もさほど気にならなくなってしまうのだ。ラストの種明かしは……う〜ん……ひとひねりせずにはいられない作者の性格が出ている感じ?
──
【以下、ネタバレ】
「白雪姫」的なオチというのは分からないでもないが、個人的には、とどめはママエ自身の手でお願いしたかったかな?
オトナへの階段として。シリーズものらしいので、そのあたりの事情からママエのキャラは変えたくないかもしれないけれど。
島田荘司『異邦の騎士 改訂完全版』
2015.1.20|review

評判通り、ミステリの教科書のような精緻に構成されたストーリーに一気読み。
序ー記憶を失った男。ふとしたことから出会った女との蜜月。飄々としてつかみどころのない、しかし憎めない人柄の青年、御手洗潔との不思議な友情。
破ー失われた過去への執着とともに、理性を失ってゆく女。過去を辿るなかで知った、自身にまつわるおぞましい事件の存在。
急ー復讐。御手洗潔による推理。愛の完結。
ところどころで引っかかっていた事柄が、まさかこのようにつながっていたとは……そして、読了後にはその秀逸なタイトル(ロマンティック・ウォリアー)に感服。
全編をつらぬく、昭和の湿り気を帯びた空気感も重要な要素。
米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』
2015.1.24|review

人一倍「執念深い」小山内サンと人一倍「口を出したがる」小鳩クンとは、おなじ高校に通う同級生。ふたりとも、どうやら過去にそんな性格が災いし手痛い目にあっている様子。高校入学を機にそんな「短所」を封印し、「小市民」として地味ながらも穏やかなスクールライフを送ろうと誓うふたりだったが、皮肉なことにそんなふたりの前に次から次におかしな事件が起こり……。
いわゆる学園を舞台にした「日常の謎」モノ。文庫書き下ろしの四部作。この『春期〜』は、第1作だけにまだまだプロローグといった印象。今後に期待をもたせる感じ。「おいしいココアの作り方」は、もっと単純なやり方もあるように思うのだが、賢吾のキャラクターに引っかけつつ、読者が思いもしないような方法を披露したかったってこと、かな?
※アアルトコーヒー庄野さんからのおすすめ本
万城目学『鴨川ホルモー』
2015.1.28|review
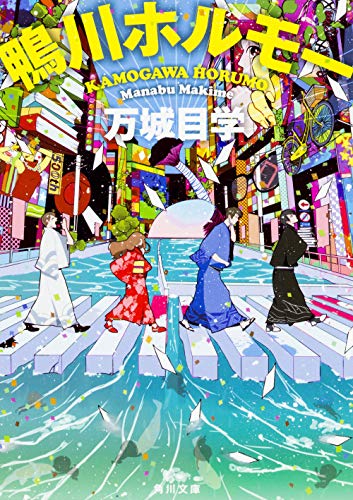
生まれ変わったら、大学生活は京都で送りたい。是が非でも。鴨川の河岸に等間隔で並んだカップルを見て以来、ずっとそう思っている。もしも京都で大学生活を過していたら、この人生もまた相当ちがったものになっていたにちがいない。かえすがえすも残念である。
ひとことで言えば「青春小説」だが、こんな小説の舞台は京都をおいてほかにない。バカバカしさが(だいたい100匹のオニを引き連れた大学生って!)、奇妙にリアルでありうるのは、なによりもここでは「京都の大学生たち」が主人公だからである。憧れと嫉妬をもって読んだこの小説、かなり面白い。悔しいけれど。
最後に、大学生活を京都で送った人たちになにかメッセージするとするなら次のように言わせてもらう。人生におけるあなたのピークはすでに終わっている、と。
米澤穂信『夏期限定トロピカルパフェ事件』
2015.2.2|review
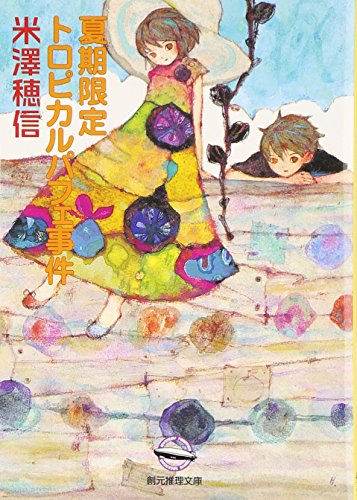
ちょっとクセのある高校生ふたりが身近なナゾに挑む地方都市を舞台にしたライトなミステリ……
と思いつつ読んだ前作『春期限定〜』だったのだが、この作品ではいい意味で読者の予想を裏切ってくれる。
前作では、主人公たちがしばしば口にする「小市民」とか「互恵関係」といった言葉がいちいち口実めいていて、なんだか喉に刺さった小骨のように鬱陶しくも感じられたのだが、今作ではその意味が少しずつ明らかになり輪郭を帯びてきた感じ。小佐内サンが暗黒すぎて不気味ですらある。
「過去」を葬り去りたいふたりだが、どうもそうはいかない様子。次回作がいよいよ楽しみになってきた。
パトリック・デウィット『シスターズ・ブラザーズ』
2015.2.4|review
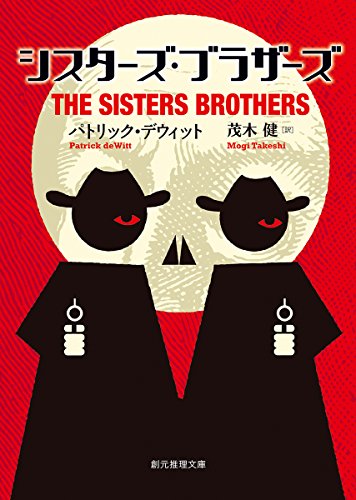
チャーリー&イーライ・シスターズは、泣く子も黙る兄弟殺し屋。「山師ウォームを殺れ」との雇い主からの依頼を受け、オレゴン・シティからゴールドラッシュに沸くサンフランシスコめざしハチャメチャな旅がはじまる。
暴力、博打、裏切り、復讐、泥酔、皮肉な笑い……
知っているところでは、ブコウスキーの小説、コーエン兄弟やタランティーノの映画とおなじ匂いをもつ小説。破天荒で不思議な彼らの旅は、また家族再生の旅でもある。
事件は次から次に起こるも、そこにミステリー要素はなし。解説にある「ウェスタン・ノワール」という表現がいちばん近いかな。
北杜夫『どくとるマンボウ航海記』
2015.2.6|review

現実逃避には紀行文がいちばん。できれば、凡人とは目線がズレていて、しかもコミカルなのがいい。『どくとるマンボウ航海記』は、まさしくそんな条件を満たす絶好の一冊。
「掘りだされて一年目のゴボウのごとく疲れ果てた…」(上陸がうれしくてついはしゃぎすぎたマンボウ先生)
「もっとも安くもっとも面白い場所を古ギツネのごとく捜しだす…」(古参乗組員について)
「海と空の中間の色彩で、ほそく一直線におどろくほど起伏なくつづいている」「それはいかにも涯がなく,窺いきれぬほど暗黒なものを蔵しているかのようだ…」(船上から目にしたアフリカ大陸の眺めについて)
こんな独特の表現とともに、いまはもう二度とこの目で見ることはできない60年近くも前の世界が生き生きと立ち上がってくるのだから、なんとすてきなことだろう。
中島京子『小さいおうち』
2015.2.12|review
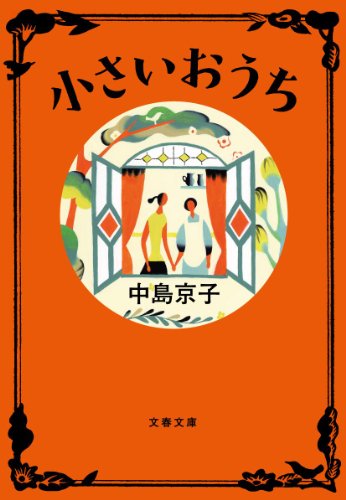
坂の上の小さいおうちとそこに暮らす人たちの世界、さらには、その小さいおうちを取り巻く世界。さいしょは同じだったはずのそのふたつの「世界」は、戦争の足音が大きくなるにつれ次第にズレてゆく。やがて小さいおうちは、まるで荒波にもまれる小さな船のように思わぬ方向へと流されてゆくのだった。
語り手は、この小さいおうちとそこに暮らす人びとに深い愛情を感じている女中のタキ。晩年、タキが綴る手記をもとにストーリーは進んでゆくが、それを「盗み読み」する甥っ子のいかにも現代っ子らしい視点がミックスされているのがこの小説の特徴といえるだろう。おかげで、物語が「昔話」に終わらずに済んでいるからだ。
「謝らなくていいわ。わたしが欲しいのは、心のゆとりなのよ」と奥様の時子は言う。また、巻末に収められた作者との対談で、船曳由美さんは次のように述懐する。「戦争というのは、そういうハイカラな、もっとも大事な心に響くものからなくなっていくんだというイメージがありますね」。
街から、心にゆとりをもたらす物や店が次第に消え、またそうした考え方がなんとなく憚られるようになったら要注意だ。ここ日本にあって、庶民にとっての戦争とはある日突然に火蓋が切られるといったものではなく、平和な日常のすきまからじわじわと浸み込み、気がついたときにはもう手の施しようがなくなっているのだ。
松葉一清『帝都復興せり!―「建築の東京」を歩く』
2015.2.17|review

著者は関東大震災による壊滅的な被害からの約10年間、いわゆる「復興期」の建築ラッシュこそが現在の東京の原風景をつくったと考え、昭和10(1935)年に都市美協会が発行した写真集『建築の東京』を手に、そこに収められた500件ちかい建物を地道なフィールドワークによって訪ねあるく。
訪ねあるいた昭和61(1986)年、『建築の東京』発刊から50年を経過した時点で踏査できたのは450軒、すでに半数以上の建築が姿を消していた。建物の現存を確認すると同時に著者は、そのわずかな期間のうちに出現した建築の数もさることながら、そのスタイルの百花繚乱ぶりに驚かされる。
アールデコ、ドイツ表現派、フランク・ロイド・ライト風、インターナショナルスタイル、古典風、日本趣味……そうしたさまざまな様式と思想があたかも当然のごとく並立し、ときに混交しながら乱れ咲いている。その折衷的なあり方こそが、「復興期」の建築のなによりもの特徴であると著者は言う。
建築に限らず、そこには西欧の文化をわずかな時間のうちに受容し消化していった島国「日本」の姿があるのではないか。
ヘレン・マクロイ『幽霊の2/3』
2015.2.20|review

読者には早々に犯人とその手口をなんとなく仄めかしておいて、種明かしはジワジワあぶりだしのように時間をかけてというのがこの小説のスタイルなのだろうか?
まんまとじらされてイライラしながら読了。
登場人物の会話のなかに出てくる「イギリス人はかんたんなフランス語の題がつけられた小説を好む」というエピソード同様、この作品からチラチラ顔を覗かせるディレッタントな雰囲気は、ヘレン・マクロイが「意図して」流行小説風の装いをしてみせたということなのだろうか?(他の作品を読んだことがないのでわからない)いや、ただの考え過ぎ?
登場人物や舞台をはじめ、とても洒脱な雰囲気をもったミステリだと思う。そんな中、探偵役のベイジル博士が他の登場人物たちと比べてヒューマンな魅力に欠けるので、なんとなく事件は解決しても物足りない気分になってしまうのだった。笑
寺田寅彦『銀座アルプス』
2015.2.28|review
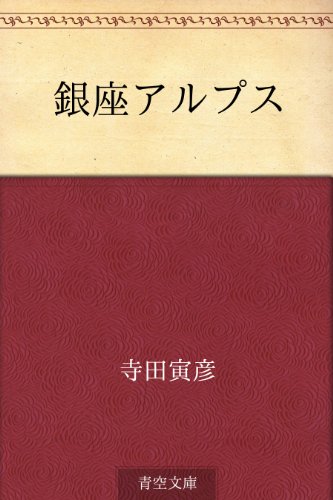
「雪や寒い雨の日にコーヒーのうまいのはどういうわけであるか気象学者にも生理学者にもこれはわからない。空気が湿っていて純粋な「渇(かわき)」を感じないために、余裕のできた舌の感覚が特別繊細になっているかもしれないと思われる」。つい先日ネットでみかけたこんな一節をあらためて読みたくて、パブリックドメインにつき無料でダウンロードできるキンドル版で入手した。明治12(1879)年生まれの著者が、昭和8(1933)年に発表したエッセイである。
記憶の「対流」によって、前後に流れる明瞭な時間の感覚を失ったまま、しかしかえって部分的にはさながら映画のように鮮明に思い出される明治の「銀座」の光景が、幼少時代の、青春時代の、著者のまなざしを通して投射される。
「心がにぎやかでいっぱいに充実している人」にはあえて避けて通りたい銀座のにぎわいも、「心の中に何かしらある名状し難い空虚を感じている」人にとっては、そこに行けばさながら「アルプス」のごとく「空虚が満たされそうな気がして」つい足がつい向いてしまう、著者はそう語る。
もういっぽうで、このエッセイが発表された昭和8年当時の銀座について思いをはせる必要がある。関東大震災で壊滅歴な打撃を受けた東京は、国を巻き込んでの大規模な帝都復興のスローガンの下、雨後のタケノコのごとく近代的な建築がつぎつぎと誕生する。
「摩天楼」とまでは呼べないまでも、モダンでノッポの「ビルヂング」を山々の連なる嶺として、また、きらびやかなネオンの輝く様を咲き乱れる草花として、著者は突然姿を現した「銀座」の姿を「アルプス」に見立てたのであろう。そこには、新しく誕生した都市の姿を愛で、称賛する著者の心持ちをうかがうことができる。その証拠に、著者は都市を破壊する地震への備えを訴えてこのエッセイを締めくくるのだ。しかし皮肉なことに、そのわずか10年ほど後に「戦争」がこの美しい「アルプス」を蹂躙してしまうことを、まだこのとき著者は知らない。
木村衣有子『銀座ウエストのひみつ』
2015.3.2|review

流行りに飛びつかない、「変えない」のではなく「変わった」と(お客様に)気づかせないように変えることをもってよしとする……
東京を代表する洋菓子舗「ウエスト」の「ウエストらしさ」をめぐる論考は、また、はからずも「東京らしさ」をめぐる論考にもなっている。その意味で、この本が関西の出版社から登場したということも興味深い。
現社長を中心に、職人やウエイトレスら「ウエスト」を支える人びとの言葉には仕事への愛着がうかがえるが、どこかおっとりとしていて変にこけおどしなところがないのがいい。よくあるカリスマ社長が伝授する成功の秘訣といった趣きは皆無。アクの強さや個性より、社是である「真摯」という言葉を羅針盤にして帆船「ウエスト」号は今日も鷹揚に航海をつづけるのである。
泡坂妻夫『11枚のとらんぷ』
2015.3.11|review
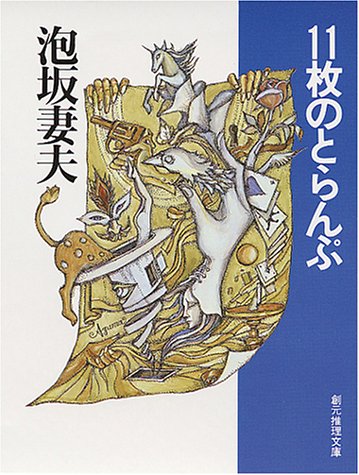
さほどマジックに関心があるわけではないため、たびたび書店で目にしながらも触手ののびなかった一冊。ところがふとしたきっかけで手にし読み始めたところ、思いのほか〝愉しい〟一冊であった。
とある地方都市の、アマチュアマジシャンの同好会「マジキクラブ」。その晴れ舞台ともいえる発表会でのドタバタ騒ぎを描いた第一部。そして、殺人事件の発生。メンバーそれぞれの紹介にもなっている。
第二部は、メンバーのひとりである学究肌の鹿川が11のトリックを小説形式で描いた私家版『11枚のとらんぷ』がまるのまま収められている。主人公はそれぞれメンバーが実名で登場する上、後の謎解きに役立つ伏線が多数ちりばめられている。
ジャックタチの映画を彷彿とさせる、世界中の奇術師や愛好家たちが一堂に会する一大イベント「世界国際奇術家会議」の乱痴気騒ぎの中、ちいさな事実の積み重ねが犯人の姿をあぶりだしてくる第三部。そして、思いがけないシナリオの存在。自身、奇術愛好家として知られ玄人はだしの腕前をもつマジシャンでもあったという著者だけに、この章は愉悦にひたりつつ書いたであることが読者にも伝わってくる。だからこそ、読んでいて楽しい。日本の奇術史の紹介や明治時代にヨーロッパに渡った日本人奇術師の横顔なんてとても勉強になる。
作中、フランス人マジシャンが口にする「私は現象のごたごたした奇術は好みません。その代わり一つの奇術の中にある不思議さを、私は大切にいたします。一人息子のようにね」というセリフは、奇術愛好家である著者の美意識の表明であるとともに、事件の謎を解くひとつのきっかけにもなっている。
久生十蘭『魔都』
2015.3.17|review
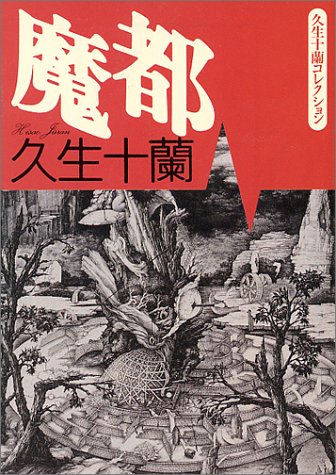
昭和9(1934)年の大晦日、三流新聞の記者である古市加十は、ひょんなことから銀座のはずれのバーで安南国の「王様」と引き合わされる。
そのまま「王様」の妾宅へ連れてゆかれた古市は、偶然にもそこで愛人の殺害現場を目撃、さらに「王様」は謎の失踪をとげる。これはたんなる偶然なのか、それともなにかしらの罠なのか。古市はこの「特ダネ」で一発あてようとみずから事件の渦中へと身を投じる一方、その冷徹さから恐れられる警視庁の真名古刑事もまた、そこにとてつもない陰謀の匂いを嗅ぎ取り独自に捜査を開始するのだった。
政治的な思惑や安南におけるボーキサイトの利権をめぐる争い、裏切りや騙し合い、組織の腐敗など、まさに闇鍋のように混沌としたこの時代の空気に充満した傑作探偵小説であると同時に、モダン都市東京を描いた貴重なポートレイトでもある。
物語は、大晦日の宵の口にはじまり年が明けた2日未明に大団円を迎えるまでの1日半ほどの出来事を描いている。初出は雑誌「新青年」昭和12(1937)年10月号から翌13(1938)年10月号まで連載された。ざっくり言うと、一日の出来事を一年間で書くという趣向だったわけである。そのため、あらためて続けて読むとやや冗長だったりご都合主義的に感じ取られる箇所もないではないが、そのあたりの事情を汲めば気になるほどでもない。
じつは、終盤までこれは本邦初(?)の警察小説なのではないか、と興奮しながら読んだ。上層部の権力闘争や組織の腐敗と戦いながら、懐に「辞表」をしのばせつつ真実を突き止めようと孤軍奮闘する刑事の姿は、この小説のもうひとつの読みどころでもある。ところがどうしたわけか、最終章ではいきなり義理人情的な決着がなされてしまう。
「定本久生十蘭全集1」(国書刊行会)に付された解題で、江口雄輔氏は次のようなエピソードを紹介している。「軽井沢の山荘でシャンパンや生卵を摂りながら、『魔都』の最終回を口述筆記させられた、という土岐雄三の証言もある」。もしそうだとすると、この最終章での決着への違和感はやはり執筆当時の「趣向」から生まれたものといえるかもしれないが、震災から10年あまりを経て完全に復興をとげた帝都東京の近代的な「顔」とは裏腹に、いまだ精神的には前近代を引きずっていた30年代の東京の、まさに「時代の気分」といったものが臆せず表出されているようでむしろ興味深くもあるのだ。
この目次を見よ
2015.9.6|book
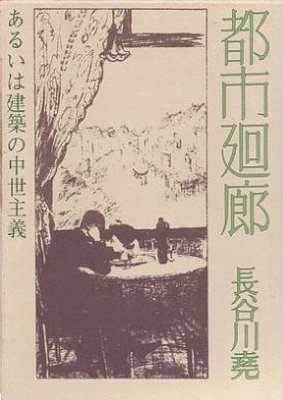
中世主義というキーワードから、大正時代の建築を読み解いた刺激的な論考。というのでは、この長谷川尭による『都市廻廊あるいは建築の中世主義』という本をまったく説明できていない。建築史というのは表向きの顔、じっさいには明治と昭和のはざまに花ひらいた大正という時代を、ある一面から徹底的に抉ったギラギラとした思想書なのである。そしてまずはともかく、この詩的な目次を見よ!
長谷川 尭『都市廻廊あるいは建築の中世主義』
目次
第一章
「所謂今度の事」をめぐって
叛 逆 者
大正元年のCOCA COLA
三田の丘の上
小さいものから
高松政雄のラスキン
新しい心斎橋と日本橋
りうりうと仕上がったのでお芽出度い
河のなかの「江戸の唄」
妻木頼黄という建築家
「陸の東京」への咆哮
水上のシャンゼリゼ
荷風の中世主義
日和下駄に蝙蝠傘
裏町と横道を行こう
軽蔑なしに羨ましい
細長い〈囲い地〉
コバルトの空の下の虞美人草
水上都市の構想
「メイゾン鴻の巣」
芝の上に居る
復元街区
小屋談義
「物いひ」
四十二年組
山崎静太郎の構造の主体性の主張
反 論
レアリテとヴェリテ
第二章
〈囲い地〉について
囲壁の内側
都市改造の根本義
バ ラ ッ ク
相 互 扶 助
復興都市の建築美
賀川豊彦の学会での講演
ギルドとサンジカ
〈都市〉としての」ハワードの発明
『ガーデン・シチーに就て』
樹木をよける道
コテージ
内部のふくらみ
日本のカントリーハウス
ヴォーリズと近江八幡
モリスと云ふ先生
ある提案
第三章
『様式の上にあれ』
考え方の変化
未来への遁走
現 在
神の臨在
量塊・表面・平面
陰 影
北への視界
ストックホルムの石
バルセロナで
雪の中に立つ
部分から全体へ
手と機械
私のロマネスク
あとがき
原田マハ『ジヴェルニーの食卓』
2016.2.11|book

歴史に名を残す画家たちの〝最後の日々〟を、身近で接した女性たちの眼をとおして描き読後に静かな余韻を残す短編集。
登場するのはマティス、ドガ、セザンヌ、そしてモネの4人。たとえば、マティスをとりあげた『うつくしい墓』は、老いてなお枯れることを知らない天才のインスピレーションとその創造を支える周囲のひとびとの献身的な愛を若いメイドの眼をとおして語らせながら、それが同時にマティス晩年の傑作《ロザリオ礼拝堂》誕生の隠れた物語にもなっている。
それぞれの物語には、共通して女性たちが早朝「窓を開ける」シーンが登場する。 それは、刻々と迫る敬愛する老画家との「別れ」へのカウントダウンであり、また、〝最後の日々〟を共にできることへの「歓び」をあらわしているのではないか。
実在の画家たちが登場するとはいえすべてはあくまでもフィクションであり、そういうことがあったのかもしれないし、またなかったのかもしれない。けれども、そうした事実関係の詮索よりも、史実をもとに、その隙間をていねいにパテで埋めてゆくような作者の驚くべき想像力と知的な遊び心をこそ楽しむべき本なのだと思う。これもまた、「絵」を愛するひとつの方法にちがいない。
「Hemisphere」04号
2016.2.12|book
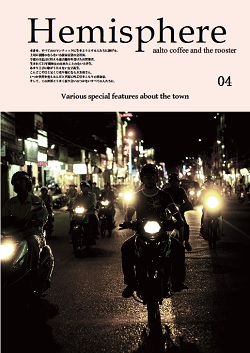
徳島アアルトコーヒーの庄野さんが発行するZINE「Hemisphere」の第4号が出ました。特集は「town」。庄野さんの人柄を反映して、今回も多彩な執筆陣が参加しています。ぼくもまた、前号に引き続き文章を書かせていただきました。
執筆陣は次のとおり
- キッチンミノル(フォトグラファー*表紙写真)
- 木下綾乃(イラストエレーター)
- 甲斐みのり(文筆家)
- 堀部篤史(誠光社店主)
- 堀内隆志(cafe vivement dimancheマスター)
- 高山大輔(かもがわカフェ)
- 長谷川ちえ(エッセイスト、in-kyo店主)
- 落合恵(イラストレーター)
- 井口奈己(映画監督)
- 熊谷充紘(編集者)
- 福岡晃子(チャットモンチー)
- 曽根雅典(三軒茶屋nicolas料理担当)
- 石亀政宏(夜長茶廊店主)
- 大塚いちお(イラストレーター・アートディレクター)
- カサイミク(コピーライター)
- 岩間洋介(moi店主)
- 中原中也
- しゅんしゅん(素描家)
- 山田稔明(シンガーソングライター)
- トラベラーズチーム(TRAVELER'S FACTORY)
- タナカヨシユキ(ツバメコーヒー店主)
- tomoko style(漫画家)
- 藤原康二(ミルブックス主宰)
- 田辺玄(WATER WATER CAMEL *付録CD)
- 広瀬裕子(作家・翻訳家)
- 坂口安吾
- 福田利之(イラストレーター*絵)
ところで、庄野さんからの依頼は「〝town〟というお題でなにか書いて下さい」というシンプルなもの。迷った挙句、ぼくはかつて吉祥寺に移る前5年半ほどお店をやっていた荻窪という街のこと、そこで出会い、(たぶん)街を後にしたひとりのお客様とのエピソードを、コール・ポーターの「町を出よう」というスタンダードナンバーに引っ掛けて書かせてもらいました。「カフェ」とは、出会いの場所であると同時に時間であり、ときにその記憶でもあるということ。
どこかで、なにかの折に手に取っていただければ幸いです。なお、当店でも現在お取り扱いしておりますのでご希望の方はぜひお求めください。
〝北欧っぽさ〟と竹山実のデンマーク
2016.5.7|book

渋谷のランドマーク「109」をはじめ、数々のポスト・モダン建築で知られる建築家・竹山実。『そうだ!建築をやろう―修業の旅路で出会った人びと』(彰国社)は、札幌に生まれ学生時代を東京で過ごした彼が、その後アメリカからデンマークへと渡り歩くなかで出会った〝忘れ得ぬひとびと〟をピックアップし、その思い出を綴った回想録である。
1962年、アメリカを離れることになった竹山は、デンマークに渡り、シドニーオペラハウスのコンペを勝ち取ったばかりのヨーン・ウッツオンのアトリエに職をみつける。地図を見ながら、コペンハーゲンから北へ車で1時間ほど離れた海辺の町にあるウッツオンのアトリエまでようやく辿り着いてみると、アトリエにはウッツオン本人はおろか、留守番の所員の姿すらみあたらない。そして、ドアに貼られた一枚のメモ書きにはこんなことが書かれていたという。
──「ミノル。よく来た。家の中に入って、着替えて海岸に来い。今日は稀に見る絶好の日和だから、われわれはみんな海で遊んでいる」。
北欧らしいといえば、いかにも北欧らしいエピソードではないか。大きなコンペを獲ってしっちゃかめっちゃかになっていて当然のときに、天気がいいからといって全員が職場放棄して遊んでいるなんて。気候風土から「暮らしぶり」が生まれるとしたら、一年を通してなんとなく気候のよい日本で日本人が一年中なんとなく働いているのも頷ける。これは、以前スウェーデンの福祉施設でインターンとして働いた経験のあるお客様から聞いた話なのだが、温厚な同僚たちが唯一声を荒げて言い合いをしていたのが「夏休み」の予定を調整しているときだったという。晴れたら休む、は、北の厳しい自然を生き抜くために培われた「智慧」のひとつなのかもしれない。
もうひとつ、同じ本のなかに彼がデンマーク王立アカデミーで教鞭をとっていたころの学生にまつわるエピソードがあるのだが、これがまたいかにも〝北欧っぽい〟とぼくは思うのだ。
竹山によると、建築家をめざす当時のデンマークの学生たちは「実在しないものに夢の理想を追い求める創造の姿勢」からは一様に無縁だったという。彼らにとって「創造力」とは、「いままでに見たことのない空間や形態」を発想する力を指してはおらず、「あくまで現実に存在していて実際に経験できる対象から出発し、それをよりよい次元にレベルを高めることに必要な力」を指して言われるべきものなのだ。彼らに言わせれば、たとえそれがオリジナルな発想を持ったものであったとしても、「実際に使用する社会の人びとの支持を得られないなら」ダメということになる。
個性で目立つよりも、現実に寄り添いつつ、そこに新しい価値なり意味なりを付与することをもって「クール」とするような考え方は、おそらく長い時間をかけて北欧の人びとに広く共有されてきた考えなのだろう。そしてこれは、なぜ北欧デザインはシンプルなのか? という問いへのひとつの答えになっていると思うのである。
シャーリイ・ジャクスンが描くうすら寒い世界
2016.12.12|book

シャーリイ・ジャクスンのビターな短編集『くじ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)を読む。断っておくとこれ、いわゆるミステリじゃないです。ブラックユーモア+サイコ・スリラー+奇妙な味がブレンドされた物語が22編。
表題作となっている『くじ』は、雑誌「ニューヨーカー」に掲載されるやいなや大反響を巻き起こしたとされる作品。
舞台は、どこかアメリカの田舎町。住民は子どもも含め300人ほどで、どうやら彼らの多くはトウモロコシを栽培する農家である。この町の広場では、開拓以来、年1回住人全員参加の「くじ引き大会」が行われてきた。かつては他の町でも行われていたが、最近ではこの「行事」が守られている町もめっきり少なくなった。その日もわいわいと雑談に花を咲かせながら、またいそいそと、町人たちはくじを引くために広場に集まってくる。田舎町のほのぼのとした祭りの情景は、しかし、ハッチンスン夫人が「あたり」を引いたことで一気にカオスへと転じるのだった……。
くじに「あたる」ことがかならずしもラッキーでない(たとえばPTAの面倒くさい役員とか……)という局面は重々承知なはずなのだが、全体にのどかな田舎町の祝祭ムードが溢れているだけに読者が受ける衝撃も大きい。上げておいて落とすがシャーリイ・ジャクスンの「極意」とみた。いったいどんな顔をしてこれを書いていたのだろう、このひとは。
連作ではないのだが、登場人物がみな似通った名前なのも興味深い。もちろん、似通ってはいるが同じ人物ではない。まったくの別人。つまり、落語に登場する「熊さん、八っつぁん」同様、実質的には「匿名」なのであって、彼らの物語はまた、読んでいる私たちの物語でもあるということだ。それゆえ、そこに存在する悪意もまた、だれの心の中にも、もしかしたらあなた自身の心の中にも潜んでいるかもしれない悪意なのであり、つまるところ、シャーリイ.ジャクスンの描く世界のうすら寒さとはまさにその点につきるのではないかと思う。
空からお届け
2017.5.28|book
昭和5(1930)年8月、世界一周中のドイツの巨大飛行船「ツェッペリン伯号」が日本に飛来した。
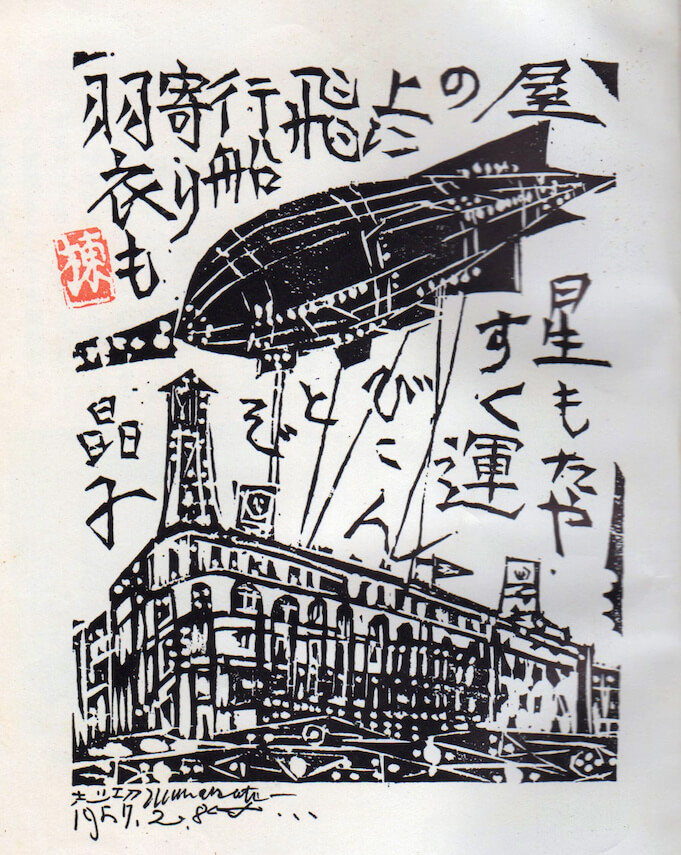
高島屋の宣伝部長、後に総支配人として辣腕をふるった川勝堅一は、大阪高島屋の屋上にこの「ツッペリン伯号」を繋留した合成写真をつくり、親交の深かった与謝野晶子のもとを訪ねる。「デパートも、地上でお買物を配達するばかりでなく、今に、空から運ぶ時代も来ると考えますから、この写真に、何かお歌を一つお願いします」。
すると晶子は、「それは面白い思いつきでしたね」と次のような歌をすぐに詠んでみせたという。
──屋の上に 飛行船寄り 羽ごろもも 星もたやすく 運びこんとぞ
いまドローンを利用した配送の実験が行われている最中だが、80年以上前のデパートマンはすでにそんな未来の到来を予測していたわけである。
── 川勝堅一『日本橋の奇蹟』(実業之日本社)より 画像は、棟方志功の木版に晶子の歌を添えたもの。
04.07.2018
2018.7.4|book
ここ1週間ばかり、東京は看板が飛ばされやしないか心配になるような強い風が吹き荒れている。注意報が発令されるような強風が、こんな何日間もやまないなんて珍しいのではないだろうか。なんとなく気になるので書いておく。

ところで、きょうは無性においしいコーヒーが飲みたい気分だった。じゃあ自分で淹れれば? という声が聞こえてきそうだが、ちがうのだ。誰かが、自分のために、目の前で淹れてくれたコーヒーが飲みたいのだ。ワイン、紅茶、抹茶、バナナジュース、焼酎…… ひとくちに飲み物といってもいろいろだが、コーヒー、とりわけハンドドリップのコーヒーは他のどれよりも「手料理」に近いところがあるのではないか。おなじ豆をおなじ道具で淹れても、淹れるひとのちょっとした手クセのようなものが影響するのか不思議とみなちがう味になる。そしてそこが愉しい。そこが嬉しい。だから、どうせもてなしてもらうのならぼくはコーヒーでもてなされたい。
獅子文六の娯楽小説『コーヒーと恋愛(可否道)』には、目分量で、傍目にはざっくりとしたやり方ながらどんな口うるさいひとも唸らせるうまいコーヒーを淹れる女主人公が登場する。ひとつ言えるのは、「そんなアホな」と頭ごなしに言うひとはたぶん一生ほんとうにおいしいコーヒーにはありつけないだろうということ。
『三人噺 志ん生・馬生・志ん朝』という本を読んだ。ミルブックスのF社長(まあ、わざわざ隠すまでもなく藤原さんなんですけど)が、おもしろかったからと持ってきてくださったなかの一冊。著者の美濃部美津子は、昭和の名人古今亭志ん生の長女にして、先代の金原亭馬生、古今亭志ん朝の実の姉にあたるひと。亡くなる間際、志ん生が身の回りの世話をしていた著者に対して、もし「志ん生」の名前を継がせるなら兄の馬生ではなく志ん朝にと言い残したといったエピソードなど、近親者ならではの貴重なエピソードにも豊富であっという間に読んでしまった。ちなみに、このエピソードについていえばなにも馬生が志ん朝よりも劣るといった意味ではなく、カラッと明るく華のある志ん朝の芸風のほうがより「志ん生」の名前にはふさわしいからという理由である。ぼくは、噺からやさしさがこぼれるような馬生の「笠碁」が大好きなのだが、幼い頃から病弱でおとなしく、やさしい子供だったというエピソードを知り、なるほどなあと納得した。
それにしても、「なめくじ長屋」と呼ばれたちいさな家に志ん生と馬生、志ん朝の3人がいたということのスゴさをなんとか伝えたくていろいろ考えてはみたのだが、結果、ひとつのどんぶりにトンカツと天ぷらとうなぎの蒲焼がのっているような状態という胸焼けするような比喩しか思いつかなかったのでやめる。