あんですMATOBAの「シベリヤ」
2018.6.4|sweets
◎ 仮説「シベリアはどこからきたか?」
人間は挟みたがる動物である。ーー美味しいものを美味しいものでサンドしたら、ものすごく美味しいものができるんじゃないか、そう考えるのはごく自然なことである。生まれながらに持ち合わせた人類の本能である。子供のころ、好みの厚さにスライスしたチーズをうす焼きせんべいで挟んで食べることにハマり、すんでのところで肥満児になりかけたぼくが言うのだから間違いない。

水ようかんをカステラでサンドした「シベリア」というお菓子がある。最近では、ジブリ映画『風立ちぬ』でその存在を知ったというひともけっこういるようだ。この「シベリア」が登場したのは明治時代の終わり、あるいは大正時代の始めごろと言われている。ただし、どこの誰が最初につくったのか? その点についてははっきりとしない。そりゃそうだ。思うに、「シベリア」は日本のそこかしこで、おそらくほぼ同時多発的に生まれたにちがいないのだから。
「シベリア」が誕生した当時、「カステラ」と「ようかん」といえば数あるお菓子の中でもとりわけ人気のある、いわば〝ツートップ〟といった存在であったろう。そんなあこがれのお菓子ふたつを前に、「挟みたい……」という欲求にとらわれた人間はけっして一人や二人ではなかったはずだ。そこかしこにいた。少なく見積もっても全国の津々浦々に数十人、あるいは百人くらいはいたかもしれない。そして、ついにその野望を叶えた者、つまり「ようかんをカステラで挟んで食べた者」は、当然、周囲の人間をつかまえてその〝武勇伝〟を自慢せずにはいられなかった。「あのさ、ようかんをカステラで挟んで食べてみたらめっちゃ美味しかったんだよね」。
もちろん、それを聞いた者はさっそく自分もためしてみたにちがいない。まだやっていない誰かをつかまえて自慢するために、である。伝言ゲームじゃないが、なかにはカステラをようかんで挟んでしまうおっちょこちょいもいたかもしれない。そして、耳ざとい商売人たちはさっそく商品化して自分の店の棚に並べた。それが評判となり、広く世間に「シベリア」が認知されるに至ったのである。--もちろん、証拠はない。
◎ あんこ屋さんのシベリア
浅草の観音裏の交差点、かつて吉原に遊びにゆく男たちが馬の背に揺られて通った「馬道」にもほど近い一角に「あんですMATOBA」なるパン屋はたたずんでいる。一見したところ、こう言ってはなんだが、とりたててこれといった特徴もないごくふつうの街場のパン屋である。ところが、じつはこの「あんですMATOBA」、そのルーツを大正13(1924)年にまでさかのぼることのできる「あんこ屋さん」のアンテナショップなのである。
母体は業務用の餡を製造販売している「的場製餡所」という会社で、関東大震災の翌年に日本橋の箱崎町にて創業、終戦後になってここ浅草に移転したと会社案内には書かれている。製餡所のパン屋さんだけに、主力商品はもちろんあんぱんである。つぶあん、こしあんにはじまり、かぼちゃ、ずんだ、栗、焼き芋と20種類ものあんぱんが並ぶ店頭は圧巻だ。なかには、うぐいすあんを中に入れてしまった「メロンあんぱん」などという〝武闘派〟まで存在する。そんななか、ひっそり冷蔵ショーケースに鎮座ましましているのが「シベリヤ」※ である。
ところで、ときどき勘違いをしているひとがいるけれど、カステラのあいだに挟まっているのは「あんこ」でも「ようかん」でもなく「水ようかん」であり、またそこが重要なポイントでもある。カステラという甘いケーキで挟んでいながらもベタベタしすぎず、また重くなりすぎないのは、なによりそれが「水ようかん」だからと言っていい。おそらくこのかたちに落ち着くまでにはさまざまなドラマがあったのではないか。

さて、その「あんですMATOBA」の「シベリヤ」だが、玉子の味のしっかりするきめ細かいカステラとさっぱりめの水ようかんのバランスがすばらしい。アガーでなく、寒天で固めた水ようかんだったらこうはいかなかったろう。それぞれが主張しすぎると、「あ、いまオレの口の中にはようかんさんとカステラさんがいるな」と感じてしまいがちだが、この「シベリヤ」ではそういうことはない。ベストフレンド。あんこ屋さんのつくった「シベリア」は、あんこを知り尽くしたプロなればこその精妙なバランスを感じさせるつくりなのだった。 ※「シベリア」については、「シベリア」と「シベリヤ」というふたつの表記が混在している。「シベリア」という表記のほうが一般的なようだが、レトロスイーツ的には「シベリヤ」という表記も捨てがたい。たとえば『甘話休題』の古川緑波は「シベリヤ」と書いている。今回の「あんですMATOBA」の場合、商品名は「シベリヤ」である。そこで、具体的に商品に関する記述の部分では「シベリヤ」、一般的にこの菓子全体にかんする記述については「シベリア」と使い分けた。
◎ DATA
店舗名/あんですMATOBA
創業年/大正13(1924)年「箱崎製餡所」として創業
商品名/シベリヤ
発売年/不明
価 格/220円(税込)
購 入/ホームベーカリーあんですMATOBA
住 所/東京都台東区浅草3−3−2
WEB/http://www.matoba-seian.co.jp/andesu
※2018年6月1日現在
マツヤのロシアチョコレート
2018.6.6|sweets
◎ 「モロゾフさんのチョコレート」が食べたい

きっかけは一冊の本だった。革命の混乱の中、祖国ロシアを脱出し、たどりついた神戸で亡命者としてチョコレートをつくり、広めたモロゾフ父子の波乱に満ちた生涯を描いた川又一英『大正15年の聖バレンタイン:日本でチョコレートをつくったV.F.モロゾフ物語』(PHP研究所)である。
かいつまんで紹介すると、モロゾフ父子は、現存する菓子メーカー「モロゾフ」の創業者である。大正15(1926)年に神戸で産声をあげた「モロゾフ菓子店」は、それまでの国産チョコレートの常識を覆す手の込んだ高級チョコレート菓子により在留外国人や富裕層の邦人らを主な客層として人気を得たが、昭和11(1936)年、契約上のトラブルから父子は会社を離れ、それと同時にみずからの名前であるにもかかわらず「モロゾフ」という屋号を掲げることを禁じられてしまう。やむなく、「バレンタイン菓子店」、戦後は「コスモポリタン菓子店」という屋号で店を切り盛りし、平成18(2006)年に廃業するまで80年間にわたって日本の地でチョコレートをつくりつづけた。
つまり、モロゾフ父子直系のチョコレートは「モロゾフ」から「バレンタイン菓子店」へ、さらに戦後になって「コスモポリタン製菓」へと受け継がれ、その廃業とともに途絶えたことになる。しかし、食べられないとなるとよりいっそう食べたくなるのが人情というもの。なんとか食べることはできないか、どこかにこれらの店で修行し、その後独立開業したひとはいないものか……。そんなことをかんがえて調べてみたところ、新潟にある「マツヤ」という菓子店の創業者が戦前、モロゾフ父子のもとで修行時代を過ごしたひとであることがわかった。しかも、代替わりした現在も「ロシアチョコレート」を店の看板商品として掲げていると知り、「モロゾフさんのチョコレート!」とさっそく買いに走ったのだった。
◎ ロシアにはない!? ロシアチョコレートの謎

マツヤの公式サイトによれば、先代の松村喜代司は、戦前ロシア人の職人の下で「ロシアチョコレート」の製造技術を身につけたということになっている。
先代、松村喜代司は昭和2~3年頃に当時の「モロゾフ」(現:コスモポリタン)で修行し、チョコレートやキャンディー作りの技術を学びました。修行を終えた後は、東京のチョコ・キャンディメーカー「タガミ」にてチーフを努める等し、その後独立。東京目黒でチョコレートショップ「ローヤルチョコ」を開きました。
昭和2、3年ごろとすると、「モロゾフ菓子店(コンフェクショナリー・F・モロゾフ)」がそろそろ軌道にのり、製造力を高める目的で日本人の職人を起用し始めた当初ということになる。このころはまだ息子のバレンタインも修行中の身であったことから、松村がそこで教えを受けたのはおそらくハルビンから連れてきた職人だったろう。彼らもまた命がけで祖国を離れ、行き場を失った白系ロシア人たちであった。
さて、ではモロゾフ父子がつくりマツヤにその伝統が引き継がれている「ロシアチョコレート」とは、はたしてどのようなものなのか。
一応、ロシアチョコレートとはポマードカと呼ばれるクリームやドライフルーツ、ゼリーなどをチョコレートでくるんだお菓子ということになるが、ざっと調べてみたかぎり、おそらく「これがロシアチョコレートだ」といった明確な特徴や定義は存在しないのではないか。さらに言えば、「天津丼」が中国に存在しないのと同様、「ロシアチョコレート」なるお菓子も現在のロシアには存在しない。それは帝政ロシア時代、貴族や裕福な商人に愛された高級チョコレート菓子のことを指し、モロゾフ父子が、革命を逃れて外国に渡った白系ロシアの職人の手を通して「ロシアチョコレート」として日本に広め、定着させたものだからである。
◎ ロマンを味わうチョコレート
いよいよ「マツヤ」のロシアチョコレートを食べてみる。

マツヤのチョコレートは、マトリョーシカをかたどったこの化粧箱も人気のひとつだ。じっさい、プレゼントにしたら喜ばれそう。箱を開けると、中には色とりどりの包装紙にくるまれたチョコレート菓子が1個ずつ12種類。イラストもレトロでかわいいし、なによりデザイン的にはキリル文字がいい味わいを醸し出している。
ロシアチョコレートは、まず「センター」と呼ばれる中身をつくり、それをチョコレートでコーティングしてつくられる。最初にあげた『大正15年の聖バレンタイン』には、職人たちが厨房でチョコレートをつくる様子が描かれているが、その光景とマツヤの公式サイトで公開されている「作業工程」とをくらべてみるとほぼ変わっていないことがわかる。手作業による戦前のチョコレートづくりが、驚くことにほぼそのまま現在にまで引き継がれているのだ。ひとつひとつ、愛おしみつつ口に運びたくなる。
たとえば「チョコクリーム」は、まずベースとなる練乳と砂糖を煮詰めてつくったポマードカにビターチョコを加え、大理石のボードの上に流して冷やし固める。次にそれを一口大に切り分け、チョコレートでコーティングしたら出来上がり。濃厚でまろやかなリッチな味わい。バレンタイン ・F・モロゾフがつくったこのチョコレート菓子に、父親のフョードルは「ムーンライト」という美しい名前をつけて店に並べた(『大正15年の聖バレンタイン』)。

12種類の味は同封のリーフレットにそれぞれ説明されてはいるが、ここはひとつ包装紙の好みでチョイスして、どんな味と出会えるかという楽しみ方をおすすめしたい。栄華をきわめた帝政ロシア時代のチョコレート菓子が、はるか遠い極東の島国に漂着し、根付き、いまもひっそりと可憐な花を咲かせている。マツヤのロシアチョコレートの隠し味は、ロマンである。
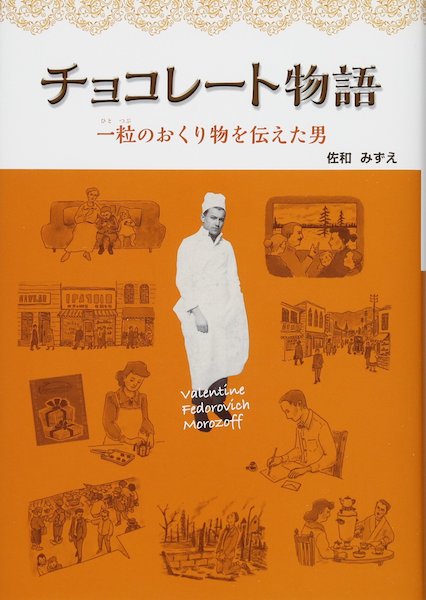
モロゾフ父子の生涯について興味を持たれた方には、いま入手しやすい本としてこちらがおすすめです。
『チョコレート物語 一粒のおくり物を伝えた男』佐和 みずえ
◎ DATA
店舗名/ロシアチョコレートの店 マツヤ
創業年/昭和5(1930)年 「ローヤルチョコ」として東京・目黒にて創業
商品名/ロシアチョコレート
発売年/昭和5(1930 )年?
価 格/1,280円(税抜き) 12個入りマトリョーシカ化粧箱
購 入/そごう横浜店催事にて購入 オンラインでも購入可
住 所/新潟県新潟市中央区幸西1丁目2-6
WEB/http://www.choco-matsuya.com
※2018年6月5日現在
レトロスイーツのある風景 #2
2018.6.8|sweets
佐藤ちひろさんの刺繍によるショートケーキ。

佐藤さんは、デンマークで出会った「エスカ」と呼ばれる刺繍入りの小箱を日本に紹介している作家さんです。写真は、佐藤さんがほどこした刺繍をポストカードにしたもの。
ところで、日本ではおなじみの「ショートケーキ」ですが、じつは外国には存在しないって知っていましたか? まさに〝日本生まれの洋菓子〟なのです。起源については諸説ありますが、一般に広く知られるようになったのは昭和30年代以降ではないかといわれています。フレッシュなイチゴに生クリームをたっぷり使うショートケーキにとっては、鮮度こそがなにより肝心。ショートケーキが普及するには、家庭用冷蔵庫の普及が必須だったというわけです。
クリームの純白とイチゴの赤、こうして刺繍にしてもよく映えます。
210文字
2018.6.8|facebook
ツイッターでつぶやいたものの140文字ではうまく伝えきれなかった文章を、すこしだけ多い210文字にしてあらためて伝え直します。
────
ベルリンの壁が崩壊して国家に「寿命」があることを知り、改ざんや隠蔽をきっかけに傾いてゆくさまを見て大企業にもまた「寿命」があることを知った。
お店にとってのお客様もそうで、諸々の事情によってよく来てくださっていたお客様もある日パタリと姿を見せなくなる。仕方ない。これも「寿命」みたなものだ。
そして、だからこそ、長い間たとえ時々でも継続的に来てくださるお客様は文字どおり「有り難い」存在であり、感謝の気持ちしかない。
横浜・喜久家のラムボール
2018.6.12|sweets
◎ 「港」のスイーツ

港町には「港のおんな」がいるように、また「港の菓子」がある。横浜の元町に店をかまえる喜久家の「ラムボール」は、まさにそんな「港の菓子」のひとつ。
ところで、港にはふたつの「顔」がある。外国からの「入口」という顔と、外国への「出口」という顔である。日本にやってくる「洋菓子」も、ほぼこのふたつの「顔」を経由している。カステラや金平糖、ボーロといったお菓子は、よく知られるようにポルトガルから長崎の出島という「入口」をとおして日本に到来した。神戸や横浜といった居留地に暮らす外国人から日本の職人に伝わったレシピもすくなくない。
そのいっぽうで、外国へと渡った日本の料理人が寄港地でたまたま口にし、それがきっかけとなって日本でもつくられるようになったレシピもある。前者が受け身であるのに対して、日本人がじっさいに本場のものを口にし、日本人の口に合うかをよく吟味したうえで日本の食材や風土環境、当時の設備に合わせてアレンジしているという点でこちらはより積極的といえる。
こうした日本から出て未知の甘味と遭遇した人びとの多くは、当時日本郵船の外国航路でパンやデザート作りに携わっていた職人たちだった。吉田菊次郎『西洋菓子彷徨始末〜洋菓子の日本史』によれば、日本で洋菓子づくりに携わっている人びとのルーツをさかのぼると大きくふたつの流れに分類することができ、そのひとつが「日本郵船」出身者の流れだという。そしてじっさい、今回とりあげる「ラムボール」をつくっている喜久家の創業者・石橋豊吉もまたかつては「日本郵船」の外国航路でパンや菓子を焼くベーカー部門ではたらく一人であった。
大正13(1924)年の創業当初からつくられていたという「ラムボール」の発祥(※)についてははっきりとしたことはわからない。居留地だった横浜では、こういうお菓子をつくって欲しいという外国人からのリクエストに応えてつくられるようになったものも少なくないという。この「ラムボール」が、あるいはそういうお菓子のひとつだった可能性はじゅうぶんある。ただ、欧米ではクリスマスのお菓子としてポピュラーな「ラムボール」だけに、ある年のクリスマスにどこか停泊した港町でこれを口にした石橋氏がそのレシピを持ち帰り、後にじぶんの店でつくり売るようになったとかんがえるとなんとなくロマンティックではないだろうか。
※横浜ではホテルニューグランドもまたラムボールをつくっているが、こちらは終戦直後、GHQに接収されていた時代に持ち込まれたレシピが起源とされている。参考記事:
元町の老舗洋菓子店「喜久家」のオリジナルスイーツ「ラムボール」誕生秘話を徹底レポート! はまれぽ.com
◎ ラム好きのラム好きによるラム好きのための

喜久家の「ラムボール」は、1個がゴルフボールくらいの大きさのチョコレート菓子である。パティスリーのケースに並んだ独創的で華やかなケーキに慣れてしまった目には、ずいぶんと大人しく映るのはいたしかたないところ。じつは、この「ラムボール」がボール状の、正真正銘の「ラムボール」になったのは昭和10年くらいのことで、それまでは大きく焼いたものを四角く切り分けて売っていたのだとか。四角だった時代にはどういう商品名で売られていたのだろう……。
さて、今回は、その「ラムボール」を2個購入。バラの花が描かれた専用の化粧箱がまたなんとも昭和な雰囲気で、レトロスイーツ愛好家にはうれしい。さっそくふたを開けると、とたんにラム酒の芳醇な香りがふわっと立ちのぼり鼻腔をくすぐる。

「ラムボール」は焼成せず、ケーキの切れ端をラムレーズンなどと一緒に丸め、しばらく寝かせた後にチョコレートでコーティングしてつくられるため、生地はとてもしっとりしている。そして押し寄せるラム酒の香り……。とはいえ、けっしてしつこいわけではないあたり工夫を感じさせる。ただ、子供やアルコールが苦手な人はご用心(注意書きあり)。
ところで、今回は、ひとつを賞味期限(1週間)ギリギリまで寝かせた上で食べてみた。はたしてどんな変化があるか? 生地がよりしっとりとしたのはもちろん、全体に味の調和がとれたようだ。チョコレートにしっかりと覆われているせいか、ラム酒の香りが飛んでしまうということもなかった。まさに、大人の横浜みやげにうってつけである。※

ひとことで言えば、大人の味。好き嫌いはあるかもしれない。すくなくとも、「下戸」と言っていいくらいなのに子供のころからラム酒の香りに目がなくうっとりしてしまうぼくにとっては、わざわざこれを買うためだけのために横浜まで行ってしまいたくなる、そんなお気に入りのレトロスイーツ。横浜に遊びにいくときにはぜひチェックしてもらいたい。
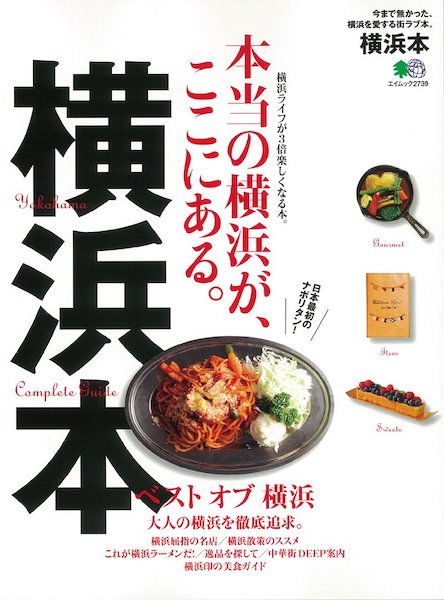
※ハマっ子目線の横浜ガイド本で、喜久家の「ラムボール」が「ハマっ子が選ぶ使える手土産第1位!!」に!
横浜本 今まで無かった、横浜を愛する街ラブ本。 (エイムック)
◎ DATA
店舗名/喜久家
創業年/大正13(1924)年
商品名/ラムボール
発売年/不明(創業当初から販売との説もあり)
価 格/2個480円(税抜き)
購 入/横浜・元町本店
ほかに、横浜駅相鉄ジョイナス内にも売店あり
WEB/http://kiku-ya.jp/
※2018年6月5日現在
7RULES
2018.6.20|facebook
「校閲者」 牟田都子(むた・さとこ)さんの日常に密着したドキュメンタリー番組『7RULES(セブンルール)』が、昨夜フジテレビ系列にてオンエアされました。
じつは、moiが吉祥寺に移転して以来ずっと、都子さんにはあるときは仕事の、あるときは息抜きの場所としてコーヒーを飲んでいただいたり、またポストカードをお求めいただいたりと可愛がっていただいています。番組の中でもそんな様子がちらっと登場します。
お客様としての都子さんは、ひとことで言えば「気配りのひと」。周囲のちょっとした空気の変化にも反応し、つねに先回りして気遣ってくださいます。番組中、コメンテーターのYOUさんがはからずも「神!」とおっしゃってましたが、ぼくも同感です。テレビを観ながら大きく頷いてしまいました。校閲のしごとをされているからあのような気配りが自然にできるのか、それともそのような性格の持ち主だからこそ校閲のしごとに向いているのか…… たぶん、その両方なのでしょうね。「天職」というのはこういうことなのだろうなあと、番組を観てあらためて感じました。
なお、この『セブンルール』1週間限定で関西テレビの動画視聴サイト『カンテレドーガ』にて無料視聴できます。とても興味深い内容だったので、ぜひ多くのみなさんにご覧いただきたくここでご紹介させていただきました。
http://ktv-smart.jp/pc/movie/index.php?key=53061
26.6.2018
2018.6.27|art & design

府中市美術館で「長谷川利行展 七色の東京」。
府中の美術館は近隣の小学校の団体鑑賞が多いが、あらかじめ予定をウェブサイトで確認しておけばかち合うことはない。今回は、昼休みの時間帯を狙ってゆく。
利行は、猛烈なスピードで三原色を散りばめて一枚の絵を仕上げたという。実際、そんな荒々しさにまず目を奪われるが、その一方で、そこになんとも言いようのない繊細な詩情が流れていることに驚かされる。利行は、若い頃まず短歌の世界で頭角をあらわし、後になって詩作にも興じた「言葉のひと」である。それだけに、直観的に置かれたように見える色ひとつひとつにも、じつは利行なりのきっぱりとした論理というか文法があるのかもしれない。「フォービスム」というひとことで括るには、あまりにも多才なひと。
会場の最後に飾られた一枚は、死の前年に描かれた「荒川風景」という作品。その「透明さ」はたじろくほどである。繊細な心を隠す鎧のような厚塗りはもはやなく、利行の存在はその風景の中にすっかり溶けてしまっていた。
帰りは、そんなことをつらつら考えながら20分弱の駅までの道のりを歩いたのだが、さすがに連日の仕事疲れでボロ雑巾のようになっているからだに30度を超える炎天下はこたえた。不本意ながら、駅のチェーン店にかけこみ薄いアイスコーヒーで生き返る。
乗り換えの新宿駅のコンコースで古本市が開かれているのを見つけ、ちらっと覗くつもりが気がつけば1時間半の滞在。
27.06.2018
2018.6.28|column
日々ぼんやりカウンターに立っていると、知らず知らずのうちに女性の洋服のトレンドにくわしくなっていたりして驚く。
たとえば、去年の夏は爽やかなレモンイエローやブラッドオレンジのような赤色のロングスカートが流行っていた。それに対して、今年の夏もおなじような色をしたスカート姿をよくみかけるが、どうやら去年の流行よりも少しばかり渋目の色調になっているようだ。強いて言えば、からし色とレンガに近い赤色だろうか。ざっくり言えば黄色と赤色でおなじなのだが、今年のそれと去年のそれとではわずかに違う。それは、さしてファッションに関心のない人間だったら「ま、おなじ『赤』だからいいっしょ!」とか「あれ? 去年もおなじ色の買ってなかった?」とか言っちゃうくらいの違い、である。
逆に言えば、流行に敏感な人ほどそのわずかな違いに神経質になり、「去年の黄色」や「去年の赤」を身につけて街に出ることをためらってしまうだろう。「微細な差異」と言ったのは、たしかボードリヤールだったろうか。なるほどファッションとは、〝着る自意識〟なのである。あ! いますごくいいこと言ったって感じなんだけど、これってすでに誰か言ってたっけ?!
28.06.2018
2018.6.29|column
渋谷駅の、井の頭線の改札と山手線、銀座線の改札をむすぶ連絡通路はちょうどスクランブル交差点を一望できるビューポイントらしく、いつ通っても外国からの観光客でにぎわっている。あるいは、東京のガイドブックに紹介されていたりするのかもしれない。
ついこのあいだも、通勤ラッシュの人波を横切ってさまざまな国籍の人たちが、だがみな一様にうれしそうな表情で窓に駆け寄り、ガラス越しに交差点の様子を写真や動画に撮ったり、また自撮りしている場面に遭遇した。そしてそれは、まるで防波堤の切れ目からちらりと青い海が見えたとたん我慢できず走り出す夏休みの子どものようでなんともいえず微笑ましい光景だった。
とはいえ、さんざん見慣れたものにとっては、正直なところ「そんなに交差点が見たいか?」という気がしなくもない。だってさ、交差点だよ。しかしそうかんがえると、思わずひとをして駆け寄りたい気分にさせてしまう渋谷のスクランブル交差点というのは相当すごい。おそらく世界広しと言えども、そんな交差点はここくらいのものだろう。魔性の女ならぬ魔性の交差点だ。好きすぎて「自宅の庭にスクランブル交差点を作ってしまったアメリカの大金持ち」とか出現しても、とりたてて不思議ではないくらいだ。
これはもっと積極的にビジネスに活用したほうがいいんじゃないか? と、渋谷にくるたびにかんがえる。たとえば、スクランブル交差点をイメージした携帯ストラップだとか、ハチ公広場の屋台で売る「名代・スクランブルエッグ(姉妹品「池袋駅東口五差路」もよろしく)」だとか、VRで家にいながらにしてスクランブル交差点を渡っている気分になれる映像ソフトとか……。しかし、そんな妄想に浸りながら歩くものだから、いつも渡り切るまでに最低5人くらいとぶつかりそうになる。悪いことは言わない、渋谷のスクランブル交差点を渡るときは、無心で進め。
29.06.2018
2018.6.29|food & drink
うっかり切り落とした眉毛、さっき鏡で確認したところだいぶ生えてきた。これで、もう毎朝2Bのエンピツで描く必要もない。
気象庁が、例年より22日(!)早い梅雨明けを発表。すでにここ数日、連日真夏日&熱帯夜で街にはイライラしているひとも多そうだ。朝、バスの中で運転手に食ってかかるいま流行りの「切れる老人」に遭遇する。ところが、相手がそれほど流行ってはいないが「切れる運転手」だったため車内はちょっとした修羅場に。もし手元に麻酔銃があったら、たぶん両方とも仕留めていたと思う。みんな仲良くね。
先日お店に遊びにきてくれた知り合いから聞いて衝撃を受けた話。北欧、とくにスウェーデンやフィンランドではザリガニを食べて夏の到来を祝うならわしがあるが、以前スウェーデンでザリガニを食べたらなんと「中国産」だったらしい。値段や、需要と供給のバランスの関係上、最近では「輸入物」が増えているとのことで、日本の「土用の丑の日」とおなじ現象が遠い北の国でも起こっているのだ。ちなみに、その知り合いのおすすめは「埼玉産のザリガニ」。いや、冗談じゃなく本当に。なんでも埼玉県に食用のザリガニを養殖している人がいるのだとか。
夕刻、いつもサンドイッチ用に使っているパンを購入しているパン屋さんのスタッフの方々がそろってご来店。うれしい反面、いつも感じることだが客と店員の立場が逆転するとどういうわけか変に照れくさいものである。しかし、これまで一度もみずから名乗ったことがないにもかかわらず、なぜぼくが「moi」の人間とわかったのだろう? と思ったら、以前来てくださった別のスタッフの方から聞いたと知り納得。でも、考えてみたらそのスタッフさんにも名乗った憶えないんだよなあ……。
30.06.2018
2018.6.30|column
この暑さでは無理からぬこととはいえ、土曜日とは思えないあんまりな売り上げに泣いている。こういうときは、あらゆる物事をついネガティブな方向で考えてしまいがちだ。朝ごはんに納豆を食べたのがよくなかったのか(ちゃんと長ネギは抜いた)とか、店主が高橋一生に1ミリも似ていないのがいけないのか、とか…… 答えは出ないし、あるいはその全部じゃないかという気にもなる。なので、みんな来て。
ほぼ毎日、夕方のある時間帯に犬を散歩させているひとりのおじさんを見かける。しかし、よくよく考えてみたら、そのおじさんはいつも犬を肩に乗せて歩いているので、厳密にいえば「犬を散歩させている」のではなく「犬を担いで散歩している」が正解だということにさっき気づいた。当然、犬にしたってそれを「散歩」とは捉えていないだろう。「さて、今日もそろそろおっさんに運ばれるとするか……」。
肩越しにのぞくつぶらな瞳が、どこか腑に落ちないといった風に見えるのはたぶんそのせいだと思う。
大阪から「オーボエ吹き」の小林千晃さんがひさしぶりのご来店。東京で何かあると、忙しい合間を縫っていつも顔を出してくださるありがたいお客様のひとり。今回は、「隣町珈琲(トナリマチカフェ)」の釈徹宗さんのトークイベントで演奏するのが目的とのこと。ちあきさんといえば、めっちゃ好きなエピソードがあって、それは初詣に出かけたお寺にほら貝を吹いている山伏がいたので試しに吹かせてもらったところ、見事一発できれいなハイトーンを決めその場で山伏にスカウトされたという話。いつか、華やかなドレスに身を包んだちあきさんが豪快にほら貝を吹く姿を見てみたい。

