北村薫『夜の蝉』
2012.6.5|review

「私と円紫さん」シリーズの第2作とのこと。初夏から梅雨、そして盛夏のころが舞台となる。
前作とのいちばん大きな違いはといえば、物語の世界の規模が主人公を「軸」にぐっと狭まり、そのかわりより深くなったことだろうか。前作ではホームズとワトソンのようであった「円紫さん」と「私」の関係も、本作では主役はあくまでも「私」、「円紫さん」は謎解きの指南役といった役どころで一歩引いたかたちに収まっているように感じられる。その点、読後の印象も、ミステリよりは人情噺的な色合いを強く受ける。
読むことで感じるある種の生々しさは、前作よりも一段と「私」の内面に触れていることから生じるたぐいのものだろう。当然、その余韻もまた変わる。それは蝉しぐれのように、いつまでもシーンと頭の中に残響する。
北村薫『秋の花』
2012.6.10|review
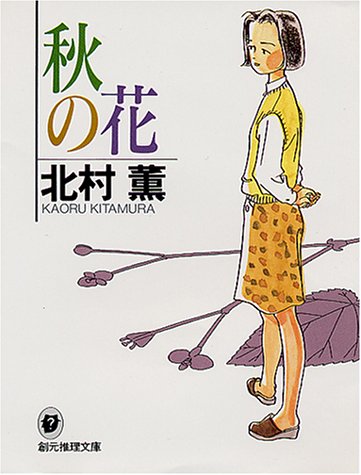
トリックは読み解けてもそこにカタルシスはない。むしろ残るのは、息苦しさ…。
幼なじみのふたりは、なぜこのような「事件」に巻き込まれなければならなかったのか? ふたりの出会い、なにげない会話や思い出…… そうしたエピソードがていねいに描かれ、それによって読者はそれが起こるべくして起こったこと、「偶然」のひとことでは片付けることのできない出来事だったことを思い知らされる。それはまた、主人公である「私」にも、そして読者にも、いつ起こっても不思議ではないということでもある。その厳然たる事実が、読むものを不安にし息苦しくさせるのだろう。
「私と円紫さん」シリーズ第3弾であるこの『秋の花』は、いわゆる「事件らしい事件」が起こる点、そして長編であるという点で明らかに前2作とはちがっている。物語の「軸」はますます「私」の日常へとシフトし、終盤近くなって登場する「円紫さん」もトリックを解明しはするが解決はしない。とはいえ、推理小説の体裁をとりながら、人間の感情の深い部分に触れようという著者の意志は第3作であるここでも一貫している。
北村薫『六の宮の姫君』
2012.6.13|review

へぇ、こういう「ミステリ」もアリなのか…… と驚き、戸惑いつつも一気に読み終えた。
いかにして芥川龍之介は短編「六の宮の姫君」を書くに至ったか? が、この「円紫さんと私」シリーズ第4弾となるこの作品をなす「謎」である。とはいえ、その底に流れるものは(よりミステリらしい風貌をした)前作『秋の花』から変わっていない。それは「操られるように巡り会い別れる」人と人との「繋がりの不思議さ」である。
コテコテの文学少女(死語? いま風に言えば「本ガール」?笑)である「私」が、親友の「正ちゃん」やバイト先の上司「天城さん」、文壇の長老「田崎先生」、そしておなじみ「春桜亭円紫師匠」らとの問答(キャッチボール)を通して徐々に「謎」の核心に近づいてゆくさまを描いた、静かに高揚してゆく唯一無二の「文壇ミステリ」。
最後に引用される親友にあてた無邪気な手紙の一節が、なんともいえない切なさをもって心に迫る。
北村薫『朝霧』
2012.6.16|review
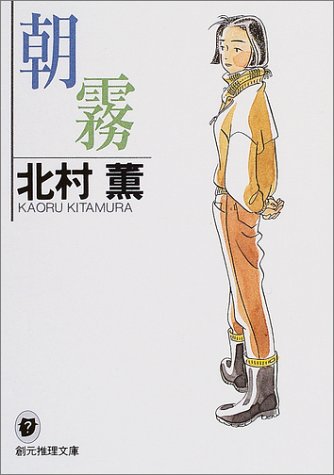
霧の中にあるものの姿は見えないけれど、そこにあるはずのものを思い、心を寄せることはできる。
北村薫の「円紫さんと私」シリーズはこれが第5作にして、いまのところ最終作。最後に収められた『朝霧』は、このシリーズを象徴するかのような珠玉の短編。
ひとを想うことの尊さが、そこにはある。
──
◎ 追記〜「円紫さんと私シリーズ」を読んで
これは、《探偵》と《探偵見習い》の話だと思った。
《探偵》はナゾを解く。でも、それは難解な殺人事件などではなく、ひとが生きてゆくなかでしばしば出会うナゾである。そのナゾは、人と人とが出会い、また別れる中でさまざまな姿をもって出現する。だから、そのナゾを解くには誰かが書いた《知識》に頼るだけでは解くことはできない、ヒントにはなりえたとしても。ひとを想い、心を寄せることではじめて解き得るナゾなのだろう。知識だけでなく、ひとの心の機微に精通した「円紫さん」は、そのことを辛抱づよく《見習い》である「私」に教えてゆく。「私」の成長とともに「円紫さん」の出番が減ってゆくのは、だから当然のことなのだ。ふたりはまさに「師匠」と「弟子」なのだ。
ところでこのシリーズはまだまだ続くのだろうか? たしかに、「朝霧」の最後のセンテンスは「続き」を暗示するようにもみえる。けれども、と同時にそれはまた「リドル・ストーリー」なのだとも思える。「その後」は読者の手にゆだねられた。きっと、そしてそれは少しばかり淋しいことではあるけれど、これで「完結」なのだろう。
小谷野敦『21世紀の落語入門』
2012.6.21|review

うーん、「21世紀の」というよりも「天の邪鬼のための」落語入門?
本文中うなづける箇所も少なからずあるのだけれど、読み終わってなんとなくモヤモヤっとした感じが残るのは、かゆいところにあと一歩のところで手が届かないからだろうか?
たとえば、「私は『現場主義』というのが嫌いなのである」と主張する著者が「寄席に行かずともよい」と言うとき、当然というべきかその「理由」を聞きたいと思ってしまうのだが、それがすっきり明かされないのである。名画は、やはり海外の美術館へ行ってでも「現物」に触れなければという意見に対する著者の回答は、こうである。「飛行機に乗れないこっちとしては、けっと言うほかない」。うーむ。著者がなぜ飛行機に乗れないのかはよくわからないが(タバコが吸えないから?)、「現物」に触れずとも名画を楽しむことができるという説得力十分な「理由」を知りたいところではある。これだとむしろ、もし飛行機に乗れたらホイホイ行っちゃいそうな印象すら受けるのだけど……。
著者は、「落語を聴くには寄席に行くべし」とか「現在活躍している落語家を聴くべし」といった思考が(じっさいはわからないが)最近の落語好きのあいだの「主流」と感じていて、そういう「風潮」に対して「いや、落語にはもっとちがう楽しみ方もあるよ!」というのが言いたくて、勢いでこの本を書いたんじゃないだろうか? そんな気がした。
ちなみにぼくは「録音」、しかも「志ん生」の録音(「品川心中」)から入ってまったく聞き取れず、悔しくて何度も聞き返しているうち7回目か8回目で突然、頬にサーッと品川の海風を感じたような気がして、それをきっかけについ半年ほど前から落語にハマった人間なので、著者が言うように過去の名人の録音でも十分落語はおもしろいと思っているが、行けるものならできるだけ寄席にも足を運びたいと思っている。著者とちがって寄席の雰囲気が好きということもあるが、それ以上に、「テキストが確定していない」落語ならばこそいまこの時代の聴き手として、自分の感覚に合う落語と出会いたいという気持ちが強くあるからである。
入江相政『侍従とパイプ』
2012.6.26|review
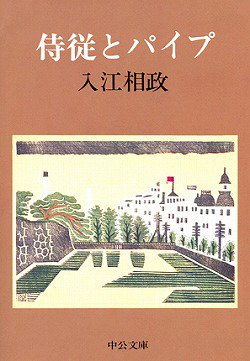
「人間 天皇」の《プロデューサー》とまでは言わないが、侍従・入江相政の目からみた昭和天皇にまるわるエピソードの数々は、終戦後のあるエポックに、かなりの破壊力をもって「現人神」という神秘のヴェールを取り去り、国民に人間味あふれる人物として天皇を印象づけるに十分だったのではないか。たとえば、御巡幸で訪れた四国の片田舎での「事件」は、「現人神」から「人間」への過渡期(昭和25年)に人々が「天皇」という存在をどう受容したかを物語るとても興味深く、かつ可笑しいお話だ(「お上とお風呂」)。
収められた文章ではやはり、「皇室」での知られざるエピソードを綴ったものが断然読んでいて楽しいが、一方、この本の後半、「侍従」という特殊な立場から離れて書いた文章にもこのひとのエッセイストとしての豊かな天分は感じられる。個人的に印象に残ったのは、他人の評価にいともかんたんに押し流されてしまう「日本人のたよりなさ」について書いた「流されて」、戦後、焼け跡にできた防空壕を改装して一家4人、庭でジャガイモやカボチャを育てつつ暮らした際の思い出をつづった「壕舎記」など。特に「壕舎記」からは、敗戦後の日本人の腹をくくった強さ、したたかさのようなものがある種の手応えとともに伝わってくる。
「今から考えればあのころは『なりふり』をかまう必要はないし、教養とかなんとかいうものはとっくにどぶに捨ててしまったし、ただ食うことだけ考えていればいいような、いっそすがすがしい時代だった」
こういう心持ちをバネにしてこそ、ほんとうの「復興」はかなうものなのかもしれない。著者がまだ若かった折、父親が建ててくれた家とともに息子に贈った「この家がお前の競争者だ…」という言葉の重みもすごい。すごすぎる。むかしの市井の人というのは、こんなにもすごいことを言うものなのか。すっかり感心してしまった(「中間搾取」)。

