坂道の多い町
2009.7.1|travel
「坂道が多く 世界のどこよりも不便だ」

とは、アキ・カウリスマキの映画『カラマリ・ユニオン』の冒頭、15人の男たちがこの町からの「脱出」を決意して読み上げる口上の中の一節。そしてじっさい、この町には坂が多い。こんな気持ちよく晴れ上がった日ならともかく、情け容赦なく道が凍てつく冬の季節、このあたりを移動するのはけっしてたやすいことではないだろう。のんきな旅人でもそのくらいはよくわかる。
昼間は大丈夫だと思うけど、まあ、気をつけて

現地の友人からそう言われたこのあたりは、たしかに観光客がカメラなどぶらさげてヘラヘラ歩くには不似合いな一帯である。ポルノショップや怪しげなマッサージ店が軒を連ね、パブの前では飲んだくれのオヤジどもが昼間っからたむろしている。あまり目つきのよろしくない人々も少々。とはいえ、まあ、ここはヘルシンキ。東京でいえば歌舞伎町や大久保あたり、浅草の裏通りに深夜のセンター街を歩くくらいの心づもりでいればなんとか対応できるだろう。じっさい聞いたところでは、大久保あたりではうかつに写真なんて撮れないらしいし。ポケットに忍ばせておいて、撮りたいときはさっとシャッターを切る。そんな芸当のできるコンパクトのフィルムカメラがこういうときには威力を発揮する。
ホームレスにジロジロ見られながら歩いていると、底抜けに陽気なチャイニーズのおやじから中国語で話しかけられた。奥さんいわく、「さっき食事の配給所みたいなとこに並んでたよ、あのひと」。「同胞」と思われたのだろうか? それともそこまで町に溶け込んでいた? いや、そんなこともないと思うのだが(笑)。
とはいえ、ちょっとスノッブな匂いのある「Design District」よりも、案外このあたりの「猥雑さ」のほうが肌に合うというのもまた、事実。近ごろでは若いアーティストたちが好んでこのあたりに居を構えているらしいが、なにかをつくりだそうというひとびとにとってヘルシンキは少しばかり「清潔」すぎる気もしなくない。かえってこれくらいがちょうどいいのかもしれない。
お茶目系
2009.7.2|travel
ところで、戻ってから何人かのお客様にこんなふうに言われたのだった。
「ブログにフィンランドの写真とかアップされるんですか?」
すでに何回かアップしていたころだったのでこちらもいまひとつ要領をえず、あ、いや、もうちょっとずつアップしたりしてますけど・・・なんて応えていたのだが、どうやらそんなことみなさんよくご存知といった様子。これはいったいどういうこと!?
そして気づいたのだ。もしかしたら、みなさんが期待しているのはいかにも北欧らしいさわやかな写真なんじゃないだろうか、と。そういえば、たしかに夏のフィンランドへと誘うような清涼感あふれる写真なんてほとんど紹介していない(そもそも、ないのだが)。それどころかアラビア、マリメッコ、かもめ食堂といった「定番アイテム」すら登場していないといったありさまだ。
どうやら気づいてみれば、ぼくの目にはもう、ユルくて味があってキッチュな魅力をたたえた、そんなお茶目なフィンランドしか飛び込んでこなくなってしまったらしい。

それはたとえばこんな写真に表れている。
言うまでもなく、街角にひっそりたたずむ写真館のショーウィンドウなわけだが、もちろんこの写真の「ツボ」はといえば右下の仲良しおばあちゃん二人組のポートレイトである。「ヴァップ」に撮られたものだろうか、ふたりの頭に乗っかっているのは卒業式で授与される「白い学生帽」。ということは、
ふたりは学生時代からの親友なんだね?
なんて、写真館のショーウィンドウをのぞきこみながら思いに耽っている観光客はたしかにそう多くはないだろう。

そしてこんな写真にも。
街角でみつけたヒップホップデュオ、NIKO ja TAPSAのフライヤー。おでことおでこの引っつき加減がいかにも妖しく、目がはなせない。こういうお茶目なものを「発見」しては、日本に戻ってからネットで検索して「素性」を調べ上げる。旅の醍醐味、である。

さらには、こんな写真だって。
にぎわう日曜日のハカニエミのマーケット広場。というよりも、「主役」はむしろ写真の中の味のある(あり過ぎる?)オヤジたちの姿。おなじマーケット広場でも観光客相手のカウッパトリよりハカニエミのほうに足が向いてしまうのは、こういう普段着のフィンランド人(ジャージ姿の、という意味ではない)に混じってお店をひやかしたりしているとちょっとだけその土地と親しくなれそうな気がして、その感覚を楽しんでいるということなのだろう。
ヘルシンキところどころ
2009.7.3|travel
雨のイソロバ。

Iso-Robaとは、Iso-Roobertinkatuという「通り」の通称。真ん中がちょっとしたプロムナードのようになっているとはいえ、エスプラナーディのような華やぎ? を欠いたごくごくふつうの商店街。そんなとりわけスペシャルじゃない感じが気に入って、ゴールデンウィークの映画イベントではタイトルとしてこの「イソロバ」という名前を拝借したのだった。街角にさりげなく佇むちいさなシネクラブ、そんなイメージだ。
関係ないけど、「メリー・ポピンズ」のことをフィンランドでは「マイヤ・ポッパネン」って言うんですね。

車に乗り込もうとするひと。
20世紀初頭の「ユーゲント・シュティール」の建物が並ぶカタヤノッカやエイラ、クルーヌンハカあたりは、ぶらぶらたてものを眺めながら散歩しているだけで楽しいエリアだ。日本語版はなかったけれど、インフォメーションに行くとそんなヘルシンキ市内のユーゲント・シュティールを紹介する建築マップも配布されている。

この柵の感じ・・・。学校、なんでしょうね。子供たちの気配が感じられないのはもう夏休みだから。

肉屋のトラック(たぶん)。グッドデザインです。無骨なはずなのに、街にしっくりなじんでいる。
シルタサーリ。このおだやかな眺めが好きで、いちど水辺にたつホテルに宿泊してみたいと思うのだが予算オーバーでまるっきり無理。せめてベンチに腰掛けて、のんびり本など読んで過ごしたいもの。とはいえ、じっとしているのがもったいない、そんな旅人にはそれもなかなか難しいというのが現実だったりするのだが。
公園の片隅のキオスキは、夏だけオープンするこじんまりとしたカフェになっている。イナタいけどやたら落ち着く。ここはいろんな意味でオープンなカフェ、なのだ。


ちなみにここの公園、地元のひとびとが日々丹精こめて手入れをしているおかげでヘルシンキの他のどこよりも一年中きれいな花々を咲かせるのだと教えてくれたのは、映画『かもめ食堂』のアソシエイト・プロデューサーとしてもおなじみの森下圭子さん。なるほど、ちいさいけれど、こんなにもみんなから愛されている、なんてしあわせな公園なのだろう。
身から出たサビ
2009.7.5|travel

フィンランドへ旅立つ前、「ミスター・サルミアッキ」ことユッシさんからのリクエストは、ユッシさんお気に入りのLEIJONAのサルミアッキを買ってきて欲しいというものだった。念のため説明しておくと、サルミアッキというのは「世界一マズい」などと表現されることも多い漆黒のグミである。
で、もちろん、しっかりLEIJONAのサルミアッキは早々にゲットしたわけだが、ここはやはりぼくの「サービス精神」と言うのだろうか? 、ユッシさんの「コレクション」にいまだ登場していない「珍品」はないものかと、ついついスーパーのお菓子売場で目を皿のようにしてしまう自分がいるのだった。
というよりは、
まっ、自分が食べるわけじゃないから、できるだけ変なヤツにしちゃえ
っていうのが正直なところ。で、発見したのが上の写真のコイツである。パッケージを見るかぎり、AITOというスウェーデンのメーカーのものらしい。ずいぶん昔に買ったサルミアッキ本によればドクロ型のサルミアッキというのはとりわけ珍しいものでもないのだが、スーパーマーケットで売られているのは初めて目にしたので迷わず買ってしまった。とはいえ、もちろん自分が食べるつもりは毛頭ない。
ところが、さすがは「ミスター・サルミアッキ」。ユッシさんは「必要以上に」親切なのだった。そして「お裾分け」という名のもと、このオドロオドロしいサルミアッキを食べるはめになってしまった自分が、いる。身から出たサビ。後悔先に立たず、である。
肝心の味はといえば、本体はともかく、周囲にまぶしてある粉末の永遠に溶け合わないハーモニーのような「あまじょっぱい刺激」が、不愉快この上ない波動となって容赦なく押し寄せてくる。ほんとうに、まったくこんなもん買ってきたのは一体どこのどいつだ! と怒鳴りつけたい気分である。
ヘルシンキのカフェ(やや感傷的に)
2009.7.6|travel

いまはなきヘルシンキのカフェ、MUUSA(ムーサ)。当時ヘルシンキに暮らしていた建築家の関本竜太さんが、「とっておきのカフェ」と言ってこっそり教えてくれたのがここだった。
おばちゃまがひとりで切り盛りするこじんまりとしたカフェだったが、カウッパトリ(マーケット広場)のすぐ目と鼻の先という位置ながらほとんど観光客の目には留まらないという絶妙のロケーションで、地元のひとびにとってはちょっとした「隠れ家」として愛されているようだった。
その後、映画「かもめ食堂」の特典DVDでも小林聡美さんが(森下圭子さんのおすすめということで)紹介していたので、知っている方、あるいは実際に行かれた方もいるにちがいない。上の写真はぼくが行った、たしか2004年か05年に撮ったもの。どうやら2007年にクローズしたらしい。
MUUSAがすでにないことは知っていたのだが、Kirje kahvila(キリエカハヴィラ)までがなくなっていたのには正直ショックをうけた。
じつはなにをかくそう、カフェとポストカードショップを併設した空間という点でいまのモイをつくるときイメージをふくらますうえで参考にしたのが、かつてヘルシンキ中央郵便局(Posti)の一角にあった「手紙カフェ」という名前のこのカフェだったのである。取材のときなどよく、「ヘルシンキの中央郵便局に『手紙カフェ』というのがありまして」なんて説明していたのだが、、、これからは「過去形」で話さなくてはならないようだ。

写真は現在のものだが、かろうじてWayne's Coffeeのコーヒーサーバーが設置されているものの、残念ながらかつての面影はまったくないといっていい。それにしても、Waynes(←フィンランド人は何と発音するのだろう? ヴァユネス? それともふつうにウェインズ?)のヘルシンキにおける増殖ぶりはここ数年さらにエスカレートしているようだ。個人的には、そんなに面白い話ではない。

ところで、かつて「MUUSA」があった場所には、いまべつのカフェができている。強い風と冷たい霧雨を避けて逃げ込んだそこは、KULMA KAHVILA(クルマ・カハヴィラ)という、兄サンが一人で切り盛りする店だった。
四年も経てば、世の中いろいろ変わるのはいたしかたないこと。フィンランドだってまた例外ではないのだ。
フィンランドで買った3枚のCDと買わなかったCD。
2009.7.7|travel
フィンランドでは自分のため3枚のCDを手に入れた。
まずは、Emma Salokoski Ensembleの2枚目のアルバム「Veden Alla」。
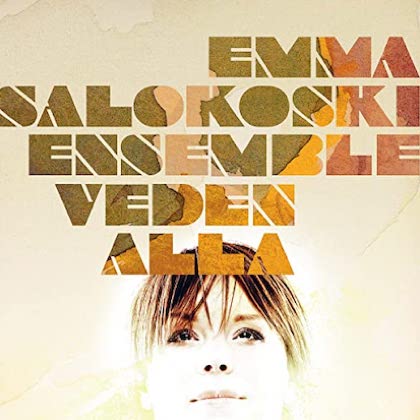
エンマ・サロコスキのアルバムはファーストをもっている。2、3年前、どうしても欲しくてフィンランドにゆく斉藤さんにお願いをして買ってきてもらったのだった。やけにユーロが高いころで、確実に3,000円以上した憶えがある。フィンランドではCDはエラく高いのだ。その後、たしか去年、ファーストにボーナストラックを追加した日本盤が出ている。透明感のあるボーカルが清々しいノルディック・ボッサ。ほとんどすべての曲がフィンランド語で歌われているのも魅力的。たまたま、ウーデンマーンカトゥにあるIvana Helsinkiのショップをのぞいたときちょうどかかっていたのもこのアルバムだった。
昨年リリースされたこのセカンドは、前作の世界観をより深く掘り下げたつくりでアルバム全体としての充実度はぐっと高まった印象。最後に寄ったストックマンのCD売場で9.9ユーロになっていたため購入。

そしてヴァイオリニストPekka KuusistoとジャズピアニストIiro Rantalaのデュオによるライブ盤「Subterraneo」。ことしの1月にケーブルファクトリーで収録されたもので、タンゴやジャズを非常にくつろいだ雰囲気で演奏している。Special Thanksに「名前はわからないけど、収録中静かにしてくれていたとなりのスタジオのヘヴィメタバンドのみなさん」とあって笑ってしまった。こういうアルバムは、まず確実に日本では出ないので18.8ユーロでも購入(にしても、高いなぁ)。
ヘルシンキの場合、STOCKMANNのCD売場でもANTILLAのTOP10でも、Digelius MusicやLevykauppa AXといったCDショップでもCDの値段自体はそんなに変わらない。値段は定価と、半額程度のディスカウントコーナーの二種類になっている。ただ、前者のような母体の大きなショップのほうがディスカウントになっているCDの種類や量は多い気がするので、お目当てのCDがあるひとはまず先にそういったショップでチェックしたほうがいいかもしれない。
ちなみに余談だが、以前紹介したDVDでビル・エヴァンスが招かれて演奏していたヘルシンキの邸宅はこのペッカの実家である。
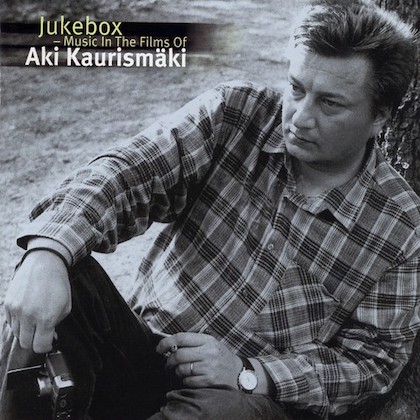
さらにもう一枚、アキ・カウリスマキの映画で使われている音源をあつめたコンピ「Juke Box : Music In The Films Of Aki Kaurismaki」。二枚組で23.5ユーロ。やっぱり高いが、以前少し日本で出回ったときに買い損ねたままだったので迷わず購入。じつはなにより聴きたかったのは、『真夜中の虹』のエンディングに登場する「虹の彼方に」。歌っているのはフィンランドの国民的歌手で、「キング・オブ・イスケルマ」ことOlavi Virta。

実は買おうと思ったけど止めたのは、The Stance Brothersのアルバム「Kind Soul」。ザ・ファイブコーナーズクインテットのテッポ・マキュネンのプロデュースによる、ヴァイブをフィーチュアしたものすごくクールなクラブジャズ。買うのをよしたのはおぼろげながら日本盤が出ていたような記憶があったからで、19ユーロも出して買っておきながら日本でもっと安く出回っていたら悔しいと考えたからだ。結果は正解。このあいだCDショップで手に入れた国内盤は2,500円弱でボーナストラック入り。
フィンランドでCDを買うひとは、国内盤の有無や値段、輸入盤の入荷状況など出発前にざっと調べておいたほうが安全だ。
地味だけど、、、アールト
2009.7.8|travel
世界最小のアールト建築。

ヘルシンキの中心部、エロッタヤ(Erottaja)にポコッと建つ地下入り口である。奥行きはそこそこあるものの、正面からみるとご覧のとおり、ひとが一人通れる扉が三つ並んだだけのコンパクトさ。
60年代初頭にアルヴァー・アールトのアトリエではたらいた経験をもつ武藤章『アルヴァ・アアルト』(鹿島出版会)によると、「冬戦争」直後の1940年におこなわれた地下防空壕のコンペで一等を穫ったプランだそう(実際に完成したのは1951年)。
おなじ本によれば、このときのアールトの案は
広場の地下に防空壕を設け、その入口を交通分離帯の中におき、しかも入口の周囲をガラス張りにすることによって交通機関の視野を妨げないようにする
というものだった。
一見気づかなくても、ちょっとしたディテールが紛れもなくアールト。

現在は地下駐車場の入り口となっているため利用者以外なかに入ることはできないが、地下がちょっとした商店街のようになっていた時代もあるようだ。かつては防空壕の一角が「公衆便所」として利用されていたようで、先ほどの本にはおもいっきり「地下の公衆便所の入口」と紹介されている。

ぼくらは、ここに車を停めていたえつろさんにくっついて地下の駐車場まで下りることができた。地下鉄の駅とおなじく、いざというときにはいまでも「シェルター」として活用される。もちろん、そんなことにはけっしてなりませんように。
さらに地味に、アールト
2009.7.9|travel

アルヴァー・アールトの設計によるトゥルン・サノマット(トゥルク新聞)の本社ビル。引きで撮ってもあまり面白くないので(シロウト的には)、あえて変な角度から撮ってみた。
愛嬌のない、古ぼけたビルにしか見えないのだけれど、設計されたのが1928年から29年にかけてと聞けばビックリする。だって、80年前だよ! 昭和4年! あのやたらとドッシリした造りのヘルシンキ中央駅の駅舎が完成したのが1919年なわけだから、当時のひとびとの目にトゥルン・サノマットのある意味「色気」のない建物はどんな印象に映ったことだろう。
ところで散歩の途中、偶然みつけたのがこの瀟洒なホテル↓。

もともとはイギリス人実業家の邸宅として建てられ、80年代からホテルとして使われている(とホテルのウェブサイトには書かれている)。そして1920年代にはアルヴァー・アールトがここに事務所を構えていた時期もあったようだ。こんなチャーミングな空間の中であんな過激なプロポーションの建物を構想するというのは、やっぱり先進的な感覚をもったひとなのだろう。一般的には、この作品をプロローグにして、つづく「パイミオのサナトリウム」で一気にアールトの「個性」が爆発すると言われている。
それはそうと、なんとかならないかと思うのはアールト建築のトイレの問題(男子の小のほう)だ。
といっても、じっさいぼくが入ったのはフィンランディアタロとアカデミア書店のあるビルくらいなものだが、(小)便器どうしの間隔があまりにも狭いので便器はあるのに並んで使用することができないのだ。フィンランディアタロでコンサートを聴いたときには、休憩中律儀にひとつおきに使用していて行列ができているのだった。仮に便器が6個並んでいたとすると、3個しか使えないということ。だったら最初から4個にすればいいのにという話なのだが。さすがに相手がアールトともなると、「あのぅ、先生、便器の間隔がちょっと・・・」なんて言えなかったのだろうか?
壁に注目!
2009.7.10|travel

ヘルシンキのクルーヌンハカ。時間つぶしに雨の中、ひとりでぶらぶら散歩していて出くわした小劇場。
ぱっと見は地味なのだけれど、よく見るとたくさんの「色」が絶妙に配分されていて思わず「きれいだなぁ」と呟きながらシャッターを切った。カメラを持っていないときにはたぶんけっして目に飛び込んでこないかもしれない風景。

トゥルクの大聖堂。
なんとか「侵入」できないものかと、建物の周囲をぐるぐる歩いていて発見したのがこの壁に埋め込まれた石碑だ。ラテン語? もちろん読めないが、歴史の重みだけはぼんやり感じられた。

こちらもトゥルク。駐車場の壁の、ずいぶんと高いところに貼られていたステンシルっぽいポスター。塀によじ登って片手で撮影。写真を撮りたいがどうにも恥ずかしいというときは、心のなかで「旅の恥はかき捨て、旅の恥はかき捨て」と念仏のように唱えることにしている。
破れっぷりがステキ。
CAFE LUFTのシナモンロール
2009.7.11|korvapuusti

ヘルシンキのカフェ、CAFE LUFTのシナモンロール。
フィンランド基準からするとやや小ぶり、見た感じでは冷凍だろうか? 甘みがやや強く、どちらかというとスイーツっぽいところもそう感じるゆえん。焼き色がかなりしっかりついているが、たぶんそれも冷凍だからじゃないだろうか。
でも、案外このシナモンロールがおいしかったりするのであなどれない。手作りの素朴なシナモンロールもいいけれど、このレベルのシナモンンロールが手軽に食べられるのならそれもよし。冷凍なら、どこのブランドのものかこっそり教えてほしいくらいである。

ちなみにLUFTがあるのはカッリオのはずれ。周囲はポルノショップやパブ、ちょっといかがわしい雰囲気の漂うタイ式マッサージの店などが数多くあるエリアだが、通りをはさんだ向かいには大きな銀行があるせいでお昼にはスーツ姿のビジネスマンやOLもたくさん訪れる。むかし中目黒にあった「オーガニックカフェ」をもっと素っ気なくしたような雰囲気で、フィンランドにはめずらしい、日本人がイメージする「カフェ」に近い雰囲気をもつお店。夜にはDJが入ってパーティーがおこなわれたりもするらしい。
K.E.Avikainenのシナモンロール
2009.7.12|korvapuusti

ヘルシンキの下町、丘のてっぺんにひっそりたたずむちいさなレイポモ(パン屋さん)、K.E.Avikainenのシナモンロール。
この場所で40年以上商売を続けてきたというおばあちゃんのつくるシナモンロールは、まさに「コルヴァプースティのお手本」と言いたくなるようなすばらしいカタチ、そして味。カルダモンとシナモン、砂糖のバランスもほどよく、しっかりした焼き色もぼくの好みにぴったりなのでした。

ところで、こういうお店を訪ねるときには、なんといっても「お行儀よく」しなければならない。その町に暮らすひとびとが大事に守り、育ててきた場所にお邪魔するわけだから。そこに流れる「空気」を乱さないようよくよく注意をしなきゃいけない、そう思うのだ。
つたないフィンランド語(というよりは単語の羅列?)でいろいろと買い込んで、(他に誰もお客様がいらっしゃらなかったので)記念に一枚パチリと写真を撮らせてもらって店を後にしたのだった。
生活の句読点
2009.7.13|cafe
2002年の7月、「moi」を荻窪にオープンしたときぼくはウェブサイトに、一杯のコーヒーは
「生活にとっての句読点のようなもの」
と書いた。

仮にこの世の中に「句読点」が、つまり「、」や「。」が存在しなかったとしても、ぼくらは文章によってコミュニュケーションすることはできる。じゃあ、「句読点」なんて不必要なんじゃないかと問われれば、あるいはそうかもね、と答えることだろう。と同時に、それについてはぼくはこんなふうにもかんがえる。なくてもいいけど、でもあったほうが全然いいものなんじゃないかな?、 と。
なんだか理屈っぽくなってしまったけれど、ぼくはこの「句読点」をそのまま「カフェ」、あるいは「一杯のコーヒーとともにカフェですごす時間」と言い換えてもかまわないんじゃないかと思っている。カフェもまた、なくてもかまわないが、でもあったほうが全然いいもの、だからである。
ところでこれはちょっとした愚痴と思って聞いてほしいのだが、残念ながら、ぼくの暮らす東京でカフェを取り巻く状況は相変わらず厳しい。まずは「不必要」と思われるものから削ってゆく、そんなとき、お茶をする時間(そして、お金)はいちばん最初に削られる対象であり、いちばん最後になってようやく戻ってくるものであるらしい。「句読点」を削ってもとりあえず文章は成立するから・・・。そんな論理の下、こうして生活から「句読点」が消えてゆく。
「句読点」を欠いた生活はしかし、それを欠いた文章とおなじで味気なく、息苦しい。旅行や大きな買い物は文章にたとえれば段落を変えるようなもので、一時的なリセットになったとしてもまた「句読点」のない生活がつづけば呼吸困難になるのはあきらかである。べつにコーヒーである必要はないけれど、風通しよく生きるためにほんとうに必要とされているのは「段落を変える」ことではなく、日々の暮らしのなかに適当なタイミングで「、」や「。」を打つことなのだ。ぼくはそう思っている。
そしてだから、それでもぼくはカフェをやっている。
ヘルシンキという街は、ぼくに言わせれば、「句読点」のもつ意味を知っているひとびとが暮らす土地である。街のそこかしこに、生活に精妙なリズムをもたらす「句読点」がある。都市の真ん中に、ちょっとひと息つくのにうってつけの公園があり、森があり、水辺がある。そしてもちろん、カフェがある。
白状すれば、ぼくはフィンランドで飲むコーヒーの味は好みではない。でも、フィンランドのカフェで、そこに暮らすひとびとに混じってコーヒーを飲む時間がとても好きだ。機能的なもの、合理的であることを重んじるはずのフィンランドのひとたちが、「時間がないんだから省いちゃえ!」とはならずに、あのように足繁くカフェに入りコーヒーをすすっている姿は意外でもある。かれらの合理的な発想の裏側に、一見「無用」とも思えるカフェですごす時間があったのか!、そんな感じである。
今回のフィンランドの旅でぼくは15、6軒ほどのカフェに入り、そこで思い思いの時間をすごすひとびとを眺め、また黙々と仕事に打ち込むひとびとの姿をみた。それはまた、ぼくにとってはなんともしあわせで、また眩しい光景だった。そしてそんな光景を眺めながら、
「この仕事もなかなか捨てたもんじゃないな」
なんて、性懲りもなく相変わらず食えないことをかんがえていたりするのだった。
さてと、
なんとなく切り上げるタイミングをつかめないままだらだらと続けてきたこの旅行記ですが、とりあえずこのあたりで(いい加減)終わりたいと思います。いつもながらお付き合いくださいましたみなさま、どうもありがとうございました!
「純粋なる形象 ディーター・ラムスの時代―機能主義デザイン再考」
2009.7.14|column
男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく、なんて言うつもりは毛頭ないけれど、機械はやっぱり機械らしく、あってほしいもの。
「機械らしく」というのはぼくの場合、まず角張っていること、それにツマミやメーターといったいかにも「機械らしい」アイテムが適切に配置されていることがとにかく必須条件である。人間工学だとかエアロダイナミクスだとか、それはたしかにいいものなのかもしれないが、おかげでさまざまな機械(自動車や電車を含む)がどんどんフニャフニャしたかたちになってゆくのはどうにもこうにも見るに耐えない。
で、なにが言いたいのかというと、府中市美術館に行き「純粋なる形象 ディーター・ラムスの時代―機能主義デザイン再考」という展覧会を観てきたのである。
ディーター・ラムスという名前にピンと来なくても、彼がデザインを手がけたドイツのブラウン社(BRAUN)の製品なら誰しも一度は目にしているのではないだろうか? かく言うぼくもそうで、ディーター・ラムスという名前こそ知らなかったものの、彼が関わったモノなら電動シェーバーにコーヒーミル、コーヒーメーカーに目覚まし時計など子供のころから家で親しんできたものばかりである。そういうところはちょっと、フィンランドの家庭におけるカイ・フランクの存在に似ていなくもない。
電動シェーバーにはじまり、オーディオ、キッチン雑貨、プロジェクター、カメラのフラッシュ、時計、電卓、家具などラムスがデザインに関わった製品の数はざっと五百以上にも及ぶが、それらはどれも基本的には
── 丸と四角(ときどき三角)
によって構成されているといっていい。


たとえばL2というスピーカー(1958年)、あるいは、RT20というラジオ(1961年)なんかはまさにその典型。
とりわけ、このラジオはほんとスゴイ。いかにも「機械らしい」四角いフォルムにメーターや必要最小限のツマミを配したデザインはまさにシンプルの極みといった感じであるのに、ごらんのとおり無骨な印象はまったく、ない。
正面からみて左側に円形のスピーカーを配し、右側にはタテ型のチューニングメーターと九つのツマミが並んでいるのだが、L字型に配置したツマミ類とメーター、それに「BRAUN」のロゴとを線で結ぶと四角形になるよう計算されているのだ。なので、ゴチャゴチャいろいろなアイテムがあるにもかかわらず、印象としては左側に丸、右側に四角というまるで幾何学的に構成された図面のようにしか見えないのである。こんな具合で一事が万事、ディーター・ラムスというひとのデザインは計算されつくしたタイポグラフィーのように整然とした美しさで貫かれているのだった。
それ以外でいうと、ぼくの目を惹きつけたのは会場の一角にひとまとまりに展示されていた卓上、そして携帯のライターだった。そういえば子供のころ、こういった感じの卓上ライターが家にもあった。点火するためボタンを押し込むときの、子供にはけっこうな重みと「カチッ」という鈍い音がなつかしく思い出される。ぼくはタバコは吸わないけれど、こんなライターならひとつくらい家に置いておくのも悪くないかもしれない。ただときどきなんとなく火を点してみたりするだけの目的で。
機械らしい機械には、意味もなくただただ純粋に触れてみたい、そういう誘惑がまたつきものなのである。
サルミアッキのポスター
2009.7.15|finland

フィンランドの国民的お菓子(?)サルミアッキのポスターです。
1950年代、FAZER社(ファッツェル)の「PAX」のためにERIK BRUUNがデザインしたポスターの復刻版です。前々から欲しかったので、荷物になるのも厭わず買ってきてしまいました。サイズは70×100cmあります。
もし興味ある方がいらっしゃいましたらお店ででもお問い合わせ下さい。
◎ 追記 その形状から「サルミアッキ」だとばかり信じていたのですが、ミスター・サルミアッキことユッシさんより「PAXはラクリッツィ(Lakritsi)ですよ」とのご指摘をいただきました。2007年にレトロなパッケージで復刻されたのですが、ぼく自身まだ食べたことはなかったようです。ちなみにサルミアッキもラクリッツィも真っ黒いリコリス(甘草)風味のグミですが、塩化アンモニウムで独特の塩味をプラスしたものがサルミアッキと呼ばれます。というわけで、このポスターは「ラクリッツィのポスター」というのが正解です。訂正させていただきます。さすがはミスター、ありがとうございました!
日蝕
2009.7.22|column
日蝕、残念ながらここ吉祥寺ではまったく観測できませんでした。
わざわざこの日のために観測用のメガネを購入したスタッフは、朝、出勤してきた時点ですでにテンション下がり気味。次第にブツブツと独り言がふえて何を言っているのかと思えば、「なんなんですか? この天気」「あまたつーっ」などと悪態をついている。しまいにはメガネを放り出し、「太陽が見たくなったらいつでも使ってください!」と投げやりな発言まで飛び出す始末・・・
とはいえ、ここモイではそんな「残念なアナタ」のため、毎日お楽しみいただけるバーチャルな「日蝕」をご用意しています。その名もずばり、「eclipse(=蝕)」というコーヒー&ティーカップで提供するコーヒーです。


ほら、こんな感じ
お天気にかかわらず、目にもやさしく、そのうえ心安らぐ「黒い太陽」。ぜひご賞味あれ!
Hanako 2009.8.13号
2009.7.23|publicity
本日発売の雑誌『Hanako』はおなじみ完全保存版「東京カフェ案内」。
とっておきの一杯がある、極上カフェへ。
というテーマのもと、ここ「moi」も特別なコーヒータイムが過ごせるカフェとしてご紹介いただいています。渋谷の「カフェ マメヒコ」さん、中目黒の「CAFE FACON(カフェ ファソン)」さん、それに西荻窪の「どんぐり舎」さんといったそれぞれ個性豊かなお店と一緒に掲載していただいているのがうれしいところです。
書店でみかけましたら、ぜひ手にとってご覧いただければと思います。
速報 ピロイネンカフェ@+casE gallery
2009.7.25|event

いま、代々木上原にある+casE galleryではマリメッコとのコラボレートでも知られるフィンランドの家具メーカー、PIIROINEN社のスタイリッシュでカラフルな椅子(↑)が展示されています。
そしてこの秋、一日限定でその+casE galleryがピロイネンの椅子に腰掛けてフィンランドの雰囲気を味わえる「カフェ空間」に変身します。題して、
『ピロイネンカフェ@+casE Gallery~カフェとデザインでフィンランドを感じる一日。』
この一日カフェに、TRADE WINGさんとともにmoiも参加させていただくことになりました。
ピロイネンの椅子がならぶ明るいギャラリースペースにフィンランドのカフェを思わせるドリンクバーを設置、パンや焼き菓子などとともにセルフスタイルでドリンクをお楽しみいただけるほか、会場内では北欧カフェ雑貨の販売なども予定しています。
さらに当日は、「ヘルシンキ カフェめぐり」というタイトルでわたくし岩間がカフェのマスター視線でフィンランドのコーヒー、そしてカフェについてお話しさせていただく時間もご用意しております(無料。ただし事前のお申し込みが必要です)。先月のフィンランド旅行の際に得た最新情報もお伝えできそうです。申し込みが少ないとかなり恥ずかしいので・・・ぜひご都合のよい方は遊びにいらして下さいね。お待ちしております!
◎ ピロイネンカフェ@+casE Gallery~カフェとデザインでフィンランドを感じる一日
日 時:9月26日[土]12時~18時(トークは14時~、16時~の2回)
会 場:+casE gallery (代々木上原)
入場料:無料 ただしドリンクその他は有料。
ご注意:トークのみ事前のお申し込みが必要です。
なお、+casE galleryのウェブサイトにはまだ情報はアップされていませんが、イベントの詳細およびトークのお申し込み方法につきましては下記のサイトでもご案内しております。ご参照ください。よろしくお願い致します。

こちらは正真正銘のフィンランドのカフェ。
カフェ&レストラン 7月号、8月号
2009.7.26|publicity
コラムを書かせていただいている雑誌『カフェ&レストラン』(旭屋出版)のご紹介です。
7月号の特集は、夏らしく「サラダ」。そういえば、フィンランドでは毎日半分ゴハンがわりにサラダを食べていた。カレー味やエスニック風味、クスクスにお米を使ったものなどがどうやらトレンドのようであちらこちらで見かけた。パパイヤやメロン、ぶどうにザクロといったフルーツが入っているのも特徴的でした。Yumicoさんは、フィンランド人にとっての果物は「ベリーとリンゴだけっ」と言い切ってましたが(笑)言い得て妙、かも。
連載の「CAFEをやるひと×BARをやるひと」のテーマは、「情報発信、やってます」。
イベントをやったり、原稿を書いたり、そんな飲食以外の仕事をどんなふうに考え、やっているのか、そんなことについて書いています。珍しく? 今回はふたりの着地点、同じでしたね(笑)。
続いて、先日発売になったばかりの8月号は「エスプレッソ大特集」。
ここ数年、おいしいエスプレッソを飲ませてくれるお店がふえていますね。職業としての「バリスタ」も注目をあつめ、抽出技術も世界レベルにまで達している模様。個人的には流行のバールよりも、いまは亡き京都の「ちきりや」のような、手動のエスプレッソマシンで「濃いコーヒー」を出してくれる街場の喫茶店とかなつかしいです。あとは、十数年前、西麻布にあった「Beach」とか。深夜遅くまで営業していたエスプレッソバール。いまもあるのだろうか?
連載「CAFEをやるひと×BARをやるひと」のテーマは、「カレンダー問題」。いかにもあまのじゃくらしく? いわゆる「ハッピーマンデー」に噛みついてます(笑)。
書店等でお見かけの折にはぜひ手に取ってごらん下さい。
NIKO ja TAPSA あるいは顛末記
2009.7.27|finland
どうやら、フィンランドの「毒」がカラダにまわったらしい。

ヘルシンキの街角で偶然フライヤーを目にしたフィンランドのヒップホップユニット、NIKO ja TAPSA(ニコ&タプサ)のことが、帰国後、気になってしかたない。こんなことならCDを買っておくべきだったと後悔することしきり。断っておくが(断るまでもなく?)、ぼくがヒップホップのCDを欲しいなんてかんがえることはめったにない。けれども旅で耳にしたフィンランド語のあの独特の「語感」を思い出し、また楽しむのにまさにヒップホップはうってつけ、である。それにあの、ポップといえばいえなくもないジャケットのアートワーク、若いんだかオヤジなんだか見当のつかないふたりの風貌もまた、ある意味チャーミングだ。まあ、そんなふうに感じてしまうことからして、すでに全身に毒がまわっている「なによりもの証拠」なのだが。
もちろん、かれらのCDを手に入れる方法がないわけじゃない。じっさい、この6月から9月上旬にかけて身近なひとびとが誰かしらフィンランドを訪れている。頼もうと思えば頼めないこともないのだ。しかしモノがモノだけに誰にでも頼めるものじゃないということは、ぼくがいちばんよくわかっている。
だって、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
たとえば、死ね死ね団の『Greatest Baka Hits』を買おうとしているニュージーランド人。はたまた、「蒲焼きさん太郎」を箱買いしようとしているナミビアのひと。ちょっと恥ずかしくはないだろうか? となると、そんな恥ずかしいお願いをできそうな(=そんな恥ずかしい思いをさせたところで平気そうな・・・笑)ひとといって思いつくのはせいぜい3、4人といったところ。そのなかで近々フィンランドに行く予定のあるひとといえば・・・、そうおなじみのみほこさんである(笑)。断っておくが(断るまでもなく?)、みほこさんはヒップホップは聴かない。だが、フィンランド語のできるみほこさんなら「なんか、友だちに無理矢理頼まれちゃって」とか、「甥っ子がヒップホップ好きなのよね~」とか、とにかく流暢なフィンランド語で「言い訳」できるだろう。これなら無闇に恥ずかしい思いをさせることもない。
こうして、いまぼくの手元にはNIKO ja TAPSAのCDがある(ありがとう、みほこさん)。
70年代のソウルミュージックからサンプリングされたバックトラック。ニコとタプサによる、どことなくおっとりとしたMC。もともとが韻を踏みやすい言語のせいか、フィンランド語のラップはやけに「調子よく」聞こえてしまうのだが、その「調子のよさ」がかえって面白く聞こえてしまうのはこちらがたぶん、ふだんヒップホップになじみがないせいだろう。
物は試しとさっそく店でかけてみたのだが、スタッフからのブーイングを俟つまでもなくほんと、まったくmoiの空間には合いませんね・・・。どうやら、店主の密かな愉しみとするしかないようである。
それではどうぞ、NIKO ja TAPSAで「すばらしい日々」。
Blossom Dearie『Sings:Blossom's Own Treasures』
2009.7.29|music
ひと頃、小鳥の声が入ったCDを探していた。カフェのBGMに使えるんじゃないか、そうかんがえたのだ。
探してみるとたしかにないこともなかったが、残念ながら店でかけられそうなCDとなるとほとんどなかった。ヒーリング、っていうんですか? なんのひねりもない陳腐な音楽が重ねられているものだったり、あるいは、さまざまな種類の鳥たちがさながら「紅白歌合戦」のごとく次々に登場しては美声を自慢げに披露するようなものだったりと、どうもぼくの抱いているイメージとはかけはなれたものばかり。
ぼくが欲しいのは、森のどこか一カ所に集音マイクを立てて鳥の声や木立を吹き抜ける風の音をそのまま、できうるかぎり最小限の加工しかほどこさずに収録したようなCDなのである。だが、ひと握りの物好きのためにCDをつくってくれるほどレコード会社はヒマではない。じぶんが集音マイクを担いで森にゆくか、さもなくばどこかの親切な音の採集家がプライヴェート音源を譲ってくれるのを待つしかないだろう。早い話、あきらめろ、ということだ。
その代わり、と言ってはなんだが、いま、ぼくの手元にはブロッサム・ディアリーのCDがある。

大好きな「Sunday Afternoon」をはじめ、可愛らしい楽曲がならんだ1973年発表のアルバム『Sings』に、さらにブロッサム自身が書いた曲ばかりを合計8枚のアルバムからあつめた2枚組のCDだ。
低音の鳴らないモイのスピーカーで薄めの音量でこのCDを流すと、なかにはグルーヴィーなベースラインをともなう曲なんかもあるのだが都合よく? カットされて、もともと小鳥みたいな彼女のヴォーカルばかりがあたかも本当に、小鳥のさえずりのように聞こえてくるのだった。そしてカフェの空気もわずかばかり鮮度を増すのだ。
余談。
このアルバムにはブロッサム本人と親交のあった音楽ライター、高田敬三氏の文章が寄せられていて、そこにはごく近い距離で接したひとしか知りえないような貴重なエピソードも披露されており興味深いのだが、個人的に「うれしい発見」だったのは次のふたつ。
その1。1978年にブロッサム・ディアリーが来日した際、吉祥寺のジャズクラブ「サムタイム」でも公演がおこなわれたということ。モイの前の通りをまっすぐ進んでサンロードとぶつかる手前の地下に、「サムタイム」はある。もしかして店内のどこか、壁かなにかに彼女のサインが残されていたりするのだろうか・・・
その2。ブロッサム・ディアリーのお母さんはノルウェーからの移民だということ。じぶんが惹かれるものはいつも、どこかでほんの少しだけ北欧とつながっているのだ、という意味で。
グレン・グールド『アンド セレニティ』
2009.7.30|music
ここはひとつ、音楽の力に頼るほかなさそうだ。
よりによってこの時期に、自宅のリビングのエアコンが壊れるなんて。なんとか交換してもらう手筈はついたものの、こちらもこちらで昼間家にいる時間が少ないため、果たしていつになったら無事新しいエアコンが設置されるのやら見当もつかない。
とりあえずは、いますぐ体感温度を2度ばかり下げてくれる、そういう音楽が必要だ。
雪やこんこに雪の降る街を、歌われている情景はたしかに涼しいが、口ずさんでみたところでいっこうに涼しくはならない。ただバカにみえるだけだ。おなじ理由から、「津軽海峡・冬景色」もおすすめしない。かえって暑苦しい。どんなに寒々しい情景を歌っても暑苦しい、これはある意味、演歌のスゴさであると「発見」した。
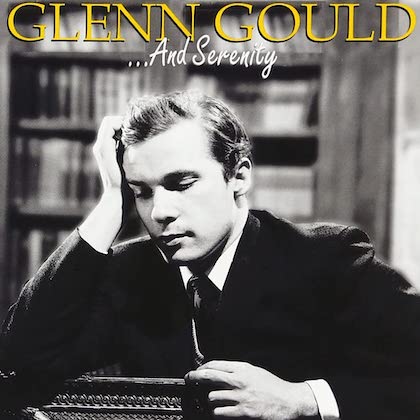
そしてたどりついたのは、グレン・グールドの『... And Serenity 瞑想するグレン・グールド 』。J・S・バッハからブラームス、シベリウスにいたる音楽から、「静謐さ」というキーワードのもとセレクトされたさまざまな楽曲がならんでいる。
じつをいえば、ふだんこういったたぐいの企画盤にはほとんど食指をそそられないのだが、このCDはべつ。そこには、「グールド」というブランドで一儲けをたくらむ浅知恵とは明らかに異なる「深い共感とリスペクト」のようなものが感じられるからだ。じっさい、ライナーノーツにはこんなグールド自身によることばが引用されている。
芸術の目的は、アドレナリンの瞬間的な放出ではなく、驚きと穏やかな心の状態を、生涯かけて築いてゆくことにある。
一時的な熱狂よりも、静かに持続する内面的な感興こそを追求した音楽家が、ひとつひとつの音符と誠実に対話するその模様を収めたドキュメント、それがこの『... And Serenity 瞑想するグレン・グールド』というアルバムに結実している。
夏でもコートと手袋を手放さなかったという逸話の残るピアニストは、「心頭滅却すれば火も亦た涼し」という禅師の言葉のような境地を、じっさい生きていたのだろうか。グールドの弾く硬くひんやりしたピアノの音色が、心とからだの火照りをゆっくり鎮めてくれる、すくなくとも、そんな気がする。
これでエアコンのない夏を快適に過ごせるなら言うことないのだけれど。



