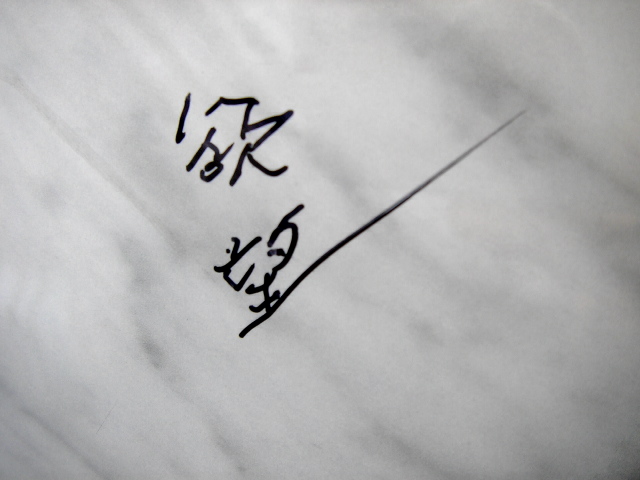ピースフルな土地
2007.7.2|travel

ひとことで言うなら、「出雲」はピースフルな土地だった。
出雲大社を訪れるひとはふつう、駅を出たらそのまま参道を通り境内へと吸い込まれてゆく。ところがぼくらは参道から逸れて二十分ほど歩き、『古事記』にも登場する「稲佐の浜」へと出た。来る途中、電車のなかで見たあのポスターにも描かれていた場所である。
夏には海水浴客らで賑わうとのことだが、この時期人影はまったくみあたらない。しかも海は驚くほど静かで、耳を澄ましてもただ上空を旋回するトンビの声が聞こえてくるばかり、波音さえも届いてこない。そうしてさまざまに「青」の階調を変えながら、やがて海ははるか彼方で待ち受ける空と溶け合いひとつになる。空と海との境界が失われるところは、古代のひとにとってはまたあらゆる「境界」が失われるところでもあったろう。じっさい、旧暦の十月ここ出雲にあつまってくる八百万(やおよろず)の神々はみな、海よりここ「稲佐の浜」に到着し「大社」へと向かうと信じられている。まるで真空状態にあるようなこの静かで平和にみちた浜辺に佇んでいると、なるほどそんな信仰も理解できるような、そんな気分になってくるのだった。

稲佐の浜からは、「神迎の道」を歩いて出雲大社へとむかう。その名前どおり、稲佐の浜に到着した八百万の神々が「竜蛇さま」(神々の到来を告げるため竜神がつかわした蛇)を先頭に通るための道である。浜に立つ石灯籠が、そこがまた出雲大社の「入口」であることをあらわしている。幅にして約三メートルほどのその道には、翁の顔をあしらった瓦屋根をもつ黒っぽい塀の家並みや、あるいはいかにも古そうなちいさな社なども見受けられるものの、おおかたは床屋や中華料理屋が居並ぶごくふつうの住宅街の道と変わらない。観光客のためではなく、あくまでも長い歳月をそこで過ごしてきた出雲の人々ひとりひとりのための「心の道」なのだと思う。参道に近づくと、竹でつくられた小さな桶に思い思いの花を挿し軒先に飾る家が目立つ。こうした自然体の「もてなし」にあって、マニュアル主導の「ホスピタリティー」にないもの、それは吹き抜ける風のような清々しさではないか。

はじめにも書いたが、「出雲」は実にピースフルな土地である。日本最古の神社がある「聖地」にもかかわらず、いかにもといった感じの強力な磁場のようなものが一切感じられない。いや、それはたまたまぼくが「スピリチュアル」だとか、「パワースポット」だとかいったものに無頓着なせいもあるだろう。そうしたものを感じたいひとにとっては、あるいは「ビンビン感じられる場所」ということだってあるかもしれない。けれども、そのどこまでも平和でのどかな町を散策しているうちに、ぼくはむしろこのような土地こそ日本の神さまが棲む場所としてはふさわしいような気になっていた。
こんもりとした山と波静かな海に囲まれたこの豊かな土地で、踊りを舞ったり酒をのんだり、相撲に興じたり、ときには「兄弟げんか」をしたりもしながら、日本の土地を大きな手のひらでつつむように守っているおおらかな神さまたち……。日本人ならだれでも心当たりのあるおおらかな信仰心のルーツを、なんだかそこで垣間見た思いがしたのだ。
出雲大社
2007.7.3|travel
そして、出雲大社へやってきた。
木製の大鳥居が立つ「勢溜(せいだまり)」から、いよいよ参道がはじまる。前に訪れたときはまだ小学生だったし、ぜんぜん記憶になかったのだけれど、今回とても驚いたのは参道がかなり急な下り坂になっていることである。てっきり神社というものは、だいたいが高い土地に建てられるものとばかり思っていたからだ。戻ってきて調べたら、実際この「下り参道」というのは珍しいらしい。

だいぶ下ったところから撮影したのだが、それでもまだまだ下っている。緑に覆われているということもあるけれど、「おおやしろ」といわれる建造物がまったくといってよいほど目に入らない。いったい、どうしてこんな谷底のような土地に社を構えたのだろう?不思議に思ってちょこちょこ調べてみたものの、それらしき記述にあたらない。ただ、『古事記』の中には出雲大社のはじまりをめぐるこんなエピソードが登場するという。出雲大社の祭神である大国主命(おおくにぬしのみこと)は、「国譲り」の条件として「私の住む所として天子が住まわれるような壮大な宮殿を造ってくれるのなら、国を譲り、世の片隅で静かに暮らしましょう」と言ったというもの。つまり、これはまったくの推測でしかないのだけれど、国を譲った大国主命の隠遁の地であるからこそ、それにふさわしい場所として、海と山に囲まれた谷底のようなこの土地が選ばれたということなのかもしれない。
小さな橋を渡り松並木の参道をしばらく歩くと、青銅の鳥居が現れ、「拝殿」を臨むことができる。

ラッキーにも(?)バスガイドさんの団体と遭遇。これだけ大勢のバスガイドといっぺんに出くわすということは、たぶんそうあることじゃないだろう。ちなみにガイドさんたち、触ると一生お金に不自由しないといわれる「銅鳥居」に、若さにまかせて思いっきり触ってます。もちろん、オトナはそういうことはしません。恥じらいながらめいっぱいしがみつく、これ正解。
これが、「拝殿」。

重さ1.5トン、長さ8メートルという巨大なしめ縄がかかっている。1.5トンといわれてもピンとこないというひとのために説明すると、「KONISHIKIの5人分」である。長さは「猫ひろしの5人分」。ていうか、KONISHIKIってそんなに重いんだ!ちなみに「神楽殿」には、重さ5トン(KONISHIKIの17.5人分)の「しめ縄」もある。
拝殿の奥に隠れるようにしてあるのが、国宝の「本殿」である。本殿へは一般の参拝客は入れないうえ、周囲をぐるりと塀が囲んでいるせいで様子を窺うことすらむずかしい。まさに隠れてあるのだ。

西洋人としてこの本殿への昇殿をはじめて許されたラフカディオ・ハーンは、興奮を隠しきれない様子でこんなふうに記している。「神道の真髄は、書物の中にあるのでもなければ、儀式や戒律の中にあるのでもない。むしろ国民の心の中に生きているのであり、未来永劫滅びることも、古びることもない、最高の信仰心の表れなのである」(池田雅之訳)。ふだんはなんのためらいもなく前を素通りしているにもかかわらず、なにか特別なことがあったり、お正月になったりするとごく当然であるかのようにいそいそと「お詣り」にでかける神社の存在というのは、たしかにラフカディオ・ハーンの言うとおり「心の中に生きている」ものなのかもしれない。
抹茶色の城下町
2007.7.5|travel


松江は抹茶色の町だ。江戸時代、茶人のお殿様がいたからにちがいない。じっさい、町をあるいていてやたらと目につくのは和菓子の店、それにお茶屋さんだ。旅の途中、マクドナルドやスタバはいちどだって目にしなかったというのに。
京都、そして金沢と並ぶ「茶の湯」の町として知られるここ松江は、たしかに町全体が抹茶のような深々とした、また清々しい「緑」に覆われていた。


松江に茶の湯を広めた不昧公(ふまいこう)こと松平治郷の墓所のある月照寺はまた、「山陰のあじさい寺」としても知られている。天気予報でみた「傘マーク」はいったいどこに消えてしまったのだろう。予想外の夏の太陽に、あじさいの花もなんとなく当惑気味。
不昧公の墓所に供えられていた白い百合の花に、これまた鮮やかな緑色したアマガエルを発見。こうやってずっと、雨が来るのを待ちかまえているのだろうか。


ちなみにこれは、その名もずばり「不昧公」というデザート。無糖の抹茶ゼリーに、白玉、あずき、それにアイスクリームがのっている。
松江をあるき、その町の空気を吸っていると、ここで抹茶を点てることはごく自然なことと思えてくるから不思議である。それはたぶん松江が、抹茶の色と香りが似合う町だからにちがいない。松江の土にはきっと抹茶がしみこんでいるのだ。
東京に戻ったら、ぼくもいつもコーヒーを淹れているような気分で抹茶を点ててみよう。
薄茶を点てる
2007.7.6|travel

というわけで、なにかと影響をうけやすいぼくは、東京にもどってから薄茶を点てているのである。お抹茶は不昧公直々に命名したという銘茶「中之白」。もちろん松江で買ってきたもの。 ウス茶糖
とはいえ茶道の心得は皆無ゆえ、ひたすら見よう見まねでやっている。いままでインスタントコーヒーを飲んでいたひとが、不意に自分でコーヒーをドリップするようになった感じとでも言おうか。つまるところコーヒーにせよ抹茶にせよ、それじたいを味わうこと以前に、コーヒーを淹れる、抹茶を点てるというそのプロセス、その時間を味わうことこそがぼくは好きなのだとあらためて思った。
もちろん「かたち」に興味がないわけではないがさすがに敷居が高い。bleu et rougeさんのおっしゃるとおり、ナンチャッテな茶道教室なら大歓迎、やる気マンマンなのだけれど……
明々庵
2007.7.7|travel

松江城の天守閣を臨む高台に、不昧公の好みにあわせてつくられた茶室「明々庵(めいめいあん)」がある。このあたり、木々が鬱蒼と生い茂るちょっとした台地になっていて、かつてその麓で暮らしていたラフカディオ・ハーンによると、ウグイスやフクロウはもちろん、ときにはホトトギスの啼く声まで聞かれたそうだ。
待合から茶室につづく明々庵の「露地」。
岡倉天心によると、「露地」の役割とは「外界とのつながりを断ち、新鮮な感受性を呼び覚まして、茶室での美的体験を存分に味わえるように備えさせる」(大久保喬樹訳)ことにある。つまり、このほんの短い小道で、客は自分自身をリセットするのだ。茶室でお茶をふるまわれることで「リセット」されるのではなく、「露地」で「リセット」することによって茶室での体験がよりいっそう特別なものになるというわけだ。もし、喫茶店や居酒屋にも「露地」があったなら、店で会社や家庭の愚痴をこぼすひとが減るかもしれない!?
日ごろ雑然とした場所で生活しているせいか、茶室の清潔かつ簡潔な空間には単純にあこがれるものがある。そういうところに住めないのなら、そういう気持ちを呼び覚ましてくれる空間を身近につくるというのも手だろう。moiもそういう場所になれたら最高なのだけれど。

← 茶室をのぞきこむ怪しげな人影(=店主)。
山陰グルメ
2007.7.8|travel
おまっとさんでした。たべものシリーズです。
せっかく山陰まで来たのだから地のものを、できればカジュアルに楽しみたい。そう思って出かけていったのが、松江駅近くの「根っこ」というお店。地元で人気らしく、OLやサラリーマンらでずいぶんと賑わっていた。すっかり気に入ってしまったぼくらは、けっきょく二晩連続で通ってしまったのだった。
まずは付き出し。あん肝煮、骨せんべいとおかひじき、それに葉ごぼうという取り合わせ。


続いては「地魚の三種盛り」、手前からノドグロ、トビウオ、それに白バイ(ジョン&パンチではない)。
ノドグロは、関東ではアカムツという名前で知られている魚。たぶんはじめて食べたと思うのだけれど、脂がのっていてとても美味しい。
鳥取で作られている無添加ソーセージ。ふわっふわ。


「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」のひとつ、いまが旬のモロゲエビの唐揚げ。背わたが少ないうえ皮もとても柔らかいのでアタマからシッポの先まで、平気でバリバリ食べれてしまう。
こちらは、しまね和牛のタタキさん。


豆いっぱいのピザには三種類の豆がはいっている。そのなかではじめて口にしたのはワレット豆。サヤエンドウとインゲンを足して2で割ってデカくした感じ。やわらかくて、ちょっと甘味があってさやごと食べれる。島根県産とのことで、およそ東京では見たことがない。美味しいのに……。帰りにスーパーマーケットによってひと袋買ってきた。たっぷり入って百八十円也。

刺身が脂がのっていてとても美味しかったので、オススメというノドグロのしゃぶしゃぶに挑戦する。
口の中ですっと溶けてしまう感じ。あまりにも火が通りすぎるとほろほろっと崩れてしまうので、サッと湯にくぐらす程度がちょうどいい。
そのほか、撮影する間もなく胃袋に消えていったのは白イカの生干し。地元でつくられているざる豆腐や新たまねぎのサラダ、それにこのお店のルーツであるおでんの盛り合わせ(八十歳をすぎたおばあちゃんが元気に厨房に立ち煮込んだもの)も美味しかった。
ごちそうさま!
旅にもってゆく本
2007.7.9|travel
旅のたのしみのひとつに、旅に携えてゆく本を選ぶというたのしみがある。結局ほとんど読まないままに帰ってきてしまうことが多いとなると、やはり「選ぶ」という行いのうちにたのしみを見い出しているといったほうが正しそうだ。
今回携えていったのは二冊。まずは、星新一『ほら男爵現代の冒険』。

はじめて出雲・松江にいった小学生の夏、もっていった本だ。そのころクラスの「学級文庫」では星新一の本が大人気で、たぶんそんなこともあって持っていったのだと思う。行きの寝台列車(ブルートレイン)で読むつもりだったのだが、はじめて乗る寝台列車がうれしくそれどころではなかった。
深夜まで、うれしくて列車の中を行ったり来たりくりかえしているうち「ちょっと、ぼく?」、車掌さんに呼びとめられた。
「鼻血出てるよ」
興奮のあまり鼻血を出していたのだった。「ちょっと待ってて」と言うと、車掌さんはトイレットペーパーをぐるぐると腕に巻きつけもどってきた。「ほら、これをつめときなさい」と手渡され鼻にトイレットペーパーをつめて眠ったので、けっきょく本は読まなかった。というわけで、ある意味リベンジである。
大人になって読む星新一は、あらためて面白い。軽快な文体とスパイスのようにぴりっとくるシニカルな表現、それに「近未来」への洞察の深さ……子供のころに全部読んじゃったというひと、あらためてこの夏読み直してみてはどうだろう。
もう一冊は、岡倉天心『新訳・茶の本』。

出発前、ちょうどこの本をめぐってとても刺激的な企画を進行中のKサンからメールをいただいた。じつはずいぶん前のこと、この本を読もうと思い立って岩波文庫版を手に入れたのだが、そのあまりにも格調の高い訳文に圧倒されあっという間に逃げ出したのだった。けれどこれもなにかの偶然、せっかく「『茶の湯』の都市」に出かけるのだしもういちど挑戦してみるか、と気をとりなおした。調べてみるとこの『茶の本』、いろいろな翻訳者による版が存在している。
大久保喬樹氏によるこの訳文はとてもこなれていて読みやすいうえ、各章につけられた解説も親切だ。日本人とはいえ「茶道」についての知識なんてまったく持ち合わせていず、しかも日本的な美意識からもほど遠い生活をしているのだから、ある意味ぼくも「外国人」みたいなものである。あらためて感心することや驚かされることもすくなくない。なかにはなんとなく納得したり、また理解できたりすることもあり、「ああ、やっぱり日本人なんだなぁ」とあらためて感じてみたり……。
「不可能を宿命とする人生のただ中にあって、それでもなにかしら可能なものをなし遂げようとする心やさしい試みが茶道なのである」
なんて、わかったようなわからないような、でもちょっとぐっとくる一文ではある。ストーリーよりもむしろ、ちょっとした一文の印象のほうが強烈に記憶に残る、これはもしかしたら本を旅先で読んだときならではの特徴といえるかもしれない。
島根ブーム!?
2007.7.10|travel
東京にもどってすぐ、「石見銀山」の世界遺産登録が決定。さらに今週の土曜日には、松江を舞台にしたテレビドラマ『島根の弁護士』(仲間由紀恵主演)が放映されるという。また、cactus408のいずみさんからも島根にいくつか気になるお店があるとの熱い(?)メールが……
これはもしやちょっとした島根ブーム!?
おそらく半年後には「クウネル」が松江・出雲特集を組むことでしょう(笑)。
くぐれない鳥居
2007.7.11|travel

散歩をしていて発見、思わずギョッとしたのは松江の中心部、宍道湖の湖畔にたつ須衛都久(すえつぐ)神社のこの鳥居。くぐれないじゃん!
いったい、どうしてこんなことになってしまったのか?「いやぁ、たまたま気づいたらこんなになっちゃってね」ってことはないだろう。それにだいたい、どうしてこのままにしているのか?気になって仕方ないのである。
一応、ぐるりと回りこむとちゃんとくぐれる別の鳥居があるので参拝客が困ってしまうということはなさそうである。もともと湖畔の埋め立てかなにかをする前にはこの神社は宍道湖の水辺にあったらしく、どうもこの鳥居も湖に面した水際にあったらしい。
が、けっきょく理由はわからずじまい。理由を知っているひとがいたら、ぜひ教えてもらいたいものである。
どうせ浮ぶとなれば、
2007.7.13|travel

さいしょの日に行った島根県立美術館では、ちょうど有元利夫の回顧展「有元利夫-光と色 想い出を運ぶ人」がひらかれていた。
その名前はもちろん、作品も本の装幀やCDのジャケットなどでよく見かけてはいたもののこれまでまとめて観る機会には恵まれていなかった。どれもルネッサンスのフレスコ画を思わせる世界だが、その世界はまたどこかSF的でもある。すべての作品を貫くムードは、「静寂」というよりは「真空」であり「無重力」といった感じ。それにしても、いくら平日の夕刻とはいえ、だだっ広い展示室にはぼくら以外だれもいない。完全な貸し切り状態、ぜいたくといえば、ぜいたくだが……

会場には、ところどころ有元が遺したエッセイなどからの一節が抜粋して紹介されているのだが、そのなかにこんな一文をみつけた。それは、彼の絵画のなかでよく人物や花が「臆面もなく」宙に浮いていることに対して彼なりに解釈をほどこしたもので、それを彼は「エクスタシーの表現」だと言う。そしてその一節はこうしめくくられていた。
どうせ浮ぶとなれば、青い空に白い雲。
切り取られたある一節だけとりあげてああだこうだと言うことはそもそもがまちがいだが、時間からも空間からも解き放たれた無我の状態、そのもっともピュアな姿を青い空に浮ぶ白い雲に有元は「みた」のではないか。そういえば、かれの作品に描かれる雲、いびつなひし形がななめにずれながらいくつか折り重なったような独特のフォルムをもつ雲もいままさに刻々と姿を変えているそのさまを描いているようで、一見とても「静的」な印象のあるかれの作品に通奏低音のようなリズムをこっそりもたらしている。
そのときぼくは、飛行機のなかで読んでいた『茶の本』に登場するタオの老人の話をかんがえていた。「天にも地にも属さないために天地の中間に住んでいた」という老人の話だ。そうか。それが「天」であれ「地」であれ、なにかに属するということは、その「属すること」と引き換えに「重力」をもつということでもある。
有元利夫の絵、ひとの生活と自然とのあたかも「波打ち際」のような松江という土地、空と海とが溶け合い、この世とあの世とが交感する出雲、葦原中国(あしはらのなかつくに)と神話にいわれるこの日本の土地……

今回の旅を方向づけたのは、思えば、「どうせ浮ぶとなれば、青い空に白い雲」というこのちょっと詩的な一節だった。「あいだ」や「中間」や「境界」や「際(きわ)」をそこかしこに「発見」し、そのつど「重力」から解放されてゆく旅。呼ばれて、よかった。
もうひとつのガイドブック
2007.7.14|book

ガイドブックというとふつう、旅に出る前にひらくものと相場がきまっている。事前に目的地の情報を仕入れたり、ときには旅の目的そのものをみつけるためひらくことだってある。まさに道しるべ、である。
その一方で、旅に行ってきたひとのためのガイドブックといえるものもある。旅のなかで出会った風景、音や匂いなど五感を介して刻みこまれた記憶が、その土地の印象や理解をぐっと深めてくれる。たとえば、松江、それに出雲を旅してきたひとにぜひ手にとってほしいのは、ラフカディオ・ハーン『新編・日本の面影』である。
これは、日本での日々やその印象をつづったラフカディオ・ハーンの代表作『知られぬ日本の面影』に収められたエッセイを厳選し新たにまとめ直したもので、池田雅之氏の訳文もこなれていてとても親しみやすい。さいしょ手に入れたときは完読できないかななどと思っていたのだけれど、気づけばあっという間に読み終えてしまっていたほど。
五感が研ぎすまされるという感覚は海外旅行にでかけたときなど、ぼくらもまた体験する感覚だが、このときのハーンはまさにそんな感じだったのだろう。あこがれの東洋の島国で見聞きするすべてが、全身が感度のいいアンテナのようになったかれの感覚をビンビンと刺戟しているさまが手にとるように伝わってくる。そしてその理解の深さと洞察の鋭さは、このエッセイをたんなる「見聞録」以上に価値のあるものにしている。読んでるこちらのほうが、「なるほどなぁ」とか「あ、そういうことだったんだ」とか感心さえられることしきりである。
それにもうひとつ、「音」に対する感性がすごい。橋を渡るひとびとの下駄の音、湖を行き来する船の音、虫や鳥の声にひとびとが打つ柏手の音……たぶん日本人であればあまりに「日常」すぎて気にもならないようなさまざまな「音」がここでは確実に拾われ、見事に描写されている。いくらここ日本の話とはいえ百年以上も前の遠いむかしの情景にもかかわらず、やけに生々しく感じられるのはきっと、こうした「音」がぼくらに伝えてくるライブ感のせいだろう。
すべての旅好きのひと、必読の一冊だと思う。
ふたつの「豊かさ」をめぐって
2007.7.15|travel

松江をたつ直前、一時間半ほど時間があいたので松江の中心部、茶町、京店から殿町あたりといったかつての繁華街を散歩してみた。
こういってはなんだが、寂れていた。梅雨時の平日の昼下がりといったことを差し引いても、老舗旅館や観光客相手の店がならぶ町並みはあまりにも閑散としている。空き店舗もやたらと目立つ。みじかい旅のなかでぼくが出会った松江、それに出雲がすばらしく豊かな場所だったことを思うと、そのあまりのギャップに戸惑わざるをえない。
松江や出雲ではどこでも-町のまんなかでさえ-、ちょっと手をのばしさえすれば自然の息づかいを感じ取ることができ、その自然の恵みであるふんだんな海の幸や山の幸は旅人の胃袋をみたしてくれた。豊穣のシンボルである大黒さま、つまり大国主命がここ出雲の地に祀られていることはたんなる偶然ではないのだと、この土地を歩くとよくわかる。同時にそこは「茶の湯」の都であり、小泉八雲が愛した素朴な人々が語り継ぐ神話と伝説の都市であることも忘れられない。
にもかかわらず、この豊かな土地であるはずの島根県がどうもけっして「豊か」ではないらしいのだ。じっさい2005年のある調査によると、ここ島根県の「人口減少率」は秋田、青森についで第三位だという。その土地で暮らしてゆけないから若者は仕事を求めて県外へと流出してしまう。結果いよいよ高齢化に拍車がかかり生産力は減衰する。悪循環である。路線バス(市バス)にのって気づいたのだけれど、ここでは高齢者からも運賃をとっている(割引制度はあるらしい)。高齢化が著しい場所ほど、逆に老人福祉が手薄になるという矛盾である。
いまの時代、殺伐とした土地であっても、大きな自動車工場のひとつもあればその土地は「豊か」に潤おう、そういう時代である。そういう時代に生きているのだから、それをむやみに否定してもしょうがない。ただ、すべての価値の尺度をそこに寄せていってしまうということについてはやはり疑問が残る。この目で見て触れた松江、出雲が「豊か」ではなかったとはけっして思えないからだ。乱暴に言えば、「豊かさ」にはたぶん質的な豊さと量的な豊さとがあるのだろう。島根県の「豊かさ」は、「量的な豊さ」こそを「豊かさ」だと定義する資本主義社会にあっては、手のひらですくった水のようにみすみすこぼれ落ちてしまうものなのだ。

茶の湯についてかんがえてみる。それはもともと武士のものだった。信長や秀吉といった戦国時代の武将たち、つまり現代に生きるぼくらよりもずっとシリアスに現実と向き合っていたひとびとが「茶の湯」を愛し、茶人を庇護してきたというのはなんとなく不思議な気がする。生死をかけて権力の座を奪い合う血なまぐさい日常と、「茶の湯」というどこかスローな儀式とのあいだの関係性がいまいち見えにくいからだ。けれども、よくよくかんがえれば「量的な豊さ」を極めようとする武人が、むしろそれゆえ「質的な豊さ」を必要としていたというのは自然なことである。天下をとるような人物は、「量的な豊さ」の有限を知っている。その虚しさを埋めるためにも、おそらく「質的な豊さ」を味わうセレモニーとしての「茶の湯」を渇望したのかもしれない。俗世を離れた極限的に小さな世界でパンパンに膨張した風船のような密度の濃い時間を過ごすことで、「量的な豊さ」に埋没しそうな自分自身をリセットしたのではないか?ちなみに、「量的な豊さ」のみに走る経営者たちの行く末については、ここ最近のニュースをみればおわかりのとおり。
生まれたときにはすでに、わけがわからないまま「量的な豊かさ」を追求する経済原理にからめとられてしまっているぼくらもまた、戦国武将にとっての「茶室」のような仕掛けをたぶん求めている。戦国武将のようにみずから進んでそうしたシステムに飛び込んだわけではないぶん、本当はぼくらのほうがずっとそういう「仕掛け」を必要としているのだ。無自覚なだけに始末が悪い。けっきょく、さまざまな「ストレス」として表面化してはじめて気づくのだ。
静かでおだやかな土地に行きたいと思って松江・出雲へと出かけたぼくは、思えばおなじ理由でフィンランドへも出かけていたのだった。ふたつの都市がもつ波長は、ぼくにとってとても似ている。それは「質的な豊さ」を実感できるという意味で似ているのであり、いってみればそこには「茶室」のような仕掛けがある、ともいえる。不意におこるその土地へ行きたいという直観には、どうやら従ったほうがいいみたいだ。
さて、22回にわたってお送りしてきたこの「松江、出雲の旅」もそろそろおしまいです(だいだい気も済んだので!?)。一応、念のためお知らせしておくと、実際の旅はたったの二泊三日でした(笑)。呆れつつも忍耐強くおつきあいくださったみなさま、ありがとうございました。