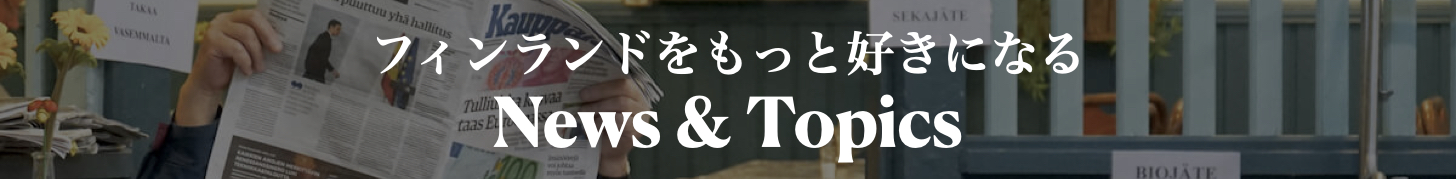あしたかん?── 子どもの頃、路地に迷いこんだ先で外国の古い教会のような建物をみつけた。まわりの建物と雰囲気がぜんぜん違っていたから、自分がどこにいるのかわからないような気持ちがした。あとで地図を調べてみると「自由学園明日館」とあった ──
*
そんな明日館で、SADI 北欧建築・デザイン協会 主催による特別講演会『人を中心に据えてこそ、真の建築は生まれる|True architecture exists where man stands in the center』が、2025年10月24日に開催されました。この講演会では、アールト建築の代表作でもあるセイナッツァロの町役場でガイドツアー【AALTO TALKS】を行なっているピーター・デ・フロート氏とアニッカ・ヴァンデヴェルデ氏のおふたりから、アールト建築の特徴やその魅力について聞くことができました。
冒頭で「本日は、アルヴァ、アイノ、そしてエリッサ・アールトのストーリーをお話ししたいとおもいます。アールト建築は20世紀を象徴する建築といえるでしょう」とピーターさん。そして、アニッカさんからは「アメリカの詩人ミュリエル・ルーカイザーはこう書いています──世界は原子でできているのではなく、物語でできているのです。とても詩的な表現ではありますが、建築というものも物語によって構成されていると私たちは理解しています。歴史的・個人的な背景、素材、技術、性格、自然環境、すべての物事はつながっています」という言葉がありました。
数多くの資料が残されているアールト建築とはいえ、実際にアールト本人の目的や理由を確かめることはもうできません。アールトの遺産を引き継いでいくためには、残された人々で語り合い、アールトの物語を紐解いていく必要があるのではないでしょうか。

近年、展覧会『アイノとアルヴァ 二人のアアルト』、書簡集『アイノとアルヴァ』、映画『AALTO』などにより、アイノ・アールトの再評価が進んできました。アールトの建築やデザインにおいて、アイノはどのような部分を担当していたのでしょうか。実務面でも大きな役割を果たしていたアイノの名がこれまでおもてに出てこなかったのはなぜでしょうか。
ヘリット・リートフェルトとシュレーダー夫人、ル・コルビュジエとシャルロット・ペリアンといった著名な建築家の隣にいた女性たちの例を挙げながら、「Who did what?|誰がなにをしたのか」という隠された物語を想像していきます。
リートフェルトの設計したシュレーダー邸について、あるジャーナリストから「Who did what?」と質問されたシュレーダー夫人は、こう答えたといいます「この家は私たちの子どもなんです。自分の子どもにそんなこといわないですよね」。もしかすると、アイノ・アールトも同じような気持ちだったのかもしれません。もちろん社会の風潮もあったはずですが、自らの評価や名声よりも素晴らしい建築やデザインに貢献することに価値を見出していたという側面もあったのではないでしょうか。
ピーターさんとアニッカさんのおふたりが、アールト建築の物語を交互にリレーするように語るのを聞きながら、当時からこのような共同作業がふつうに行われていたら、もっと素敵だったかもしれない。そんなふうに感じていました。

そして話題は、ルイ カレ邸、ヴィープリ図書館、セイナヨキ図書館、パイミオ サナトリウム、セイナッツァロの町役場といった代表的なアールト建築へと移っていきます。
そのなかでとくに興味をひかれたのが、ロシアとの国境近くの街イマトラにあるスリークロス教会(ヴオクセンニエミ教会)でした。2021年に「THREE CROSS HELP」というスリークロス教会を修繕するための募金についてご紹介したことがあったためです。
ピーターさんが「アールトが設計した教会のなかでももっとも素晴らしい」というように、スリークロス教会は、アールト建築の傑作といわれながら、老朽化により修繕が必要となっていました。そこで建築家の彦根アンドレアさんを中心に「THREE CROSS HELP」という団体が設立されました。スリークロス教会を紹介するオンラインイベントも開催され、たくさんの募金があつまり、その修繕にあてられました。
まだまだ資金が不足しているとはいえ、遠く離れた日本からフィンランドにある教会を救うために、いちはやく善意の気持ちが届いたという事実は、アールト建築にまつわる物語として、ずっと覚えておきたい、語られていってほしいものです。

講演のまとめとして、「どうしてアールトの建築やデザインはいまでも価値をもちつづけているのでしょうか?」という問いに、AALTO TALKSのおふたりは5つの理由を挙げました ── ひとにやさしいデザインであること、有機的な建築であること、既成概念にとらわれないこと、挑戦的な姿勢をもつこと、モダニズムへの批評を怠らないこと。
物語を語ることで、生き続けるものや生命を吹き返すものがあります。講演の後、SADI会員のみなさんが「実際にフィンランドでアールト建築を目にしたあとで今回の話を聞くとより深く理解できる」と話されていました。いつかまたフィンランドでアールト建築をみる機会があったなら、この日の物語を思い出したいとおもっています。
*
── Alvar Aaltoについての記事を書くとき、きっと直されるだろうなとおもいつつ、こっそり「アールト」と表記しつづけています(「アルヴァル」と書きたい気持ちをグッと抑えつつ)。既成概念を壊すとか挑戦的というわけでもなく、きっと意地っぱりなだけです、笑。いまでも明日館を「あしたかん」と呼んでいるように。

text + photo : harada
So Long, Frank Lloyd Wright – Simon & Garfunkel