広瀬和生『この落語家を聴け!』
2012.1.28|review
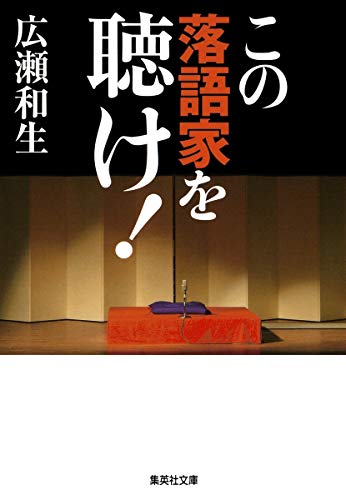
唐突に「落語」に興味をもって一ヶ月そろそろ寄席や落語会に出かけてナマの高座にも触れてみたい…… この本と出会ったのは、まさにちょうどそんなタイミングのことだった。
著者はヘヴィメタ専門誌「BURRN!」の編集長にして、年間1500を超える高座を観続けてきたというライブ至上主義の、筋金入りの「落語好き」である。著者によれば、現在の落語シーンは「名人」と呼べるような存在こそ極端に少ないものの、その一方で若手や中堅の噺家のなかに数多くの逸材が存在する、いわば「黄金時代」なのだという。そして、そのせっかくの「黄金時代」を満喫するために、いままさに寄席や落語会で聴くことのできる噺家たちを取り上げ、紹介したのがこの本『この落語家を聴け!』である。
寄席や落語会に出かけようと思ったが、いったいいまどんな噺家がいて、どんなネタを高座にかけているのか皆目見当がつかない。寄席の番組表を見たはいいが、なじみのない名前ばかりで誰を目当てに足を運べばいいのかわからない。そんなとき、この本はとても役に立つ。なぜなら、いくら百花繚乱の「黄金時代」とはいえ、すべての噺家が面白く、わざわざ時間を割いてまで聴くに値する噺家とはかぎらないからである。
しかしぼくらの生きるこの時代には、幸いなことにインターネットという文明の利器がある。まずはこの本でとりあえず聴いてみたい噺家をチェックした上で、ネットでさらに検索をすればその噺家のさまざまな情報(プロフィールや本人によるSNS、落語会の情報から、場合によっては高座の動画まで)にかんたんに触れることができる。これだけで、初心者にとってはひどく「敷居が高い」と感じていた寄席や落語会がぐっと身近なものになる。そして寄席や落語会といったライブ空間では、ときには新たな魅力的な噺家との出会いが待っているかもしれない。
落語をまったく知らないひとではなく、落語にちょっと興味をもったひとがさらなる深みにハマろうというとき紐解くと恰好の手引書になるにちがいない。
立川談春『赤めだか』
2012.2.1|review
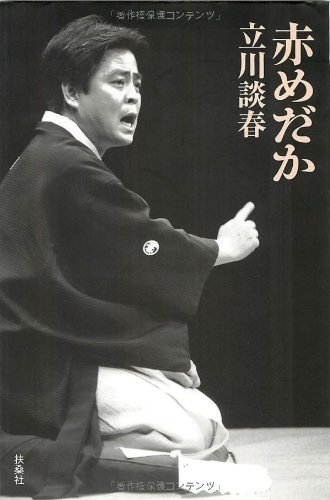
いまをときめく人気落語家がその地獄の修業時代をつづった半生記は、カラッとした文体もあいまってそんじょそこらの青春小説も吹っ飛ぶおもしろさ。
「本当は競艇選手になりたかった」少年は、課外授業の寄席に登場した立川談志の「芸」(というかその「存在」?)に打ちのめされ、高校を中退し半ば勘当状態のまま立川流に入門する。そんな彼を待ち受けていたのは、「個としての自由も権利も認められない」、つまり「人間」として扱われない「前座」としての地獄の修業……。もちろん、その「地獄」の実体はといえばほぼ100%師匠(イエモト)である立川談志という破天荒な人物にあるのだが。
ちなみにタイトルの「赤めだか」とは、談志が可愛がっていた金魚のこと。いくらエサを与えてもいっこうに成長しないその金魚をみて、弟子たちが密かに名付けたのがこの「赤めだか」という呼び名である。当時、落語協会を飛び出した草創期の「立川流」の内情はというと、まさにカオスそのもの。そんなカオス状態の中、未来への展望もなく溺れそうになりながら必死にあがいている自分たちの姿を、水がめの中で大きくなれずにいる「赤めだか」の姿に重ね合わせたのだろう。
とかくハチャメチャと思われがちな師匠「立川談志」という人間を、「いや、そんなことはないのですよ、実は……」というのではなくハチャメチャなままに談春は描く。じっさい談春にとっての師匠(イエモト)とは、離れて忘れたほうが身のためと知りながら忘れきれない、思いきれない魅力をもつ「悪女」のような存在だと言う。そしてここに、師匠と弟子とが「愛憎」によってきつく結ばれた「立川流」の特殊性があるのかもしれない。
一見したところ優等生的な印象のある談春が、まさかこんな無頼派とは…… その「意外性」もこのエッセイをいっそう楽しくしている。
堀井憲一郎『落語の国からのぞいてみれば』
2012.2.10|review

ある日突然「落語の国」に迷い込んでしまったビギナーにとって、この一冊はなかなか便利な「道しるべ」となっている。
ここでは落語の歴史やあらすじ、おすすめの噺家などが紹介されるかわりに、落語に登場する人たちー 熊さんや八っつぁん、長屋のご隠居や与太郎といった魅力的な人物たち ーのことばや動きの背景をなす「感覚」について、「時間」「金銭」「結婚」「恋愛」「酒」「死」といったキーワードを通して語られる。
たとえば「時そば」という有名な噺(はなし)の下げ(オチ)は、「九ツ」と「四ツ」という江戸時代の時間の数え方を知っているか知っていないかでその面白さがずいぶんとちがってくるように思えるし、現代よりもずっと「一年」という区切りの単位が重かった時代の噺(はなし)だからこそ、「芝浜」のおかみさんは「大晦日」に真実を告げるのだと合点がゆく。「夢」が「現実」に変わるとしたら、そのタイミングはまさに一年の変わり目にしかありえないからである(以上は、読みながら勝手に感じたぼくの解釈)。ほかには、じっさいに著者が「東海道」を日本橋から京都まで歩いたときの体験から語られる江戸の人々の「歩き」にかんする考察も、ふだんそんなこと考えたこともなかっただけにおもしろく読んだ。
ぼく自身は知らなかったのだが、著者は週刊誌などで活躍する人気コラムニストとのこと。読むひとのなかにはその軽い口調が気に障るひともいるかもしれないが、落語や町人が活躍する時代劇などに関心のあるひとにとっては、おそらくきっと興味深く読めるのではないかな?
江國滋『落語無学』
2012.2.19|review
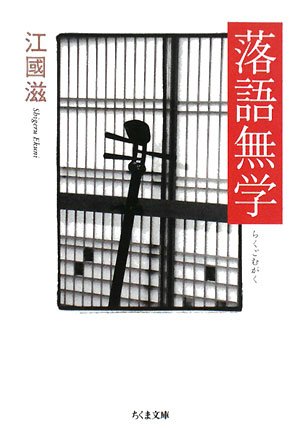
さいしょ「江國滋」という名前からなにやら堅苦しい評論めいたものをイメージして身構えたのだが、いざ読み始めてみればなんてことはない、とても軽やかな落語コラム集。
なるほど江國滋というひとは「落語」についても書くのかぁと思ったら、もともとフリーとして出発したときの肩書きは「演芸評論家」だったのですね…… 無知でスイマセン。そしてこれは、さまざまなところに発表したコラムをまとめて単行本化した『落語三部作』のなかの一冊とのこと。
批評をしようというのではなく、ひとりの落語愛好家として「落語の世界」に「生きる悦び」を思いのままに語るその言葉は、やはりおなじように「落語の世界」に魅了されるものの心にまっすぐ届く。音楽でいえば「嬉遊曲(ディヴェルティメント)」のような肩のこらない愉しさが、この本にはある。
「間(ま)の芸」を特徴とする江戸落語に対し、上方落語の最大の特徴にして魅力を「饒舌の芸」とする「上方落語の魅力と特質」と題された短い論考でも、著者は、その特質を知ることで「上方落語」というまた魅惑的な風景と出会えることを約束してくれる。否定したり、貶したりくさしたり、そういった言説の一切登場しない読んでいてとても気持ちのいい一冊だった。
4/24 春風亭一之輔真打昇進披露興行
2012.4.24|rakugo
きょう、4/24に池袋演芸場(四月下席昼の部)でおこなわれた「春風亭一之輔真打昇進披露興行」の番組です。参考までにどうぞ。
半輔(開口一番)「子ほめ」
春風亭朝也 「黄金の大黒」
桂 才紫 「たらちね」
アサダ二世 奇術
五明楼玉の輔 「宗論」
いなせ家半七 「京の茶漬け」
鈴々舎馬風 「艶歌の花道(美空ひばりメドレー~カエルの体操)」
ロケット団 漫才
春風亭一朝 「看板のピン」
~お仲入り~
真打昇進披露興行(舞台下手より市馬、さん喬、一之輔、一朝、馬風)
市馬/相撲甚句 さん喬/フラダンス、一朝/横笛、馬風/ホワイト餃子(笑)
柳家小菊 俗曲
柳亭市馬 「雑俳」
春風亭正朝 「祇園祭」
柳家さん喬 「真田小僧」
林家正楽 紙切り(相合い傘、あやめ祭り、龍、メーデー)
春風亭一之輔 「青菜」(※この興行では「初」)
安藤鶴夫『巷談 本牧亭』
2012.5.5|review

まず、「雨の降ることに感謝し、晴れて、喜び、風が吹いてもありがたいと思い、雪が降っても、ああそうか、と思う」そんなふうに淡々と、ただ「芸」にのみ生きる講釈師「桃川燕雄」の端然とした佇まいが魅力的だ。
変わりゆく昭和の東京の片隅で、ただ一カ所、講談の定席としてその灯を守りつづける「本牧亭」がこの「ものがたり」の舞台。「生まれたときからの寄席の娘で、それがもう血になっている」と自他ともに認めるおかみさんの「おひで」をはじめ、寄席の常連や「芸」のこと以外はからっきしダメ人間といった風情の芸人たちの愛すべき姿が、ここではまるで子供がだいじな「宝物」を抱きしめるかのように、やさしく描かれていて感動する。そうだ、そうなのだ、寄席はたんなる劇場(ハコ)ではない。寄席とは、さまざまなひとがそれぞれに、ちいさな喜びや悲しみによって結ばれたとてもとても人間臭い、ちいさな「町」のような場所なのだと、この「ものがたり」は教えてくれる。
ある日、若い興行師「湯浅」は、思いを寄せる娘義太夫「桃枝」のたっての希望で生まれて初めてローラースケート場を訪れる。カラフルな洋服を身にまとった若者たちに混じって、大音響で流れる流行の音楽にのって颯爽と滑る「桃枝」。その姿をひとり2階の見学席から見守りながら、「湯浅」はてっきり自分と同じ世界で同じ空気を吸っていると信じていた「桃枝」が、あたかも変わりゆく東京の風景のように自分からどんどんと遠ざかってゆくような気分にとらわれ、その恐怖とも孤独とも言いがたい感情におののく。そしてその焦燥が、やがて「湯浅」の人生を思わぬ方向へと狂わせる。
移りゆく時代の波に翻弄されながらも、不器用に自分らしく生きようとする心やさしき人たちの姿がここにはある。
松本尚久『落語の聴き方 楽しみ方』
2012.5.14|review

ナルホドソウイウコトカ。「落語」の最大の特徴を、「歴史」とは切り離された「時間」、語り手と聴き手とが回転木馬のように「同じ時間を生きる」ことにあるとして、歌舞伎や演劇、講談や能、アニメやコミックなどと比較しながら解説したとても興味深く、説得力のある一冊。
日本史の知識も時代劇への関心もさっぱりないにもかかわらず、うっかり「落語」にハマってしまった超初心者としては、かねがねこんなことでは「落語」を存分に楽しめないのではないか? というコンプレックスにも似た感情があったのだが、伝統芸能としての「落語」はいまひとつの過渡期にさしかかっていると著者が言う第8章「現代の落語」を読んで、ほんのわずか救われた気になったのだった。
ここで著者は、現代の噺家が担わなければならない課題として「距離」という問題を挙げる。つまり、落語に描かれた情景や風俗からすっかり遠ざかってしまった現在、落語の語り手は「みずからの位置とはなしの距離を ー その遠さを ー 」厳密に定め、示さなければならない。そうして、その「距離感」から「遠景としての八五郎や与太郎を、あるいは隅田川や長屋を現在に出現させる」ことではじめて、現代の落語は「芸」として成就するのだ、と。
つまり、落語の語り手がしっかりその「遠さ」を定め、示すことさえできれば、江戸時代や明治時代の情景や風俗とはさっぱり無縁な現代を生きているボクのような聴き手でも、いっしょに「回転木馬」にのって八五郎や与太郎の暮らす長屋を訪ねたり、春の隅田川でのんびり船遊びに興じたりすることができるというわけだ。
ひとまずは、目の前にそんな「情景」を出現させてくれるような噺家を追いかけてみようと思う。
和田誠『落語横車』
2012.5.20|review

ダールが好きだったりブラッドベリが好きだったりするのと同じように、落語のSF的な、奇想天外な噺に惹かれると言うイラストレーター和田誠。
ここには、そんな和田誠による創作落語が5編(うち4編は『和田誠寄席』にて実際に小三治、小朝、扇橋、二ツ目時代の雲助らによって口演されたもの)と、口演時に催された際におこなわれた山藤章二らとの座談会、そして落語にまつわるコラムのいくつかが収められている。
コラムでは、ホール落語の企画にかかわっていた若いころの話(このあたりの話は自伝的エッセイ『銀座界隈ドキドキの日々』でも触れられているが)が中心。まだ志ん朝が朝太、談志が小ゑんと名乗っていた時代の話だ。当時のジャズメンの落語好きをとりあげた「落語とジャズ」などは、落語家とジャズマン、その双方と交流のあった著者ならではのエピソードで「或る時代の証言」としても興味深い。
正直、個人的には、すでに存在する「古典」にスパイスをふりかけたかのような和田誠の「落語」はさほど面白いとも思えなかったのだが、おなじ噺を著者による「原本」と小朝による「口演バージョン」とで並べて読むといろいろなことに気づかされて興味深い。そこで小朝は、サゲを含む全体にわたって「換骨奪胎」と呼んでいいほどの大胆な改変をおこなっているのだが、その一方で、そこにこそ「書かれたもの」から「語られるもの」への跳躍、そのためにことばが必要とする筋力のようなものが垣間見られてただただ感心させられるのである。
吉川潮『江戸前の男―春風亭柳朝一代記』
2012.5.29|review

落語家、5代目春風亭柳朝の伝記小説ではあるけれど、ある典型的な「江戸っ子」の破天荒な一代記として読んでも面白い。
一時は志ん朝、談志、円楽とともに「四天王」などと呼ばれながら、他の3人とくらべるとどうも地味で影の薄い印象のある柳朝だが、この本を読むとそれもまたこのひとの「江戸っ子気質」に理由があったのか、と納得できる。
「自分が主役でないと思ったら、一気に隅のほうに引っ込んで悪あがきを見せない。石にかじりついてでも、ここで逆転してやろうなどという根性がない。淡白、見栄坊、恥ずかしがり屋……」
とはいえなにより落語が大好きで稽古熱心、「芸」で他の3人に劣っているというわけではまったく、ない。とりわけ「大工調べ」や「宿屋の仇討」といった噺では、その切れのいい江戸っ子口調や啖呵で魅せてくれる。そしてまた、惣領弟子の一朝師匠をはじめ現在寄席で活躍しているお弟子さんたちに、その「粋」な芸風がしっかり受け継がれているのはまったくもって素晴らしいことだと思う。
小谷野敦『21世紀の落語入門』
2012.6.21|review

うーん、「21世紀の」というよりも「天の邪鬼のための」落語入門?
本文中うなづける箇所も少なからずあるのだけれど、読み終わってなんとなくモヤモヤっとした感じが残るのは、かゆいところにあと一歩のところで手が届かないからだろうか?
たとえば、「私は『現場主義』というのが嫌いなのである」と主張する著者が「寄席に行かずともよい」と言うとき、当然というべきかその「理由」を聞きたいと思ってしまうのだが、それがすっきり明かされないのである。名画は、やはり海外の美術館へ行ってでも「現物」に触れなければという意見に対する著者の回答は、こうである。「飛行機に乗れないこっちとしては、けっと言うほかない」。うーむ。著者がなぜ飛行機に乗れないのかはよくわからないが(タバコが吸えないから?)、「現物」に触れずとも名画を楽しむことができるという説得力十分な「理由」を知りたいところではある。これだとむしろ、もし飛行機に乗れたらホイホイ行っちゃいそうな印象すら受けるのだけど……。
著者は、「落語を聴くには寄席に行くべし」とか「現在活躍している落語家を聴くべし」といった思考が(じっさいはわからないが)最近の落語好きのあいだの「主流」と感じていて、そういう「風潮」に対して「いや、落語にはもっとちがう楽しみ方もあるよ!」というのが言いたくて、勢いでこの本を書いたんじゃないだろうか? そんな気がした。
ちなみにぼくは「録音」、しかも「志ん生」の録音(「品川心中」)から入ってまったく聞き取れず、悔しくて何度も聞き返しているうち7回目か8回目で突然、頬にサーッと品川の海風を感じたような気がして、それをきっかけについ半年ほど前から落語にハマった人間なので、著者が言うように過去の名人の録音でも十分落語はおもしろいと思っているが、行けるものならできるだけ寄席にも足を運びたいと思っている。著者とちがって寄席の雰囲気が好きということもあるが、それ以上に、「テキストが確定していない」落語ならばこそいまこの時代の聴き手として、自分の感覚に合う落語と出会いたいという気持ちが強くあるからである。
7/10 瀧川鯉橋 真打昇進披露興行
2012.7.10|rakugo
本日7/10に国立劇場演芸場(平成24年7月上席)でおこなわれた、「瀧川鯉橋・真打昇進披露興行」の番組です。ご参考までに。
瀧川 鯉ちゃ(開口一番)「桃太郎」
瀧川 鯉八「新魔術」
瀧川 鯉朝「置泥」
ナイツ 漫才
柳亭 楽輔「鰻屋」
春風亭 小柳枝「船徳」
~ 仲入り ~
口上 舞台下手より 鯉朝(司会)・平治・鯉橋・鯉昇・楽輔・小柳枝
桂 平治「平林」
瀧川 鯉昇「馬のす」
北見マキ 奇術
瀧川 鯉橋「井戸の茶碗」
鯉橋師匠、端正ななかにもトボケた味わいがあり、なごやかで愉しい高座でした。今後、寄席の顔付けに「鯉橋」という名前があったら要チェックです。。
「仏馬」の下げ 考
2012.8.24|rakugo
こう、なんだかモヤモヤっとする、モヤモヤモヤ。このあいだ(2012年8月21日 新宿・紀伊國屋ホール)聴いた柳家喬太郎師匠による古典落語『仏馬(ほとけうま)』の下げ(サゲ)のことである。
ひとまず、その【あらすじ】から↓
とある農村、坊主の弁長と小坊主の西念のふたりが檀家回りをしてお布施を集めている。ふるまい酒ですっかりいい気分の弁長に対し、西念は檀家からの貰い物をすべて持たされてすっかりヘトヘトである。
土手にさしかかると、一頭のおとなしそうな黒い馬が木につながれて休んでいる姿が目に入る。これはいいと、弁長は勝手に西念の荷物をぜんぶその馬に背負わせると、自分は酔いをさましてから戻るのでお前は馬と一緒に寺に戻れと西念を帰してしまう。
酔っぱらいの弁長は、土手から滑り落ちないようさっきまで馬がつながれていた木に腰紐で自分の体を結わえると、うつらうつら居眠りをはじめる。そこに戻ってきたのが馬の持ち主のお百姓さん。自分の馬が、どうしたわけか坊さんに化けてしまったのだから驚かないはずがない。弁長は弁長で、放蕩のため仏罰が当たり畜生道に落ちていたのだが、修業の甲斐あってふたたび人間に戻れたなどとその場しのぎのウソをついてごまかす。
半信半疑ながらも、百姓はそんな弁長を家に連れ帰り酒でもてなす。またしても酔っぱらってしまった弁長は朝になってようやく寺に戻っていった。寺に戻った弁長に、住職は西念が連れ帰った馬を市で売って金に換えてくるよう言いつける。しばらくして、馬がいなくなってしまい不便な百姓は市へと馬を買いに出かける。すると見覚えのある一頭の馬が……。
「こりゃあ弁長さん、弁長さんだろ? また仏罰に当たったか?」と馬の耳元にささやく。くすぐったい馬は大きく「ちがうちがう」とかぶりを振ると、お百姓さん「とぼけたって無駄だ。その、左耳の付け根の差し毛がなによりの証拠」。
この噺、じつはとても珍しい噺で、喬太郎師を除いて高座にかけているのは弟弟子の喬之進さんくらいだそうである(参照☞柳家喬太郎『落語こてんパン』ポプラ社)。それもそのはず、二ツ目時代に速記本でこの噺と出会った喬太郎師が苦労して自分のネタに仕上げてきたのがこの『仏馬』なのだ。たしかに落語家がこぞって高座にかけたがるような確実に笑いのとれる滑稽噺とはいえないものの、弁長さんならずとも居眠りしたくなるような村はずれの土手の長閑さ、朴訥で信心深い田舎のお百姓さん、なんとなく憎めない高田純次的テキトーさの「弁長さん」と、のんびりゆるゆる頬の緩むような佳品だと思う。
ところが、、、問題はその「下げ」のわかりにくさである(【あらすじ】下線部分参照)。なんだろうか、いったい、これは? 馬の耳元の差し毛(白っぽい毛)をみてお百姓さんはそれが「弁長さんの生まれ変わり」と確信するわけだが、噺の最中にそんな「下げ」にもってゆくための仕込みもないし、そもそもだいたい坊さんに毛…… ということじたいおかしくはないですかっ? そのせいか、弟弟子の喬之進さんなどは「弁長さんだろ? ごまかしたって駄目だ、酒臭いもの」という独自の「下げ」を採用しているらしい。とはいえ、これにしても馬が酒臭いだなんていまひとつ理屈に合わないような気もする。それでも、あえてこの「下げ」を使いつづけている喬太郎師には、それ相応の喬太郎師なりの強いこだわりがあるにちがいない。
そう思って、早速ネットで調べたり、喬太郎師の著書の解説を立ち読みしたり、東大落語会編『増補版 落語事典』などというものものしいタイトルの本にあたったりしたのだが「下げ」にかんする注釈はいっこうに見当たらない。ああ、モヤモヤモヤモヤ……。
ならば、と自分なりにこの「下げ」について推理してみることにした。まずは「差し毛(の馬)」について、仏教的なエピソードなどあるか調べてみようと思ったのだった。すると、まず遭遇したのがWebディクショナリー。
鹿糟毛(しかかすげ)
馬の毛色の種類で、鹿毛馬に白い差し毛が入ったものをこう呼ぶらしい。ぼくはそのむかし、競馬にハマり競走馬の一口会員だったこともあるので馬の毛色については詳しい!? 褐色の毛色をもつ馬は「鹿毛(かげ)」、より黒ければ「黒鹿毛(くろかげ)」、さらにもっと黒いものを「青鹿毛(あおかげ)」と呼ぶ。「鹿糟毛」という呼び名ははじめて耳にしたが、
白い差し毛の入った鹿毛馬
であることはすぐに想像がつく。お百姓さんはみずからの馬を「クロ」と呼んでいたので、ただの「鹿毛」よりは黒っぽい「黒鹿毛」に差し毛の入ったものだったのではないだろうか。さらに面白いことに、アイウエオ順のWEBディクショナリーの「しかかすげ」の上をふと見やると、こんな言葉をみつけたのだった。
四箇格言(しかかくげん)
へぇ~、「しかかすげ」と「しかかくげん」ってコトバの響き、ちょっとというか、けっこう似てるよね? ね!(五十音順に並んでいるのだから似ていて当然だが) と思いつつ説明を読んでみる。
日蓮が、他宗が仏の道から外れているとして折伏(しゃくぶく)するために唱えた、「念仏無間(むけん)・禅天魔・真言亡国・律国賊」の4句
とのこと。なんたる偶然! 「馬」の前に「お坊さん」!! そして日蓮宗といえば、頻繁に落語に登場する宗派でもある。おそらく落語が盛んに作られた江戸末期~明治時代当時、「南無阿弥陀仏」の浄土宗、浄土真宗と並んで庶民に浸透していたのがこの「南無妙法蓮華経」の日蓮宗だったのだろう。たとえば、おっちょこちょいを直したい男が願掛けに向かうのは「お祖師様」こと杉並の妙法寺だし(『堀之内』)、お題目に引っ掛けて「お材木で助かった!」とダジャレで下げたかと思えば(『おせつ徳三郎 下』)、甲州出身の豆腐屋が嫁を連れてお参りにゆくのは日蓮宗の総本山、身延山久遠寺である(『甲府ぃ』)。ほかにもたくさんある。だから、まあ、これといった証拠はないとはいえ、この噺に登場するのが日蓮宗のお坊さんだったとしてもとりたてて不思議ではないだろう。
ならば弁長さんと西念さんは、村じゅうの檀家を回っては「四箇格言」を述べ、お題目のありがたさを説いて回っていたのではなかろうか。もちろん村人の多くも日蓮宗の熱心な信徒だったろう。(かなり無理な展開になってきましたが、どうか置いてかれませんように!)
もういちど、噺のラスト、下げにいたる箇所を確認してみる。
お百姓さんは、市で自分が飼っていた「クロ」に瓜二つの馬をみつける。
お百姓さんは、それをふたたび馬にされてしまった哀れな「弁長さん」だと信じている。
お百姓さんは、馬に「弁長さん」と呼びかける。実際にはただの「クロ」である。
馬(「クロ」)はくすぐったいので首を振るが、
お百姓さんは、「弁長さん」がとぼけて否定しているのだと疑う。
そして下げのひとこと「とぼけたって無駄だ。その、左耳の付け根の差し毛がなによりの証拠」となる。
ここからいよいよ無理無理な推理に突入!! 作者も時代も不明ながら、この『仏馬』がつくられたころは
1)現代よりも、庶民の間に日蓮宗の教えが浸透し身近な時代であった
2)現代よりも、ウマという動物が家畜として身近な時代であった
と仮定してみる。当然、落語を聴く庶民のなかにも「四箇格言」という単語や「鹿糟毛」という単語は(程度の差こそあれ)耳になじみがあったのではないだろうか? ならば、「お材木(お題目)で助かった!」なんてダジャレ同様、『仏馬』を聴いたかつての庶民たちもまた「しかかすげ」に「しかかくげん」を、「しかかくげん」に「しかかすげ」を連想できたんじゃなかろうか? などと思ったりするわけである。つまりこれは、
「しかかすげ」の馬「クロ」に、「しかかくげん」を説いて回る「弁長さん」の姿を引っ掛けることで「下げ」としている
と理解できる(キッパリ)。そう考えれば、時代の移り変わりとともにこの『仏馬』という噺が演じられてゆかなくなったこともまた、理解できる。だって現代は、馬なんて牧場か競馬場にでも出かけないかぎり出会えない疎遠な存在だし、一部の限られた信徒の方を除いては日蓮の教えもまたなじみの薄いものである。これじゃあ、まったく「下げ」なんて理解できるはずもないじゃないか。
などと長々と書き連ねてきたわけですが、実はなんの根拠もないすべて屁理屈にすぎません。ごめんなさい。速記本の「下げ」が、たとえば「この鹿糟毛がなによりの証拠」となっていればかなり確度は上がりますけどね。このままでは、あまりにまどろっこしすぎます(笑)。
正直言うと、この下げの本当の意味を知っている通りすがりのご親切などなたかが、「いやいや、キミ、それは全然ちがうよ、真相はね、~だよ」と教えて下さることを期待しつつ書いた、これはいわば「釣り」の記事であります。最後までおつきあいいただいた方には、ホント申し訳ありません!! というわけで、これを機に『仏馬』の「サゲ」の正しい意味がわかり、このモヤモヤが雲散霧消してくれますように……。
【追記】
とことん考えたら、じつはこれはすごーく単純な「下げ」なんじゃないか? ということに気がついた。三段論法で説明すればこういうことになる。
・「左耳の付け根に差し毛のある馬」は、「クロ」(お百姓さんの馬)である
・「クロ」は、仏罰に当たった「弁長さん」が姿を変えたものである
∴ 「左耳の付け根に差し毛のある馬」は、「弁長さん」である
この三段論法は、お百姓さんが「弁長さんは仏罰にあたって馬に姿を変えた」と信じている限りにおいて成立する。つまりお百姓さんは、市でみかけた馬がまちがいなくかつての自分の愛馬「クロ」であることさえ確認できれば、すなわちそれが同時に「弁長さん」であることも確信できるのだ。
どんなにとぼけたって無駄だよ。ほら、左耳の付け根に差し毛がある。ってことは、お前はまちがいなく「クロ」、つまり(「クロ」に姿を変えた)「弁長さん」だ!!
ああ、なんて単純なんだ。たぶん噺の中途に、「クロ」には左耳の付け根に差し毛があるという仕込みがあればもっとすんなり分かるのだろう。ただ、そこまで説明的にならずとも、「下げ」の部分でお百姓さんが
「あっ、間違いねぇ、お前さんは弁長さんだな? なんとなれば、「クロ」とおんなじ左耳の付け根に差し毛がある」
とでもやや大げさに叫べば、べつだん仕込みなどしなくても気持ちよく下がるんじゃないかとシロウトは思うわけなのだけど、さて、いかがでしょ?
柳家喜多八・三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎『落語教育委員会』
2012.8.24|review
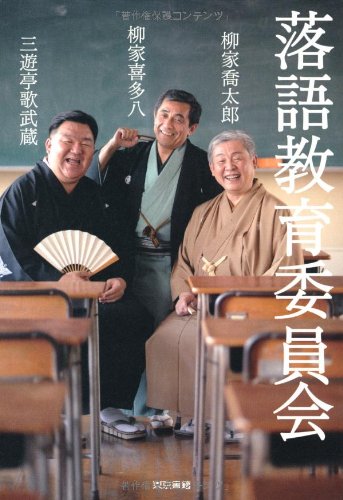
同タイトルの落語会をシリーズで開催する噺家3人による対談集。
「教育委員会」という看板をタテに(?)なかなか踏み込んだ会話もしているあたり、ふだんそういった類いの話がこちら側には伝わってこないぶん興味深い。
そういえば、登場する3人のうちのひとり柳家喜多八師匠が出演した落語会に出かけたときのこと、終演後会場にいた主催者にむかって「なんで落語って事前にネタを予告しないの?」と食ってかかっている客がいたのだが、奇しくも喜多八師本人がこの本の中でその「答え」を語っている。
「でもほんとうは、トリというのは格好をつけなきゃいけないのよ。見栄をはらないとね。(中略)前にどんな噺が出てきても、それにかぶらないネタは持ってるぞ、と。まあ、ハッタリというか、見栄というか」(118頁)
つまりは、噺家の「美学」ってことですね。
他に、芸人という立場からお客さんについて語っている「噺家の了見、お客さまの了見」も面白い。個人的には、それがライブである以上よりよい芸と出会いたければ「よい客」になるのが早道とかんがえるので、ここに語られている内容はいろいろ参考にもなった。なかには、
「ツイッターとかブログとか、個人の自由だからいいんですけど、責任とらなくていいのに発言できることを知っちゃったでしょ?
憶測でものを書くくせに記名制じゃないから、責任をとらない」(喬太郎師)
などという辛口の意見も。そういう「無責任」な発言が勝手にひとり歩きしてゆくのがインターネットの世界であるというのは飲食店をやっている人間として身にしみて知っているだけに、まったく同感。発言することが問題なのではなく、匿名で、責任をとる必要のない環境で言いたいことだけ言う風潮が問題なのですよね、つまり。
藤井宗哲『寄席―よもやま話』
2012.9.6|review
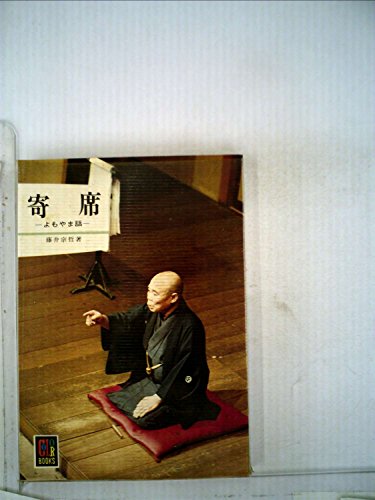
ときに「浮世の学問所」とも呼ばれる「寄席」という場所にスポットをあてた興味深い一冊。
著者は寄席で、「江戸や明治のころの職人や、武士や、さまざまな人たちの考えかた、生活ぶりなどの知識を得た」ばかりではなく、それらを通じて「人間として生きてゆくうえでの価値判断、そういったことまで教わりました」と語る(「はじめに」)。それはおそらく、いまもむかしも変わらないのではないだろうか?
ただノスタルジーをかきたてられる場所というだけでは、三百年以上も「寄席」は生き残れなかったろう。
カラーブックスらしく、寄席や寄席を支える人々の姿、そこに登場する芸人たちの表情、客のたたずまいなど興味深い写真も多数。だが、それ以上に興味深かったのは『醒睡笑』に始まり、上方、江戸における「中興の祖」たちの存在、そして三遊亭円朝から現代へと至る落語の変遷を、色物もまじえつつ「寄席」という場所が形成されてきた歴史としてまとめた巻末の解説文。たとえば、いまでも頻繁に口演される「野ざらし」という有名な落語が、明治期に活躍した三遊亭円遊によって現在のような滑稽噺として改作されたのはよく知られるところだが、そこには円遊なりのやむにやまれぬ「事情」があったことなど、この一文を介して知ることができた。
純愛もの?としての「不動坊」という噺
2012.11.11|rakugo
鈴本演芸場で、林家たい平師匠の「不動坊」を聴く。
「不動坊」という噺を聴いたのは、これが二回目。最初聴いたときには、後半のスラップスティックコメディー的な展開に「バカバカしい噺」という印象しか持たなかったのだけれど、なんだか今回はちょっとツボがちがった。ただこれはたい平師匠の演じ方というよりも、自分の心持ちのせいだろうと思う。
「不動坊」は、いい噺だ。「純愛」である。
長屋の大家さんとのやりとりにはじまり、長いあいだ思いを寄せていた未亡人「お滝さん」との縁談をもちかけられた吉兵衛のテンションが振り切れて妄想が爆発する前半も、たしかにバカバカしいことこのうえない。しかし、お滝さんの夫で講釈師の「不動坊火焔」が巡業先で客死したことを聞いた吉兵衛が驚きつつも大家に漏らすこんな言葉が、なかなかいい。
「お滝さんは、なにを隠そうあっしのおかみさんなんですよ、三年前っから」
いきなりなにを言い出すんだ? この男は…… と呆れる大家に、こう説明する。三年前、長屋に引っ越してきたお滝さんにすっかり一目惚れしてしまった吉兵衛。頭の中は寝ても覚めてもお滝さんワールド、恋煩いである。悩んで悩み抜いたあげく思いついたのは、「しばし、自分のおかみさんであるお滝さんを不動坊に貸してやってるのだ」と思い込むという案。身勝手である。身勝手にはちがいないが、まあ、誰にも迷惑はかけていないのでいいのである。じっさい、吉兵衛はこの「エアーおかみさん」ことお滝さんを思って仕事に精を出し、小金も蓄える。そんな吉兵衛の《真面目さ》を知っているからこそ、大家はお滝さんに吉兵衛との再婚をすすめ、お滝さんも「吉兵衛さんとなら……」と応えるのである。
「じゃあ、不動坊からお滝さんを返してもらおう!!」
ここに、奇跡が起こった。とはいえ、たんなる偶然のいたずらではなく、はたから見れば身勝手でバカバカしい妄想でも本人にとっては大真面目というふるまいがサヨナラ逆転満塁ホームラン的に恋愛を成就させてしまうところにこの噺の古きよきハリウッド映画的な心地よさがあるのではないか?
後半はご存知のとおり、ヤキモチから「長屋のアイドル」お滝さんを奪還しようと「お化け騒動」を仕掛ける三人組+万年前座の噺家によるドタバタ劇へと発展するのだが、その失敗は目にみえて明らかだ。だって、吉兵衛とは「了見」がちがうんだもん。
スラップスティックコメディー的な爆笑よりも、むしろ個人的にはこの「不動坊」という噺、吉兵衛のまっすぐな、ときにまっすぐ過ぎる一途な思いを祝福したいそんな噺といえる。
柳家小里ん『五代目小さん芸語録』
2012.11.15|review
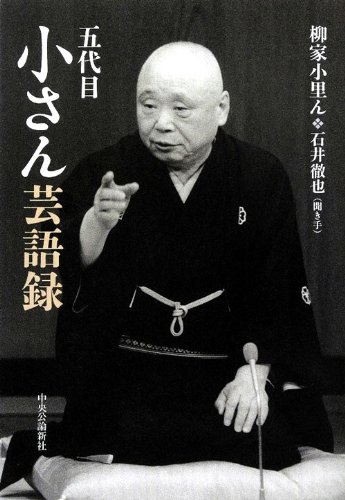
「落語は季節感と情景と人物が描ければ自然に面白くなる」「無駄なことは絶対に言うな」……。
この本は、五代目小さんの内弟子として、師匠の高座のみならずその「ことば」に数多く接してきた柳家小里んへのインタビューを通じて、五代目小さんの「芸」の精髄を後世に伝えるべくまとめようと試みた意欲作。
小さんがたびたび高座にかけた噺54席について、
①その噺の「型」がどこから伝わってのか?
②五代目を介してどのように広まっていったか?
③それぞれの噺の「勘所」はどこにあるのか?
を探ってゆく。五代目小さんについていえば、一般には芸談をあまりしないと思われていたというが、弟子が直接もしくは間接的に耳にしたその「ことば」は、簡潔でありながら物事の胸ぐらを瞬時にとらえるような迫力にみちていて、まさに噺の「急所」といったところ。落語を聴きこめば聴きこむほどに味わいを増す一冊といえそう。
「落語は大衆芸能じゃない。落語を本当に好きな奴のもんだ。大衆に合わせると落語のよさはなくなるよ」。コンビニとファミレスだけの世界なんて、たしかに便利にはちがいないが味気ないよね。
柳家花緑『落語家はなぜ噺を忘れないのか』
2013.1.28|review

噺が身についているから、落語家は噺を忘れない。
その「さおだけ屋はなぜ潰れないのか」的なタイトルから、《落語家が明かすマル秘暗記術》のような内容を期待するときっと肩すかしを食うだろう。落語家が噺を忘れないのは、ただ台詞を暗記しているだけではなく「立体的に」覚えているからだと著者は言う。それが「噺が身につく」ということであり、それはただただ稽古の賜物でしかない。ではいったい、落語家は噺を身につけるためにどんな具合に稽古を重ねているのか?この本の「肝」は、そこにある。
個人的には、花緑師が演じる『笠碁』がいままで聴いた誰の『笠碁』とも違うため、いったいその「型」がどこからやってきたのか知りたくて手にしたため、最後まで興味深く読むことができた(第4章「自分のネタを作る〜『笠碁』への挑戦」が、そのまま花緑版『笠碁』の誕生秘話(?)となっている)。これを読んで、花緑版の『笠碁』が、いわば伸び縮みする「時間」感覚という視点から再構築されたものであることがなるほど、よくわかった。ただ、「時間」という視点なら、従来どおりのサゲでもけっして矛盾はしないようにも思うのだけど。水滴が落ちてくるのも忘れて笠をかぶったまま碁盤にかじりつくおじいちゃんの大人げない様子から、碁を打とうにも相手がいない、そんな「待った」の日々の長さが手に取るように伝わってくるから。
落語家はどのようにして噺を自分のものにするか。落語好きなら読んで損はない、落語家の「了見」がよく伝わる一冊。
柳家小満ん『べけんや』
2013.2.23|review
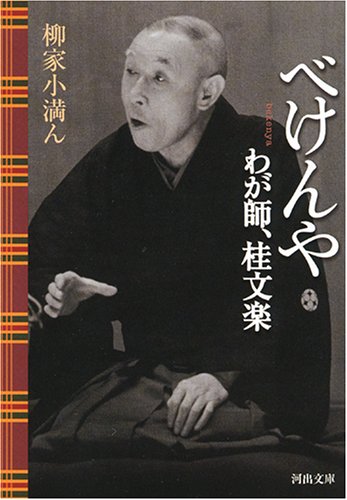
たとえば、第3章「師匠の食事」。
なんて「美しい」朝食なのだろう。名人・八代目桂文楽の「芸」から受ける ─端正、緻密、モダン、色気─ といった印象のすべてが、毎朝「黒門町」の長屋で繰り返される、さながら「儀式」のようなその食事風景からも同じように感じられたのは驚きである反面、また当然のような気もした。まさにその「人」こそが「芸」そのものであり、そういう生き方が許された時代、いわば「巨匠の時代」の芸術家なのだろう(その点で、「修業中の弟子の目からみた師匠」という切り口は同じでも、立川談春の『赤めだか』とは決定的にちがっているように思われる)。
その意味で、この『べけんや』に綴られた桂文楽というひとのことばや振る舞いは、その芸をより深く理解する上で役に立つことはあっても、けっして邪魔になるということはないように思う。
また、「伝説」ともいえる「勉強し直してまいります」というよく知られる台詞がとっさに口をついて出た文句ではないと知るとき、文楽というひとの「引き際」に対する美意識に感心するとともに、その、自身をみつめるまなざしの峻厳さには凄みすら感じる。師匠の死後、著者(柳家小満ん)が五代目小さんの元に引き取られることになった経緯なども静かに感動的なエピソード。
三遊亭円朝『三遊亭円朝探偵小説選』
2013.4.3|review
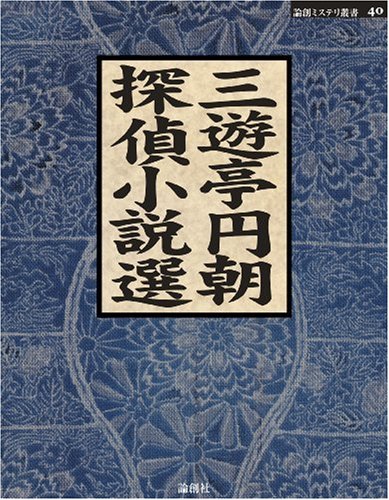
「落語中興の祖」三遊亭円朝が「翻案」を手がけたミステリ(あるいはサスペンス)仕立ての物語5編を収めたアンソロジー。
円朝といえば「真景累ヶ淵」「鰍沢」「死神」「怪談牡丹燈籠」といった名作落語の作者として、また円山応挙をはじめとした幽霊画のコレクターとして知られる大名人であるが、ここでは翻訳ではなく翻案というとおり、モーパッサン『親殺し』(→『指物師名人長二』)などの海外文学を人づてに聞き知った円朝が、同時代の市井の人々にも理解しやすいよう舞台や登場人物を日本に移し、また言文一致体に直すと同時に、部分的に原典にはないシーンや人物を登場させることでよりテンションの高い作品にまで磨き上げた珠玉の《創作》作品が取り上げられている。
収録されているのは、
『英国考子ジョージスミス之伝』
『松の操美人の生埋』
『黄薔薇』
『雨夜の引窓』
『指物師名人長二』
の5作品。表題には「探偵小説」とあるがべつに誰かしら「探偵」が登場し謎解きをするわけではなく、どれもどちらかといえば「ミステリ的要素、あるいはサスペンス的要素の強い人情噺」といった趣きである。
円朝というひとはつくづくモダニストであったのだと、ところで、このアンソロジーを読むとよくわかる。ひとつには、やむにやまれぬ事情があったといはいえ芝居噺の世界を離れ、扇子と手ぬぐいのみであとは「ことば」の力だけによる素噺へと転向、近代落語のひとつのスタイルを築き上げた改革者であるという点で。もうひとつには、みずから江戸時代に生まれ江戸の美学を貫くことに執心しつつも、明治維新後の近代国家の礎を築いた思想家や文学者などと積極的に交わることで、異文化をどん欲にみずからの「芸」に吸収していったという点で。円朝による《翻案》のプロセスについては、それが比較的明らかな「指物師名人長二」についての考察「『名人長二になる迄』〜翻案の経路」が余録として収められているので、それを読むと面白いと思う。
江戸から明治へ、その移り変わりを「激動の時代」と呼んで片付けてしまうことはかんたんだが、実際そこに居合わせた人々にとってはとても容易には受け容れがたい、しかし差し迫った大問題であったにちがいない。思うに、この《翻案》という作業は三遊亭円朝にとって、「落語」という芸を「要」として、江戸と明治というふたつの時代を結びあわせ、乗り越え、受容するためのひとつの試みだったのではないか。その意味で、円朝はその翻案物を通じて同時代の、同じ境遇を生きる市井の人たちのための「水先案内人」をみずから買って出たのだ、とぼくはなんとなくかんがえずにはいられない。心やさしき名人の姿がそこにある。
矢野誠一『落語家の居場所―わが愛する芸人たち』
2013.6.16|review

トラウマ?
はたまたナントカ症候群?
運よく「巨匠の時代」に居合わせてしまったがために、その後ずっと食い足りない気分を抱えながら過ごさざるを得ないこういう《不運》のことをはたしてなんと呼ぶべきか?
この『落語家の居場所』という本について、志ん生や文楽、圓生ら往年の「巨匠」たちと身近に接してきた筆者は、「むかしほど落語にのめりこむことのできないでいる自分」を発見し、それでも断じて「團十郎爺い」にはなりたくないと抵抗をみせながらも、けっきょくは「世紀末落語論」をめざしたつもりが「『よき時代の落語讃歌』にかたちを変えてしまった気味がある」と告白する。
とはいえ、この本からは年寄りの昔話に付き合わされたようなうっとうしさはほとんど感じられない。ひとつには、それは筆者が過去と現在とを比較するような書き方を意識的に避けているからだろうし、もうひとつには、現在にも通じるや寄席の「気分」といったものが、さながらRPGの「アイテム」のようにこの本の随所に隠されて(?)いて、そのつどいろいろなことにあらためて気づかされるからではないか。
「つまり、ふだん着で、ふだん使っているものを手にして、ふだんの声で、ふだんの言葉ではなすのが、落語なのである」(「古今亭志ん生の執念」)
これからの新作落語について。三遊亭圓歌の「中沢家の人々」や林家木久蔵(現木久扇)を引き合いに出しながら(風俗描写やナンセンスな状況ばかりにたよらない)「ますますパーソナルな色彩を加えていくような気がする」(「寄席」94.2.16)
三代目小さんと圓遊についての夏目漱石による評をとりあげ、小さんの方を持ち上げるのは漱石が「なにより江戸趣味のひと」だっかからと指摘、むしろ「新しい時代にふさわしい感覚」にあふれていたのは圓遊の方であった(「世紀末落語論」)
今日の落語を取り巻く状況について、聴衆をふくめた当事者たちのその危機感の薄さは四半世紀前とまったく変わっていないと指摘する一方で、そのぬるま湯につかっているような居心地のよさがかえって「激しい世の移り変わりという時間の流れのなかで、少しも動かない静かな時間をつくり出していたことに、じつは最近になってやっと気づいた」(「世紀末落語論」)
生涯つつましい長屋暮らしを通したことで知られる彦六の正蔵師匠に、反面、コーヒーは自分で挽いた豆をサイフォンでたて、食堂車でオートミールの食べ方を著者に得意げに教授し、「落語家のなかでホームスパンのジャケットを最初に着」るようなモダンな横顔があったことをはじめて知った。へぇ〜(「林家正藏の反骨精神」)
その他にも落語好きには刺激的なエピソードや指摘が多数。
橘蓮二『カメラを持った前座さん』
2013.8.28|review
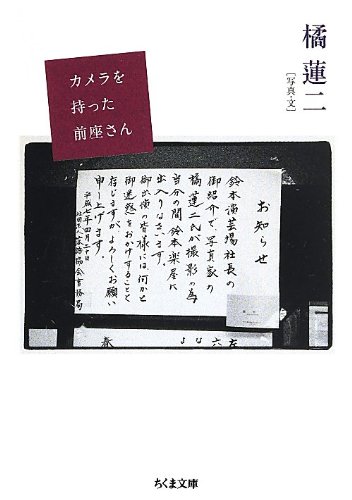
まさに「決定的瞬間ならぬ演芸的瞬間」!
時間調整のために入った本屋さんで、たまたま手にとりパラパラめくったが最後、そのままレジへ直行。よっぽどのことがないと、ふだん写真集は買わないんだけどなァ……。
ここで被写体となっている噺家の姿から伝わってくるのは、落語が、〝没入〟と〝俯瞰〟のギリギリの均衡の上に初めて成立する至芸であるということ。その所作は即興などではなく、練って練って、練り上げられてできたカタチなのだというのが手に取るようにわかる。その意味でも、オフショットではなく、高座での写真が多いのもうれしい。木之下晃が撮影した演奏家の写真からそのひとの音がきこえてくるように、橘蓮二というひとの写真からもまた、たしかに、そのひとの声がきこえてくるからだ。
「橘蓮二は十八年前、演芸に救われた写真家です」というあとがきの一節に集約されるような、それぞれの芸人に寄せたエピソードも淡々としているぶん、余計に心にしみる。いい買い物をしました。
【落語メモ】萬橘師匠の「田能久」
2013.9.7|rakugo
三遊亭萬橘師匠で「田能久(たのきゅう)」をきいた(あらすじ→「落語400文字ストーリー」様)。萬橘師は、〝親孝行〟というよりも、〝久兵衛が一人前の役者になるべく肚を決める〟までのドラマにフォーカスする。そして結果、それが〝親孝行〟につながる。〝親孝行〟はどちらかといえばオマケなのである。
役者になることを決意した倅に、反対するかわり、「田畑は売ってしまうがそれでかまわないか?」と覚悟を迫る母親も、とっさにカツラをつけて女や坊主に〝化けた〟久兵衛に対し、感心するかわりに、「上手く化けたつもりかもしれないが了見がなってない」とアドバイス(?)するうわばみ(大蛇)も、結果的には久兵衛が一人前の役者になるべく〝肚を決める〟後押しとなる。そもそも、巡業先から郷里にあわてて帰るきっかけとなる「母が急病」との手紙も、萬橘バージョンでは、他の役者に人気を持ってゆかれたことでくさった久兵衛による〝自作自演〟という趣向。
最後、うわばみが久兵衛にむかって千両箱(大金)を投げつけるのは、肚を決めた久兵衛がその後ますます芸道に精進した結果、成功して大金持ちになったことをあらわしているのだろうか。「独演会」とは銘打ってあるものの、実質的には「勉強会」というスタンスなのか、手探りの口演ではあったけれど(ネタおろし?)、いずれ、よりブラッシュアップされた〝萬橘版「田能久」〟をきける日が楽しみである。
広瀬和生『落語評論はなぜ役に立たないのか』
2013.10.30|review

「BURRN!」編集長として音楽評論の世界に携わってきた著者が、落語評論家としてのみずからのアティチュードをまとめた一冊。
ここで著者は、落語の本質を「同時代の観客の前で演者が語る芸能」としたうえで、評論家とは「ツウの客」「最も良い客」であろうとすることで「演者」と「客」の中間に位置する「媒介」として、客の側に語りかける者、いわば「水先案内人」のうような存在であるとする。それゆえ入門者に対しては、歴史でもあらすじでもなく、まず同時代の「誰を聴けばいいか」という情報を提供することこそが評論家の役割ということになる。そしてこうした立場から生まれたのが、著者の『この落語家を聴け!』(2008年、集英社文庫)である。ここでも、最後に特別付録として「『落語家』『この一席』私的ランキング2010」が収められており、本編と付録とで一応は(というのは、本人がこれは「落語ファンとしての2010年の総括であって「決して『お薦めの落語家』のガイドではない」とわざわざ断っているので)「理論と実践」のような構成がとられている。
「なぜ知っている噺を何度聞いても面白いのか?」「『ネタバレ』で問題無し」「マクラの意味」など、落語初級者にとって興味をそそられる内容もすくなくない。
広瀬和生『談志の十八番:必聴!名演・名盤ガイド』
2014.2.17|review

クラシック初心者がいきなりフルトヴェングラーに手を出すのがキケンなように、落語初心者がいきなり立川談志に手を出すのはマズいのではないか?
そんな直観から、なんとなくずっと遠ざけてきた談志の落語。正直、まだまだ手を出す気にはなれていないが、いつか「その日」がやってくるであろうことは間違いない。「その日」に備えて、この本を手に取ってみた。
この本では、談志の「追っかけ」を自称する著者が、談志の手がけた数多い噺の中から誰もが認める得意の大ネタ10個(「鼠穴」「居残り」「芝浜」など)に加え、古典落語、談志ならではの噺、滑稽話、その他というカテゴリーから8個ずつの計42個をピックアップ、世に出ている音源をもとに詳細に比較しその特徴を挙げることで、絶えず更新され続ける談志落語の魅力について紹介してゆく。
談志ビギナーにとっては、どのあたりから手を付けるかということの大まかな「地図」になるし、ある程度すでに触れてきたひとにとってはまだまだ未知の領域があることを知るきっかけになるのではないだろうか。
五街道雲助『雲助、悪名一代 芸人流、成り下がりの粋』
2014.3.1|review

雲助師匠は、ぼくの中でちょっと〝ふしぎ〟な存在だ。他の噺家があまりやらない根多を持っていたり、他人から稽古をつけてもらわないという逸話もどこかで耳にした記憶がある。そういえば、二ツ目時代にはイラストレーター和田誠氏による新作落語も口演していたはず。〝一匹狼〟とでも言うのだろうか。さてさて、いったいどんな人物なのだろう?
そんな単純な興味を胸に読み始めた。
結果、ますますその〝ふしぎさ〟に輪が掛かったように思える。生まれ育った本所での暮らしぶり。情熱を傾ける対象をみつけると一気に燃え上がる青年時代のエピソード。十代目馬生の一門に身を置くことになったいきさつ。大師匠・志ん生の思い出や志ん朝一門に対する思い。古い速記本から根多を広げてゆくようになった背景には、師匠を失った孤独と同時に反骨精神も感じられる。また、入り浸っていたという浅草のハチャメチャな居酒屋の思い出や野坂昭如ら酒場で出会った人々との交友録からは、雲助師の意外な素顔も垣間見ることができ興味深い。
文中、みずからの生き様を称してたびたび言われる「成り下がり」という言葉については、その名前にふさわしく「雲」の如くひとところにとどまらず、自由に芸人としての一生をまっとうしたいという、雲助師による反ストイシズム宣言(?)と受け取った。
長井好弘『新宿末広亭のネタ帳』
2014.4.7|review

落語家という仕事が、寄席という場所が、新宿末廣亭のネタ帳(=寄席の「セトリ」)7年分を紐解くことで見えてくる。
毎日20人を超える芸人が登場する寄席。よって、ひとりあたりの持ち時間はせいぜい15分といったところ。その短い出番に、誰がどんなネタを掛けたのかを淡々と書き留めたものが寄席の「ネタ帳」である。
「我々の商売は、15分座って独り言を喋ったらそれで業務終了」とは瀧川鯉昇師のマクラだが、そのわずか15分の出番のために、落語家は「ネタ帳」でその日すでにどんなネタが掛かっているのかを確認し、噺が重複しないよう、全体の流れを損なわないよう配慮した上でみずからの高座に挑む。つまり、それなくしては寄席という場じたいが成立しないくらい重要な、いわば《羅針盤》、それが寄席にとっての「ネタ帳」なのだ。
寄席はまた、落語家にとって大切な修練の場でもある。長い噺をエッセンスはそのままに寄席で演じられるサイズにまで刈り込む創意工夫、演じなれたネタにさらなる磨きをかけるための試行錯誤、それらは寄席という《ホーム》なくしてはなしえないと、インタビューに答える噺家たちは異口同音に語る。なかには、そうした日々の鍛錬の積み重ねから、寄席専用の「勝負」ネタを編み出した落語家も。
寄席を出るとき、思わず「あぁ、楽しかった」と口に出るのは、芸人ひとりひとりのネタよりも、むしろ全体の流れ(グルーヴ)が気持ちよかった日であることを、この本を読みながらあらためて思い出した。
橘蓮二『この芸人に会いたい』
2014.7.9|review
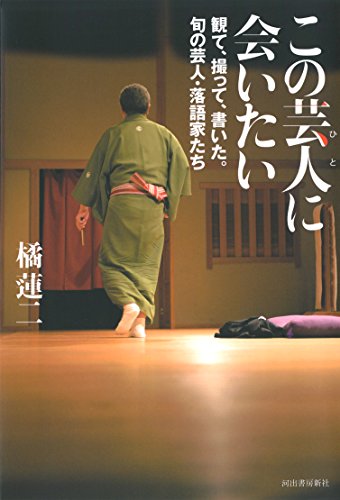
まるで、豪華な顔付けの「寄席」に出くわしたかのような満足感を得られる写真エッセイ。
開口一番に登場するのは、小三治師の弟子のなかでも若手真打ちの筆頭格、柳家三三師。本番前、高まる集中力の中まったくカメラの存在を意識していないかのような張りつめた表情、一転、高座の上での弾けるような活きのよさが印象的だ。
成城ホールで撮影された立川こしら師、鈴々舎馬るこさん、そして三遊亭萬橘師の3人会。馬るこさんのNHK新人演芸大賞受賞後のお祝いモード全開のこの日、こしら師がつけている「どくろ」紋の帯はポッドキャストで馬るこさんがプレゼントしていたものだなぁ。じんわりと感動。
既刊の『カメラをもった前座さん』でも思ったことだが、ぼくは個人的に橘さんが撮影した市馬師匠が好きだ。せせこましいところの一切ないゆったりとした高座が魅力的な師匠だが、被写体としての市馬師はこんなにも表情豊かなんだなぁ。
色物さんも多数。必殺仕事人の決定的瞬間がばっちり捉えられている。ふだんは見ることのできない寄席のお囃子さんたちの表情も新鮮。
そして、この本でトリに登場するのは柳家小三治師。「小三治師匠の高座は、ただ感じること。その一言に尽きる」。まさしくその通り。そしてそれは、写真を観るときの「作法」にもまた通じているのでは?
あ、そうか、だから小三治師がトリなのか。
長井好弘『新宿末広亭―春夏秋冬「定点観測」』
2014.10.29|review

タイトルにあるように、1999年5月下席から2000年5月中席までの一年間、新宿末広亭に足を運んでの「定点観測」がこの一冊のテーマである。
読んで感じるのは「寄席は生きもの」ということ。お客さん、演者、天候……
さまざまな要素の組み合わせいかんによって寄席の表情もくるくる変わる。著者が通いつめた時期が、いわゆる「落語ブーム」前夜のもっともゆるみきった時代であったのも、逆に「寄席」が主役の読み物としてはかえっておもしろい。たとえば、いま2014年におなじことを試したとしても、こんな空気感は出ないのではないかなぁ。結果的に、ある意味しっかり「時代」を切り取ってしまっているところが興味深い。
『古今亭志ん朝』河出書房新社編集部
2014.10.29|review
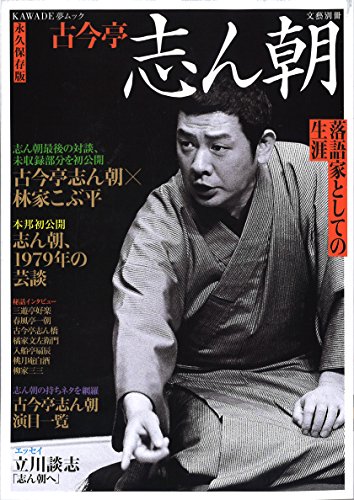
本人による芸談、対談、志ん朝に縁のある、また志ん朝を愛する人物によるエッセイ、後輩芸人たちへのインタビューからなるアンソロジー。掲載されたインタビュー等の大半は石井徹也氏がおこなっている。資料として演目一覧も所収。
読み進めてゆくうちに、いくつかのキーワードが浮上。
◎ 黒門町
いわずと知れた八代目桂文楽。独自の美意識に貫かれ、磨き上げれた楷書の「芸」。若き志ん朝は、みずからの範をこの黒門町にしていたようである。父として、師匠として、草書の「芸」の巨人、志ん生を身近に見ていたため、逆方向に突き進んでいったようだ。談志いわく、よくもわるくも「作品派」。
◎ くどさ
あるいは、わかりやすさ。芝居が好きで、役者をめざしたほどの人ゆえ、客席からみたときのわかりやすさ、イメージの共有を徹頭徹尾考え抜いたひとであったようだ。たしかに、説明調でありくどいのだが、聴いているときにはあまりそれを意識させないのは志ん朝の生まれ持った「芸品」のなせる技なのではないか。
◎ 太陽
「志ん朝師匠と関わりを持ったことがある人は、師匠のことを話すとき、本当にうれしそうな顔をする」と編集後記にあるように、後輩芸人たちのインタビューはしばしば志ん朝のことを「太陽のようなひと」と語り、しくじったときの経験までもうれしそうに語っている。
志ん朝の人となりを知るにつけ、落語の世界をあっという間に吹き抜けた一陣の、爽やかな風のように思う。
岡崎誠『かまくら落語会―いまから昔から』
2014.11.4|review
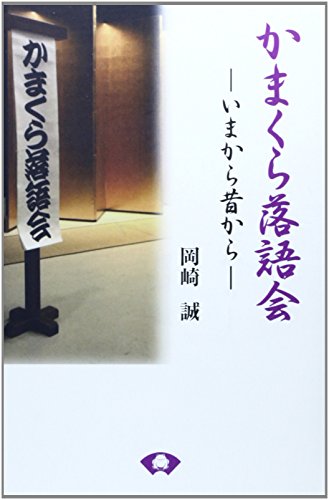
昭和47年にスタートした地域寄席の老舗「かまくら落語会」。その代表世話人を引き継ぎ、26年間あまり運営に携わってきた人物による貴重な記録。
著者の岡崎氏は本職が物理学者ということもあり、過去の資料を引きながらの叙述は読み物としてのおもしろおかしさには欠ける反面、出演した噺家とのやりとりや失敗談も含め感傷を排し事実のみを綴る「実直さ」に世話人としての人柄や落語会の会員に対する思いが感じ取られる。
地域寄席の貴重なドキュメントであるとともに、世話人とお客様、そして演者の三位一体によってつくられてきた歴史の重みに敬意を表したくなる。
6/2 国立演芸場6月上席【寄席おぼえがき】
2015.6.8|rakugo
思いのほか用事が早く片付いたので、隼町の国立演芸場まで足をのばしてみる。6月上席は現「落語協会会長」にして「日本歌手協会会員」、柳亭市馬師匠が主任。渋めながらも、ゆったり寄席の雰囲気を味わうにはなかなかいい顔付けである。ちょうど、開口一番の圭花さんが高座に上がったところで着席。いっしょうけんめい寄席に通いはじめた頃よくみかけた前座さんだが、噺を聴くのはひさしぶり。「一目上がり」。ずいぶん腕を上げたなぁ(上から目線でスミマセン)と思って調べたら、もう来春には二つ目昇進という香盤だった。
市楽さんの明るい高座につづいて、百栄ちゃん登場。きょうはなんとなく「寿司屋水滸伝」が聴きたい心持ちだったのだが、いつものマクラから入ったのは自作の「誘拐家族」。いっときはあんなに「寿司屋水滸伝」が続いたのに、聴きたいと思うとなぜか遭遇しない不思議。思春期の子供をもつ家庭ならどこにもありそうな状況設定、間の抜けた悪人、いつのまにか立場逆転…… いわゆる「新作」だが、目先のギャグに走ることなく〝落語らしさ〟をきっちり押さえている。現代が舞台でも、だからただの「お笑い」にはならない。やっぱりそこは「落語」なのだ。
自由自在にピアニカとリコーダーをあやつる「のだゆき」の音楽パフォーマンス、縁がなかったのだがようやく観れた。笑いで(お客様を)掴んで、芸で感心させる。のだゆきさんもそうだが、若手の色物さんはみな構成の巧みさで際立つ。
ふつうに演っても、そもそも「落語」はおもしろい。ぼくは、そう思う。でも、ちょっとした「間」やしぐさ、表情が加わるとき、さらに、ものすごくおもしろくなる。一九師匠の「桃太郎」に食い足りなさを感じてしまったのは、あるいはそのあたりに原因があるのかも…… そんなことを考えているうち、気づけばあっという間に仲入り前。いちど寄席で聴いてみたかった桂南喬師匠。
三代目金馬師匠の弟子もいまとなっては貴重……なのかな? もしかしたら当代と、あとは南喬師だけ? 落語を聴きはじめた当初、とにかくお世話になったのは志ん朝と先代金馬の音源だった。そんなことをふと思い出す。ネタは「鰻屋」。往来の真ん中で、ぼんやり西日に照らされて突っ立っている友だちをみつけた男が、「ご馳走してやる」と飲みに誘う。ところがこの友だち、せっかくの誘いにもかかわらず行きたくないという。聞けば、このあいだ、やはり別の友だちに誘われてひょいひょいついていったはいいが、ひどい目に遭ったらしい。そのエピソードを、「しょーもねぇーなぁ」とときに面白がりながら、ときにダメだししながら聞く男。しっかり者の兄貴分なのだ。お人好しでぼんやりした友人は、どうやらいたずら好きで小賢しいべつの友人にからかわれたらしい。南喬師の噺から、男3人ののんきな人間関係が浮かび上がる。「鰻屋」に行くと、主人が暖簾から顔をキョキョロのぞかせて職人の帰りを待っている。主人の様子がすでにウナギである。だいたい、ウナギに名前をつけて可愛がるとか、もはや「アンタ鰻屋に向かないよ」と忠告したいレベル……。〝士族の商法〟が身近だった時代ならいざ知らず、個人的には、いま聴いて面白いのは断然「素人鰻」より「鰻屋」かもしれない。
仲入りのとき、劇場の係から「鈴をお持ちのお客様は、かばんの中にしまって下さい」との声掛けがある。高座中、ずっとカラカラと鈴を鳴らしている客がいたので、実際のところはピンポイントの注意だったわけだが、とたんに会場のあちらこちらから鈴の音が鳴りだしたのには驚いた。まさか「熊除け」ということもないだろうし。「おばさんはなぜ声に出してメニューを読みたがるのか?」という日頃から抱いている身近な疑問リストにもうひとつ、「おばさんはなぜ持ち物に鈴をつけたがるのか?」というのも加えておこう。
さて、食いつきはダーク広和先生。出し物が日本の古い奇術だったからだろうか、いつもはスーツ姿なのにきょうは派手な袴姿で登場。ダーク先生の、こういう細かすぎてかえって伝わりにくい(?)こだわり、じつはけっこう好きだったりする。勝手に脚が飛び出す、DIY感覚あふれるテーブルとか。そういえば、ブログを拝見したところダーク先生はかなりのコーヒー通。しかも、生豆をハンドピックして自家焙煎したり、コーヒーの木を栽培したりと本格的だ。つくづく凝り性なのだ。泡坂妻夫の『11枚のとらんぷ』を読んだとき、まっさきに思い浮かんだのはダーク先生の姿だった。ヒザ前は、〝幻の噺家〟として有名(?)な小のぶ師匠。てっきり堀井憲一郎さんがつけた惹句かと思いきや、一時期、ご本人みずからそう名乗っていらっしゃったらしい(『青い空、白い雲、しゅーっという落語』)。最近ではすっかり寄席の出番も増え、それどころかトリを勤めるほどの活躍ぶり。さほど〝幻〟でもなくなったが、それはきっとよいことなのだろう。ありがちな粗忽者の小咄ではなく、「行き倒れ」についての詳しい解説からの「粗忽長屋」。小のぶ師匠の高座は2度目だが、大きなしぐさ、間、スピード、なんともいえない独特の〝おかしみ〟が特徴的。昭和こいる・あした順子先生のユルい笑いの後は、いよいよトリを勤める市馬師匠の登場である。
〝さんぼう〟(どろぼう、つんぼう、けちんぼう)のマクラから「片棒」に入る。ケチで有名なある商家の大旦那、食うものも食わずお金を貯め込んだはいいが、そろそろ息子に身代を譲ろうと思い立つ。しかし、譲るにあたってはできるだけ自分と金銭感覚が近いほうがいい。そこで、3人いる倅を呼びつけ、もし自分が死んだらどんなお弔いを出すか? と尋ねてそれぞれの金銭感覚をはかろうと試みるのだが……。派手好きの長男に祭好きの次男、「だめだこりゃ」とは言わないが、ドリフターズでおなじみ「もしものコーナー」である。あきれかえる父親の前に、最後に現れたのが末っ子の鉄三郎。兄貴たちとは違い、〝質素〟な弔いにするという鉄三郎。それを聞き、よろこぶ親父。ところが、チベット式のお弔い(鳥葬)、フライング出棺、菜漬けの樽などなど、鉄三郎の〝質素〟はもはや大気圏に届かんがばかりの〝ファンタジー〟。当然「だめだこりゃ」となる筈なのに、なぜか身を乗り出してくる父親の様子がおかしくも、哀れ。ご自慢の美声で木遣りから祭り囃子、ついには美空ひばりまで飛び出す、客席も大喜びの「鉄板ネタ」であった。
そしてあらためて、市馬師匠の噺に身をあずけているときの、なんともいえない心地よさについて。〝巧い〟とか〝おもしろい〟というよりも、ふわーっとしてなんだかとても〝気持ちいい〟のだ。半年に一回くらい、ものすごく市馬師匠の高座が恋しくなるのもきっとそのせいだろう。じっさいのところ、半年に一回くらい市馬師匠がトリを勤める寄席に足を運んでいる。さて、つぎは年末、「掛け取り」でも。
──
6/2 国立演芸場 6月上席
開口一番 柳家圭花「一目上がり」
◎ 柳亭市楽「強情灸」
◎ 春風亭百栄「誘拐家族」
◎ のだゆき(音楽パフォーマンス)
◎ 柳家一九「桃太郎」
◎ 桂南喬「鰻屋」
〜仲入り〜
◎ ダーク広和(奇術)
◎ 柳家小のぶ「粗忽長屋」
◎ 昭和こいる・あした順子(漫才)
◎ 柳亭市馬「片棒」
6/17池袋演芸場6月中席後半夜の部【寄席おぼえがき】
2015.6.24|rakugo
連雀亭で、夢吉さんご本人から披露目のチケットを購入したのが、あれはもう4ヶ月も前のことだったのだなァと遠い目になりながら池袋演芸場へ。バタバタの4ヶ月であった。先月の浅草につづき、真打昇進襲名披露興行は2回目である。もう1回、国立演芸場にも行くつもり。
断続的に土砂降りの雨が降る悪天候ながら、ざっと見渡したところ場内は7、8割の入り。トリを勤めた夢吉改メ2代目夢丸師匠は、マクラでご両親のエピソードをふってからの「明烏」。これはもう、今後の夢丸師匠の〝鉄板〟ネタになることまちがいなしの弾けっぷり。夢丸師匠は、ことさら現代的なクスグリで笑いをとろうというところはなく、かわりに登場人物の性格をデフォルメすることで〝モンスター〟に仕立ててしまう。結果、噺はファンタジーのように、SFのようになり、それに応じて〝滑稽さ〟もまた大波のようになって押し寄せてくるのだ。
勉強ばかりで世間を知らない倅の堅物ぶりもかなりなものだが、それにも増して、その倅になんとか人並みの遊びを覚えさせようとあれやこれやと腐心する父親のパッションがものすごい。だいたい近所の遊び人に金を渡し、息子をだまして吉原に連れてゆくよう手引きをする父親なんているはずない。だから、所詮この噺はファンタジーなのだ。そして、ファンタジーをファンタジーとしてキッパリ描き切ってこそ面白い。夢丸師匠の「明烏」は、そういう演出に思える。暴走する父親に対し、母親はというと、心配こそしているものの、そこまでは望んでいない。いい着物を出すよう夫に言われながら、モタモタして催促される台詞からそれがわかる。気が進まないのだ。真っ当。手引きを依頼されるふたりにしても、チンピラというよりは、遊び好きだが貧乏な町内の顔見知りという位置付け。ほどほどにワルではあるが、父親の「暴走」にあきれるだけの常識は持ちそなえている。つまり、息子と父親は、対極にあるとはいえ、その〝モンスターっぷり〟で似た者親子なのである。この図式をひっくり返すと、これを機に息子は落語によく登場する道楽者の若旦那にすっかり変身し、反対に、見かねた父親は頑固な堅物に変身してしまったなんていう〝後日談〟もできるかもしれない。帰り道、もう一回ニヤリとできる「明烏」。
ほかには、仲入りに小遊三師匠の代演で登場した鶴光師匠、そしてヒザ前の小柳枝師匠、ふたりのベテランがさすがの貫禄をみせた。鶴光師匠の「試し酒」は、酔うほどにボヤキっぽくなってしまいには主人にまでチクチクやりだすところが可笑しくってたまらない。大酒呑みの名前が「久蔵」ではなく「井上」なのは、誰かに引っ掛けていたのかな? さらーっと流しているようで、けっして薄口にならないのが小柳枝師匠の至芸。あの年齢にしてあのスピード感、そして「間」。どこが面白いとかうまく形容できないのだけれど、そこはかとなく面白い。〝旨味〟とでもいうか。とにかく、聴けるうちにたくさん聴いておきたい落語のひとりである。
ところで、歌丸師匠が腸閉塞が原因で入院されたとのこと。先月、板付きで高座に上がった歌丸師匠は、まるで上半身だけ座布団にのっているかのようにみえるほどの異常な痩せ方で幕があいた瞬間、仰天した。声には張りがあったので安心したのだけれど。適切な処置の下、一日も早く高座に復帰されますように。
──
2015年6月17日[水]
池袋演芸場 6月中席後半 夜の部
笑松改メ春風亭小柳
朝夢改メ三笑亭小夢
夢吉改メ二代目三笑亭夢丸
真打昇進襲名披露興行
開口一番 昇市「たらちね」
◎ 三笑亭可女次「魅惑のアジアンツアー」
◎ マグナム小林(バイオリン漫談)
◎ 三笑亭夢花「くどき武士」
◎ 春風亭柳之助「家見舞」※代演
◎ 松旭斉小天華(奇術)
◎ 雷門助六 小咄、あやつり踊り
◎ 笑福亭鶴光「試し酒」※代演
~仲入り~
真打昇進披露口上(下手より)
夢花(司会)、助六、夢丸、小夢、小柳、小柳枝、鶴光
◎ 三笑亭小夢「皿屋敷」
◎ 春風亭小柳「悋気の独楽」
◎ 春風亭小柳枝「新聞記事」
◎ やなぎ南玉(曲独楽)
◎ 三笑亭夢丸「明烏」
7/8国立演芸場7月中席【寄席おぼえがき】
2015.7.10|rakugo
遠くにある台風の影響か、ときおり大粒の雨がバラバラっと落ちてくる。ふだんなら、四ツ谷駅から麹町を抜けて国立演芸場のある隼町まで歩いてしまうところだが、怪しげな空模様に負け地下鉄で永田町まで。ところが、いまひとつJR四ツ谷駅の構造が頭に入っていないため、南北線への乗り換えに手間取ってしまう。余裕をもって出たつもりが、二番太鼓にうながされ、けっきょく汗の引くのを待つ間もなくいそいそと客席へ。
応援していた噺家が真打に昇進するというのは、こうも嬉しいものなのか。夢吉改メ二代目夢丸師匠の披露目に足を運ぶのも、浅草、池袋につづきこれで3回目。その〝目出度さ〟に便乗したい、そんな気分もある。そのうえ、きょうの顔付けは個人的にツボなので期待も大きい。
まず、開口一番に登場したのは今いちさん。初めて聴く前座さんである。落語協会とくらべると、落語芸術協会の前座さんたちは総じてフリーダムな印象があるけれど、どうやら新作派の方らしいこの今いちさんからもそんな印象を受ける。でも、噺のほうは「初天神」を手堅く。
ずっと気になっているのに、どういうわけかタイミングが合わずなかなか聴く機会に巡り会えない、そんな噺家が何人かいる。そのひとりが小痴楽さんだったのだが、ようやく聴けた。小痴楽さんは、二ツ目にしてすでに〝スタイル〟をもったひとである。それは、自分の個性をじゅうぶん理解した上で、その個性がより輝くようなネタを選んでいるからにちがいない。要は、〝センスがいい〟のだ。「強情灸」。その〝がらっぱち〟な雰囲気が、いかにも「江戸っ子らしい」。「いかにも…」というあたりがインチキ臭く、また可笑しい。「祇園祭」や「大工調べ」も得意としているようだが、さぞかし面白いにちがいない。
続いて、鯉橋師匠が高座にあがる。数年前、同じここ国立演芸場で真打昇進の披露目をみたのがなつかしい。「牛ほめ」。鯉橋師匠の与太郎は、とても愛らしい。父親から「ほめ言葉」を教わるときだって、ちゃんと真剣に覚えようとするのだ。とはいえ、最後には結局こんがらがっちゃうんだけれどね。ところで、この鯉橋師匠はじめ、芸協の若手はなかなかの層の厚さだ。ほかにも、小助六師匠、夢丸師匠、二ツ目だと小痴楽さん、宮治さん、前座で音助さん、鯉んさん…… もっと聴いてみたいと思わせる噺家が何人もいる。彼らにもっと出番が増えれば、寄席のお客さんもぐっと若返るんじゃないだろうか。
ウワサの東 京丸・京平師匠の漫才も初聞き。「ウワサの…」というのは、「ラジカントロプス2.0」というラジオ番組にナイツのふたりが出演したとき、このベテラン漫才師にまつわる抱腹絶倒のエピソードを披露していたからである。漫才を観ながら、いちいちそれを思い出して笑いが止まらなかったのだが、横で口の悪いおばちゃんが「なに、このヘタクソな漫才!」などとおもいっきりdisっていたので気が気でなかったです…。おばちゃんのご機嫌が直ったのは、入院中の歌丸師匠に代わって登場した文治師匠の「源平盛衰記」のおかげ。横目でのぞいたら、プログラムの文治の名前に大きく「◯」がつけられていた。「源平盛衰記」というと、まっさきに思い出すのはYouTubeでみた先代の三平師匠の高座。お客に、「このひとは一生懸命『源平〜』を語ろうとしてる」と信じさせてしまうところが三平師匠のクレバーなところである。必死に語ろうとしているのに、油断するとつい脱線しちゃう面白さ。「源平盛衰記」がそのじつ漫談でありながら、あくまで「源平盛衰記」であって「漫談」といわれないのは、ひとえにその点につきるのではないか。
賑やかな文治師匠の後は、五代目圓楽一門会会長の三遊亭好楽師匠が登場し、仲入りを勤めた。こういうおめでたい席では、芸が「化ける」ようにと縁起をかついでおばけの噺をしたりするというマクラから、「三年目」。鶴瓶師匠のときも思ったのだが、テレビで顔の売れている落語家はみんないい着物をきている。好楽師匠の着物も、素人の目にもわかるくらいすばらしかった。
仲入り後は、口上から。幕が開くと、下手より司会の夢花師、鯉橋師、文治師、夢丸師、小文治師、そして好楽師と並んでいる。これまでは、同時昇進の3名が一緒に並んだが、国立演芸場は日替わり出演のため夢丸師のみ。先代の夢丸師に可愛がられ、名跡を譲ることについても相談を受けたという好楽師が音頭を取って三本締め。
空を飛んだり、竜巻で一回転するアクロバティックな夢花師匠の「反対俥」の後は、より〝本寸法〟が際立つ(笑)小文治師匠の「親子酒」。かたちがきれいな噺家だ。演出が、よく聞き知っている「親子酒」とはずいぶんちがう。「ただいまかえりました」倅がしっかりしているのが面白い。しかし、それもつかのま、親父同様、気持ちとは裏腹に一気にグズグズになってしまうのだった。どこまでも似た者親子なのだ。ヒザは、ボンボンブラザーズのモダン太神楽。パントマイムをとりいれた繁二郎先生の動きが、もはやMr.ビーンにしか見えない…。余談だが、心臓の悪いひとはボンボン先生が出演されるとき、2〜4列目あたりに座ってしまうとキケンです(笑)。ぼくはいつも、どうしたわけかそのあたりに座ってしまい肝を冷やす。
トリは、夢吉改め二代目夢丸師匠。たくさんの「待ってました!」の声に照れながらの登場。お、「幾代餅」だ! メソメソした清蔵のキャラは、「明烏」の息子同様で夢丸師のお得意。清蔵と親方は、抱き合って男泣きしたりして、「職人と親方」というよりは、なんとなく「高校野球の選手と監督」のよう。
心に残ったのは、幾代太夫が清蔵に年季が明けたら女将さんにして欲しいと頼むとき、「あなたのおかみさんにして下さい」とわざわざ町人風の言葉遣いで言い直すところ。こうやって書いてしまうとクサいけど、「傾城に誠なし」といわれる世界に身を沈めながらも、なお幾代太夫が誠実な人物であり、またいかに誠実な人間を求めていたか、これからは町人としてつましく暮らしていきたいと願う彼女の覚悟が一瞬にして伝わる箇所である。だいたい、太夫ともなれば、その言動からして清蔵が「野田の醤油問屋の若旦那」なんかではないことはとっくにお見通しのはず。清蔵の心を知るためあえてその嘘につきあう、そういう〝賢さ〟をもった女性なのだ、幾代は。
思えば、清蔵と、落語家になりたい一心で新潟から家出同然で東京にやってきた入門当時の夢丸師匠とはほぼ同じくらいの年齢だったのではないか。17歳くらい? 思い続けて、ついに幾代太夫の真心を射止めた清蔵の一途さと、ついに真打の晴れ舞台に立った落語好きの少年の一途さとが重なって、ちょっとグッとくる高座であった。大入り。
ちなみに夢丸師、確認できてないけれど、この披露目中、もしかしたらトリのネタ全部替えたのではないだろうか…。
──────
2015年7月8日
国立演芸場 7月中席
夢吉改メ二代目三笑亭夢丸
真打昇進襲名披露興行
開口一番 古今亭今いち「初天神」
◎ 柳亭小痴楽「強情灸」
◎ 瀧川鯉橋「牛ほめ」
◎ 東 京丸・京太平(漫才)
◎ 桂文治「源平盛衰記」 *歌丸代演
◎ 三遊亭好楽「三年目」 *五代目圓楽一門会
〜 仲入り 〜
◎ 口上 下手より夢花(司会)、鯉橋、文治、夢吉改メ二代目夢丸、小文治、好楽
◎ 三笑亭夢花「反対俥」
◎ 桂小文治「親子酒」
◎ ボンボンブラザーズ(太神楽曲芸)
◎ 三笑亭夢丸「幾代餅」
1/24鈴本演芸場11月下席夜の部【寄席おぼえがき】
2015.11.25|rakugo
8月のあたま以来なので、なんと3ヶ月半ぶりにナマで聴く落語。単純に聴きたいと思う落語会と自分のスケジュールが合わなかったということもあるが、じつはここのところ気の塞ぐようなことが多く、こういうときにこそ落語を聴きたいと思う反面、なんとなく気分がのらないということもあってすっかり時間があいてしまったのだ。でもいい加減、ここはひとつ無理やり羽交い締めにしてでも笑わせてくれるような落語が聴きたいと思っていた矢先、鈴本演芸場11月下席の番組表が目にとまった。
── 特別企画公演|喬太郎 ハイテンション 高カロリー
コレしかないでしょ。
上野駅そばのイアコッペでごはんを調達し、開場15分ほど前に到着したらすでに数十人の行列ができていた。このなかには、ぼくのような心持ちの人間も幾人かはいるのだろうか。
ここのところ不思議とよくあたる圭花さんが開口一番。「道灌」。そつがない。ご隠居がなにか言うたびいちいち混ぜっ返す、そのテンポがいい。それはそうと、相変わらず青々とした丸坊主だけど二ツ目になったら伸ばすのかな。
左龍師匠の「家見舞」。さすがに手堅い。そして、江戸っ子二人組の兄貴分、けっこう食べちゃうんだね。その後、お腹の具合は大丈夫だったかな。お勝手にいるらしい兄ィの「おっかさん」にときおり話しかけるのだが、それがいい。新築の家に奥行きを感じさせるのだ。
奇術うんぬんというよりも、すでに「アサダ二世」というひとつの確立された「芸」なのではないか。ふつうに自宅の近所の様子をおしゃべりしてるだけなのに、すでになんともいえず胡散臭いのだから。
新「二ツ目」のお披露目。駒松改メ金原亭馬久(ばきゅう)。持ち前のいい声でおめでたく「厄払い」を。ちなみに、「馬久二(ばくに)」という先代馬生の気に入っていた名前から「二」を取ったのが名前の由来とのこと。
ちょっと予想外というか、一朝師匠の「宗論」がこんなに可笑しいとは思わなかった。耶蘇教にかぶれた倅の調子も変なのだが、それ以上に旦那の叫ぶ「馬鹿ーッ」という甲高い声がもうたまらない。いままで聴いた「宗論」のなかでも抜群。
「若手」とはいえ、寄席育ちの自在さというか、ときにはしたたかさすら感じさせるホンキートンク。関係ないが、漫才コンビのボケツッコミの立ち位置ってべつに決まりがあるわけじゃないんだな。いまさら気づいた。
この後、仲入り前に天どん〜白鳥と円丈師匠の弟子がつづく。トリの喬太郎師匠も、新作、古典の〝両刀使い〟なのでどんなネタをもってくるかわからない。さて、こんなとき天どん師匠はどういうネタをかけるのだろう、興味津々で眺めていると、「わりと珍しい噺をやりますよ。珍しいってことはあんまり面白くないってことだからね」と断っておいて「肝つぶし」に入る。この流れで、新作でも、かといって手垢のついた古典でもなく、こんなちょっと渋めの噺をもってくるあたり新作派と思わせておいてじつは「落語マニア」の天どん師匠らしい。さりげなくこういう〝仕事〟ができるからこそ、このひとは仲間から愛されているのだろうなァ。キラリと光る采配。
弟弟子がいい感じに場をならしてくれたので、当然のごとくやりたい放題の白鳥師匠なのであった。自作の「ナースコール」でもおなじみのミドリちゃんが、今回は就職記念にと自由が丘出身の大学の先輩を歌舞伎町のホストクラブへと招待する。イケメン相手にいい感じに盛り上がっているところに自称「江戸っ子」の「お大尽」マダムが登場、ふたりの邪魔をする。このマダム、「江戸っ子」というのは真っ赤な嘘で、じつは千葉県の「内房」出身。泥酔して正体をあらわしたマダムは、埼玉県出身のミドリちゃん、そして千葉県の「外房」を攻撃しはじめる。すると、突然なぜか自由が丘出身のはずの先輩が怒り出し……。菜の花体操やMAXコーヒーが飛び出す、なるほどこれが噂にきく「千葉棒鱈」か。
仲入り後、まずは太神楽曲芸の翁家社中。小楽、和助ふたりで登場。芸はいままでとなんら変わらないし、むしろふたりになったぶん苦労もあったりするのかもしれないが、まだ和楽師匠が存命だったころの3人組の印象が強いせいか舞台の上がなんとなく寂しい。小花さんは一緒にやらないのかな。
文左衛門師匠がやる「千早ふる」の演出はちょっと変わっている。歌の訳(わけ)を尋ねる相手が、よくある「ご隠居」ではなく「兄ィ」なのだ。ちょっと「手紙無筆」みたい。いたずら心からテキトーなことを教える「ご隠居」に対し、見栄っ張りの「兄ィ」はというと知らないくせに「知らない」とは言えない。苦し紛れにテキトーなことをひねりだす「兄ィ」のキャラは、いかにも文左衛門師匠に似合う。そして、「千早ふる〜文左衛門バージョン」のサゲはおなじみ「(「とは」の意味は)◯◯にまかせた!」と後の出番の演者に丸投げするパターン。きょうはもちろん「喬太郎にまかせた!」
紙切りの二楽師匠。開口一番、「『とは』の意味には触れないでいいと楽屋で確認をとってきました」と笑いをとる。リクエストのお題は、「申(さる)」と「春画」。「触れないでいい」と言われても、ちゃんと後につなげる律儀さはさすが。
喬太郎師匠、いつになく髪が伸びている。忙しくて床屋に行く暇がないのかな? などと余計なお世話。旅先で出会った味、ホッケの刺身、秋田の「オシャレそば」……そんな旅にまつわるマクラから「抜け雀」へ、と思ったら、なんだか様子がちがう。文無しの絵師が描くのは、おなじく文無しの表具師が置いていった衝立ではなくて、土管。絵も「すずめ」ではなく、「はんぺんみたいな、水餃子みたいなもの」。翌朝、近所の人たちが大騒ぎする声で目覚めた旅籠の主人は、そこになんと土管から抜け出た二次元怪獣「ガヴァドン」の姿を発見するのだった。えーーーーっ!?「抜けガヴァドン」!?自分は「ウルトラマンとゴジラと赤塚不二夫、横溝正史、都筑道夫、そしてつかこうへいで出来ている」(『ラジカントロプス2.0』出演時のコメントより)と公言する喬太郎師匠の真骨頂といってしまえばそれまでだが、「抜け雀」という名人もののバリバリの古典落語と、子供たちのいたずら書きが怪獣に実体化してしまうウルトラマンのエピソードをつなげてしまうその卓越したアナロジーの才、やっぱりこの師匠は「天才」だ。そればかりではない、噺の途中おかしなくすぐりがちょこちょこ挟まるなと思っていたら、なんと最後にそれが「千早ふる」の歌の訳(わけ)として完成するというミラクル!!ヒザ前の文左衛門師匠の高座からわずか30分弱でこれを考え、しかも噺の中に入れ込むなんて!!ウルトラマンのポーズを決めて「トワッ!!」って……もう最高、降参です。
──
2015年11月24日
上野・鈴本演芸場11月下席夜の部「特別企画:喬太郎 ハイテンション 高カロリー」
開口一番 柳家圭花「道灌」
◎ 柳亭左龍「家見舞」
◎ アサダ二世(奇術)
◎ 祝二つ目昇進〜金原亭駒松改メ馬久「厄払い」
◎ 春風亭一朝「宗論」
◎ ホンキートンク(漫才)
◎ 三遊亭天どん「肝つぶし」
◎ 三遊亭白鳥「千葉棒鱈」
〜お仲入り〜
◎ 翁家社中(太神楽曲芸)
◎ 橘家文左衛門「千早ふる」
◎ 林家二楽(紙切り)
◎ 柳家喬太郎「抜けガヴァドン〜千早ふるver.」

12/16連雀亭ワンコイン寄席【寄席おぼえがき】
2015.12.17|rakugo
ひさしぶり、番組が3部制になってからは初の連雀亭。「ワンコイン寄席」は、時間が繰り上がって11時30分からの60分となった。少ない休日を有効活用できるのでありがたい。そしてきょうは、落語協会所属の二ツ目3人による落語会。
◎ 柳家ろべえ「もぐら泥」
こんなに入っている連雀亭は初めて見た、とろべえさん(たぶん20名以上の入り)。いつも自分が出るときはつばなれがやっとなのに、みんなつる子めあてなんでしょうとお客さんへのぼやきから、縁起がいいとされるドロボウのまくらへ。ぼやきながらも、二ツ目に昇進したばかりのつる子さんにちゃんとエールを送るいい先輩。
「もぐら泥」。店の主人と、縁の下で身動きがとれなくなった泥棒。そのやりとりを、カメラが切り替わるように交互に繰り返すやりとりが楽しい。周囲を気にしながら塀の下を掘っているときのしぐさは、どうしてなかなか堂に入っている。いっぽう、凄んだり哀願したり、捕まってからの必死の様子も滑稽だ。泥棒なのに、なんだかあまりにも可哀想でつい味方してあげたくなってしまう噺である。それにしても、ろべえさんを聴いていると、つくづく喜多八師匠のことが好きなんだなぁと感心してしまう。師匠の得意ネタをしっかり受け継ぎつつ、さらにそれがろべえさんの噺に変化していったら「殿下」としても安心、盤石の師弟関係といえそう。
◎ 古今亭始『時そば』
最近ミスiDで特別賞を獲ったつる子さんから、応募にあたっては色々と相談を受けたという始さん、受賞したのはある意味自分のおかげと恩を着せる。「時そば」。ひさしぶりに始さんを聴いたのだけど、相変わらずの安定感。とくに、ペラペラと愛想を述べる男の調子のいいこと! 対する、それを真似する男は「川越生まれの小江戸っ子」。ただ「『時そば』を聴いた」というよりも、ちゃんと「始さんの『時そば』を聴いた」という感じ。型は崩さないがどこか弾けてる、そこが始さんの魅力かもしれない。
◎ 林家つる子『壺算』
先輩から散々まくらでいじられたつる子さん、始さんとろべえさんは落語協会のオシャレ番長ツートップと持ち上げ、アドバイスが受賞に導いたのかもとその貢献を認めながらも、「つくづく賞金のない賞でよかった」としれっと逃げてみせるあたりうまい。ある落語会でのこと、開口一番で「子ほめ」をかけていたら後の出番の演者が遅れているため引き延ばすようにとの指示が出た。考えた挙句、「子ほめ」の赤ん坊の名前を「寿限無」ということにしてそのまま続けて『寿限無』に入ってなんとか急場をしのいだとのこと。そんなつる子さんは、落語を聴いていて、ある噺の登場人物とべつの噺の登場人物がもしかしたら同一人物なんじゃないか、とふと思うときがあるという。そして、(前のネタを受けて)「時そば」の男はきっとこの男と同じなんじゃないだろうかと『壺算』へ。なるほど、考えたこともなかったけれど言われてみれば……。『壺算』の男も、「買い物上手」というよりは、数字を巧妙に弄んだイタズラだもんね。初めて聴く噺家さんなのでよくわからないとはいえ、こういうつる子さんの想像力は、たとえば新作をつくったりする際にも武器になったりするのではないか。目のキョロっとした愛くるしい顔で表情たっぷりに演じるのも、自分の武器をちゃんと知っている証拠。クレバーなひとである。
先輩二人が新二ツ目に花をもたせ、新二ツ目もしっかりそれに応えてみせる、そんな趣のなごやかな会だった。
──
2015年12月16日
神田・連雀亭ワンコイン寄席
◎ 柳家ろべえ『もぐら泥』
◎ 古今亭始『時そば』
◎ 林家つる子『壺算』
12/22柳家小三治独演会【寄席おぼえがき】
2015.12.25|rakugo
最高気温16度、うっかりすると年の瀬ということすら忘れてしまいそうなポカポカ陽気の中、大山の板橋区立文化会館へ向かう。「柳家小三治独演会」。ことし初。去年とはうってかわり、この時期になってようやく小三治師匠を聴ける。
小三治師匠の「独演会」は、まず弟子(ときには一門の二つ目)が開口一番をつとめ、その後、中入りを挟んで一席ずつというのがデフォルト。開口一番に登場したのは、三番弟子のはん治師匠。旅のまくらから、三枝(当代の文枝)師匠がつくった『妻の旅行』へ。夫とその息子の会話だけなのに、ありありと「モンスター妻」の姿が浮かび上がってくるおかしさ。定年後、妻の顔色をうかがいながら日々を過ごす気の毒な夫が、はん治師匠の姿と重なっておかしさも倍増。
ところで、三枝、はん治、小三治という3つの名前を聞いてまずまっさきに思い出されるのは、三枝師匠が六代目文枝の名前を襲名する折、小三治師匠が寄せたお祝いのコメントのこと。落語家としての先行きに悩んでいた自分の弟子のひとりが、ある日、三枝師のつくった噺と出会ったことでふたたび自信をつけ、いまもひとりの落語家として歩んでいることへのそれは心温まる感謝のことばであった。
はん治師みずから高座返しをし、いよいよ小三治師匠の登場である。目の不自由なひとにまつわるエピソードから、差別用語を使わなければ差別もなくなるとかいえばそういうわけじゃない、日頃からコミュニュティーの一員として接することこそ大事なんじゃないだろうかと『錦の袈裟』に入る。そうそう、そうなのだ、しっかり者のおかみさんがいる与太郎が、町内の若い衆と一緒に繰り出した吉原でちょっといい思いをするこの噺は、滑稽なだけでなく、江戸の隅っこに存在する〝長閑なユートピア〟を舞台にしたあったかいエピソードなのだ。聴いていてぬくぬく気持ちがいい。翌日、法事の席で〝錦のふんどし〟を付けた和尚の様子までが思い浮かぶ。
中入り後、時間の関係か、まくらもそこそこに『初天神』。金坊の押し付けあいに敗北したおとっつぁん、やむなく初天神でにぎわう神社へと金坊を連れてゆくのだが、ことあるごとに「(おかみさんが)羽織をモタモタ出しやがるから」と繰り返し愚痴るのがおかしい。フリーダムな金坊は当然言うことをきくはずもなく……。
団子屋でおとっつあんの真似をする金坊、おねだりの〝知恵〟を授けるしたたかな凧屋のおやじ、次から次へと繰り出される祭りの日ならではの賑やかなエピソード。でもやはり、なんといっても小三治師の「初天神」は、金坊そっちのけで凧揚げに夢中になってしまうおとっつぁんに尽きる。純真無垢というか、まさにこの親にしてこの子あり。サゲまで行かず途中で切られてしまうことの多い、またそれで十分に楽しい噺ではあるけれど、やはりこの凧揚げのくだりまで行ってこそ〝一卵性父子〟の面白さが伝わるのだなァ。
♪いいな、いいな、人間っていいな… ふつうに人間を描きながら、いやだからこそ、噺の末端にまであたたかい〝ひとの血〟が通っている。小三治師匠の落語を聴いた後は、たとえそれがどんな噺でも、心にぽっとあたたかい気持ちを灯しつつ家路につくことのできる安心感。ぼくにとって〝小三治落語〟がスペシャルな理由は、そこにある。
──
2015年12月22日 大山・板橋区立文化会館
◎ 柳家はん治『妻の旅行』
◎ 柳家小三治『錦の袈裟』
〜中入り〜
◎ 柳家小三治『初天神』
2/9鈴本演芸場2月上席夜の部【寄席おぼえがき】
2016.2.10|rakugo
菊志ん師匠には寄席が似合う。
浅めの出番で高座に上がり、それまで重たかった客席の空気をガラッと変えて下がってゆく、そんな場面に幾度か出くわした。〝仕事人〟という呼び名がぴったりの噺家。
じつはなにをかくそう、師匠がトリを務める日に寄席を訪ねるのは今回が初めて。火焔太鼓、浜野矩随、寝床、百川、子別れ、明烏、しじみ売り。初日からここまでに掛けたネタをみずからのブログに師匠が挙げていた。さて、今日はなにを掛けるのだろう? 菊志ん師匠らしい、カラッと明るく楽しい噺だとうれしいのだけれど。
それはともかく、である。昨晩の鈴本演芸場の客席は様子がヘンだった。噺の途中で突然立ち上がり舞台に背を向けて仁王立ちする男がいるかと思えば、スーツ姿のおっさんグループはいちいち茶々を入れて水を差す。ビニール袋のガサガサ音は終始鳴り止まず、振り返って睨みつけるおばあちゃんがいる。気持ちはよくわかるが、こちらとしてはどうにも落ち着かない。浅草ならいざ知らず、鈴本でここまでのことはあまりない。とはいえ、寄席に通っていればこういうことだってあるのだし、そんな客席だからこそ百戦錬磨の寄席芸人たちの仕事ぶりに触れるいい機会かもしれない。そんなふうに考えて諦めることにした。
開口一番は、小せん師匠の弟子のあお馬さんで「金明竹」。達者な前座さん。言い立ても早口言葉風の一辺倒ではなく、ゆっくり喋ってみたりと変化をつけて工夫がある。そもそも骨董品の名前からしてすでに呪文のようなのだから、早口じゃなくても、上方の訛りでなくてもけっきょく与太郎やおかみさんには通じないのである。
続いて、二つ目の志ん吉さんは「子ほめ」。八五郎は、ガサツというよりはテキトーな感じ。いっそのこともっと軽い人物にしちゃっても面白いかも。鏡味仙三郎社中は、仙三郎と仙成のふたり。仙成さんは初めてだが、早回しのスピード感は若いだけあってさすが。急病の圓太郎師匠に代わり登場したのは燕路師匠。「パンフレットに私の名前は出ておりませんが、深く考えずにただ身をまかせていただければ極楽にお連れすることになっております」と「だくだく」へ。絵に描いたネコに、わざわざご丁寧に「タマ」と名前まで入れるところが面白い。客席も一気に温まる。燕路師匠、かっこいい。
菊千代師匠は、娘の縁談をめぐり母親と娘の奉公先のおかみさんとがとんちんかんなやりとりをする「お千代の縁談」。自作のネタだろうか。いかにも寄席らしいマギー隆司先生のマジックにほっこり。馬石師匠の「鮑のし」は、甚兵衛さんが大家のところにアワビを届けるくだりまで。はたして目論見どおり一円は貰えたのだろうか。なんか、きっと貰えそうな雰囲気だったな。
一朝師匠が中入りだと、ちょっと得をしたような気分になる。その上、師匠お得意の威勢のいい江戸言葉が〝炸裂〟する「三方一両損」ときたら、もう文句なし。大岡裁きの見事さよりも、「こいつら絶対また喧嘩する」という苦笑いのほうが勝る「三方一両損」。絶品。
ホームラン。勘太郎先生が、最近逮捕された清原に似ているというまさにタイムリーな話題から。いつものテレビショッピングネタだが、最近ご無沙汰だったので初めての製品も登場。スマホで客に商品を検索させたりと、ざわつく客席をあえて巻き込んでの今夜は浅草仕様!? はじめて聴く鬼丸師匠は、自作の「新・岸柳島」。大学時代、小田急線の車中でヤンキーに絡まれた出来事をネタにした新作。サゲを聴いてなるほど納得。面白い。ヒザは二楽師匠の紙切り。ハサミ試しの「桃太郎」は誰も取りにこないのに、師匠が「ご注文はありますか?」と口にした途端5人くらいが一斉に大声で叫んだのには驚いた。二楽師匠、すかさず「落ち着いてください」。お題は、浅田真央、流し雛、浦島太郎と織姫の雪合戦(同時に叫んだふたつのお題を合体)。
いよいよ主任の菊志ん師匠登場。「戻ってくる芸人がみんな顔を紅潮させているのできっと今日のお客様はやりやすいのでしょう」と、まずは持ち上げつつさらりと牽制。さすが。
旅先で実際にあったちょっとコワい出来事のマクラから、旅の乗合船がサメに取り囲まれてしまう「鮫講釈」へ。おなじ噺でも、主人公が上方のひとで金比羅参りの帰りの出来事だと「兵庫舟」、お伊勢参りの江戸っ子が主人公だと「桑名舟」と名前が変わるのだとか。ということは、「桑名舟」の後半に講釈師が登場し、「五目講釈」を披露すると「鮫講釈」になるということか。
前半は、江戸っ子二人組と同船した上方のひとによる謎かけ。客席から入る茶々もうまく取り込んで噺を進める師匠。講釈師、一龍斎貞山の弟子で貞船(ていせん)先生が登場するところでちょっと地噺風に「うまい」講釈師の説明がおもしろおかしく入るのだが、こういう説明は講談にあまりなじみのない人間にはありがたい。「鮫講釈」のなかには、最後の一席なのでいろいろな読み物をあえてミックスして…… という型もあるようだが、菊志ん師匠の「鮫講釈」に登場する貞船先生は一見立派にみえるが、そのじつ胡散臭くも思える人物。緊張で混乱しているのか、はたまたテキトーなのか判然としない。やけっぱちな感じもする。
五目講釈に入ってからは、そのスピードと勢いとに圧倒されたか、すっかり酔漢も大人しくなってしまった。あの客席にしてこのネタだったのだろうか。さながら菊志ん師匠の技アリといったところ。
──
2016年2月9日
上野・鈴本演芸場2月上席夜の部
開口一番 柳家あお馬「金明竹」
◎ 古今亭志ん吉「子ほめ」
◎ 鏡味仙三郎社中(太神楽曲芸)
◎ 柳亭燕路「だくだく」
◎ 古今亭菊千代「お千代の縁談」
◎ マギー隆司(奇術)
◎ 隅田川馬石「鮑のし」
◎ 春風亭一朝「三方一両損」
〜仲入り〜
◎ ホームラン(漫才)
◎ 三遊亭鬼丸「新・岸柳島」
◎ 林家二楽(紙切り)
主任:古今亭菊志ん「鮫講釈」
池袋演芸場8月下席昼の部
2016.9.2|rakugo
ここ数ヶ月、私事でバタバタしていたせいでしばらく寄席からも遠ざかっていた。およそ7ヶ月ぶり。迷走する台風10号の進路に気をもみながらの池袋演芸場。
──
池袋演芸場 八月下席昼の部 千秋楽
開口一番 小かじ「二人旅」
◎ 三遊亭わん丈「こじらせ親分」
◎ 林家たけ平「小田原相撲」
◎ 柳家さん助「汲み立て」
◎ ホンキートンク 漫才
◎ 三遊亭金馬「蝦蟇の油」
◎ 古今亭菊志ん「酢豆腐」
〜 お仲入り 〜
◎ 林家ひろ木「看板のピン」
◎ 宝井琴柳「安兵衛道場破り」
◎ 鏡味仙三郎社中 太神楽曲芸
◎ 柳家三三「三味線栗毛」
──
開口一番は、三三師匠の弟子小かじさんで「二人旅」。線の細い師匠に対して、高校球児のようなバリバリ体育会系な風貌の小かじさん。なかなかメンタルも図太いところがあるのだろうか、途中、なぞかけのくだりでセリフが飛んでしまうアクシデントも、そつなく笑いにつなげてサゲまで。
二ツ目に昇進してまだ間もないわん丈さん。前座時代から注目していたひとりだが、二ツ目になってから聴くのは今日がはじめて。高座を下りてきて「兄さん、今日の高座には魔物がいます」と報告した小かじさんに、「お前だヨ!」。前座時代、すぐ上の先輩としていろいろ面倒を見た間柄ということでほのぼのとした幕開き。最近の学校では、アレルギー対策のための給食の「検食」が大変らしいというマクラから自作の「こじらせ親分」。「乙女趣味」な親分のお世話に四苦八苦するヤクザの組員が、不意の思いつきで「給食」を始めると言い出した親分に「検食」で対抗するお話。前半の「乙女趣味」、後半の「給食」とそれぞれに面白いのだけれど、ちょっとつなぎ目に唐突な印象も。「なんにでもすぐ影響されてしまう親分」というエピソードが前提にあると、より滑らかにつながるかなぁなどと考えたり。
ところで、ここでふと思ったのだが、きょうの番組、これはちょっと「男子校」っぽいかもしれないと。
たけ平師匠は「小田原相撲」。得意の地噺を「林家」の自虐ネタもまじえつつ自信たっぷりと、真打らしい余裕のある高座。本日の「学級委員」か。
さん助師匠も、真打昇進後、はじめて聴く。「怪しさ」にいっそう磨き(?)がかかったような。なんとなくどよめく場内…… マクラなしでいきなり「汲み立て」へ。「錦の袈裟」同様、与太郎がちょっとおいしい役どころの噺。「有象無象ーー」嬉々として叫ぶ与太郎に、口惜しがる町内の若い衆のコントラストが可笑しい。さらに、テレビカメラが切り替わるようなメリハリがあったらもっと面白くなるかも。
ここで ホンキートンクが登場。「男子校」っぽさは最高潮に?!
はじめて聴く当代の金馬師匠。御年87歳。おじいちゃんがニコニコ座布団に座っていれば、それだけでもうほっこりする。釈台を前に「なにもべつに受付しようってんじゃありません」。これはもう、間違いなく「校長先生」のギャグである。「蝦蟇の油」の酔っ払ってからの口上は、うん、やっぱり味があるなぁ。
菊志ん師匠は、そうなると、ひょうきんな社会科の先生だ。「酢豆腐」(や「ちりとてちん」)は、騙されて腐った豆腐を食べさせられる相手がとてもイヤな人物として描かれていないと、なんだかつい可哀想になってしまってあまり楽しめない。その点、菊志ん師匠の〝イケメン風〟若旦那にはイラっとさせられる。たとえて言えば、真っ黒に日焼けしてシャツの胸元が大きく開いているイメージ。思い出すだけで、あぁ、イラっとする。こうして、古典落語の世界は現代とぜんぜん地続きなのである。そして、最後まで怒り出すことなくたいらげてしまう若旦那スピリットに、「なんかこいつスゲェ」とかえって感心させられてしまうのもいつものこと。
仲入りを挟んで、ひろ木さん。初めて。師匠の影響なのか、ふわふわ様子が落ち着かない。おじいちゃんならともかく、若い噺家さんだと「大丈夫かな?」と余計な心配をしてしまう。ネタは、アンケートの結果を受けて「看板のピン」。あと、これはテレビなどで顔の売れたひとを師匠にもつ落語家に多いような気がするが、「◯◯の◯番目の弟子で〜〜と申します」と自己紹介するのがどうも個人的には苦手である。サラリーマンじゃないのだから、肩書きよりも実力で名前を印象づけて欲しいと思ってしまうのだ。
三三師匠の「ホットケーキフレンド」としてかつて某テレビ番組に登場したこともある、講談の琴柳先生。ここが男子校だったなら、さしづめベテランの国語の先生といったところ。初席で聴いたときは、時間も短く声も聞き取りづらかったのだが、今回はじっくり楽しめた。「安兵衛道場破り」。勢いで圧倒するのではなく、心地よい緊張感が持続する。
仙三郎社中の太神楽(若い仙成さんがを難易度の高い曲芸をさらっとやってのけてしまうので体育っぽい)に続いて、いよいよ三三師匠の登場。「三味線栗毛」。三三師匠がよくかけているのは知っていたけれど、ついに遭遇! 「三味線栗毛」好き(「錦木検校」ではなく)としては感無量。三三師匠の「錦木」は、御武家様の角三郎と気が合うくらいだからその人物にはいじけたところがまるでない。貧しく、目も不自由だが、それでいてさっぱりした気性の持ち主。そんな錦木も、角三郎が家督を継いだと聞き、万が一自分が「大名」になるようなことがあったら「検校」にしてやろうといういつかの口約束を思い出し、いてもたってもいられず病身を引きずって角三郎を訪ねてゆく。だが、いざ角三郎と面会した錦木は、角三郎の「約束を憶えているか?」という問いにぐっと言葉を呑み込み「憶えていません」と答える。なぜだろう? こうしてなるべくして大名になった角三郎、その立派な姿を前に気圧されたということもあるだろうし、なにより「口約束」を盾にとって成り上がろうとする自分のあさましい根性が恥ずかしくなったのではないか。しかし、その「高潔さ」が錦木と角三郎のあいだを身分を超越したフラットな関係に変え、また「検校」にふさわしい人格に持ち上げる。角三郎は言う。「俺は憶えているぞ」。最高の演出。そして、馬の名前をめぐって戯言を言い合うふたりは最上のファンタジーの世界に生きている。現実にはけっしてありえないヒューマニズムが、落語の世界にはこうしちゃんと息づいている。ぼくが落語を聴くのは、そこにすべての人間の生きるべき場所があるからだ。
柳家を中心に、三遊亭も林家も古今亭もいるにぎやかな男子校のような芝居だったが、最後はきっちり「担任」の先生が締めてくれた。一服の清涼剤のような「三味線栗毛」のハッピーエンディングはさながら台風一過の青空のようだなァと地下の演芸場を後にし表に出てみると…… あれ? どうしたことか、豪雨。
2016年8月30日
5/16 鈴本演芸場5月中席夜の部
2017.5.16|rakugo

何度聴いても、やっぱり小せん師匠の「御神酒徳利」は気持ちがいい。御礼に貰った小判をぜんぶ女中にあげちゃう心優しい善六さん。大坂から江戸に帰る言い立ても、なんて心地よいのだろう。
きょうは先代小さん師匠の命日だったそうで、小せん師匠「御神酒徳利」、扇辰師匠「道灌」、三語楼師匠「長短」など、孫弟子のネタ選びには<小さんトリビュート>な趣きも。
開口一番/一猿「寿限無」
◎ かゑる「弥次郎」
◎ アサダ二世(奇術)
◎ 三語楼「長短」
◎ 扇辰「道灌」
◎ ニックス(漫才」
◎ 琴調「清水次郎長伝〜お民の度胸」
◎ 歌奴「阿武松」
〜お仲入り〜
◎ ぺぺ桜井(ギター漫談)
◎ 文蔵「馬のす」
◎ 二楽(紙切り〜学校寄席、安芸の宮島」)
◎ 小せん「御神酒徳利」
11.07.2018
2018.7.12|column
笑いのツボが似ている。これは、友人にせよ恋人や夫婦にせよ、長く一緒に過ごすうえで食べ物や洋服の趣味以上にじつは大切なのではないか。
ときどき、ぼくが落語が好きで寄席に通ったりしていることを知るひとから、オススメの噺や落語家を尋ねられることがある。おそらく相手は軽い気持ちで訊いているのだと思うが、訊かれるこちらからすればこれはなかなかの難問で、つい毎回口ごもってしまいなんだかもったいぶっているような感じになってきまりが悪い。
というのも、相手の笑いのツボが自分と似ていればまったく問題ないのだが、もし違っていた場合「なあんだ、面白いというから聴いてみたのにぜんぜん笑えないじゃないか」などと思われてしまうのが怖いからなのである。たとえば、ぼくはあまり新作落語が好きではないのだが(まったく聴かないというわけではない)、いま面白いと評判の若手落語家の新作をほとんどクスリともせず聴き通したことがある。これは、この落語家の新作がつまらないというわけでなく、自分の笑いのツボとことごとく違っていたからにちがいない。実際、周囲には笑っているひとも多かったのだ(一緒に行った知り合いは笑っていなかったが)。
それに、落語をよく聴くひとなら知っているように、落語の中にはたとえば人情噺や怪談噺、あるいは元々は講談のネタであったものを落語に移し替えた噺など、笑わせることに重きを置いていないネタもたくさんある。また、同じ噺でも演じ手によってまったく印象が異なるといったことも少なからずあったりする。なので、これから落語を聴いてみようというひとが面白い落語と出会うための近道は、まず自分と笑いのツボが似ている人で、しかも落語が好きという人をみつけるところから始めるのがいい。
とはいえ、なかなかそううまくそんな人と出会えるものだろうか? その点、ぼくの場合、落語を聴きはじめた当初、日ごろからこの人は楽しいなあと思っていた人で、しかも落語にもくわしいという人が周囲に2、3人いたおかげですんなり落語の世界に分け入ってゆくことができた。
たとえば、そんな「水先案内人」のひとりにコバヤシさんがいる。まだ、ぼくがほとんど落語家の名前さえまともに知らなかったころ、彼女がおすすめしてくれた何人かの噺家は例外なく面白く感じたのだが、これは、コバヤシさんとぼくの笑いのツボがどこか似ているということがまずあったからだろう。
コバヤシさんはこうも言う。「寄席を一歩出たとたん、なんのネタをやったか思い出せないくらいが丁度いい」。けだし名言である。落語は寄席という小さな宇宙の中でのみ通用する〝ファンタジー〟なのだから、寄席の中だけで完結するくらいの「程よさ」こそが肝心だ。
だいたい、ぼくは落語に余韻を求めていない。それどころか、余韻を残さないことにこそ、芝居や映画と決定的にちがう落語の美学があるとさえかんがえている。いちど寄席の外に出たならば、あとは「ああ、楽しかった」という気分だけがフワッと残ればそれで十分だ。
そういうわけだから、ぼくの好きな落語家に共通するのは、スーッときれいに余韻を切ることの上手さであり、またそこから生まれる「軽さ」である。
たとえば春風亭一朝師匠、瀧川鯉昇師匠、柳亭市馬師匠、桃月庵白酒師匠、三遊亭兼好師匠、柳家小せん師匠、古今亭菊志ん師匠、三遊亭萬橘師匠、雷門小助六師匠、それに三笑亭夢丸師匠といった人たちがいますぐ寄席で聴ける、ぼくの好みにかなった落語家である。思い浮かぶままに。ご参考まで。




